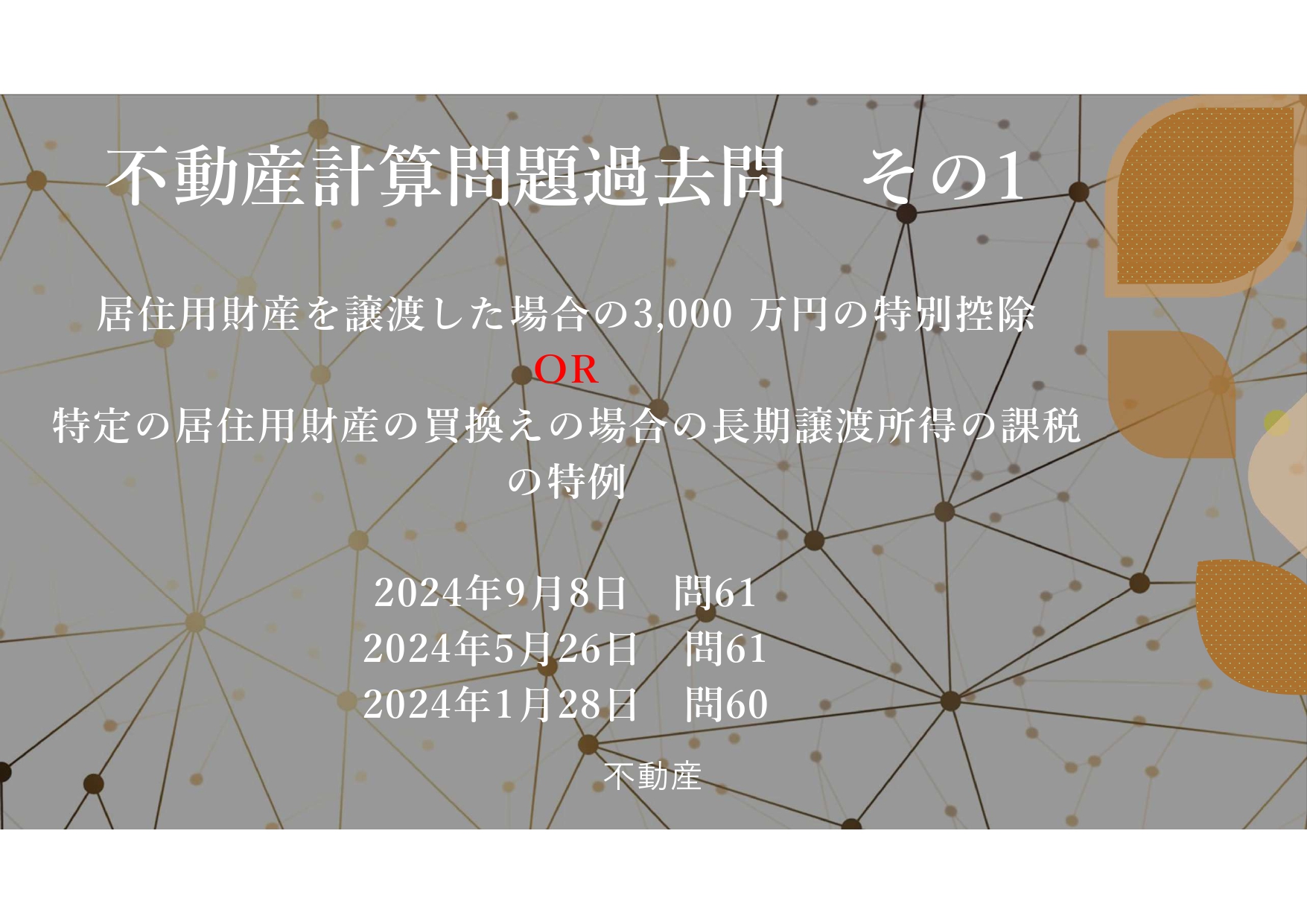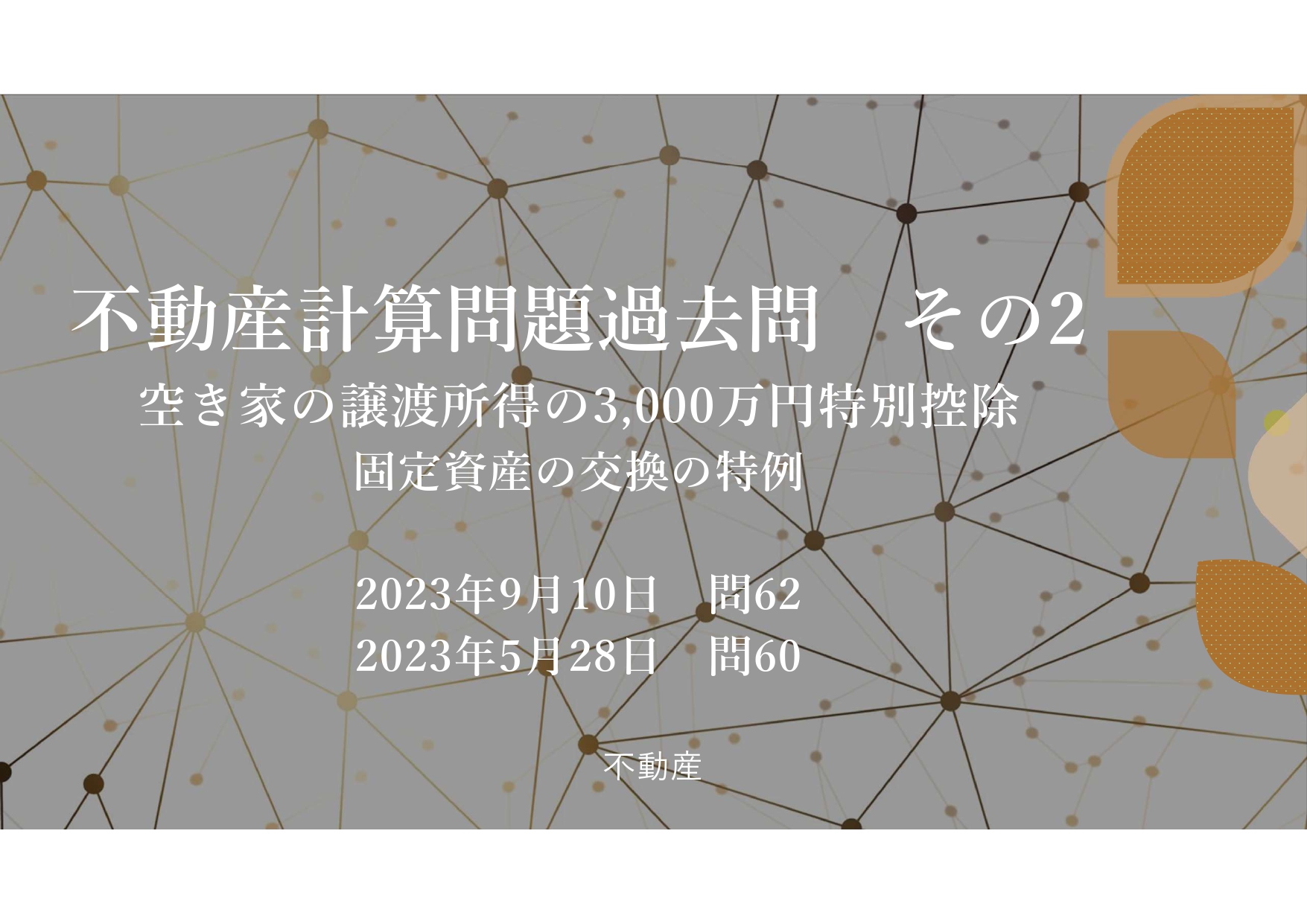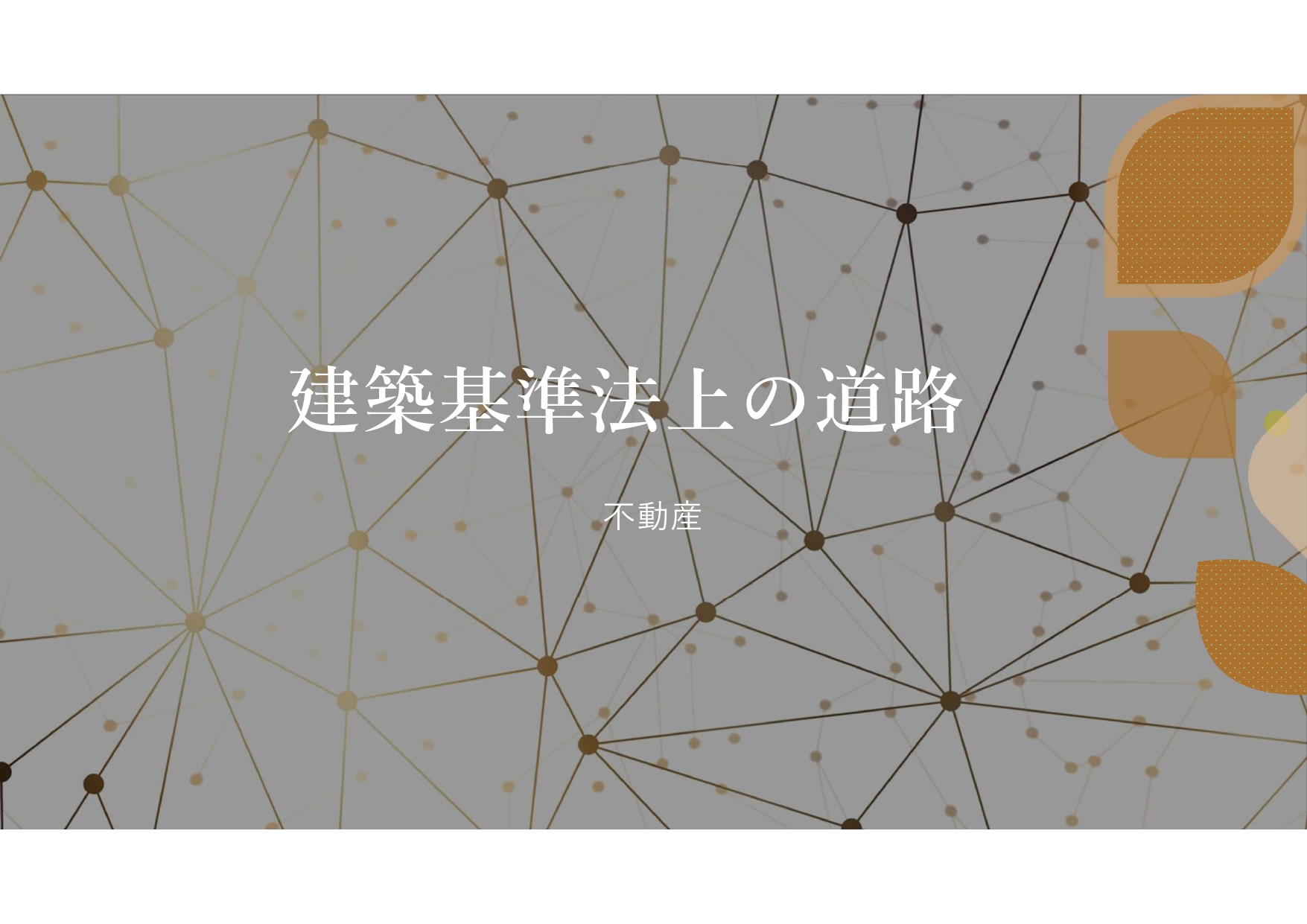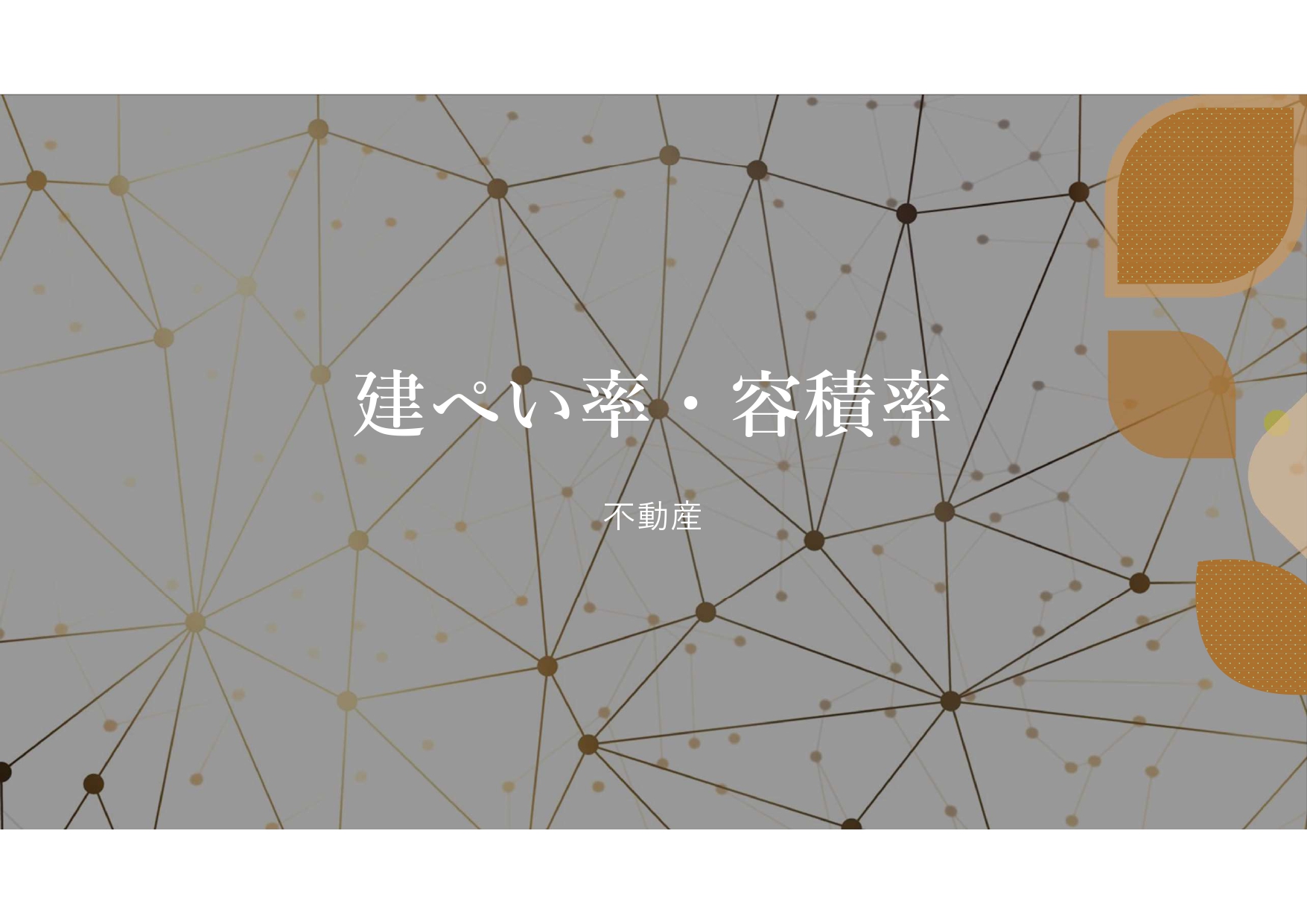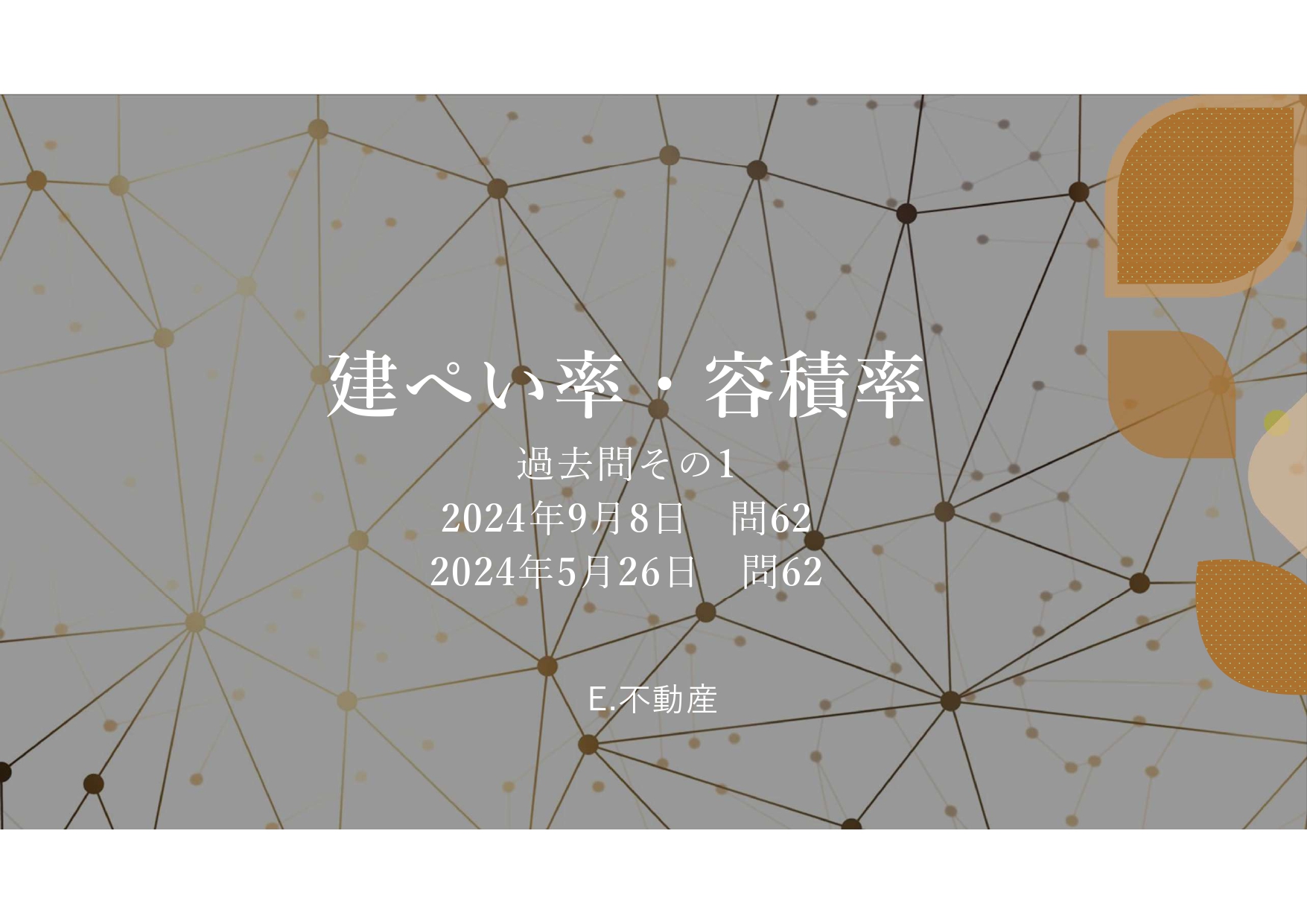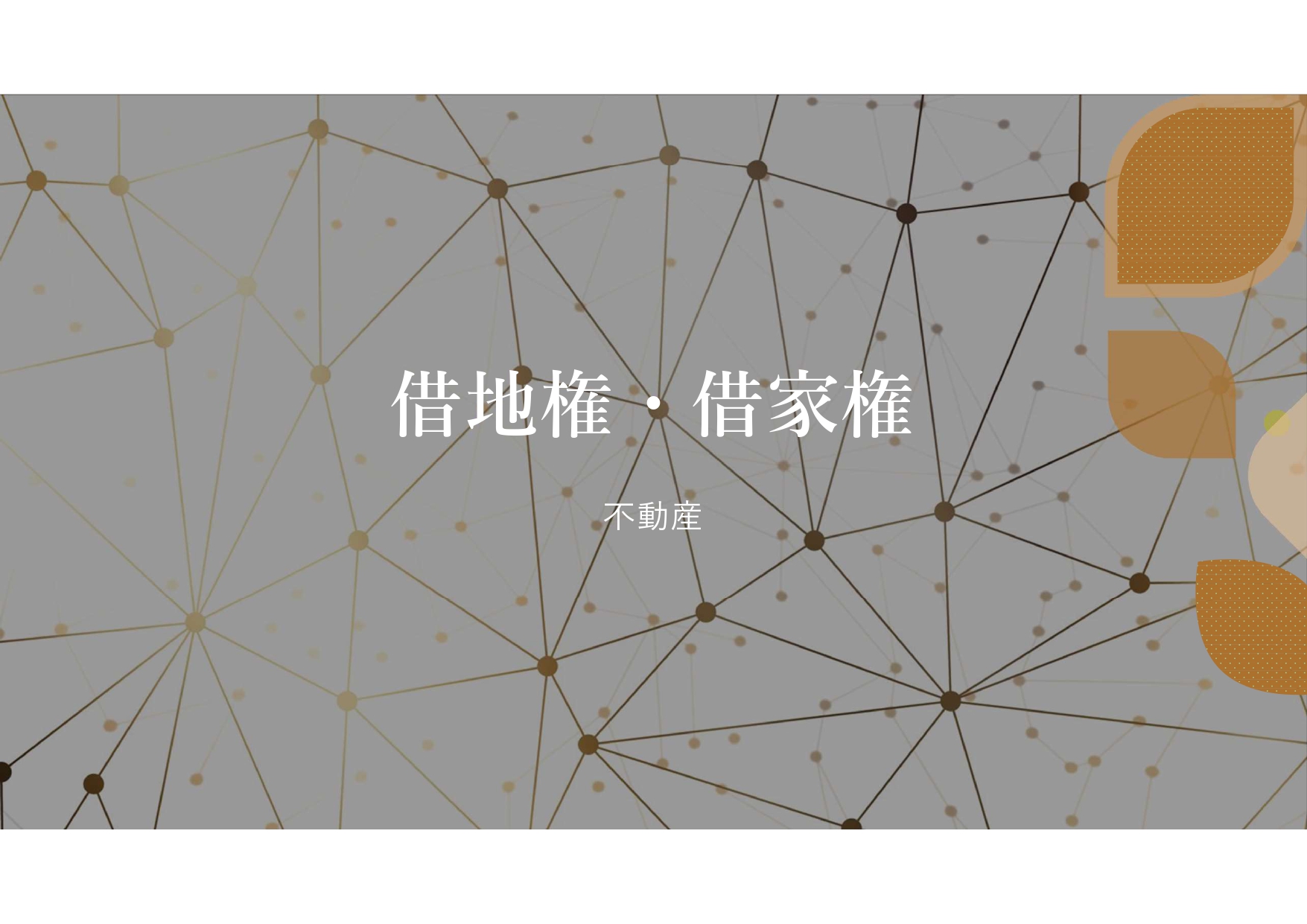不動産の有効活用法・投資判断手法 過去問

これは、不動産を売る方(活用を含む)と買う方(投資判断)の立場の逆な方に向けての
FPの立場からの提案を前提にした問題です。
売買の双方が得をする「Win-Win」であればよいのですが、現実はそううまくいかず、得をする人もいれば、損をする場合もあります。
大切なのは、それぞれが納得する形で収まることだと思います。
間違っても争いごとを招かないように配慮しながら、提案を行う必要があります。
基礎編では、この不動産の有効活用につき、基本的な知識を身に着けることを目的に過去問の紹介と説明を行っていきたいと思います。
また、実技試験を念頭に置いた「不動産の有効活用」という記事を以前にアップしていますので、よろしければご覧ください。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
| 不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 等価交換方式は、地主が所有する土地の全部または一部を提供し、事業者が建設資金を負担して当該土地に建物を建設し、完成した建物とその敷地の所有権等を地主と事業者がそれぞれの出資割合に応じて保有する手法であり、地主は自己資金を使わず、建物の一部を取得することができる。 (b) 建設協力金方式は、地主が金融機関から建設資金を借り受けて、所有する土地に事業者の要望に沿った店舗等を建設し、その建物を事業者に賃貸する手法であり、建設資金は賃料の一部で返済していくため、事業者が撤退するリスクや契約内容を事前に精査しておくことが肝要である。 (c) 事業受託方式は、地主の依頼を受けた事業者が、地主が所有する土地の有効活用の企画、建物の建設や建設する建物の管理・運営等を受託し、賃貸事業の運営を行う手法であり、地主は建設資金を調達する必要はなく、建物の所有名義は事業者となる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

建設協力金と事業受託方式を混同して覚えちゃうんだよな。
等価交換方式は、デベロッパーが介入してくれる用途地域の土地でないと難しいよな。

(a)これは正しいね。土地のありながら、資金が乏しい場合など、活用が検討できるよ。
(b)これも読解で混乱しそうだけど、資金を借りるのは事業者だね。土地所有者は土地を貸出て、建設協力金を差し引いた一定の家賃を受けることができ方式だね。
(c) 事業受託方式は地主が資金と土地を出し、事業運営をデベロッパーが行う方式だね。
よって適切なものは1) 1つだね。
2023年9月10日 問41
| 下記の〈条件〉に基づく不動産投資におけるDSCRとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮せず、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。 〈条件〉 投資物件 :賃貸マンション(RC造5階建て、築5年) 投資額 :4億円(資金調達:自己資金1億円、借入金額3億円) 賃貸収入 :年間2,500万円 運営費用 :年間800万円(借入金の支払利息は含まれていない) 借入金返済額:年間1,440万円(元利均等返済・金利1.5%、返済期間25年) 1) 0.85 2) 1.12 3) 1.18 4) 1.74 |
正解3

DSCRって初めて聞くけど、出ている数字をなんとなく割り算して求めるんだよね。

賃貸収入2,500万円-運営費用800万円=1,700万円・・NOI
DSCR=NOI÷借入金返済額
=1,700万円÷1,440万円
=1.18
よって正解は3)
| 不動産の投資判断手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) DCF法は、連続する複数の期間に発生する純収益および復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引いて、それぞれを合計して対象不動産の収益価格を求める手法である。 2) NPV法は、対象不動産に対する投資額と現在価値に換算した対象不動産の収益価格を比較して投資判断を行う手法であり、NPVがゼロを上回る場合、その投資は投資適格であると判断することができる。 3) IRR法は、対象不動産の内部収益率と対象不動産に対する投資家の期待収益率を比較して投資判断を行う手法であり、期待収益率が内部収益率を上回る場合、その投資は投資適格であると判断することができる。 4) 直接還元法は、一期間の純収益を還元利回りにより還元して対象不動産の収益価格を求める手法であり、一期間の純収益が1,000万円、還元利回りが5%である場合、収益価格は2億円となる。 |
正解3

DCF、NPV、IRRとかアルファベットが多いと混乱するね。英語苦手でも何の略語が考えるといいかもね。

1)DCF法は、将来の収益を現在価値に割り引く手法だね。ディスカウントキャッシュフロー法だね。英語が得意なら意味から理解できるかもね。
2)NPV法は収益の現在価値-投資の現在価値なのでゼロを上回れば有利な投資といえるね。
3)これが不適格だよ。内部収益率<期待収益率 だと収益が期待を下回っているからダメだね。
4)一期間の純収益1,000万円÷還元利回り5%=収益価格2億円
よって不適格なのは3)だね。
2022年9月11日 問41
| 毎期末に1,000万円の純収益が得られる賃貸マンションを取得し、取得から3年経過後に1億6,000万円で売却する場合、DCF法による当該不動産の収益価格として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、割引率は年6%とし、下記の係数表を利用すること。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈年6%の各種係数〉 |
| 1) 1億3,327万円 2) 1億5,960万円 3) 1億6,113万円 4) 1億8,673万円 |
正解3

こういうマンションを売却して利益を得るということは現実にも行われているんだろうか?
| 不動産の有効活用の手法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 事業用定期借地権方式は、事業者である借主が土地を契約で一定期間賃借し、借主が建物を建設する手法であり、賃貸借期間満了後、土地は地主に返還されるが、地主が残存建物を買い取らなければならないというデメリットがある。 (b) 建設協力金方式は、入居予定の事業者から、地主が建設資金を借り受けて、事業者の要望に沿った店舗等を建設し、その建物を事業者に賃貸する手法であり、建設資金は賃料の一部で返済していくため、事業者が撤退するリスクや契約内容を事前に精査しておくことが肝要である。 (c) 等価交換方式は、地主が所有する土地の全部または一部を提供し、事業者が建設資金を負担して当該土地にマンション等を建設し、完成した区分所有建物とその敷地の所有権等を地主と事業者がそれぞれの出資割合に応じて保有する手法であり、地主は自己資金を使わず、収益物件を取得できるというメリットがある。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解2

この3つの手法はすごくよく出題されるから、細かい部分まで暗記が必要だね。実技試験でも問われることがあるよ。

(a) これは誤り、事業用定期借地権方式は借主は、更地にして返還しないといけないね。
(b) 建設協力金方式は、地主としては事業が継続するかどうかと、仮に事業者が撤退した時の協力金の扱いに注意する必要があるね。
(c)この説明は正しいね。等価交換方式では土地がデベロッパーとの共有になることに注意が必要だね。
よって(b) (c)が正しいので、正解は2だね