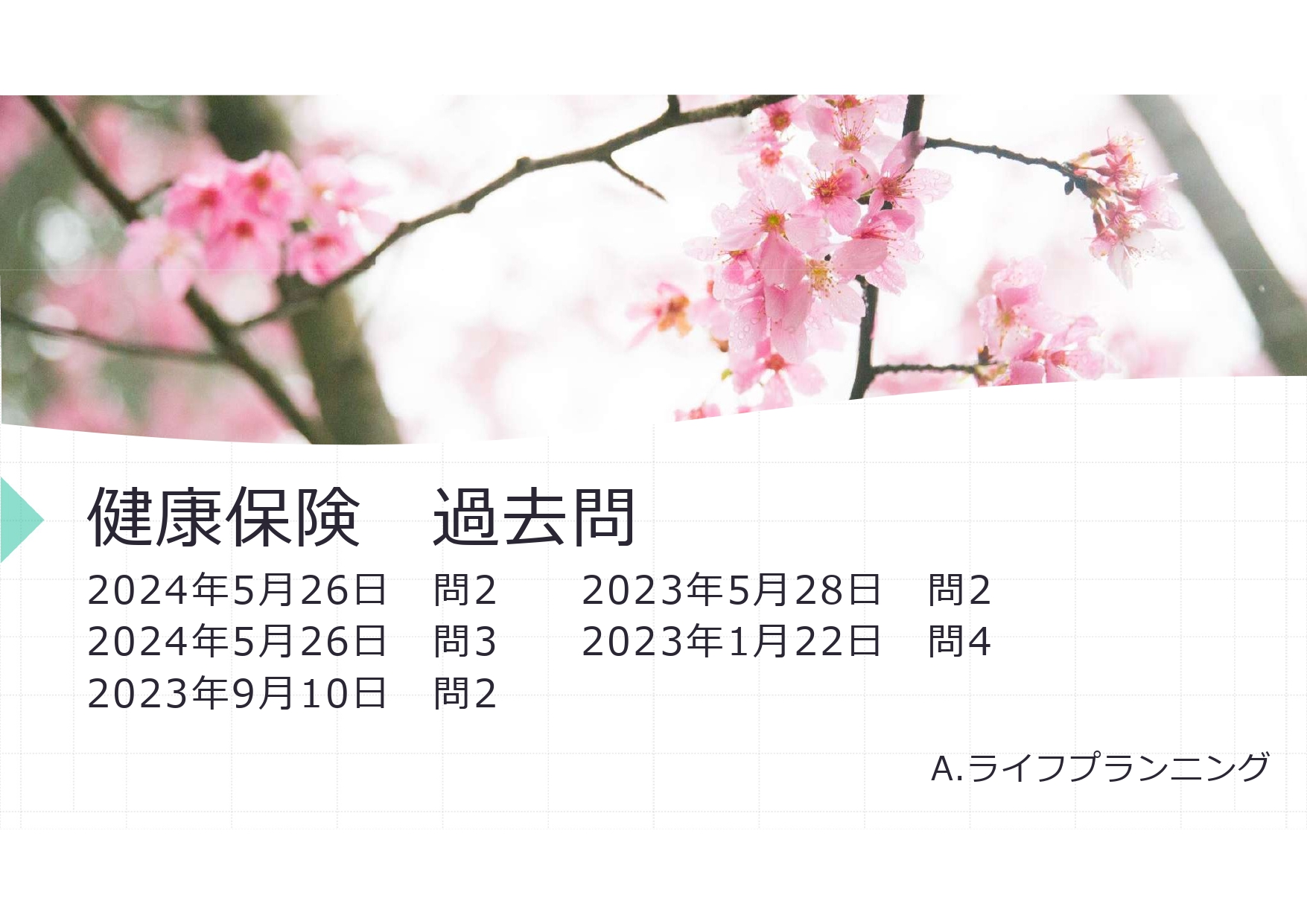
健康保険 過去問
日本国に居住している方であれば、全員が健康保険に加入されているはずです。
日本国憲法25条で以下に定められており、これを実現するための施策だと思います。
‘(1)「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
‘(2)「国は、すべて の生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
2025年12月には紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードがその役目を果たす予定です。
誰でも所持しているとはいえ、健康状態など様々で、数年来、健康保険証を使ったことが無いという方もおられると思います。
逆に、私のように不健康で、毎月、健康保険証を使っているという人もおられると思います。
私のような健康状態の者にとっては、健康保険とは本当にありがたいもので、無かったらとっくに自己破産していると思います。
そんな話は置いておいて、例のごとく過去問を見ながら、私なりの解説をしたいと思います。
なお、出所は一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
| 70歳以上75歳未満の健康保険の被保険者が療養の給付を受けた場合における一部負担金の割合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、生活保護法による医療扶助は受けていないものとする。 1) 国民健康保険の被保険者は、当該被保険者の属する世帯に属する他の国民健康保険の被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は2割となる。 2) 国民健康保険の被保険者である単身者が住民税非課税世帯に該当する場合、一部負担金の割合は1割となる。 3) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円以上である場合、当該被保険者の収入の額の多寡にかかわらず、一部負担金の割合は3割となる。 4) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である単身者の標準報酬月額が28万円未満である場合、一部負担金の割合は2割となる。 |
正解4
健康保険って皆3割負担だと思っていたけど、条件によって違うんだね。持病があったり、所得が低い人には助かるね。
1)国民健康保険は世帯単位で加入になるため、同一世帯内に現役並みの所得者がいる場合は3割負担になるよ。
2)住民税非課税世帯は以前は1割負担だったけど、今は2割負担になっているよ。
3)一見、正解に思えるけど、標準報酬月額が28万円以上でも年収が520万円以下の場合は届出により2割負担になるんだね。
4)これが正解だね、3)の続きだと、例外が無いか疑心暗鬼になるね。
2024年5月26日 問3
| 全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとする。 1) 被保険者の自己負担限度額は、療養のあった月の被保険者の標準報酬月額等に応じた5つの所得区分に応じて設定されている。 2) 高額療養費の算定上、合算する医療費の一部負担金等の額は、支払った医療機関等が同一であっても、医科診療と歯科診療に分けて、かつ、入院診療と外来診療に分けて、別個に算出する。 3) 入院時の食事療養および生活療養に係る費用、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は、高額療養費の算定上、いずれも合算の対象とならない。 4) 同一の世帯に属している夫妻がいずれも被保険者である場合、高額療養費の算定上、同一月内にそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額を合算することができ、その合算した額のうち自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給される。 |
正解4
健康保険の問題が連続して出題されることもあるんだ、しかも、適切なものを選ぶのと、不適切なものを選ぶのと違うから、頭を切り替えないといけないね。
1)これは正しいね、自己負担限度額を意識したことがある人は、所得区分アからオという、どれに当たるか意識したことがあると思うよ。
2)これも実体験があるとわかると思うけど、通院、入院、医科、歯科にわけて計算されるよ。
3)これは有名だね、高額療養費に食費や差額ベッド代は含まれないよ。ただし、通常のベッド代は含まれるよ。
4)これも文章は怪しいけど、これが正解だよ。世帯合算というやつだね。しかし、夫婦で別の保険証の場合は使えないけどね。
2023年9月10日 問2
| 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格喪失後の保険給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者は、傷病手当金の支給期間が資格喪失前の期間と通算して1年6カ月になるまで、傷病手当金を受給することができる。 2) 資格を喪失した際に出産手当金を受給している者が、資格喪失後に配偶者が加入する健康保険の被扶養者となった場合、出産手当金を受給することができる期間内であっても、出産手当金は支給されない。 3) 被保険者であった者が資格喪失の日から6カ月以内に出産をした場合、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金を受給することができる。 4) 資格喪失後に傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受給しなくなった日から3カ月以内に死亡し、その者により生計を維持されていた者が埋葬を行った場合、埋葬料が支給される。 |
正解2
出産、病気やケガで退職した場合に健康保険証が任意継続できるってありがたいもんね。会社負担分が無い分、保険料は上がっちゃうけど。
1)傷病手当金は助かるもんね。退職したら「はい、打ち切り」となったら困るね。せめて1年6か月はもらえるとありがたいね。
2)これが不適切だね、妊娠して退職したら出産手当金は支給されないとなったら、仕事も辞めれないね。まあそのためにパパ・ママ育休プラスなどが整備されてるんだろうけど。
3)これも正しいね、少子高齢化の中、子供を出産しようとする人には優しい施策が多いね。
4)傷病手当金を受給していた人が死亡した場合だから、傷病と死亡が因果関係があると考えるのが自然だもんね。
2023年5月28日 問2
| 都道府県および市町村(特別区を含む)が保険者となる国民健康保険の保険料(保険税)と全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 国民健康保険の保険料(保険税)は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額および介護納付金賦課額の合算額であり、都道府県ごとにその算出方法や料率(税率)が定められている。 2) 国民健康保険において、世帯主が被保険者ではない場合であっても、同じ世帯のなかに被保険者がいる場合、市町村(特別区を含む)は原則として当該世帯主から保険料(保険税)を徴収する。 3) 健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、全国健康保険協会の各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者を単位として全国健康保険協会が決定する。 4) 産前産後休業を開始した健康保険の被保険者を使用している事業所の事業主が、保険者等に申し出たときは、その産前産後休業を開始した月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、事業主負担分と被保険者負担分の健康保険の保険料が免除される。 |
正解1
住んでいる地域によって健康保険の保険料が違うなんて意識したことなかったな。全国一律かと思ってた。
1)都道府県ごとにその算出方法や料率(税率)が決まっているんじゃなくて、市町村ごとだね。よってこれが間違い
2)これはよく問われる論点だから覚えておくといいよ。
3)これは複雑で、ひっかけ問題を作りやすそうだから、同じく頭に入れておくといいかも。
4)これもよく問われる論点だから覚えておくといいよ。
2023年1月22日 問4
| 厚生年金保険および健康保険の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも特定適用事業所に勤務し、学生ではなく、1週間の所定労働時間および1カ月間の所定労働日数が同一の事業所に勤務する通常の労働者の4分の3未満であるものとする。また、賃金の月額には賞与、残業代、通勤手当等は含まれないものとし、雇用期間の更新はないものとする。 |
| 1週間の 所定労働時間 | 賃金の月額 | 雇用期間 | |
| Aさん(25歳) | 25時間 | 15万円 | 1カ月 |
| Bさん(33歳) | 20時間 | 12万円 | 6カ月 |
| Cさん(42歳) | 18時間 | 10万円 | 1年 |
| 1) Aさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。 2) Bさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。 3) Cさんは、厚生年金保険および健康保険の被保険者となる。 4) Aさん、Bさん、Cさんは、いずれも厚生年金保険および健康保険の被保険者とならない。 |
正解2
健康保険、厚生年金の加入条件が変わって従業員101人以上だったのが51人以上になっているね。
1)Aさんは雇用期間が2か月を超えていないため対象外
2)Bさんは全ての条件をクリアしているので対象
3)Cさんは所定労働時間が週18時間のため対象外
よって正解は 2)だね。




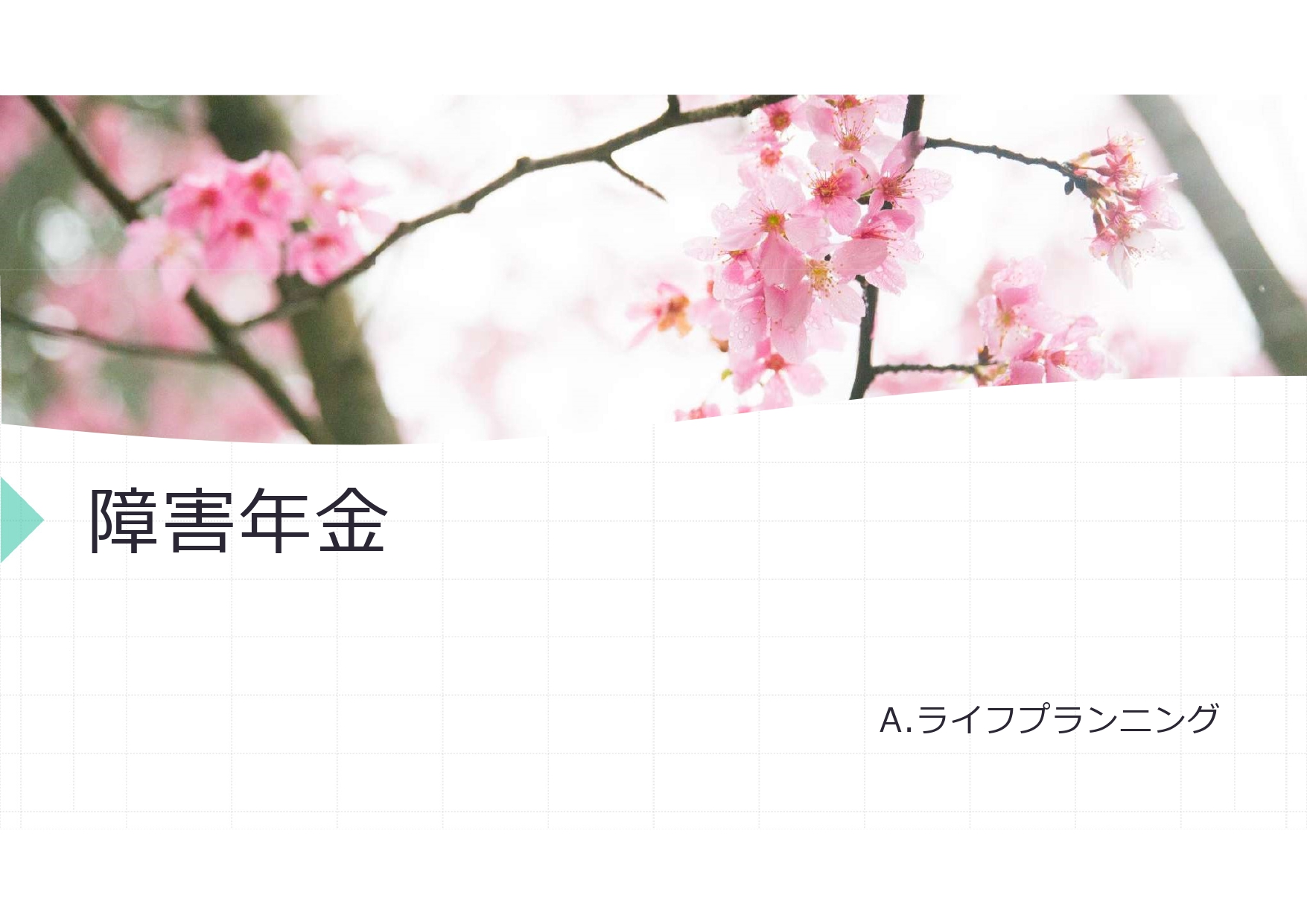
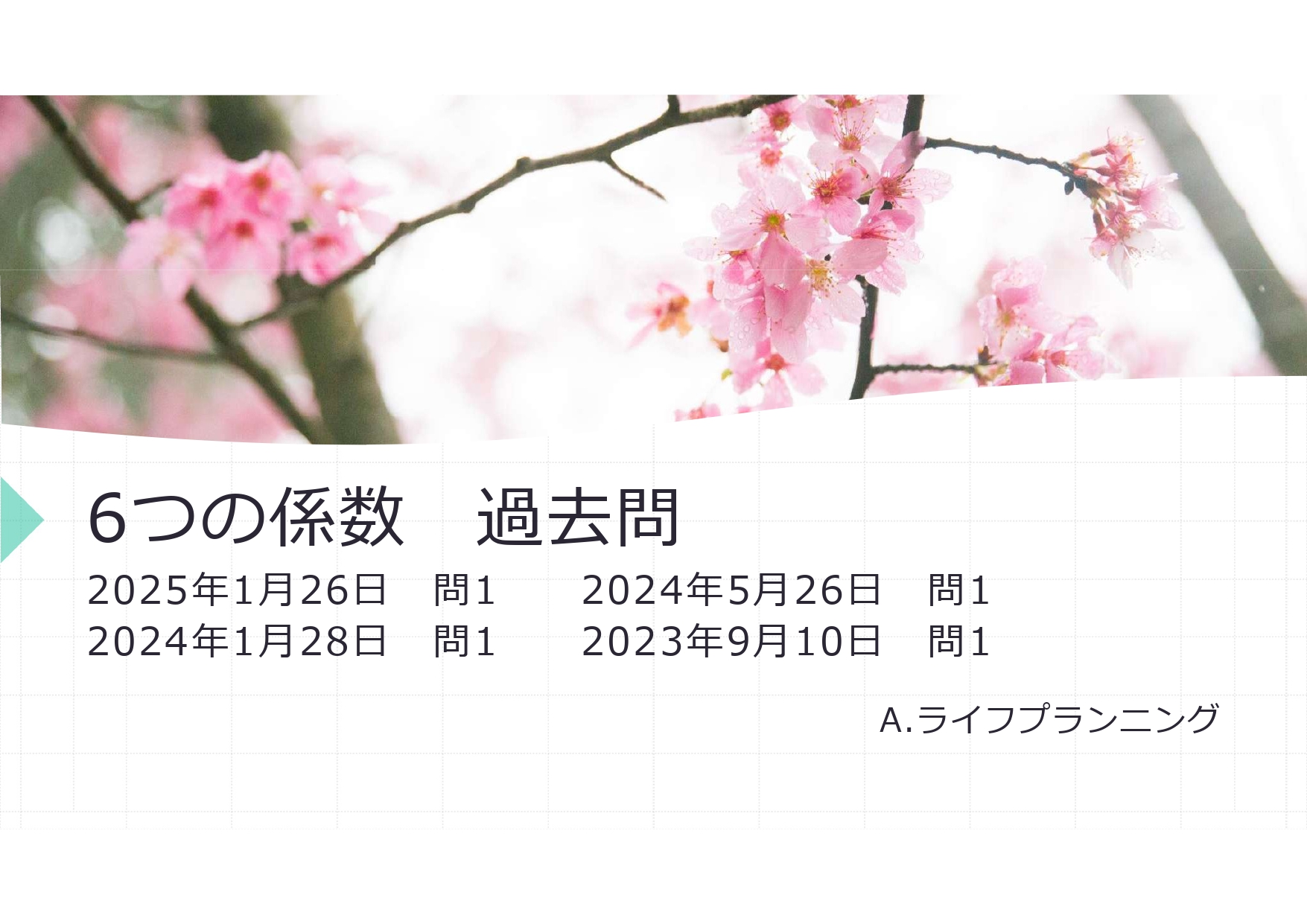
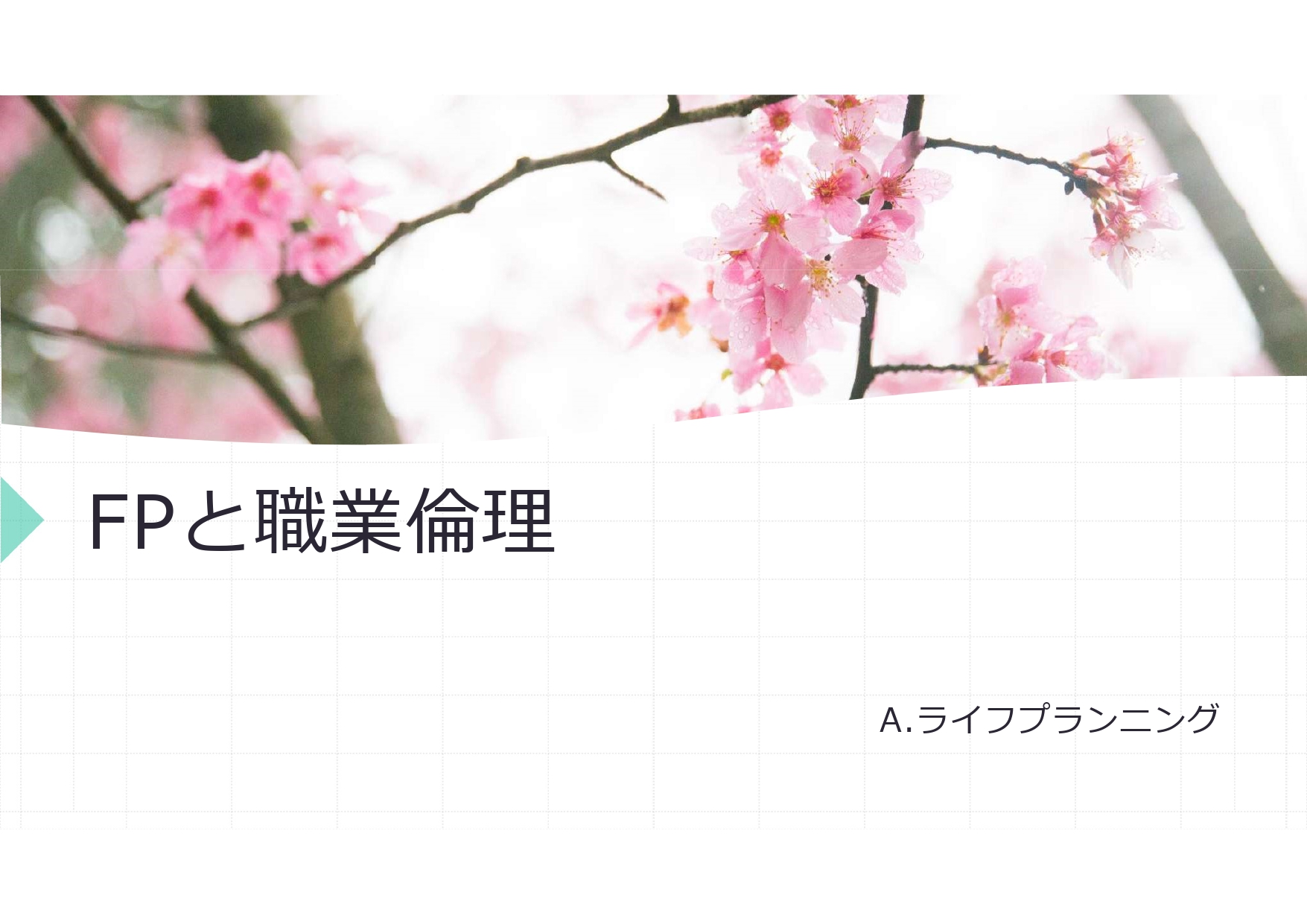
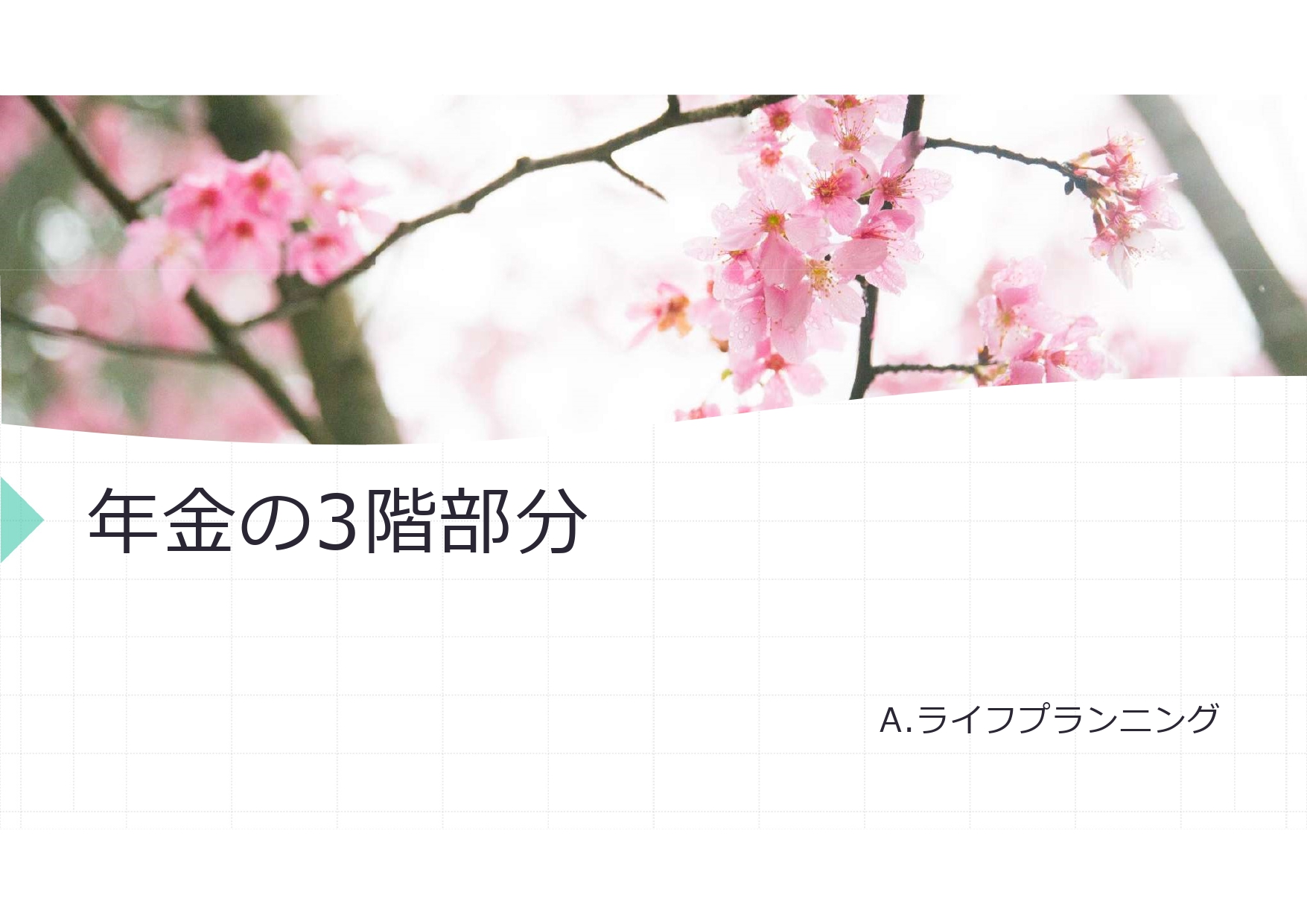

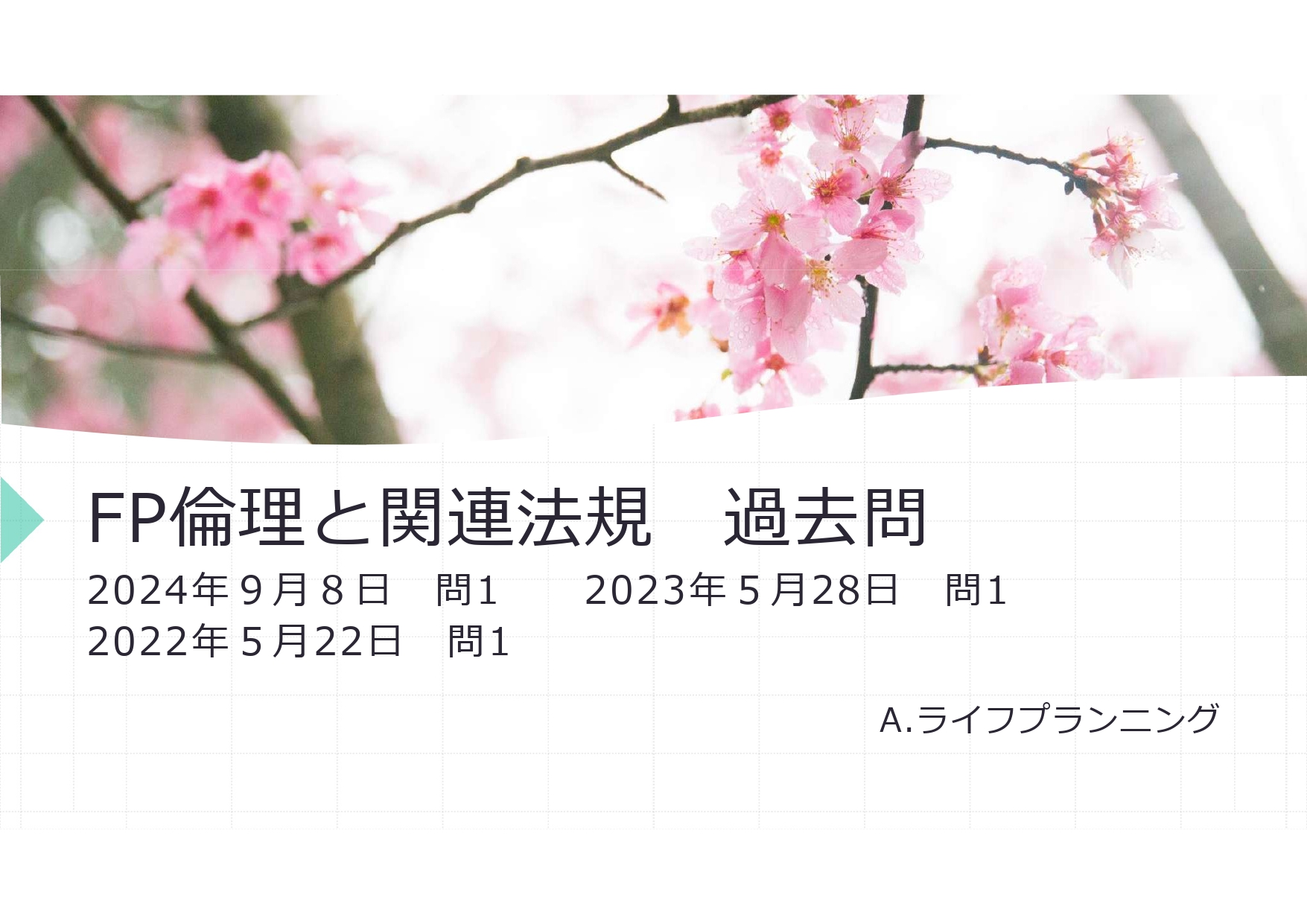


コメントを残す