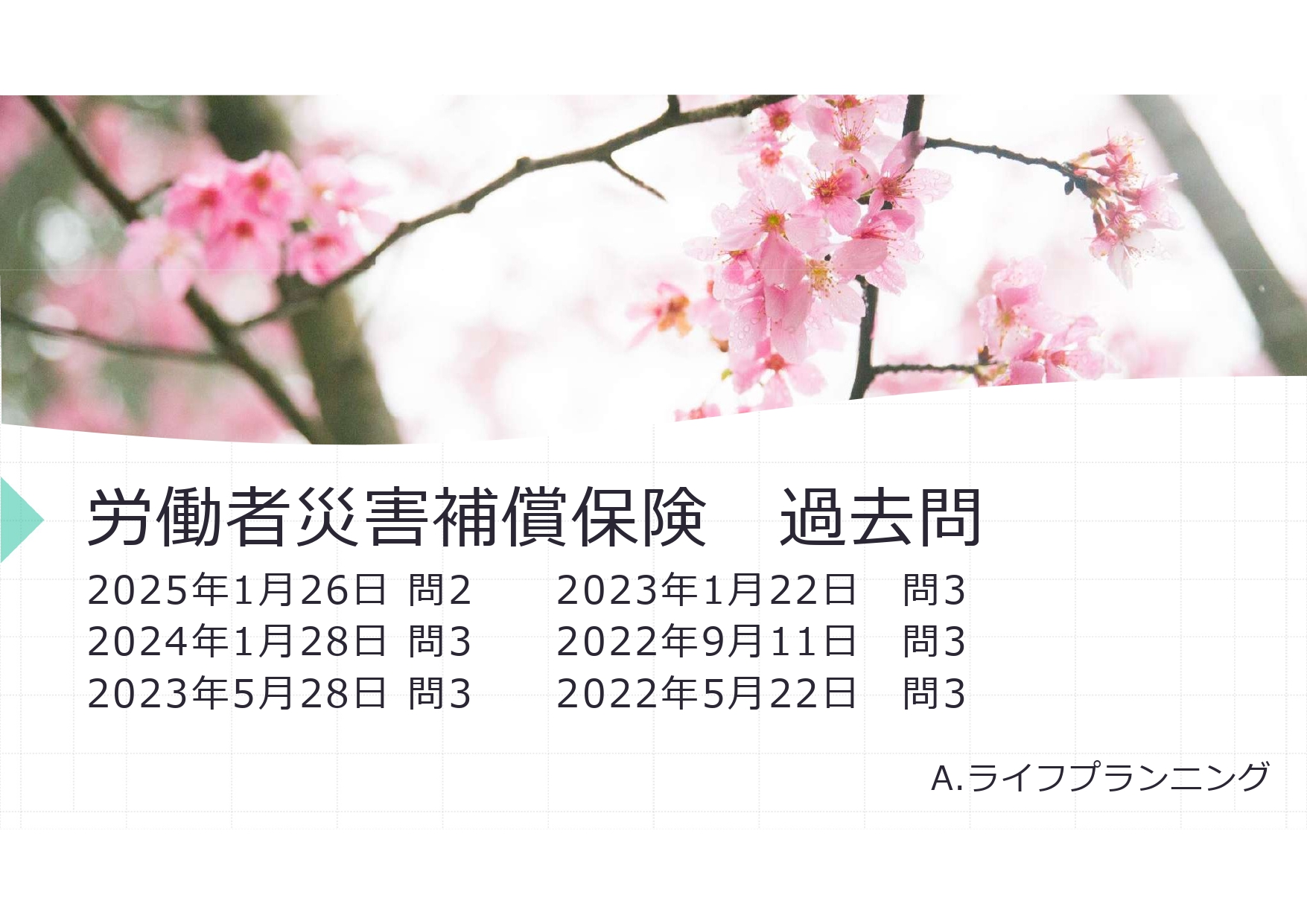
労働者災害補償保険 過去問
労災保険の問題も、FP1級学科試験基礎編では頻出の問題です。
労災保険というのはニュースで見ることはあると思いますが、なかなか身近に体験したことのある方は少ないかもしれません。
しかし、私生活同様、勤務時間内においても、予期せぬアクシデントに会うことはあります。
それによって、負傷、疾病、死亡した場合には「労働者災害補償保険」を使うことになります。
この労災保険は、正社員、パート・アルバイト、契約社員、派遣社員、日雇労働者などすべての労働者が対象です。
労災保険は細かく分かれ、傷病等級、障害等級により、受けられる給付の日数がさらに細かく分かれており記憶することはかなり困難です。
しかし、この日数や給付率など本当に学科試験ではよく出題されます。
そして、私は苦手でした。労災の補償内容や等級と、障害年金の補償内容や等級がごっちゃになってしまい、覚えるのに苦労しました。(今でも混在しています。)
それでは、一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>から問題を紹介し、私なりの説明をしていきたいと思います。
2025年1月26日 問2
| 労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 業務中に会社の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養補償給付については、一部負担金は徴収されないが、通勤途中に駅の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養給付については、原則として一部負担金が徴収される。 2) 労働者が業務上の傷病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の80%相当額が支給されるが、所定の要件を満たす場合、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が休業補償給付に上乗せして支給される。 3) 業務上の傷病による療養のために休業し、休業補償給付を受けている労働者について、当該傷病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合に、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当しないときは、休業補償給付の支給が打ち切られる。 4) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、3級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。 |
正解1
仕事中にケガをしても、職場に申し訳ないからだまっていたこととが過去にはあるな。もう20年くらい前の話だけど、その後、何もなかったからよかったけど、今、思えば、隠さず正直に話しするべきだったけどね。
1)これは定番の問題だね、業務中は個人負担なしだけど、通勤災害は負担金があるよ。よってこれが正解、本番では1)で選択できたら2)以降は読まなくてもいいかもしれないけど、精神安定剤のつもりで読んで確信するのも、ありだね。
2)休業(補償)等給付60%と休業特別支給金20%で合わせて80%支給されるよ。
3)休業補償給付は療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合には継続されると思うよ。障害の程度が所定の傷病等級に該当するときは傷病補償年金へ移行するよ。
4)ややこしいけど、障害等級の話が混在しているね。もうちょっと勉強してから、改めて説明するよ。
2024年1月28日 問3
| 労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 派遣労働者が派遣先で業務災害により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適用事業とされ、派遣労働者が通勤災害により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。 2) 数次の請負によって行われている建設の事業において、下請け事業者に雇用される労働者が業務災害により負傷した場合、原則として、下請け事業者が営む事業が労災保険の適用事業とされる。 3) A社およびB社に雇用される複数事業労働者が、脳・心臓疾患や精神障害を発症した場合、A社またはB社の業務上の負荷を個別に評価して業務災害に当たらないときは、両社の業務上の負荷を合わせて総合的に評価して業務災害に当たるかどうか判断される。 4) C社およびD社に雇用される複数事業労働者が、C社で就業中に業務災害により負傷した場合、C社のみの賃金額に基づき算定された給付基礎日額を基礎として保険給付が行われる。 |
正解3
複数事業労働って聞いたことあるけど、未経験だね。派遣や下請けなんかはニュースで知ることもあるけど、なんとなくしかわからないな。
1)派遣社員はあくまで派遣元の在籍なんだよね。よって労災適用も派遣元だね。
2)建設業における労災は、下請け、孫請けなどあるけど、元請けの労災が適用されるよ。
3)複数事業労働者の場合2社トータルで労災認定ラインを評価するよ。よってこれが適切だね。
4)全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、労災保険の給付額を算定するように近年変更になったよ。
2023年5月28日 問3
| 労働者災害補償保険の保険給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における労働者は、複数事業労働者ではないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 労働者が業務上の傷病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給され、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。 2) 休業補償給付の支給を受けている労働者について、療養の開始後1年6カ月を経過しても当該傷病が治らず、その傷病の程度が傷病等級1級から3級に該当する場合は、休業補償給付の支給に代えて傷病補償年金が支給されるが、傷病等級1級から3級に該当しない場合は、引き続き休業補償給付が支給される。 3) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級から7級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、8級から14級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。 4) 遺族補償年金の支給を受けることができる遺族の範囲は、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であるが、配偶者は年齢または障害の要件は問われない。 |
正解4
労災の問題って、障害の問題と等級とかがごっちゃになるんだよね。あと1級の障碍者手帳を持ってるからといって、障害年金の1級を受けれるわけじゃないってのも、よくわからないね。
1)、2)は設問の通りで、そのまま覚えることをお勧めするよ。
3)の障害が重度(1~7級)と軽度(8~14級)は、何級からが重度なのかという問題もありえるので記憶しておく必要があるね。
4)設問の最後に配偶者は年齢または障害の要件は問われない。とあるけど、これは妻の場合で、夫の場合は年齢や障害の要件が問われるよ。
2023年1月22日 問2
| 労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 労働者が勤務先から帰宅途中に通勤経路から逸脱し、スーパーで日用品を購入後、通勤経路に戻ってから負傷した場合、その逸脱・中断が日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合、その負傷は通勤災害に該当する。 2) 労働者が出張先から帰宅途中に負傷した場合、出張の過程全般について事業主の支配下にあり、積極的に私的行為を行うなど特段の事情がない限り、その負傷は通勤災害に該当する。 3) 派遣労働者が、派遣先で生じた業務災害により療養補償給付を受けようとする場合、派遣先の事業を労働者災害補償保険の適用事業として、療養補償給付に係る請求書に派遣先事業主の証明を受ける必要がある。 4) 複数の会社に勤務する複数事業労働者の休業補償給付の額は、原則として、業務災害が発生した勤務先の賃金に基づいて計算した給付基礎日額の 100 分の 60 に相当する額となる。 |
正解1
通勤災害にあたるかどうか?という判断が求められるね。
また、派遣労働者や複数事業労働者についても問われてるね。
1)通勤途中の日常生活上必要な行為は通勤災害と認められるという事例だね。これは食料品の買物、通院、親族の介護などが該当するね。よってこれが適切。
2)出張中は業務中とみなされ、通勤でなく業務災害にあたるね。
3)派遣労働の場合、適用されるのは派遣元事業主の証明を受ける必要があるよ。あくまで雇用関係は派遣元と結んでいるからね。
4)複数事業労働者は全ての就業先の賃金の合計を基に金額を算定するよ。
2022年9月11日 問3
| 事業主が同一でない複数の事業所において雇用される労働者に係る労働保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 1つの事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)で労災認定できない場合であっても、複数の事業所の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できる場合、労働者災害補償保険から保険給付が行われる。 2) 複数の事業所で雇用される労働者が、そのうち1つの事業所において業務上の事由により負傷した場合、労働者災害補償保険の給付基礎日額は、当該労働者を雇用する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として算定される。 3) 2つの事業所で雇用される65歳以上の労働者において、各事業所では1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であるが、2つの事業所の1週間の所定労働時間を合計すると20時間以上となる場合、所定の要件を満たせば、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。 4) 2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢被保険者となった65歳以上の労働者は、そのうち1つの事業所を離職しても、他方の事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。 |
正解4
複数事業労働者についての問題だね。これからは定年退職した方が働かれたり、副業をする方が増えて、こういうパターンが増えるのかもしれないね。
1)~3)はよく出題されるパターンなので覚える必要があるね。
4)はちょっと難しいけど雇用保険の高年齢被保険者の資格は失うよ。ちょっと注意が必要だね。
2022年5月22日 問3
| 労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 労働者災害補償保険の適用労働者には、適用事業に使用され賃金を支払われている者のうち、日雇労働者や1カ月未満の期間を定めて使用される労働者は含まれない。 2) 一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客の事業または貨物の運送の事業を、労働者を使用しないで行うことを常態とする者(個人タクシー業者や個人貨物運送業者)は、通勤災害に関する規定の適用を受けない。 3) 労働者が業務上の負傷または疾病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業4日目から休業補償給付が支給されるが、休業3日目までは、事業主が労働基準法の規定に基づき、その労働者の平均賃金の60%の休業補償を行わなければな らない。 4) 事業主と雇用関係にある労働者が、情報通信機器を活用して、労働時間の全部または一部について、自宅で業務に従事する在宅勤務を行う場合であっても、当該労働者は労働者災害補償保険の適用労働者となる。 |
正解1
労災の問題も慣れてきたら、読んだ瞬間にわかる問題もあるね。
1)これが間違いだね、労災はパート、アルバイトや日雇労働者も含まれるよ。
よって以下は正しい説明だけど念のため説明するね。
2)個人タクシーに通勤災害は無いんだね。
3)労災の場合、3日目までは事業主が60%支給するんだね。しかし通勤災害は話は別だよ。
4)これはコロナなどで在宅ワークをする方などを想定した設問だろうけど、これについても労災の対象となるということだね。
どういう労災が考えられるかは、ちょっと調べておくね。




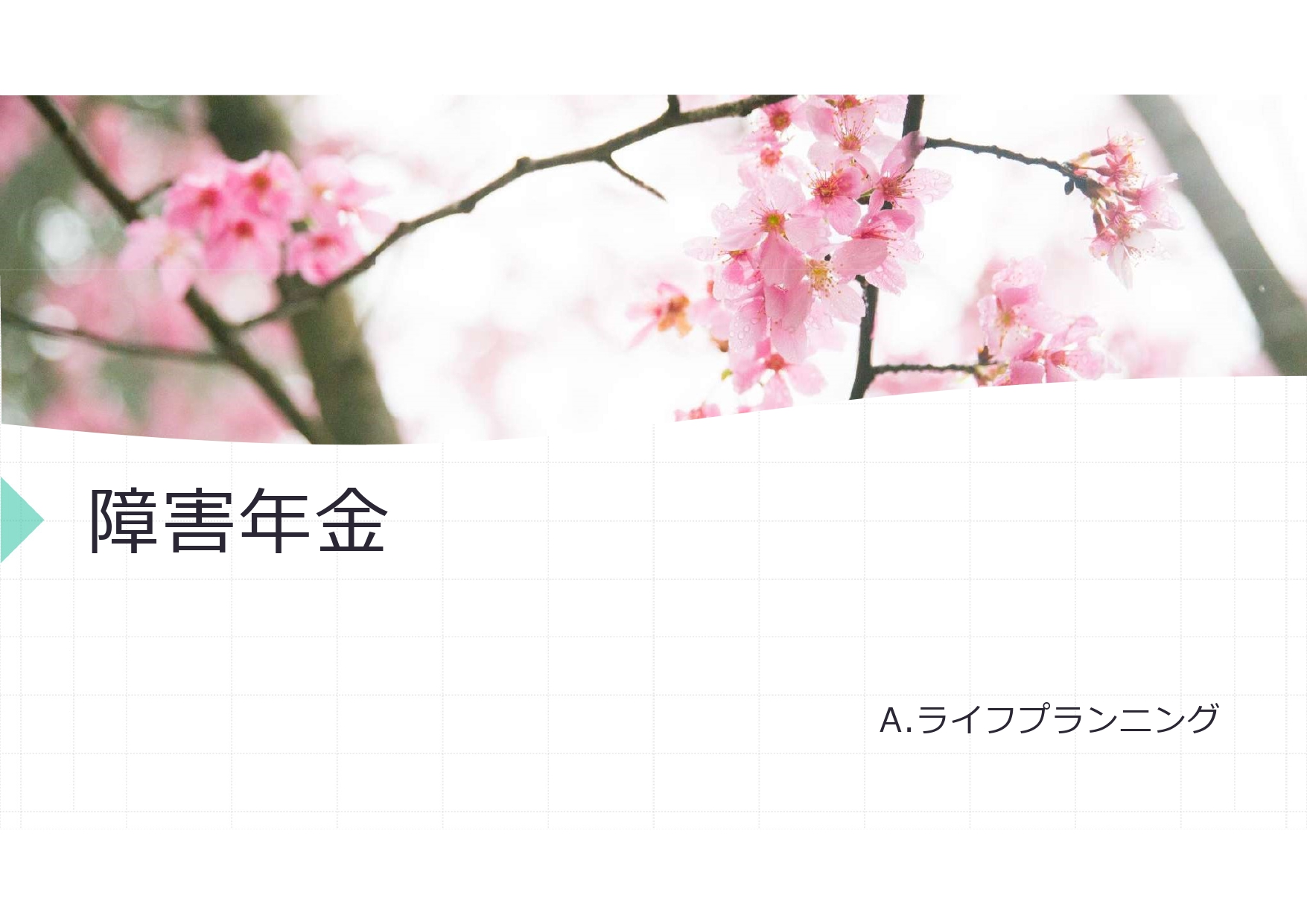
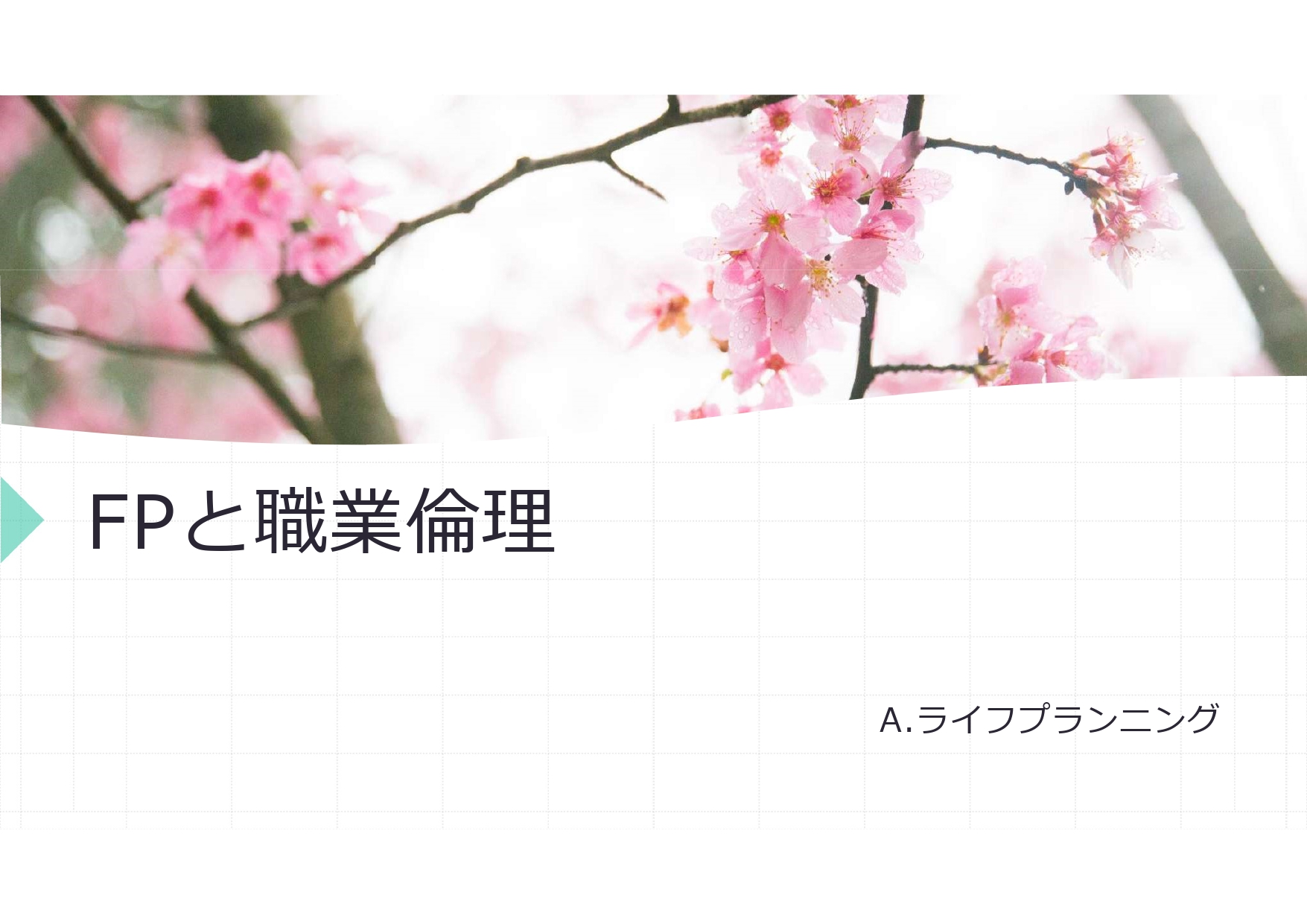

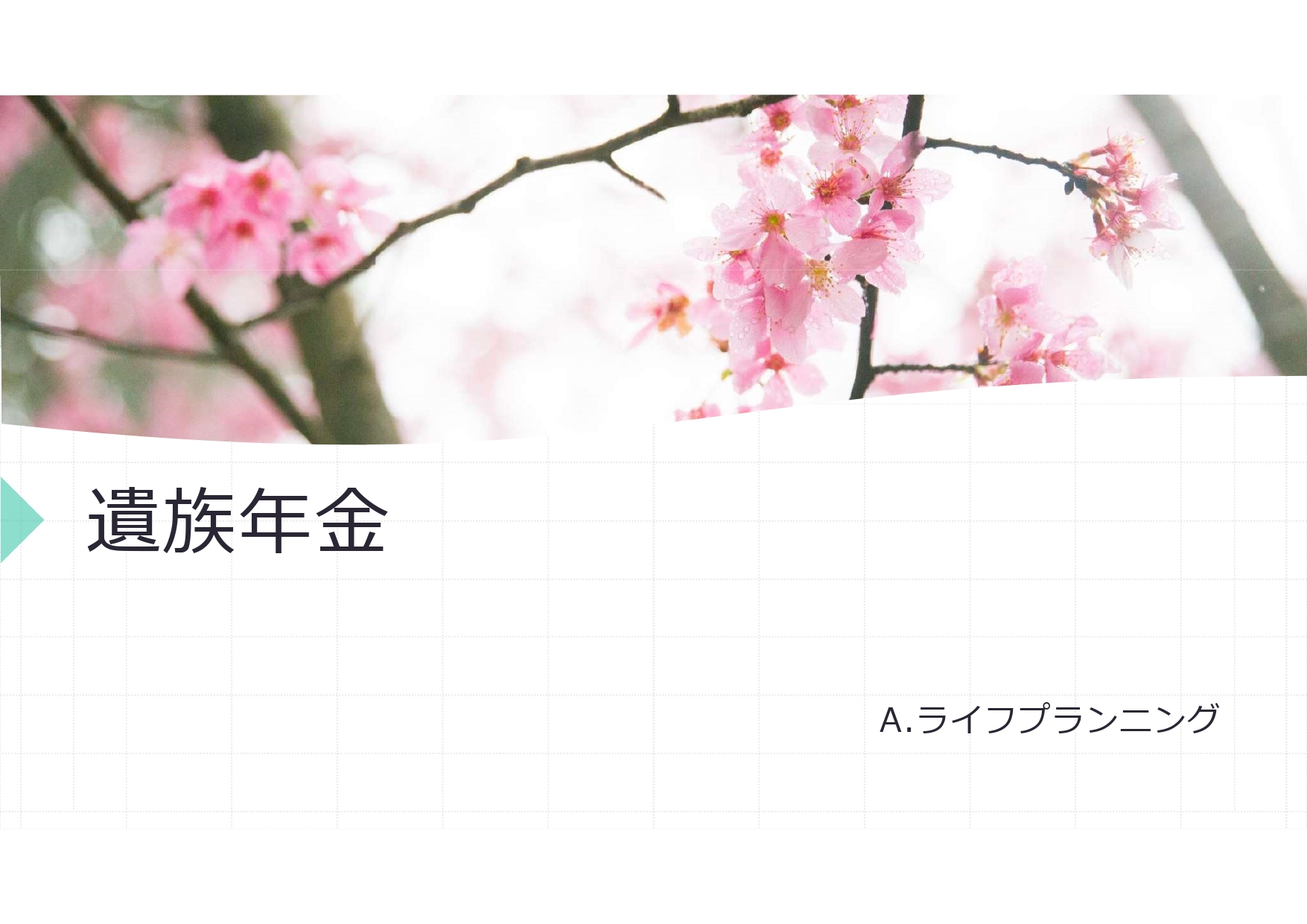
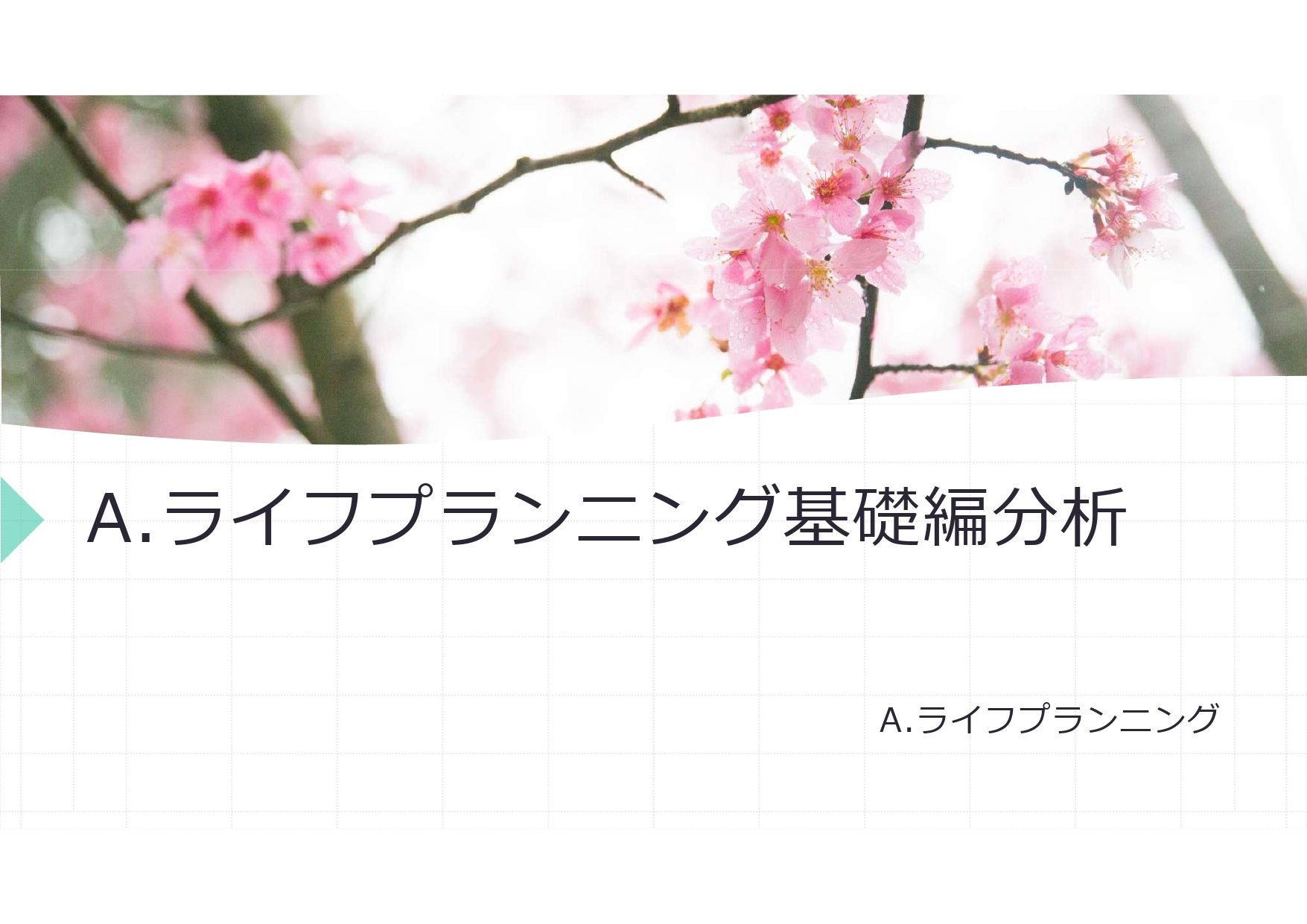
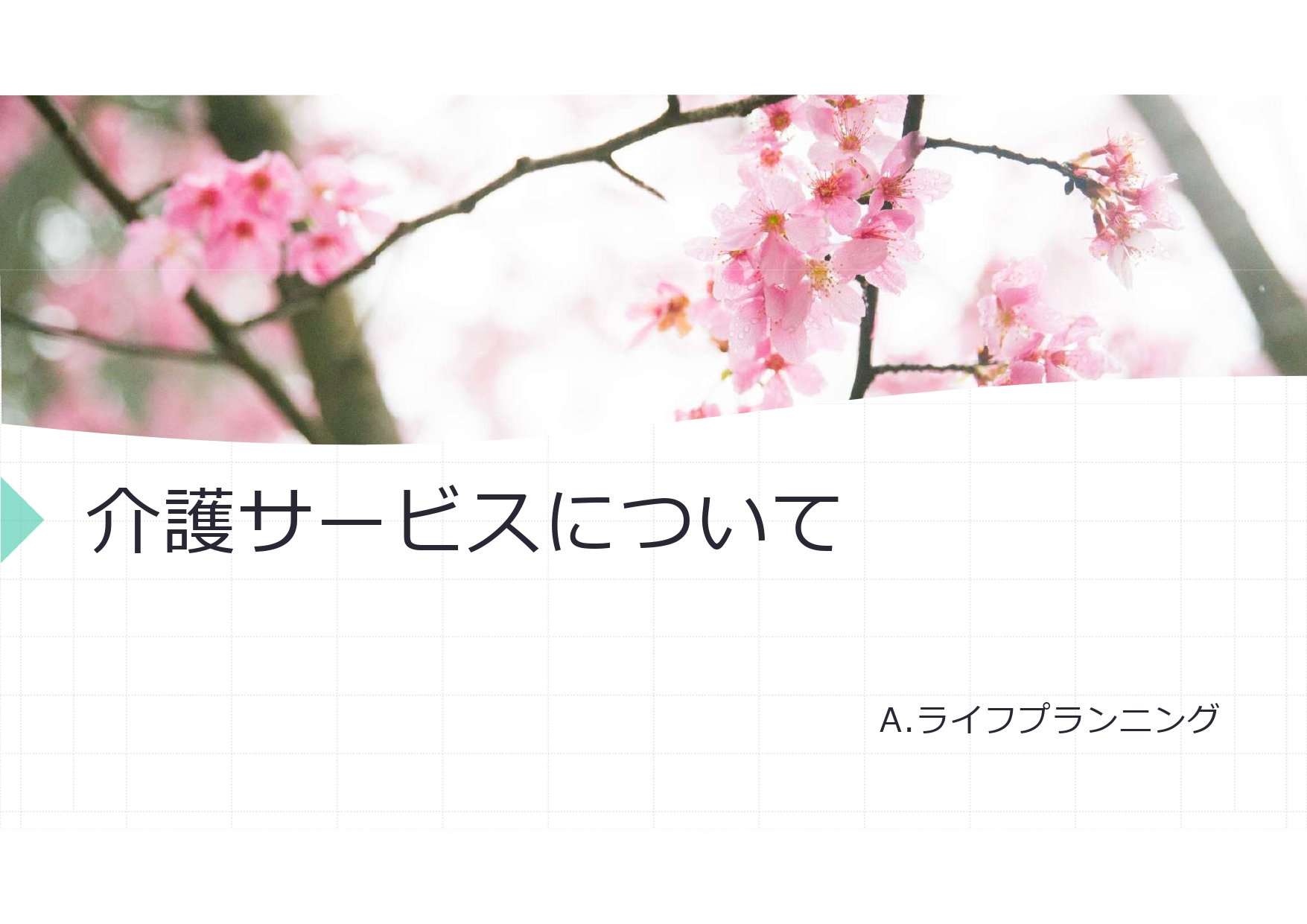
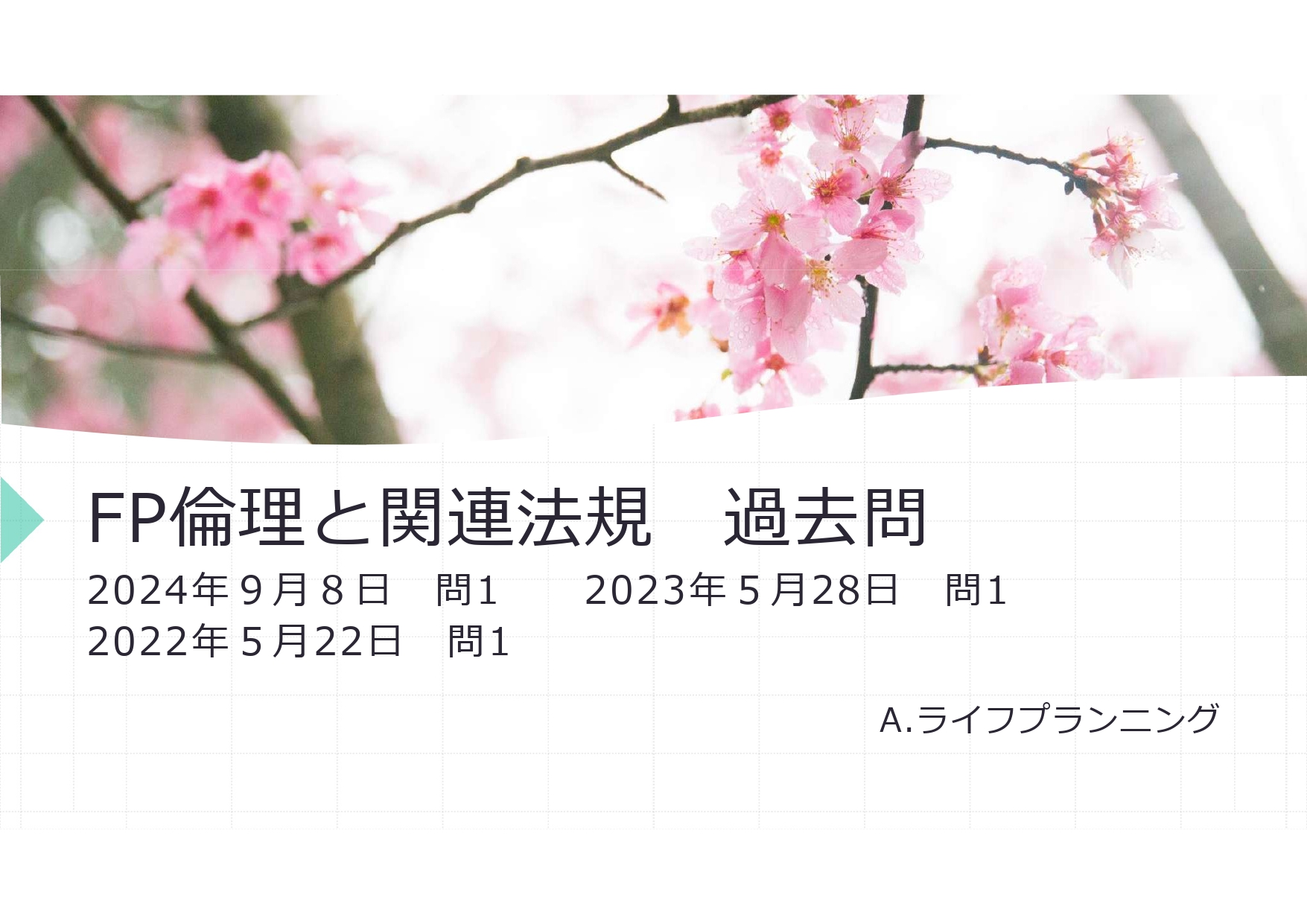

コメントを残す