
宅地建物取引業法 過去問
FPを勉強されている方は、同時に宅地建物取引主任者の資格取得を目指される方が多いと思います。
FPは1級まで取得しても専有業務がありません。それに対して宅建士には占有業務があります。
重要事項の説明
重要事項説明書への記名・押印
契約書面への記名・押印
などです。
FP1級試験においても、学科試験で問われる頻度は低いですが、実技試験Part2において、
最後に「今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?」という質問があり、ほとんどの場合、宅建士が登場します。
それは一旦置いておいて、基礎編でも数回に1度、出題されることがあり、不動産分野は難易度の上下が激しいので、確実に得点しておきたい問題となります。
質問される論点も限られ、覚えてしまえば得点できる問題だと思います。
この分野も出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>として問題を転載しております。
2025年1月26日 問35
| 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。 (a) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができない。 (b) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその手付を買主に返還することで契約を解除することができる。 (c) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の20%を超えるときは、当該売買売買代金の額の20%を超えるときは当該売買契約自体が無効になる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1
本当に宅建の試験みたいだ。文章のニュアンスの微妙な違いを読み取らないといけないんだよね。
(a) 正しい選択肢です。
(b)宅地建物取引業者はその手付の倍額を買主に返還する必要があるよ。
(c) 売買代金の額の20%を超えるときは超えた部分が無効になるのであって、契約自体は有効だよ。
よって正解は(a)だけなので、1) 1つ だよ。
2024年5月26日 問34
| 宅地建物取引業法上の重要事項の説明および同法第37条の規定により宅地または建物の売買または交換の契約を締結した場合に交付する書面(以下、「37条書面」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 宅地建物取引士は、重要事項の説明に際して、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その説務所だけでなく、事務所以外の場所やオンラインで行うことができる。 2) 重要事項説明書に記名し、その内容を説明する宅地建物取引士は、事務所等に置かれている専任の宅地建物取引士以外であってもすることができる。 3) 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面を交付しなければならない。 4) 宅地建物取引業者が37条書面を交付するにあたり、宅地建物取引士がその書面に記名し、その内容を説明しなければならない。 |
正解4
35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)の違いを理解していないといけないね。
35条書面(重要事項説明書)は説明も署名も宅建士がしないといけないけど、37条書面の内容の説明は宅建士以外が行ってもいいよ。
よって不適切なのは、4)だね。
2023年5月28日 問35
| 宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。 1) 宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主が売主に対し契約不適合に基づく担保責任を追及するためには、当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを買主が証明しなければならない。 2) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合について買主が売主に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は無効となる。 3) 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。 4) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、手付金を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、宅地建物取引業者が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることができる。 |
正解2
宅地建物取引業者が、自ら売主となるとか、相手が宅地建物取引業者だった場合など微妙に違うんだね。
1)買主は売主の責めに帰すべき事由を証明する必要は無いよ。
2)契約不適合の通知期間は目的物の引渡しから2年以上とすることが必要なので2年ちょうどでも有効だよ。
3)重要事
項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならないのは買主に対してであって、売主に対しては交付・説明は必要ありません。
4)これは適切ですね。ちなみに売主から解約する場合は手付金の倍額を現実に提供する必要があるということも併せて覚えておくといいよ。
2023年1月22日 問36
| 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、宅地の売買の媒介に関して売主および買主の双方から報酬を受け取る場合、売主または買主の一方から受け取ることのできる報酬の額は、宅地の売買金額が400万円超の場合、「売買金額×3.3%+6万6,000円」が限度となる。 2) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、建物の賃借の媒介に関して貸主および借主の双方から報酬を受け取る場合、貸主または借主の一方から受け取ることのできる報酬の額は、借賃額(消費税を除く)の1カ月分の1.1倍が限度となる。 3) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取引業者である場合、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付すれば、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。 4) 宅地建物取引業者は、建築後、使用されたことのある建物の売買または交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を契約の依頼者に交付しなければならない。 |
正解2
宅地建物取引業者の報酬の額とか覚えないといけないの?
1)細かいけど覚えておいた方がいいね、ちなみに200万円以下の場合は5%がかかるよ。
2)これも日本語がややこしいね、受取る報酬は貸主、借主合わせて賃貸1か月分+消費税だね。これが不適切。
3)、4)は正しいよ、建物状況調査(インスペクション)という用語は覚えておくといいよ。
これをする人をホームインスペクターというよ、併せて覚えてね。





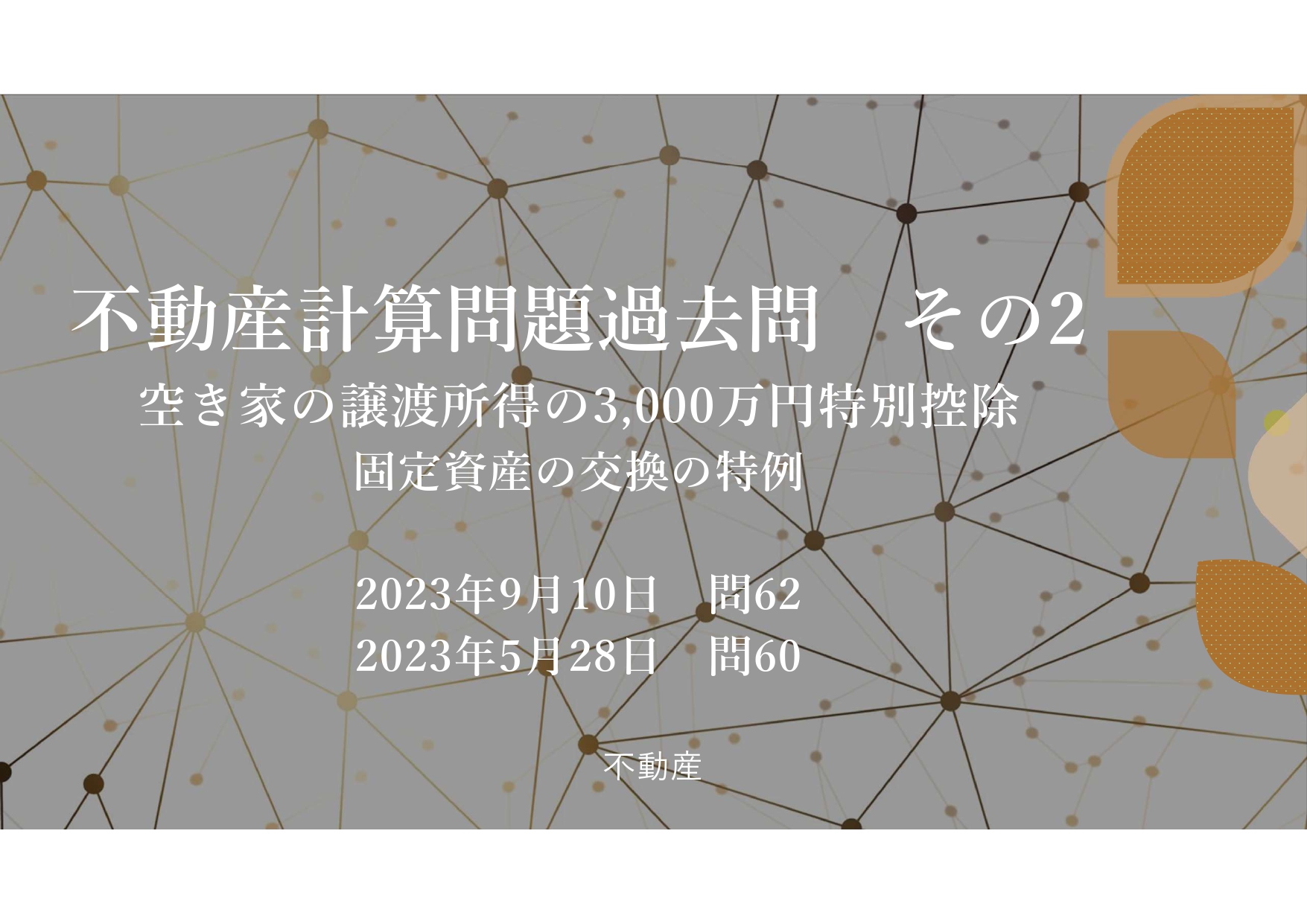

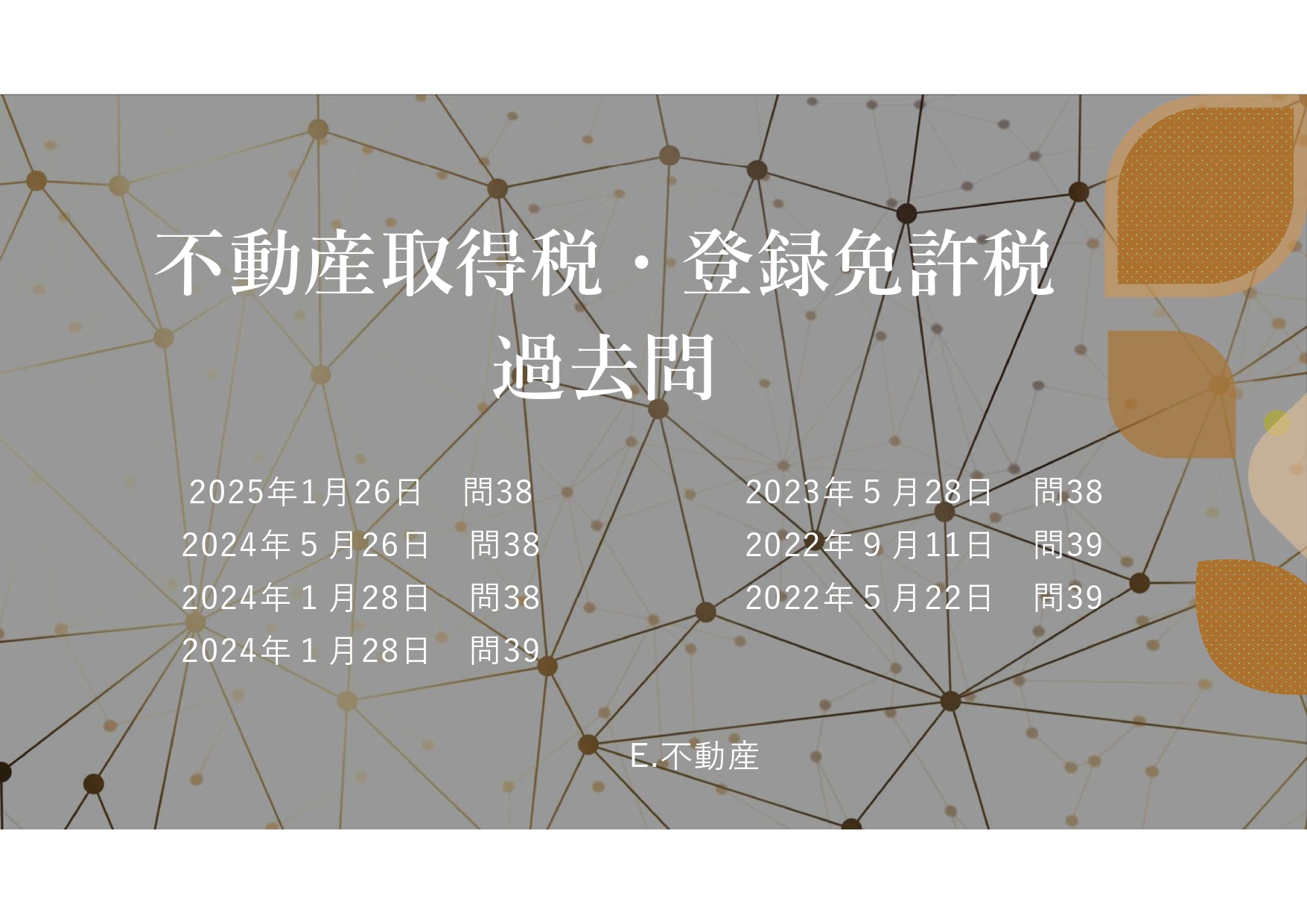

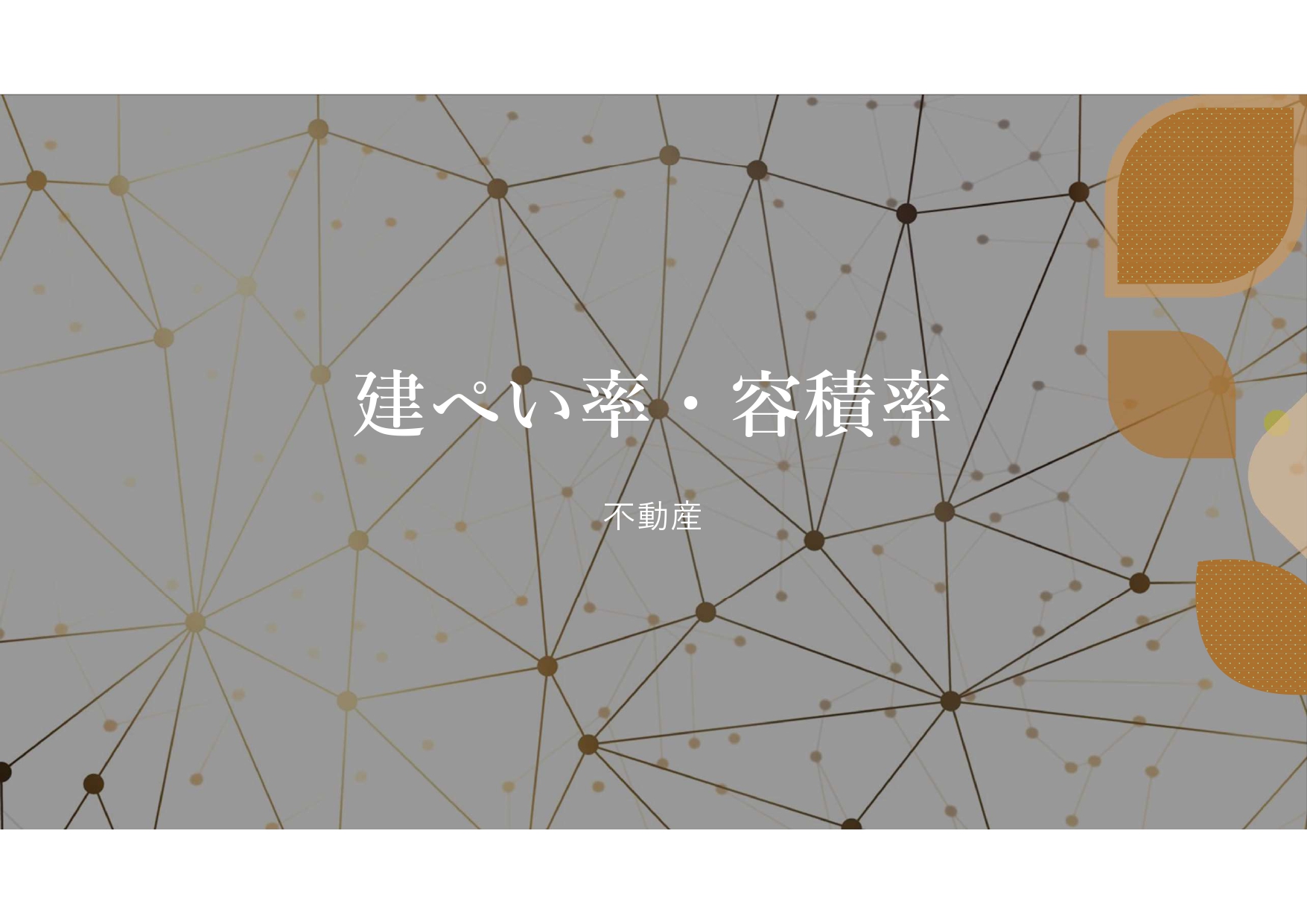

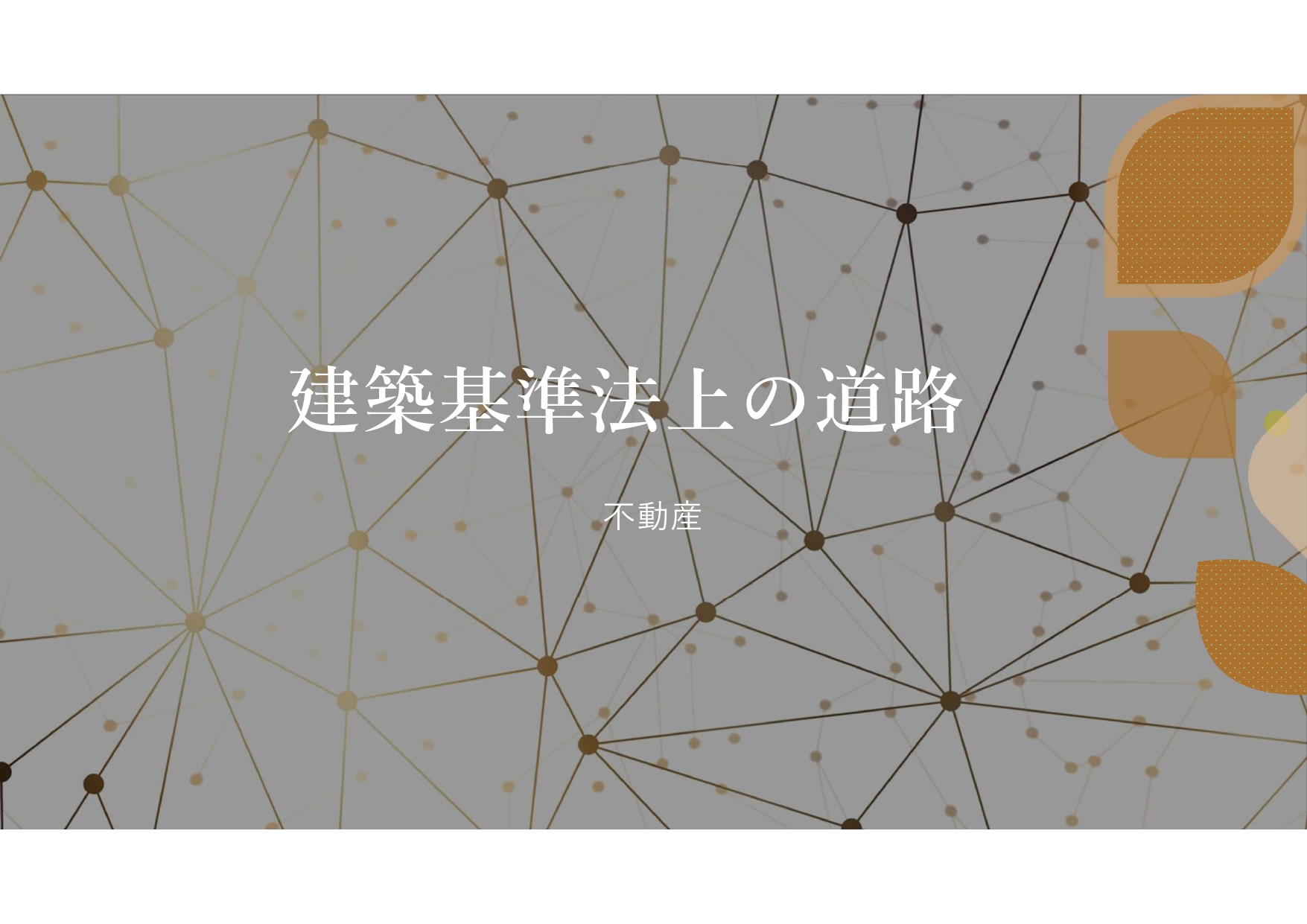
コメントを残す