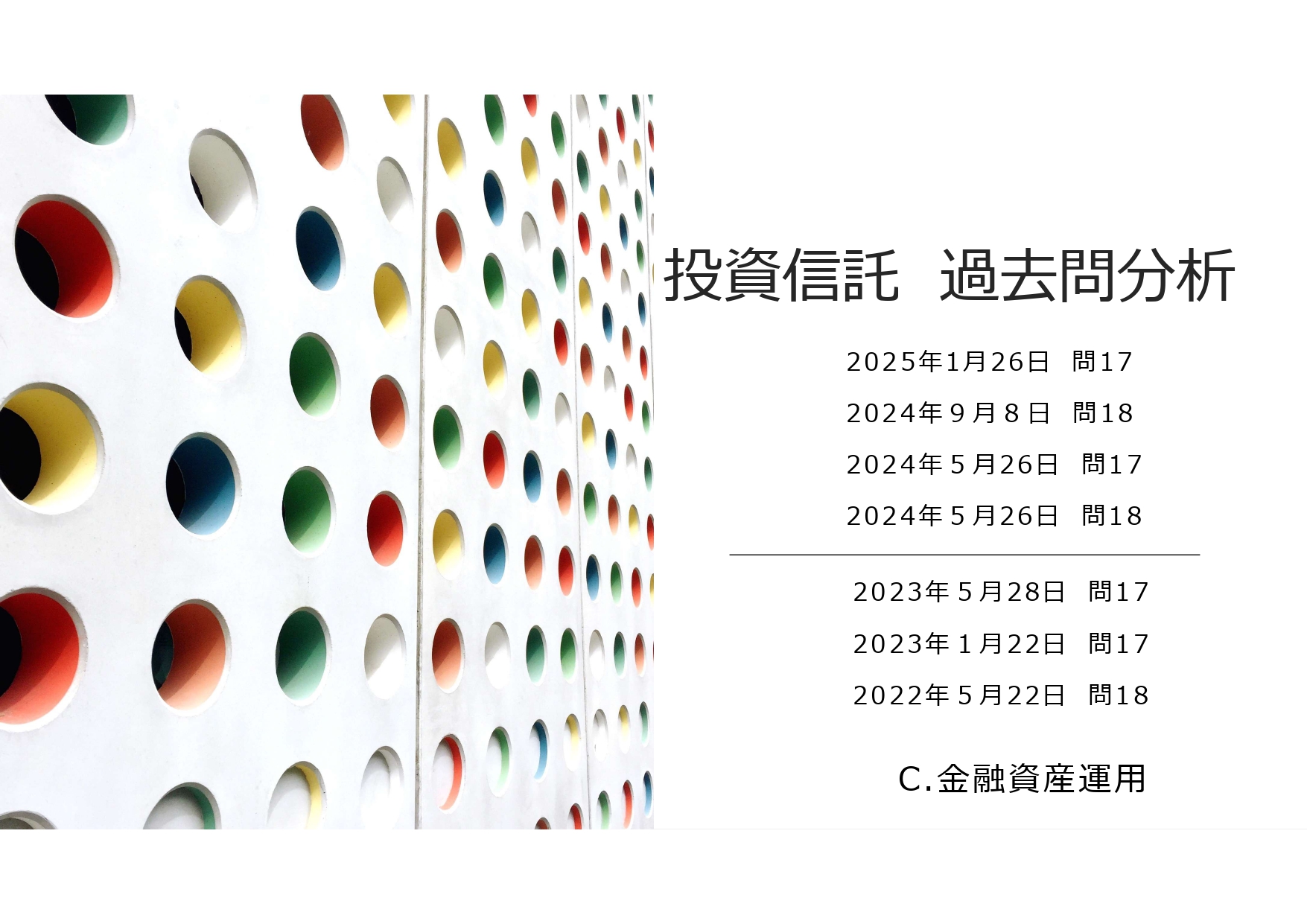
投資信託 過去問分析
昭和生まれの私にとっては、蓄えは銀行預金と相場は決まっていたように思うのですが、ゼロ金利時代に突入し、物価も上がらないが、銀行預金には利息がほとんどつかないという状態が恒常化していました。
株式投資は当たれば大きいが、失敗すれば資産を減らすというリスクが伴うため、興味があっても株式の個別銘柄に投資する勇気がなかなか沸かないものです。
投資信託は、株式銘柄の選定をプロが行って、個人投資家はリスクをなるべく減らして、少しでもリターンを得ようという商品です。
東京証券取引所などに上場している株式数は令和7年2月現在、4,000社以上に上りますが、
投資信託は株式投資信託だけでも5,500以上に上り、なかなか、一般の投資家が優劣を見極めて投資判断することは難しいように思います。
FP1級基礎編では、投資信託の問題が頻出です。
投資を検討している方に対して、判断基準を提供することは、FPが行えることだと思います。ただし、一般的な説明に留めるよう注意が必要です。
それでは、過去問の解説を開始します。
こちらもすべて、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となります。
2025年1月26日 問17
| 投資信託の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) ファミリーファンド方式の投資信託では、投資家がマザーファンドを購入することにより集まった資金を、国内外の株式や債券等を投資対象とする複数のベビーファンドに振り分けて運用が行われる。 2) ロング・ショート型の投資信託は、相対的に割安と考えられる銘柄を買い建てるとともに、相対的に割高と考えられる銘柄を売り建てることで、市場の変動にかかわらず、収益の獲得を目指すものである。 3) ブル型の投資信託は、原指標の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指標に連動する運用成果を目指すものであり、市場の上昇局面ではより高い収益率を期待することができる。 4) 外貨建MMFは、主に外国の格付の高い公社債やコマーシャルペーパー等を投資対象として運用される外貨建ての投資信託であり、株式は投資対象とされない。 |
正解1
投資信託って金融機関のお勧めされるままに選んでたから、中身をよく見てなかったな。正直、「目論見書」も最初の1ページしか読んでないかも。
1)一般の投資家が購入するのは“ベビーファンド”であり、そのベビーファンドがマザーファンドに投資をする仕組みだね。
2)~4)は正しい表記だね。ブル(牛)は下から上に突き上げる、逆にベア(熊)は上から下に振り下ろす、というのを逆にしたひっかけもよくあるから注意が必要だよ。
2024年9月8日 問18
| 日本国内で設定された追加型の公募株式投資信託(委託者指図型投資信託)の基準価額等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 投資信託の基準価額は、原則として、毎日午前9時に公表され、その日に公表された基準価額で希望する受益権口数の売買注文を行うことにより、その日の売買が成立する。 (b) 米国市場に上場している株式を投資対象とする投資信託の基準価額の算出にあたって、その株式の価格は、原則として、基準価額を算出する日の前営業日の米国市場における終値で評価し、基準価額を算出する日の前営業日における為替相場で邦貨換算する。 (c) 信託財産留保額は、投資信託を信託期間中に換金する際に徴収される費であり、換金時の基準価額に所定の料率を乗じて算出された金額が投資信託委託会社の収入となる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解4
投資信託って種類も多ければ、取引する時の手数料なんかも複雑だね。
契約したときに、窓口の人に説明してもらってるんだろうけど、まったく頭に残ってない。
(a) 基準価額はその日の終値を基に、運用会社が決定するので注文時には確定していないんだね。
(b)外国資産を組み入れた投資信託は、翌営業日での基準価額で売買が成立するよ。
(c) 信託財産留保額は投資信託委託会社の収入とはならないよ。
よって正解は 4) 0(なし) だね。
2024年5月26日 問17
| 各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 特定寄附信託は、信託銀行等が寄附に関する契約を締結した公益法人等のなかから寄附先を指定することができる信託であり、特定寄附信託で運用した収益は非課税で、信託元本については寄附金控除の対象となる。 2) 暦年贈与信託は、あらかじめ委託者と受益者が定期の給付を目的とする贈与契約を締結して設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、毎年のあらかじめ決められた日に均等額が受益者に給付される。 3) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭だけでなく有価証券や不動産とする ことができる。 4) 遺言代用信託は、遺言書の保管や遺言の執行を信託銀行等に信託するものであり、委託者の生存中は委託者が第一受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が第二受益者となる。 |
正解1
これもややこしい、初めて知った用語もあるね。
1) は、特定寄附信託は、正解だね。
2) 暦年贈与信託は、あらかじめ金額を指定するのではなく、毎年、金額を指定する必要があるよ。
3) 後見制度支援信託は、信託する財産は金銭に限定されているよ。
4) この説明は遺言信託のものだね。名前が似ててややこしいね。
2024年5月26日 問18
| わが国における委託者指図型の契約型投資信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 委託者は、受益権の発行と募集、信託財産の運用の指図、目論見書や運用報告書の作成等を行う。 2) 受託者は、信託財産の保管・管理、委託者の運用の指図に従った運用の執行、投資信託約款の金融庁長官への届出の承諾等を行う。 3) 販売会社は、投資信託の募集の取扱い、分配金・償還金の支払の取扱い、目論見書・運用報告書の受益者への交付等を行う。 4) 受益者は、投資信託約款の変更に係る書面による決議において受益権の口数に応じて議決権を有しており、当該決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行われる |
正解4
これもまったくわからないけど、4)の4分の3以上ってのがいかにもひっかけっぽいね。
その通りだね、正しくは3分の2以上だね。たまたま、これは当たったけど、〇分の〇という問題は、区分所有法や相続でもよく出てくるから、間違えないように覚えることが大事だね。特に法定相続分の計算間違いなど命取りになるからね。
2023年5月28日 問17
| 各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 後見制度支援信託は、被後見人の生活の安定に資すること等を目的に設定される信託であり、信託契約の締結、信託の変更・解約等の手続があらかじめ家庭裁判所が発行する指示書に基づいて行われ、信託財産は金銭に限定されている。 2) 暦年贈与信託は、委託者が拠出した信託財産のうち毎年一定額を受益者に給付する旨の贈与契約書を作成して設定される信託であり、年間給付額は贈与税の基礎控除額である110万円が上限となる。 3) 生命保険信託は、委託者が保険会社と締結した生命保険契約に基づく保険金請求権を信託銀行等に信託し、委託者の相続が開始した際には、信託銀行等が保険金を受け取り、受益者に対してあらかじめ定められた方法により給付する信託である。 4) 遺言代用信託は、委託者の生存中は委託者が受益者となり、委託者の死亡後は委託者があらかじめ指定した者が受益者となる信託であり、あらかじめ指定した者に対しては、一時金による給付のほか、定期的に一定額を給付することも可能である。 |
正解2
各種信託商品の特徴は以前にも出てたんだね。
2) 暦年贈与信託は、基礎控除額である110万円までは非課税で贈与できるけど、それを超えて贈与することも可能だよ。
2023年1月22日 問17
| 投資信託のディスクロージャーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 交付目論見書は、投資者が直接的または間接的に負担することとなる費用について、購入時手数料の上限金額または上限料率、運用管理費用(信託報酬)の金額または料率に関する事項に加え、当該費用を対価とする役務の内容等を記載しなければならない。 2) 交付運用報告書は、日々決算型投資信託を除き、投資信託の決算期ごとに作成し、投資家に交付しなければならない。 3) 交付運用報告書は、運用経過の説明や今後の運用方針などのほか、一定の期間における当該投資信託の騰落率と代表的な資産クラスの騰落率を比較して記載することとされている。 4) 投資信託委託会社または販売会社は、運用報告書(全体版)について、投資信託約款に定められた電磁的方法により提供することができるが、投資者から当該運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付しなければならない。 |
正解2
交付目論見書、交付運用報告書など違いがよくわからないな。
2)運用報告書は、日々決算型投資信託を除きとあるけど、毎月決算型もあるね、日々決算型、毎月決算型は6か月に1度交付されるよ。
残りの選択肢は正しいね。
2022年5月22日 問18
| 投資信託の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) MRFは、格付けの高い公社債やコマーシャルペーパー等を投資対象としたオープン型の公社債投資信託であり、主に証券会社で行う有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的とした投資信託である。 2) ロング・ショート型ファンドは、株価の相対的な上昇が予想される株式を購入すると同時に、株価の相対的な下落が予想される株式を空売りすることで、株式市場の上昇・下落にかかわらず、収益の獲得を目指す投資信託である。 3) インバース型ファンドは、先物やオプションなどを利用して、基準となる指数の値動きを上回る投資成果を目指す投資信託であり、相場の上昇局面において、より高い収益率が期待できる。 4) ベア型ファンドは、原指標の変動率に一定の負の倍数を乗じて算出される指標に連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。 |
正解3
またも、意味わからない単語のオンパレードだ。
こういった問題は、あせらず用語の意味をしっかり理解することが大切だね。
3) インバース型ファンドのインバースって“逆の”という意味だから、相場の下落局面で上昇を狙うということになると思う。
残りの1)、2)、4)の選択肢は覚えて、次回以降、同じような選択肢が出てきたときに備えるといいよ。




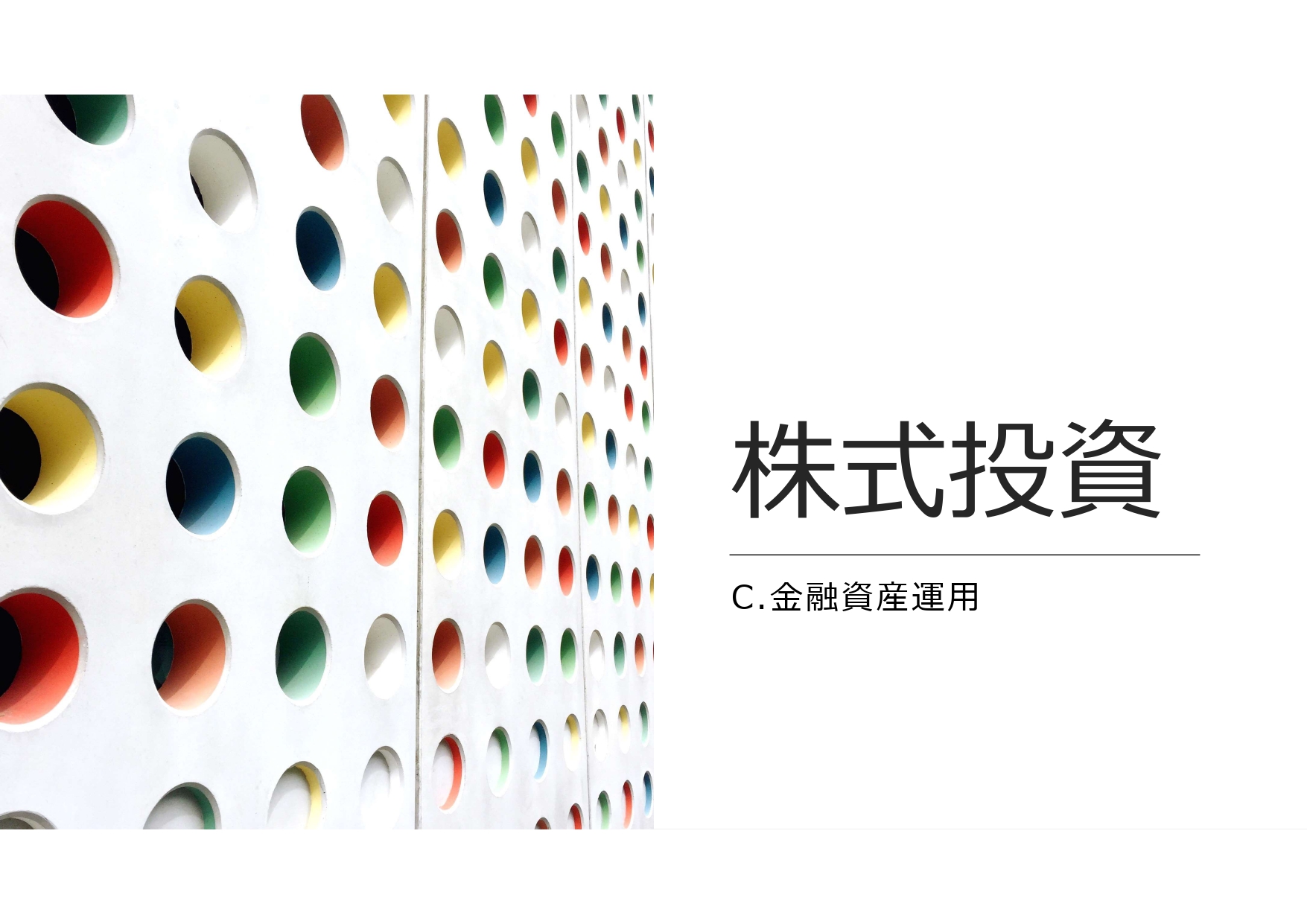
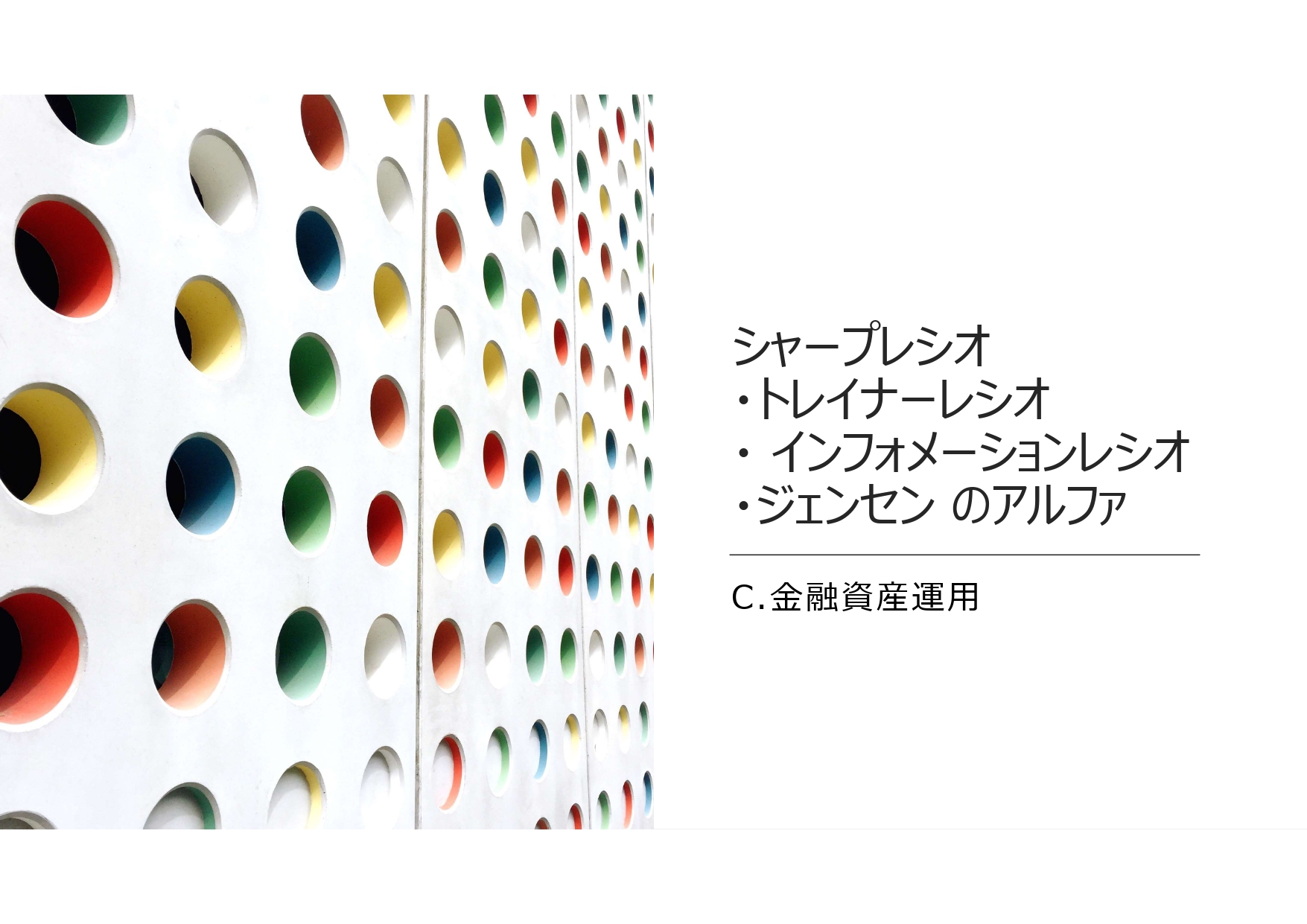
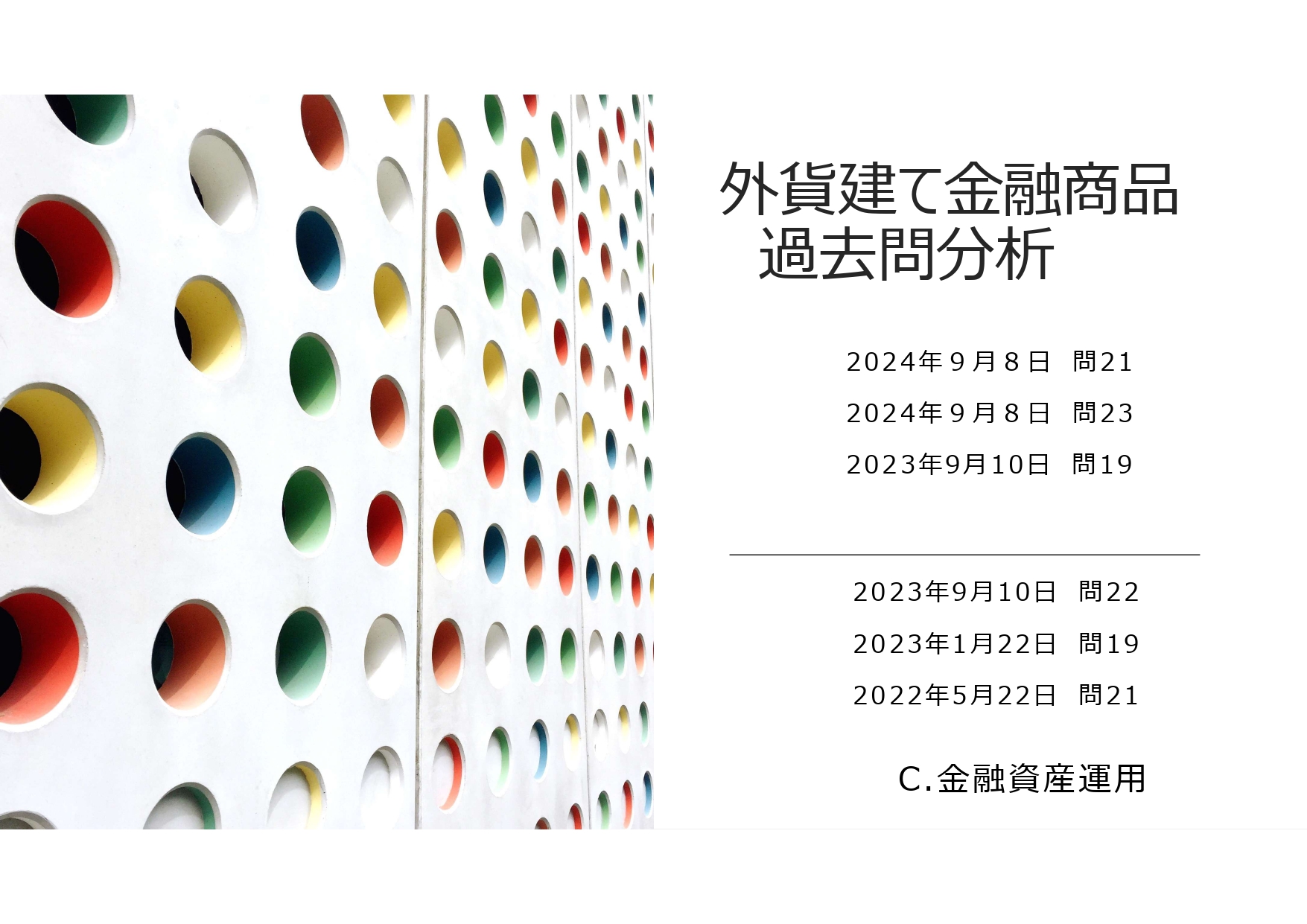
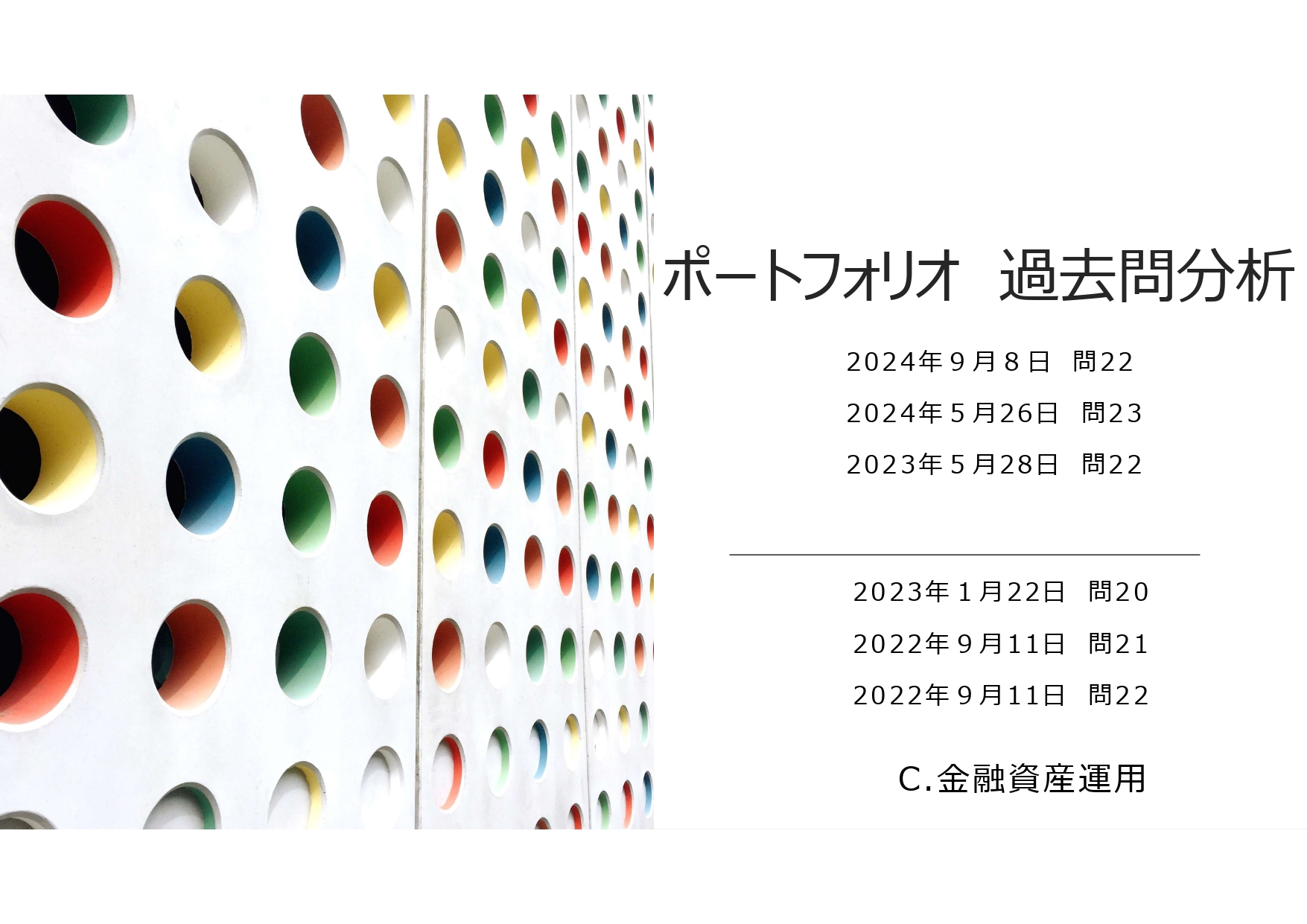
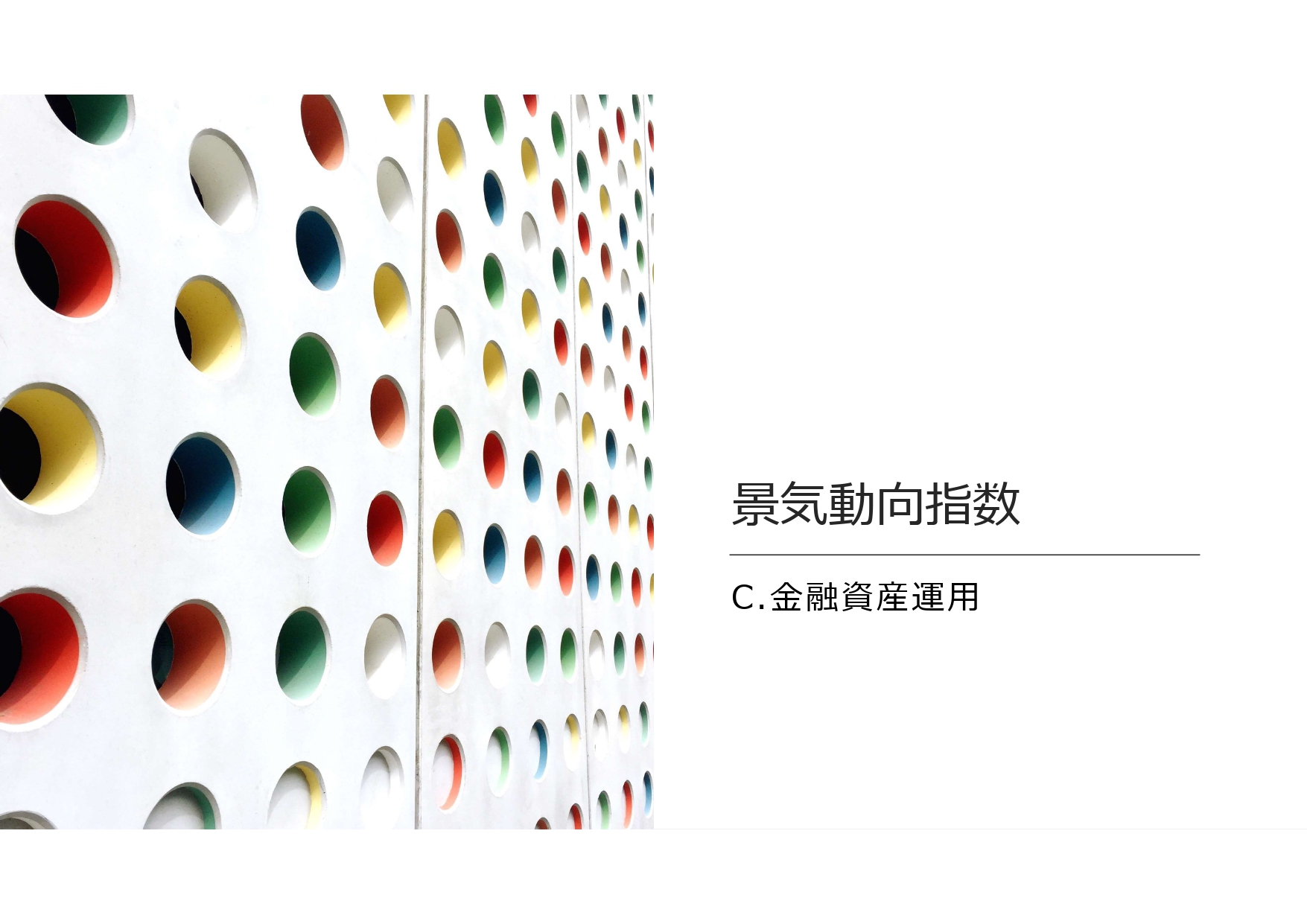
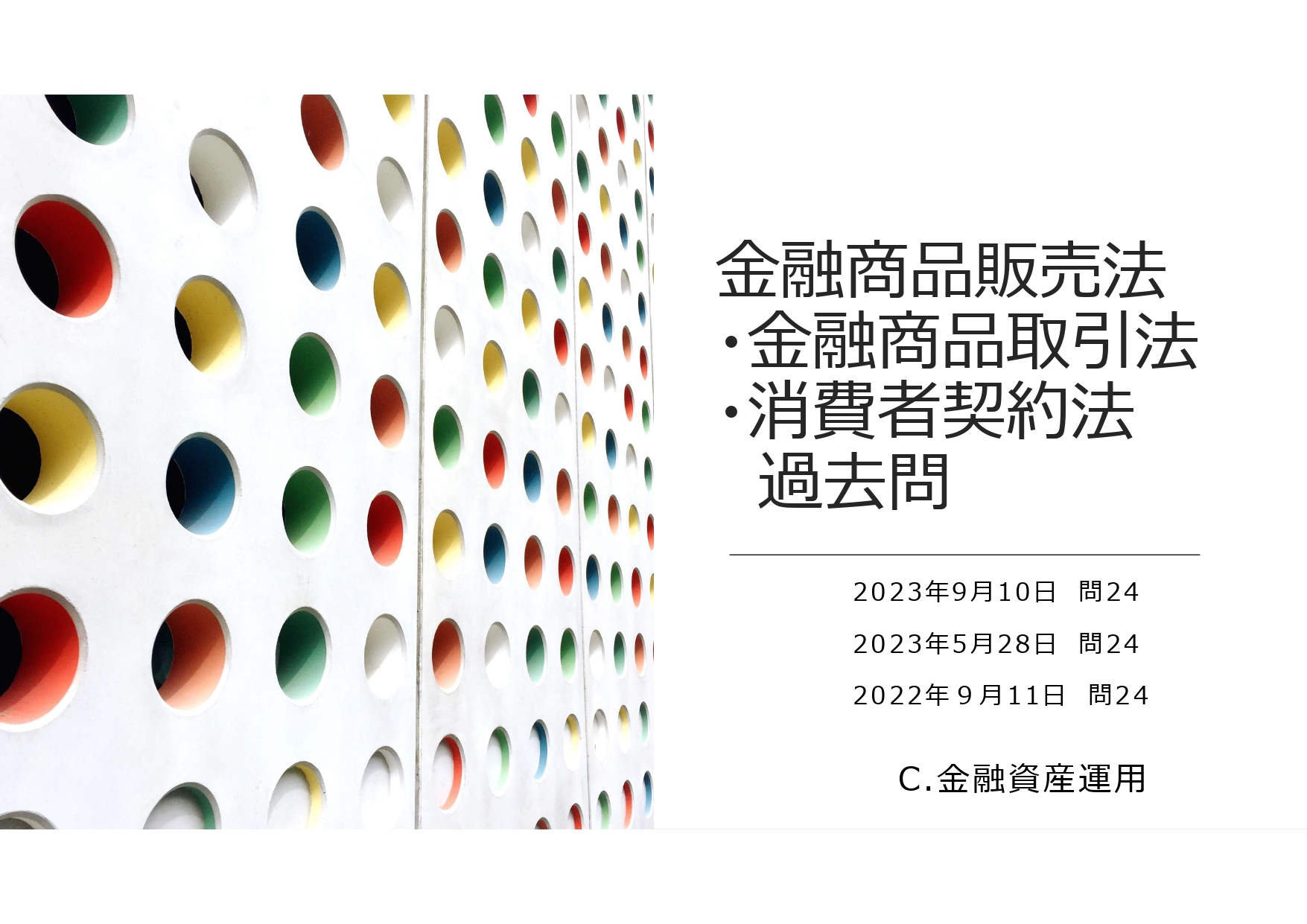
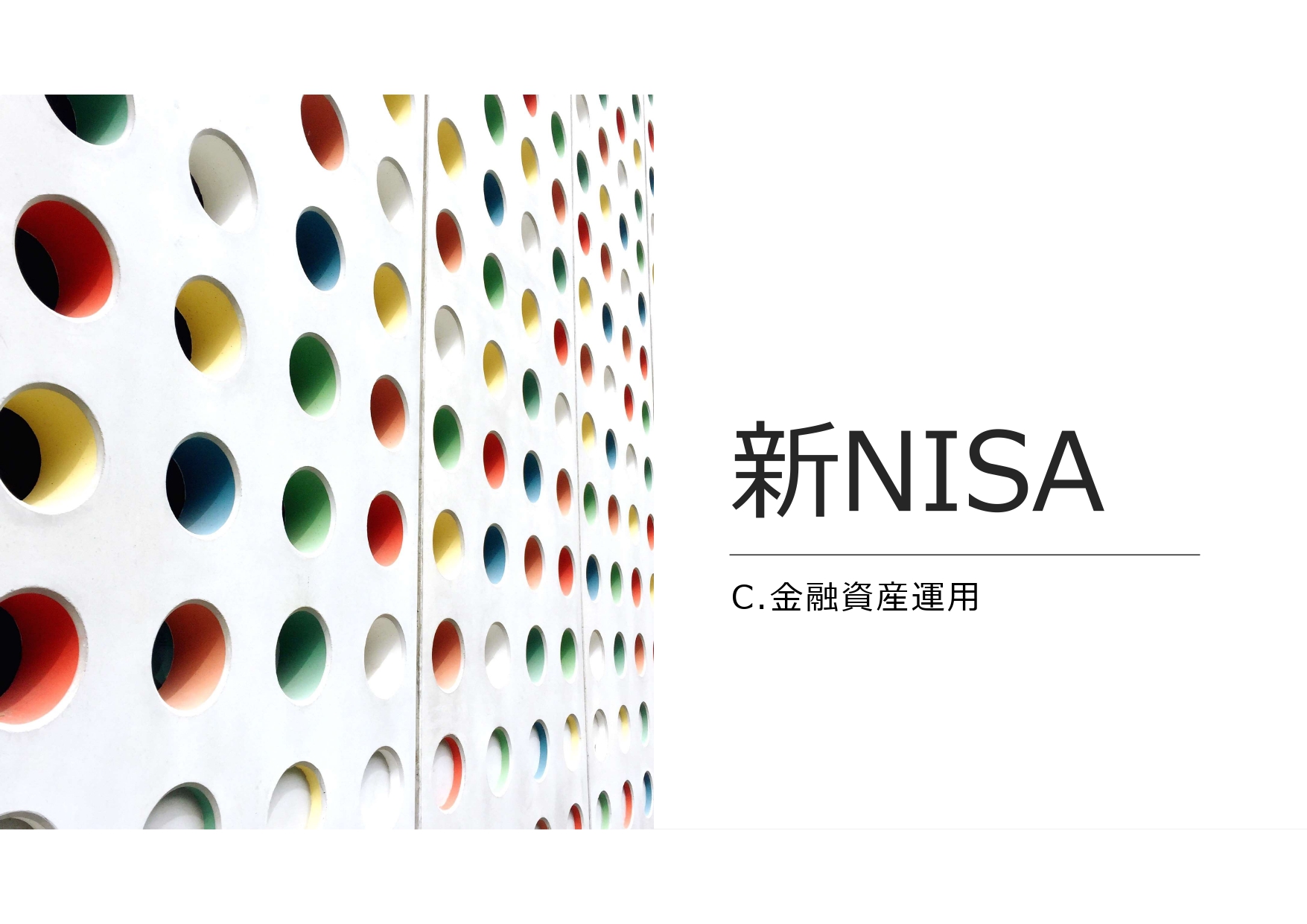
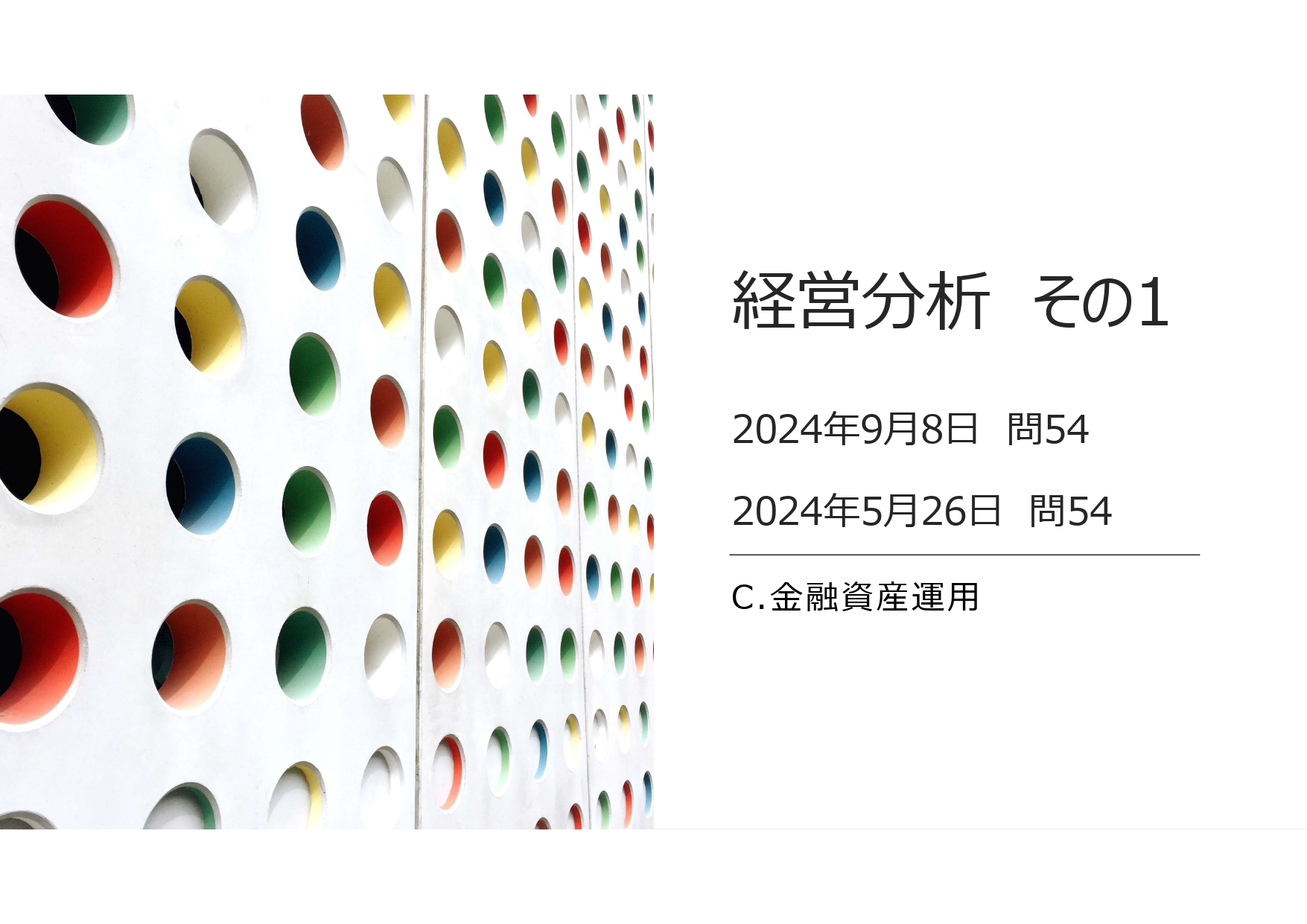
コメントを残す