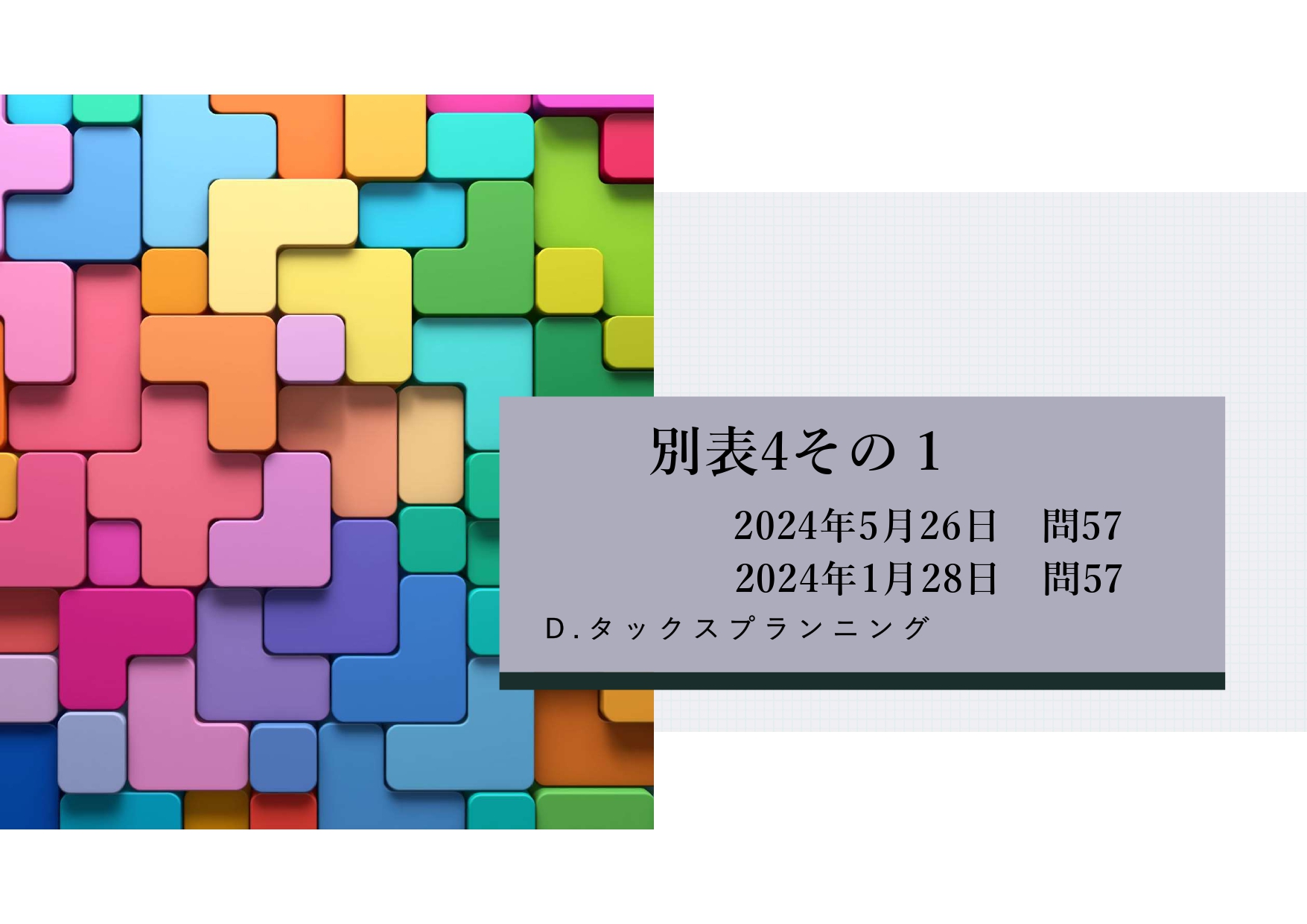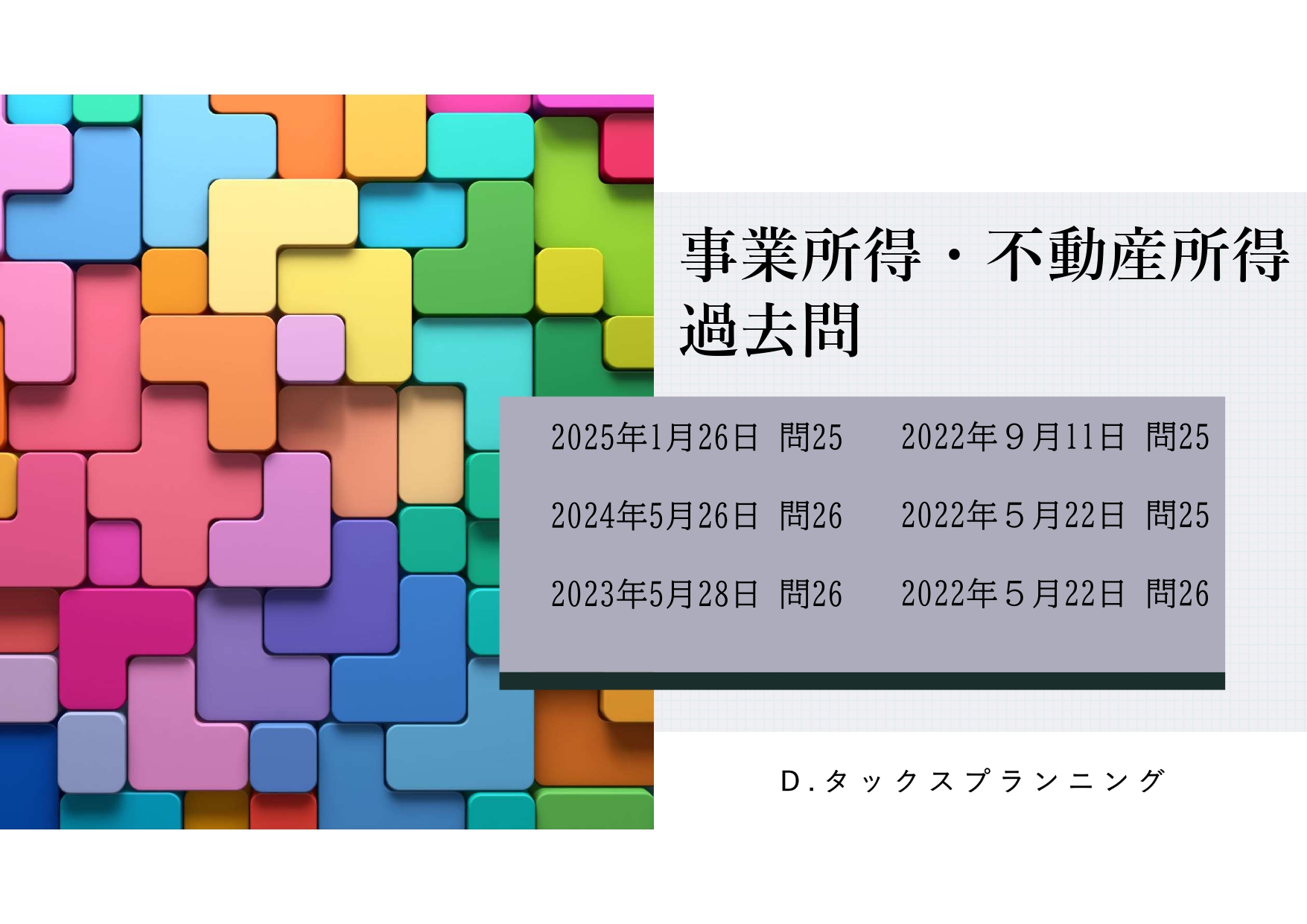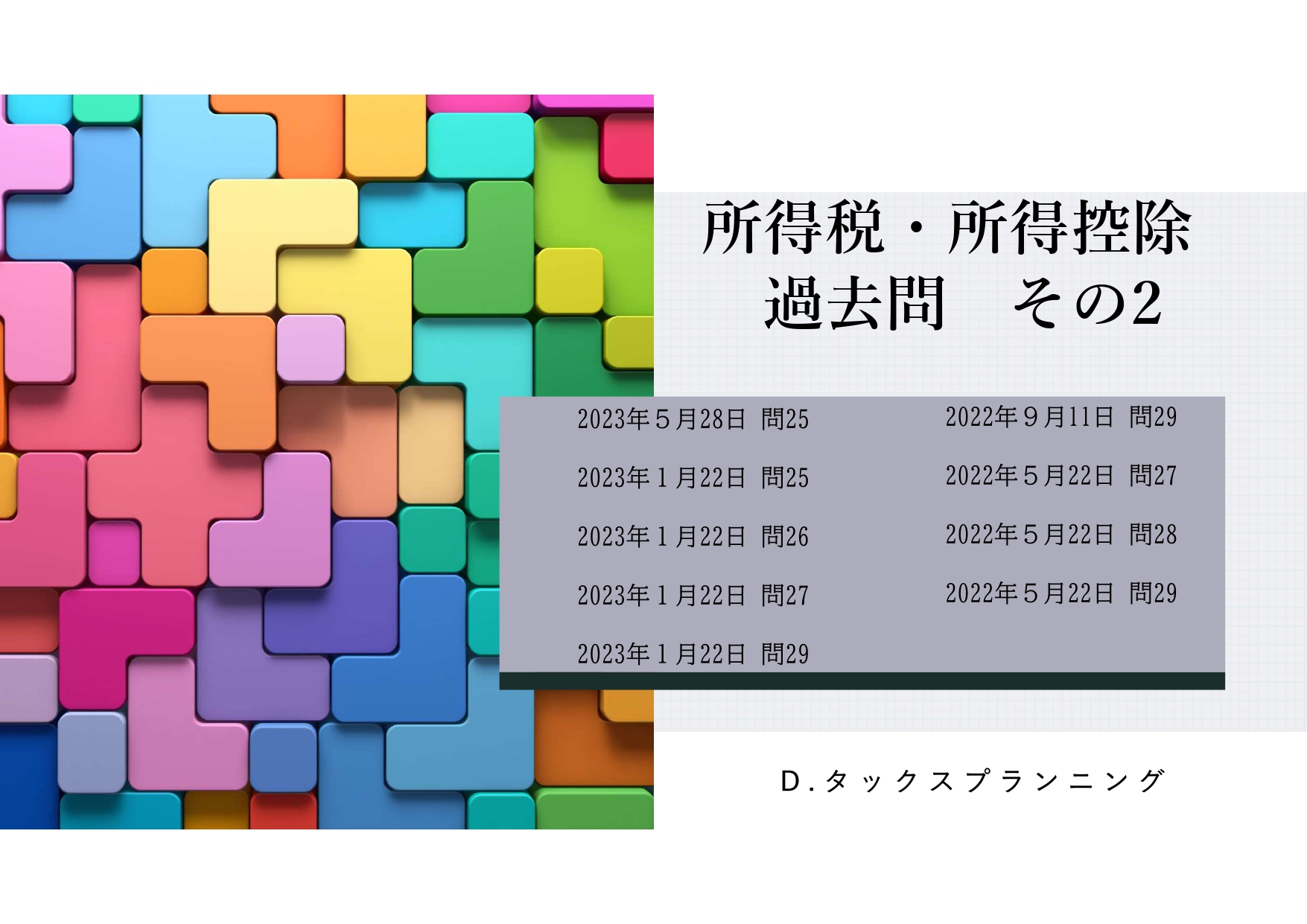法人税 過去問 その2
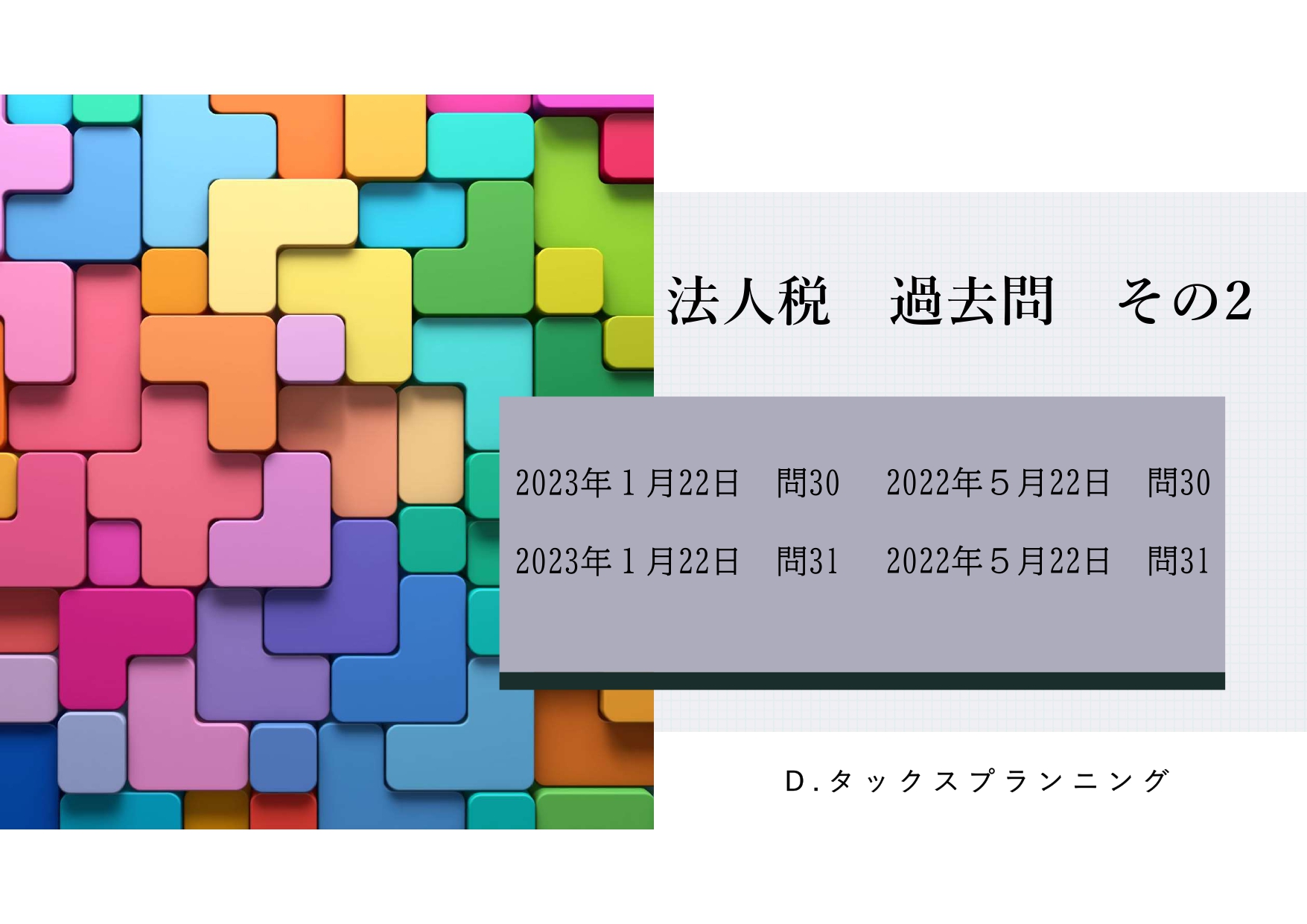
実は、会社経営をしていなくても、ご自身の勤務されている会社をみれば、イメージしやすい内容が多いと思います。
また、経理関係の業務をされている方、金融機関で関与先の経営状況を普段見られていればなおさら、取っつきやすく感じられる方も多いかもしれません。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2023年1月22日 問30
| 期末の資本金の額が1億2,000万円であるX株式会社(1年決算法人。以下、「X社」という)は、2022年4月1日に開始する事業年度において下記の交際費等を損金経理により支出した。次のうち、X社の法人税の計算における交際費等の損金不算入額として、最も適切なものはどれか。なお、接待飲食費は、得意先との会食によるもので、専ら社内の者同士で行うものは含まれておらず、所定の事項を記載した書類も保存されているものとする。 〈X社が支出した金額〉 |
| 接待飲食費の金額 | 1,300万円 | 参加者1人当たり5,000円以下の飲食費300万円を含む金額 |
| 接待飲食費以外の交際費等の金額 | 800万円 | ― |
| 1) 900万円 2) 1,000万円 3) 1,150万円 4) 1,300万円 |
正解4

応用編の別表四では、何気なく説いている問題も、文章にされると戸惑うね。

資本金1億以上なので、接待飲食費の50%が限度額だね。
よって1,300万円-300万円(参加費1万円以下の飲食費)=1000万円
1000万円÷2=500万円
500万円+800万円(飲食費以外の交際費)=1,300万円
よって正解は4)だね。
2023年1月22日 問31
| 次のケースのうち、内国法人である普通法人が、資産の価額が帳簿価額を下回ったことを理由に損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができないものはどれか。 1) 法人が有する棚卸資産について、売れ残った季節商品で、既往の実績等から今後通常の価額では明らかに販売できなくなった場合 2) 法人が有する上場株式について、その価額が著しく低下し、近い将来その価額の回復が見込まれない場合 3) 法人が有する売掛債権について、その債務者との取引停止後6カ月以上を経過したため、貸倒れが発生することが確実と見込まれる場合 4) 法人が有する固定資産について、災害により著しい損傷を被った場合 |
正解3

これは、問題文を冷静に読めばわかると思うけど、ちょっと紺頼する問題かもね。

1)売れ残った季節商品は、今後、通常価格での販売が見込めないため評価損とすることが認められるよ。
2)これは微妙な選択肢だね。評価額が50%を下回った場合は認められると思うよ。
3)売掛債権については評価損でなく、貸し倒れとして処理すべきなので、これが不適切だね。
4)固定資産について、災害により著しい損傷を被った場合は評価損として認められるね。
よって正解は3)だね。
| 法人税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 1) 2020年4月1日以後に開始する事業年度から事業年度開始の時における資本金の額が1億円以下の法人は、原則として、法人税の申告を電子情報処理組織(e-Tax)により行わなければならない。 2) 中間申告書を提出すべき法人がその申告書を期限までに提出しなかった場合には、前年度実績による中間申告(予定申告)があったものとみなされる。 3) 法人は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付した確定申告書を提出しなければならない。 4) 過去に行った確定申告について、計算に誤りがあったことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であることや、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。 |
正解1

e-Taxってやたらと勧められてるね。今は、ほとんどの申告がe-Taxになってるんじゃないだろうか。

1)e-Taxで申告するのは資本金1億円超の法人だね。問題文を冷静に読む力が試されてるね。
2)~4)は再度、出題の可能性があるから問題文をしっかり覚えることをお勧めするよ。
2022年5月22日 問31
| 法人税法上の受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 1) 製造業を営むX社が発行済株式の100%を保有するA社から受けた完全子法人株式等に係る配当については、その全額が益金不算入となる。 2) 製造業を営むX社が発行済株式の40%を保有するB社から受けた関連法人株式等に係る配当については、その配当の額から当該株式に係る負債利子額を控除した金額が益金不算入となる。 3) 製造業を営むX社が発行済株式の10%を保有するC社から受けた完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当については、その配当の額の25%に相当する金額が益金不算入となる。 4) 製造業を営むX社が発行済株式の3%を保有するD社から受けた非支配目的株式等に係る配当については、その配当の額の20%に相当する金額が益金不算入となる。 |
正解3

配当の問題は何度も出るんだね。応用編の別表四を確実に得点するためにも押さえておきたい問題だね。

1)完全子会社から受取る配当金の場合、配当金全額が益金不算入となるよ。
2)持株比率3分の1超だと関連法人に当たるから配当-それに係る有利子負債額だね。
3)持株比率5%超3分の1以下は50%が益金不算入だね。そもそも25%というのは、配当の問題で出てこないから、ここで気づかないとね。
4)持株比率が5%未満は非支配目的株式等で20%益金不算入というのも正しいよ。
よって不適切は3)だね。