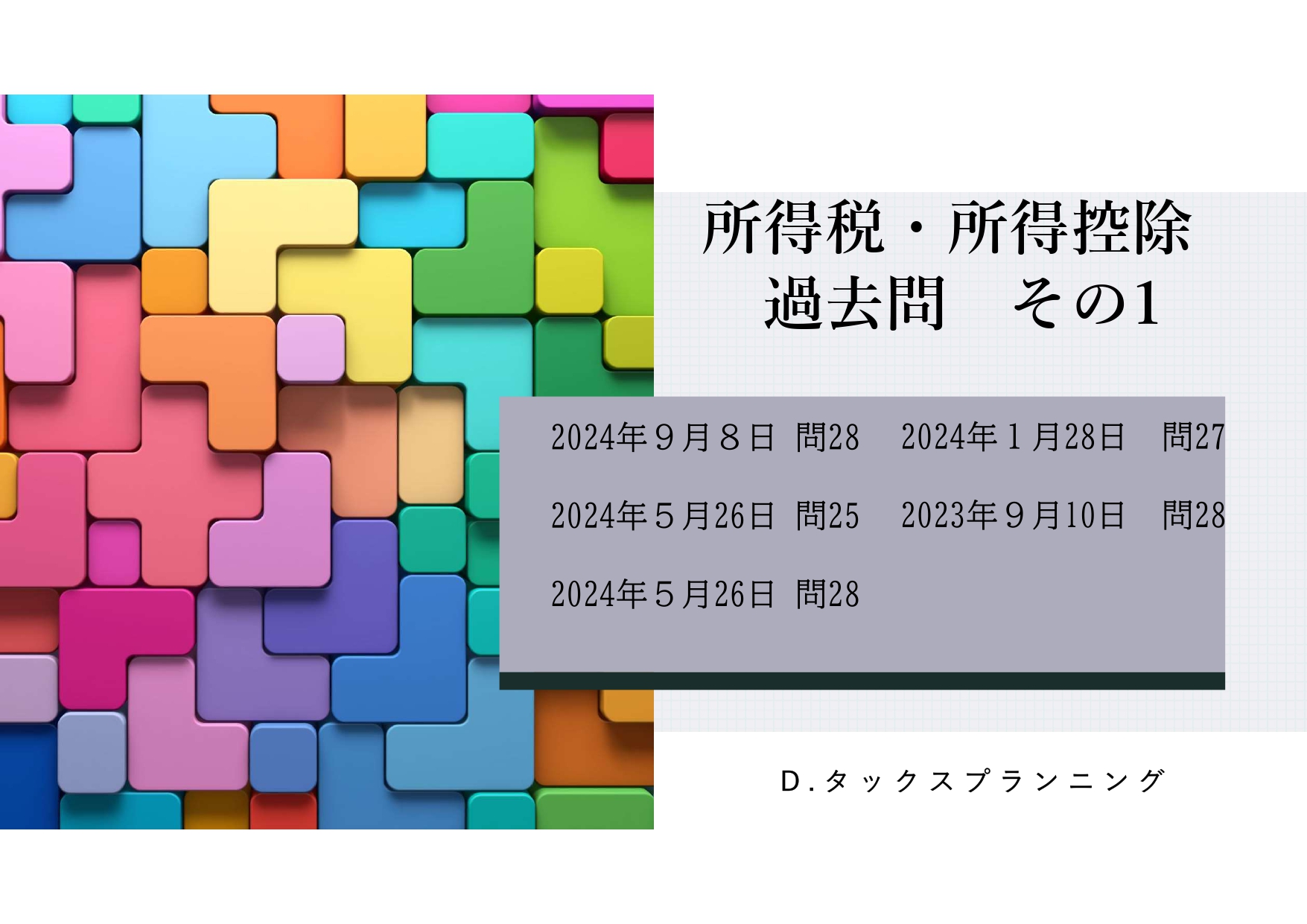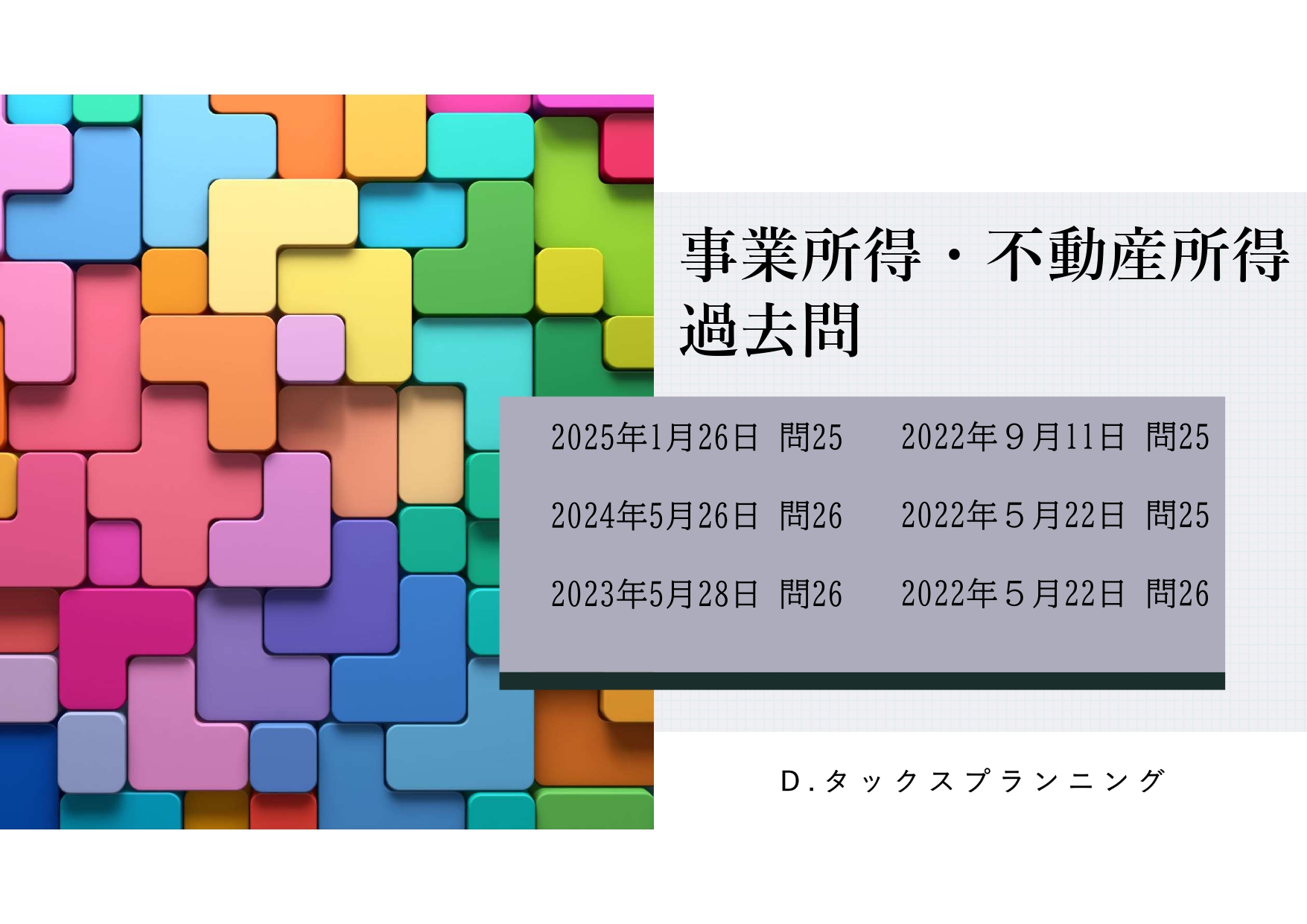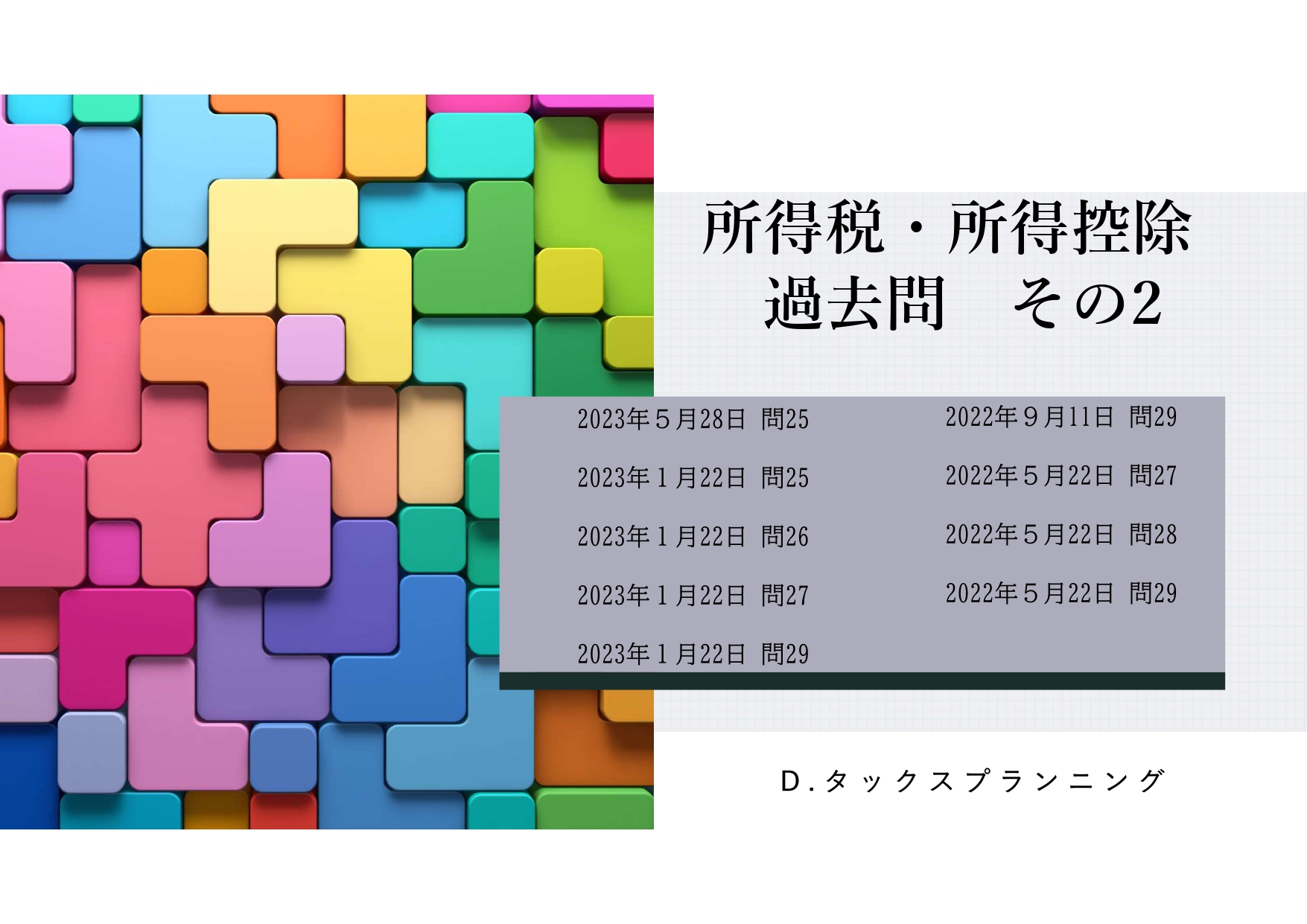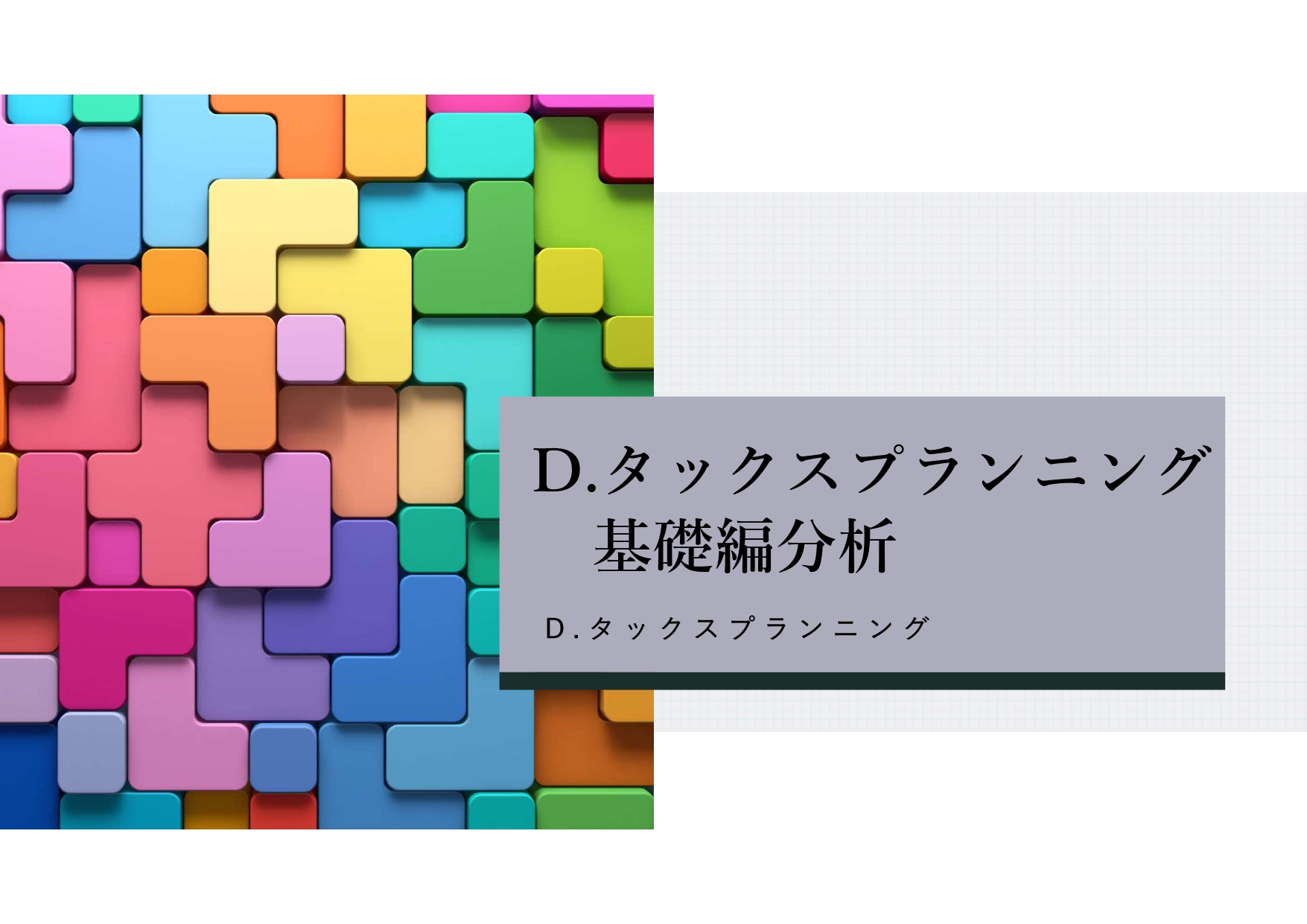配当 過去問

今回は、配当についての過去問解説を行います。
それにしても、配当で生活するのって、ある意味、夢の生活ですよね。
まあ、そのためには当然、株式を保有している必要があり、その投資が他の投資と比べて有効かどうかを判断する必要があると思いますが、
預貯金の金利がほとんどゼロに近い状態の昨今では、配当で収入を得るというのは本当にありがたいですし、生活費といわないまでも、臨時収入を得ることは助かります。
実際は、配当金だけでなく投資先の扱っている商品やサービスを使えるのも魅力的ですね。
所得の種類について過去に記事にしていますので、併せてご覧ください。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
| 法人税法上の受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当金を受け取った場合、その配当金は益金不算入の対象となる。 2) 法人が加入する生命保険の契約者配当金を受け取った場合、その契約者配当金は益金不算入の対象とならない。 3) 法人が上場株式をその配当の支払に係る基準日の3カ月前に取得して配当金を受け取り、その基準日以後3カ月以内に譲渡した場合、当該株式は短期保有株式等に該当し、その配当金は益金不算入の対象とならない。 4) 法人がJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金を受け取った場合、その分配金は益金不算入の対象とならない。 |
正解3

親子間で配当のやり取りをすることによって節税になる。ってことは無いようにルールは作られているような気がするね。

1)子会社から受け取った配当金は法人税の課税対象にはならないよ。ちなみに子会社の方でも損金算入できないね。
2)この場合、雑収入として益金参入されるね。不算入の対象とならないって二重に取り消す表現は迷うね。
3)短期保有株式等は前1か月以内に取得され、かつ同日以後2か月以内に譲渡されたものだね。これも否定の繰り返しでどっちか迷うね。
4)要するにJ-REITは算入の対象となるということだね。 よって正解は3)だね。
| 居住者に係る所得税の配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、配当を受け取ったことによる所得は配当所得に該当するものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 非上場株式の配当は、配当を受け取った株主が有する当該非上場株式の数にかかわらず、その支払の際に、配当の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収される。 2) 同一銘柄の非上場株式の配当で、1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月であるものを年2回受け取った場合、いずれの配当についても確定申告不要制度を選択することができる。 3) 同一年中にX社株式の配当20万円とY社株式の配当20万円を受け取り、確定申告において、それぞれの配当金額とあわせてX社株式を取得するために要した負債の利子30万円を申告した場合、配当所得の金額は20万円となる。 4) J-REIT(上場不動産投資信託)の分配金に係る配当所得は、総合課税や申告分離課税を選択することができ、総合課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。 |
正解1

税率が20.42%と20.315%をよく混同するんだよね。

1)配当の金額に20.42%の税率は正しいね。よってこれが正解。
2)1回の配当金額が10万円で配当計算期間が6カ月のものは年換算では20万円になるので確定申告が必要だよ。
3)配当所得は「収入金額-負債の利子」で算定されるので、20万円(X社)+20万円(Y社)-30万円(負債の利子)=10万円が配当所得となるよ。
4)J-REITの分配金は配当所得ですが、確定申告をしても配当控除は受けられないよ。
よって正解は1)だね。
| 法人税法上の益金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 1) 法人がその有する棚卸資産の評価換えをしてその帳簿価額を増額した場合、その増額した部分の金額は、原則として、益金の額に算入する。 2) 法人が株式保有割合3分の1超100%未満の法人の株式(関連法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その額から関連法人株式等に係る負債利子の額を控除した金額が益金不算入となる。 3) 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当を受け取った場合、その全額が益金不算入となる。 4) 法人が法人税の還付を受けた場合、還付加算金は益金の額に算入し、還付金は益金不算入となる |
正解1

これが企業が配当を受けた時の基本的な内容だから、2)~4)は暗記必須だね。

1)棚卸資産の評価益は益金に算入できないよ。よってこれが不適切。
2)~4)は以下の表で覚えてね。
| 持ち分割合 | 益金不算入 |
| 完全子会社(100%) | 全額 |
| 関連法人(3分の1超) | 受取配当金-有利子負債 |
| その他の株式(5%超3分の1以下) | 受取配当金の50% |
| 非支配目的株式等(5%以下) | 受取配当金の20% |

応用編の別表四では、非支配目的株式が出題されることが多いけど、年のため他の区分も覚えておくことをお勧めするよ。
この問題の正解は1)だね。
2023年9月10日 問27
| 居住者に係る所得税の配当控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は、確定申告により総合課税を選択することで、配当控除の適用を受けることができる。 2) 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、株式等を取得するために要した負債の利子がある場合、配当金額から当該負債の利子の額を控除した金額である。 3) 配当控除の控除額を計算する際の配当所得の金額は、配当所得の金額が他の所得の金額と損益通算される場合、損益通算する前の配当所得の金額となる。 4) 課税総所得金額が1,000万円を超える場合、配当控除の控除額は、当該配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から1,000万円を控除した金額に達するまでの金額については10%を、その他の金額については5%をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額となる。 |
正解4

これは、問題文を読み違えて迷宮入りするパターンだね。先ずは、わかりそうな選択肢を読解して消去していくしかないね。

1)公募株式投資信託の分配金に係る配当所得は総合課税、申告分離課税のいずれかを選択可能ですが、総合課税を選択すると配当控除を受けることが可能だよ。
2)配当所得=配当金額-有利子負債の利子だね。
3)これも正しいね。配当所得を他の所得と損益通算する場合でも、配当控除は損益通算前の金額から差し引かれるね。
4)これは単純に5%と10%の説明が逆になっているね。1,000万円までは10%、それ以上の金額に対しては5%だね。
説明文がややこしくてわけわからなくなるね。
よって、不適切は4)だね。
| 居住者に係る所得税の利子所得と配当所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、利子所得として総合課税の対象となる。 2) 同一年中に受け取った複数の上場株式の配当について確定申告を行う場合、1銘柄ごとに総合課税または申告分離課税を選択することができる。 3) 同一年中にX社株式の配当金20万円とY社株式の配当金20万円を受け取り、X社株式を取得するために要した負債の利子30万円を支払った者が、当該配当について確定申告を行う場合、配当所得の金額は20万円となる。 4) 内国法人から支払を受ける上場株式の配当について、確定申告において申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができる。 |
正解1

日本の金融機関の海外支店、外国銀行の日本支店とか、扱いの違いを覚えられないね。

1)預金の利子は日本国内だと源泉分離課税、海外だと総合課税と覚えてもいいような気がするね。これが正解だよ。
2)複数の配当を受ける場合、総合課税、申告分離課税のどちらかに統一する必要があるよ。
3)これは、同じ選択肢が後にも出てるんだね。20万+20万-30万=10万だね。
4)配当控除を受けるためには総合課税だね。申告分離課税は配当控除を受けることができないね。
よって正解は1)だね。
| 法人税法上の受取配当等の益金不算入に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 1) 製造業を営むX社が発行済株式の100%を保有するA社から受けた完全子法人株式等に係る配当については、その全額が益金不算入となる。 2) 製造業を営むX社が発行済株式の40%を保有するB社から受けた関連法人株式等に係る配当については、その配当の額から当該株式に係る負債利子額を控除した金額が益金不算入となる。 3) 製造業を営むX社が発行済株式の10%を保有するC社から受けた完全子法人株式等、関連法人株式等および非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当については、その配当の額の25%に相当する金額が益金不算入となる。 4) 製造業を営むX社が発行済株式の3%を保有するD社から受けた非支配目的株式等に係る配当については、その配当の額の20%に相当する金額が益金不算入となる。 |
正解3

これは2024年1月28日 問31で解説に出てくる表を覚えれば解ける問題だね。

勉強慣れしていない方は混乱する問題だけど、表に整理できて記憶している人には実は楽勝な問題だね。
不適切は3)だね。