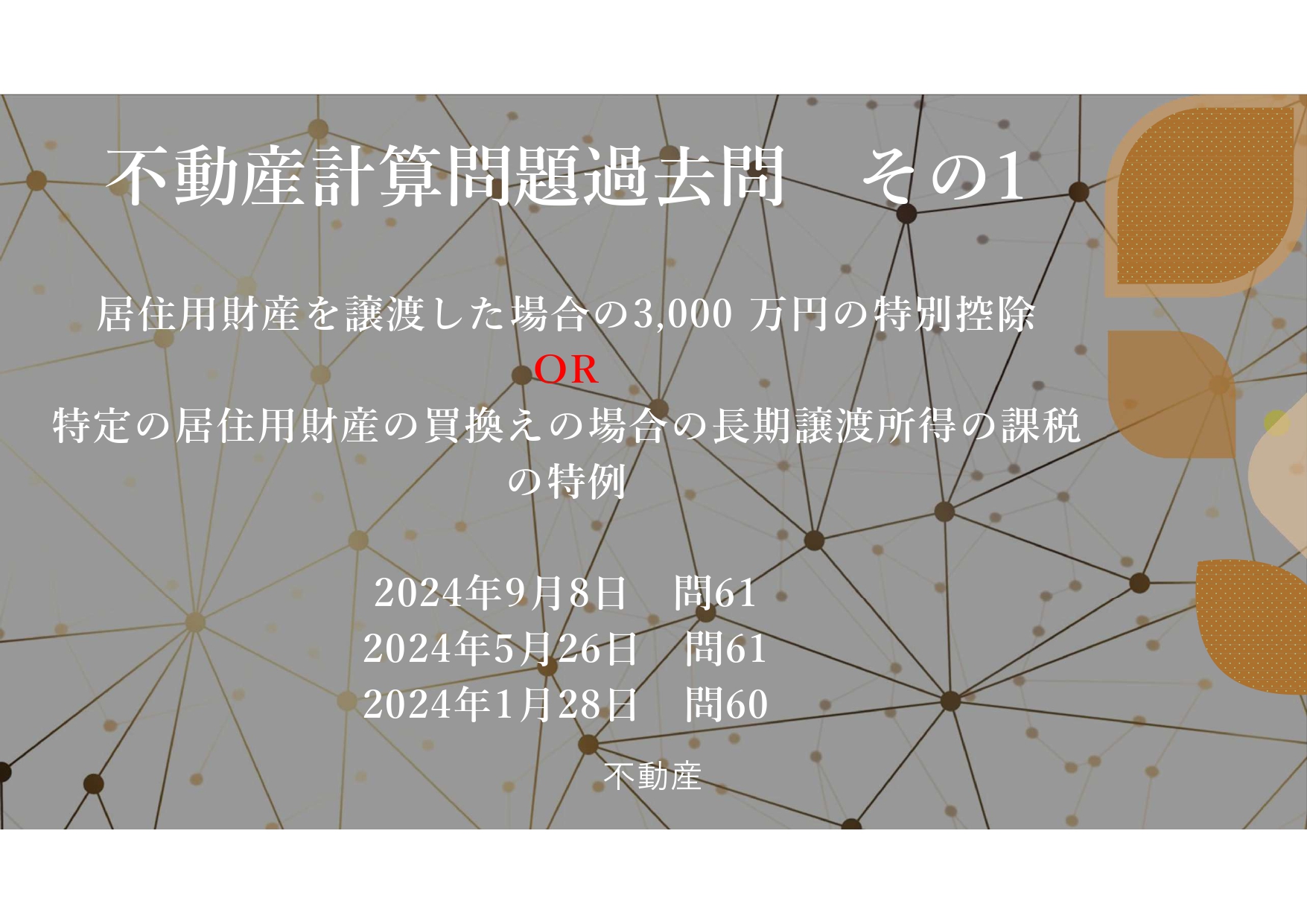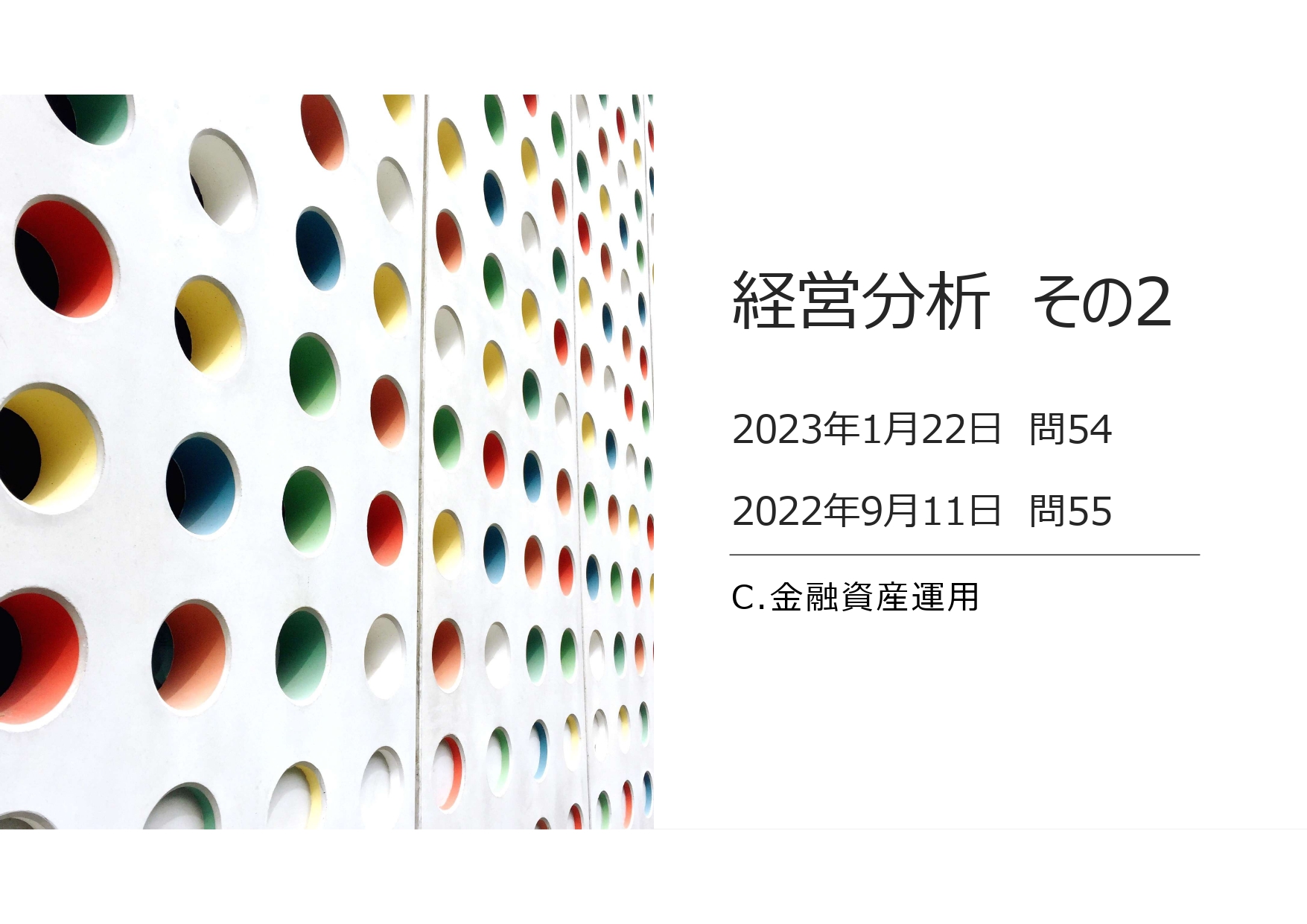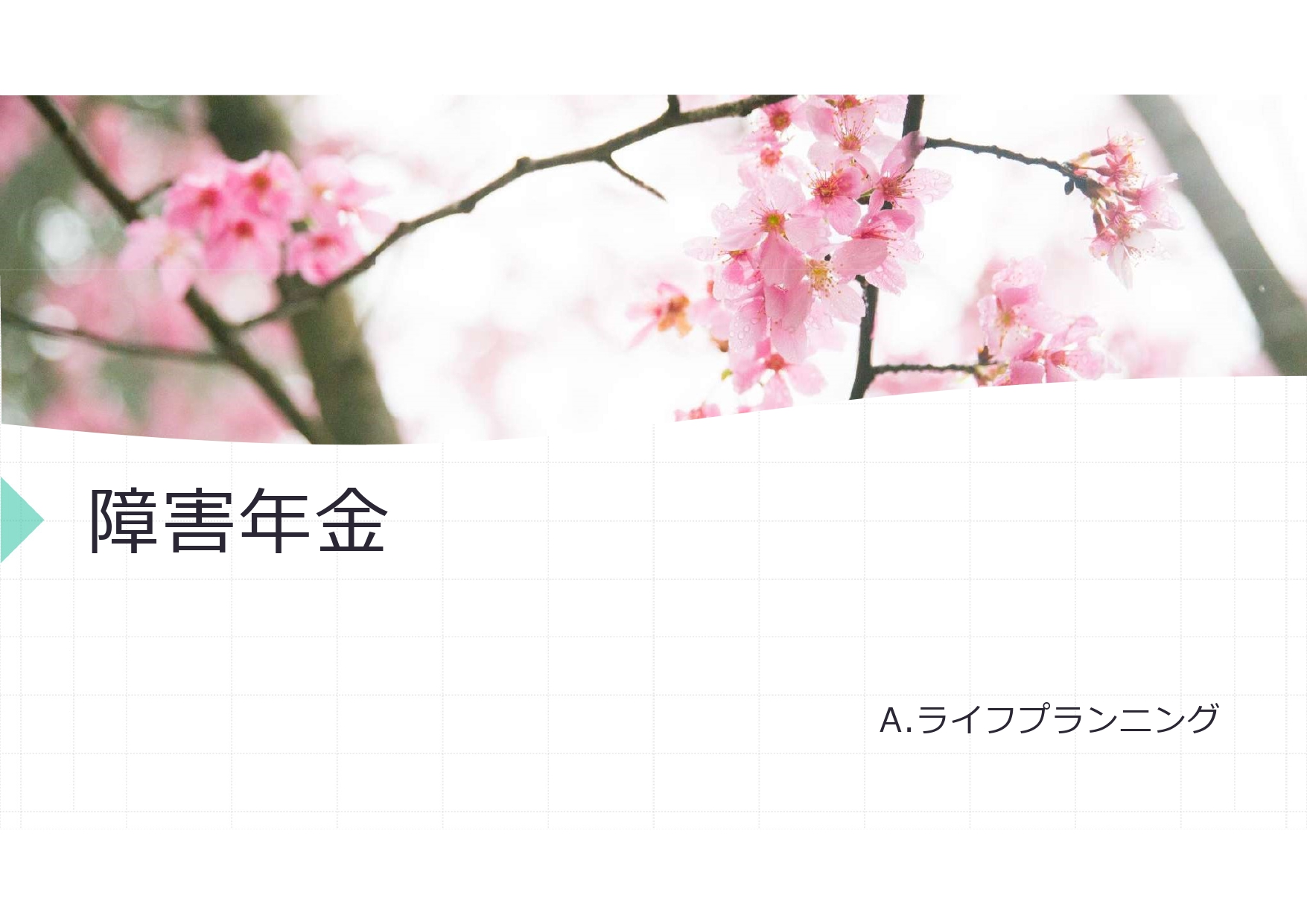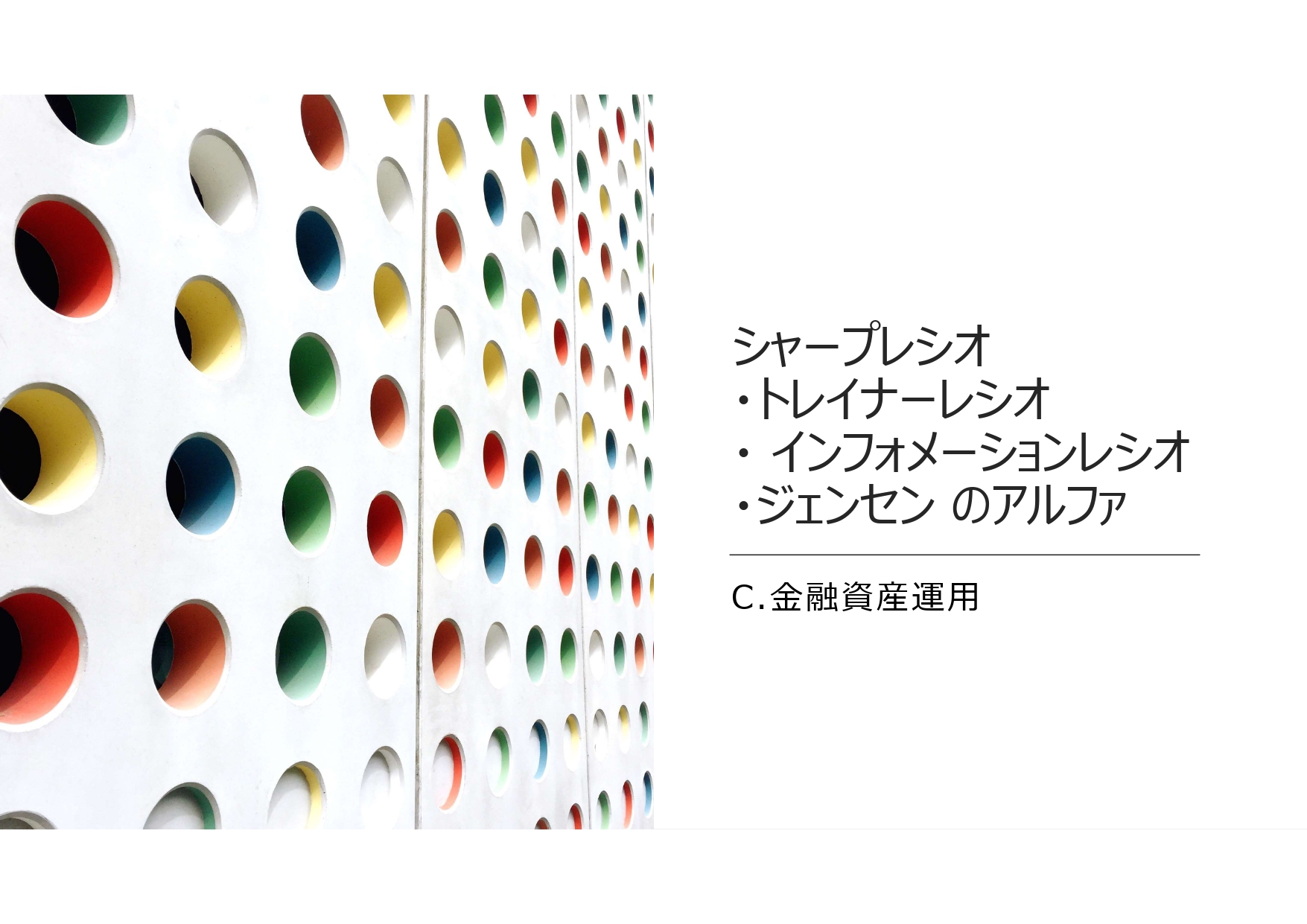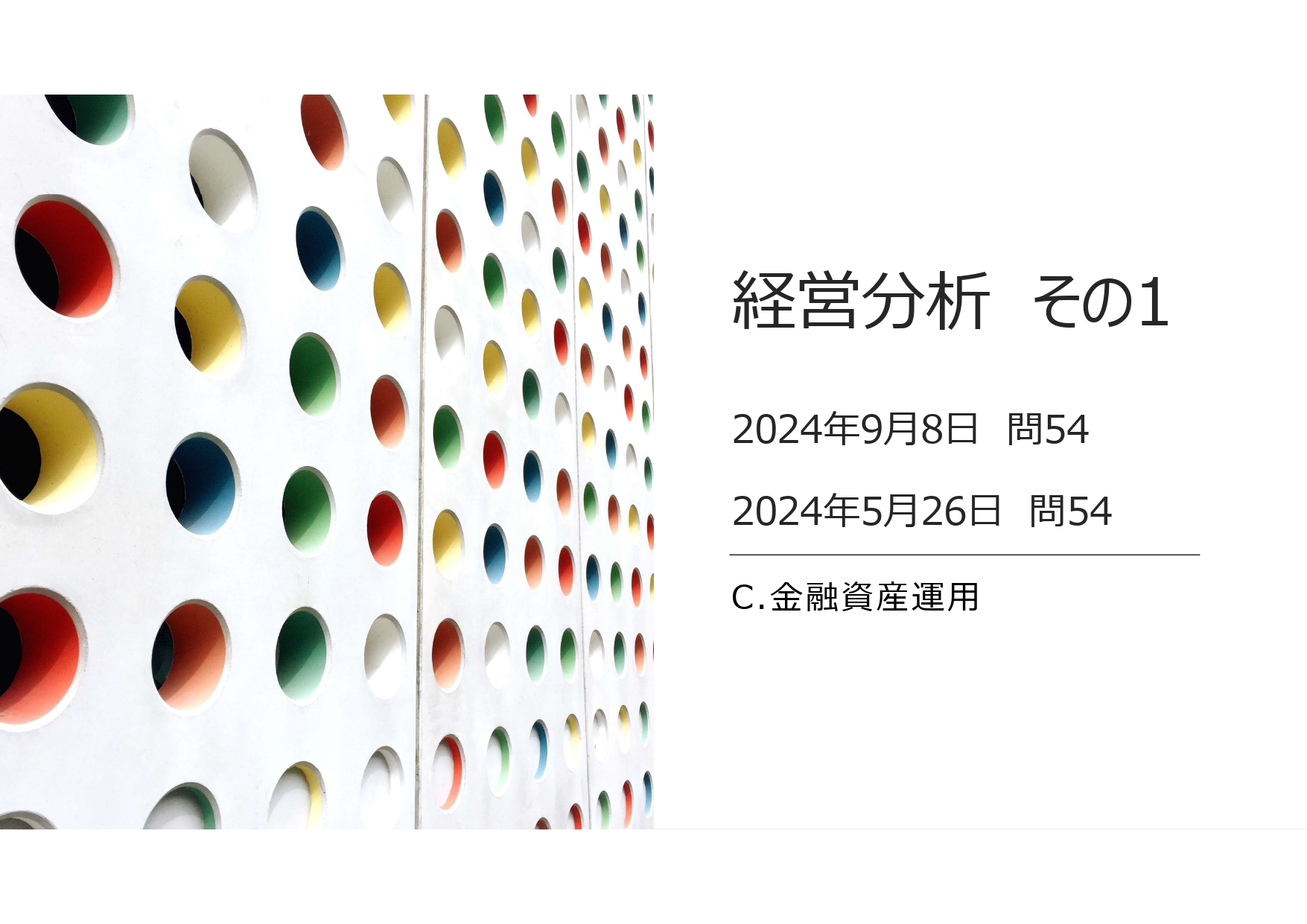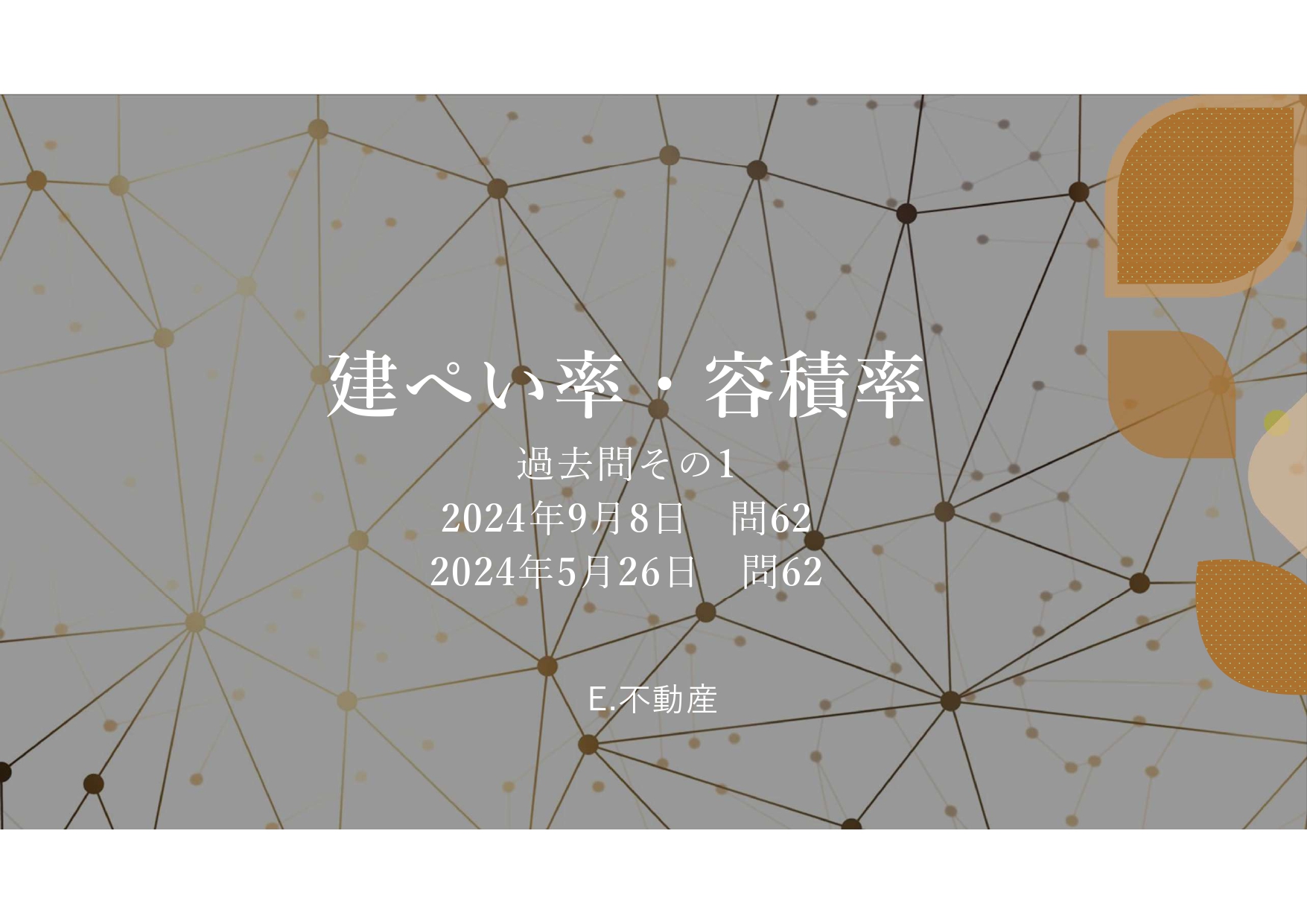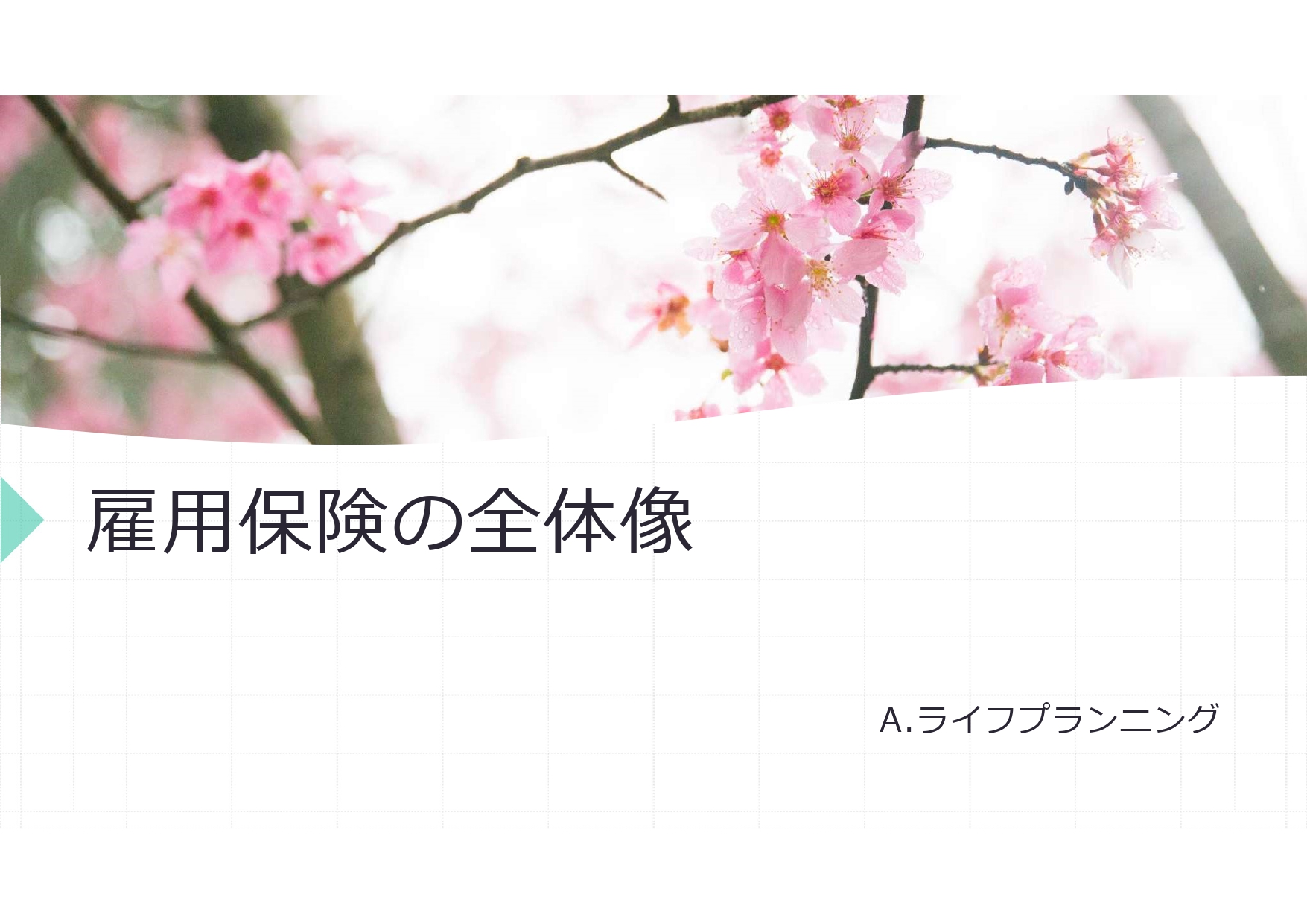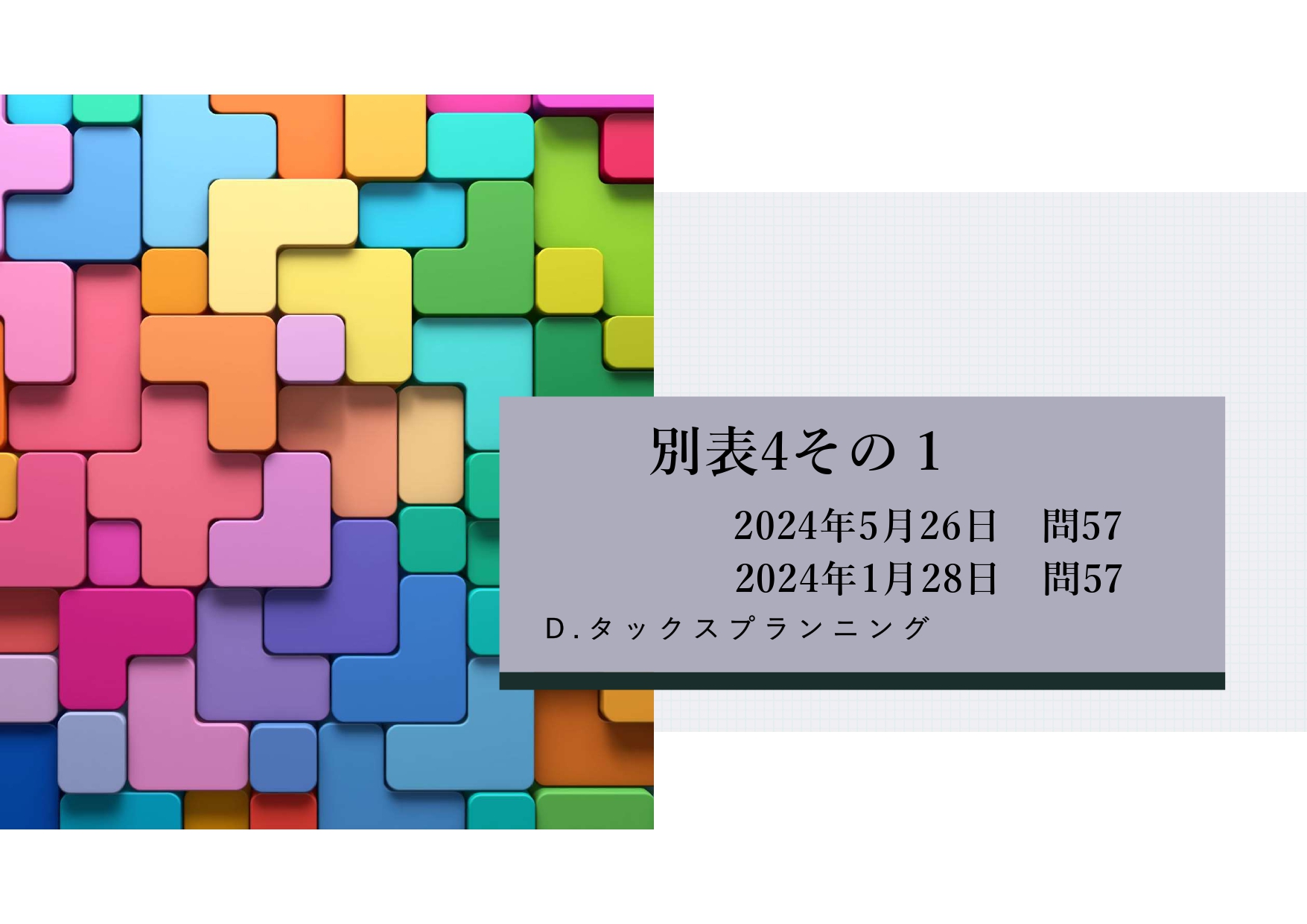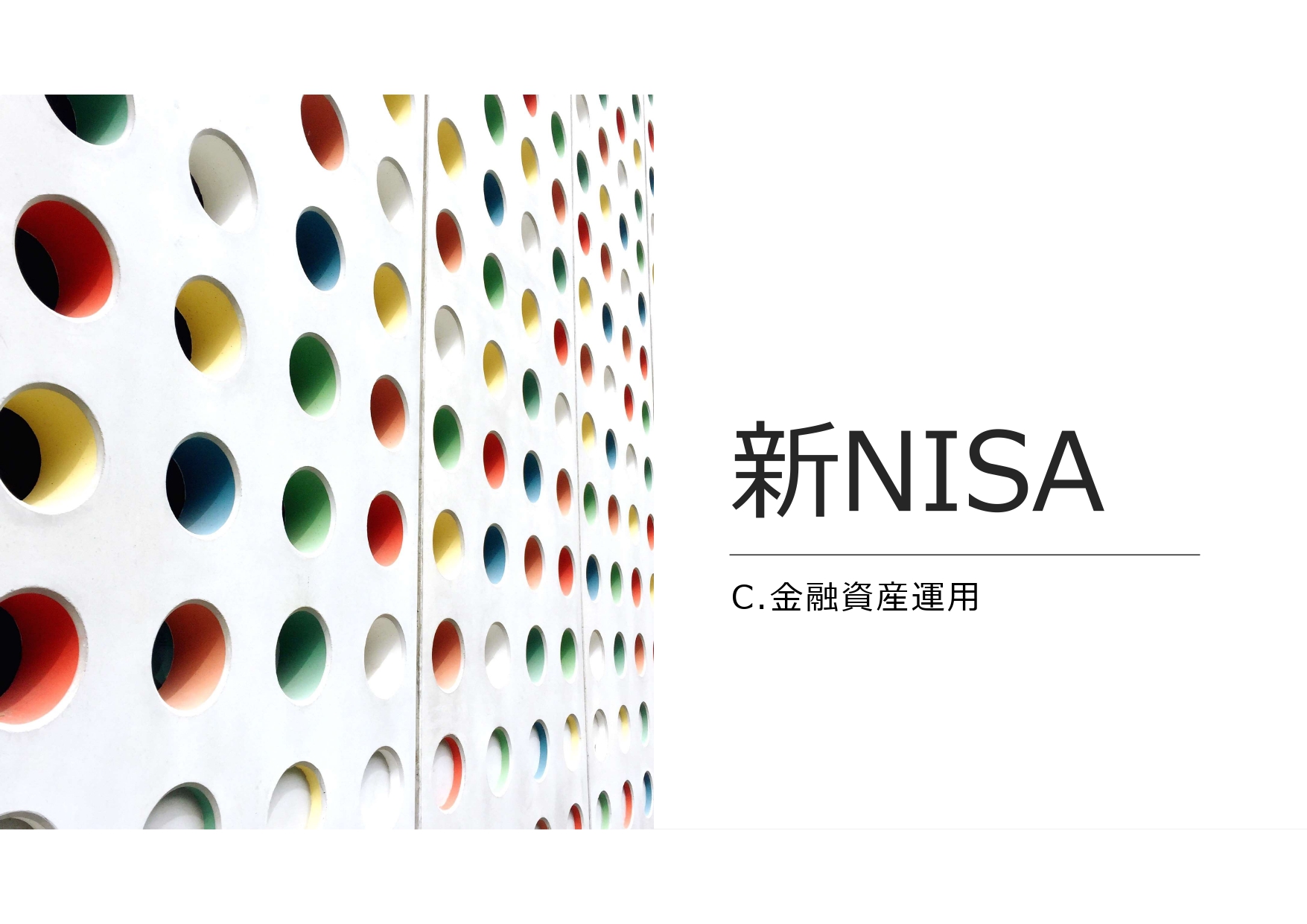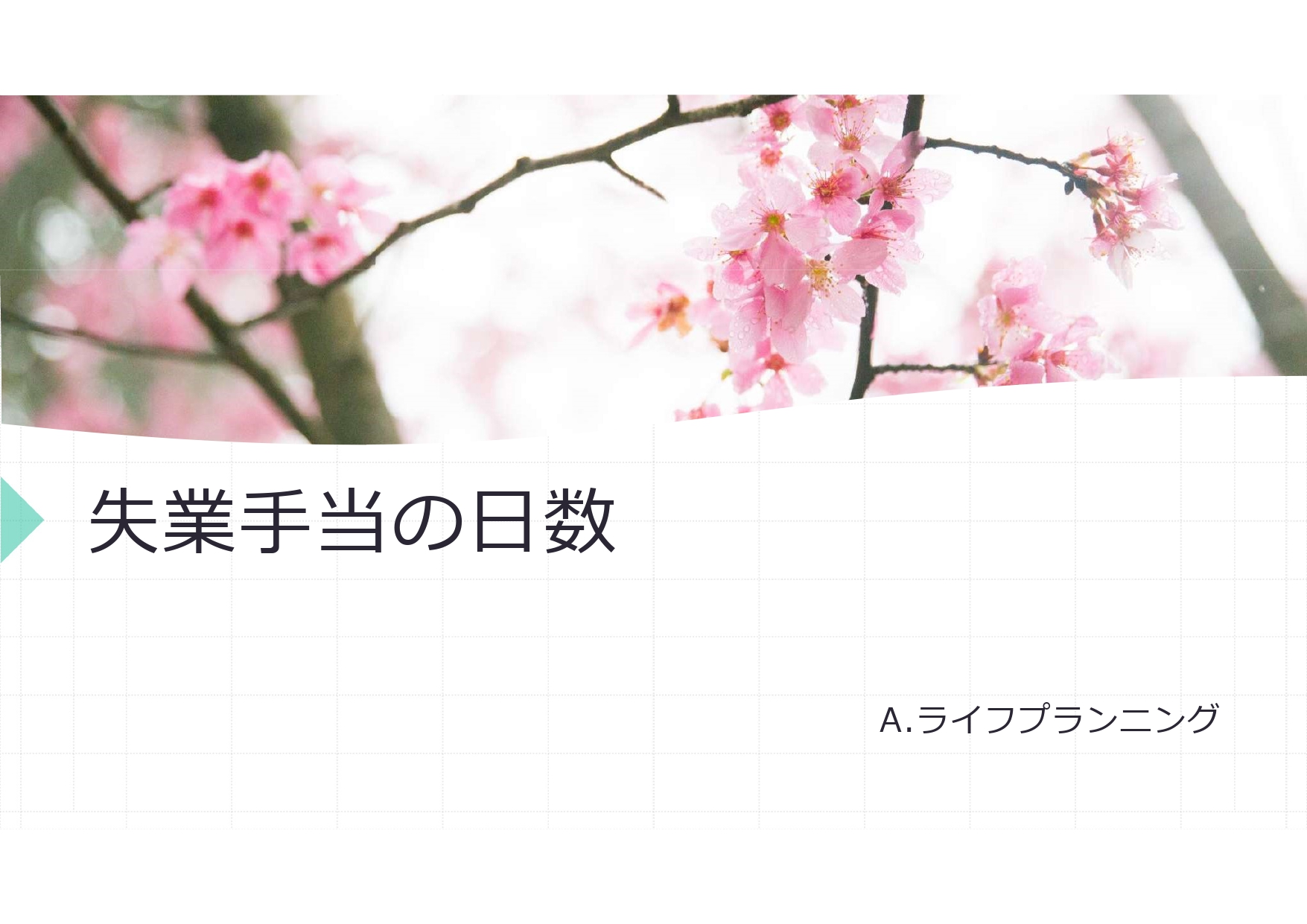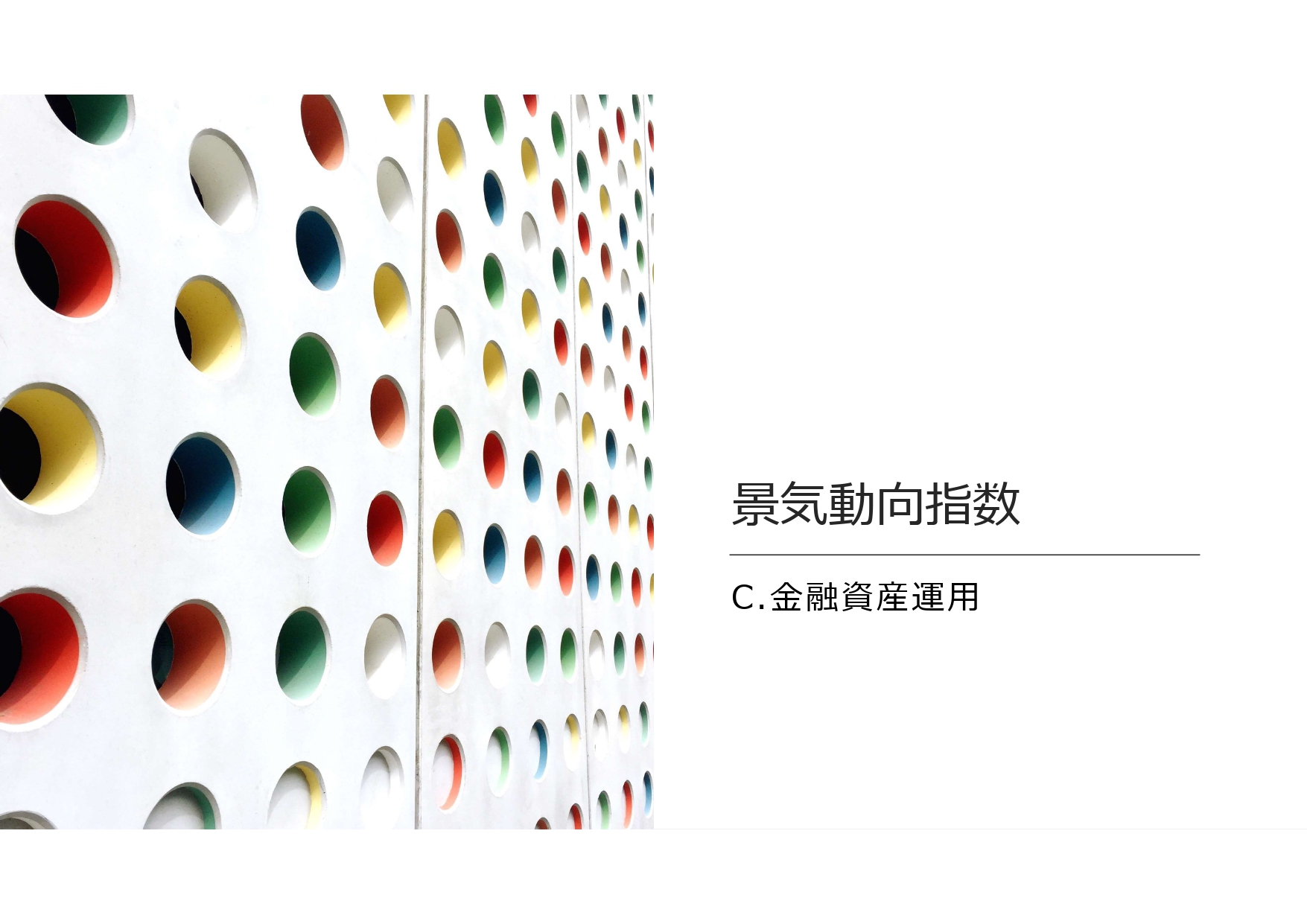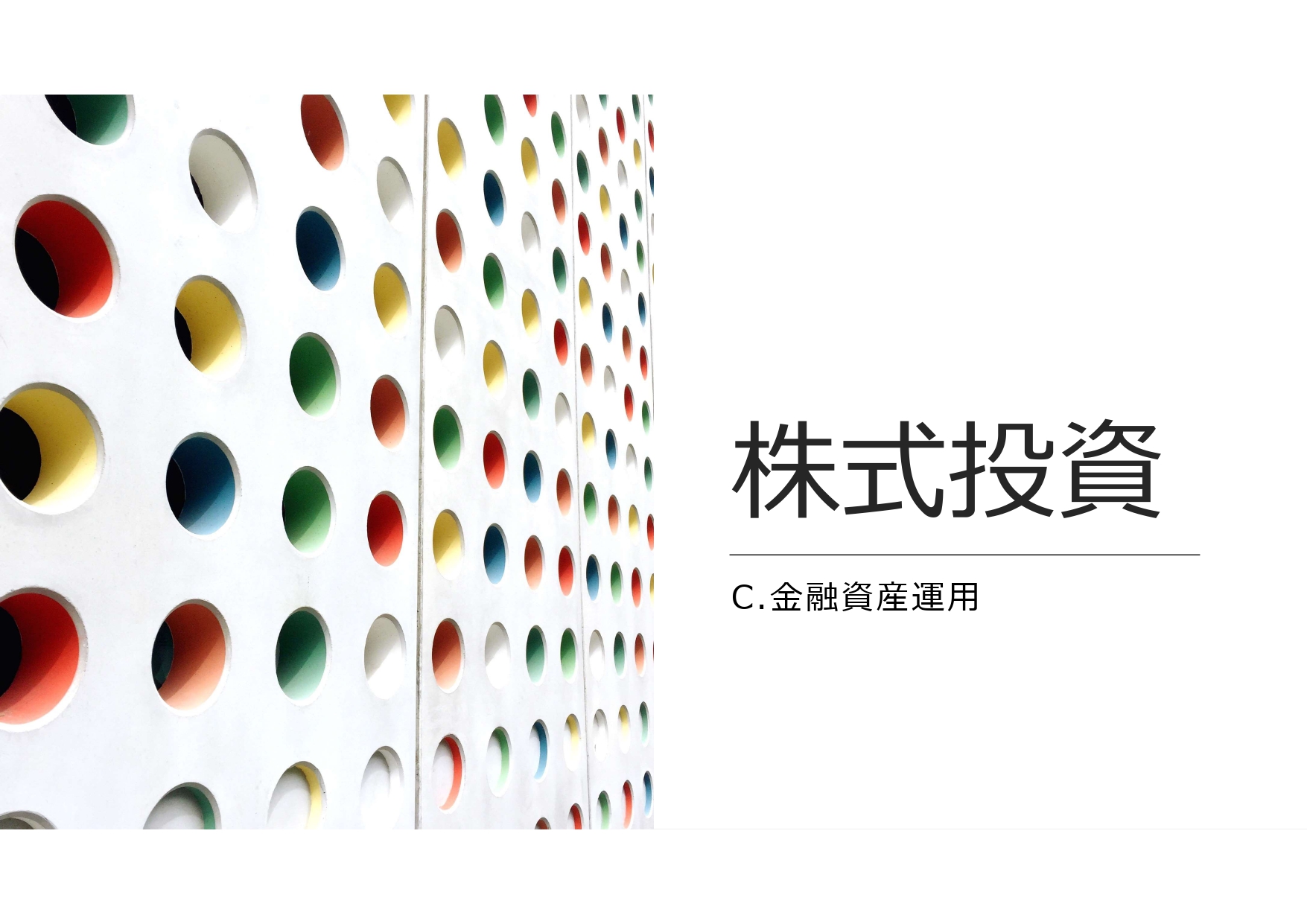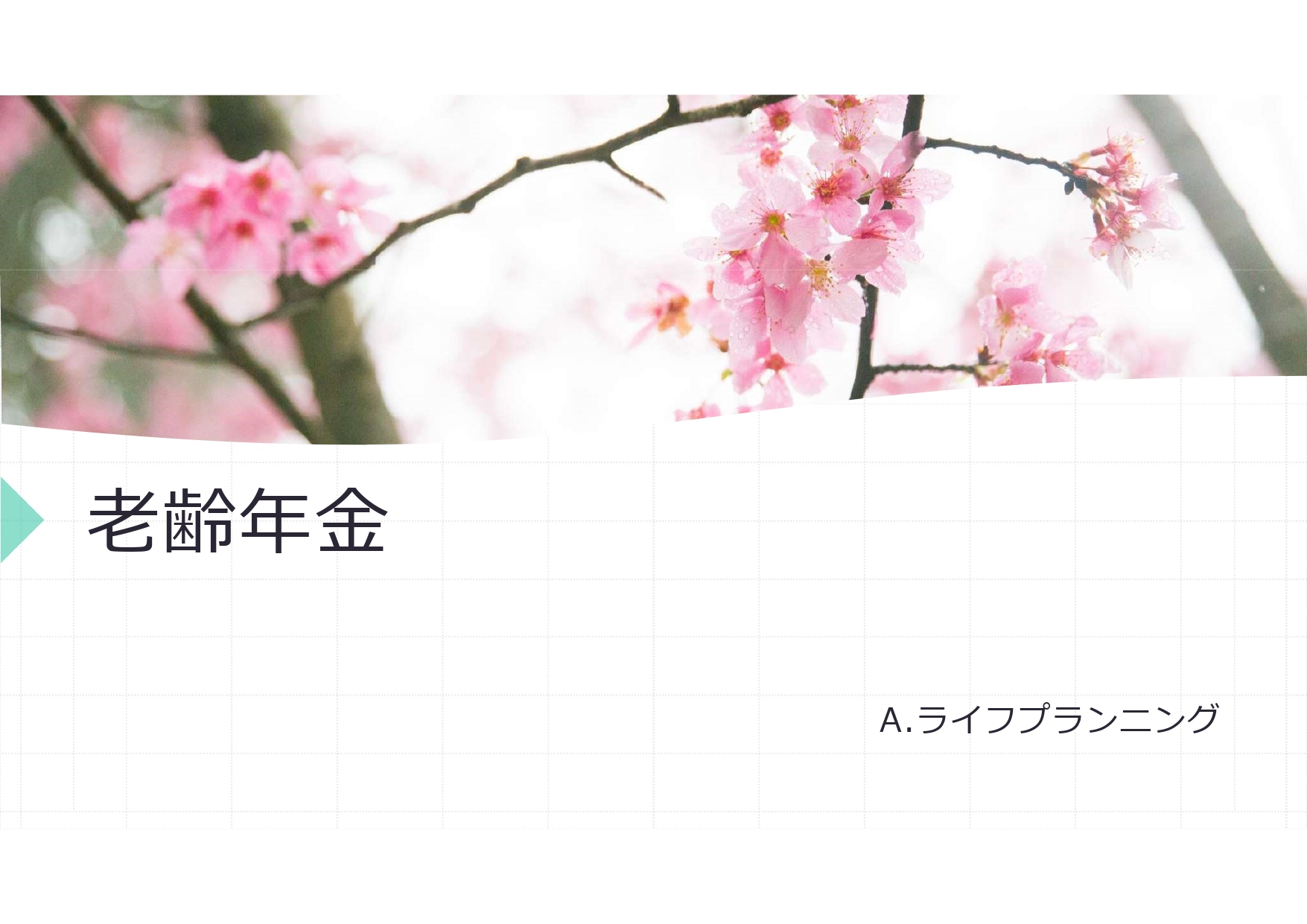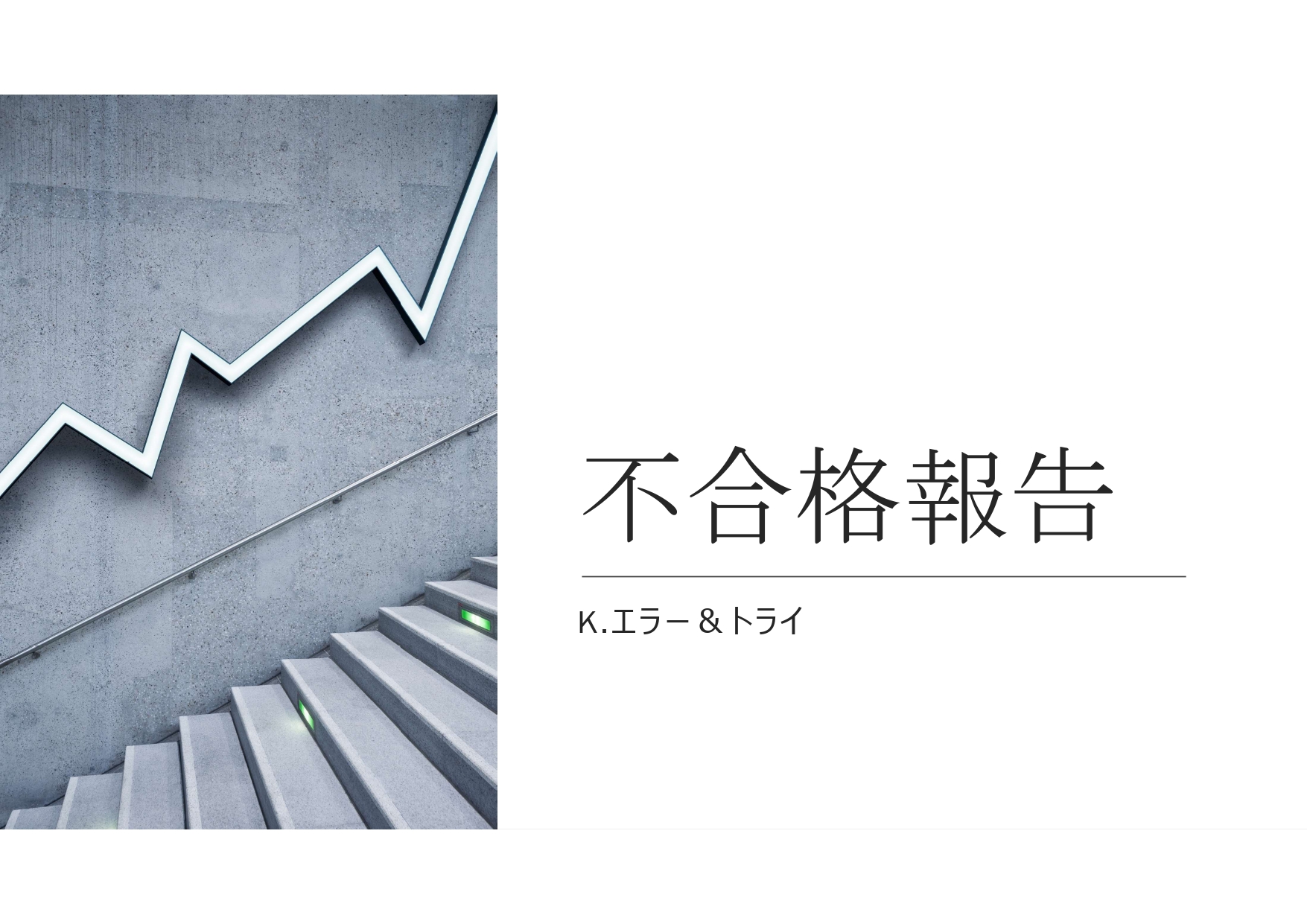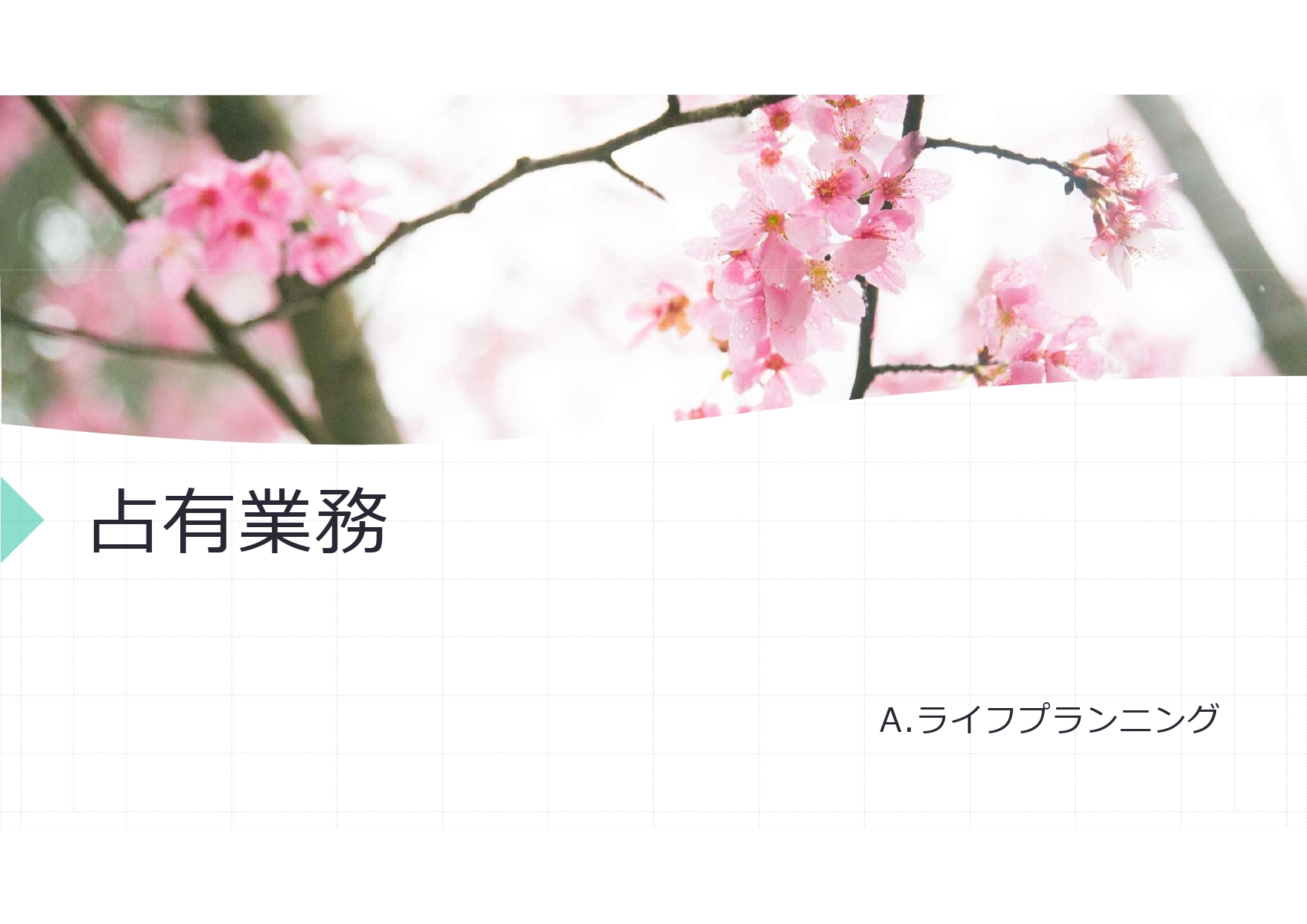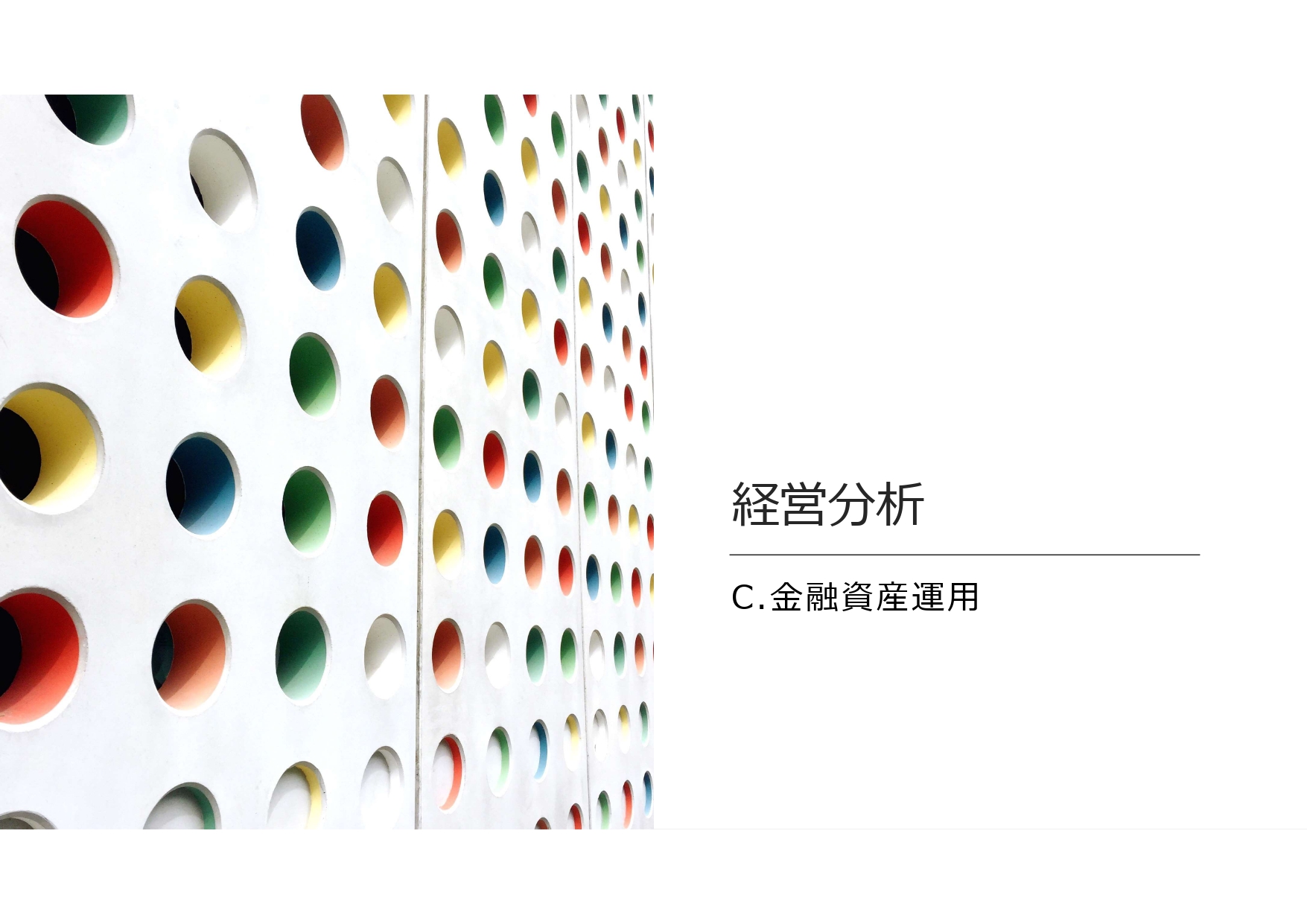居住用財産を譲渡した場合の3,000 万円の特別控除 OR 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 非常に長いタイトルですが、FP試験のE.不動産分野では、頻出の問題です。 ...
年: 2024年
経営分析 その2
またまた経営分析の過去問を紹介します。決算書を見ることは、新たな発見があるので、何度でも、繰り返し、違う年度の過去問を解いてみることをお勧めします。 2023年1月22日 問54 出所:2023年1月22日一般社団法人金融財政事情研究会1級学科試験応用編問54 ...
類似業種批准法その② 2024年1月28日 問63 問64
2024年1月28日に出題された問題の紹介をしますが、こちらの方が、以前から出題されているパターンだと思います。 今回も、自分だったら、こう解く(または本番で解いた)という手順を説明したいと思います。 ...
障害年金
障害年金で注意が必要なことは、障害の程度は常に一定ではなく、障害更新の時期に審査を受け、改めて障害年金1~3級が決まります。 これは、重度化することもあれば、改善して、障害年金の対象外となることもありえるということです。 また、混同する方も多いと思いますが、 ...
シャープレシオ・トレイナーレシオ・インフォメーションレシオ・ジェンセンのアルファ
C分野で必ずといっていいほど出題されるのが、この4つの指標を使った説明問題や、計算問題です。 正直、金融取引に特化したFPを目指すのでなければ、計算式だけ覚えて、問題文から必要事項を読み取り、計算して答えを導くのもありだと思います。 ...
別表4 その5
長かった別表4の解説も、一旦、最終回となります。 次回以降は、他のジャンルで過去問解説を行っていきたいと考えています。 2020年9月13日 問57 出所:2020年9月13日一般社団法人金融財政事情研究会1級学科試験応用編問57 ...
別表4 その4
別表4に続けて、法人税の計算がセットで出題されますが、所得金額を出した後、税金を計算する際に気をつけることがあります。 一点目は「法人税から控除される所得税額」を引き忘れないこと 二点目は「賃上げ促進税制」などの税額控除を引き忘れないこと。 ...
類似業種批准法その① 2024年9月8日 問63 問64
FPの勉強を始めた頃は、非上場株式の株価算定をすること自体の意味がわかりませんでした。 そもそも資本金÷発行済み株式数=株価 なんじゃないの? という感覚です。 また、類似価格批准方式と純資産価額方式の違いも理解が曖昧でした。 ...
別表4 その3
今回は、第3弾で、2022年5月22日、2022年1月23日の問題を解説します。 また、定番の出題として、受取配当金の問題がありますので、国税庁HPを紹介します。 受験される方は、改正後を覚えることをお勧めします。 ...
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例の説明を始めますが、先ず、この話は土地の話であること。そしてその不動産を所有している方が亡くなり、相続・事業承継が必要になった時に登場する考え方だということです。 地域にもよりますが、財産の多くを不動産が占めているという方は少なくありません。 ...
経営分析 その1
C分野 金融資産運用ではとある会社の決算書が登場し、必ずといっていいほど、なんらかの経営分析を行う問題が出題されます。 ...
用途地域その2
用途地域は13種類の地域に区分されています。 FP試験では、主に基礎編で、この地域では〇〇は建築可能かどうか問う問題が出題されます。 これを覚えるのは、結構、脳みその容量を使い、しかも紛らわしいものがあるため、間違えやすいです。 私が覚えた手順を紹介します。 ...
建ぺい率・容積率 過去問その1
FP1級学科試験で、ほぼ100%出題されると言ってもいいのが、建ぺい率・容積率を求める問題です。 これから、数回に分けて、建ぺい率・容積率の過去問を参照し、私だったら、こう解くという説明をしたいと思います。 ...
別表4 その2
応用編、タックスプランニング分野で一番の定番問題といっていいのが、「別表4」の問題であり、 それは受験生なら誰でも知っていることなので、得点源としている人も多いと思います。 ...
雇用保険の全体像
とにかくFP試験では、雇用保険分野から多数の出題があります。 ほぼ毎回、何か出題されているといっても過言ではありません。 そこで、先ずは全体像をお伝えして、その中からピックアップして解説したいと思います。 雇用の全体像 ...
別表4 その1
応用編、タックスプランニング分野で一番の定番問題といっていいのが、「別表4」の問題であり、 それは受験生なら誰でも知っていることなので、得点源としている人も多いと思います。 逆に言えば、この問題はできれば正解したい問題です。 ...
新NISA
NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。 ...
失業手当の日数
基本手当の所定給付日数 ハローワークのHPによれば失業手当は3つに分類されており 1.特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1)(3. 就職困難者を除く) 2. 1及び3以外の離職者 3. 就職困難者 となっています。ちょっとわかりやすく説明すると ...
景気動向指数
学科試験の基礎編で問われることの多い、景気動向指数 先行指数・11個、一致指数・10個、遅行指数・9個 計30個と個数が問われることもありますが、以前は、指数に入っていないものが選択肢に入っていたり、先行・一致・遅行の区分を変える問題が定番でした。 ...
株式投資
株式投資の問題は古くて、新しい問題というか、FPという仕事にとっては避けては通れない分野だと思います。 日本FP協会の実技試験では新聞の「株式投資欄」や東洋経済新報社の「会社四季報」の読み取りが、定期的に出題されます。 ...
老齢年金
FP試験では、必ず年金の問題が出題されます。 これは、受給要件や実際に給付される際の計算問題、他の制度との組み合わせや併給される際の調整など、ありとあらゆる角度からの出題が想定されます。 ここでは私が覚えた順と2024年現在の制度を考慮して解説します。 ...
用途地域その1
不動産分野で用途地域の問題がほぼ毎回出題されます。 13種類の用途地域に、建設できるもの、できないものが基礎編では問われることが多いです。 この13種類あるということも過去に出題されたことがあるため覚えておきたいです。 ...
不動産の評価
相続・事業承継の分野では、よく不動産の評価が問題になります。 これはっ実際に非相続人(亡くなった方)の財産に不動産がある場合が多く、それをどう評価するか、ということが問題になりやすいからです。 ...
不合格報告
私は2,024年5月の1級学科試験に一部合格し、9月に日本FP協会の実技試験を受験しました。 結果は不合格 例年の合格率は90%前後であり、「受験すれば、まず合格するであろう」と言われている試験なので、舐めていました。 ...
所得税と法人税の税率
所得税を求める問題は、基礎編、応用編とも頻出であり、問題文に税率表が記載してあることが、ほとんどだと思いますが、所得税の税率23%、33%のレンジはよく出題される印象があるので、覚えておいた方がいいかもしれません。 ...
所得控除
税金を計算する際に、所得から差し引くことができるものです。 ほぼ全ての項目が基礎編・応用編に出題されたことがあり、特に応用編の計算問題では、芋ずる式に次々間違うといったパターンにはまることがあるので、慎重に取り組むことが必要だと思います。 ...
生命保険でリスク管理
生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険に加入している人は、約8割の方が生命保険に加入しているとのことです。 月々の支払いが負担になり、契約を見直そうかな、と考えている人もいらっしゃると思います。 ...
占有業務
FP試験では、基礎編の序盤または、実技試験のPartⅡで専門職業家との連携に関して出題されることがあります。 主に連携が想定される士業の占有業務については、頭に入れておく必要があります。 税理士 ...
経営分析
私が、得意分野としていたのが、金融(C分野)です。 ここでは実務で使用するというより、試験を突破することに主眼をおいた解説をしたいと思います。 ...
類似業種批准法
相続・事業承継分野で必ずといっていいほど出題されるのが、類似業種批准法の計算問題です。 私は最初、見たとき「こんな計算式の問題、間違えずに回答できるのだろうか」 というか、そもそもこんな計算、何に使うのだろう?」と疑問を持ちました。 ...