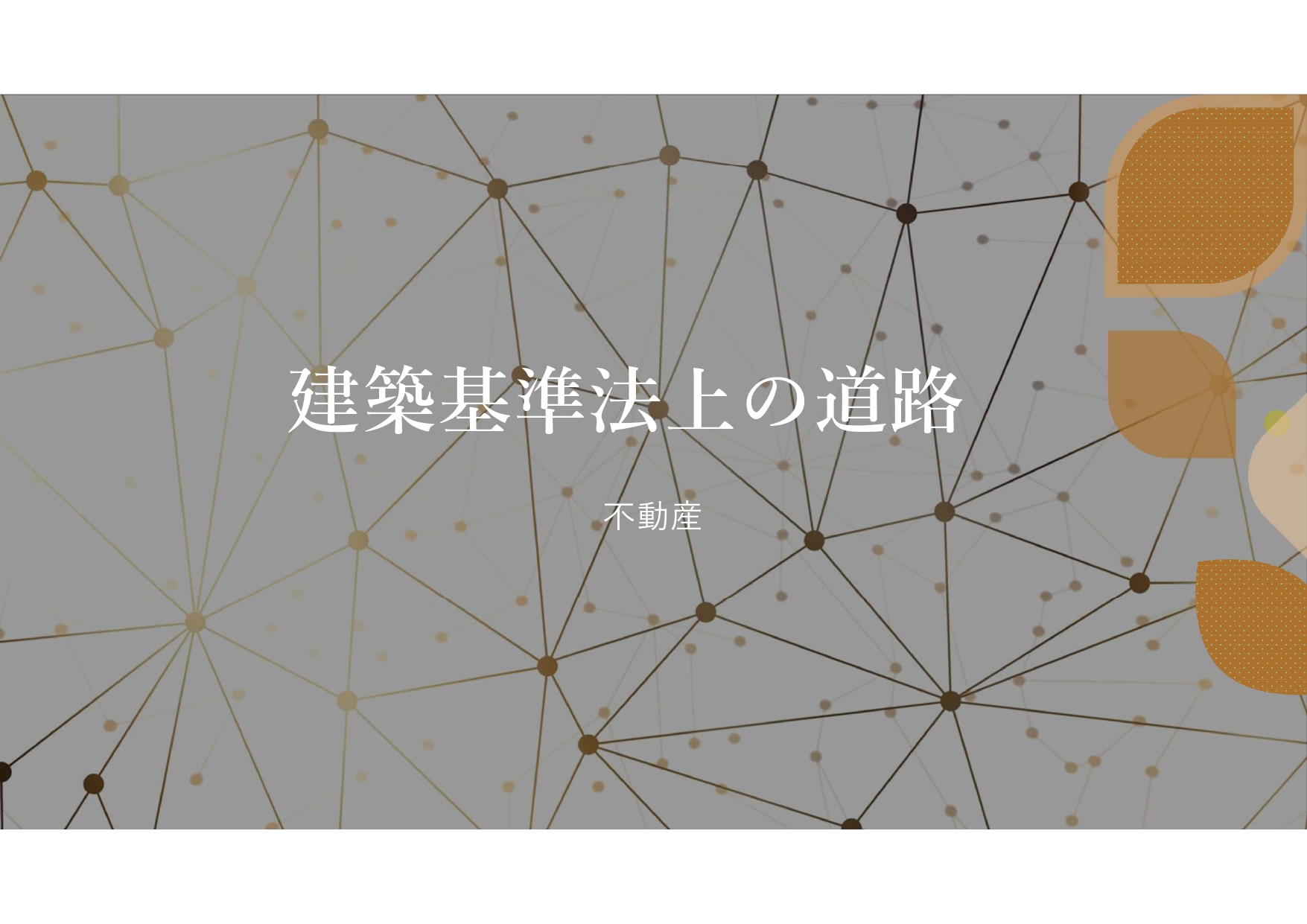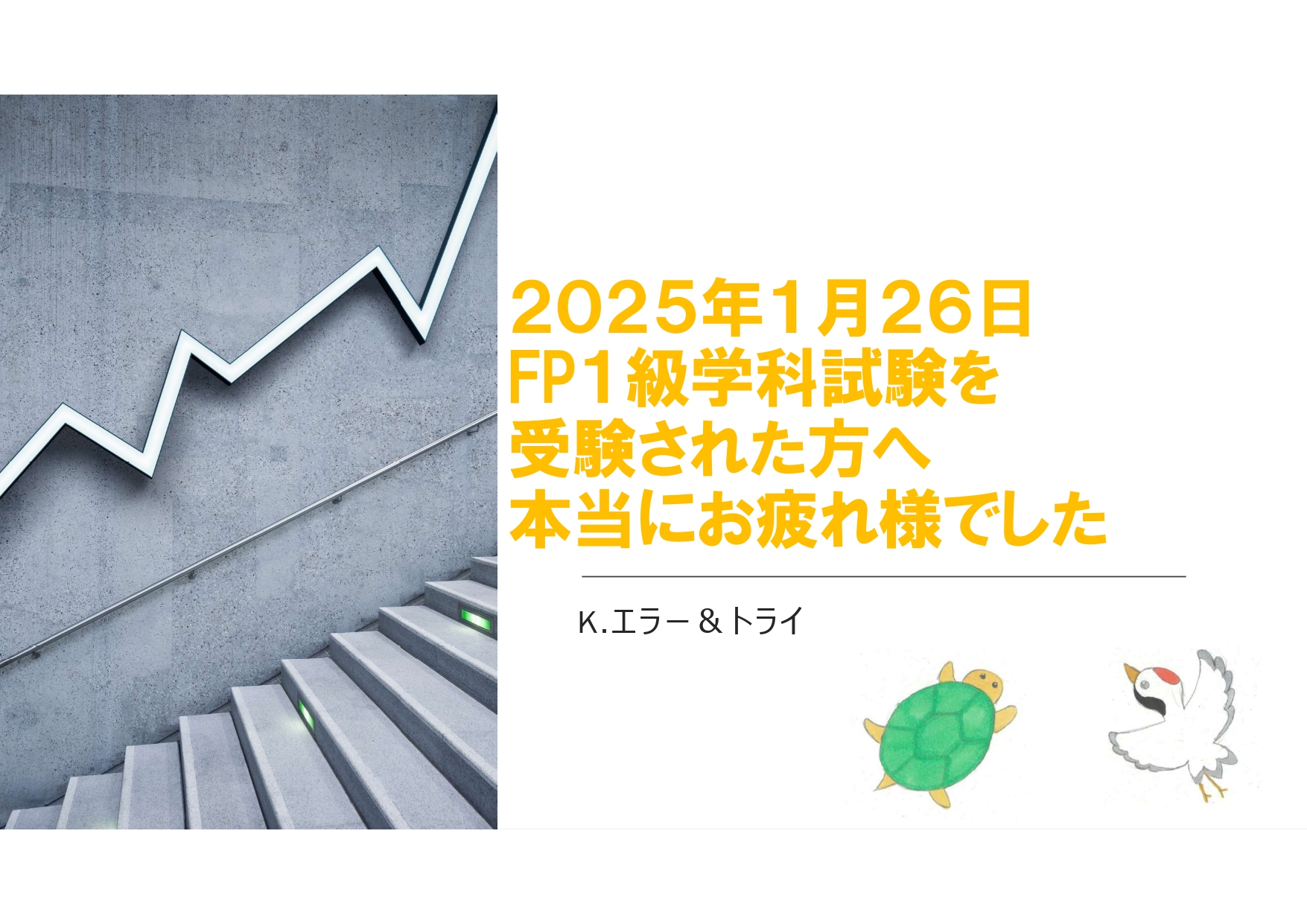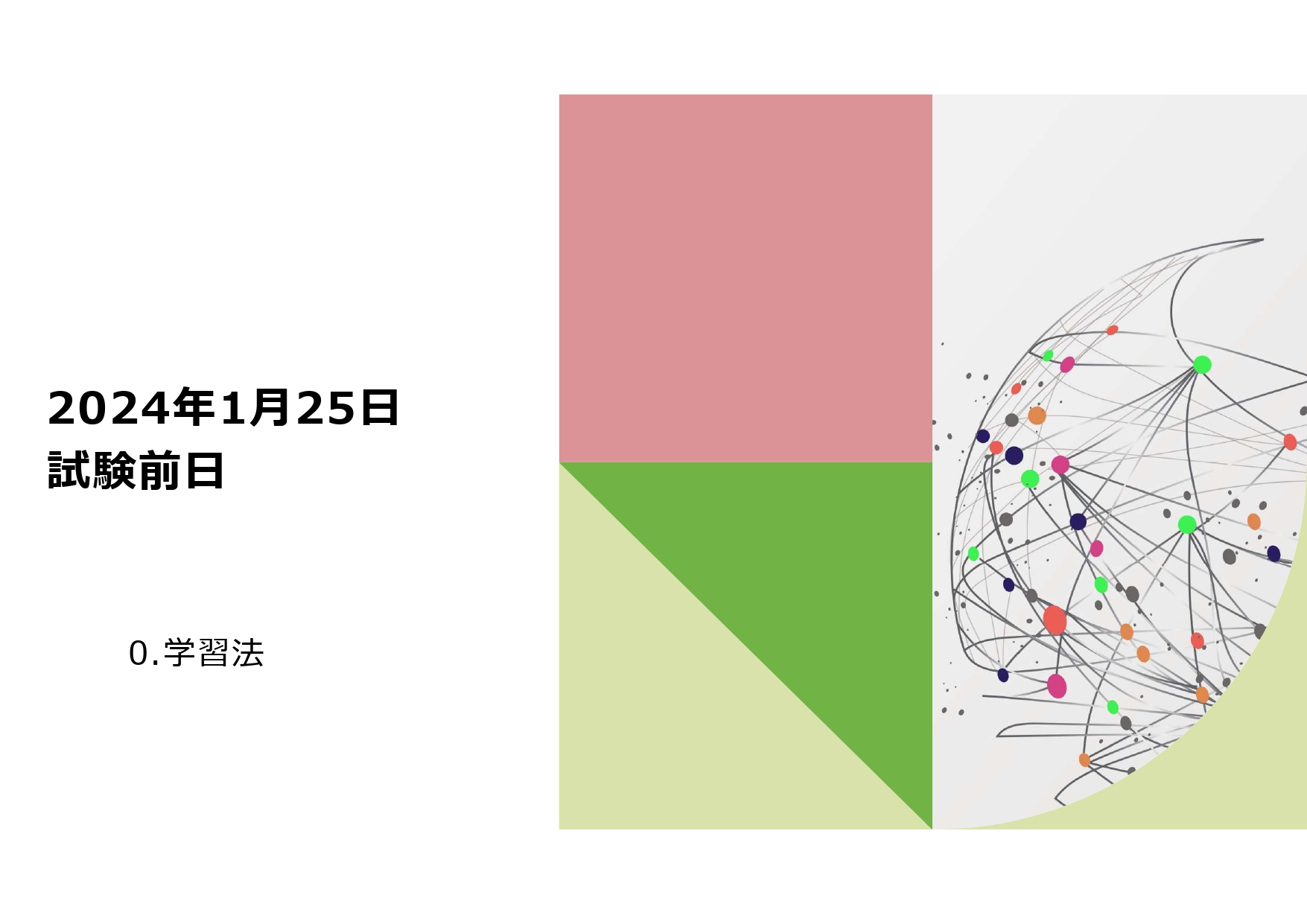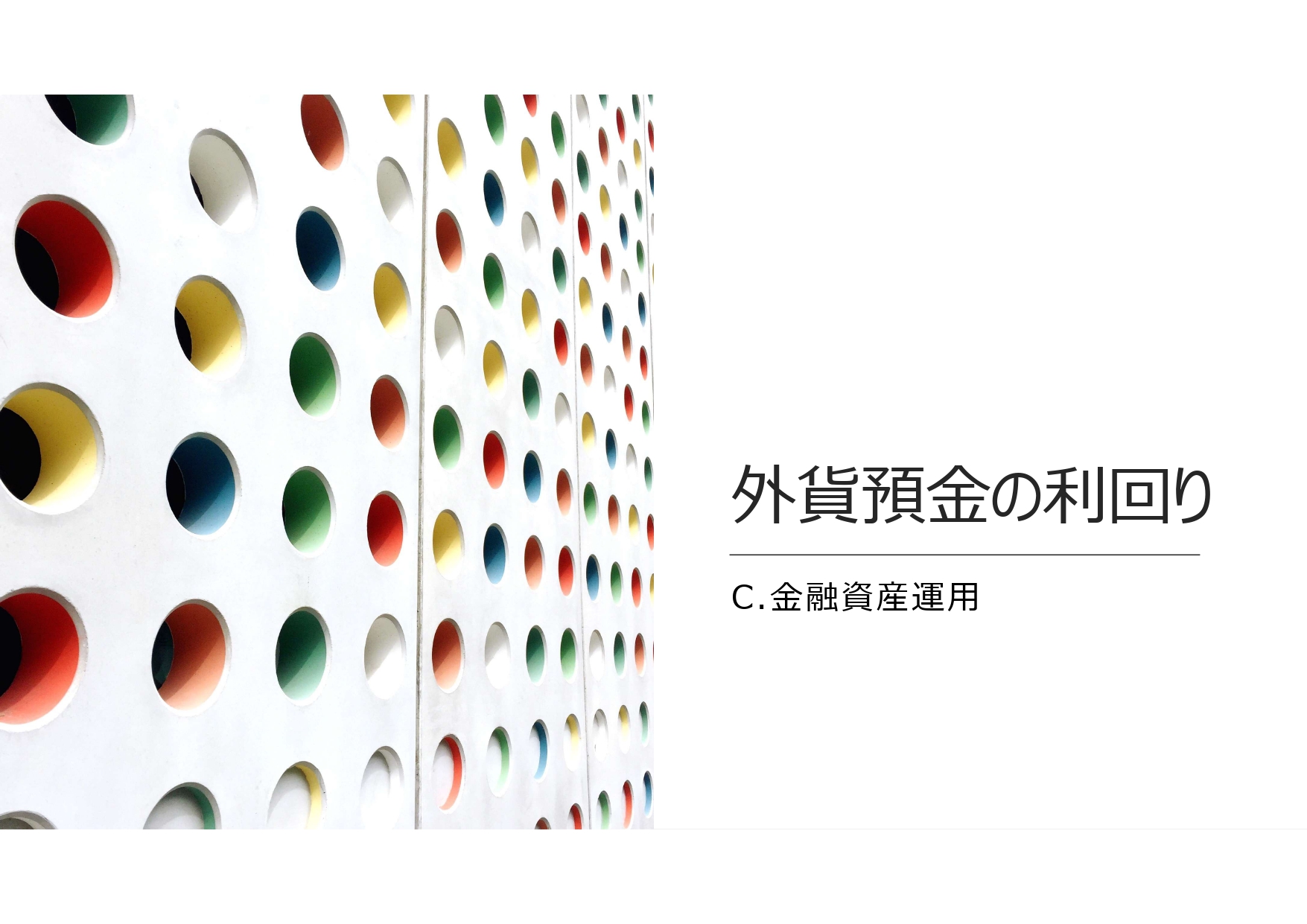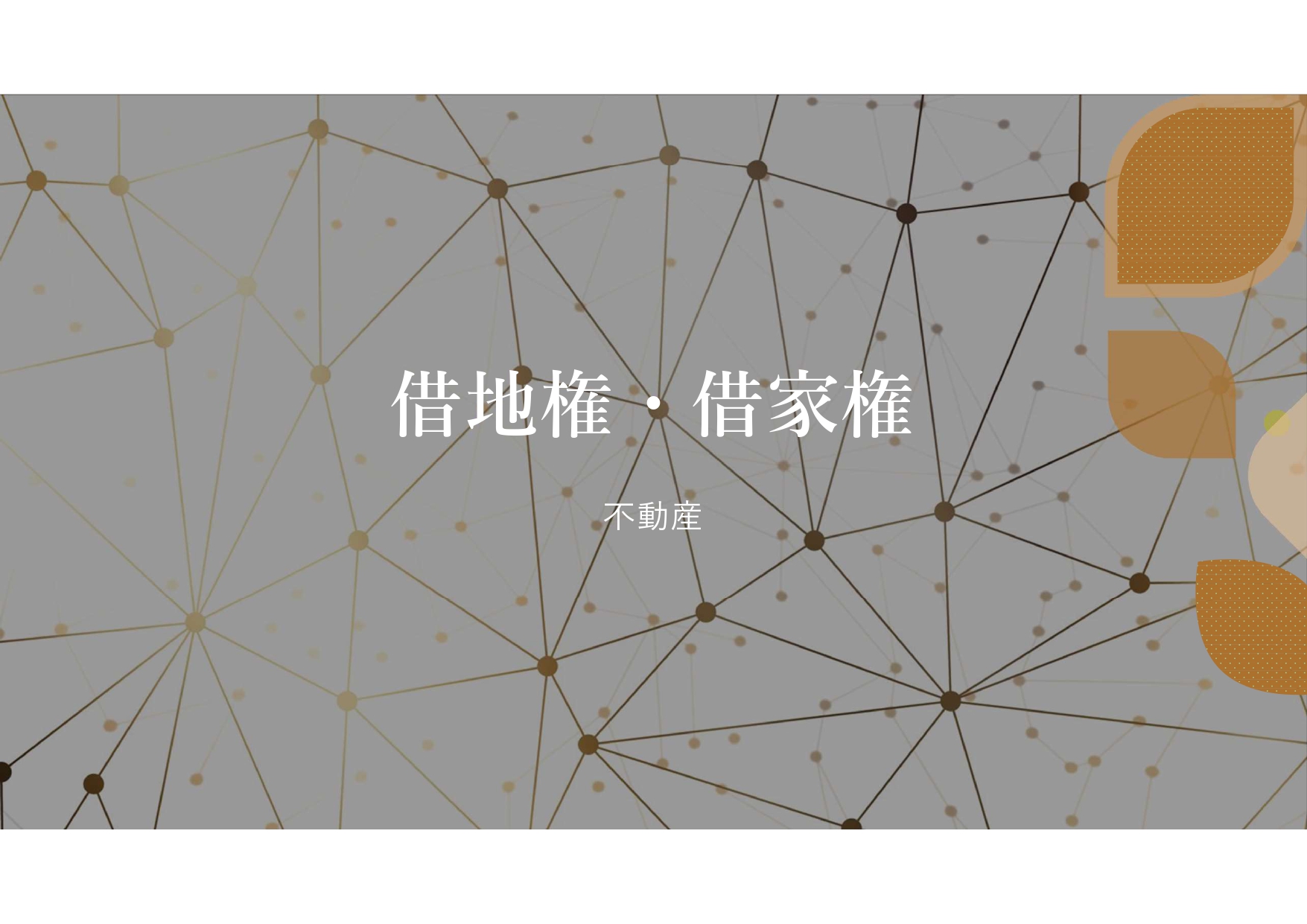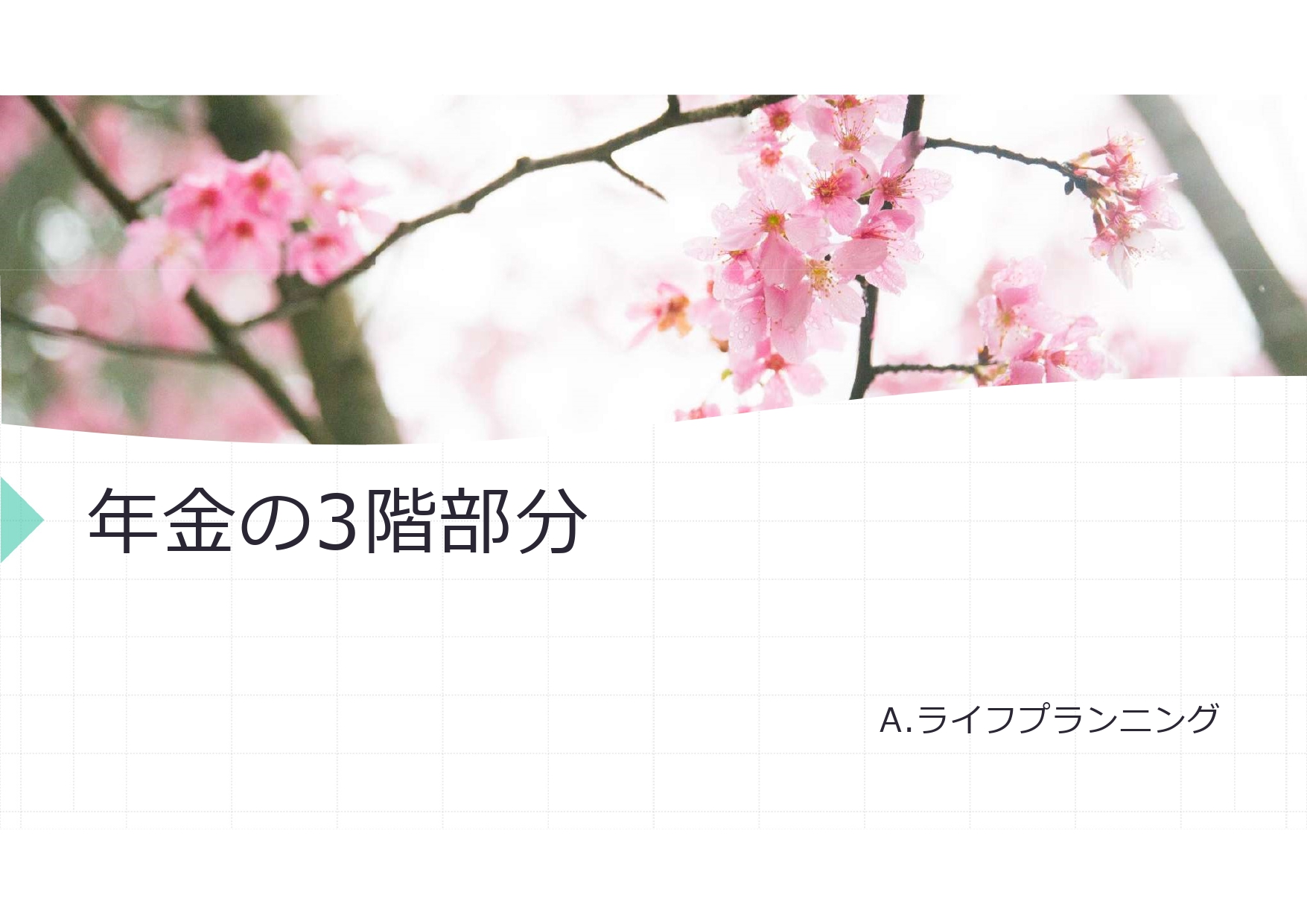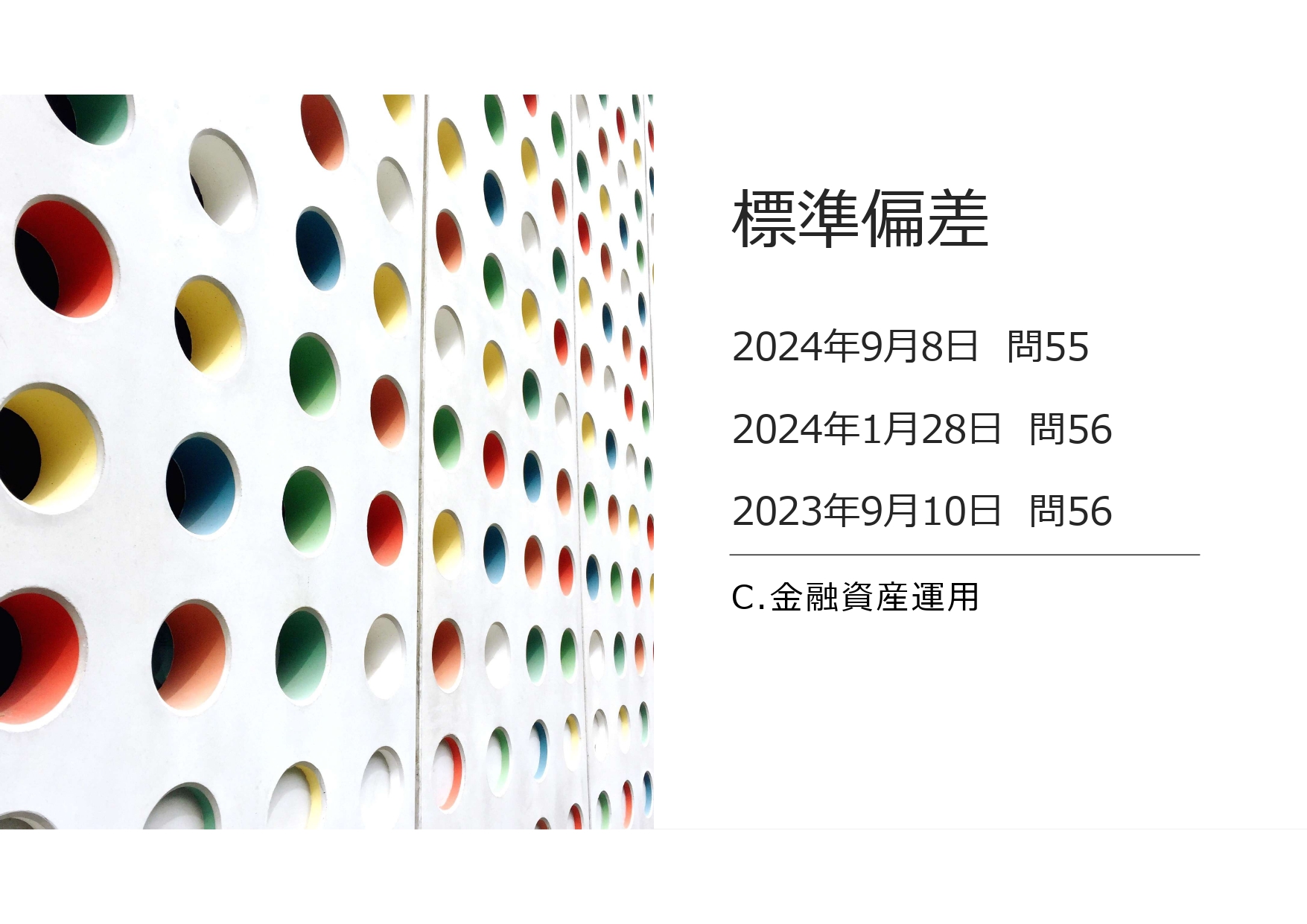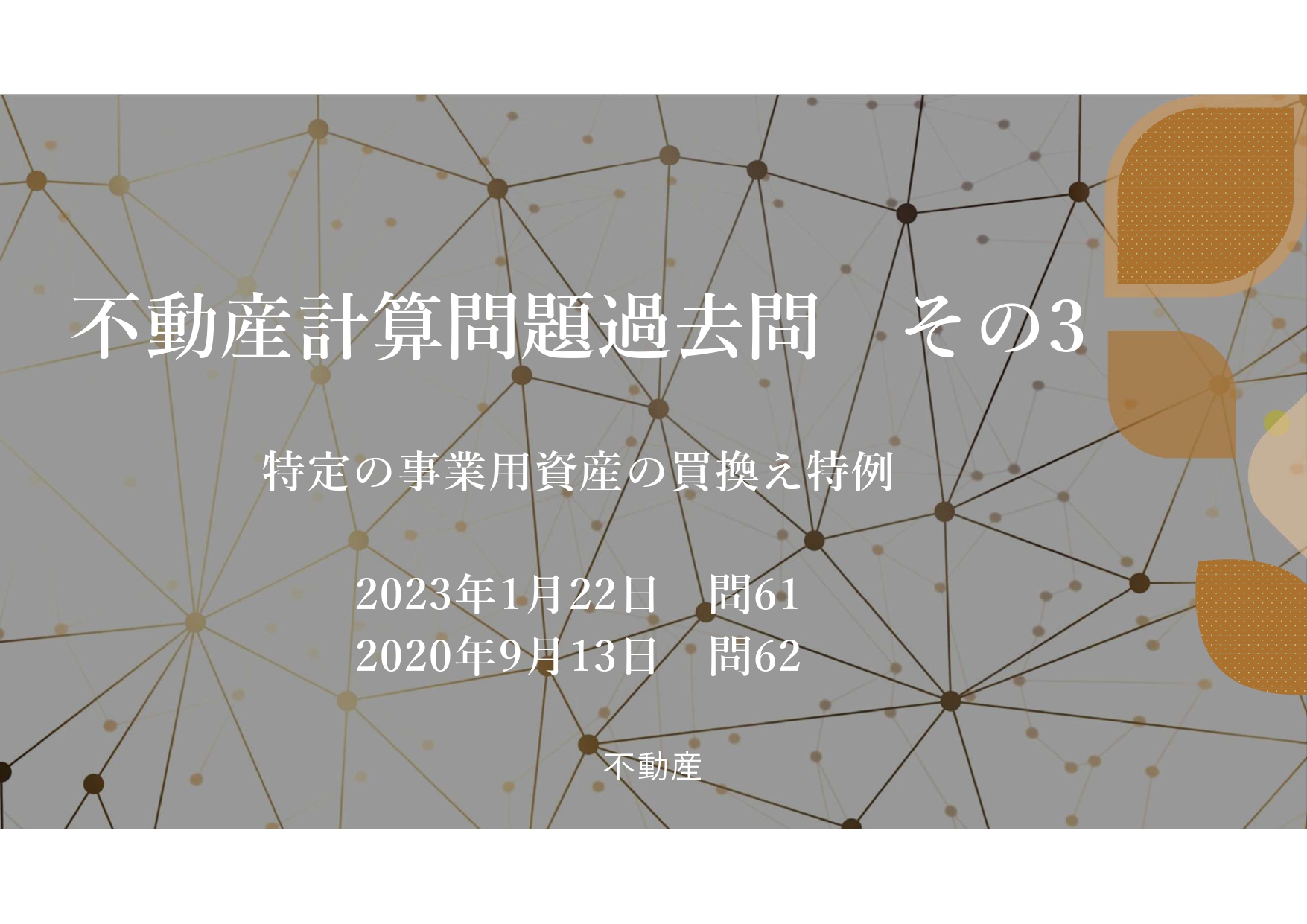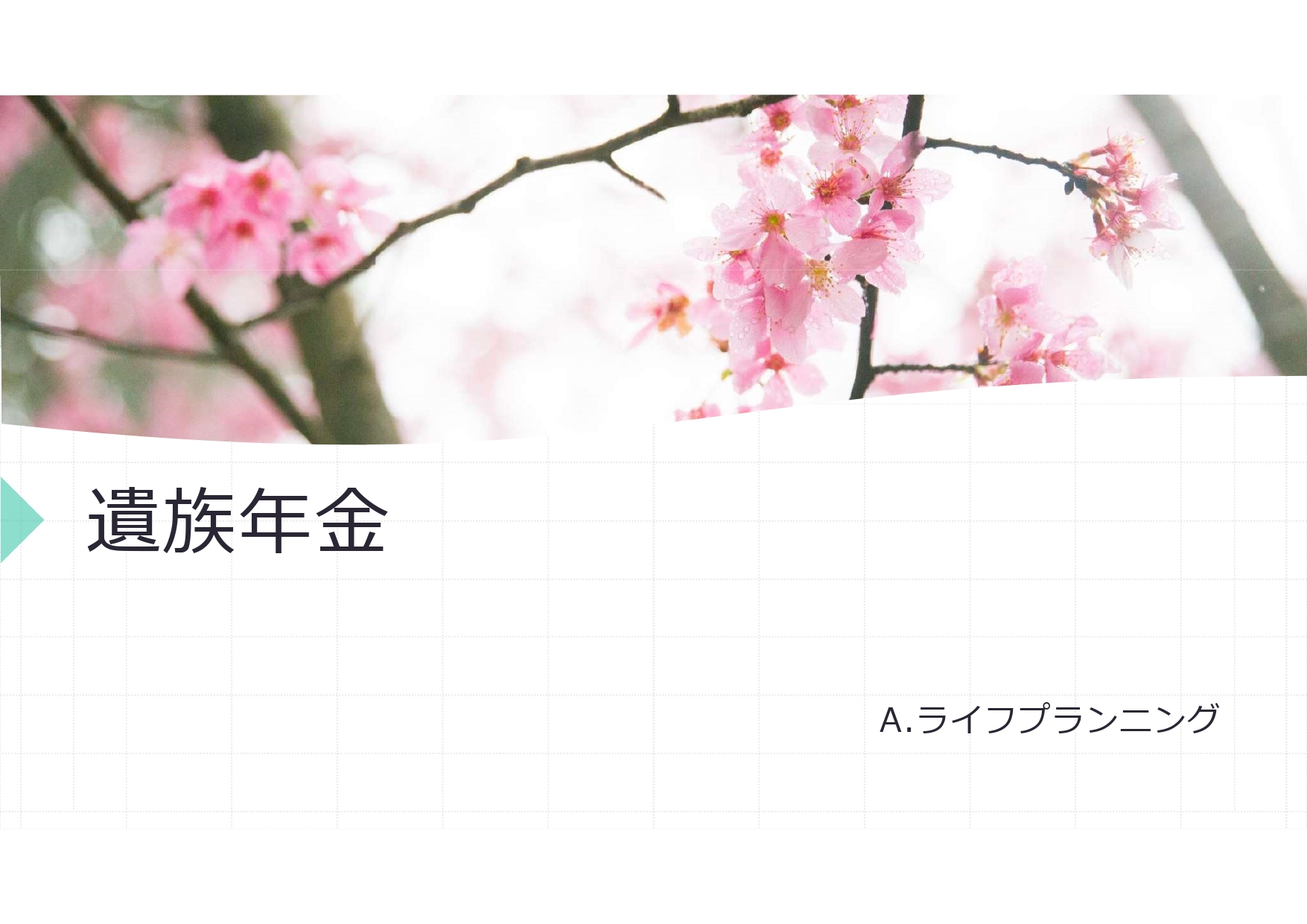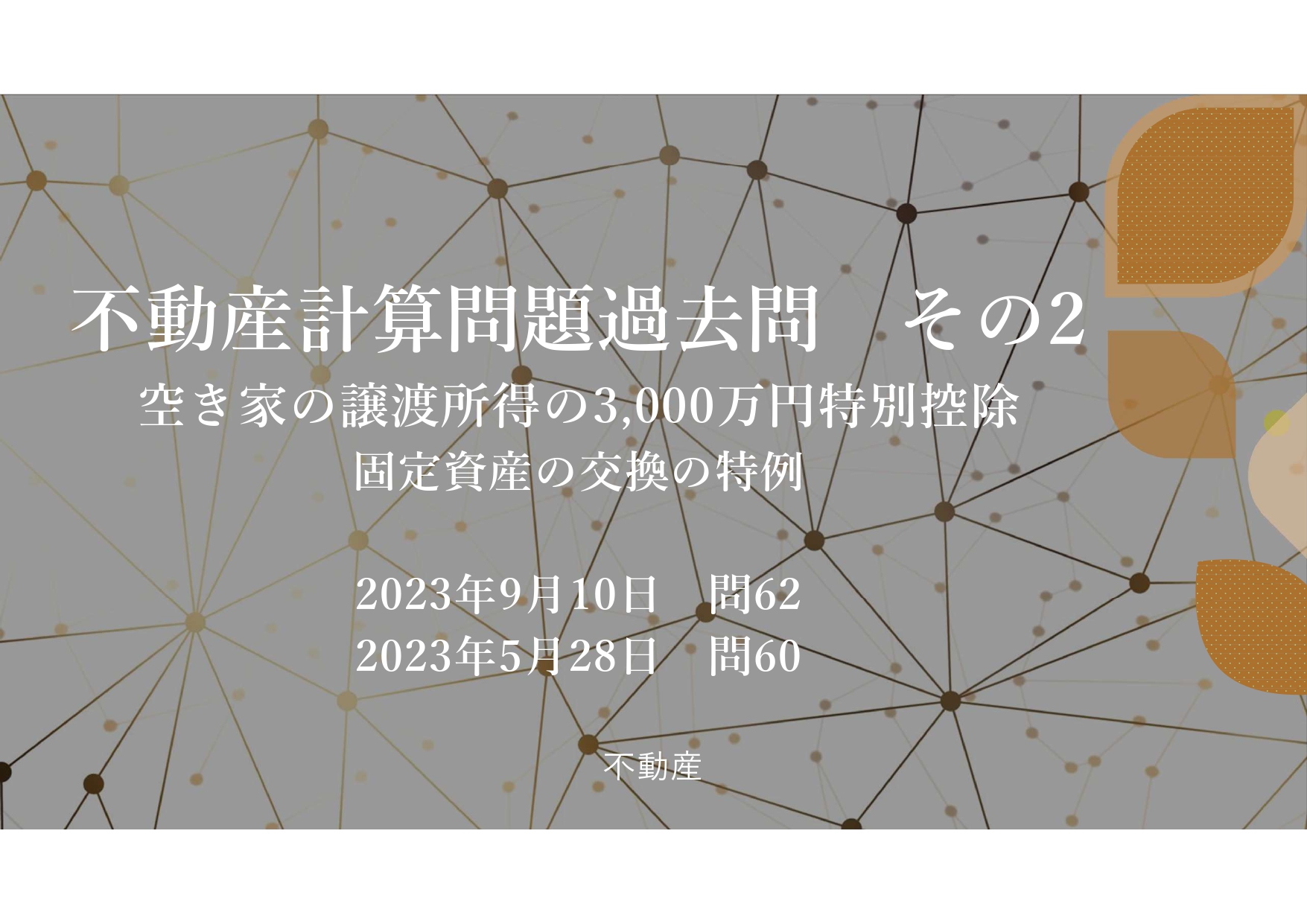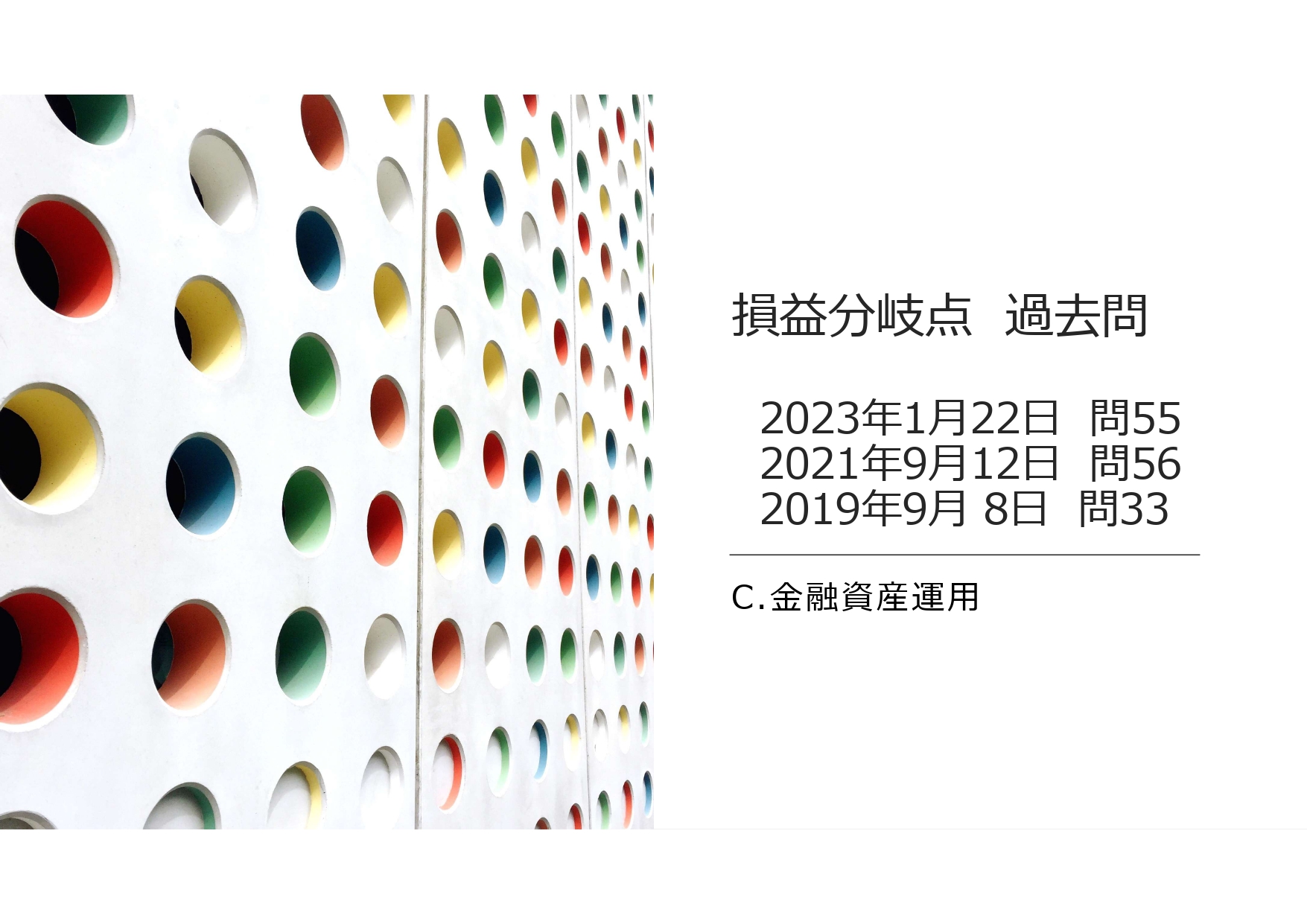道路は道路法や道路交通法で定められたものですが、 FP試験では、建築基準法42条で定められた区分がよく出題されます。 最初はピンとこなかったのですが、道路は必ず、どこかの建築物にたどり着くために設けられているものという理解を私はしています。 ...
月: 2025年1月
土地の有効活用
土地の有効活用をしたいと考えている方の相談にのるという場面も、FPならあると思います。 また、土地所有者の意向を確認する必要があります。 1.自分自身で収益を得たいから、所有している不動産を有効活用したい。 ...
エンジェル税制
所得が多く、毎年、多額の税金を納めており、何か資金の有効活用をしたいと感じている投資家(個人事業主・会社員)で志のある起業家を応援したいと思っている方はいらっしゃると思います。 ...
遺言書
FP1級実技試験では、定期的に遺言書を作成すべきとの設問が出題されます。 しかし、私の周辺に資産家が少ないのか、遺言書を作成している方に出会ったことがありません。 そこでネットで調べてみました。 出所:公益財団法人生命保険文化センター ...
直系尊属からの贈与
この問題は、実技試験で取り上げられることもありますが、 学科試験の基礎編、応用編でも頻出で、FP試験では欠くことのできないテーマです。 それぞれ金額や条件が少しづつ変化している場合があり、注意が必要です。 ...
1月試験お疲れさまでした。
1月26日FP1級学科試験を受けられた方、本当にお疲れさまでした。 3年受験を続けた経験から、少しお話させていただきます。 試験勉強で疲れた体を整えるため、一杯いくのもいいかもしれません。 しかし ...
試験前日
このブログをご覧になっている方 ありがとうございます。 試験前日になりました。 今日時点で 1.勉強が順調で、ハプニングがなければ合格できる方 2.まだ実力は整っていないが、今後の合格のため経験のため受験する方 ...
保険会社の評価
以下の4つは、意味を正確に理解していなくとも計算式だけでも覚える必要があると思います。 基礎編で用語の使い方を入れ替えたり、微妙に違う表現にしたりする正誤問題などが出るため、基本形の算式を覚えておくことが有効だと思います。 ...
インボイス制度
2023年10月1日にインボイス制度が始まり、年商1,000万円以下の中小企業者、、フリーランスで働いている個人事業主など、にわかにざわついていたと思います。 ...
障害年金 過去問
FP1級実技試験 応用編の問53といえば、老齢年金の計算か遺族年金の計算が出題されるのが定番でしたが、 2024年1月試験で初めて障害年金の計算が出題されました。私はこの時、実際に受験していて、目を疑ったことを覚えています。 ...
賃上げ促進税制
賃上げ促進税制とは、企業が積極的に賃上げを行うことを促進し、労働者の所得向上と経済の活性化を図ることを目的とした税額控除制度です。 FP試験では、新たな法改正が度々、出題され、「賃上げ促進税制」も頻出の問題となっています。 このテーマに関する出題は 応用編 ...
外貨預金の利回り
私も、外貨にはうとく、日々ニュースで流れる「1ドル150円から155円になったので円安が進んでいます。」に 「なんで1ドル150円から155円になったのに安くなったの?、高くなってるんじゃないの?」など初歩的な勘違いをしてしまう人でした。 ...
老齢年金 過去問
始めに、老齢基礎年金の計算問題の説明をするのですが、ご存じの通り、2024年4月から老齢基礎年金の満額が816,000円に変更になりました。68歳以上で既に受給されている方は813,700円 2023年から ...
土地の価格
土地の価格の算定は、基礎編、応用編、実技でも出題されることがある問題です。 公示価格は全国約2万6,000カ所の標準地が公開されています。これは、土地の価格として例えば銀座4丁目交差点などが毎年ニュースになります。 基準値標準価格は公示価格を見て、都道府県がもう少し細かく定めています。...
6つの係数
「複利は人類最大の発明だ。 知っている人は複利で稼ぎ、知らない人は利息を払う」とは、有名な発明家アインシュタインの言葉ですが、この複利を使った問題が6つの係数です。 基礎編の問題を解き始めると、第1問に出題される確率が高い6つの係数。 ...
事業者のリスク管理
災いは突然やってくる。 それが自分だけの問題なら、「仕方ない」場合によっては「自業自得」と諦められるかもしれないが、それが周りの人に迷惑をかけることになったら、そういうわけにはいかない。 他人に与えた損害に対して賠償を求められることもある。 ...
借地権・借家権
借地借家法の中でも借地権の問題は、基礎編、応用編、実技試験を通じて、出題され、細かい部分まで問われる可能性があります。 私は最初、苦手分野だったので、途中、いったん宅建の試験勉強をして、ささやかながらのベースアップを試みました。 しかし、重点的に覚えたのは以下の表と ...
年金の3階部分
老齢年金には基礎年金(1階部分)、厚生年金(2階部分)があります。 老齢基礎年金はマクロ経済スライドにより調整されます。令和6年の満額は年額816,000円( 69歳以上の既裁定者は年額813,700円)となります。 ...
遺族年金 過去問
応用編の冒頭、ライフプランニングの出題の多くは問53、最初の山場である年金の計算問題が出題されます。 今回から年金の過去問について、私なりの解説をしますが、 何しろ、年金の過去問解説は難しい、、 ...
標準偏差
FP試験のC分野 金融資産運用 では 標準偏差 という言葉が頻繁に出てきます。 標準偏差とは、集団の得点の散らばり具合を表す数値のことです。集団にいる個人個人が取った得点のバラつきが大きいほど、標準偏差も高くなります。 ...
小規模宅地の特例 過去問
応用編F分野の定番問題は類似業種批准法ですが、何回かに1回、相続税の計算問題が出題されることがあります。 ...
白色申告 過去問
今回は、タックスプランニングの定番である、白色申告について過去問を紹介して、私なりの取り組み方を説明したいと思います。 青色申告の際にも説明しましたが、 事業者の方は税理士と顧問契約を結び、先生にお任せという方が多いと思いますが、 ...
不動産計算問題過去問 その3
特定の事業用資産の買換え特例 特定の事業用資産の買換えの特例のパターンは10種類以上あり、状況により使える特例や地域性に係る要件もあるため、一概に語ることはできませんが、 FP試験の過去問で私が見つけたのは賃貸住宅への買換えのケース2事例です。 ...
建ぺい率・容積率 過去問その3
建ぺい率・容積率の過去問も3回目です。2回分の過去問紹介に加えて、今回は 2022年1月22日 問61も紹介します。 この回を取り上げるのは、初めて容積率のみ計算させる問題だったのと、 ...
遺族年金
応用編のライフプランニングの分野で、老齢年金と同様に計算問題がよく出題されています。 日本は高齢化社会であり、2,024年7月26日に厚生労働省が発表した「令和5年簡易生命表の概要」によると、2023年の平均寿命は、男性81.09年、女性87.14年 ...
青色申告 過去問
今回は、タックスプランニングの定番である、青色申告について過去問を紹介して、私なりの取り組み方を説明したいと思います。 事業者の方は税理士と顧問契約を結び、先生にお任せという方が多いと思いますが、 FPも相談を受けることが無いとも限りません。 ...
相続税・贈与税の税率
公益財団法人生命保険文化センターのHPによると、「相続税が課税された被相続人(死亡者)は9.6%」ということです。 おおよそ10人に1人くらいしか相続税がかからないという計算になりますが、FP試験では、毎回といっていいほど、相続税、贈与税の計算問題や知識問題が出題されます。 ...
不動産計算問題過去問 その2
今回、取り上げるテーマは「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」と「固定資産の交換の特例」です。 相続空き家はクローズアップされている社会問題です。 ...
建ぺい率・容積率 過去問その2
FP1級学科試験で、ほぼ100%出題されると言ってもいいのが、建ぺい率・容積率を求める問題です。 建ぺい率・容積率については、こちらもご覧ください。 2024年1月28日 問61 今回は、建ぺい率の計算はオーソドックスなものでしたが、 ...
損益分岐点 過去問
数年ごとに損益分岐点を求める出題があります。 そもそも損益分岐点とは利益がゼロになる売上高を求めるものであり、 「これ以上の売上から黒字になりますよ。」という分岐点を求めるものです。 ...