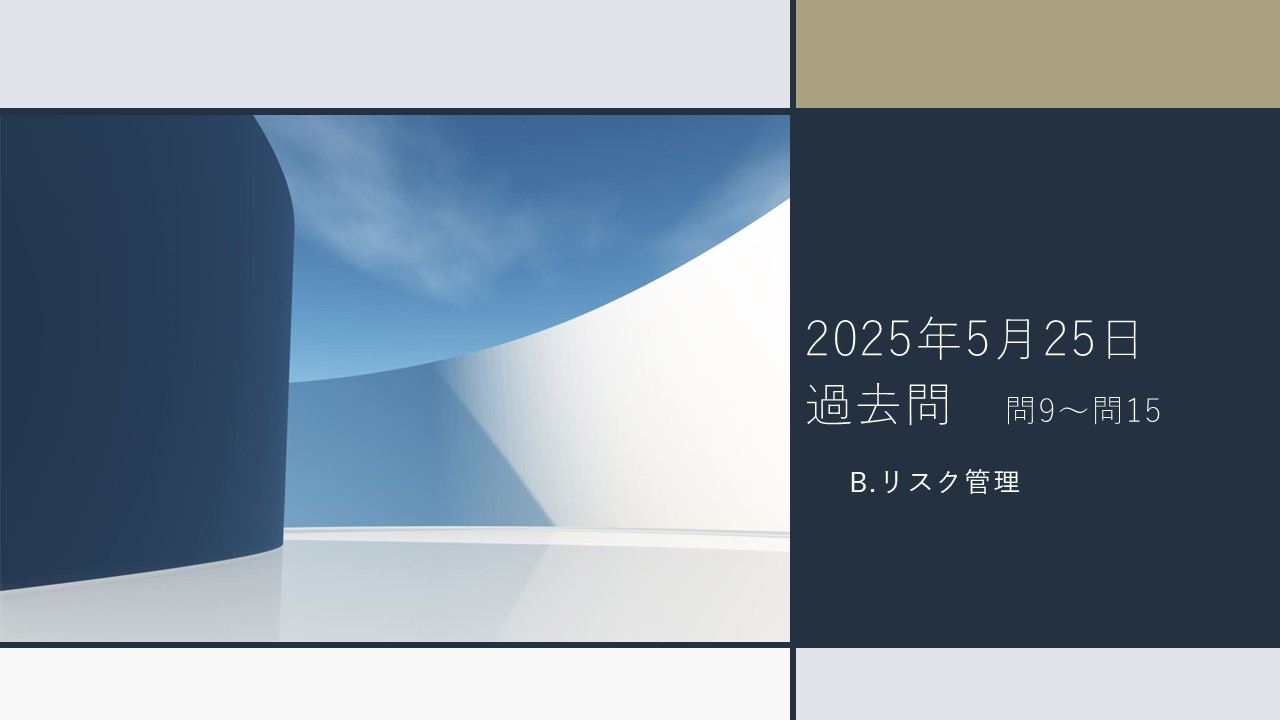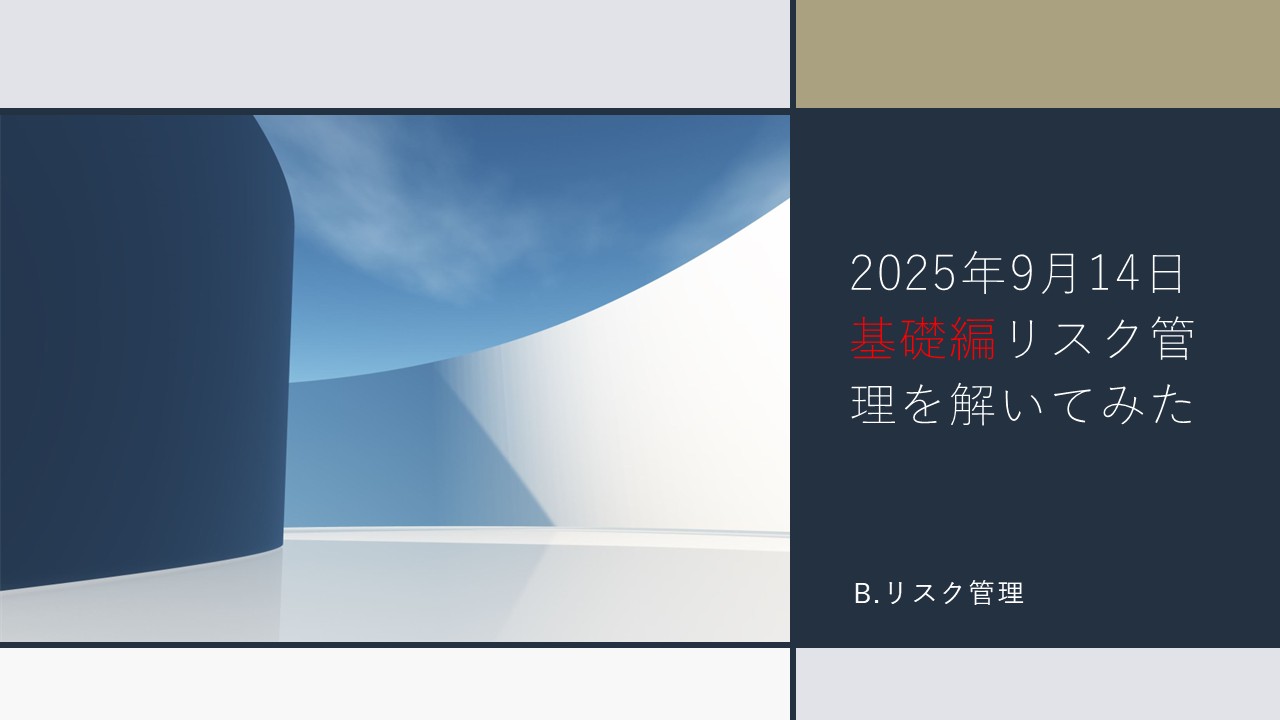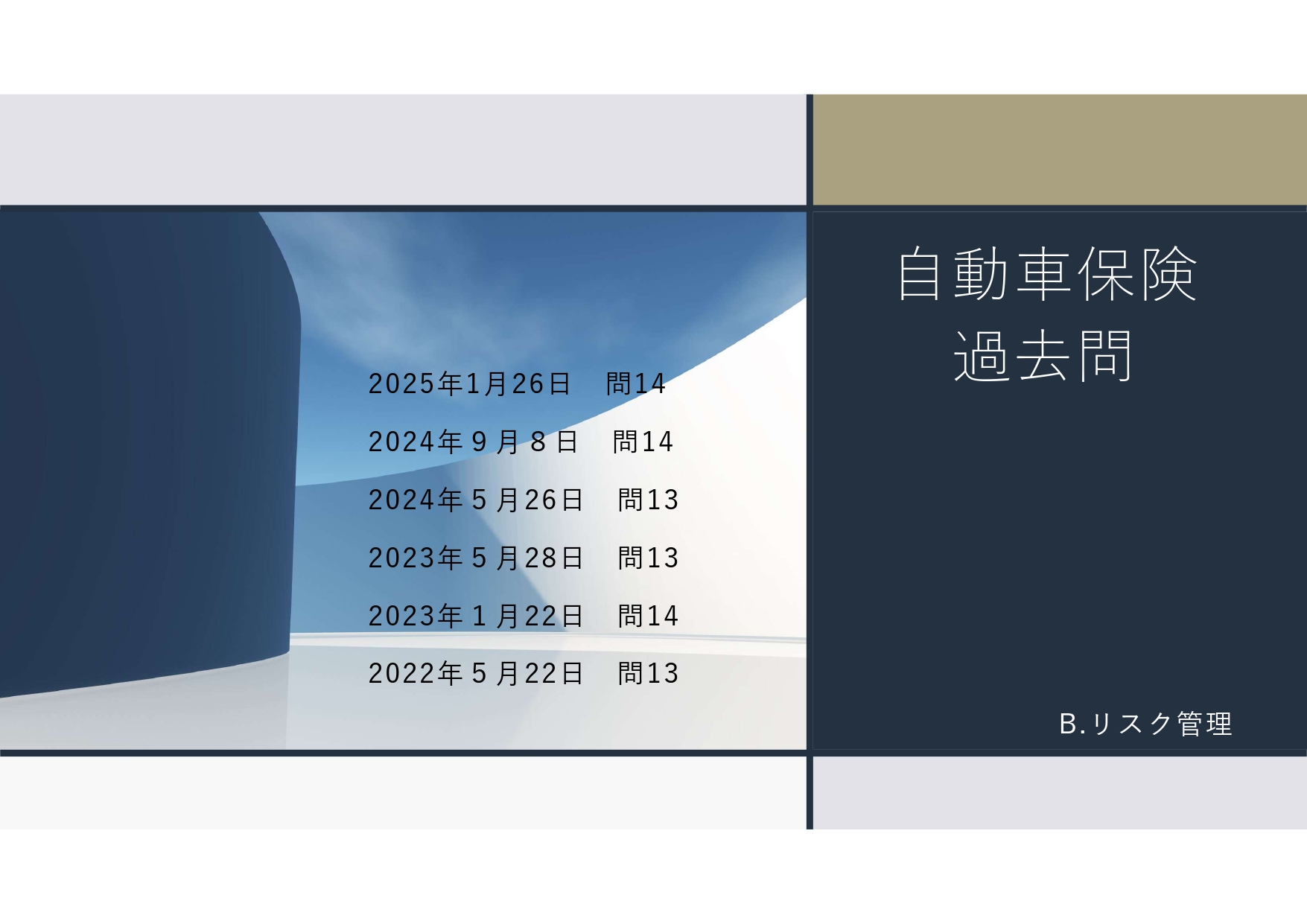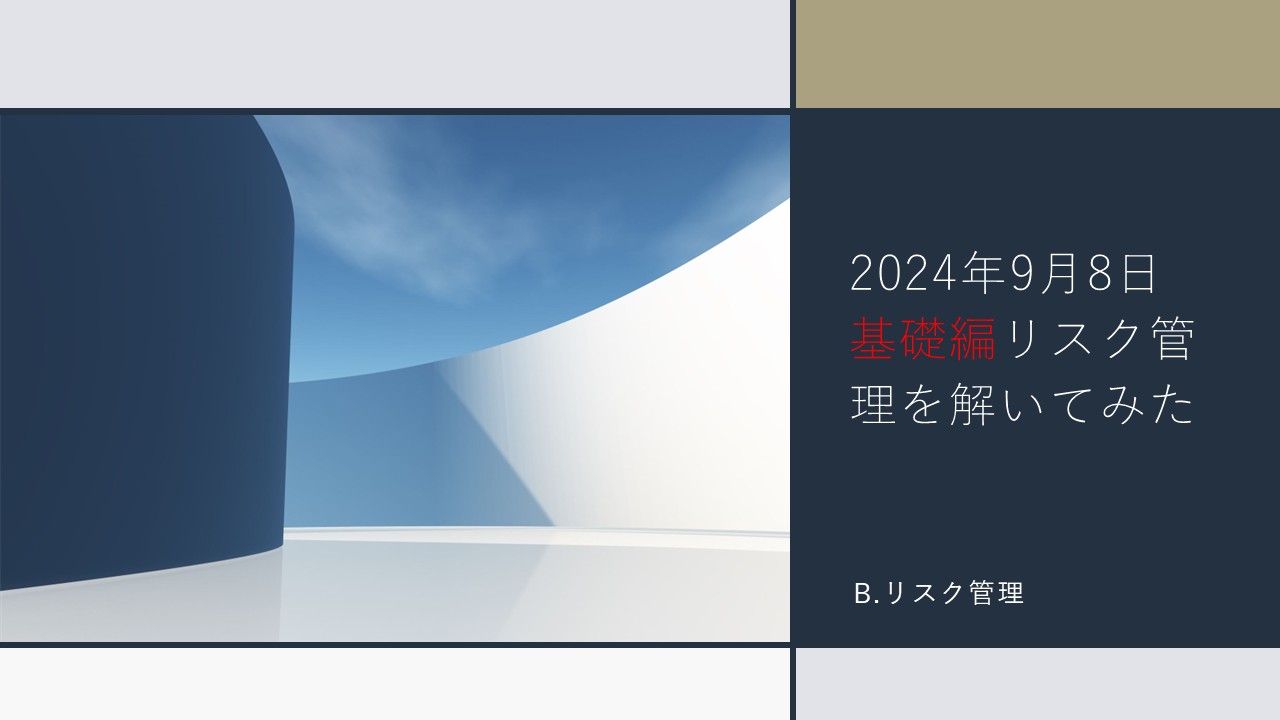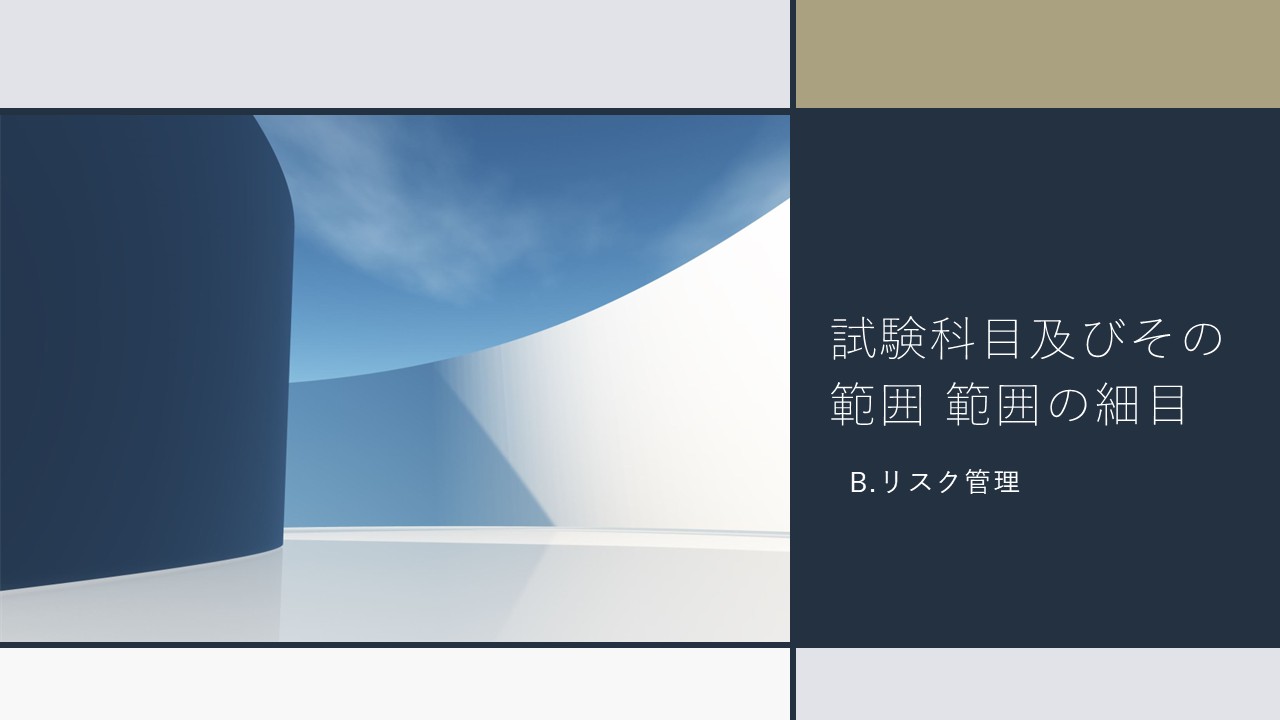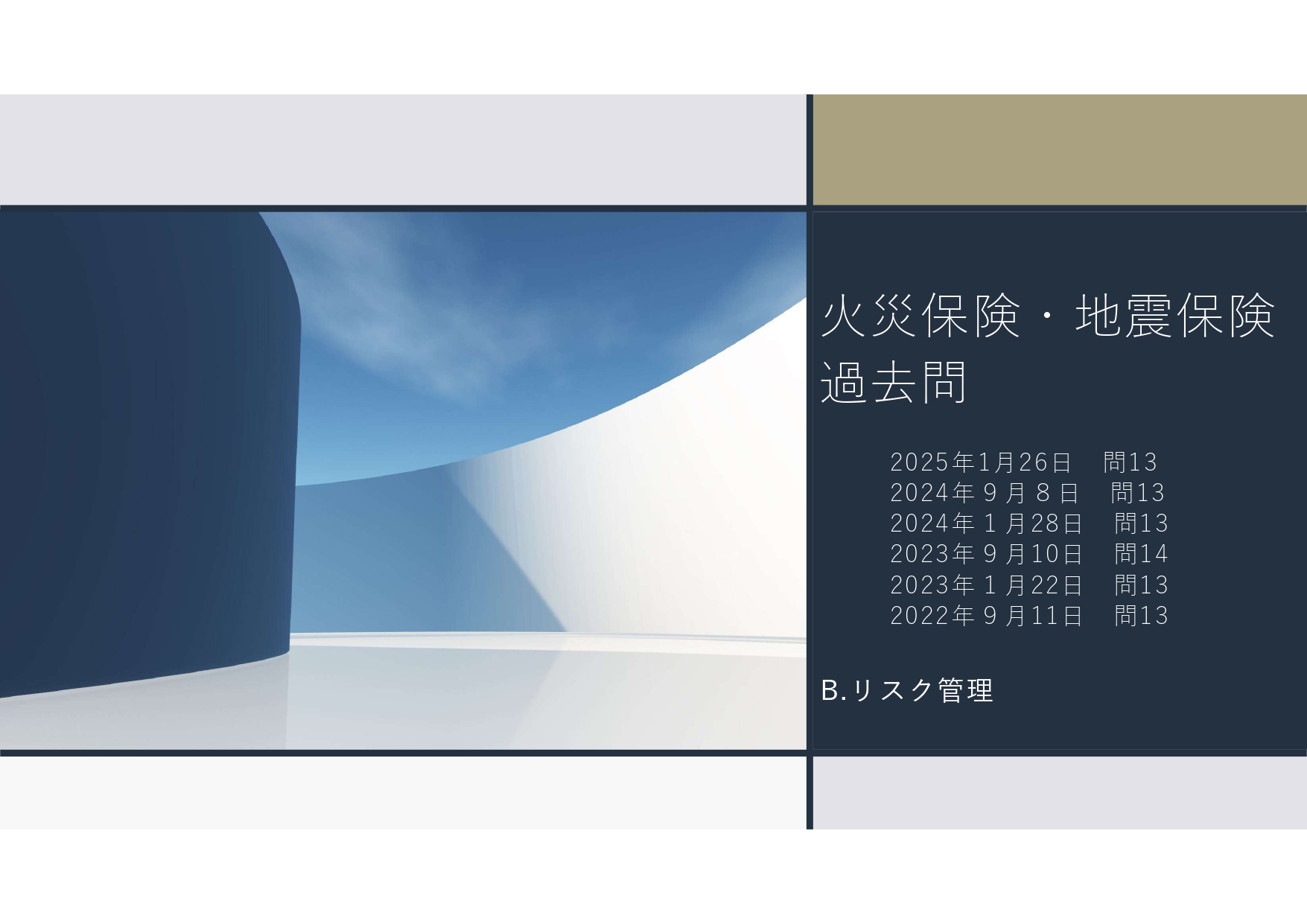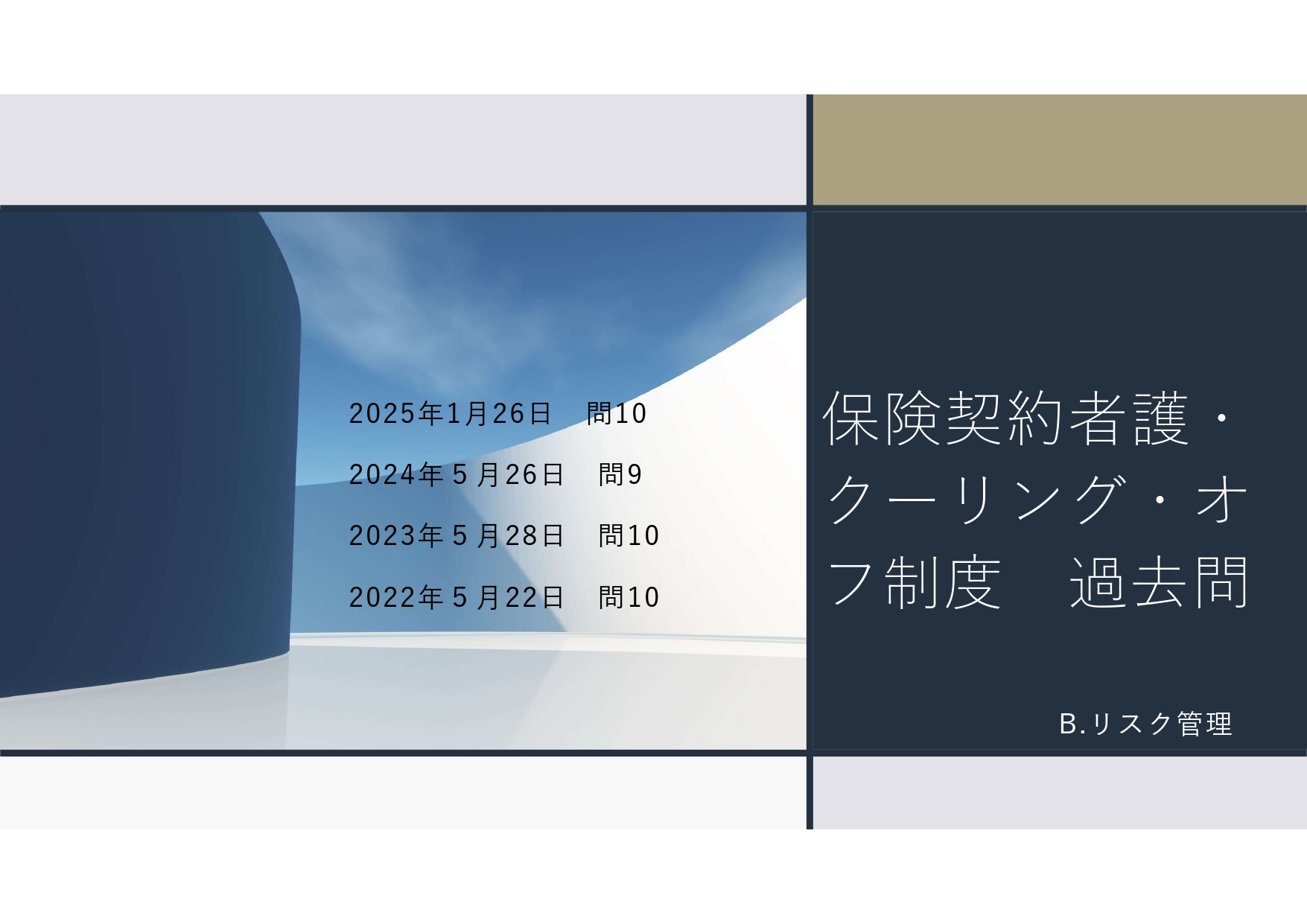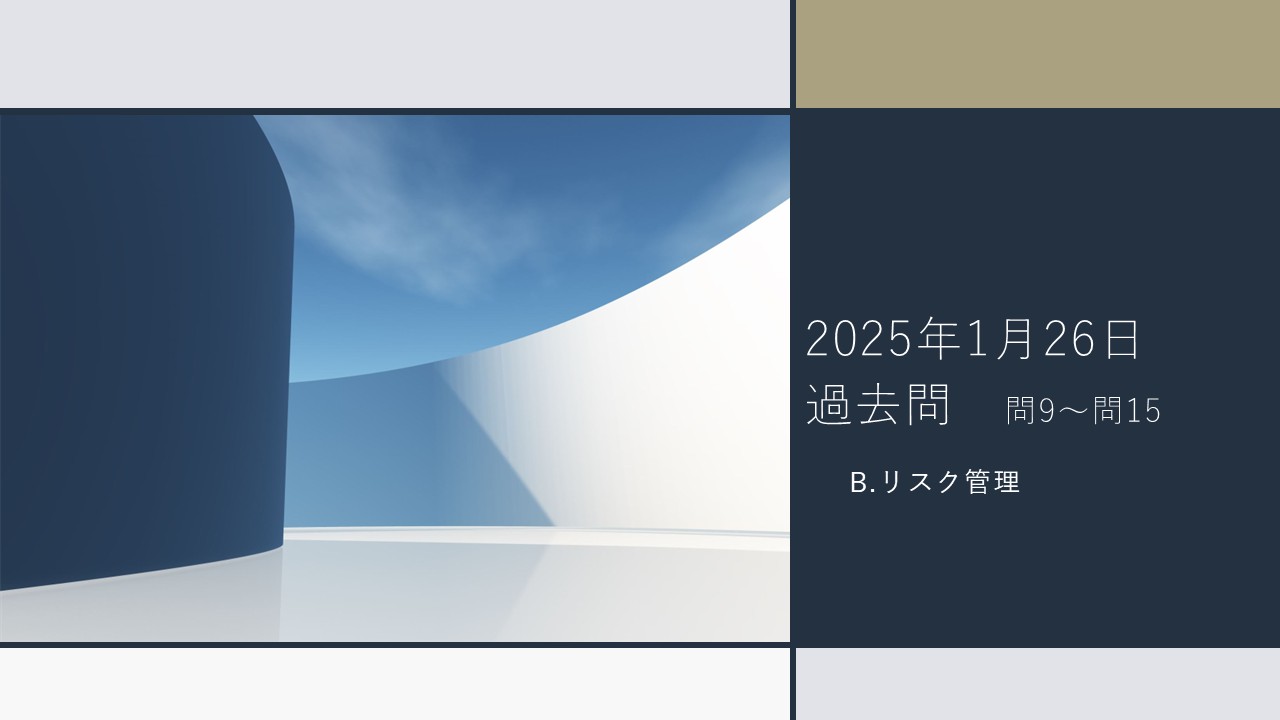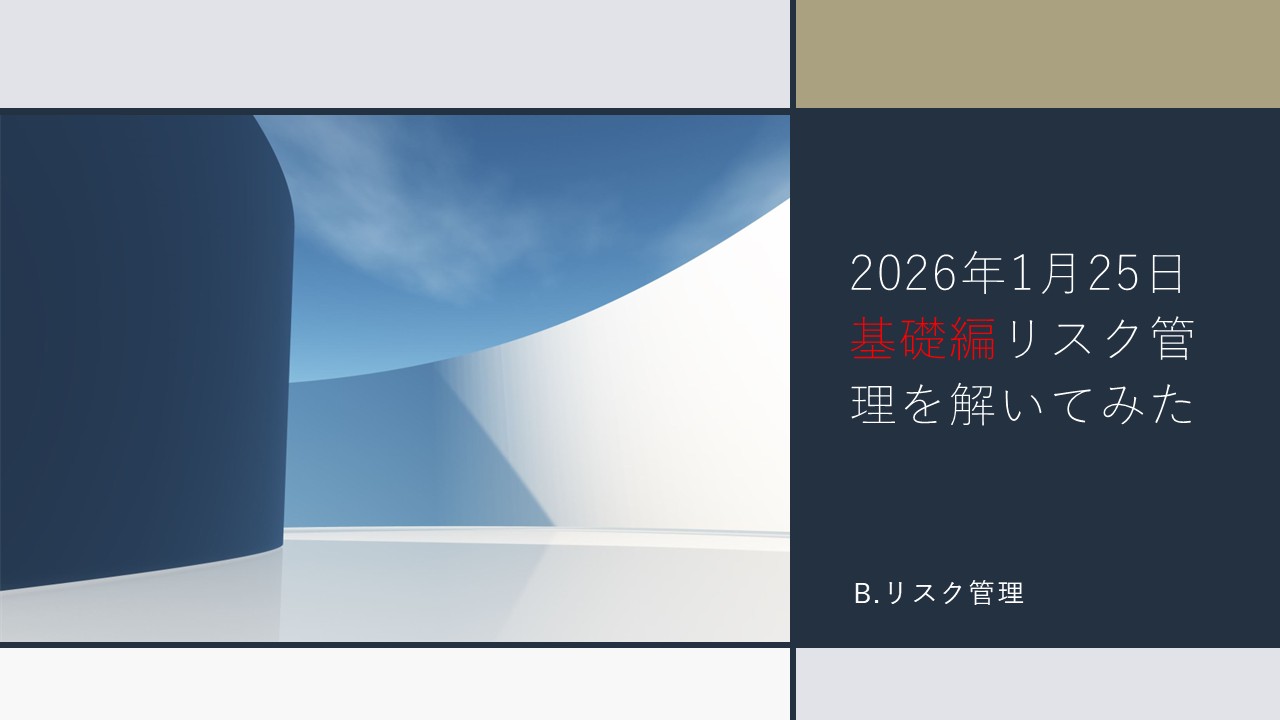生命保険 過去問 その1
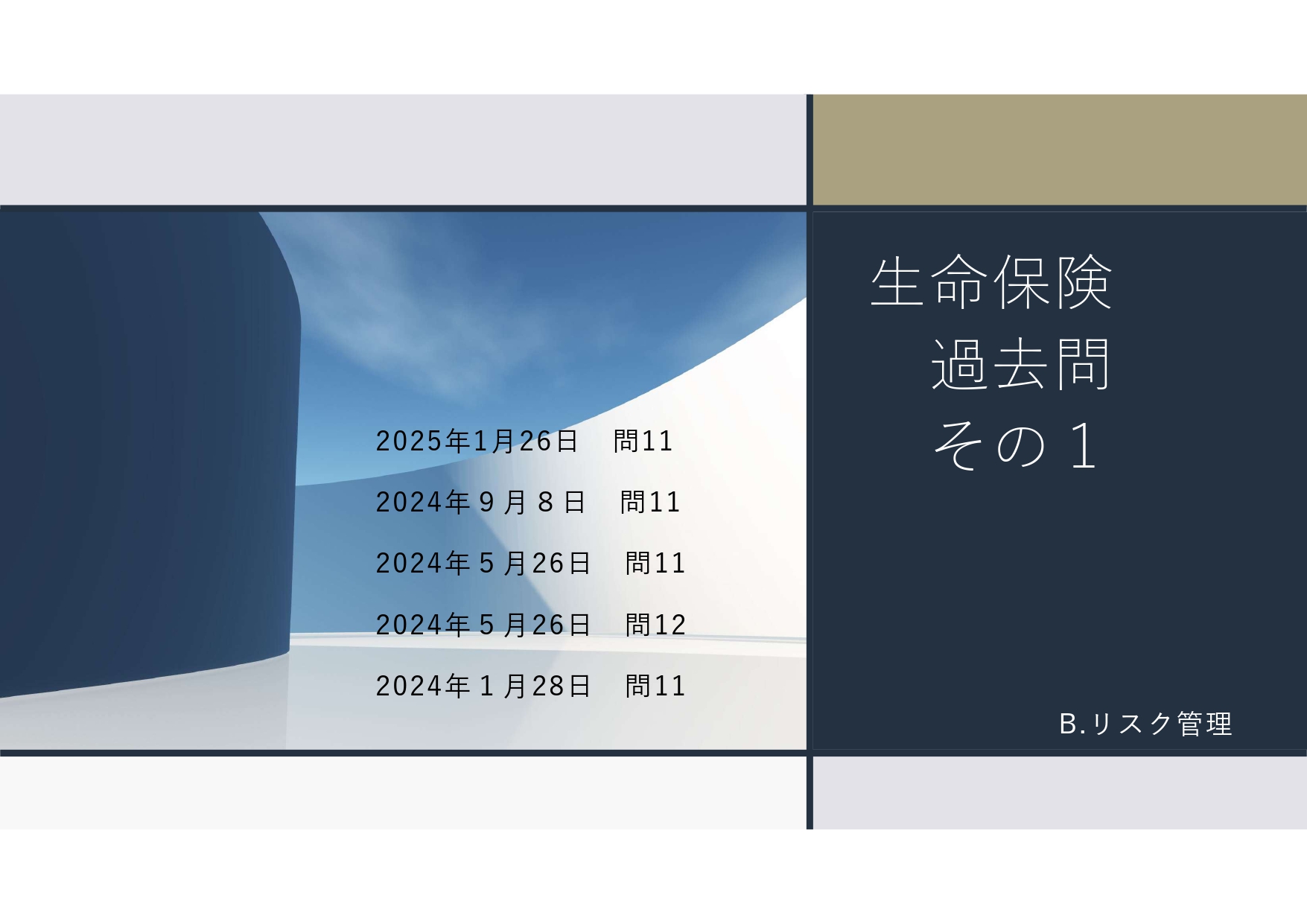
生命保険は、公益財団法人生命保険文化センター2022年度「生活保障に関する調査」によると役8割の方が生命保険に加入しているようです。
FP試験のリスク管理分野でも、生命保険の問題は、ほぼ毎回出題され、回によっては、2問、3問出題されることもあります。
つまり、リスク管理でゼロ点を回避するためには、生命保険を完璧にしておけば、ほぼ大丈夫といえるかもしれません。
今回から2022年5月試験まで、さかのぼり過去問を見ていきたいと思いますが、ボリュームが多いため、2回に分けて解説したいと思います。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2025年1月26日 問11
| 生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 逓増定期保険は、保険期間の経過とともに所定の逓増率により死亡保険金額が増加する保険であり、通常、死亡保険金額は基本保険金額の10倍に達するまで増加する。 (b) 特定疾病保障定期保険は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中などの特定疾病による所定の状態について保障する保険であり、被保険者が特定疾病により高度障害状態になった場合は、特定疾病保険金と高度障害保険金をそれぞれ受け取ることができる。( (c)収入保証保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金受取人が毎月一定額の給付金を年金形式で受け取ることができる保険であり、支払われる給付金の総額は保険期間の経過に伴って増加する。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解4

分野を問わず、いくつあるか問題は苦しめられるんだよね。全部○か全部×って選びにくいけど、FP試験では、よくあるんだよね。

(a) 逓増定期保険の説明は正しいと思うけど、通常、死亡保険金額は基本保険金額の5倍に達するまで増加するよ。10倍じゃないね。よって不適切。
る。
(b) 特定疾病保険金と高度障害保険金は重複して受け取ることはできません。よって不適切。
(c) 収入保障保険の給付金の総額は保険期間の経過に伴って減少するよ。よって不適切。
この選択肢は全て不適切なので4)だね。
2024年9月8日 問11
| 生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 契約転換は、現在加入している生命保険契約を活用して同一の保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。 2)払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。 3) 契約者貸付は、一般に、契約者が加入している生命保険契約の利用時点の解約返戻金額を限度として保険会社から貸付を受けることができるものであり、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。 4) 契約者貸付の利率は、一般に、生命保険契約の契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。 |
正解4

契約転換、払済保険、契約者貸付って生命保険って契約したらそれで終わりでなく、保険料を支払うのが苦しくなった時のことも考えないといけないんだよね。

1)積立配当金は払い戻されません。同じ保険会社の新規保険契約の保険料に充当されるよ。
2)払済保険に変更した場合、予定利率は元契約のまま維持されるんだよ。
3)貸付を受けれるのは解約返戻金額は全額でなく7割から9割くらいだよ。そんなに甘くはないね。
4)これが正しい記述だね。正しい選択肢を覚えるのは合格への近道だよ。
よって正解は4)
2024年5月26日 問11
| 個人年金保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 定額個人年金保険(10年保証期間付終身年金)の保険料は、被保険者の性別以外の契約内容が同一である場合、被保険者が女性であるよりも被保険者が男性であるほうが高くなる。 2) 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の保険料は、払い込んだ年の個人年金保険料控除の対象となる。 3) 外貨建個人年金保険の円換算支払特約とは、年金や解約返戻金等を保険会社所定の為替レートに基づいて換算された円貨で受け取ることができる特約である。 4) 個人年金保険(10年確定年金)の年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、死亡給付金受取人に対し、既払込保険料総額から既払年金合計額を差し引いた額が一括して支払われる。 |
正解3

生命保険ってなんとなく遺族が受け取るというイメージだったけど、老後の生活や、障害を負った時の生活、医療費の補助という役割も担っているんだね。

1)終身年金は、平均余命が長い女性の方が高くなるよ。生きている限りもらい続けれるもんね。
2)税制適格特約は保険料の払い込み期間が10年以上が要件なので、一時払いは対象外だよ。
3)円換算支払特約は、あくまで円で受け取れる特約であって、為替変動リスクは回避できないよ。よってこれが正解
4)個人年金保険(10年確定年金)の年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、遺族が残りの期間、年金を受け取るのが基本だよ。残りの年金を一括で受け取る方法もあるけどね。
よって正解は3)だよ。
2024年5月26日 問12
| 居住者であるAさん(65歳)は、2023年中に下記の生命保険の年金および解約返戻金を受け取った。当該生命保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aさんは給与所得者ではなく、Aさんが2023年中に受け取った下 記の年金および解約返戻金以外の収入は、老齢基礎年金および老齢厚生年金の合計350万円のみである。 |
| ① 個人年金保険(10年確定年金)の年金 契約年月日 : 1992年4月1日 契約者(=保険料負担者) : Aさん 年金受取人 : Aさん 年金額(年額) : 100万円 正味払込保険料(累計額) : 450万円 ② 一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金 契約年月日 : 2016年10月1日 契約者(=保険料負担者) : Aさん 解約返戻金額 : 1,100万円 正味払込保険料 : 1,000万円 ③ 一時払外貨建養老保険の解約返戻金 契約年月日 : 2020年10月1日 契約者(=保険料負担者) : Aさん 解約返戻金額 : 700万円 正味払込保険料 : 500万円 |
| 1) Aさんが個人年金保険(10年確定年金)から受け取る年金は、年金額から当該年金額に対応する正味払込保険料の額を控除した金額に20.315%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収等される。 2) Aさんが一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となる。 3) Aさんが一時払外貨建養老保険を解約して受け取った解約返戻金は、金融類似商品として源泉分離課税の対象となる。 4) Aさんは、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超えるため、2023年分の所得税について確定申告をしなければならない。 |
正解1

年金解約時の一時所得、雑所得、金融類似商品の見極めが必要な問題だね。
5年以内なら金融類似商品だけど、終身の解約は一時所得になるという考えでいいんだろうか?

1)個人年金保険の税率は払込保険料を控除した額が25万円以上の場合10.21%だね。よってこれが誤りだね。
時間が無ければ、2)~4)は読まなくていいと思うけど、念のため、
2)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を2017年契約で2024年に解約しているのだから、一時所得になるよ。
3)一時払外貨建養老保険は2020年契約なので、5年以内の解約の場合、金融類似商品になるよ。
4)2)の一時所得を計算すると25万円と20万円を超えるため確定申告が必要になるね。
よって誤りは1)だね。
2024年1月28日 問11
| 生命保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険の基本年金額を減額した場合、減額した基本年金額に相当する解約返戻金相当部分は、将来の増額年金として積み立てられる。 2) 指定代理請求特約における指定代理請求人の範囲は、被保険者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹とされ、甥や姪は被保険者と生計を一にしていたとしても指定代理請求人になることができない。 3) 契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の年齢等により算出され、転換時において告知等をする必要がある。 4) 市場価格調整(MVA)機能を有する終身保険の解約返戻金は、解約時の市場金利が契約時と比較して上昇していた場合には減少し、低下していた場合には増加することがある。 |
正解2

年金もそうだし、労災もそうだけど、3親等以内が対象になるかならないか、ってややこしいね。生計を一にするという定義も理解が曖昧だよ。

1)個人年金保険料税制適格特約というのは、問題文のように将来の年金を増額する原資とされるので、問題文は正しいよ。
2)指定代理請求人の範囲は、被保険者の配偶者、直系血族、同居または生計を一にしている3親等以内の親族なので、甥姪は生計を一にしていれば対象だね。よってこれが間違い。
3)契約転換制度では、転換時の保険料は年齢や保険料率で計算されるよ。
4)市場価格調整(MVA)は解約返戻金が金利に応じて変動する仕組みで、逆相関の関係にあるよ。
よって正解は2)だよ。