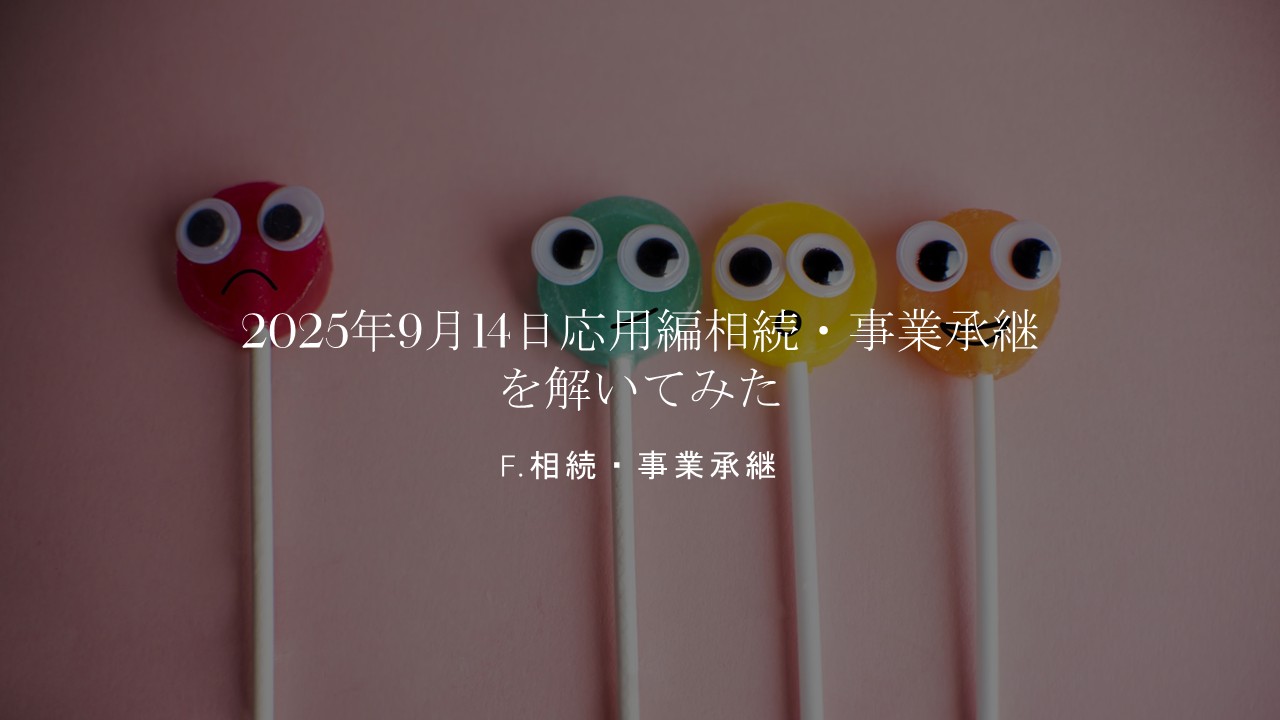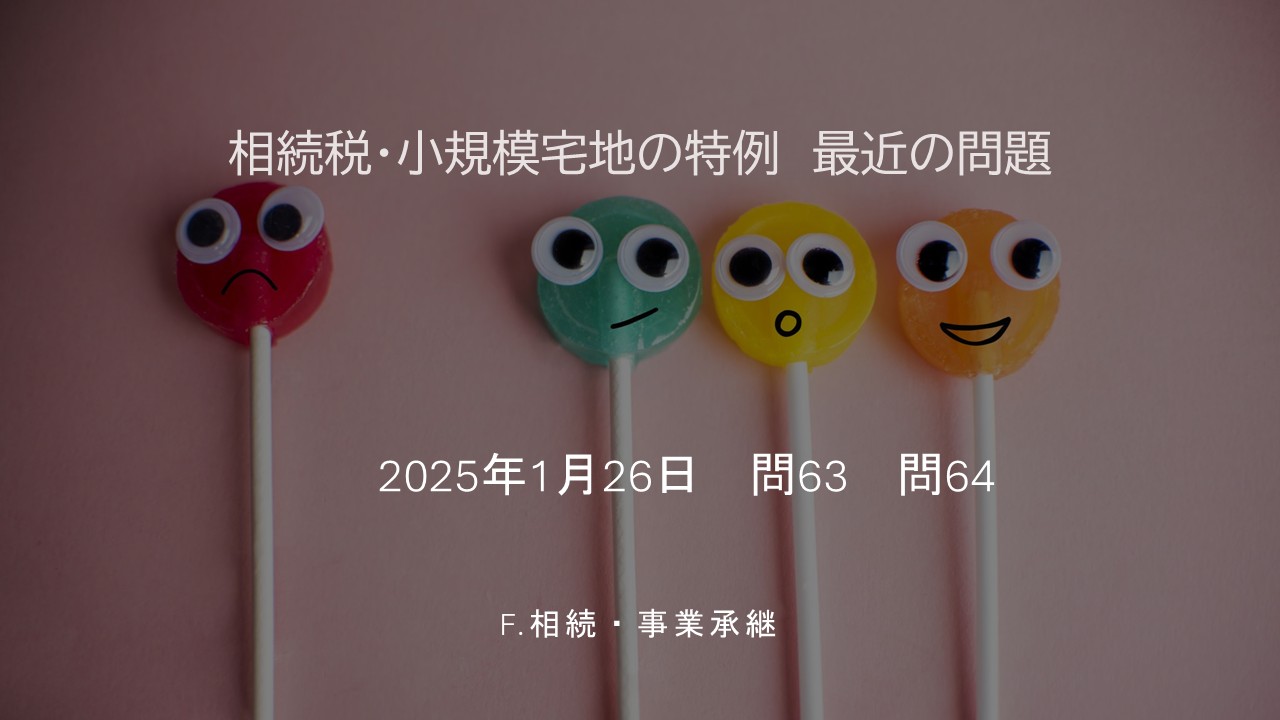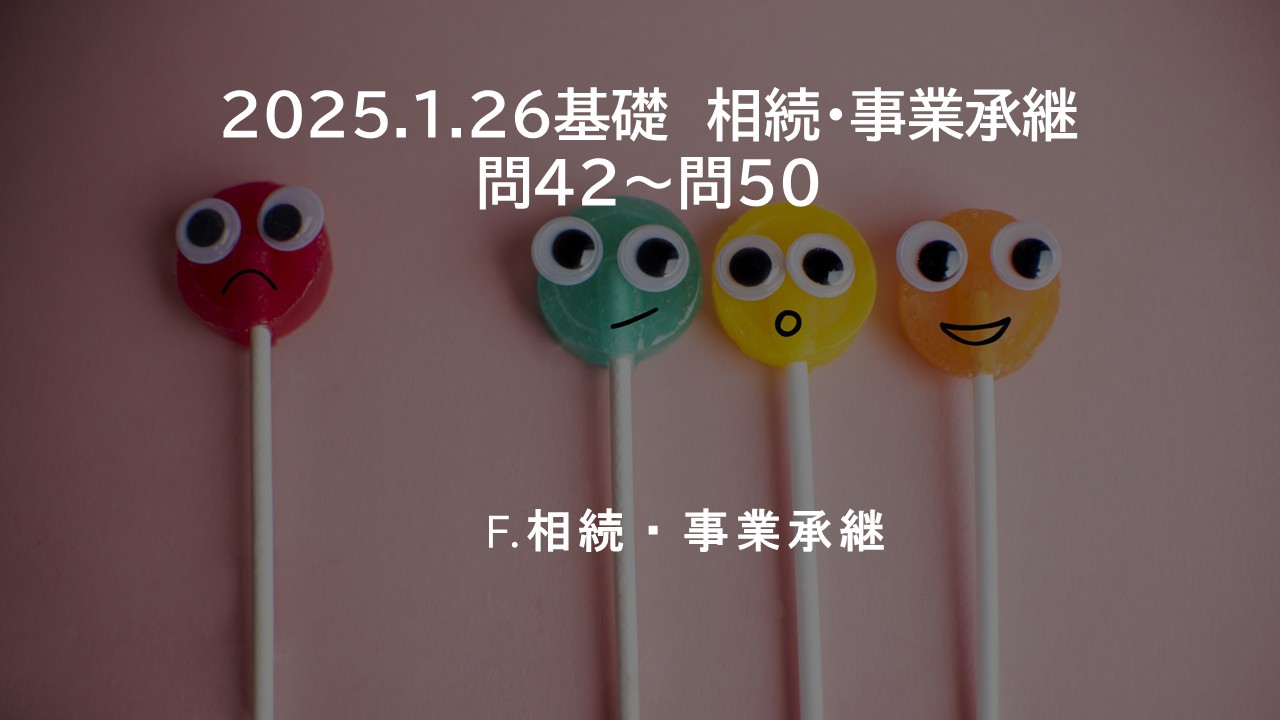取引相場のない株式の相続税評価 過去問

FP試験の相続・事業承継分野の応用編では、何しろ、類似業種批准方式、純資産方式の併用方式の計算問題が頻出です。
会社経営されている方の相続では、自社株の評価というのが問題になります。
逆に取引相場のある株式であれば、株価が日々ついていますから、それを見ながらルールにそって計算する方式があり、それに沿っていけば計算結果が求められます。
しかし、取引相場の無い株式の場合は、計算がやっかいです。
先ず、類似業種はどれに分類され、それを中分類で計算するのが良いか、小分類で計算するのが良いか判断する必要があります。
また、規模が大規模(0.7)、中規模(0.6)、小規模(0.5)によって斟酌率が変わります。FP試験ではほとんど、中規模の大か中か小ですが、まれに大規模が出題されたりもします。
これに分数の2段重ね、利益、配当、純資産をかけて株価を算定します。
応用編で、計算式は解けるけど、それを文章で説明したら、案外、難しいものです。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2024年9月8日 問48
| 財産評価基本通達上の取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 直前期末以前1年間における従業員数が70人以上の評価会社は、評価会社の総資産価額および取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。 2) 就業規則等で定められた1週間当たりの労働時間が30時間未満である従業員は、会社規模の判定上、直前期末以前1年間における従業員数に反映されない。 3) 類似業種比準価額は、類似業種の株価ならびに1株(50円)当たりの年配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)などに基づき計算する。 4) 配当還元方式において、評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合、配当還元価額の計算上、1株(50円)当たりの年配当金額は2円50銭とする。 |
正解2

応用編の問63で類似業種批准価格は散々みてるはずなんだけど、改めて文章で問われると迷うな。

1)これは正しいね。70人以上が大会社というのは意識しておく必要があるね。
2)いきなりライフプランニングの問題かという選択肢だね、30時間未満である従業員もゼロでなく、一定のルールでカウントされるよ。よってこれが不適切だね。
3)これはオーソドックスな問だね。正解だよ。
4)無配である場合、年配当金額は2円50銭で計算するのは要暗記だね。
よって不適切なのは2)だね。
2024年1月28日 問48
| 取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した土地の価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。 2) 類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。 3) 同族株主がいる会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、原則的評価方式により計算した金額によって評価することはできず、特例的評価方式である配当還元方式により計算した金額によって評価する。 4)休業中であることにより特定の評価会社に該当する会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合、配当還元方式により計算した金額によって評価する。 |
正解1

純資産価額方式とか、配当還元方式って普段意識しないもんね。当事者からしらた金額が大きく変わるから、重要な問題だろうけど。

1)これは正しいよ。3年以内に取得した土地は相続税評価額でなく、通常の取引価額で計算するよ。
2)3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、純資産価額で計算することになるね。
一般的には純資産価額だと株価が高くなるから、ゼロを防ぐため、配当を出したりするね。
3)配当還元方式か原則的評価方式のいずれか低い価格で評価するよ。
4)休業中の会社の株式を取得した場合は純資産価額方式で計算するよ。
よって正解は1だね。
2023年9月10日 問49
| 取引相場のない株式の評価方法における純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、課税時期の属する事業年度に係る法人税額や消費税額のうち、その事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額で未払いのものは負債として計上することはできない。 2) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社の株式を所有する役員が死亡し、その相続人に支給した弔慰金で、みなし相続財産とならないものは、負債として計上することはできない。 3) 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算上、評価会社が所有する課税時期前3年以内に取得した土地の相続税評価額は、原則として、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。 4) 課税時期において評価会社が有する資産の合計額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である場合、同族株主が取得した当該会社の株式は、会社の規模にかかわらず、原則として純資産価額方式により評価する。 |
正解1

よくわからない選択肢が多いね、「株式等保有特定会社」は要チェックな気がするね。

1)これが不適切だね、決算時確定しているけど、未払いというのはよくあることだもんね。
2)役員退職金などみなし相続財産となれば対象だけど、それ以外だから対象外だね。
3)これは正しいね。課税時期前3年以内に取得した土地は通常の取引価額で算定だね。
4)資産に占める株式等の割合が50%以上を占めるとと「株式等保有特定会社」なり純資産価額方式により算定されるよ。
2022年9月11日 問47
| 下記の〈X社の配当金額等のデータ〉に基づき計算したX社株式の1株当たりの配当還元価額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈X社の配当金額等のデータ〉 ・直前期の年配当金額 : 70万円 ・直前々期の年配当金額 : 50万円 ・直前期末の資本金等の額 : 1,000万円 ・直前期末の発行済株式数 : 2万株 1) 250円 2) 300円 3) 2,500円 4) 3,000円 |
正解2

わかりそうだけど、300円か3,000円って言われると迷うね。

配当還元方式は配当金を10%で還元して求めるよ。日本語が難しいけど、要は10倍するっていうことだね。
配当還元価額は2期の平均で求めるよ。
これを発行済株式数で割って求めるよ。
(70万円+50万円)÷2=60万円
60万円÷2万株=30円
30円÷10%=300円
よって2)300円
2022年9月11日 問48
| 取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 財産評価基本通達上の規模区分の定めにより、中会社に区分される会社で、課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が70%以上である評価会社は、土地保有特定会社に該当する。 2) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、株式等保有特定会社に該当する。 3) 課税時期において開業後3年未満である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合、配当還元方式により算出した価額によって評価することはできず、純資産価額方式により算出した価額によって評価しなければならない。 4) 課税時期において休業中である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が取得した場合、原則として、配当還元方式により算出した価額によって評価する。 |
正解2

特定の評価会社ってのは覚えることは限られてるようなんで、一気に覚えてしまった方がいいね。
実務では、該当しなくなるためにいろいろな方策を打つ必要があるんだろうけど。

1)土地保有特定会社は大会社では70%だけど、中会社では90%だよ。
2)株式保有特定会社は保有割合が50%以上というのは、記憶必須だね。
3)同族株主以外の株主等が取得した場合、配当還元方式による評価になるね。
4)休業中の会社は純資産価額方式だね。そもそも配当もしないだろうし。
よって正解は2)だね。