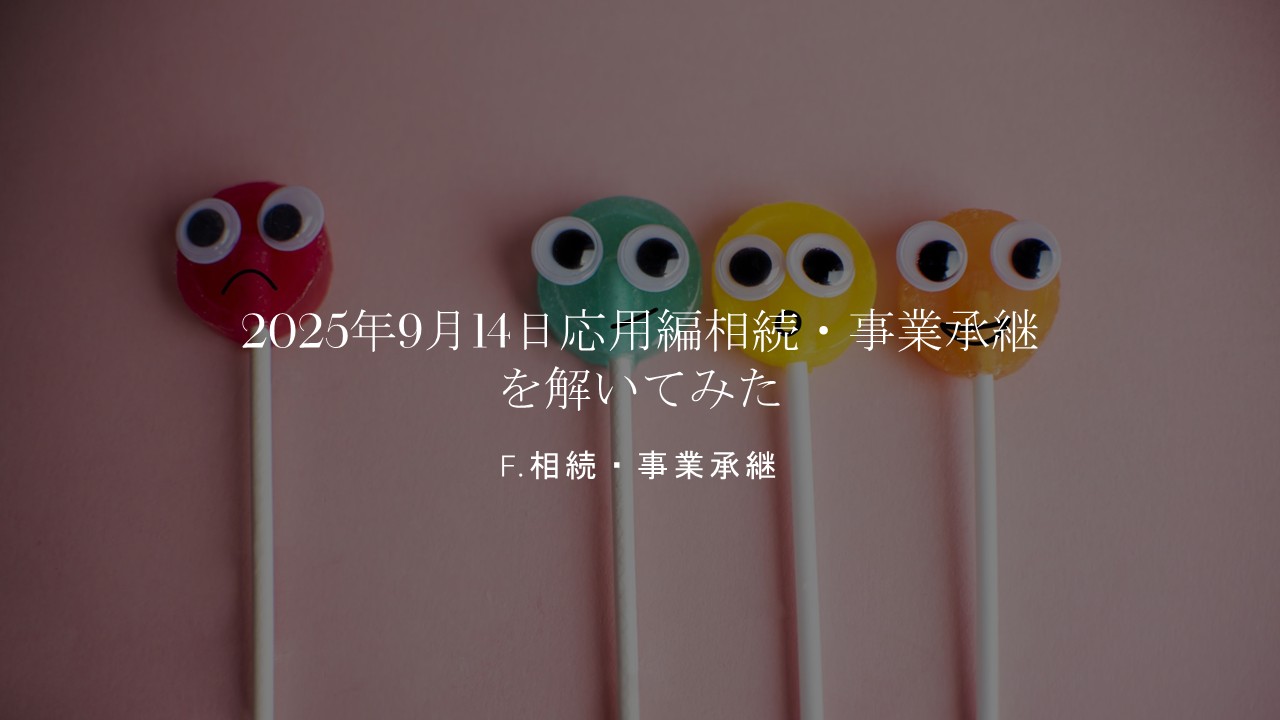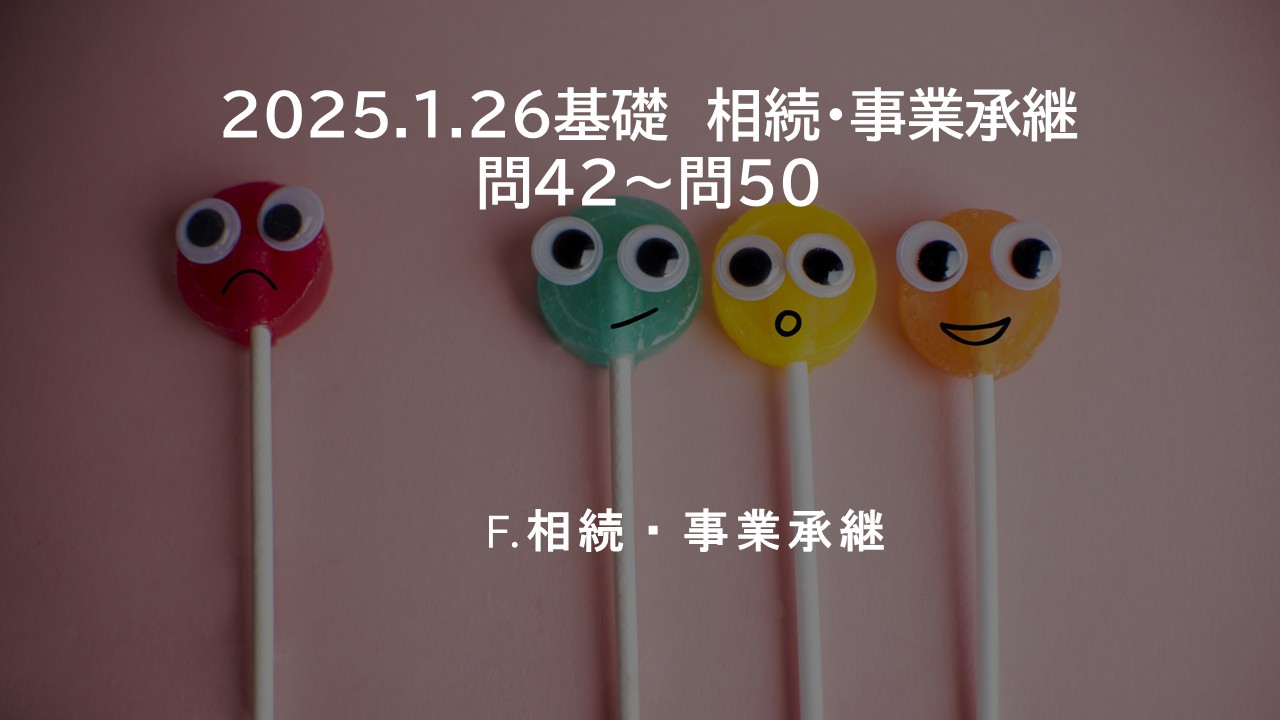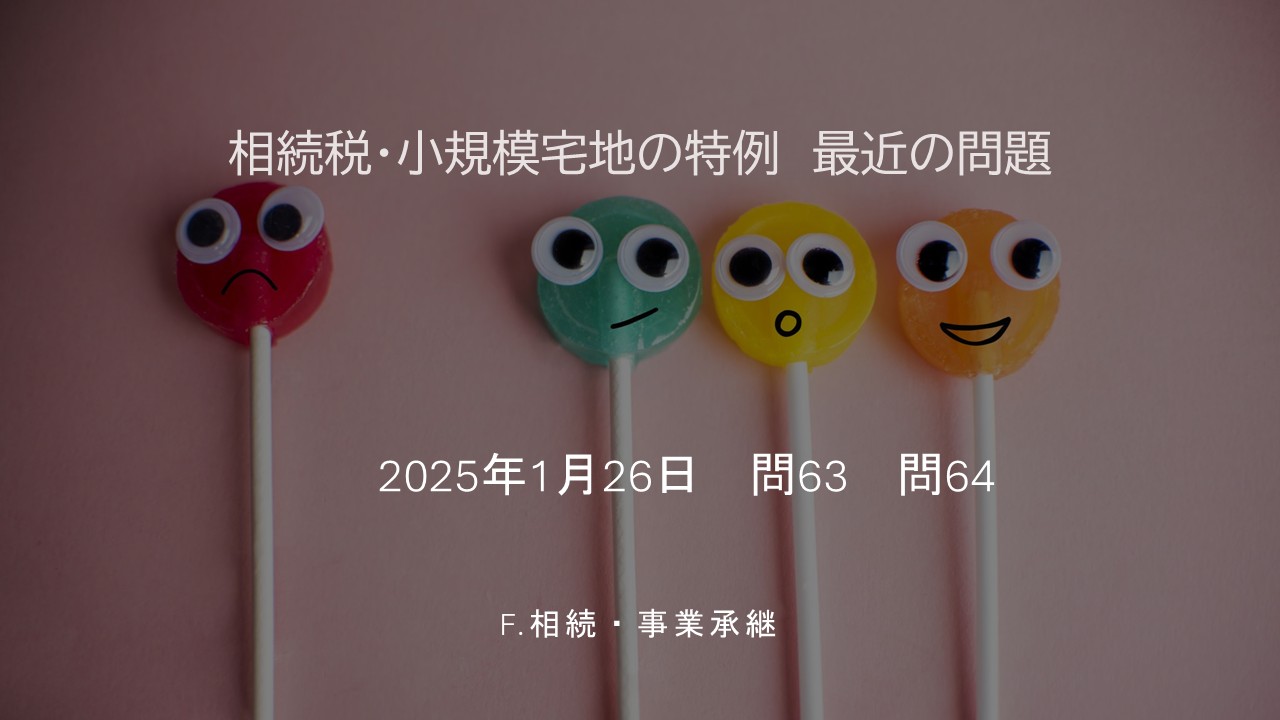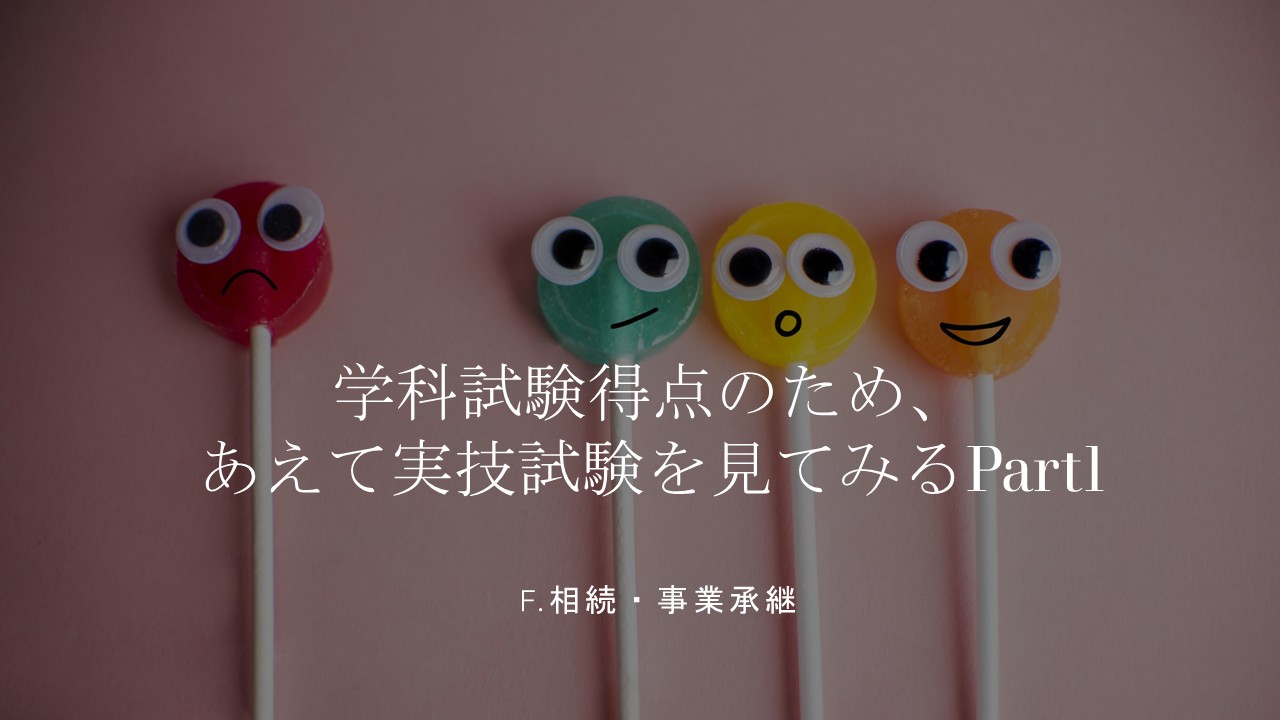相続時精算課税制度 過去問

相続時精算課税制度とは、ざっくり言うと子や孫に、2,500万円+110万円を贈与税なしで贈与できる制度です。
この110万円の暦年贈与と併用できるようになったのは2024年からで、それまでは併用することができませんでした。
この改正された部分は試験に出やすいと思われます。
この制度があることによって、親が資産を持っていても相続の際でなくても子や孫に資金をスムーズに渡すことができ、資金の循環を生むことにつながります。
とはいえ、この制度は相続時に精算するものであり、非課税となるのではないです。
相続税を計算する際には、被相続人の財産に加算する必要があることにも注意が必要です。
また、この制度を利用されるのは不動産や会社経営者の株式が多く出題されるので、そこも注意が必要です。
これまで同様、直近から過去に遡りながら、過去の問題と、私なりの説明をしていきたいと思います。
なお、問題は全て、出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>となっております。
2025年1月26日 問43
| 「相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 本特例の適用にあたっては、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物が、贈与を受けた日からその特定贈与者の相続が開始するまでの間に災害によって一定の被害を受けたことが要件とされている。 2) 本特例の適用にあたっては、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物を、贈与を受けた日から災害が発生した日まで引き続き所有していたことが要件とされている。 3) 本特例では、相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地または建物が災害によって受けた被害のうち、建物の損壊などの物理的な損失だけでなく、鉄道交通の支障に伴う土地の価格の下落などの経済的な損失も対象となる。 4) 本特例の適用を受けるためには、原則として、災害によって被害を受けた部分の価額その他の事項を記載した申請書を、災害が発生した日から3カ月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
正解2

災害などにより価値が下がってる土地、建物を贈与時の金額で算定されたら悲劇だもんね。大規模災害が多い昨今では、必要な措置かもね。

1)特定贈与者の相続税の申告期限までに被災したことが要件だね。相続開始時じゃないね。
2)相続時精算課税をした土地、建物を引き続き所有していないとだめだね。売却していたら対象外だよ。よってこれが適切だね、
3)この特例は物理的な損失を補うもので、経済的な損失は対象外だよ。これは計算、証明が難しいもんね。
4)災害が発生した日から3年を経過する日までの申告が正しいね。災害の度合いにもよるけど、3ヶ月だど厳しすぎるね。
よって適切なものは2)だね。
2024年9月8日 問43
| 相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与の年においてほかに贈与された財産はなく、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 相続時精算課税適用者が、同一年中に複数の特定贈与者からそれぞれ200万円の贈与を受けた場合、特定贈与者ごとの贈与財産に係る贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除額としてそれぞれ110万円が控除される。 2) 相続時精算課税適用者が、同一年中に特定贈与者および特定贈与者以外の者からそれぞれ200万円の贈与を受けた場合、特定贈与者から受けた贈与財産に係る贈与税の課税価格から相続時精算課税に係る基礎控除額として110万円が控除され、特定贈与者以外の者から受けた贈与財産に係る贈与税の課税価格から暦年課税に係る基礎控除額は控除されない。 3) 相続時精算課税適用者が特定贈与者から現金の贈与を受けた場合、その金額が相続時精算課税に係る基礎控除額以下であっても、当該贈与について贈与税の申告書を提出しなければならない。 4) 養親から相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた養子が、当該養親との養子縁組解消後に養親であった者からの贈与により取得した財産については、引き続き相続時精算課税制度が適用される。 |
正解4

以前は、相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れないと記憶していたけど、基礎控除額が登場したので、ちょっとややこしくなったね。

1)受贈者の暦年課税は年110万円なので、複数から贈与を受けても110万円しか基礎控除額にはならないよ。
2)基礎控除額110万円は、暦年贈与110万円とは別なので、それぞれが控除することができるよ。
3)基礎控除額110万円が創設されたことによって、110万円以下の贈与であれば申告の必要はないよ。
4)養子縁組が解消されても相続時精算課税は継続するよ。これはよくある問題だね。
よって正解は4)だね。
2023年5月28日 問44
| 相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。 2) 相続時精算課税の特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、当該特定贈与者は相続時精算課税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利または義務を承継しない。 3) 受贈者が贈与者から贈与を受けた後、同一年中において受贈者が贈与者の養子となり相続時精算課税の適用を受ける場合、養子となる前の贈与者からの贈与財産は相続時精算課税の適用を受けることができる。 4) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡し、相続時精算課税適用者がその相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要はない。 |
正解2

どの分野でもそうだけど、相続も問題文が長くて、意味を勘違いしないように注意が必要だね。肯定しているのか、否定しているのか逆にとらえると解答が反転するもんね。

1)養子縁組が解消されても相続時精算課税は継続するよ。これは暗記必須だね。
2)問題文の意味を追いかけるだけで大変だけど、これが正解だね。親より先に子が亡くなった場合は、無かったことにされるということだね。
3)この制度の要件に贈与時点で「直系卑属である推定相続人」とあるので、養子になる前は対象外だね。
4)受贈者が相続しなかったとしても、贈与者の財産を基に相続税は計算されるから、これは不適切だね。相続時精算課税の金額は相続財産に加えるということを覚えていれば、推定できるかもね。
よって正解は2)だね。