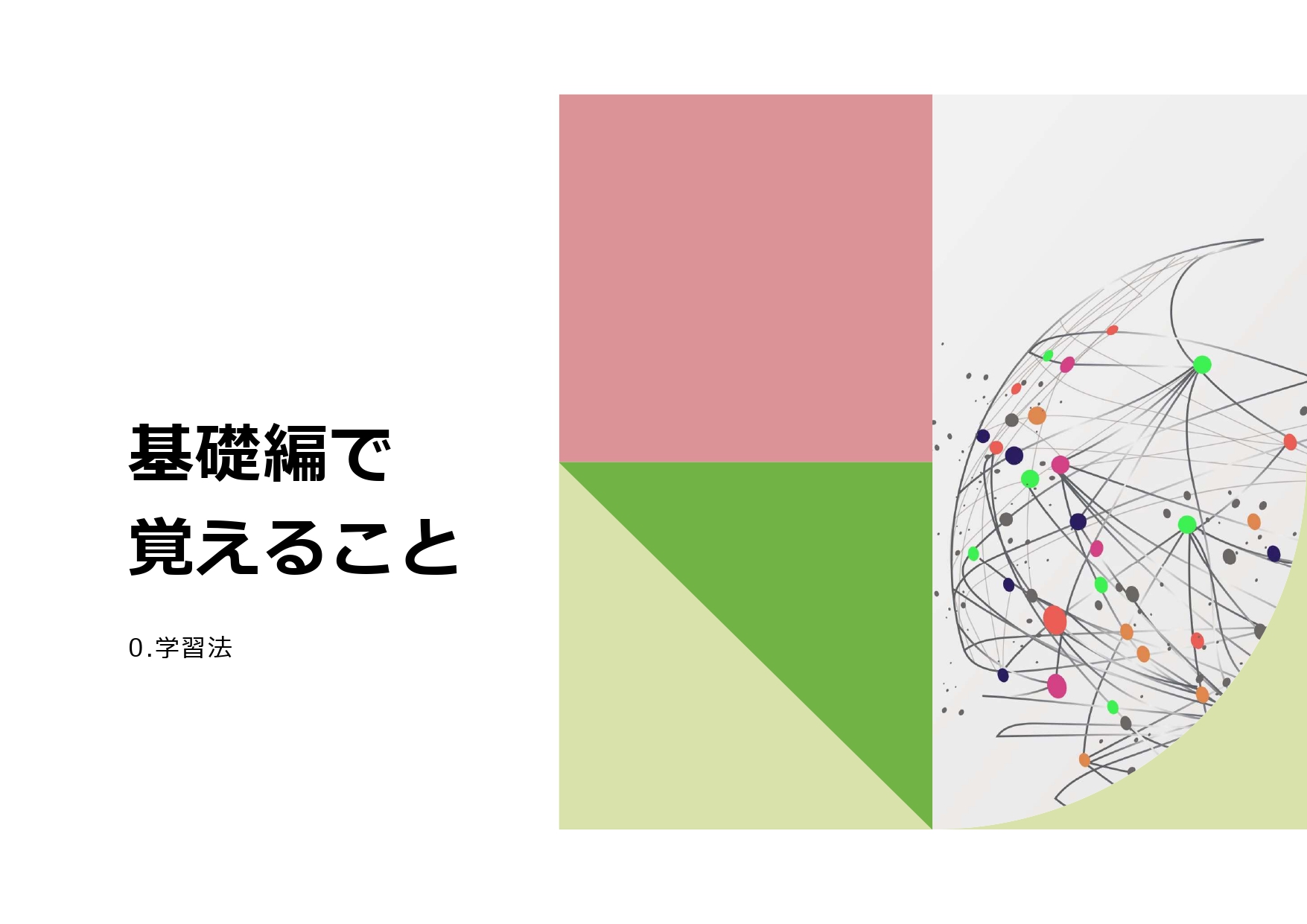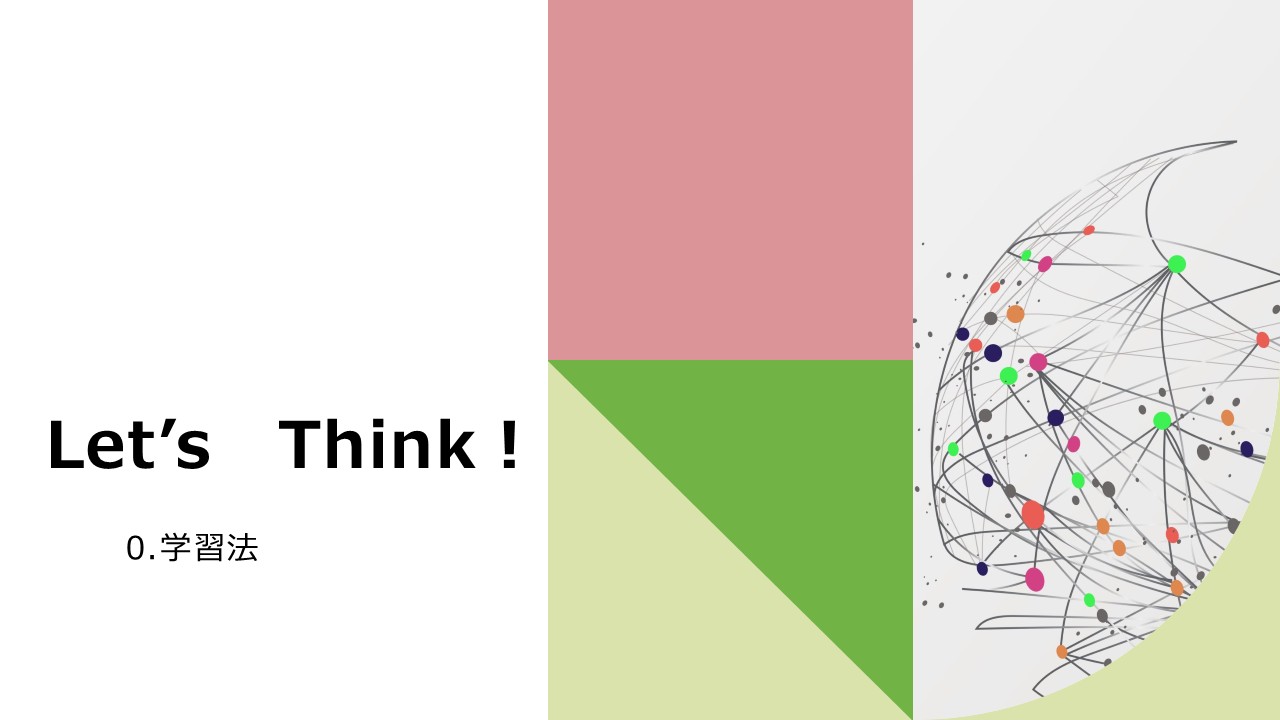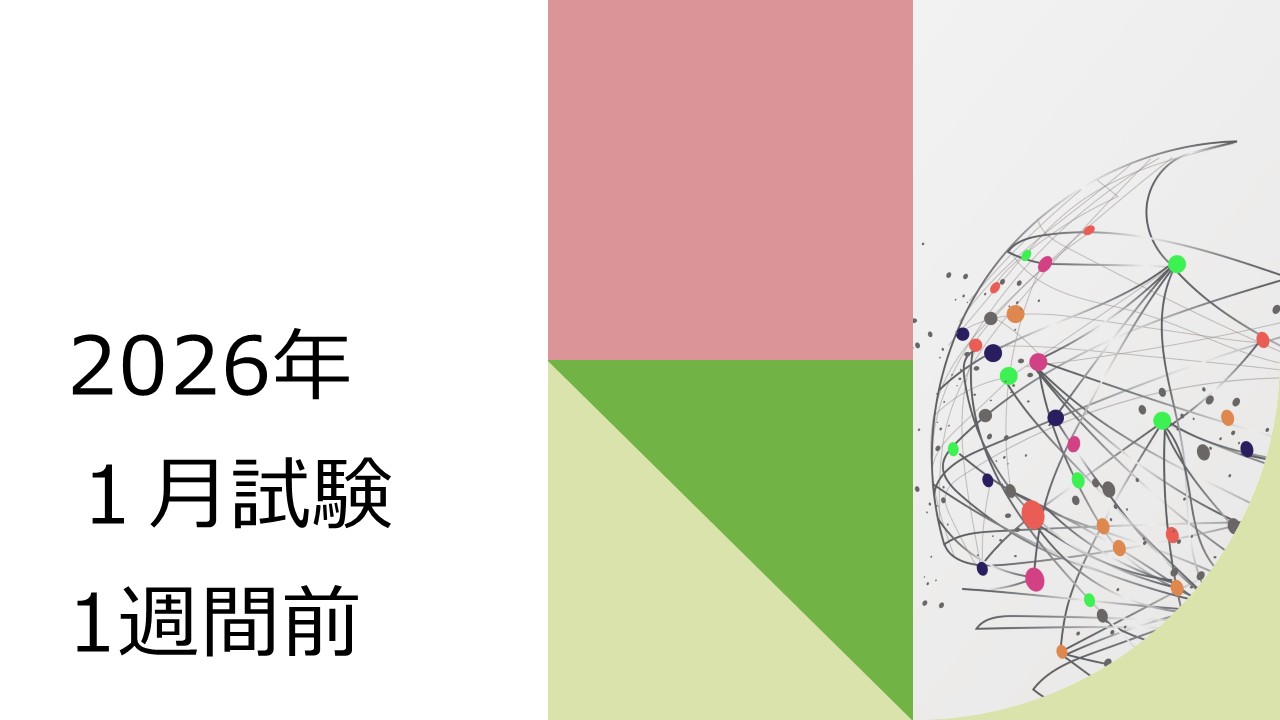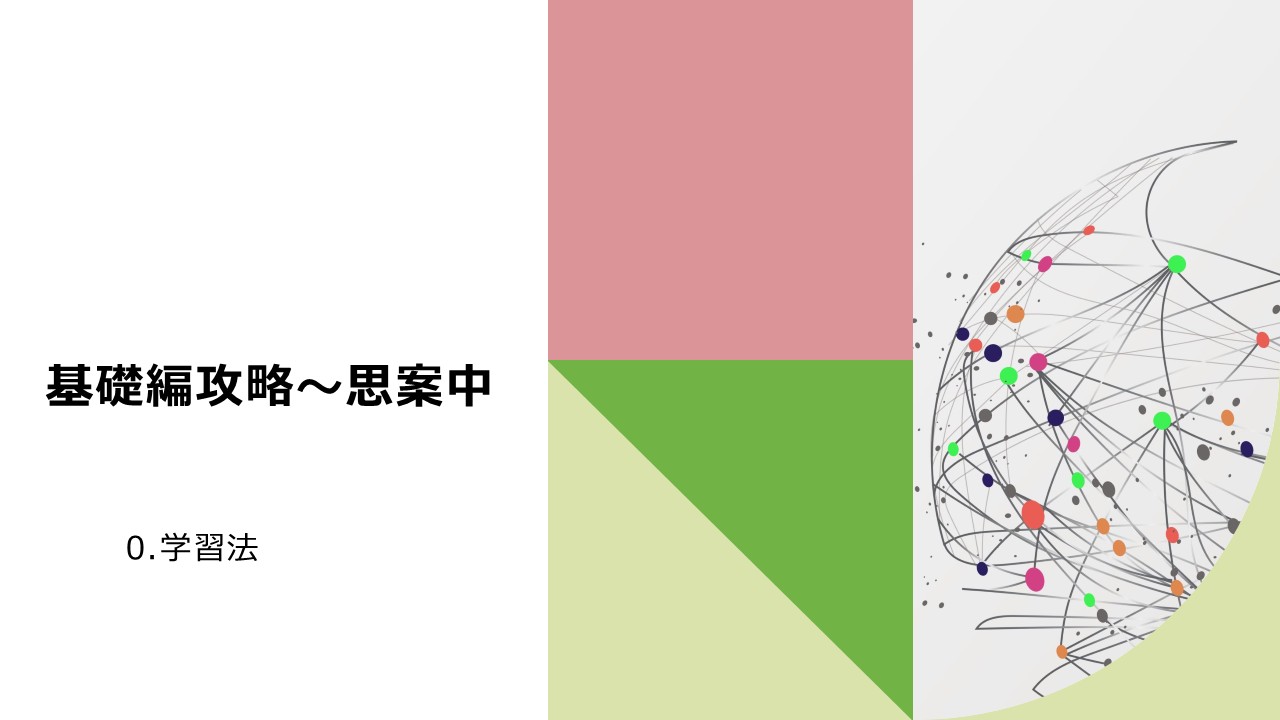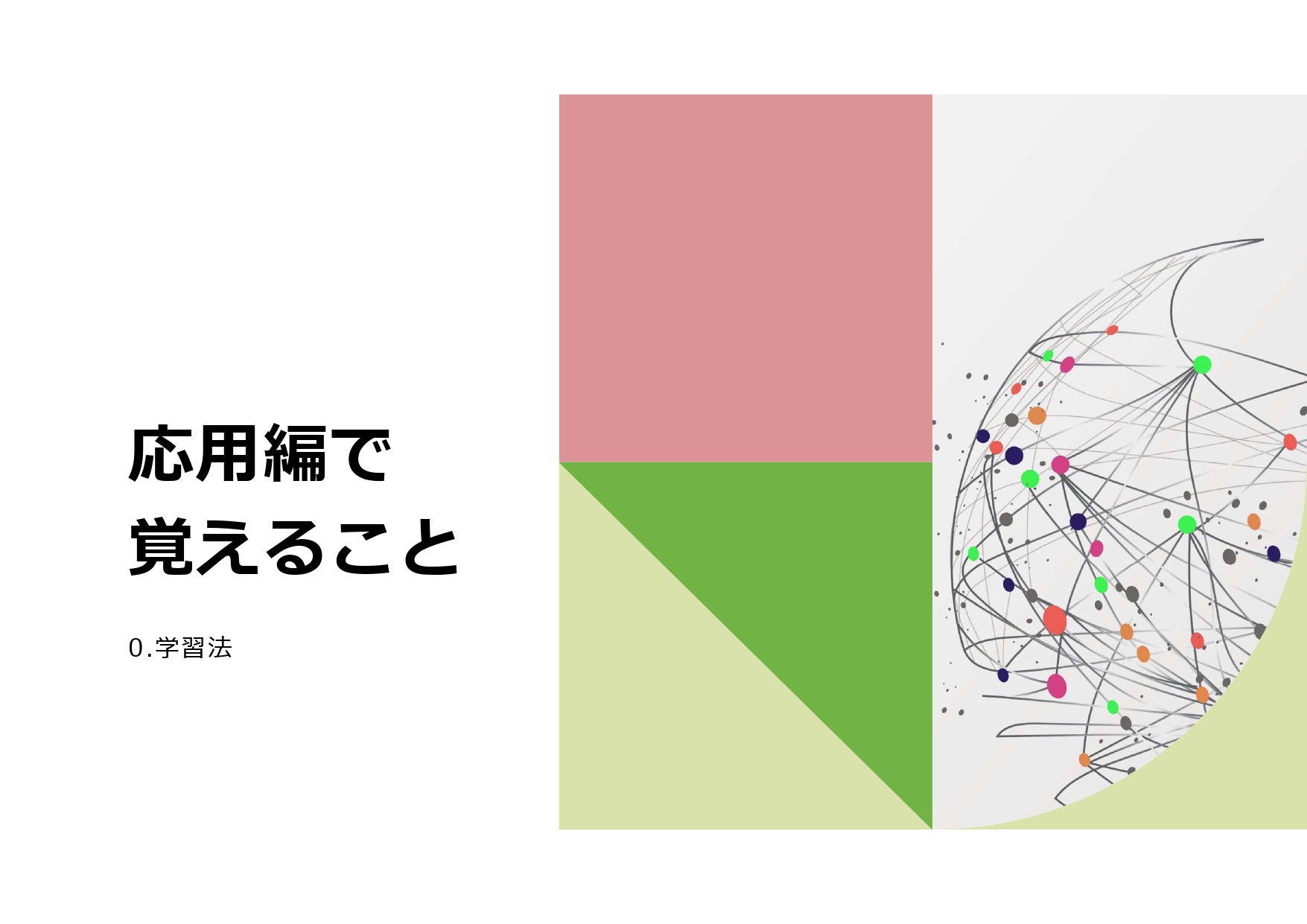試験科目及びその範囲 範囲の細目
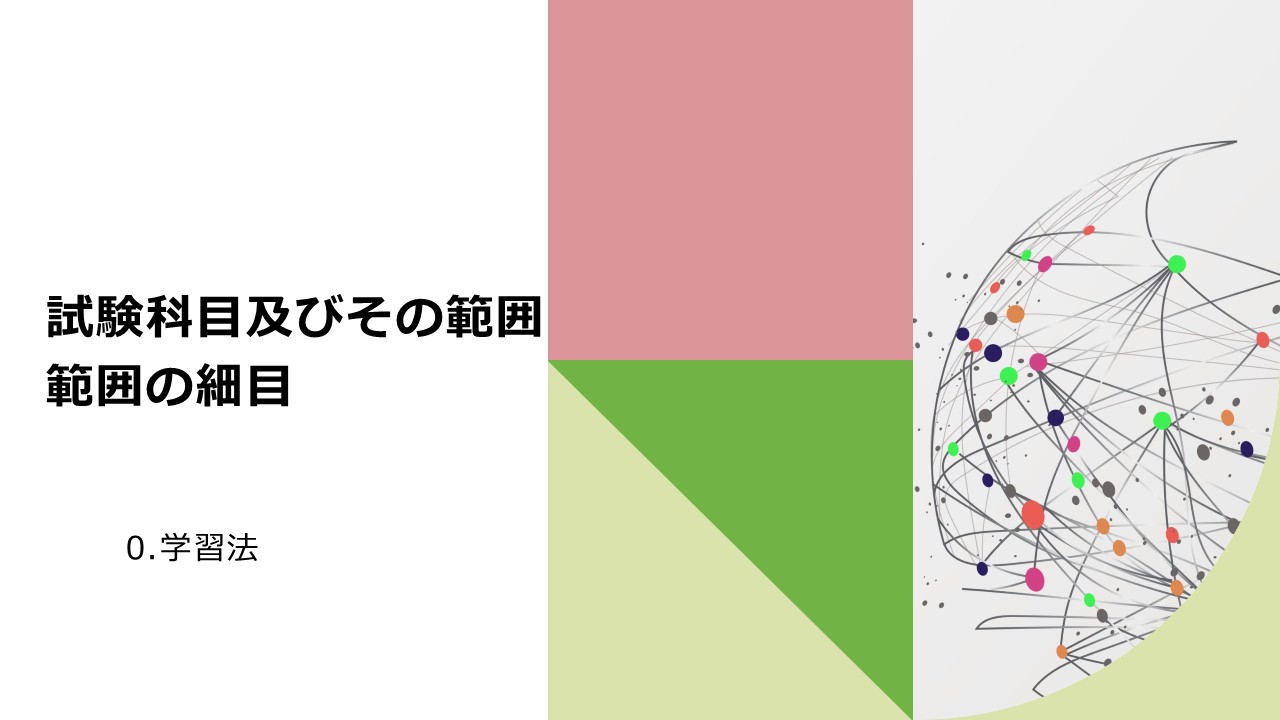
ブログを読んでいただいている方は、このタイトルを見て、当然知っているという方がほとんどだと思いますが、私がFP1級受験の勉強を始めた頃、恥ずかしながら、この存在を知りませんでした。
FP1級試験は、範囲が広く全体像をつかむのが困難な試験です。何か全体像をつかむ良い方法が無いかと予備校のテキストなど何冊も目を通したのですが、なかなか要領を得ませんでした。
そんな時、一般社団法人金融財政事情研究会(以下、きんざいと記す)のHPを見ていたところ、タイトルのPDFファイルを見つけました。
この資料を見つけた時に、これが試験の全体像で、これに記載してある項目を全て説明できるようになることが、FP技能士に求められていることなんだと確信(思い込み)ました。
私は、当初1級の部分だけに目を通しましたが。実は2級、3級の記事からも読み取れることがあると思ったので、9月試験終了後の記事では、1級、2級、3級に求められる能力について、私なりの見解を述べていきたいと思います。
それだけでなく、各項目の概略くらいは第三者に説明できるようになっておくことが求められると思ってください。
誰でも得意分野もあれば不得意分野もあります。個人的な感想ですが、きんざいで実技試験を受験することを考えておられる方は、
E.不動産とF.相続・事業承継は完璧に抑えておくことをお勧めします、
学科試験は、なんとなく理解できていれば解ける問題もありますが、面接で言葉で説明するということになったら、あいまいな理解が命取りになります。
ちなみに私は日本FP協会の実技試験も受験しました。FP協会の受験を考えておられる方はライフプランニングの6つの係数と、生命保険証書の読み取りが必須です。
金融・タックスプランニングは過去問をこなすことは当然ですが、新しいトピックスが出題されることもあるため、新聞、ニュースは注意をして見るようにすることをお勧めします。
逆に不動産、相続・事業承継は学科試験の知識でなんとか対応できると思います。
FP協会試験の大きな特徴は、あるテーマについて300字前後で説明するという問題も出題されます。
これは文章を書く習慣を身に着け、300字を体感できるトレーニングが有効だと思います。
結局は不合格となりましたが、受験のために勉強したことをこれからの受験生に参考にしていただくために、機会を見て、対策の記事を書きたいと思っています。
ここまで、2週間ほど応用編の過去問紹介を中心に記事を書いてきましたが、ちょっとブレークを挟み、ここから基礎編の過去問について紹介していきたいと思います。
どんな記事が有効かは、いまだに迷っていますが、私ならこういう勉強をするという方法も含めて9月受験生の参考になる記事にしたいと思います。