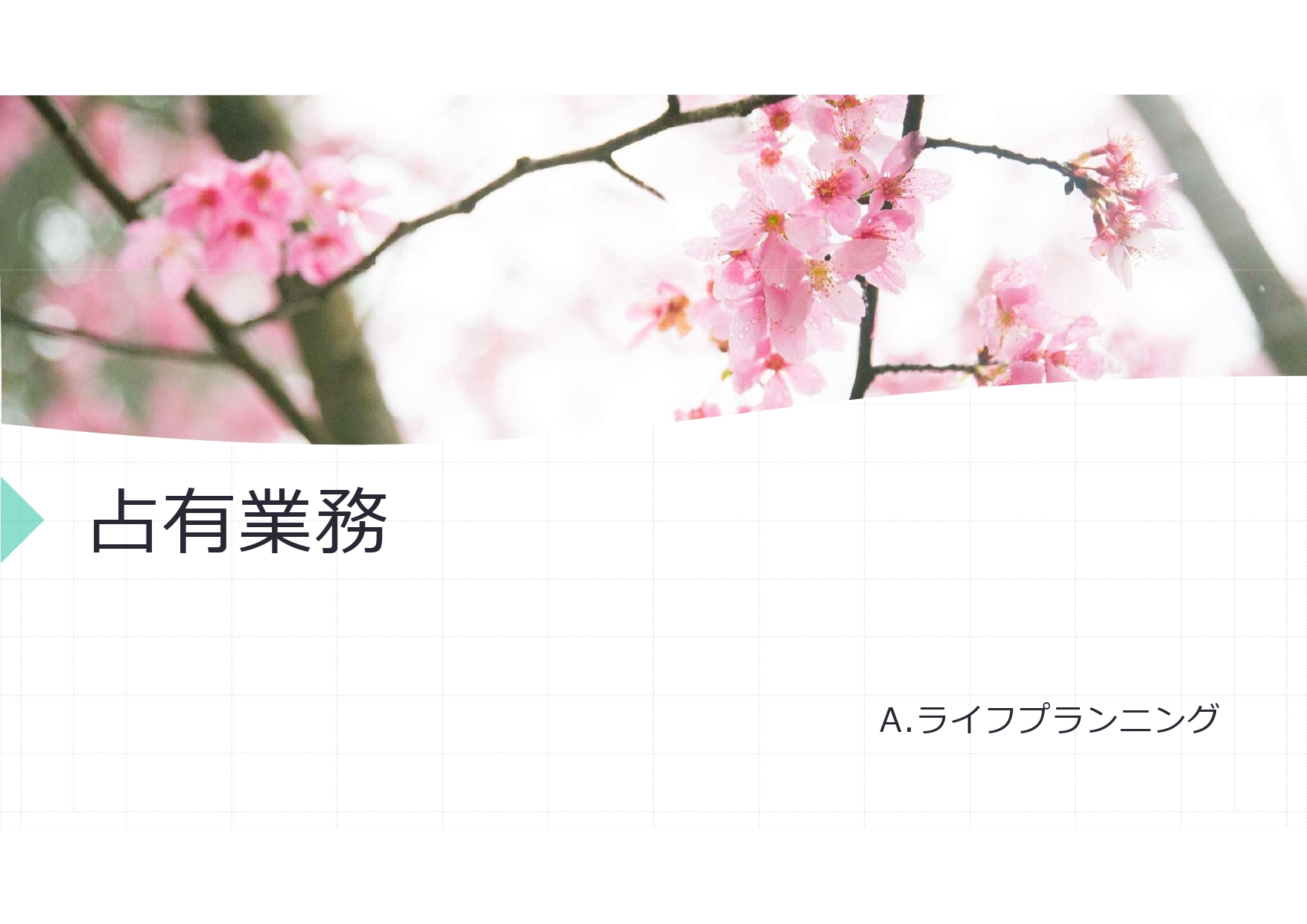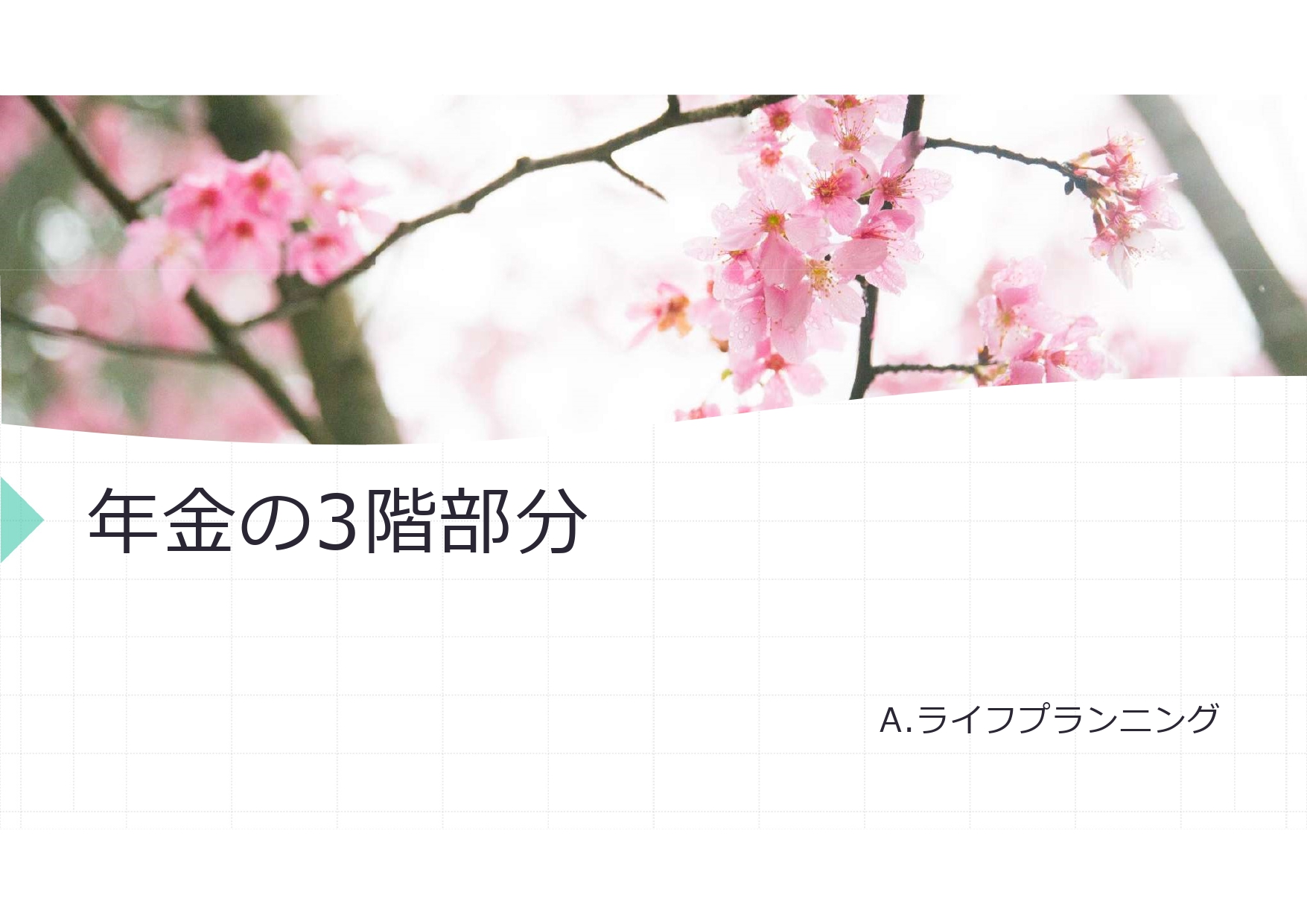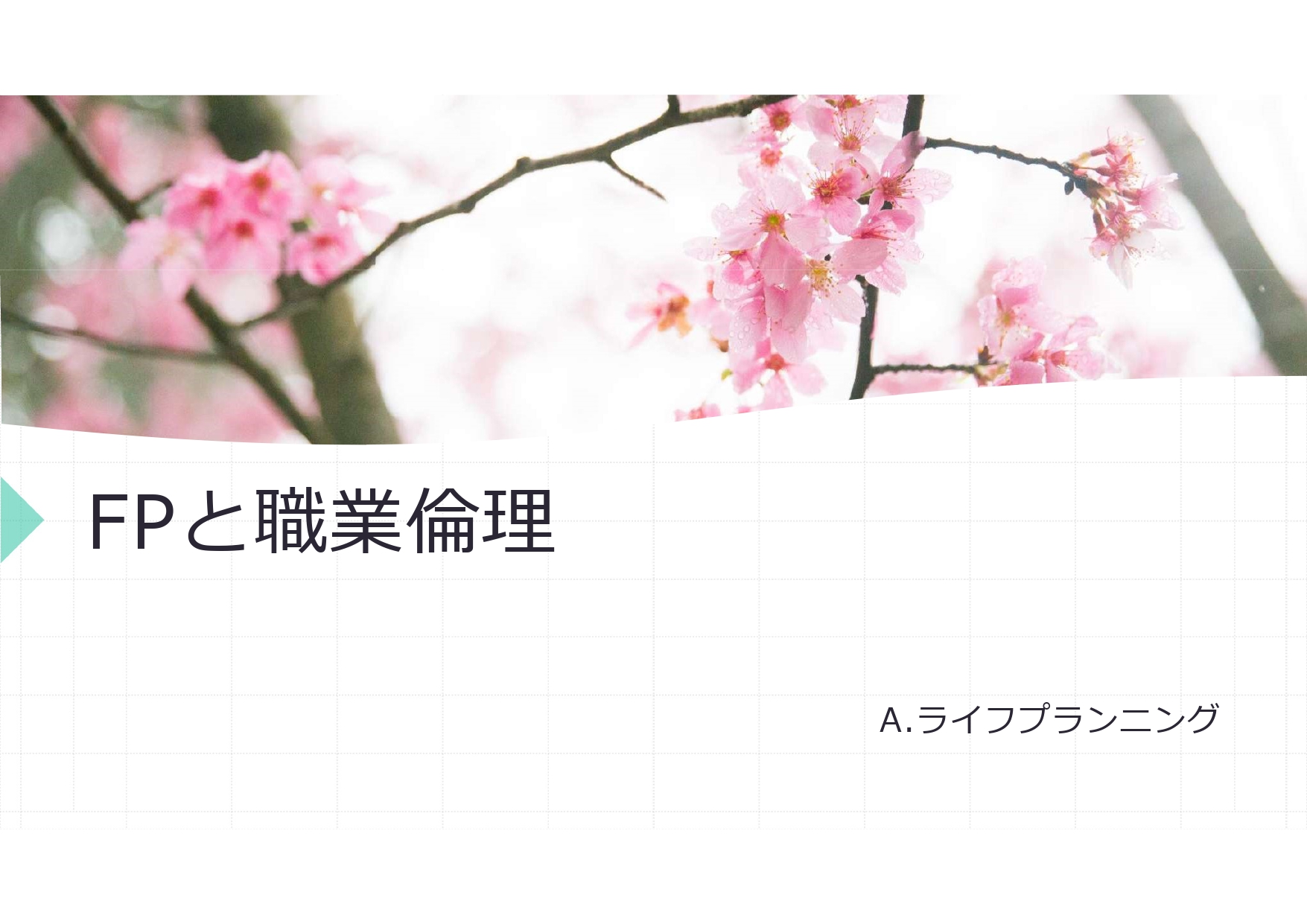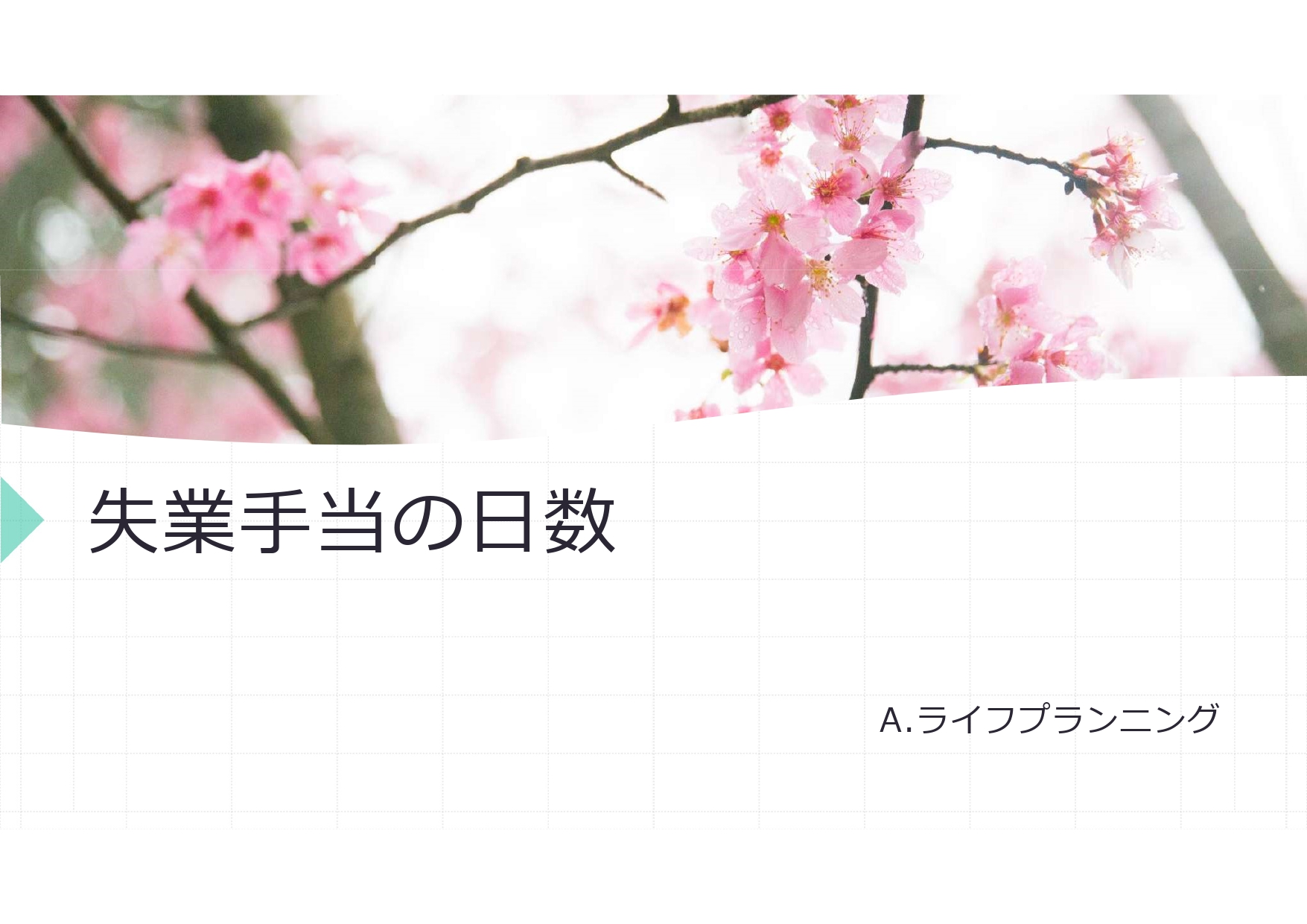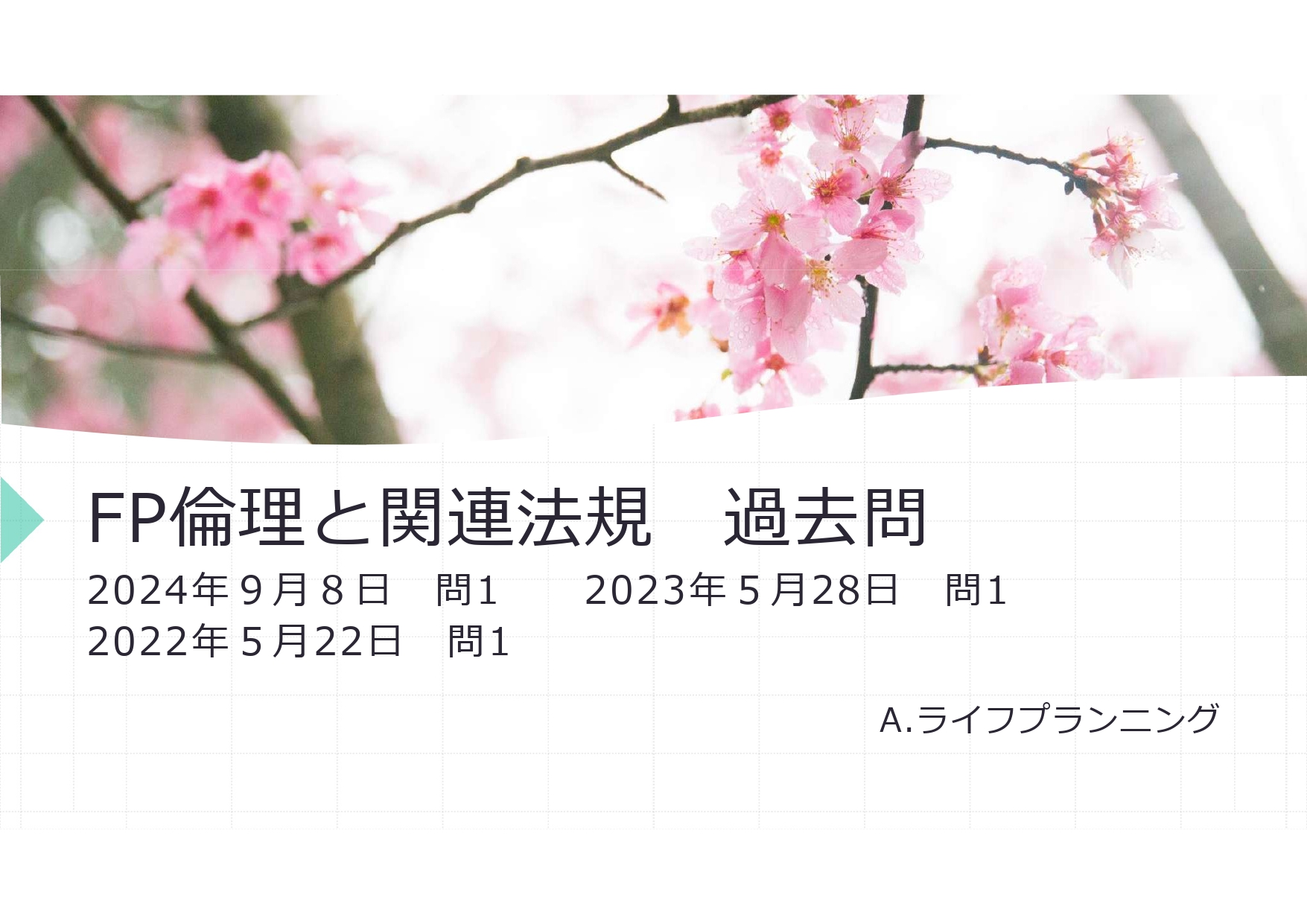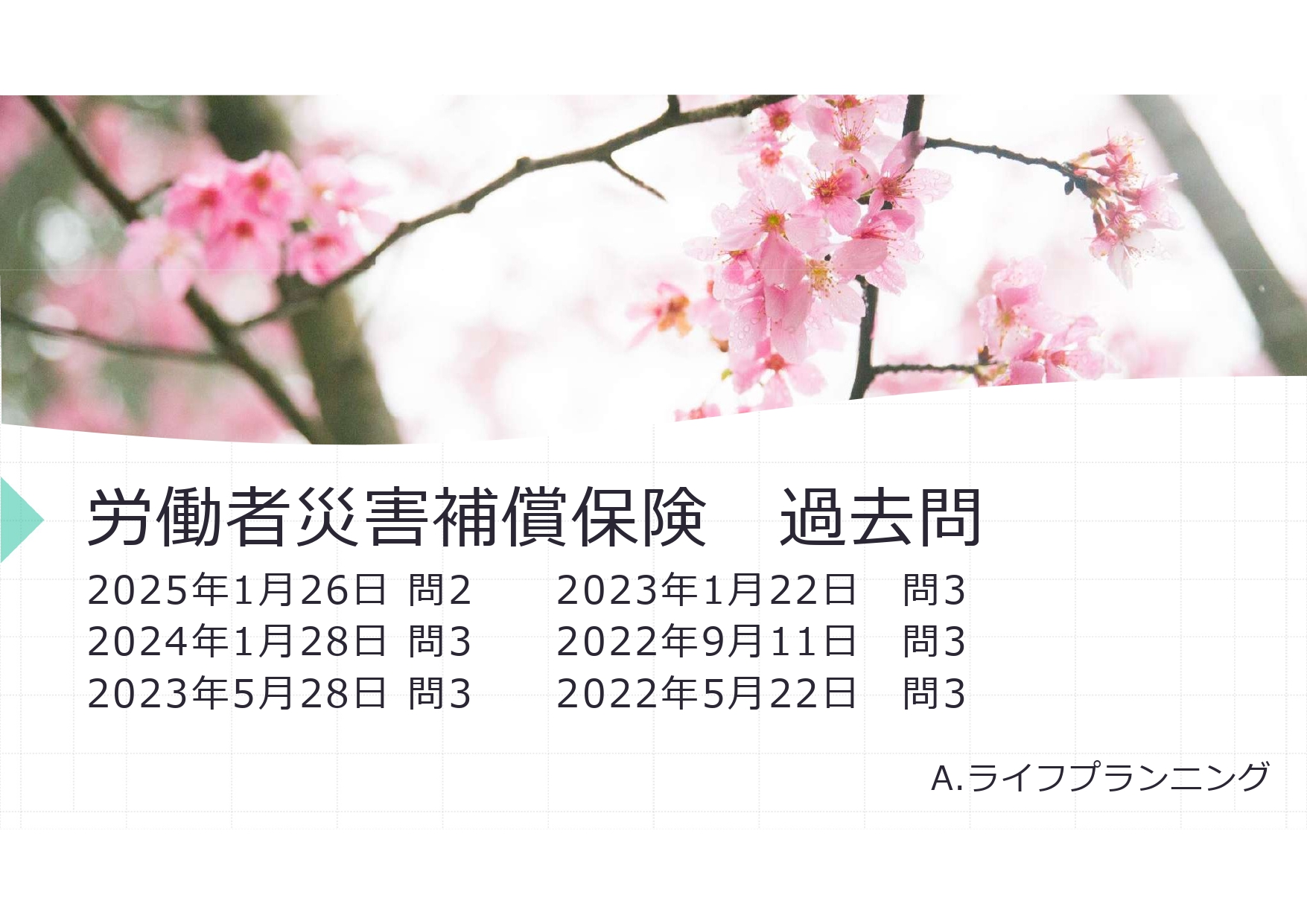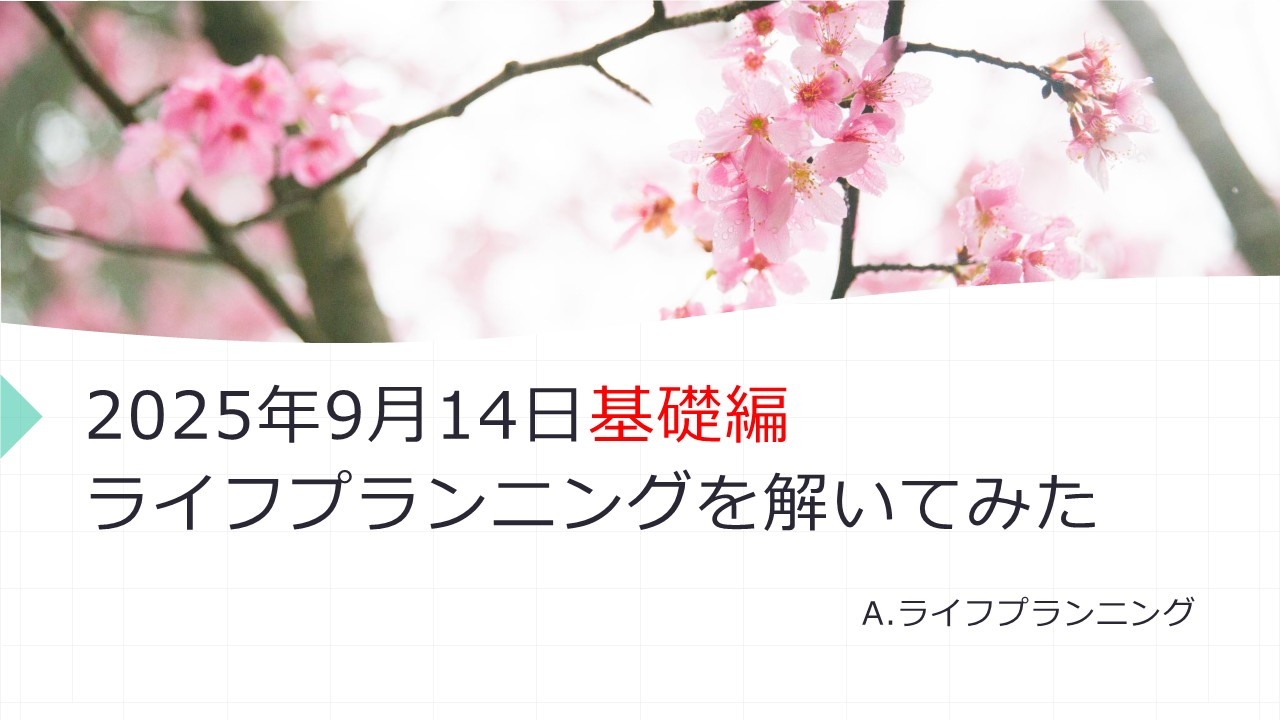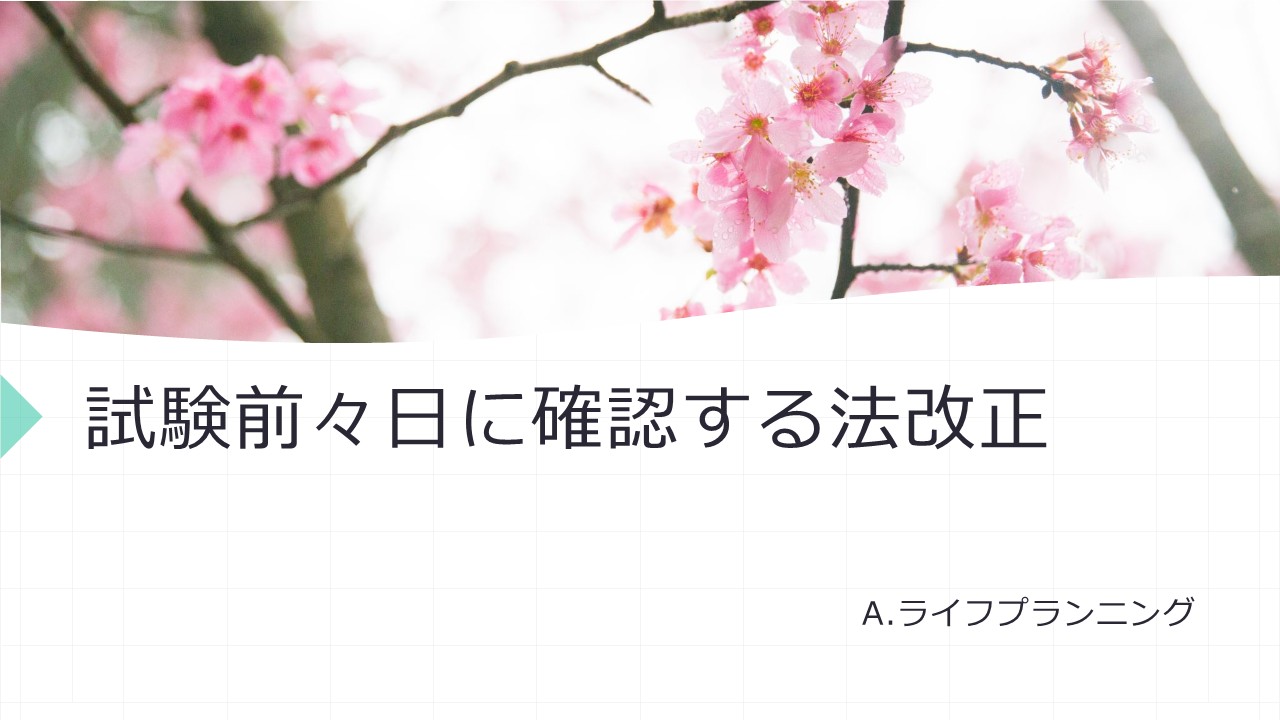2025年5月25日 基礎編 ライフプランニング
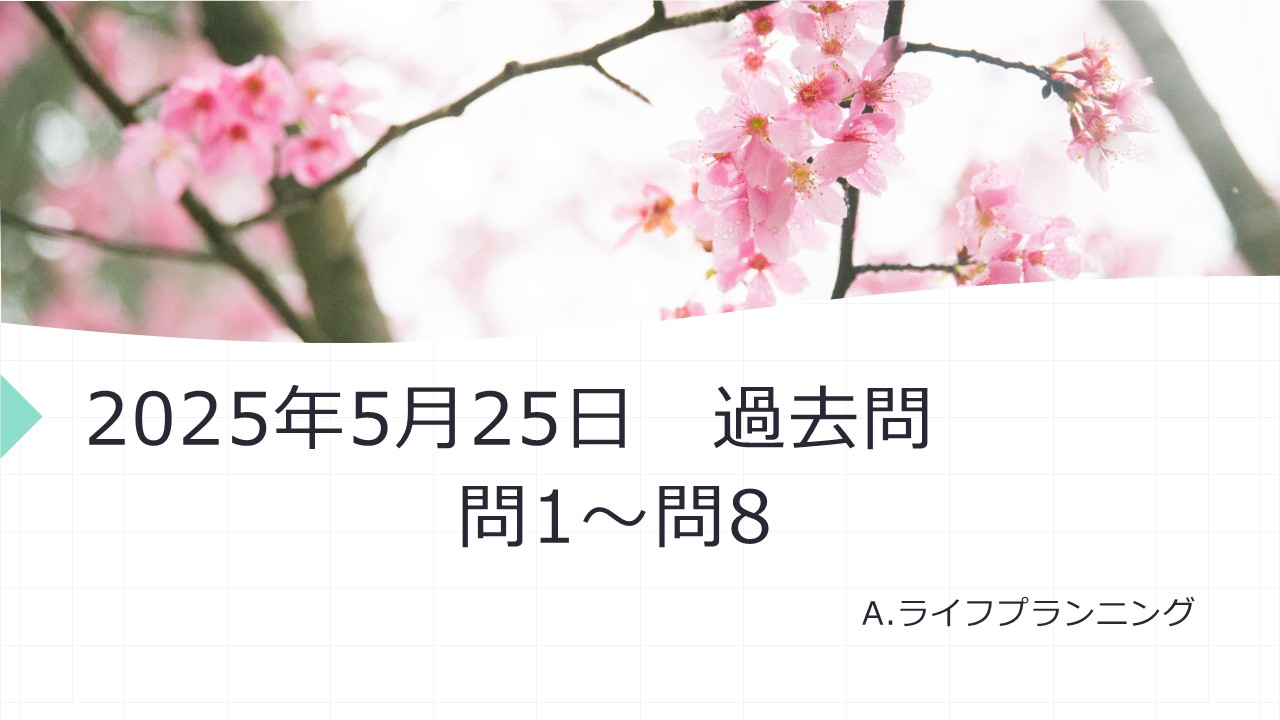
基礎編攻略について1週間考え続けましたが、よい結論が出ず、初心に戻ってつるさんかめさんのスタイルで過去問の解説を試みることにしました。
今日から20日間、5月試験、1月試験とさかのぼりながら解説を試みます。
9月試験終了後も、次の1月試験受験のため、2024年9月、5月、1月とさかのぼり解説を試みます。
なかには、上手く解説できない問題もあるかもしれませんがご容赦ください。
出所:一般社団法人 金融財政事情研究会
問1 6つの係数
《問1》 会社員のAさん(60歳)は、手元資金15,000千円のうち、8,000千円を15年間にわたって毎年均等に取り崩し、残りの7,000千円についてはそのまま5年間運用し、その後、10年間にわたって毎年均等に取り崩すことを考えている。この場合、65歳から75歳までの10年間の毎年の取崩額として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、取崩期間および5年間の運用期間中の運用利回り(複利)は年3%とし、取崩しは年1回行うものとする。また、下記の係数表を利用して算出し、計算結果は千円未満を切り捨て、手数料や税金等は考慮しないものとする。
〈年3%の各種係数〉
| 終価係数 | 現価係数 | 年金終価係数 | 減債基金係数 | 年金現価係数 | 資本回収係数 | |||||||
| 5年 | 1.1593 | 0.8626 | 5.3091 | 0.1884 | 4.5797 | 0.2184 | ||||||
| 10年 | 1.3439 | 0.7441 | 11.4639 | 0.0872 | 8.5302 | 0.1172 | ||||||
| 15年 | 1.5580 | 0.6419 | 18.5989 | 0.0538 | 11.9379 | 0.0838 | ||||||
1) 1,138千円
2) 1,217千円
3) 1,495千円
4) 1,621千円
正解4

定番の6つの係数の問題だね。
この問題は問題文を正確に読み取る能力が求められるね。
60歳現在で15,000千円の現金を持っていて、65歳から75歳からの10年間いくら受け取れるかという問題だね。
しかし、この計算8,000千円と7,000千円に分けて運用方法を変えるというのがちょっと問題を複雑にしてるね。

ちょっと問題文を整理すると
①8,000千円を15年かけて取り崩す
②7,000千円を5年間運用して、
③その後10年かけて取り崩す
①(資本回収係数15年を使用)8,000千円×0.0838=670.4千円
②(終価係数5年間を使用)7,000千円×1.1593=8,115.1千円
‘③(資本回収係数10年を使用)8,115.1千円×0.1172=951.08千円
‘(①+③)670.4千円+951.08千円≒1,621
問2 全国健康保険協会管掌健康保険
| 《問2》 全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 任意継続被保険者となった者は、当該被保険者に係る保険料の全額を負担することとなるが、任意継続被保険者の被扶養者に係る保険料の負担は生じない。 2) 出産手当金の支給期間中に退職した場合、任意継続被保険者の資格を取得しなければ、引き続き出産手当金の支給を受けることはできない。 3) 任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日以後に生じた傷病による傷病手当金の支給を受けることができない。 4) 任意継続被保険者は、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出ることにより、任意継続被保険者の資格を喪失することができる。 |
正解2

1)任意継続被保険者って失業した際に、勤めていた会社の保険を継続するか、国民健康保険に加入するか選択するんだったよね。被扶養者の保険料は払うんだっけ?
2)これはわからないね・・・
3)任意継続期間中の傷病手当か・・
4)任意継続被保険者は2年間はやめれなかったんじゃなかったっけ?

1)任意継続は家族を扶養に入れたままで可能だよ。国保では別に扶養者が国保に加入しなければいけなくなるので、大きく違う点だね。
2)出産手当金の支給期間中に退職というのはよくあることだと思うね。たいていはハローワークなどで案内してくれると思うけど、退職日が出産手当金支給対象期間に入っていない場合には支給対象にならないこともあるから、慎重に考えて退職日を決める必要があるね。
この選択肢が間違っているね。
3)任意継続期間中は傷病手当金は受けられないので注意が必要だよ。
4)任意継続被保険者って以前は途中でやめれなかったんだよね。令和4年から途中でやめれるようになったんだよね。
長くFP試験を受けている方は逆に間違えるかもね。
問3 介護保険
| 《問3》 公的介護保険(以下、「介護保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 要介護認定および要支援認定は、その申請のあった日に遡ってその効力を生ずる。 2) 要介護認定の有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれ、要介護更新認定の申請をする場合は、原則として、有効期間の満了日の120日前から満了日までの間に申請しなければならない。 3) 介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けた場合、自己負担割合は、当該被保険者の所得金額に応じて、1割、2割または3割となる。 4) 要介護認定または要支援認定に関する処分に不服がある者が介護保険審査会に対して行う審査請求は、原則として、その処分があったことを知った日の翌日から6カ月以内にしなければならない。 |
正解1

1)要介護認定および要支援認定は認定がおりたときから有効じゃないの?
2)日数、金額など選択肢に数字がある時は要注意だね。
3)介護保険の第2号被保険者って40歳~64歳で特定疾病を持っている人のことだよね。この説明は1号被保険者じゃないかな。 4)審査請求って介護度がおかしいって思ったときに保険者に行うものだよね。

1)これが正しい選択肢だよ。急な介護を要する場合、審査結果を待たずにサービス利用しなければいけない場面って考えられるもんね。
2)介護保険の要介護認定の更新手続は目安として60日前から可能だよ。
3)介護保険の第2号被保険者の自己負担割合は1割だね。1号被保険者みたいに所得で2割、3割となることはないよ。
4)この6か月以内というのが誤りで3か月以内だね。
問4 国民年金の保険料免除等
| 《問4》 国民年金の保険料免除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 国民年金の第1号被保険者が出産する場合、当該被保険者の国民年金の保険料は、原則として、出産予定月の前月から6カ月分の保険料の納付が免除される。 2) 国民年金の第1号被保険者が国民年金の保険料の全額免除を受けた期間に係る保険料について追納する場合、追納すべき額は、追納する時期にかかわらず、免除を受けた当時の保険料の額となる。 3) 国民年金の第1号被保険者が障害基礎年金の受給権者となったことにより国民年金の保険料が全額免除となった期間について、既に保険料を納付していた場合、当該保険料の還付を受けることができる。 4) 国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生の扶養義務者の前年所得が一定額以下でなければならない。 |
正解3

1)これも月数だから怪しいね。
2)追納をする場合に利息もかからないなら、もっと追納する人が増えそうなもんだけどね。
3)これも難しいね、障害基礎年金って1級、2級でないと受け取れないし、
4)学生納付特例制度を利用するのに親の所得が関係あるの?

1)国民年金の出産の免除は出産日が属する月の前月から4か月間だね。多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間だから注意が必要だね。
出産手当金の支給期間産前42日、産後56日には年金が免除されると覚えておくのもいいかもね。
2)免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるよ。
3)これが正しい選択肢です。これは知らない知識だったね。
4)学生納付特例制度を利用する場合に親の所得は関係ないね。建前として、あくまで本人が納付するものだしね。
問5 老齢給付の繰上げ支給および繰下げ支給
| 《問5》 公的年金の老齢給付の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も 適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) Aさん(1961年6月10日生まれ・男性)が、64歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、老齢基礎年金および老齢厚生年金の減額率は、いずれも4.8%となる。 2) Bさん(1963年6月20日生まれ・女性)が、62歳0カ月で老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をする場合、老齢基礎年金および老齢厚生年金の減額率は、いずれも14.4%となる。 3) 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権者であるCさん(1958年1月18日生まれ・男性)が、67歳6カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をする場合、同時に老齢厚生年金についても繰下げ支給の申出をしなければならない。 4) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得したDさん(1954年1月15日生まれ・女性)が、71歳6カ月で老齢基礎年金の請求手続をし、遡及して年金を受け取ることを選択した場合、66歳6カ月で繰下げ支給の申出があったものとみなした増額率により増額された年金額の5年分を一括して受け取ることができる。 |
正解4

1)年金の繰上げ、繰下げ問題はややこしいね。
2)1963年生まれで、36か月繰上げだから0.4%×36月=14.4%で合ってない?
3)これはわかる!繰下げは同時でなくてもできるんだよね。
4)71歳で繰下げの場合どうなるんだ?そもそも75歳まで繰下げできるようになったというのはニュースで見たけど。

1)生年月日がミソだね。1962年生まれ以降は減額0.4%×月数だけど、1961年以前は0.5%×月数になるんだね。よって誤り
2)1963年生まれの女性の場合、特別支給の老齢厚生年金が支給されるから、微妙に変わるんだよね。これが男性だったら設問どおりだね。
3)そうだね、これは切れる選択肢だね。
4)解答を見ると、これが正しい選択肢なんだね。確かに言っていることは正しいと思うけど、年金には5年の時効があったと思うんだけど。ちょっと理解があいまいなので再度、勉強します。
問6 厚生年金保険における離婚時の年金分割
| 《問6》 厚生年金保険における離婚時の年金分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「離婚等をした場合における特例」による標準報酬の改定を合意分割といい、「被扶養配偶者である期間についての特例」による標準報酬の改定を3号分割という。 1) 合意分割では、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。 2) 3号分割では、その請求をした日において離婚の相手方が障害厚生年金の受給権者であるときは、障害厚生年金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は分割の対象とならない。 3) 離婚時の年金分割において分割の対象となる厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)は、3号分割では婚姻期間中のものに限られるが、合意分割では婚姻期間外のものについても対象となる。 4) 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、分割を受けた者が老齢厚生年金の支給を受けるために必要となる受給資格期間に算入される。 |
正解2

1)離婚しちゃった場合、確かに扶養に入ってた側は何も受け取れなくなって老後の生活に困りそうだもんね。
2)3号分割で障害厚生年金を受けてた場合ってレアケースにも対応しないといけないんだね。
3)これは対象とならないんじゃないかな、離婚した人が再婚をして次の配偶者ができることだってあるだろうし。
4)これは全然、見当がつかないや。

1)按分割合の合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てることによって分割割合を決めてもらうという方法があるよ。
2)実際には障害年金を受ける状態になって生活を維持できなくなって離婚というのはあり得るケースだよ、この設問が正しいんだね。
3)分割の対象となるのは婚姻期間のみだね。
4)分割された被保険者期間に係る標準報酬は厚生年金額算定の基礎とするが、年金受給資格期間等には算入しない。というのがの正しいんじゃないかな。
離婚時の年金については弱いので、もっと勉強が必要かもね。
問7 国民年金基金
| 《問7》 国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 老齢年金は、原則として、年金額が24万円未満であるときは年に1回支給され、年金額が24万円以上であるときは年に6回支給される。 2) 国民年金基金の加入員が、4月から翌年3月までの1年分の掛金を前納した場合、0.5カ月分の掛金が割引される。 3) 国民年金基金の加入員が、国民年金の保険料の産前産後免除、法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予のいずれかの事由に該当し、当該保険料の全額または一部について納付することを要しないものとされた場合、加入員の資格を喪失する。 4) 国民年金基金に加入する場合、1口目は、15年間の保証期間が設定されている終身年金A型と保証期間が設定されていない終身年金B型のいずれかを選択する必要があり、1口目に加入した型は変更することができず、減口することもできない。 |
正解4

1)国民年金基金って自営業者の年金の3階部分のイメージだけど、実際にはよく知らないな。
2)前納の割引率とか頭に入っていないな。
3)原則として国民年金を払っていないと国民年金基金はかけれないよね。
4)これも正しいかどうか判断に苦しむね。FP試験を受けるからにはHPに目を通しておくことが有効かもね。

1)年金が12万円以上だと年6回偶数月に受け取れるというのが正しい記載だね。24万円じゃないね。
2)1年分を前納した場合、0.1月分の割引が受けられるよ。
3)例外として障害基礎年金を受けて法定免除になった場合も申し出れば継続できると思うよ。
4)これが正しいんだね。文章最後の1口目に加入した型は変更することができず、減口することもできない。というのは怪しいけど、覚えてないといけないね。
問8 住宅金融支援機構のフラット35およびリ・バース60
| 《問8》 住宅金融支援機構のフラット35およびリ・バース60に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) フラット35の融資対象となる住宅には、床面積について所定の要件が定められているが、敷地面積に係る要件は定められていない。 2) フラット35は、住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であっても、第三者に賃貸する目的で取得する投資用物件の建設・購入資金には利用することができない。 3) リ・バース60の資金使途には、住宅の建設・購入資金やリフォーム資金、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金、生活資金などがある。 4) リ・バース60の変動金利タイプの商品を利用する場合、融資対象となる住宅等に対して、取扱金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権が設定される。 |
正解3

1)床面積は一戸建て70㎡、マンション30㎡というのは覚えているけど敷地面積は知らないな。
2)賃貸マンションオーナーでもフラット35を使いたいという人はいるような気がするけど
3)リ・バース60も広告は見たことあるけど、中身は理解できていないな。
4)リ・バース60の融資を検討する際には、子や孫との相談が大切だね。

1)これは正しいよ、不動産取得税240㎡までや固定資産税280㎡までの減額措置と混在しないよう注意が必要だね。
2)フラット35はあくまで自宅として使用することが目的だから賃貸用は対象外だね。
3)リ・バース60の資金使途に生活資金は含まれないよ。よってこれが間違い。
4)これは正しいね。リバース・モーゲージとして実技試験でも出題される論点だね。