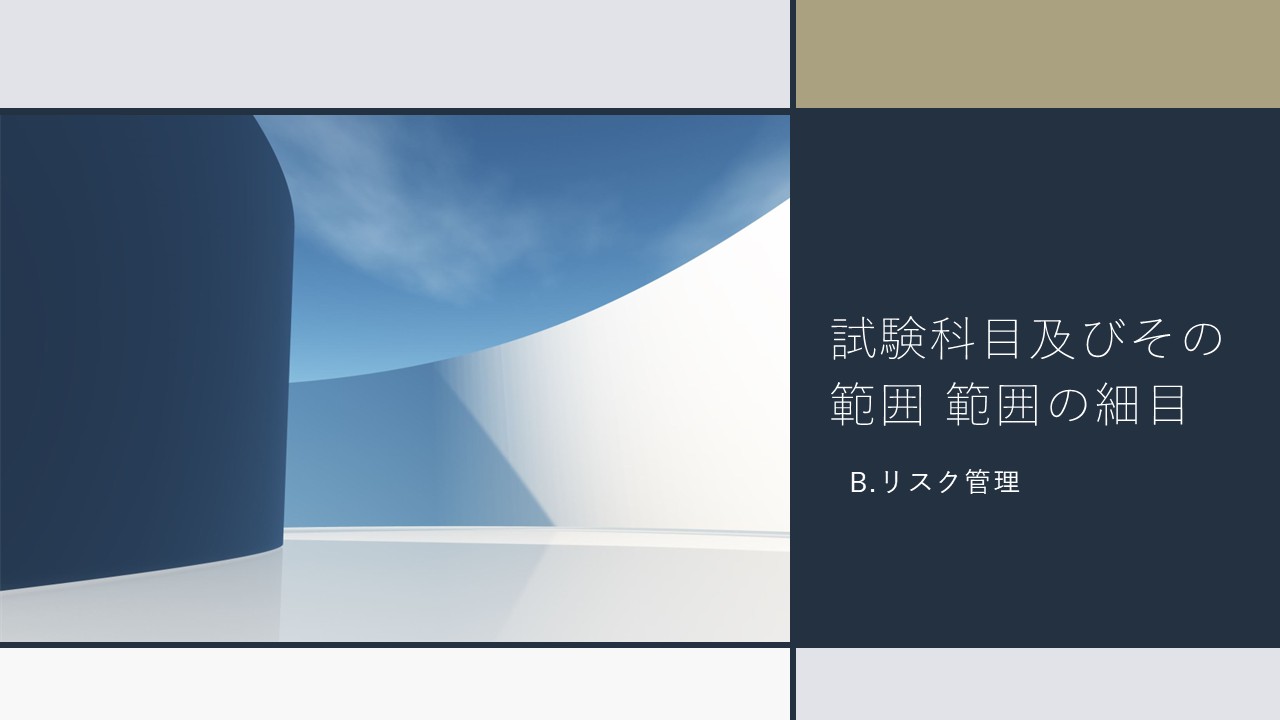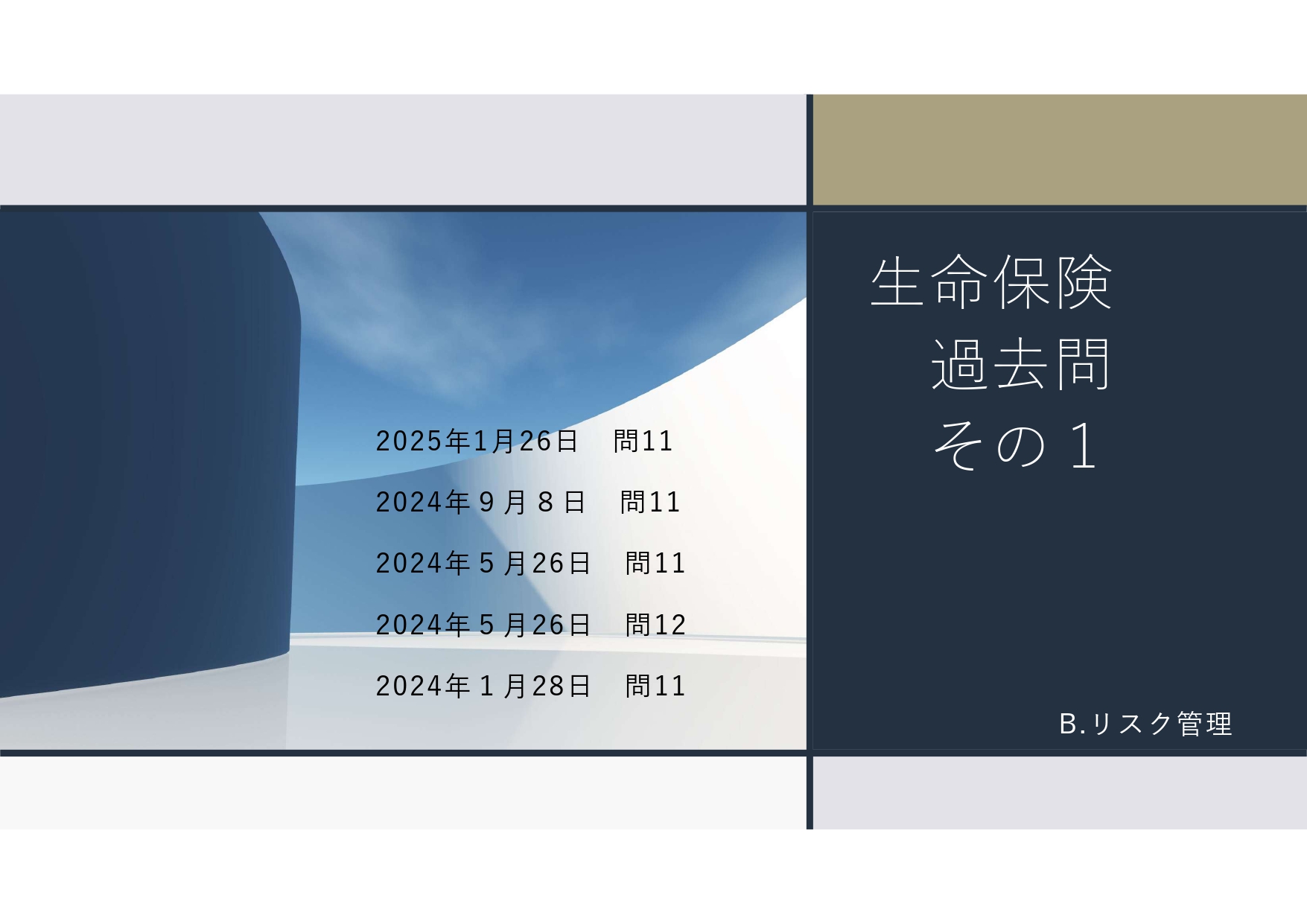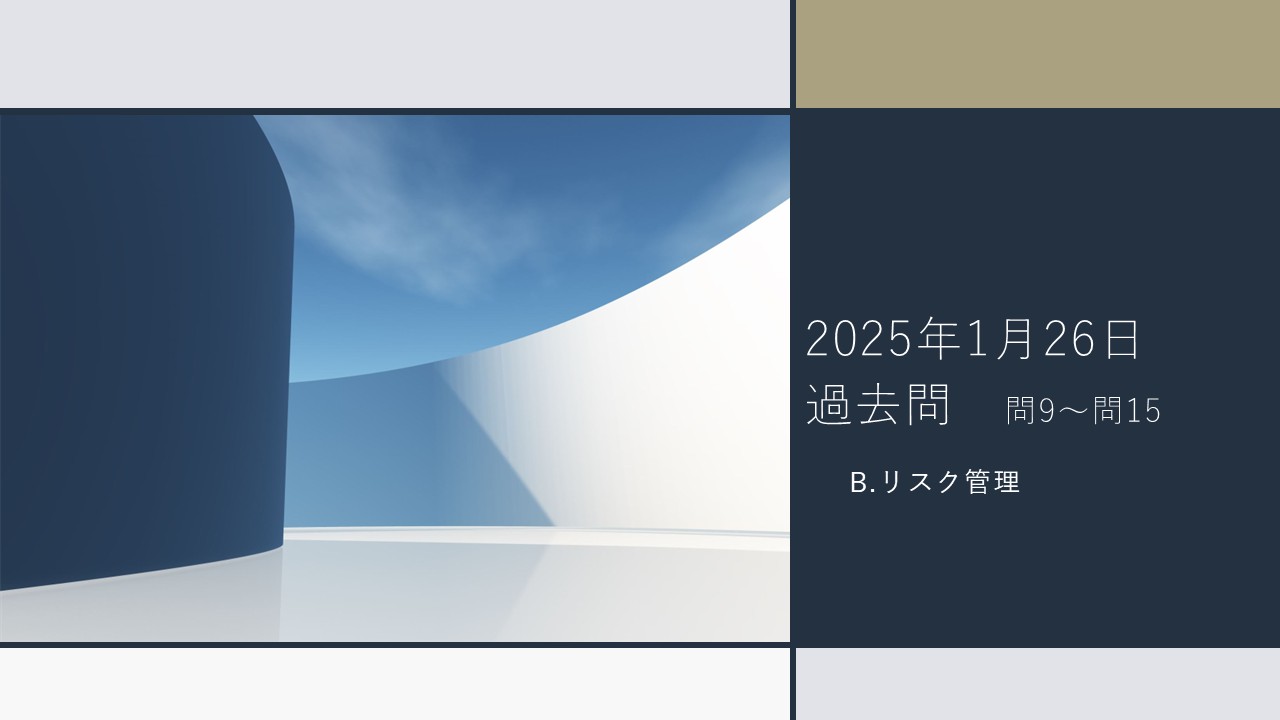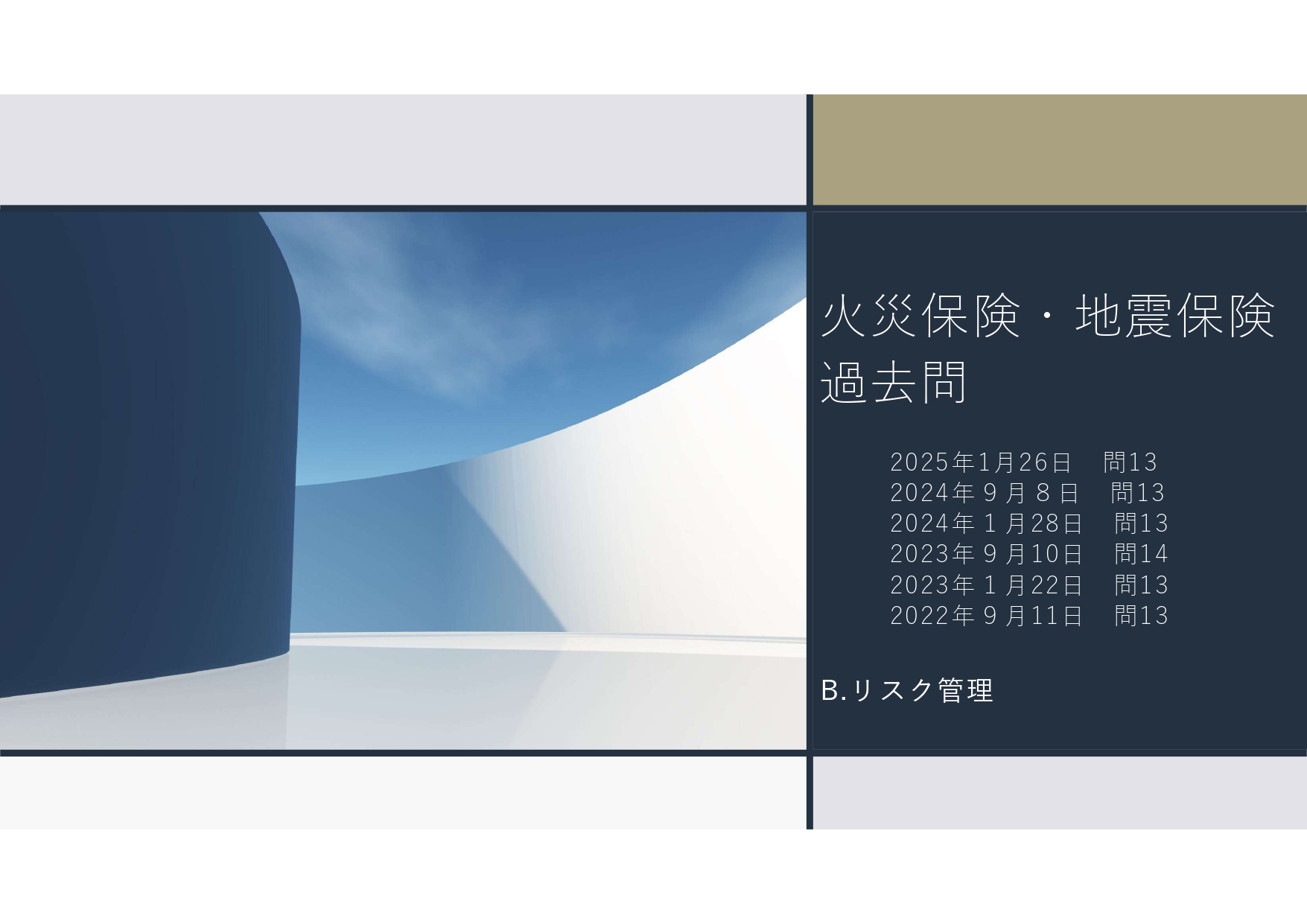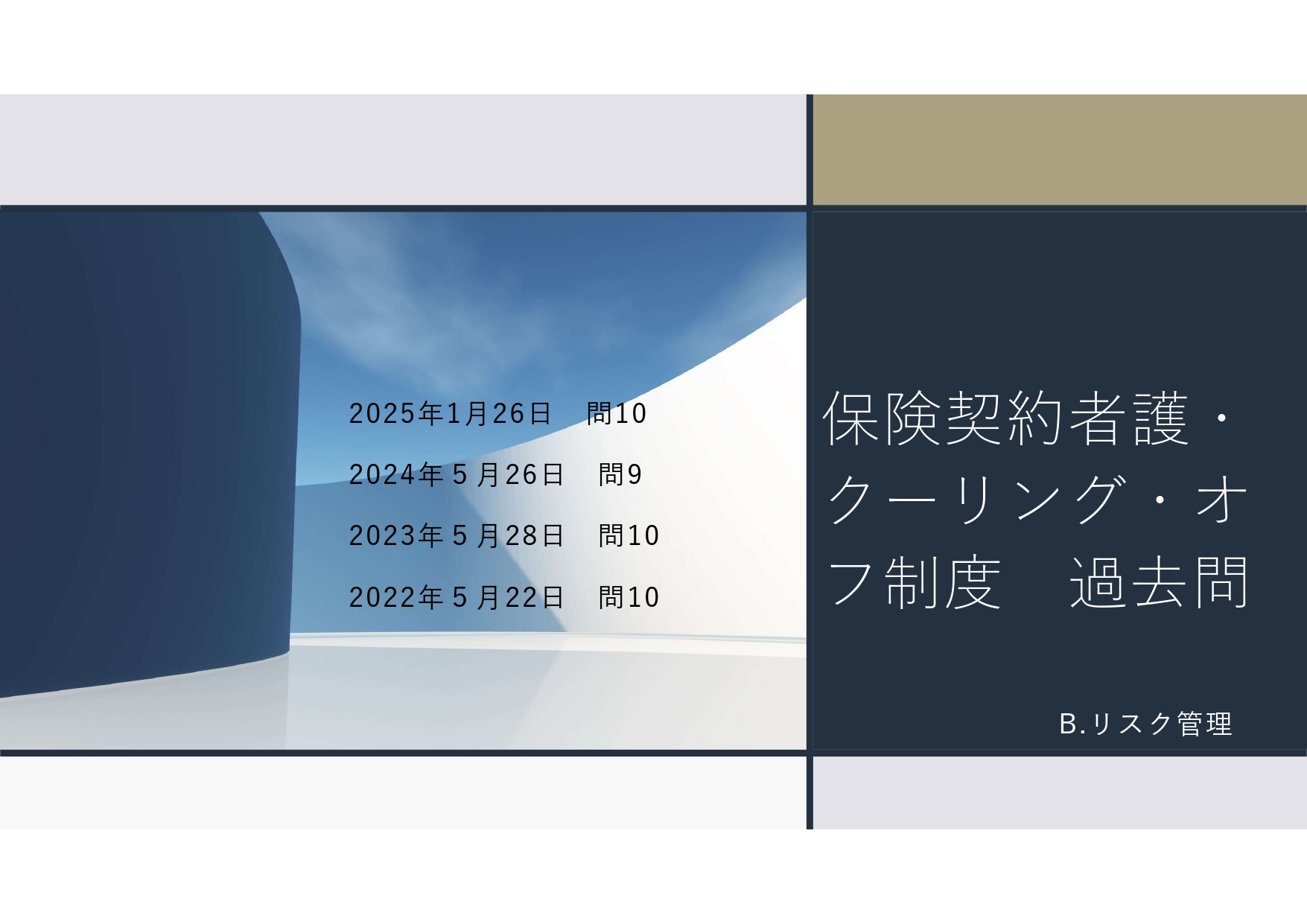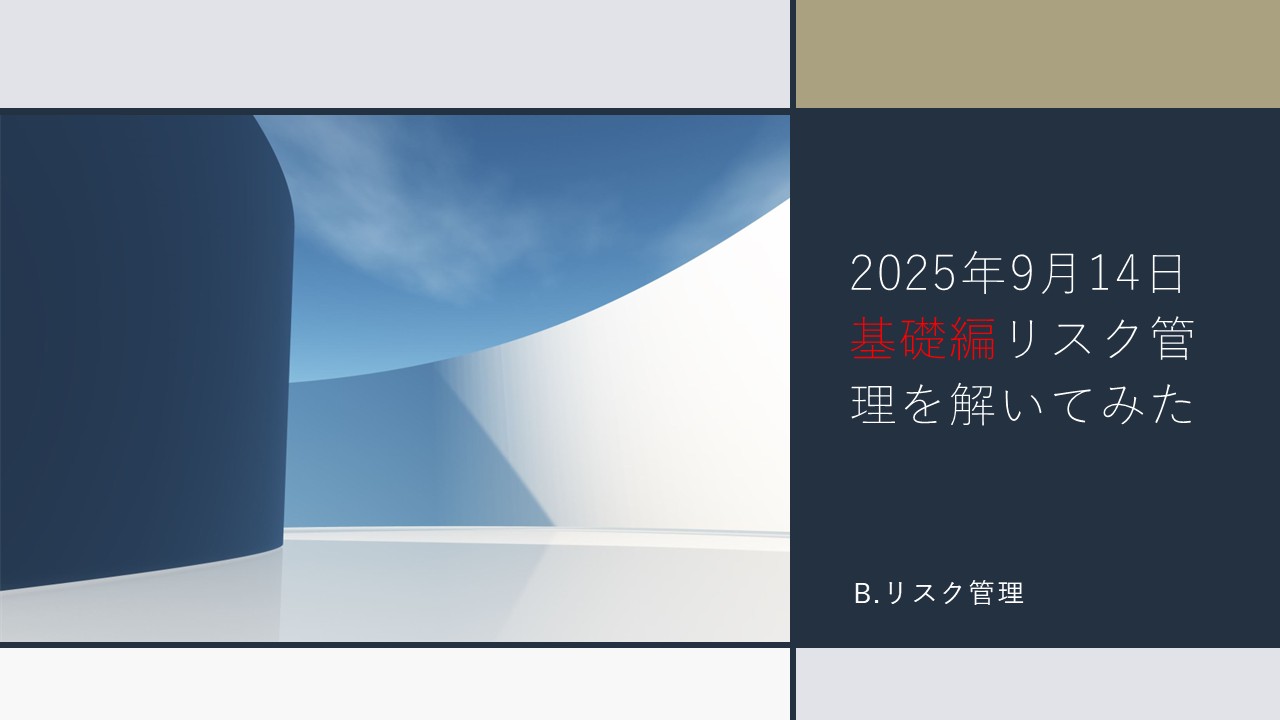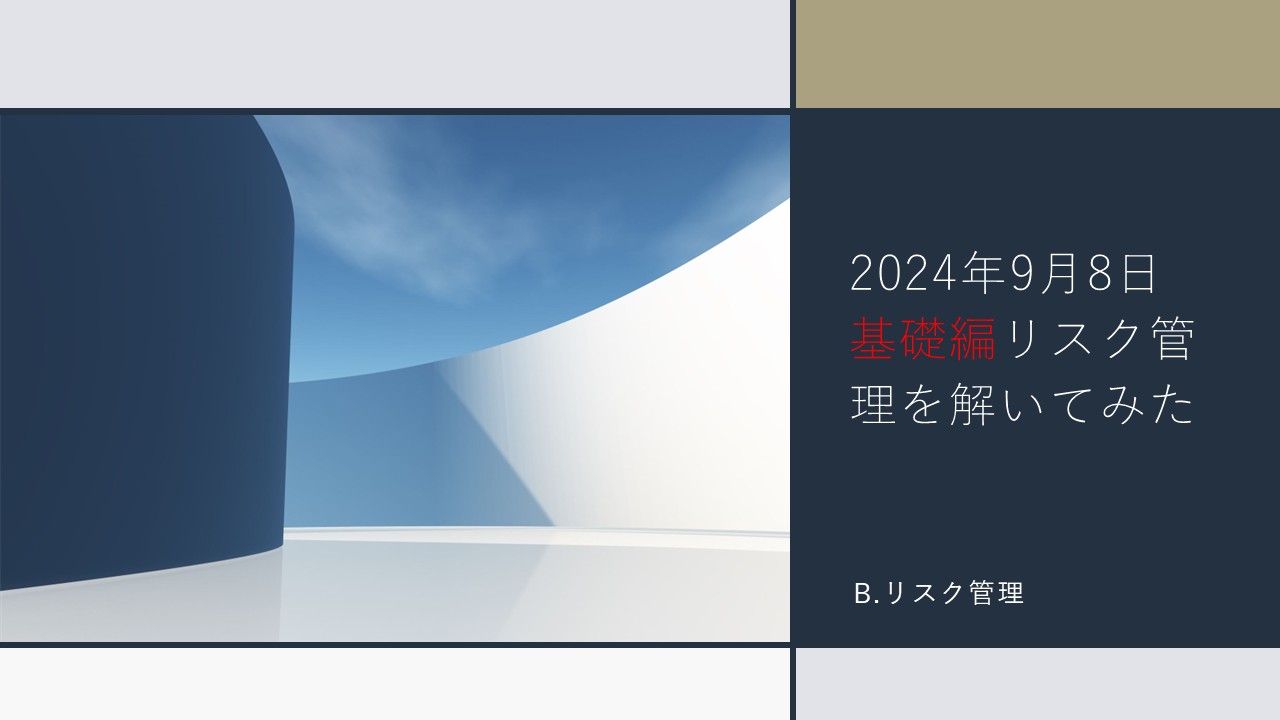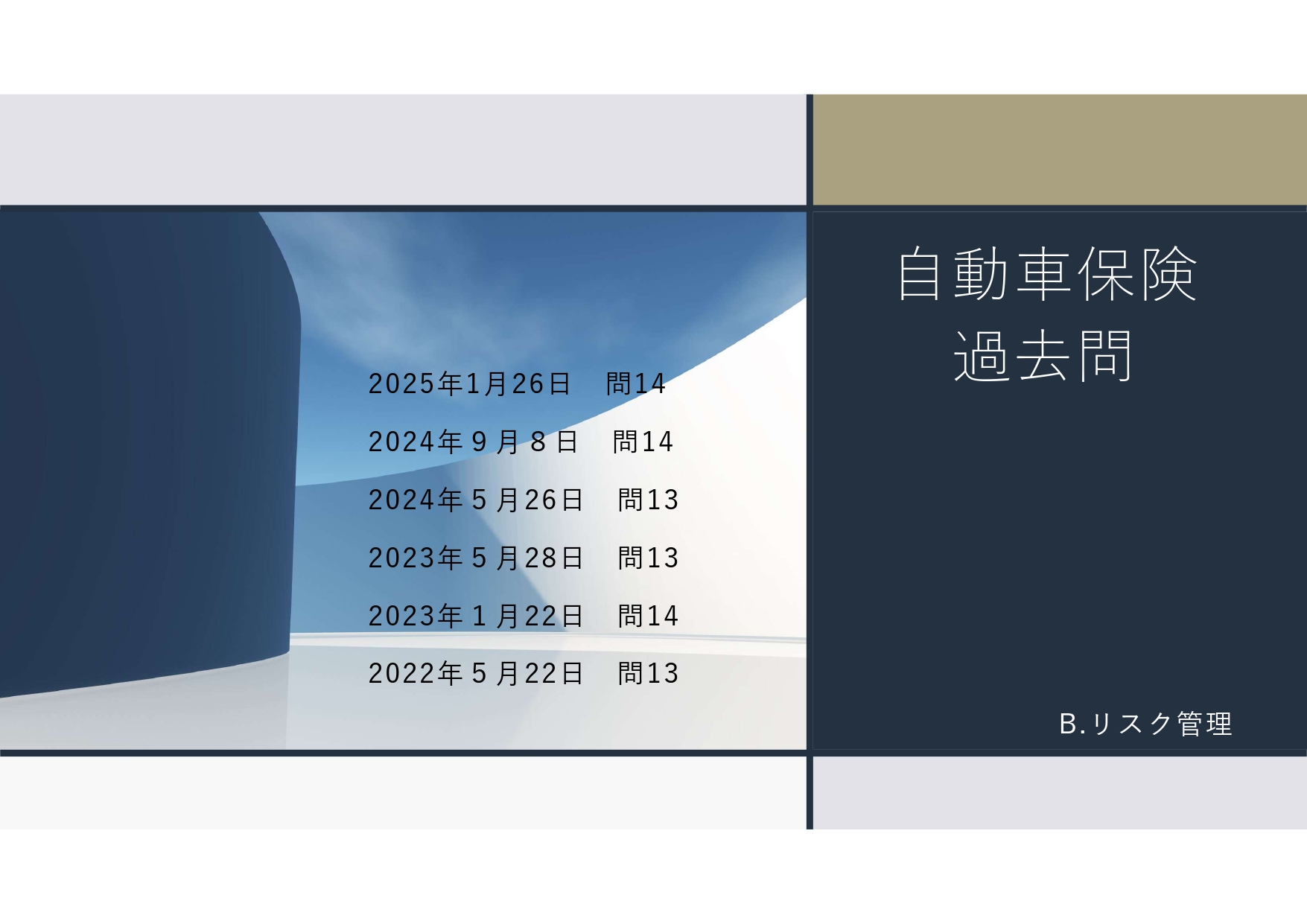2025年5月25日 基礎編 リスク管理
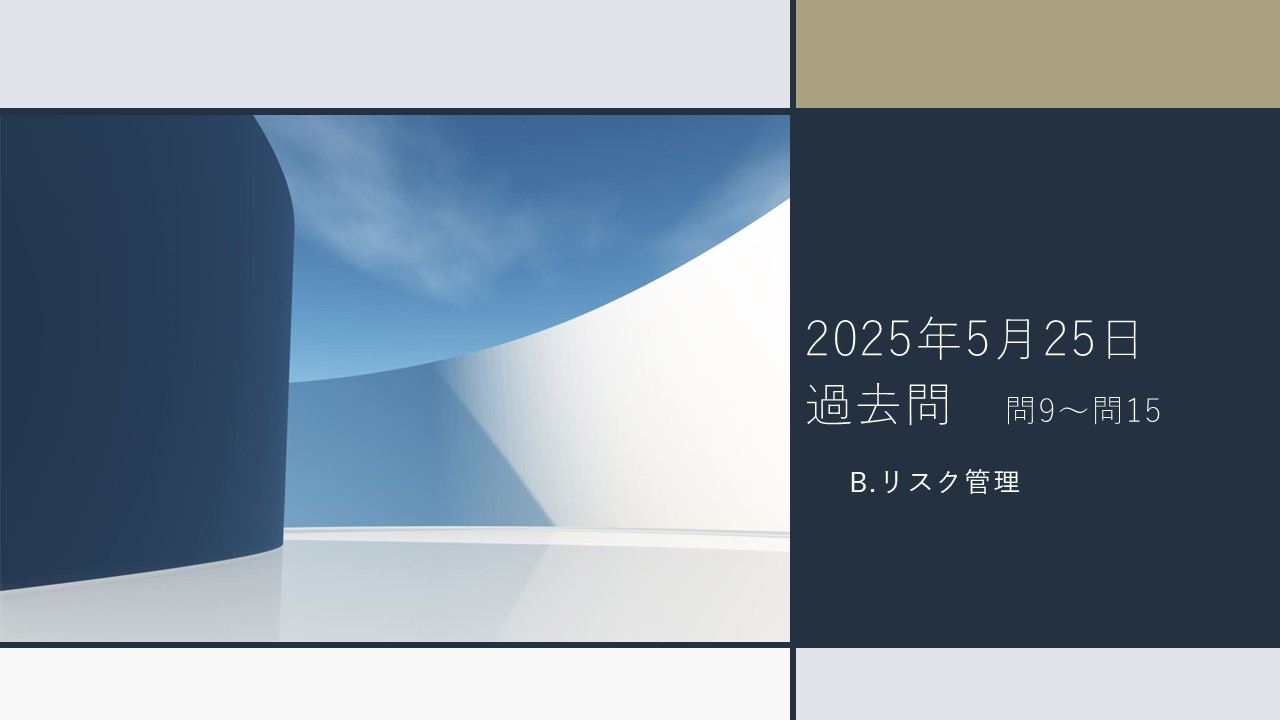
FP1級試験を勉強し始めたころ、リスク管理は苦手で当初は捨てていました。0点では足切りになると思い、1問正解することを目指し、他の分野に勉強時間をまわすようにしていました。
しかし、学科試験の不合格が続き、なんとか目標の5割を目指すため、2,022年頃から真面目に取り組むようになり、やり始めると、他分野に比べ法改正も少なく、過去問を暗記することで効率よく得点できると感じるようになりました。
2024年5月学科試験に合格でき、初めてFP協会の実技試験に取り組み始めて、保険証券の読み取り問題などが出題されることを知り、この時、初めて生命保険など真面目に勉強したかもしれません。結局は不合格でしたが・・・
また、2023年1月試験の応用編問57で解約返戻金が何所得になるか?という問題も出題され、きちんと学習していないと使える知識とはいえないことを痛感しました。
という話はいったん置いておいて、2025年5月の試験リスク管理の分野を見ていきたいと思います。
適切な解説をされているサイト、動画もありますので、それには劣りますが、精いっぱい、検証と解説を試みます。
出所:一般社団法人 金融財政事情研究会
問9 保険法
| 《問9》 保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 保険契約者と被保険者が異なる終身保険において、当該被保険者の同意がなければ、その保険契約の効力は生じない。 2) 保険契約者と被保険者が同一人である終身保険において、保険契約者の遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 3) 保険契約者と保険金受取人が異なる終身保険において、当該保険契約の差押債権者から保険者に対して解約請求がされた場合、その請求から3カ月以内に、保険金受取人が保険契約者の同意を得て請求時点の解約返戻金相当額を差押債権者に支払い、かつ、保険者にその旨の通知をすれば、当該保険契約を存続させることができる。 4) 保険給付を請求する権利や保険料の返還を請求する権利は、原則として、これらを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。 |
正解3

1)保険の契約って契約者、被保険者、保険金受取人がごっちゃになることがあるんだよね。
2)遺言による保険金受取人の変更ってドラマみたいだけど、実際にありえるかもね。
3)保険金と差押債権者ってドラマみたいだけど、実際にあるのかな。
4)保険金の請求にも時効ってあるのかな。

1)これは当然かもね、自分にかけられてる保険を知らなって怖いもんね。
2)このケースもややこしいけど、保険者にしてみれば、保険金を誰に支払ったらいいかわからなくなりそうだから当然かもね。
3)保険金は差押債権にできないような気がする。こういう場面では弁護士に相談することだね。
4)この選択肢は正しいよ。身内の不幸で冷静な判断ができない方には酷だけど、3年で時効を迎えるから、身の回りの専門家へ相談することをお勧めするよ。
問10 生命保険契約の各種手続等
| 《問10》 生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 加入している養老保険について、保険料の払込みを中止し、払済養老保険に変更した場合、一般に、変更前の養老保険の予定利率は引き継がれず、変更時点における予定利率が適用される。 2) 加入している終身保険について、保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更した場合、一般に、変更前の終身保険に付加されていた医療保障や介護保障等の各種特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約や指定代理請求特約は消滅しない。 3) 契約者貸付の利率は、一般に、生命保険契約の契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。 4) 契約転換制度により、現在加入している生命保険契約を新たな契約に転換する場合、転換後契約の保険料は、転換時の被保険者の年齢や保険料率等により算出される。 |
正解1

1)保険を払に変更することはありえると思うけど、予定利率なんて意識していないな。
2)払済に変更した場合の特約って考えたことないな。
3)なんとなく正しい気がするけど、確信がもてないな。
4)契約転換制度というものがわからないとピンとこないな。

1)予定利率は保険会社が約束した利回りだね。払済に変更した場合でも当初の予定利率は継続するよ。よってこれが誤りだね。
2)この選択肢は正しいよ。払済とリビングニーズ特約、指定代理請求特約はセットで出題されやすいよ。
3)これは正しい。問題文をそのまま覚える価値あり。ただし、ちょっと日本語を変えると意味がかわってきたりするので正確に覚える必要があるね。
4)これは正しい。問題文をそのまま覚える価値あり。契約転換制度は、生活が厳しくなると検討する方が増えるかもしれないので、FPはよく勉強しておく必要があるね。
問11 外貨建保険
| 《問11》 外貨建保険に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 外貨建終身保険は、保険業法上、特定保険契約に該当するため、保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)の適用対象外とされる。 (b) 市場価格調整(MVA)機能を有する外貨建終身保険は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映され、契約時と比較した解約時の市場金利の上昇は、解約返戻金額の減少要因となる。 (c) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする外貨建終身保険に円換算支払特約が付加されている場合、夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は、相続税額の計算上、妻が実際に受け取る円貨の額ではなく、外貨建ての保険金額を夫の死亡日における対顧客電信売買相場仲値(TTM)で円換算した額で評価する。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

いくつあるか正解の個数を答える問題にはいつも悩まされるよね。まさかの全部正解だったり、正解なしのパターンもあるからね。しかし、自信がないから正解1とか2をえらんじゃうんだよね。

(a)これは不適切だね、外貨建ということでクーリングオフができないということはないよ。
(b)過去問に何度も登場する問題だね。MVA機能は金利と解約返戻金の逆の関係にあると覚えておくといいかもね。
(c) この場合、相続開始日のTTBで評価されるよ、よって誤り
(b)が正解なので1)だね。
問12 経理処理
《問12》 X株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役であるAさんは、以下の定期保険への加入を検討している。X社の初回の保険料支払時の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。
| 保険の種類 : 無配当定期保険(特約付加なし) 契約年月日 : 2025年6月1日 契約者(=保険料負担者) : X社 被保険者 : Aさん(加入時における被保険者の年齢50歳) 死亡保険金受取人 : X社 保険期間・保険料払込期間 : 98歳満了 基本保険金額 : 1億円 最高解約返戻率 : 80.0%(経過15年目) 年払保険料 : 300万円 |
| 1) | 借 方 | 貸 方 | ||||||||
| 定期保険料 180万円 前払保険料 120万円 | 現預金 300万円 | |||||||||
| 2) | 借 方 | 貸 方 | ||||||||
| 定期保険料 150万円 前払保険料 150万円 | 現預金 300万円 | |||||||||
| 3) | 借 方 | 貸 方 | ||||||||
| 定期保険料 120万円 前払保険料 180万円 | 現預金 300万円 | |||||||||
| 4) | 借 方 | 貸 方 | ||||||||
| 定期保険料 84万円 前払保険料 216万円 | 現預金 300万円 | |||||||||
正解3

これも定番の法人の生命保険契約に関する問題だね。最高解約返戻率によって仕訳が変わることがあるのはわかるんだけど、以下なのか未満なのか迷うんだよね。

今回は比較的やさしい問題だったと思う。最高解約返戻率に注目して、50%以下だと全額費用計上、50%超~70%以下、70%超~85%以下、85%超の4段階に分けて考えるんだね。
また、50%超~70%以下、70%超~85%以下の2つは保険期間の当初4割相当の期間を経過する日まで資産計上するという問題が出題されることもあり、85%以上になるとパターン分けがちょっと複雑になるから注意が必要だね。
今回は最高解約返戻率80%だから、3)が正解だね。
問13 任意の自動車保険の一般的な商品性
| 《問13》 任意の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 対物賠償保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中にハンドル操作を誤って店舗に衝突して損壊させた場合、店舗の修理費用だけでなく、修理中の店舗の休業損害についても補償の対象となる。 2) 対人賠償保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に単独事故を起こしたことにより、同乗していた当該記名被保険者の兄が負ったケガは補償の対象となる。 3) 人身傷害保険では、記名被保険者が被保険自動車を運転中に後続車に追突されて負傷した場合、事故の相手方との示談交渉が成立していなくても保険金が支払われる。 4) 車両保険では、単独事故により被保険自動車が全損した場合、保険金額を限度に、実際の損害額から保険契約上の免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われる。 |
正解4

1)任意の自動車保険って運転する人ならだれでもお世話になっているテーマだね。これを意識せずに済んでいる人はある意味、幸運だね。
2)自動車保険って相手が家族だと対象にならないんじゃなかったっけ?兄弟は家族?
3)交通事故の示談って時間かかったりするもんね。
4)保険契約上の免責金額って理解があいまいだね。

1)これは対象となるね。店舗の休業補償を個人で負担するとなったら、ちょっと厳しいよね。
2)対人賠償保険で親や子と兄弟姉妹の扱いがちょっと違うので注意が必要だね。兄弟姉妹は対象になるんだね。
3)人身傷害保険では、標記のとおりだね。生保・損保とも保険金が出る場合と出ない場合は微妙だったりするから、保険会社の担当者とコミュニケーションをとっておくことだね。
4)保険契約上の面積金額は損害が発生した際、自己負担する金額のことだね。
全損の場合は、免責金額は差し引かれないので、これが誤りだね。
問14 施設所有(管理)者賠償責任保険
| 《問14》 飲食店を営むX社が被った次の損害のうち、X社が加入している施設所有(管理)者賠償責任保険の補償の対象とならないものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。 1) 店内で調理し、販売した弁当が原因で、自宅で弁当を食べた顧客が食中毒を発症した場合に、顧客に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害 2) 従業員が不注意により配膳中の料理をこぼして顧客の衣服を汚損した場合に、顧客に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害 3) 従業員が自転車で弁当の配達中に誤って通行人に衝突し、通行人が負傷した場合に、通行人に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害 4) 店の外壁に設置していた看板が落下し、顧客が駐車していた自動車が損傷した場合に、顧客に対する法律上の損害賠償責任を負担することによって生じた損害 |
正解1

施設所有(管理)者賠償責任保険もよく出題されるね、PL保険などとごっちゃになるから注意が必要だね。

1)これは生産物責任賠償保険(PL保険)の対象だから、これが不適切だね。自信があれば2)以下の問題は読まなくてもいいかもしれないけど、よく出題されるパターンだから読んでおくことをお勧めするよ。
問15 個人が契約する損害保険等の課税関係
| 《問15》 個人が契約する損害保険等の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) Aさんが自家用車の盗難に遭ったことにより、自動車保険の車両保険の保険金を受け取った場合に、当該損失について雑損控除の適用を受けるときは、損害額から当該保険金の額を差し引く必要がある。 2) Bさんが病気で入院したことにより、所得補償保険の保険金を受け取った場合に、入院に係る医療費について医療費控除の適用を受けるときは、支払った医療費の金額から当該保険金の額を差し引く必要がある。 3) Cさんが自宅を対象として少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象とならない。 4) Dさんが第三者に賃貸するアパートを対象として加入した地震保険の保険料は、地震保険料控除の対象とならない。 |
正解2

1)損害保険を受け取った時の課税関係ってあまり意識することないかもね。
2)入院した時に受け取る保険についてだよね。
3)少額短期保険業者ってあまり意識したことないな。
4)賃貸アパートで地震保険ってオーナーじゃないからわからないな。

1)自動車の盗難に対して出た保険金なら非課税になるので、問題分のような意識をする必要はないね。
2)病気で入院のして保険金で気をつけないといけないのは、それが治療のための保険金か就業不能になったため生活を保障する保険金か、区別することだね。
前者は医療費控除を受ける際に対象となるけど。後者は医療費控除を受ける際に差し引く必要がないよ。これもよく出題される論点だね。
3)少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象とならないよ。
少額短期保険業者について補償額、期間なども過去に出題されているので、要チェックだね。
4)地震保険料控除は自身や親族の居住する住居が対象だから賃貸アパートは対象外だね。