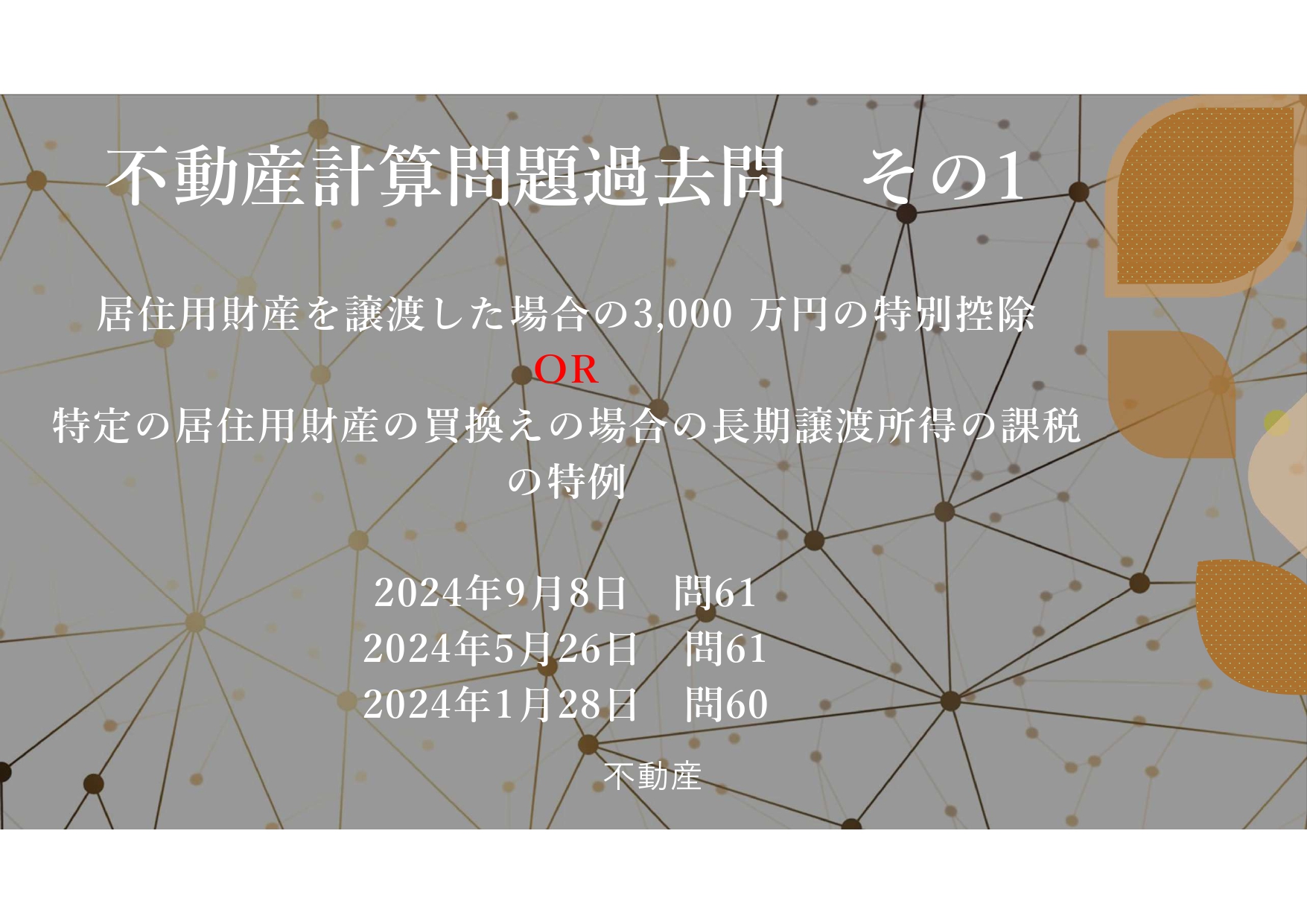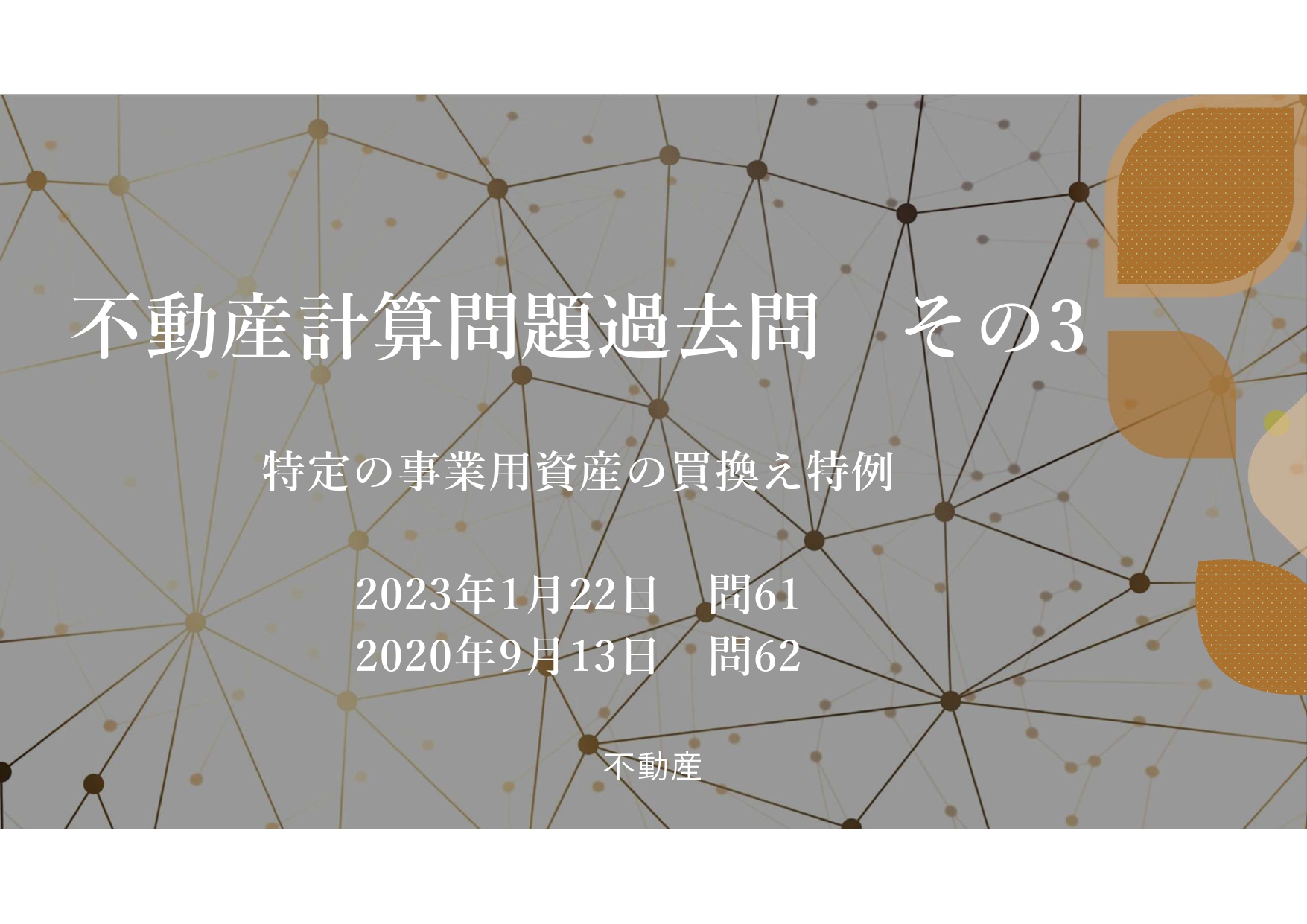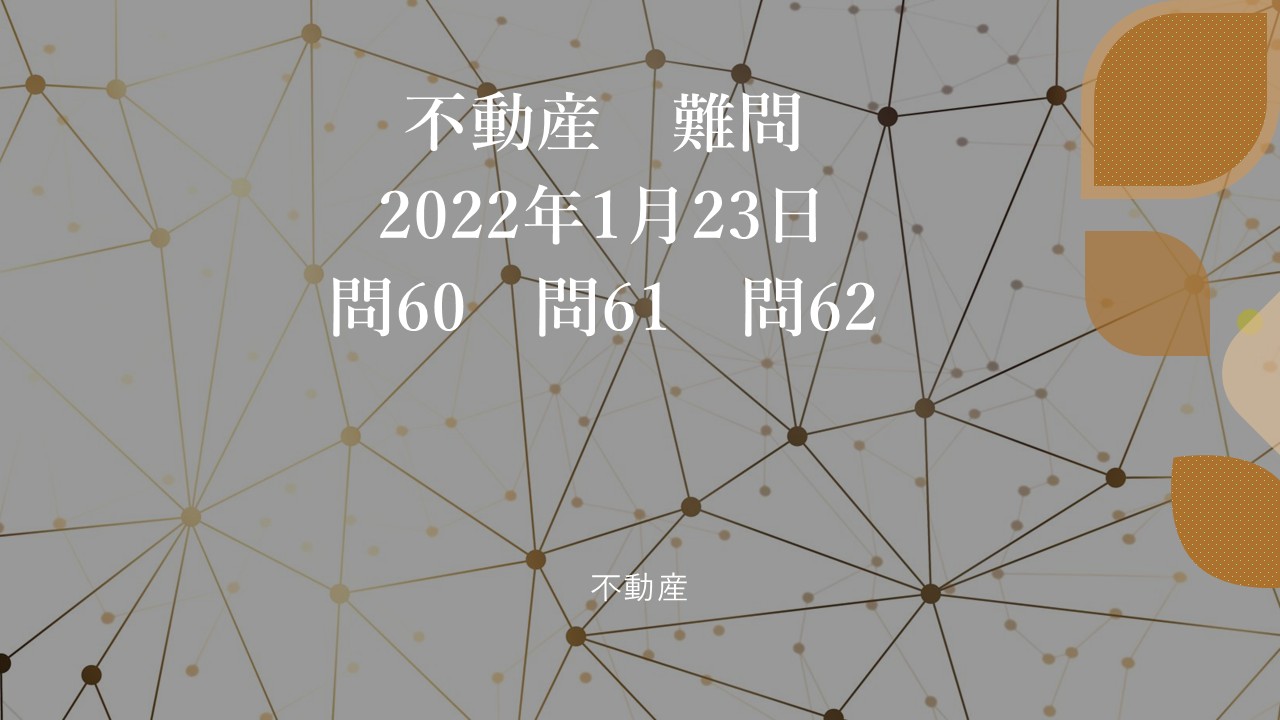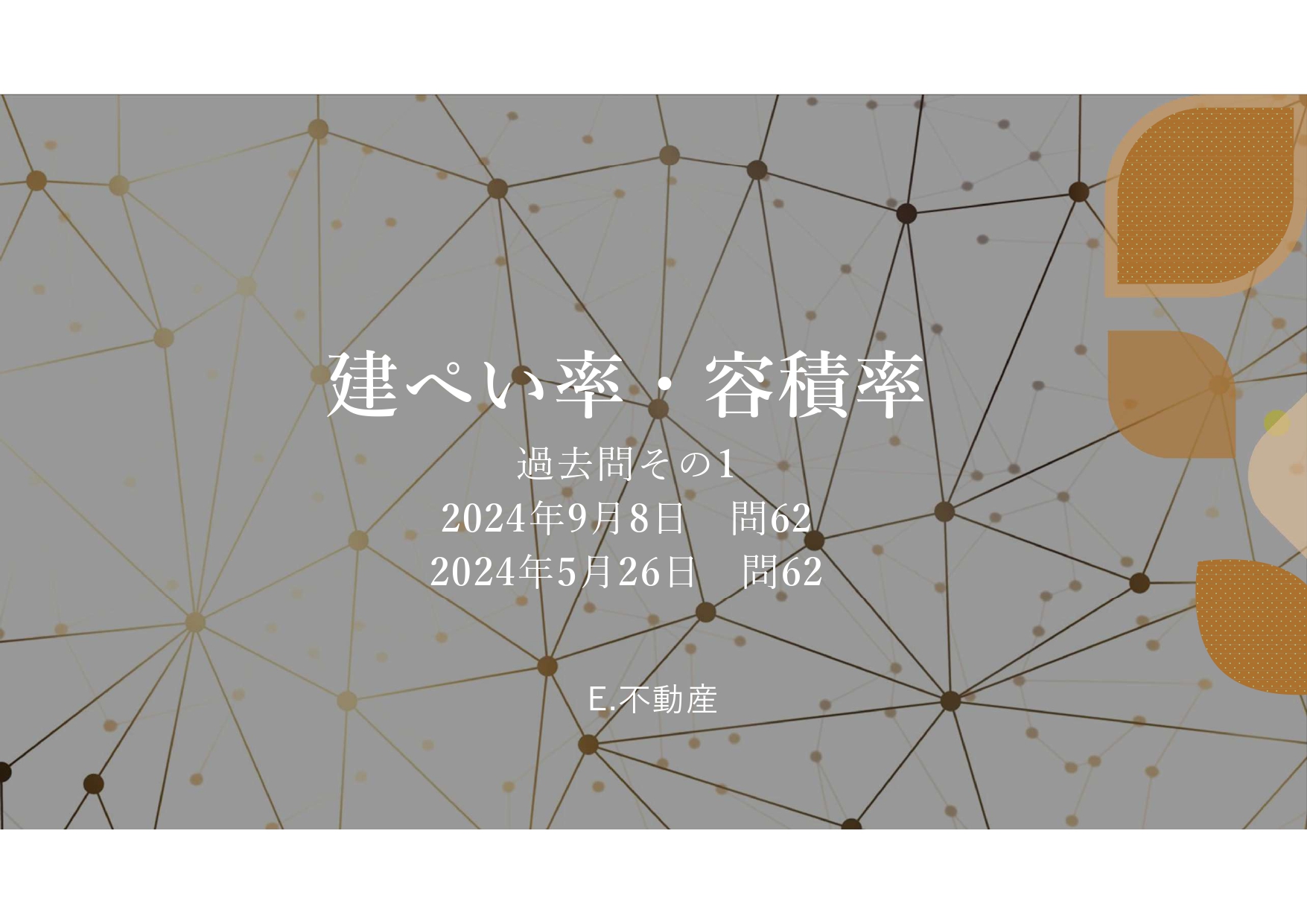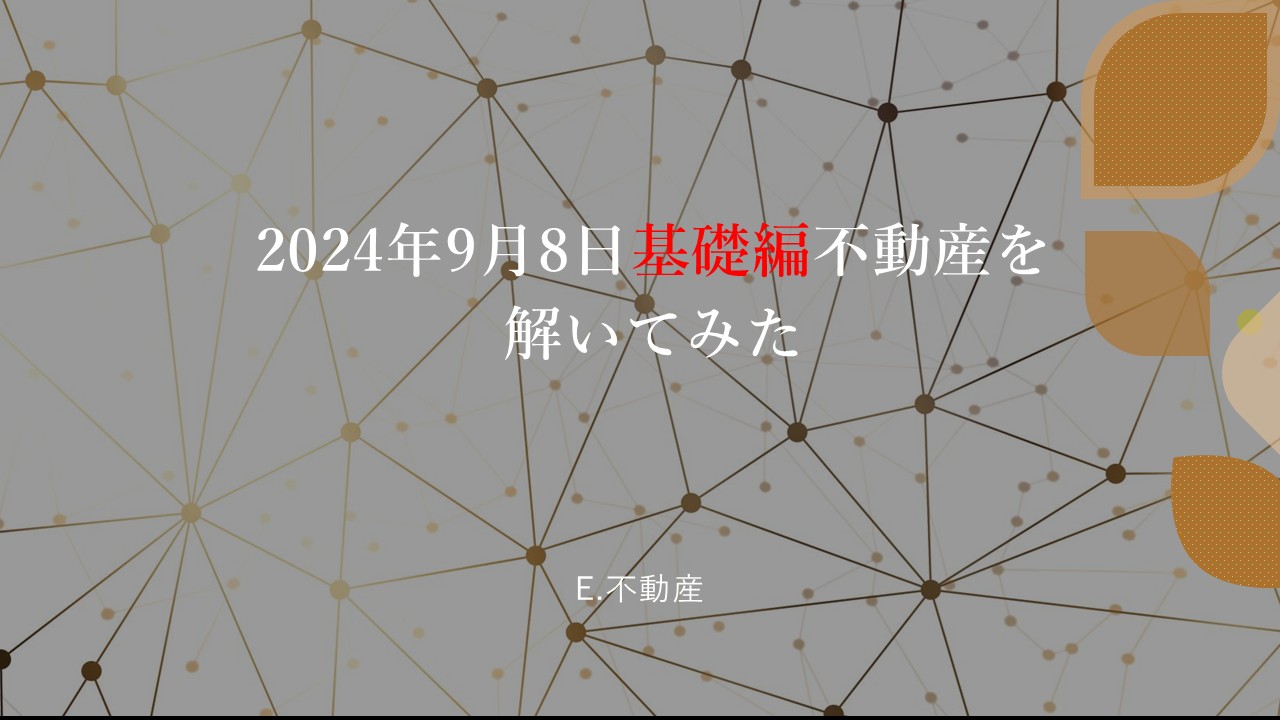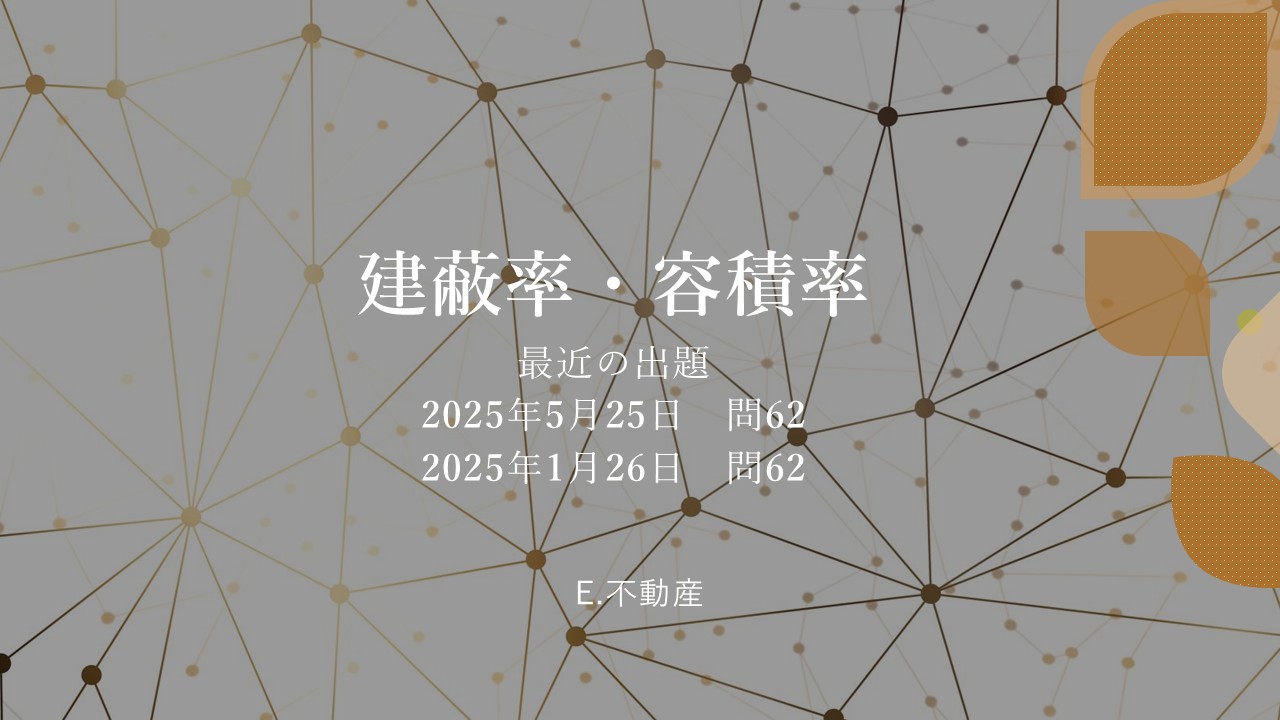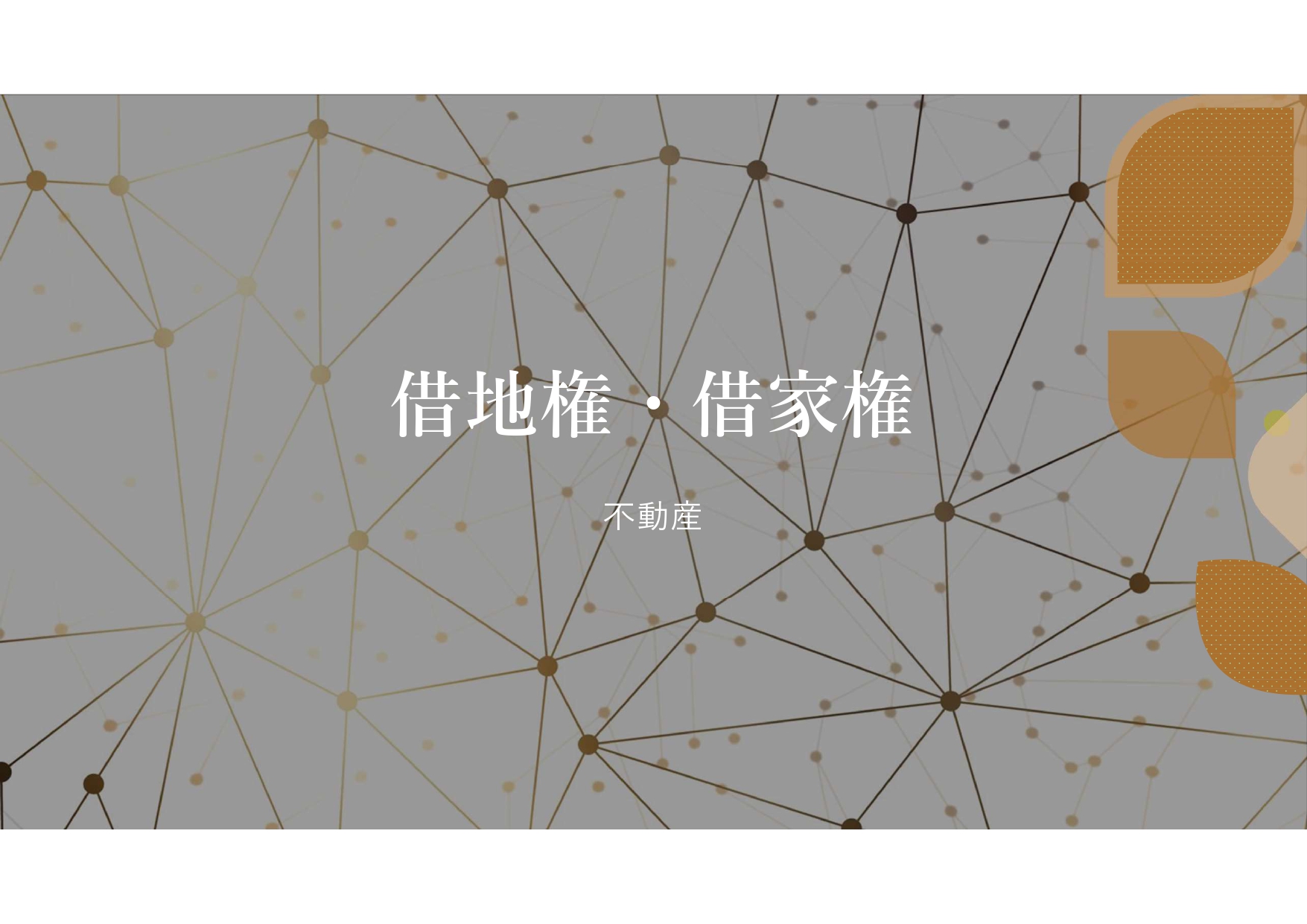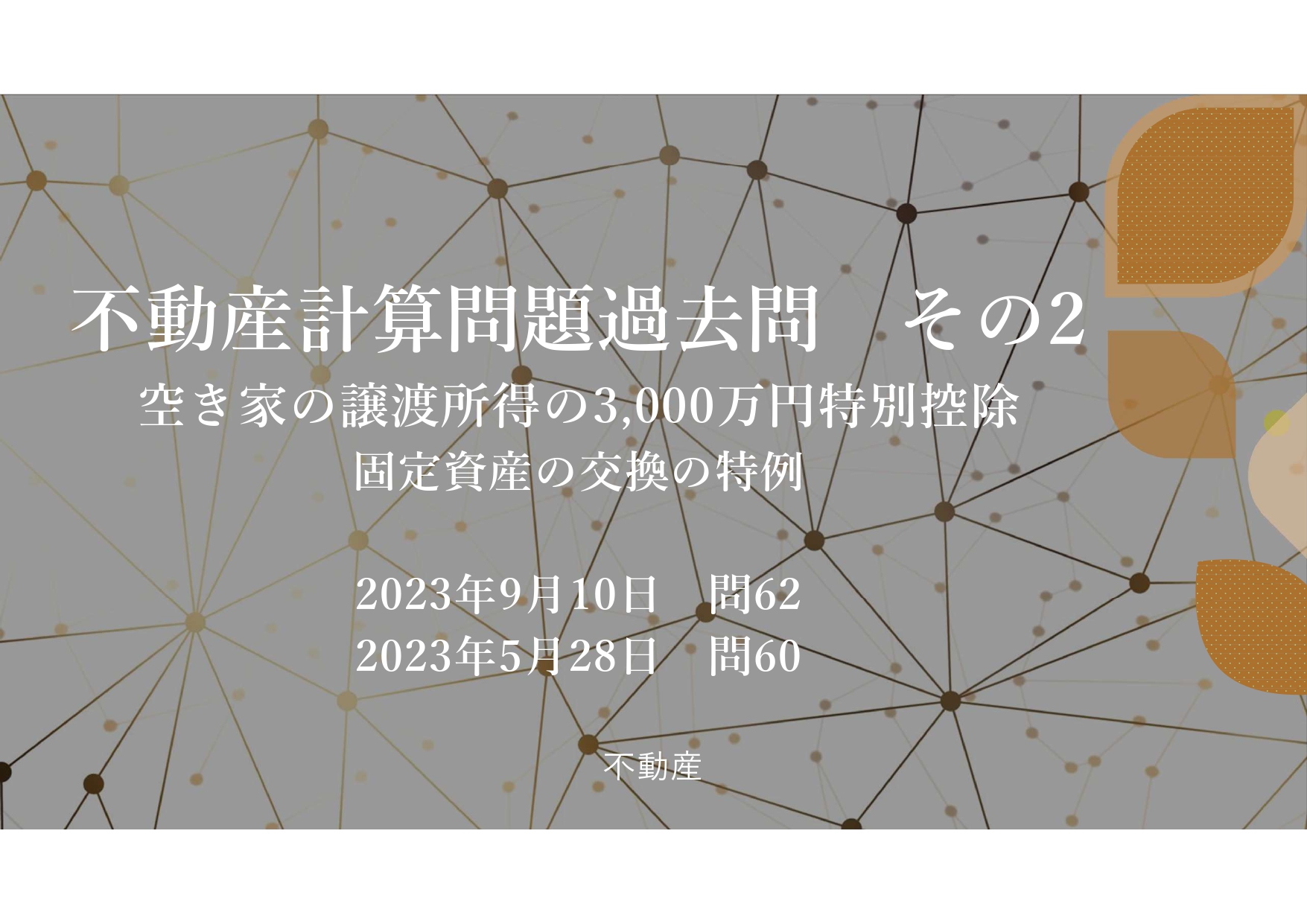2025年5月25日 基礎編 不動産
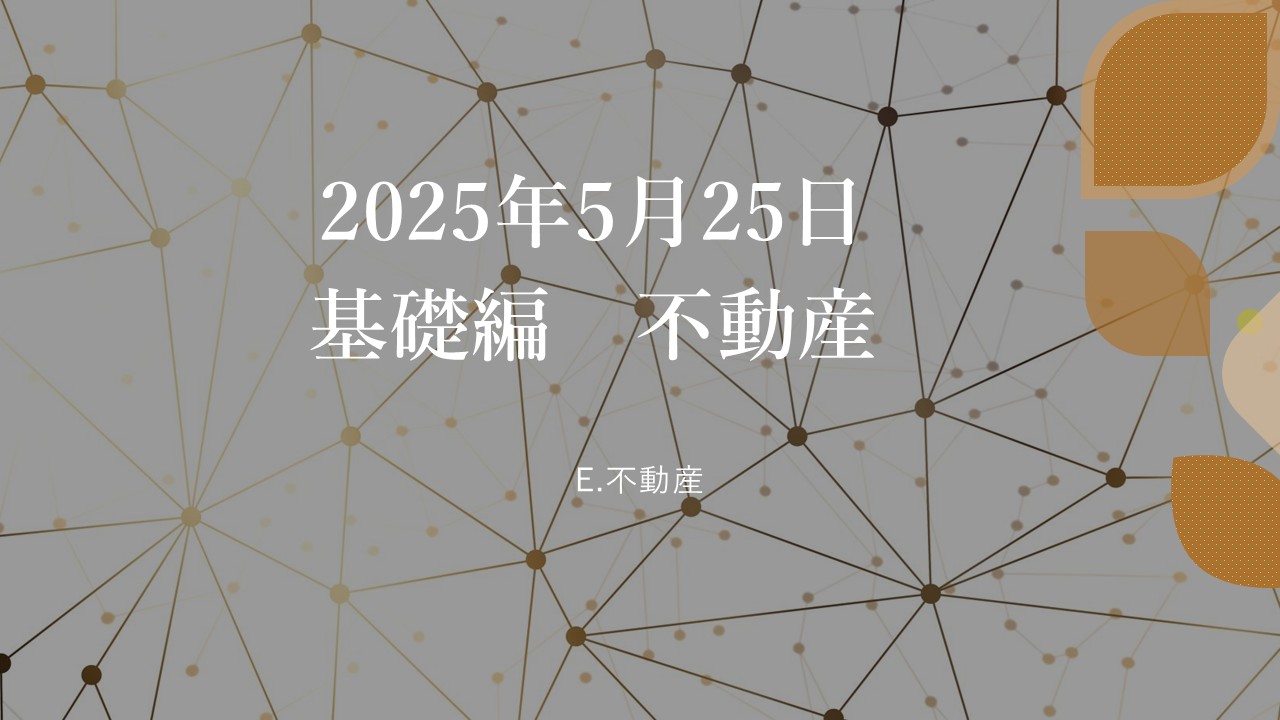
世間の方の大多数にとって、人生で1番の買い物は家や家を建てる土地ではないかと思います。
その土地を売ったり買ったりするのが不動産のテーマなのですが、かつて1980年代のバブル経済の頃には、「人類史上、土地の価格が下がったことはない」という不動産業者の売り文句があったと記憶しています。
その後、バブルは崩壊して、今は昔という話になったのですが、現在も不動産取引で多額の利益を出して、納税資金対策に苦慮するということは散見されます。
私のように過疎化が進む地方在住の身にとっては、3,000万円控除というのも信じられないと感じてしまうのですが、FPという立場は、こういった相談にも耳を傾け、税理士や司法書士、土地家屋調査士や宅建士、場合によっては弁護士などを紹介できるようしなければなりません。
2025年5月25日基礎編の問題を見ていきたいと思います。出所:一般社団法人金融財政事情研究会です。
問34 不動産登記法
| 《問34》 不動産登記法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 相続によって不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から1年以内に、当該所有権の取得に係る所有権移転登記を申請しなければならない。 2) 所有権の登記名義人について相続の開始があり、当該所有権が遺産分割協議の対象となる場合、相続人が相続人申告登記の申出をするためには、登記官に対し、共同相続人全員の連名による申出書を提出しなければならない。 3) 所有権の登記名義人について相続の開始があり、相続人が相続人申告登記の申出をした場合、登記原因や登記名義人について相続が開始した年月日、申出人の氏名・住所・法定相続分等の事項が所有権の登記に付記される。 4) 遺贈によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得に係る所有権移転登記を単独で申請することができる。 |
正解4

以前は、相続した土地や家屋の名義の書き換えは義務じゃなかったんだよね。
だから、相続した土地が祖父の名義だったってのも珍しくなかったよね。
2024年4月1日相続登記の義務化が決められ、しばらくはホットな話題として出題されるかもしれないね。

1)所有権移転登記は3年以内だね。1年ではないね。
2)相続人の1人が単独で申請は可能だよ。ただし遺産分割協議がまとまり正式な相続人が決まったら、改めて登記が必要になるよ。
3)相続が開始した年月日、申出人の氏名・住所は記載されるけど、法定相続分は記載されないよ。
4)これが適切だね。遺贈により受け取ったということは相続人固有の財産になるからね。
問35 宅地建物取引業法
| 《問35》 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合に、その不適合について買主が売主に通知すべき期間をその目的物の引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は有効となる。 2) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10%を超えることとなる定めをしてはならない。 3) 宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときは、その契約が一般媒介契約であるか専任媒介契約であるかにかかわらず、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に、当該媒介契約の目的物である宅地または建物につき、一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。 4) 専任媒介契約のうち、専属選任媒介契約を締結した依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、依頼者が自ら見つけた相手方と売買契約を締結することはできる。 |
正解1

FPを受験し始めたころ、不動産は大の苦手だったので、宅建の勉強をしばらくしたことがある。資格を取らなくても、苦手意識がある方にはお勧めだよ。

1)適合について買主が売主に通知すべき期間をその目的物の引渡しの日から2年以上と定められているので正しいね。
2)10%ではないね。2割を超えた部分が無効だね。
3)一般媒介契約である場合は指定流通機構への登録は不要だね。ちなみに指定流通機構は用語を書かせる問題が応用編で出題されたこともあるから要注意だよ。
4)専属選任媒介契約を締結した場合は、自己発見取引は禁止されるよ。これが専任媒介契約の場合は認められるから注意が必要だね。
問36 借地借家法
| 《問36》 借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問における普通借地権とは、定期借地権等以外の借地権をいう。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 1)普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。 2) 普通借地権の存続期間が満了し、借地権設定者が借地契約を更新しない場合、借地権者は、借地権設定者に対し、借地権者が権原により借地上に建築した建物について時価で買い取るべきことを請求することができる。 3)専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を50年以上とする定期借地権は、設定することができない。 4) 土地所有者に対する建物の譲渡により建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、当該建物の賃借人は、土地所有者の承諾を得られなければ、その消滅後に当該建物の使用を継続することはできない。 |
正解2

借地借家法は毎回のように、出題されているね。
借りている方と貸している方、双方が満足していれば問題はないんだろうけど、世間ではもめごとも多いから専門家の知恵が必要になるんだろうね。

1)これはよく出題されるね。「普通借地権の存続期間が満了する場合、建物があるときに限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。」というのが正しいね。
2)これが正しいね。建物買取請求権の説明だね。これが事業用定期借地権の場合だと更地返還になるので、混同しないよう注意が必要だね。
3)これは解釈が難しいね、「専ら事業の用に供する建物の所有を目的」ということから事業用定期借地権のことを問われているような気がするけど、一般定期借地権でも可能ということで、50年超でも可能ということなんだろうね。
4)建物譲渡特約付借地権が消滅した場合、希望すれば、賃貸借契約で使用が可能だよ。
問37 都市計画法
| 《問37》 都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 都市計画区域のうち、市街化区域は既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされる。 2) 高度利用地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とされる。 3) 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 4) 開発許可を受けた者が、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
正解2

都市計画法か、以前、大阪在住の際には、街が開発されて次々、新しい商業施設や遊園地ができるのを目の当たりにしていて、そのころFPの知識があったら、興味深い事例にたくさん出会えていたかもしれないけど、田舎に戻ってから、ほとんど関心を持っていない分野だね。しかし、こういうテーマにも一定の知識を持って臨まないといけないね。

1)これは適切だね。この問題文はそのまま暗記するといいと思うよ。
2)これは高度利用地区でなく、高度地区の説明だね。高度利用地区は都心の高層ビルのイメージだね。高度地区
3)これは設問の通りだね。
4)これも設問の通り、正し許可を得る必要はなく、あくまで届出だね。
許可と届出は農地法でもよく問われる内容だね。
問38 建築基準法
| 《問38》 建築基準法に規定する建築物の高さの制限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、12mまたは15mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。 2) 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限(道路斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域内における建築物には適用されない。 3) 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限(隣地斜線制限)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域を除く用途地域内における一定の建築物に適用されるが、用途地域の指定のない区域内における建築物には適用されない。 4) 第一種中高層住居専用地域および第二種中高層住居専用地域内において日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)が適用される建築物には、北側の隣地の日照を確保するための建築物の各部分の高さの制限(北側斜線制限)は適用されない。 |
正解4

用途地域と前面道路の関係は毎回、出題されるね。道路斜線制限、隣地斜線制限、北川車線制限は丸暗記必須だね。

1)10mまたは12mが正しいね。テキストや過去問を何度も見て数字の違和感を感じるようにしないといけないね。
2)道路斜線制限はすべての用途地域に適用されるよ。
3)隣地車線制限は用途地域の指定のない区域でも適用されるよ。
4)これが適切だね。基本的に適切な選択肢は暗記するようにするといいよ。特に試験直前には。
問39 登録免許税
| 《問39》 登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) Aさんが、兄と2分の1ずつの共有持分を有する土地について2筆に分筆したうえで共有物の分割を行い、単独所有となる土地について所有権移転登記をする場合、登録免許税は課されない。 2) Bさんが、戸建て住宅を新築し、建設工事を請け負った工務店から引渡しを受け、直ちにその家屋の所在や種類、構造、床面積等を記録するための建物の表題登記をする場合、登録免許税は課されない。 3) Cさんが、協議による離婚後に元妻の所有するマンションを財産分与により取得し、所有権移転登記をする場合、登録免許税は課されない。 4) Dさんが、夫の死亡により子が取得した住宅について、配偶者居住権の設定登記をする場合、登録免許税は課されない。 |
正解2

登録免許税って登記をするときにかかる税金だよね。

1)分筆って実技試験のPart2の提案でよくあるよね。所有権移転登記には登録免許税がかかるよ。
2)表題登記には登録免許税はかからないね。これはよく出題される論点だね。
3)離婚による所有権移転登記にも登録免許税がかかるよ。
4)配偶者居住権の設定登記にも登録免許税がかかるね。
問40 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
| 《問40》 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事 項については考慮しないものとする。 1) 居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡した場合に、譲渡した年の1月1日において、家屋の所有期間が10年以下で、敷地の所有期間が10年超であるときは、家屋および敷地に係る譲渡所得について、いずれも本特例の適用を受けることができない。 2) 居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、買換資産を取得した場合、本特例と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)は重複して適用を受けることができない。 3) 居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、住宅借入金を利用して買換資産を取得した場合に、本特例の適用を受けるときは、当該住宅借入金について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。 4) 居住の用に供している家屋とその敷地を譲渡し、買換資産として戸建て住宅(家屋とその敷地)を取得した場合、本特例の適用を受けるためには、買換資産となる家屋の床面積が50㎡以上で、敷地の面積が300㎡以下でなければならない。 |
正解4

応用編では定番で計算はできるけど、意味を説明しろといわれるとよくわからないんだよね。

1)「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」は土地、家屋セットでないと受けることができないよ。
2)これも応用編で慣れている人にはサービス問題かもね。どちらかを選択して適用するという問題は定番だからね。
3)これも頻出の論点だね。住宅ローン控除は前2年、後3年に特例を受けていた場合、使えないね。
4)家屋の床面積50㎡以上は正しいけど、敷地面積は500㎡以下が正しいね。
問41 不動産の投資判断手法等
| 《問41》 不動産の投資判断手法等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a)IRR法は、対象不動産の内部収益率と対象不動産に対する投資家の期待収益率を比較して投資判断を行う手法であり、期待収益率が内部収益率を上回る場合、その投資は投資適格であると判断することができる。 (b) NPV法は、対象不動産に対する投資額と現在価値に換算した対象不動産の収益価格を比較して投資判断を行う手法であり、NPVがゼロを上回る場合、その投資は投資適格であると判断することができる。 (c) DSCRは、対象不動産から得られる収益による借入金の返済余裕度を評価する指標であり、DSCRがゼロを上回る場合、対象不動産から得られる収益だけで借入金を返済することができる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

投資判断手法の問題は定番だけど、落ち着いて問題文を読まないと、言ってることを逆にとらえちゃうことがあるんだよね。

(a)内部収益率>期待収益率でないと有利な投資とはいえないね。よって間違い。
(b) これは正しいね、不動産の現在価値という計算問題が出たりもするね。
(c) DSCR=キャッシュフロー÷返済額・利子なので1を上回ると有利な投資といえるけど、1を下回るとマイナスな投資といえるね。
よって(b)のみが適切なので正解1だね。