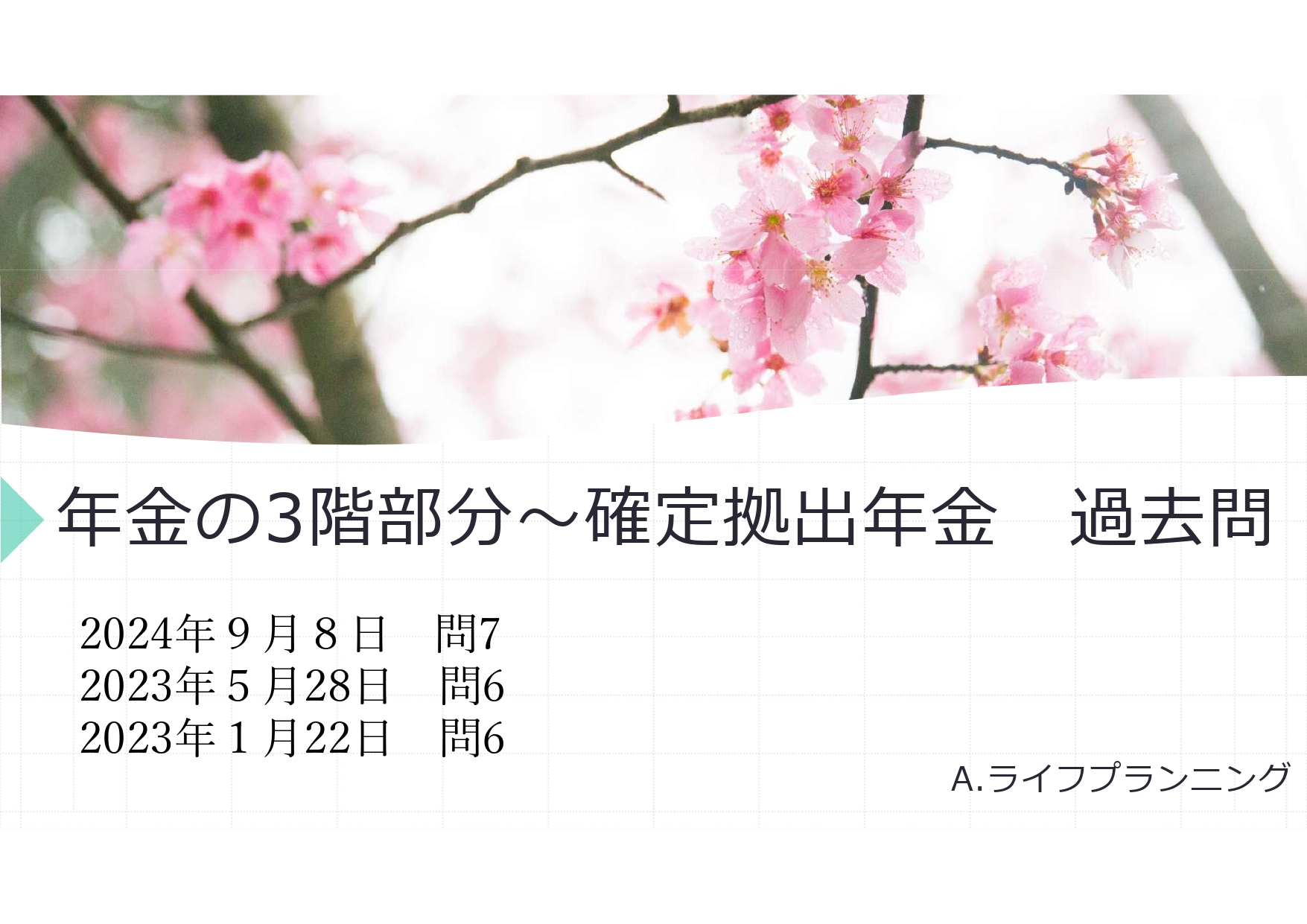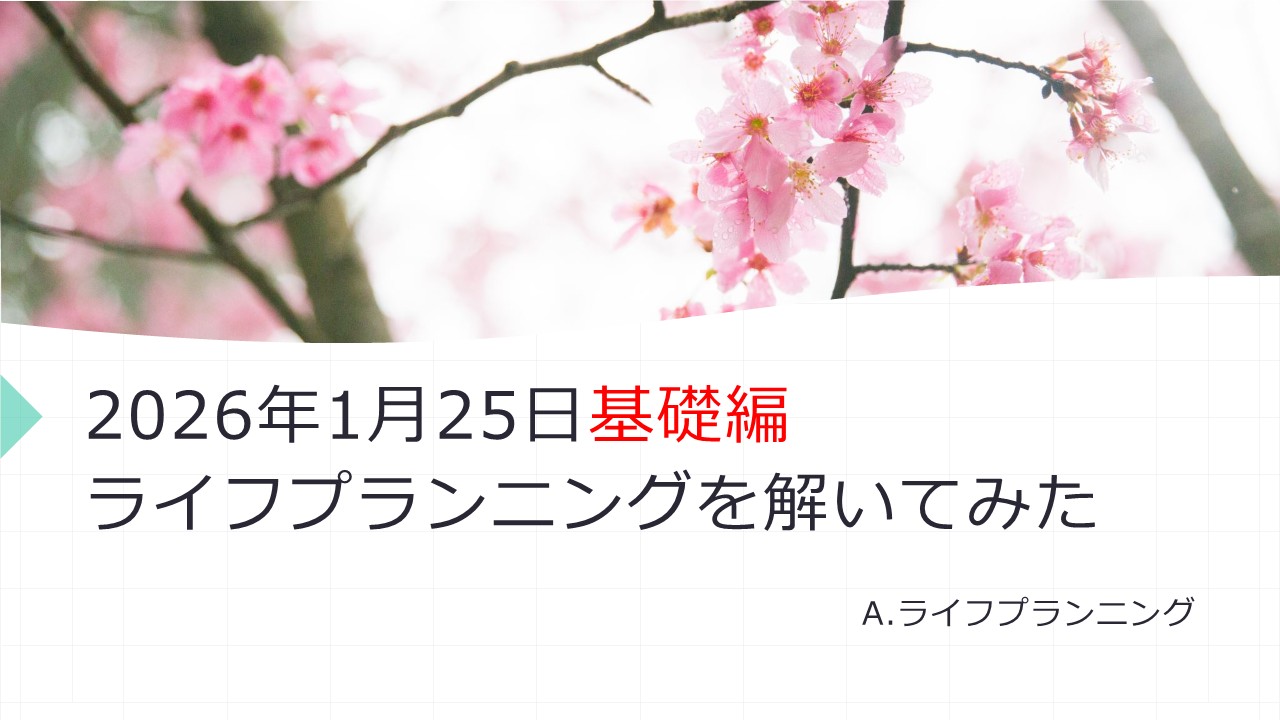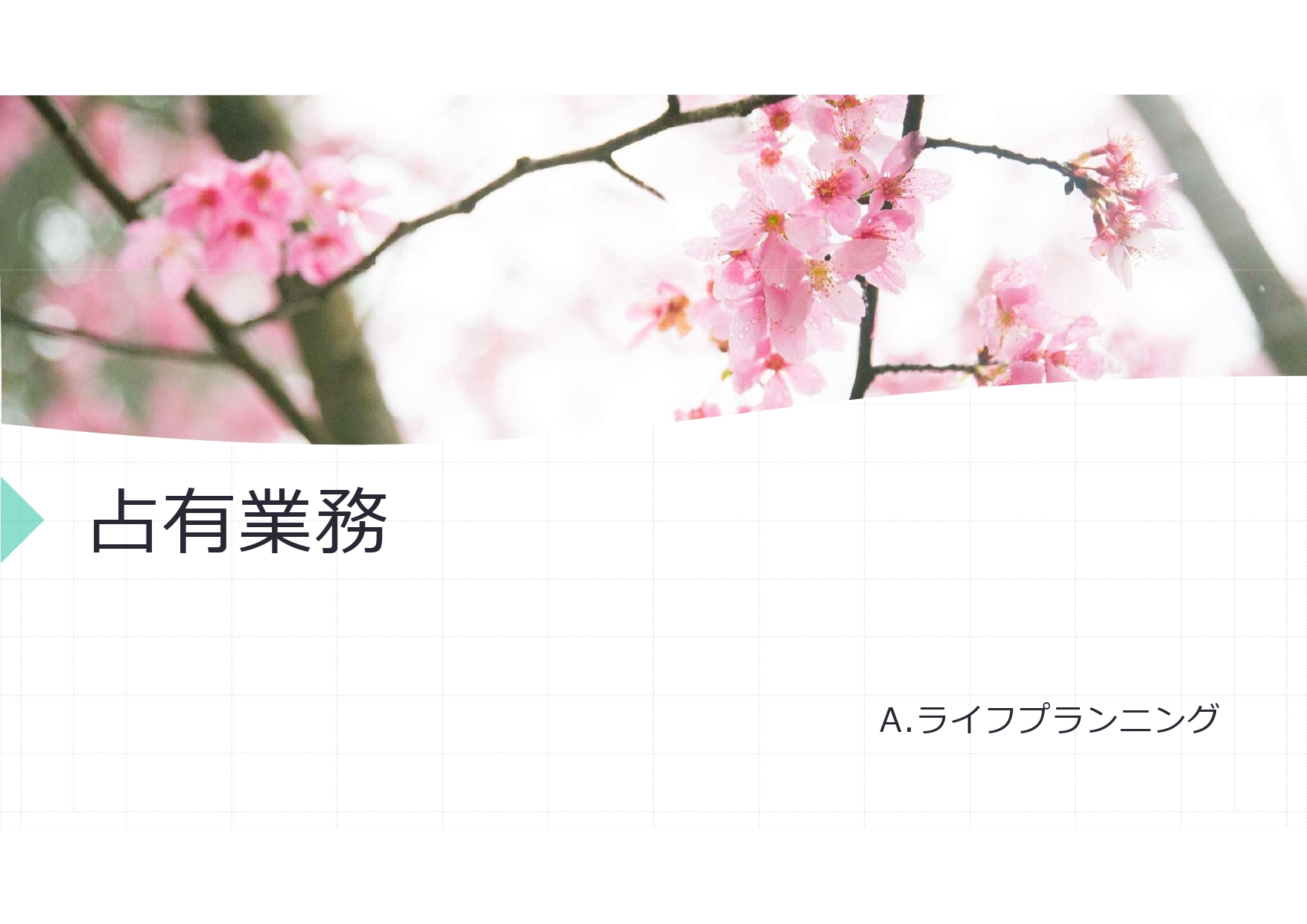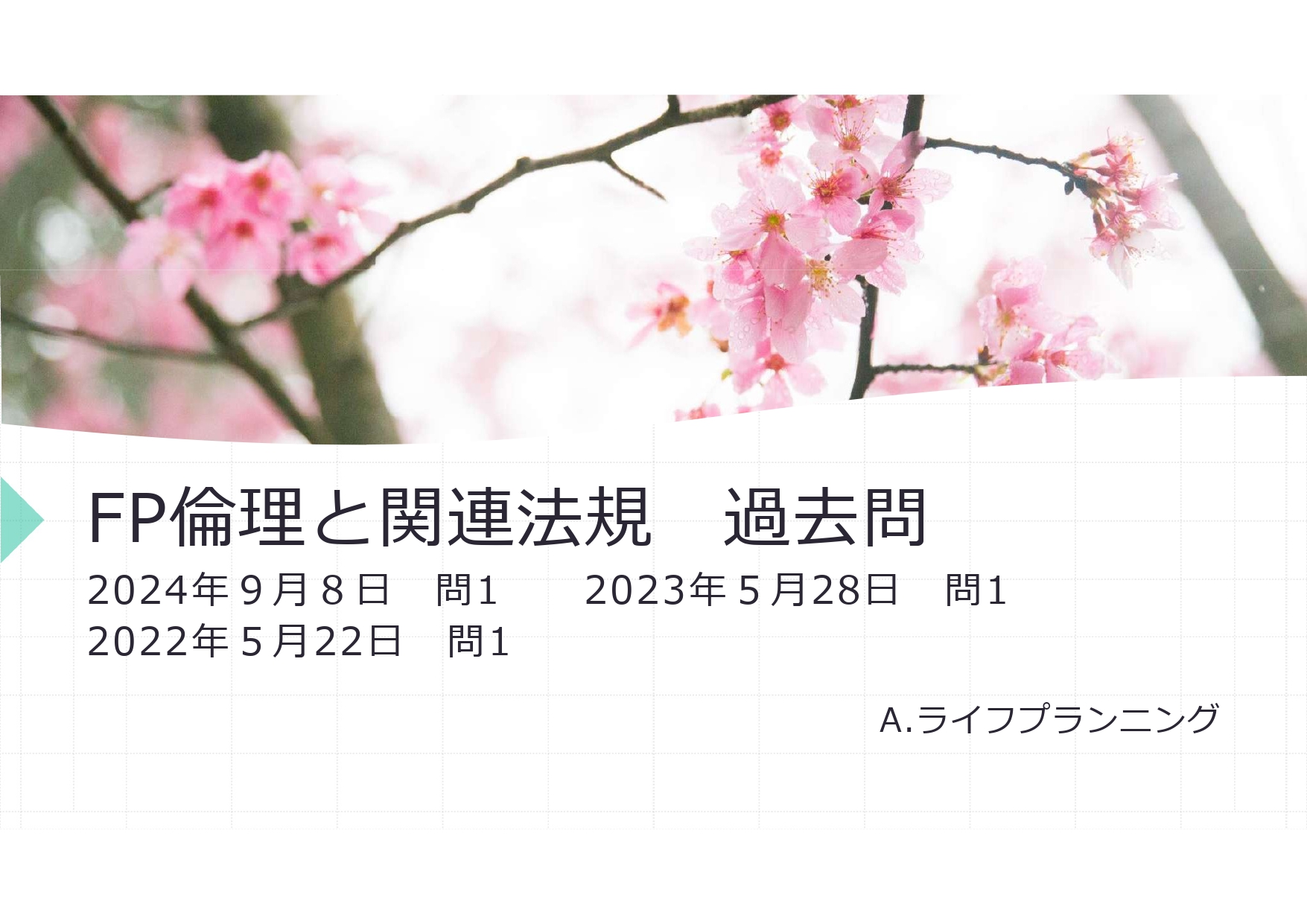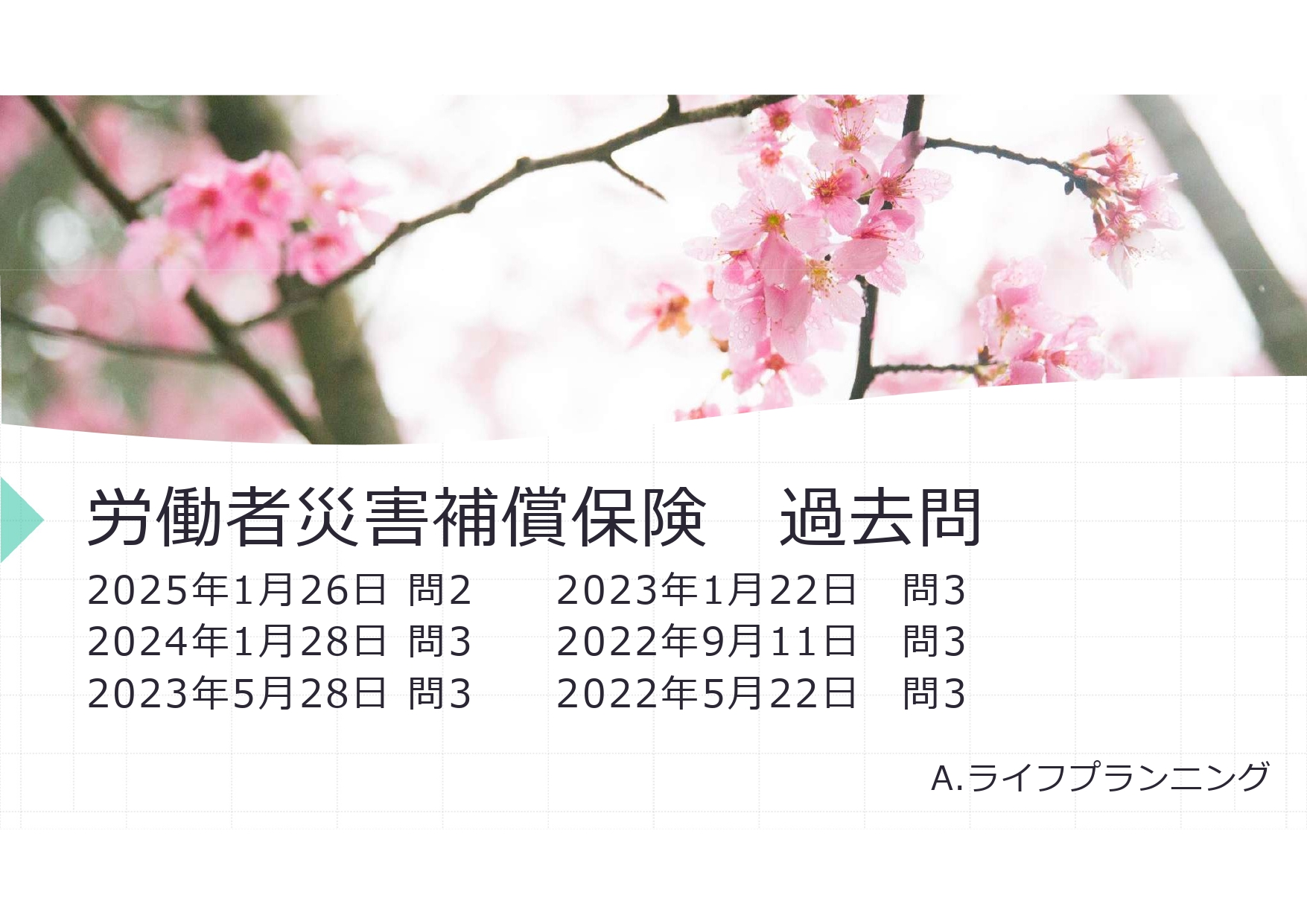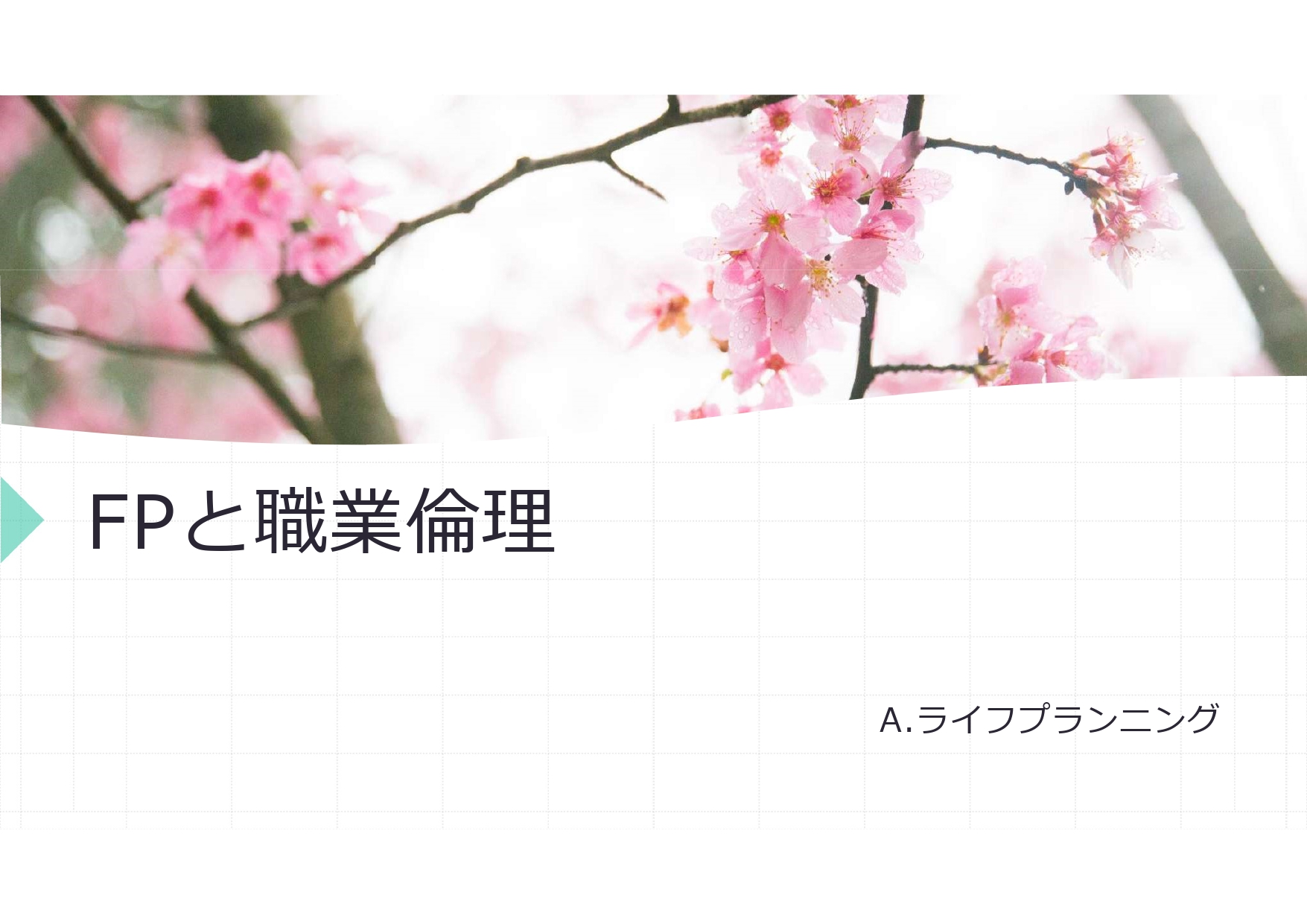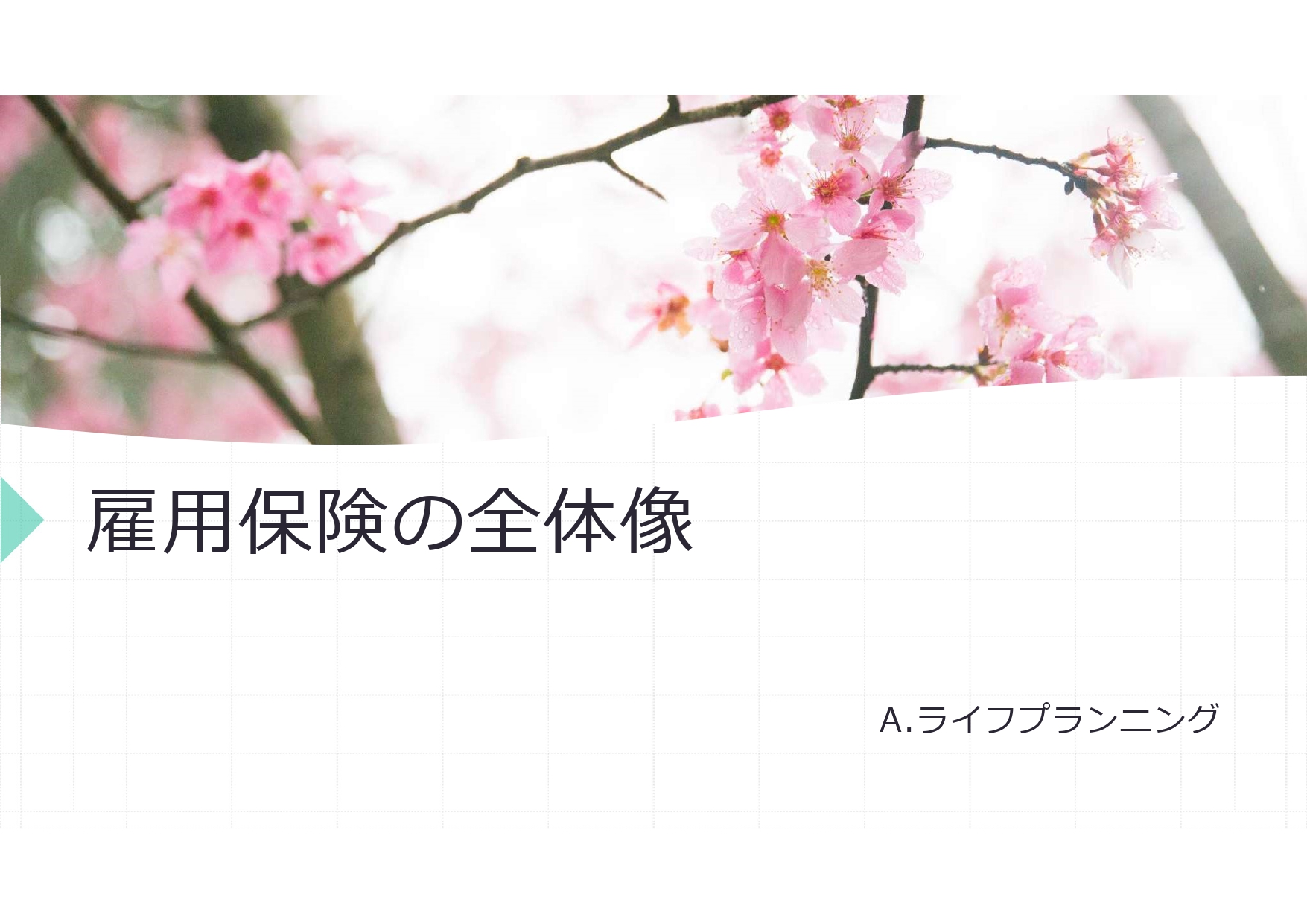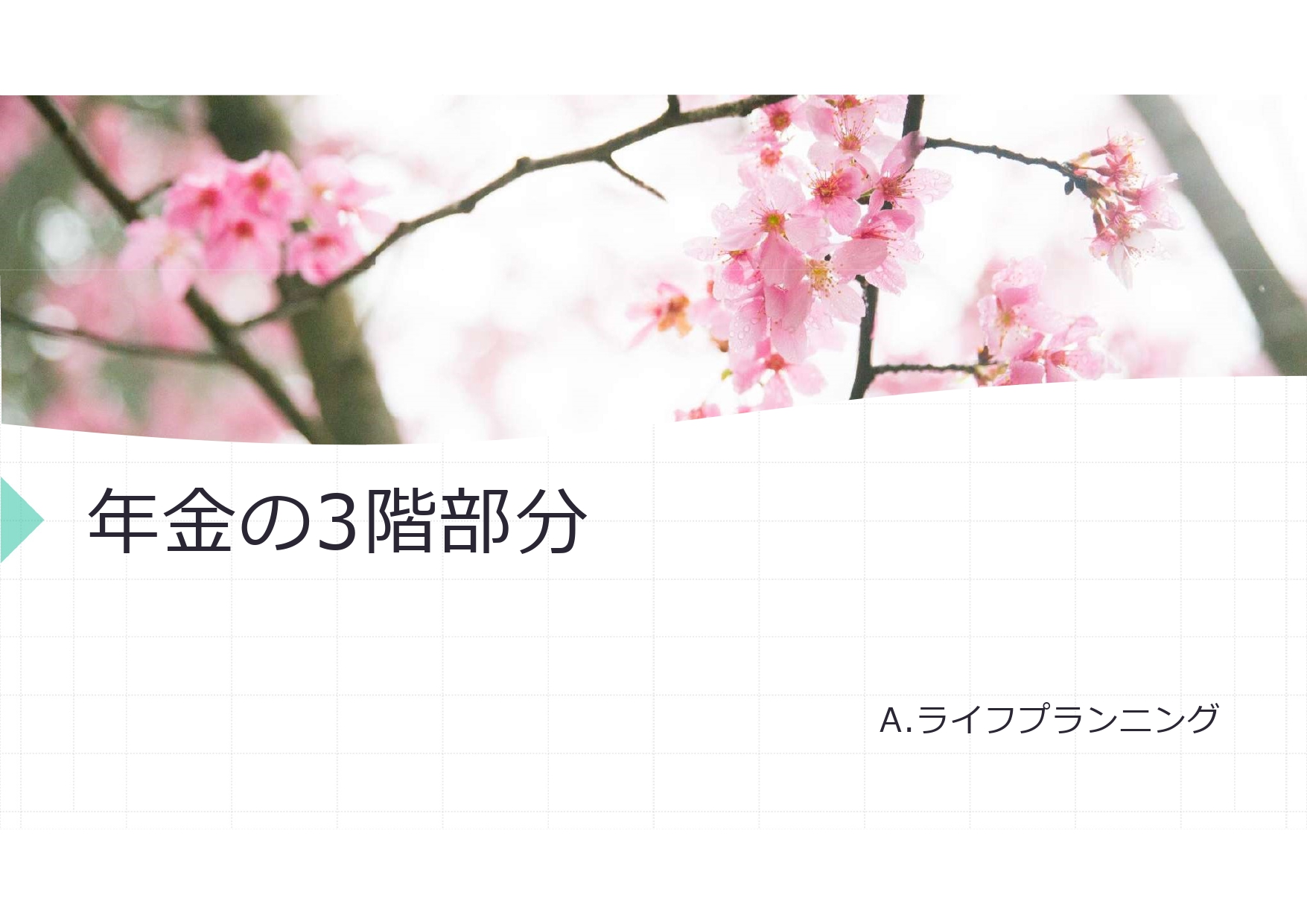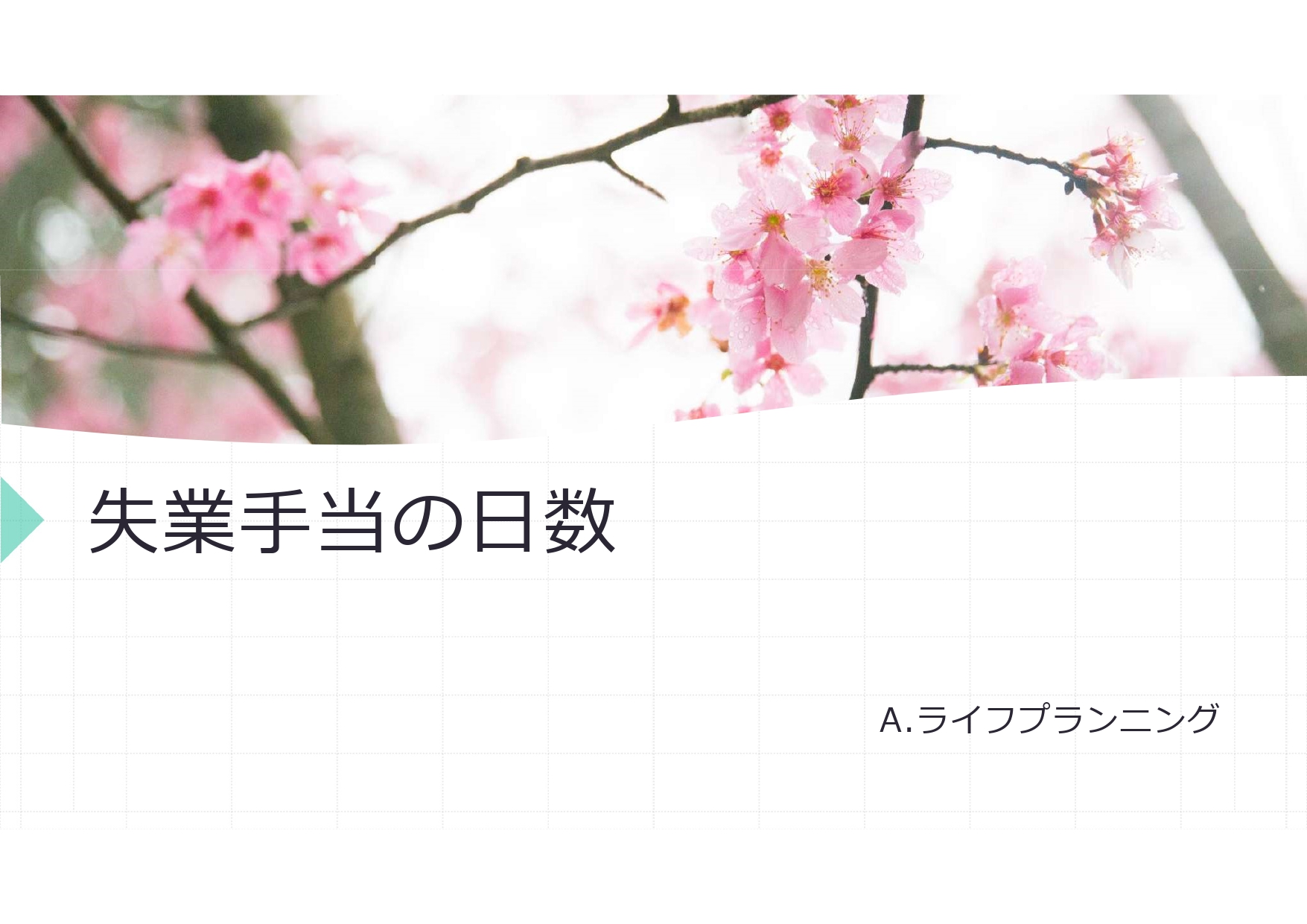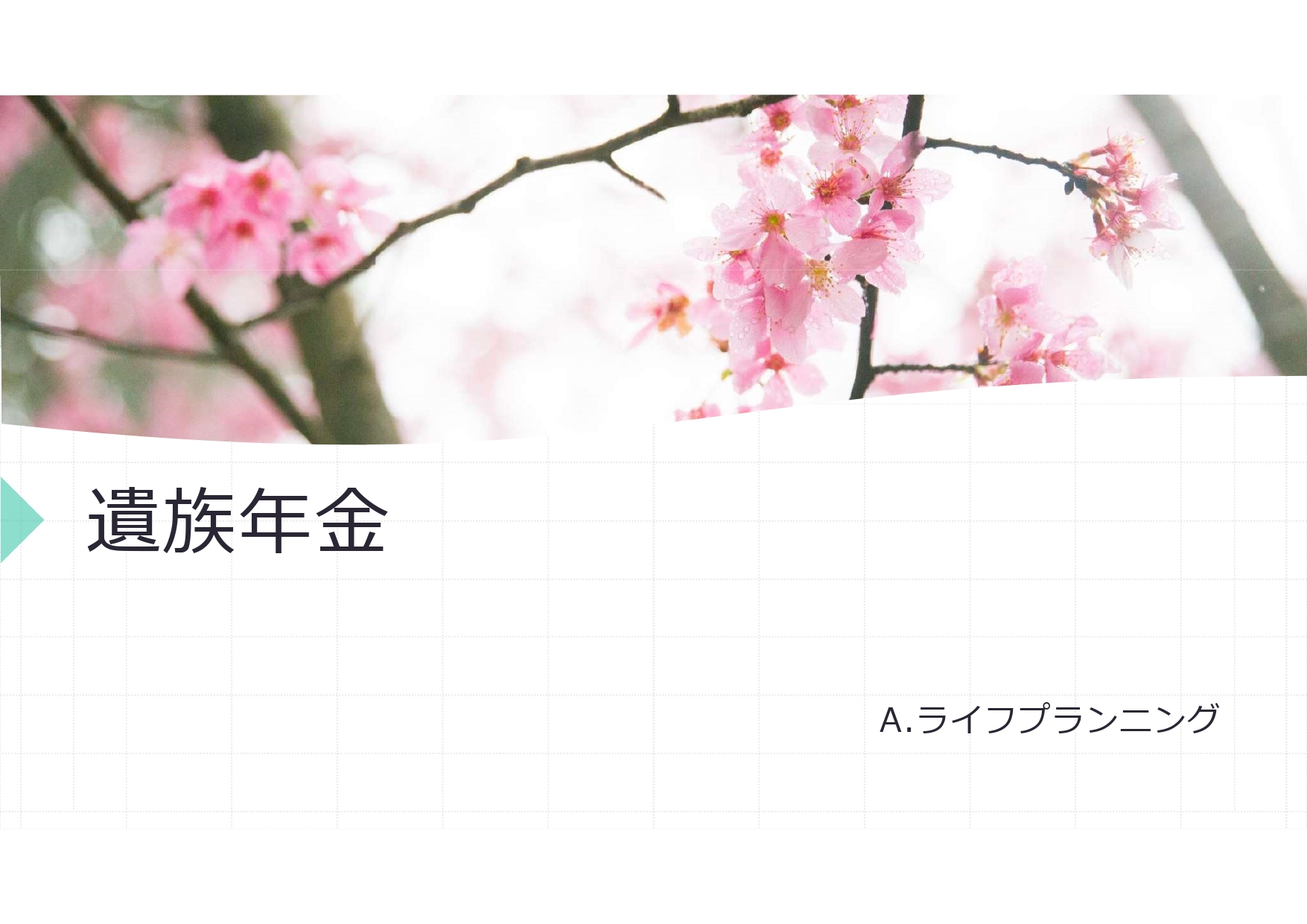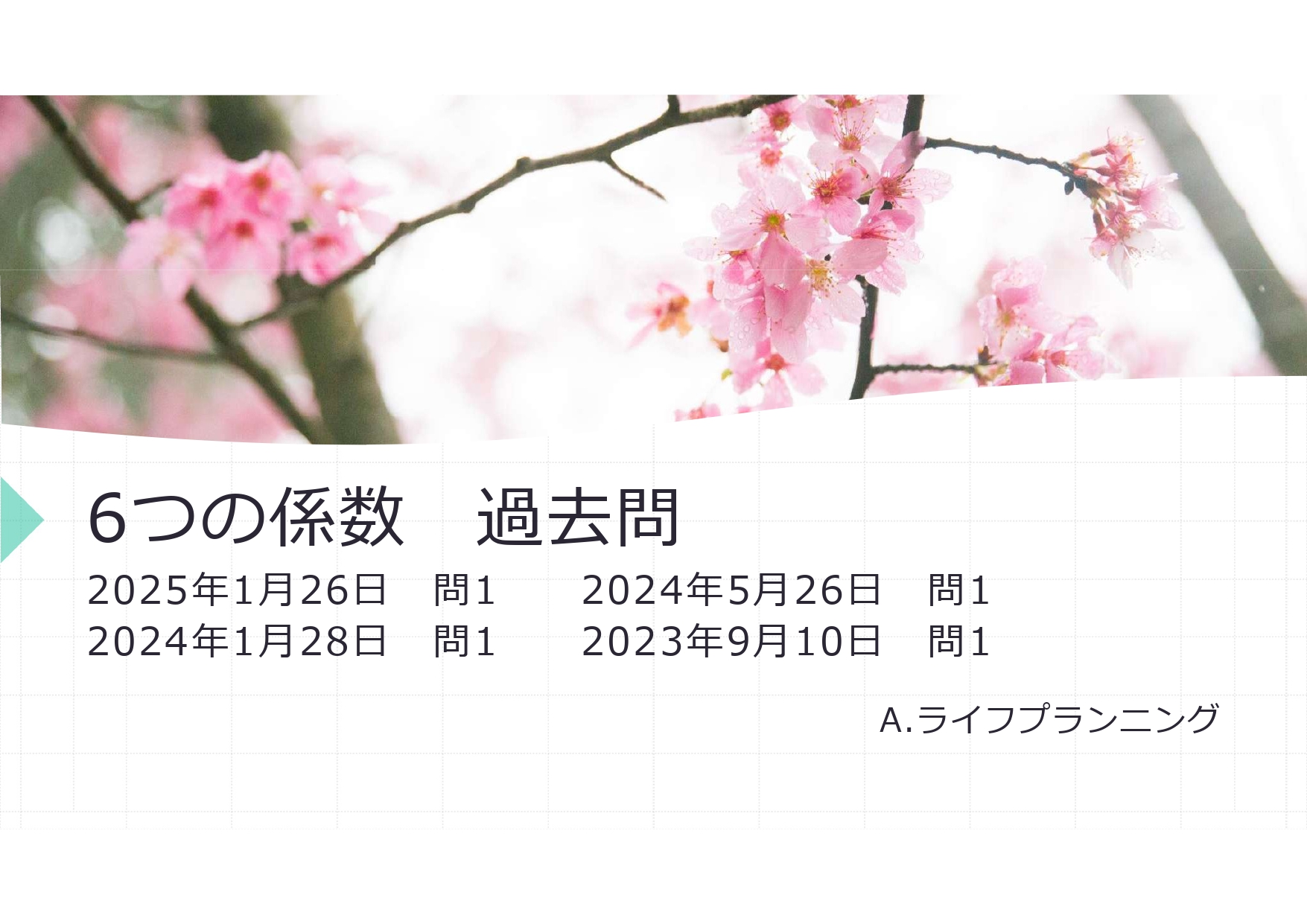2025年1月25日 基礎編 ライフプランニング
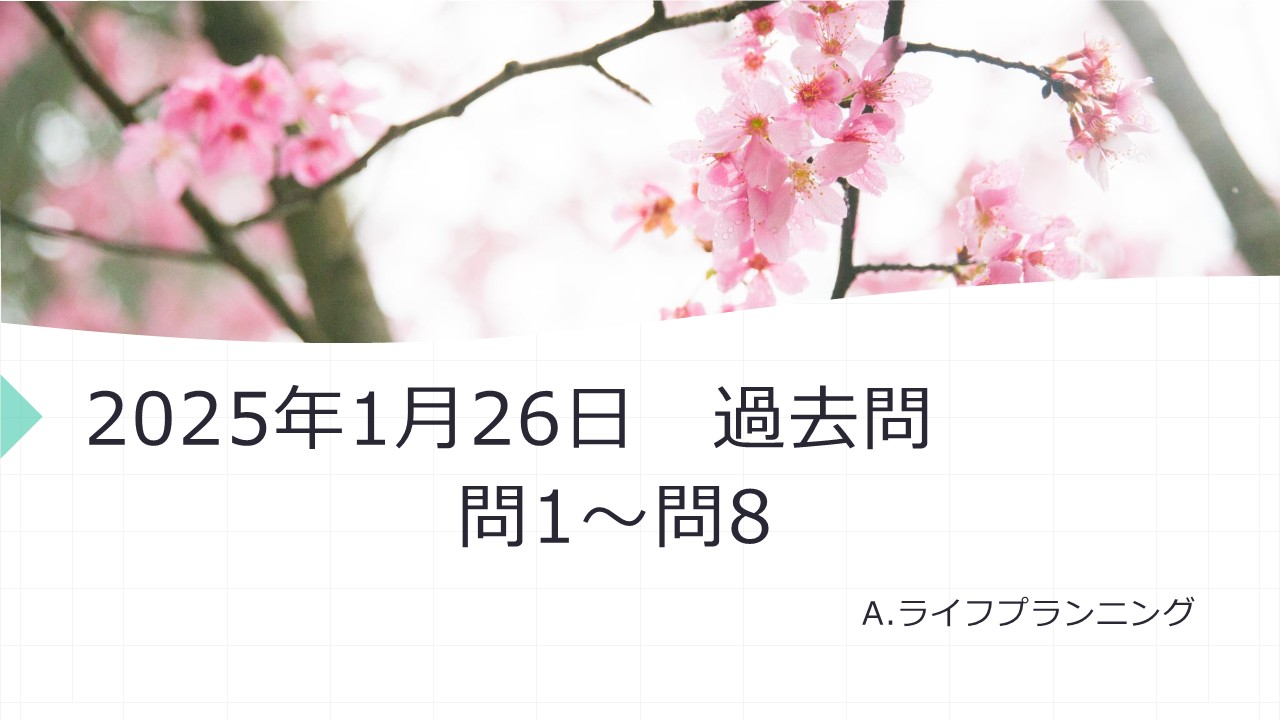
いよいよ9月試験まで10日となりました。
今日から2025年1月26日の基礎編解説を行っていきたいと思います。
このブログを始めたのが昨年の10月21日で、その準備を始めたのが9月8日のFP協会実技試験が終わった時だったので、ほぼ1年が経ちました。
試行錯誤しながら記事を書いているのですが、そこで感じたことは、過去問の解説をすることが勉強になるということです。
来年の1月試験を受ける方には、自分なりの過去問の解説をしてみることをお勧めします。
漠然とわかって、なんとなく解けていた内容も、よく理解しないと他人に説明できません。
私は、これまで説明が下手で、今も改善されていませんが、説明しようと努力することが大切だと思います。
話を基に戻して、2025年1月26日の基礎編解説をライフプランニングから開始します。
出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問1 6つの係数
| 《問1》 Aさん(45歳)は、65歳から15年間にわたって毎年800千円を受け取るために、65歳までの20年間、年金原資を毎年均等に積み立てることを考えている。この場合、45歳から65歳までの20年間の毎年の積立額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、積立期間および取崩期間中の運用利回り(複利)は年2%とし、積立ておよび取崩しは年1回行うものとする。また、下記の係数表を利用して算出し、計算結果は千円未満を切り捨て、手数料や税金等は考慮しないものとする。 |
| 終 価 係 数 | 現 価 係 数 | 年金終価係数 | 減債基金係数 | 年金現価係数 | 資本回収係数 | |||||||
| 10年 | 1.2190 | 0.8203 | 10.9497 | 0.0913 | 8.9826 | 0.1113 | ||||||
| 15年 | 1.3459 | 0.7430 | 17.2934 | 0.0578 | 12.8493 | 0.0778 | ||||||
| 20年 | 1.4859 | 0.6730 | 24.2974 | 0.0412 | 16.3514 | 0.0612 | ||||||
| 1) 383千円 2) 423千円 3) 494千円 4) 569千円 |
正解2

定番の6つの係数の問題だね。2級までと違い、2段階での計算が求められることが多いね。今回もそうだよ。6つの係数は落ち着いて解く必要があるから、私はいつも後回しにして、最後に解いてたよ。

65歳から15年間にわたって毎年800千円を受け取るのに必要な金額は年金原価係数(15年)を使って
800千円×12.8493(15年)=10,279.44千円
45歳から20年間で10,279.44千円を貯めるには減債基金係数を使って
10,279.44千円×0.0412(20年)=423.5千円
千円未満切り捨てだから 423千円が正解だね。
問2 労働者災害補償保険
| 《問2》 労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 業務中に会社の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養補償給付については、一部負担金は徴収されないが、通勤途中に駅の階段で転倒して負傷したことにより労働者が受けた療養給付については、原則として一部負担金が徴収される。 2) 労働者が業務上の傷病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の80%相当額が支給されるが、所定の要件を満たす場合、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が休業補償給付に上乗せして支給される。 3) 業務上の傷病による療養のために休業し、休業補償給付を受けている労働者について、当該傷病が療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合に、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当しないときは、休業補償給付の支給が打ち切られる。 4) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級または2級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、3級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給される。 |
正解1

労災の問題だね。恥ずかしながら人生で2回労災事故を経験してるけど、すべて会社が処理してくれたので、手続きの知識は蓄積していないんだよね。

1)これが正解だね。何度も出題されているから、間違えた人は覚えておくといいよ。
2)数字の問題だね。休業補償給付は60%支給されるよ。休業特別支給金の20%は正しいね。
3)療養の開始後1年6カ月を経過した日において治っていない場合に、当該傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当しないときは、休業補償給付は継続されるよ。
4)障害(補償)給付は1級から14級まであるよ。障害年金の1~3級、障碍者手帳の級数と混じって、よくわからなくなるから注意が必要だね。
問3 雇用保険の育児休業給付
| 《問3》 育児休業および雇用保険の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なのはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 出生時育児休業給付金の支給対象となる産後パパ育休(出生時育児休業)は、原則として、子の出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4回まで分割して取得することができる。 2)産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した期間において、事業主から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額以上の賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金は支給されない。 3) 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を分割せずに取得する場合において、妻の育児休業開始日が夫の育児休業開始日前であるときは、妻はパパ・ママ育休プラス制度を利用することができない。 4) 雇用保険の被保険者である夫婦が同一の子に係る育児休業を取得する場合において、夫がパパ・ママ育休プラス制度を利用するときは、夫は子の出生の日から最長で1年2カ月間、育児休業を取得することができる。 |
正解3

産後パパ育休というのは2022年10月から開始になるってニュースでは知ってるけど、まだ身の回りに取得した人って知らないね。

1)出生の日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、2回まで分割して取得することができるというのが正しいね。
2)支給が67%じゃなく80%だね。67%はよく使用される数字だけど、産後パパ育休は80%だね。
3)これが正解。ややこしいので、妻が育休に入る段階でよく専門家に相談して検討する必要があるね。
4)これも一見正しそうだけど、ちょっとよくわからないね、パパ・ママ育休プラス制度は2人で1年2か月取得できるという制度で、育休は原則1年ということだと思う。
問4 障害基礎年金および障害厚生年金
| 《問4》 障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 傷病に係る障害認定日において20歳未満である者に対する障害基礎年金は、原則として、障害認定日が属する月の翌月から支給される。 2) 障害厚生年金を受給するためには、保険料納付要件を満たし、かつ、傷病に係る初診日および障害認定日において厚生年金保険の被保険者でなければならない。 3) 厚生年金保険の被保険者が事故によりケガをし、障害認定日においては障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態になかったものの、そのケガが悪化して、65歳に達した日以後に障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった場合、障害厚生年金の支給を請求することはできない。 4) 障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に支給される障害厚生年金の額は、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者および18歳到達年度の末日までの間にある子がいる場合、配偶者の加給年金額と子の加算額が加算された額となる。 |
正解3

障害厚生年金は受けているから、多少は知識があるよ。最初は障碍者手帳の1級を持っていれば障害年金がもらえると思ってた素人だったけど、障害年金は受給するには結構、ハードル高いよ。

1)障害年金は20歳以降の需給となるから不適切だね。
2)初診日に厚生年金保険の被保険者である必要はあると思うけど、認定日(1年6か月後)は必要でないと思うよ。障害を負って仕事を辞めていることは現実的にもありえるもんね。
3)これが正しいね、障害厚生年金の事後重症は65歳までに手続きしないといけないんだね。
4)障害基礎年金と厚生年金のややこしいところだね。子の加算は基礎年金に加給年金は厚生年金につくんだよね。
2024年1月FP1級学科試験の応用編を解いておくことをお勧めするよ。
問5 公的年金の遺族給付
| 《問5》 公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 国民年金の第1号被保険者である夫(45歳)が死亡し、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、かつ、その夫によって生計を維持されていた妻(49歳)がいる場合、妻は60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達した日の属する月まで寡婦年金を受給することができる。 2) 国民年金の第1号被保険者である夫(48歳)の死亡により妻(45歳)が取得した遺族基礎年金の受給権については、妻が夫の父親(75歳)と養子縁組をした場合であっても消滅しない。 3) 厚生年金保険の被保険者である妻(45歳)が死亡し、その妻によって生計を維持されていた遺族が夫(42歳)と子(15歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。 4) 厚生年金保険の被保険者である者(40歳)が死亡し、その者によって生計を維持されていた遺族が父親(61歳)と母親(62歳)の2人である場合、遺族厚生年金は、受給権者が1人である場合に算定される額を2で除して得た額が父親と母親にそれぞれ支給される。 |
正解3

遺族年金は見直しが最近、ニュースになったから解けた方が多かったんじゃないだろうか。

1)これは正しいね。
2)これはちょっと難しかったかも、遺族基礎年金は再婚や養子になったときは消滅するけど、直系尊属の養子になったときは例外なんだね。
3)遺族が夫の場合は55歳以上じゃないと遺族年金は受給できないんだね。
4)これも正しいよ。年金を受給する前に子に生計を維持されてることってありえるからね。
問6 中小企業退職金共済制度
| 《問6》 中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 中退共の掛金月額は、事業主が被共済者(従業員)ごとに選択することができ、その上限額は被共済者(従業員)1人につき7万円とされている。 2) 事業主が中退共への新規加入の申込みに際して、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間の月数を掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をする場合、通算することができる過去勤務期間の月数は120月が限度となる。 3) 中退共に新規で加入する事業主は、加入月から1年間、掛金月額の2分の1相当額について国の助成を受けることができる。 4) 被共済者(従業員)が加入後1年未満で退職し、掛金納付月数が12月に満たない場合、当該被共済者(従業員)に退職金は支給されず、掛金の全額が事業主に返還される。 |
正解2

中退共は自社で退職金制度を設けるのが難しい中小企業が加入する仕組みだね。

1)掛け金は被共済者ごとに5,000円から3万円までだね。小規模企業共済の掛金が7万円だから混同しないように気をつけてね。
2)これが正しい選択肢だね。過去勤務期間通算制度の説明だね。
3)ひっかかりそうだけど4か月目から1年間が正しいね。
4)1年未満の退職者については事業者に返還されないよ。
問7 公的年金等に係る所得税の取扱い
| 《問7》 公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、納税者は居住者であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 2024年中に2年分の国民年金の保険料を前納した場合、2024年分以後の各年分の保険料に相当する金額が各年分の社会保険料控除の対象となり、前納した保険料の全額を2024年分の社会保険料控除の対象とすることはできない。 2) 69歳到達時に老齢基礎年金の請求手続をして、65歳からの4年分の年金を一括で受け取った場合、当該年金は、受け取った年分の一時所得として所得税の課税対象となる。 3)国民年金基金において、老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となり、加入員が死亡し、その遺族が受け取る遺族一時金は非課税となる。 4) 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)を受給権者の子が受け取った場合、子が受け取った当該未支給年金は、相続税の課税対象となる。 |
正解3

公的年金の所得税って、天引きされるからあまり意識しないんだよね。

1)前納制度を利用して2年分収めた場合、収めた年の社会保険料控除とすることはできるよ。
2)年金を受け取った場合は雑所得だね。一括して受け取っても、本来受け取るべきだった年の雑所得になるね。
3)国民年金基金の遺族一時金は非課税だから正しいね。遺族年金も非課税だね。
4)被相続人が受けるはずだった未支給年金を遺族が受け取った場合、受け取った方の一時所得になるね。相続税ではないよ。
問8 教育資金
| 《問8》 教育資金の準備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資を受ける際に、連帯保証人による保証の代わりに教育資金融資保証基金による保証を選択した場合、融資金から保証料が一括して差し引かれる。 2) 日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の融資金利は、父子家庭や母子家庭、交通遺児家庭等を対象として優遇措置が講じられている。 3) 日本学生支援機構の第二種奨学金は、有利子の奨学金であり、利率の算定方法として利率固定方式と利率見直し方式のいずれかを選択する。 4) 日本学生支援機構の授業料後払い制度は、大学・短期大学・専修学校(専門課程)に在学する学生の授業料について、在学中は支払不要とし、学生が卒業後の所得に応じて後払いする仕組みである。 |
正解4

教育ローンは子育てをされている方には強い味方だからね。

1)これは設問の通りだね。教育資金融資保証基金を利用した場合、保証料が差し引かれるよ。
2)これも設問の通りだね。これ以外にも世帯年収200万円以下というのも対象だよ。
3)これは正しいよ。よっぽど注意しないと気付かないけどね。
4)この制度は修士(大学院)が利用できる制度だから誤りだよ。気づきにくいし難易度が高い問題かもね。