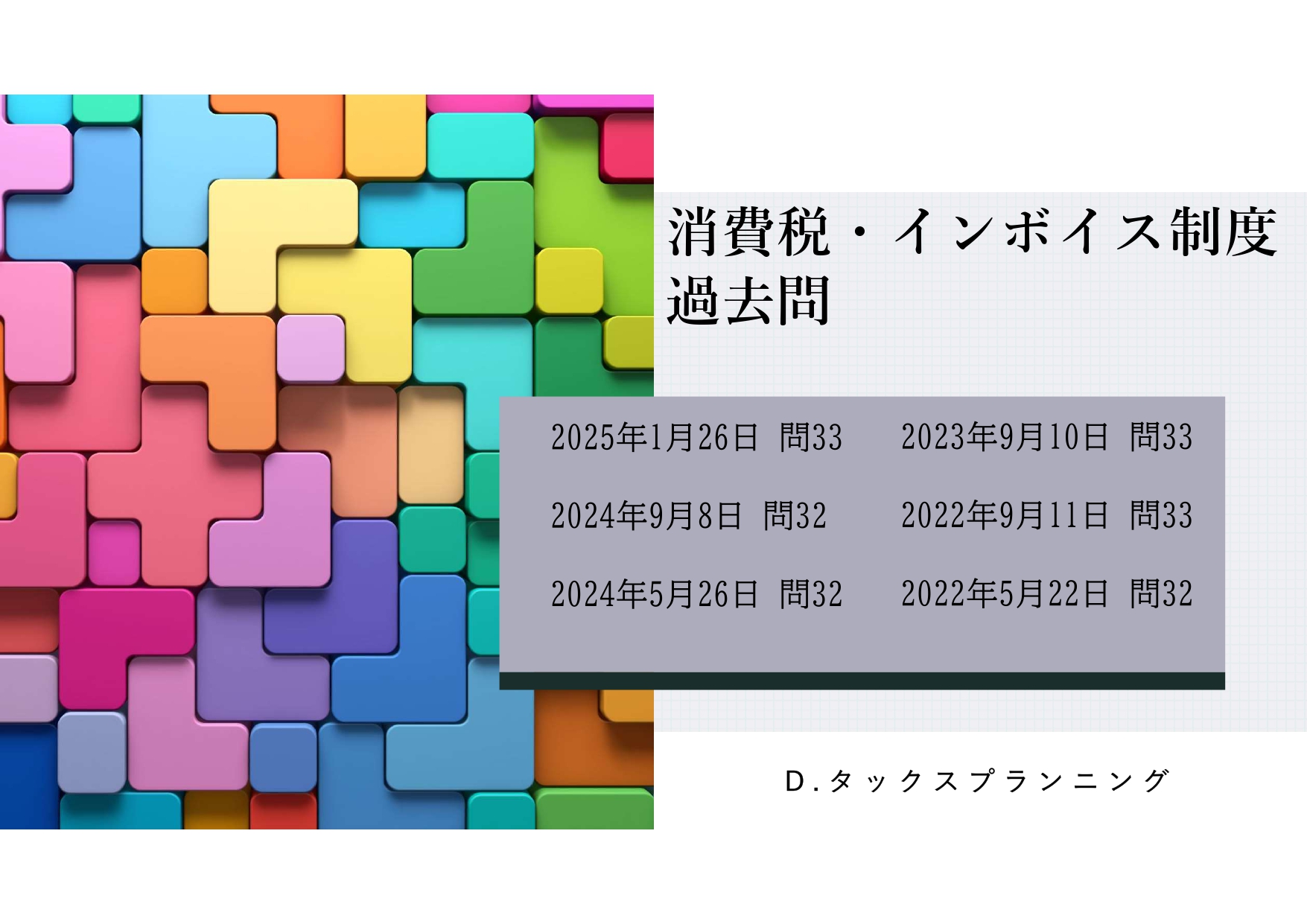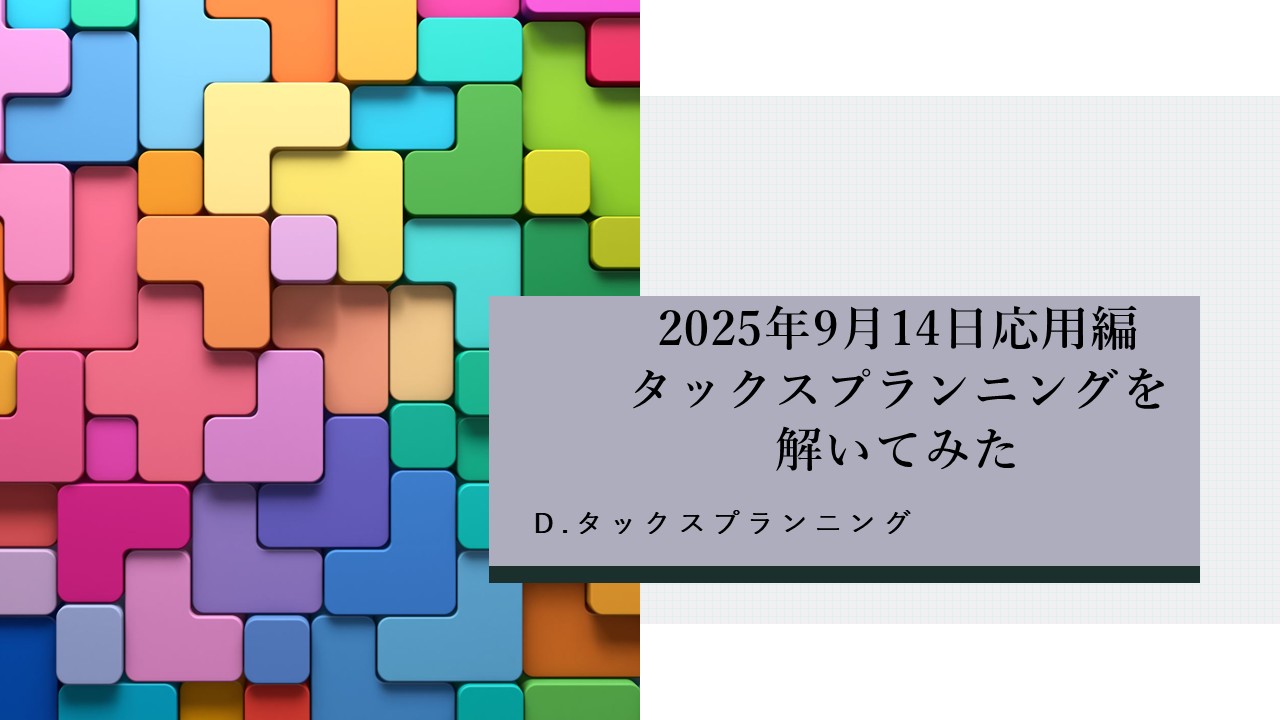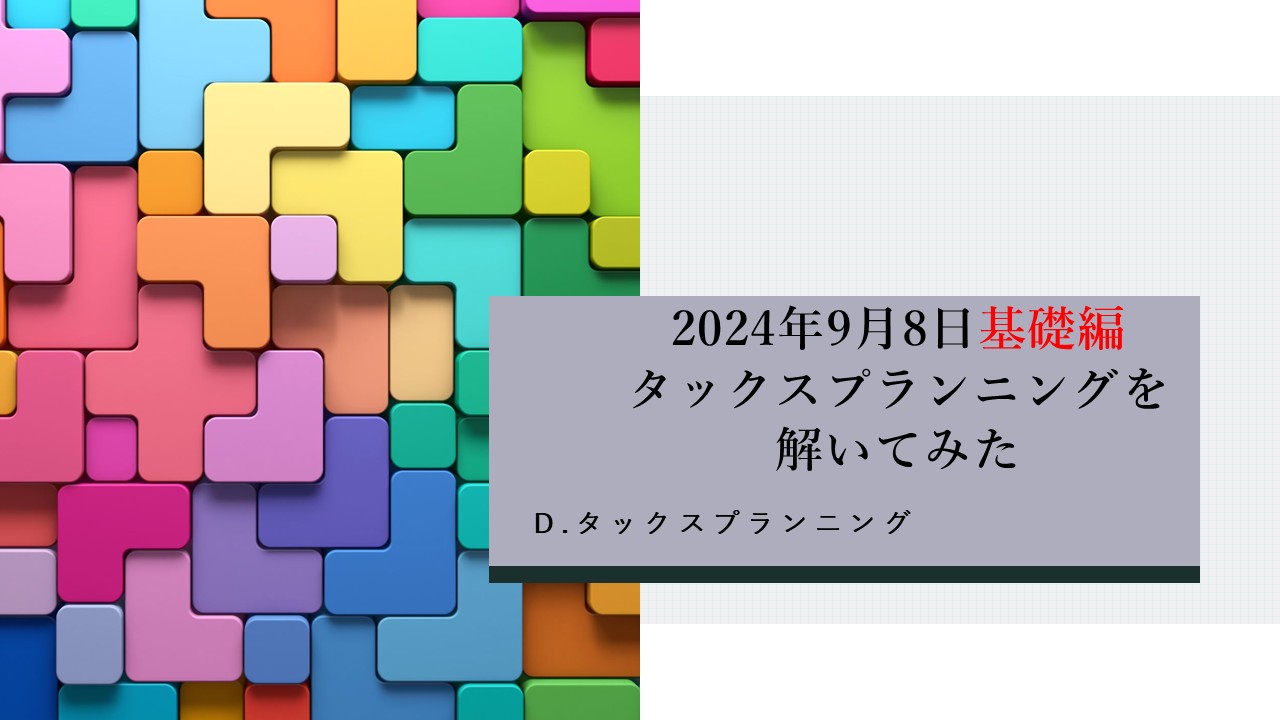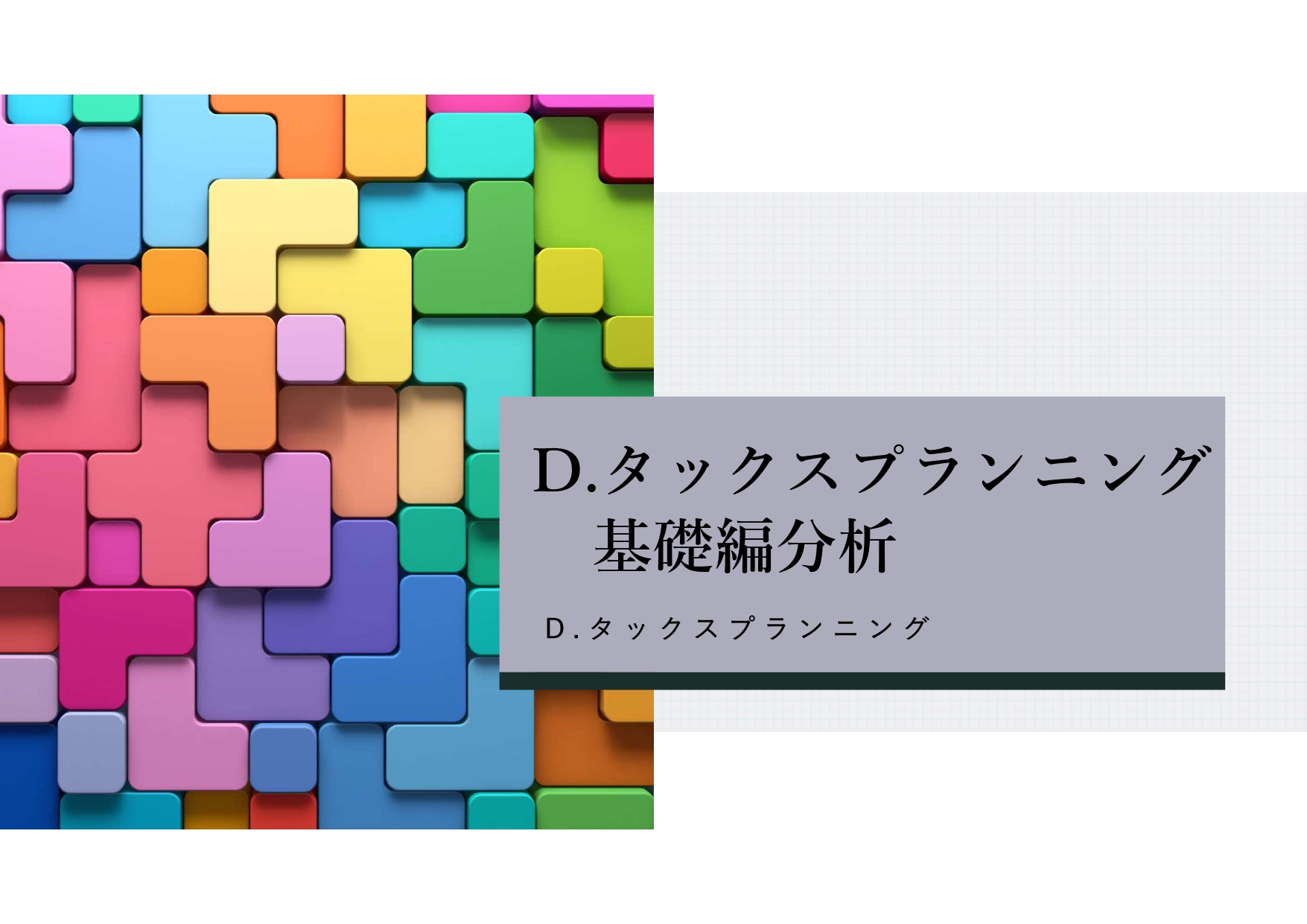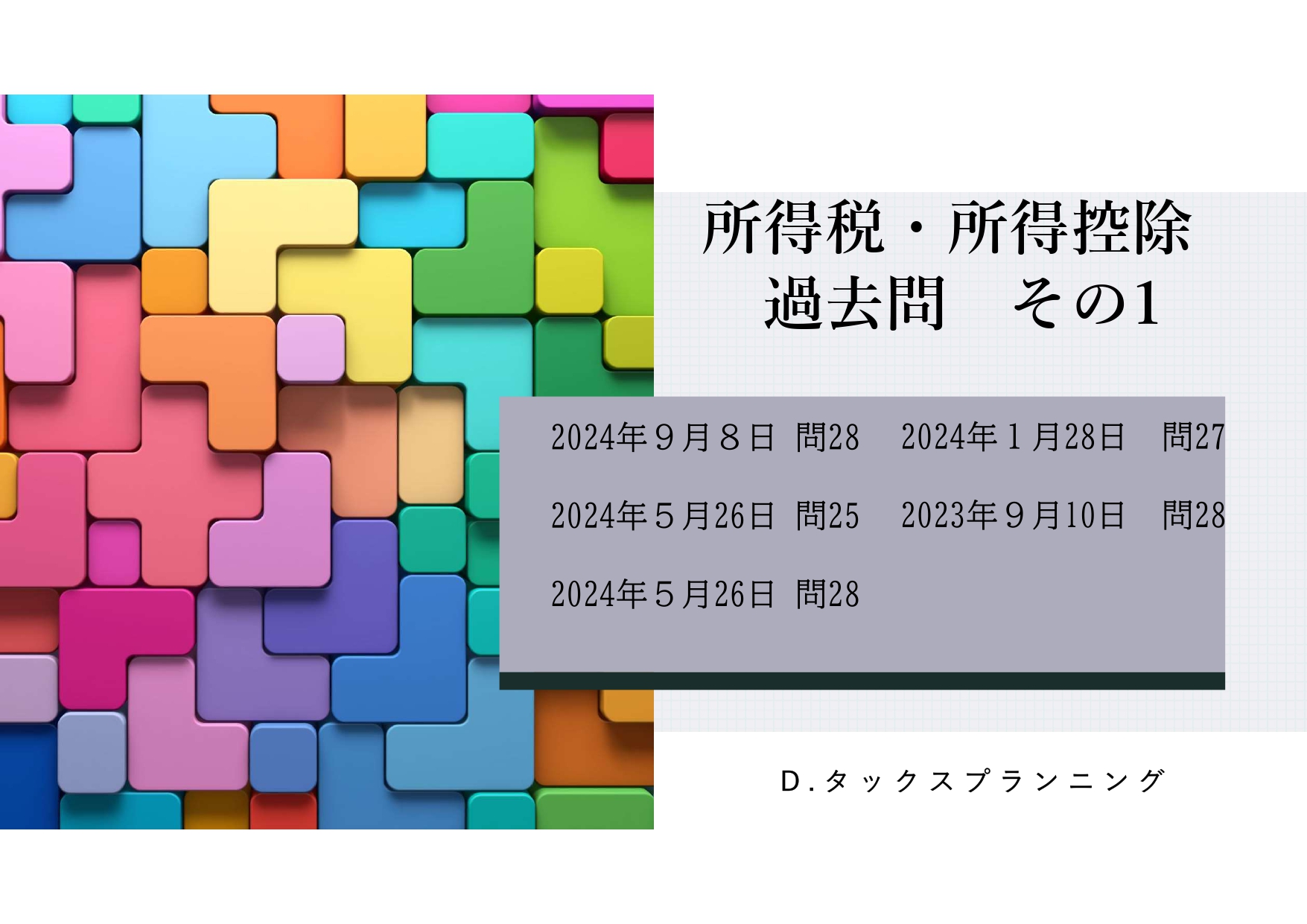2025年1月25日 基礎編 タックスプランニング
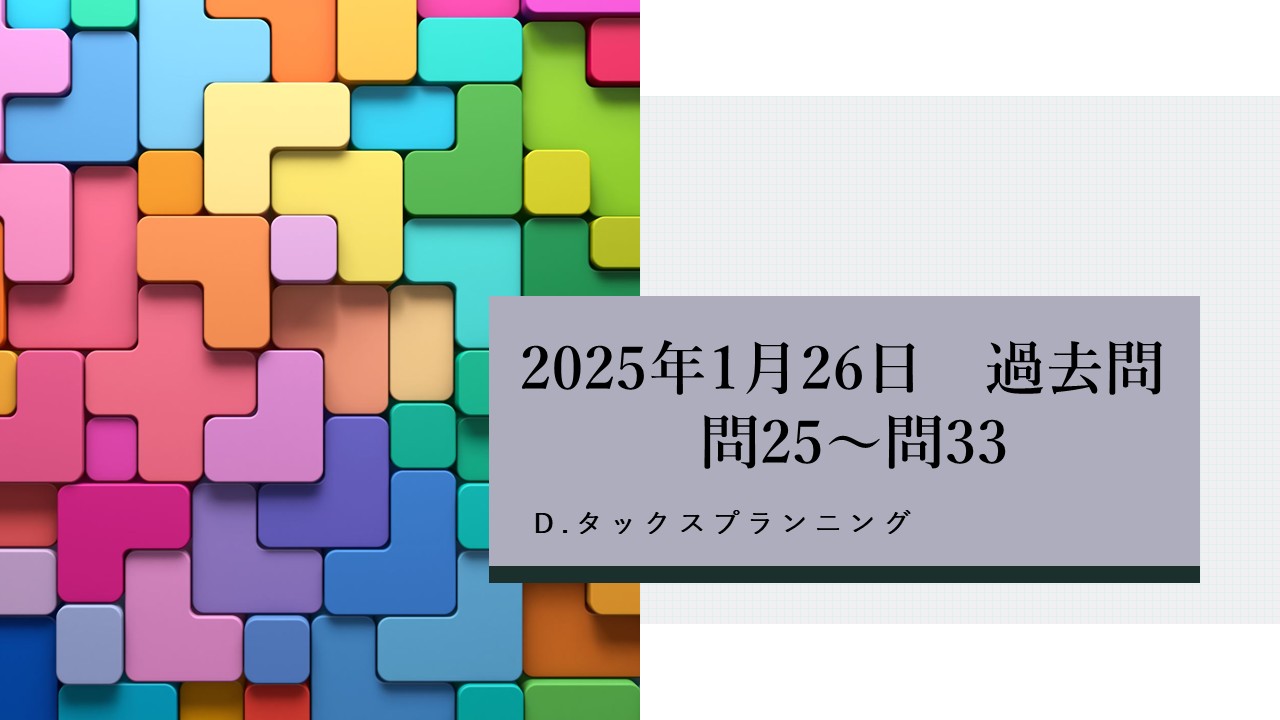
FP試験は税理士資格の二軍だと言う方がいらっしゃいます。私もそう思っています。
FP試験は6科目あるのですが、すべて税金とかかわる部分があり、勉強はタックスから始めるのがお勧めだという方が多く、私もそう思います。
税金のことは、他の科目を勉強している際にも必ず、登場して、振り返って改めて勉強しなおすことになります。
受験生には公務員や金融機関勤務、ずまり税理士事務所勤務の方もおられると思いますので、私の稚拙な説明に間違いがあれば、ご指摘お願いします。
では、解説を始めます。今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問25 事業所得
| 《問25》 居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 青色申告者である個人事業主が、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出していない場合、棚卸資産の評価方法は低価法となる。 2) 青色申告者である個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業の用に供している場合、当該事業主が配偶者に支払った家賃は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。 3) 青色申告者ではない個人事業主と生計を一にする子が、当該事業主が営む事業に専ら従事している場合、「86万円」と「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。 4) 青色申告者である個人事業主が青色事業専従者に支払った退職金は、一般の従業員の退職金について定めた退職給与規程に従って算定されたものであっても、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない。 |
正解4

個人事業を始める方で、最初から顧問税理士をつけないって場合はあると思われ、その時にFPが相談を受けるということはありえるよね。

1)「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を提出していない場合、棚卸資産の評価方法は最終仕入れ原価法だね。
届出書を提出した場合は、先入先出法、総平均法、低価法など有利な方法を選択できるよ。
2)これは不適切だね。配偶者や親族に払う家賃は経費にならないよ。
3)配偶者は86万円だけど、配偶者以外は50万円だから間違いだね。
4)これが正しいね。個人事業主は退職金は必要経費とはみなされないんだね。
問26 退職所得
| 《問26》 居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 会社員のAさん(40歳)が、病気による休職期間後に退職して退職金を受け取った場合に、当該退職金の額が勤続期間からその休職期間を控除した期間に基づき算定されているときは、退職所得控除額の計算上、勤続期間から当該休職期間を控除して勤続年数を計算する。 2) 会社員のBさん(52歳)が、障害者になったことに直接基因して勤続29年3カ月で退職して退職金2,000万円を受け取った場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,600万円となる。 3) 会社員のCさん(60歳)が、確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った場合、退職所得の金額の計算上、受け取った老齢給付金の全額が収入金額となる。 4) 会社役員のDさん(64歳)が、上場企業を定年退職した後に入社した関連会社で常勤監査役として勤務し、勤続4年8カ月で退職して退職金を受け取った場合、当該退職金は特定役員退職手当等に該当する。 |
正解1

退職金の税制については現在も議論されてるけど、労働者にとって負担は増える形になりそうだよね。

1)これが間違いだね、勤続年数という時には休職期間中も含まれることを考えたらわかるよね。
2)29年3カ月だと30年として、800万円+(30年―20万円)×70万円=1,500万円、そして障害者となったことが理由の場合100万円が加算されるので1,600万円で正しいね。
3)これは正しいね。掛金が10年以上という条件もあるけど、この問題では読み取れないし、適切だね。
4)特定役員退職手当等とは5年以下の退職者に対するもので、通常の退職金とは違い2分の1する必要はないよ。
問27 総所得金額の計算問題
| 《問27》 居住者であるAさんの2024年分の各種所得の金額が下記のとおりであった場合の総所得金額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得金額は、その所得金額が損失の金額であることを意味している。 |
| 所得金額 | 備 考 | |||
| 不動産所得 | ▲100万円 | ・不動産賃貸業を営むことによる所得 ・不動産所得の金額の計算上の必要経費に当該所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子20万円を含む金額 | ||
| 事 業 所 得 | 300万円 | ・小売業を営むことによる所得 ・青色申告特別控除後の金額 | ||
| 譲 渡 所 得 | ▲20万円 | ・金地金の譲渡により生じた損失の金額 | ||
| 雑 所 得 | ▲20万円 | ・暗号資産取引で生じた損失の金額 | ||
| 1) 160万円 2) 180万円 3) 200万円 4) 220万円 |
正解4

この問題は定番だけど、安直すぎて間違える時と、深く考えすぎて間違うことがあるんだよね。今回はストレートに考えていいパターンだったね。

不動産所得 ▲100万円―▲20万円=▲80万円
事業所得300万円
300万円+▲80万円=220万円
金地金と暗号資産は損益通算の対象外だね。
問28 住宅借入金等特別控除
| 《問28》 2024年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 取得した住宅が認定長期優良住宅に該当する場合、住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で15年間である。 2) 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋は、専ら居住の用に供する家屋に限られ、店舗併用住宅は対象とならない 3) 取得した住宅の床面積が70㎡である場合、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。 4) 住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額を、翌年分の所得税額から控除することができる。 |
正解3

住宅借入金の問題もよく出るし、まだ変わり続けるだろうから、過去問を解くときには気をつけないといけないよね。

1)平成31年に消費税が10%に引き上げられた時に最長13年になったんだよね。15年じゃないね。
2)店舗併用住宅であっても2分の1以上が居住部分であれば対象です。
3)これが適切だね。
4)控除しきれない分がある場合は、翌年の住民税が控除されるね。実際に経験がある方は強いかもね。
問28 住宅借入金等特別控除
| 《問28》 2024年中に新築住宅を取得し、同年中に入居した場合における住宅借入金等特別控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 法人が完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)に係る配当金を受け取った場合、その配当金は益金不算入の対象となる。 2) 法人が加入する生命保険の契約者配当金を受け取った場合、その契約者配当金は益 金不算入の対象とならない。 3) 法人が上場株式をその配当の支払に係る基準日の3カ月前に取得して配当金を受け取り、その基準日以後3カ月以内に譲渡した場合、当該株式は短期保有株式等に該当し、その配当金は益金不算入の対象とならない。 4) 法人がJ-REIT(上場不動産投資信託)の分配金を受け取った場合、その分配金は益金不算入の対象とならない。 |
正解3

配当金の問題は、応用編の別表四で考えさせられるけど、非支配目的株式等の20%が頭にこびりついてるからね。

1)完全子法人は全額益金不算入だね。
2)生命保険の契約者配当金は名前はまぎらわしいけど、別物で全額益金参入できるよ。
3)3カ月保有しているので、短期保有ではないので、これが間違っているね。
4)J-REITは正直わからなかったんだけど、3)が不適切だから、消去できたね。
問30 交際費等
| 《問30》 法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 食品製造業者のA社が、株主総会に出席した株主全員に対し、自社の新商品である サプリメントの試供品を提供した場合、その提供に要した費用は交際費等に該当する。 2) 卸売業者のB社が、災害を受けた得意先等の取引先に対し、被災前の取引関係の維持や回復を目的として災害発生後相当の期間内に災害見舞金を支出した場合、その支出に要した費用は交際費等に該当しない。 3) 不動産業者のC社が、本社社屋の新築記念として行った式典の開催費用として300万円を支出する一方、出席した取引先から100万円の祝い金を受け取った場合、式典の開催費用から祝い金の金額を控除した200万円のみが交際費等に該当する。 4) 建設業者のD社が、同業者団体主催の飲食を伴う懇親会(参加者数は不明)への社員2人の参加費用として3万円を支払った場合、その支払った費用のうち、1人当たり1万円に相当する部分の金額を除く1万円のみが交際費等に該当する。 |
正解3

2024年4月1日から、飲食費の損金算入の範囲が1万円になったから、5,000円で覚えてた受験生は注意が必要だね。

1)試供品は交際費じゃなく、あくまで広告宣伝費だね。
2)災害見舞金は交際費にあたらないから、これが正解だね。
3)式典の開催費用から祝い金の金額を差し引けるというルールはないね。祝い金は別途収益に計上されるね。
4)一人当たり1万5,000円なので交際費になるね。詳しいことは税理士さんと事前に相談することをお勧めするよ。
問31 資産の評価損
| 《問31》 法人税における資産の評価損に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人は内国法人(普通法人)であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 卸売業者のA社が有する棚卸資産について、仕入先であるメーカーの過剰生産により、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。 2) 衣料品販売業者のB社が有する棚卸資産のうち、季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであり、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。 3) 不動産業者のC社が有する完全支配関係のある法人の株式(完全子法人株式等)について、その発行法人であるC社の子法人が財務状態の悪化に伴い解散し、清算中となったことにより、当該株式の価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。 4) 建設業者のD社が有する固定資産について、過度の使用または修理の不十分によって著しく損耗していることにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなった場合、原則として、損金経理により帳簿価額を減額し、評価損を損金の額に算入することができる。 |
正解2

評価損が認められるのはどんな時か理解しておく必要があるね。天災によるものというのはわかりやすいけど、著しい陳腐化というのは判断が難しいかもね。

1)仕入先の過剰生産は評価損の理由にはならないね。
2)季節商品で売れ残ったものは評価損の対象だよ。これが正解。
3)清算中である場合は評価損の対象外だね。
4)過度の使用または修理の不十分では評価損できないね。問題文の書き方からなんとなく選んでも、FP試験はだいたい間違いないね。
問32 法人住民税および法人事業税
正解2

法人事業税は資本金1億円以下の場合、赤字だとかからないけど、基本的に法人経営しようと思ったら納税をしっかりするつもりでいることが必要だね。

1)これは、その通りだね。
2)法人住民税は、賦課課税方式ではないね。法人税の申告書を見ないと、どれだけ儲かっているのかわからないもんね。これが不適切だね。
3)これは正しいね。事業税は経費算入できることがひとつの特徴だね。
4)これも適切だね、複数の都道府県にまたがって事業を行っている法人はその都道府県ごとに申告が必要だね。
問33 消費税
| 《問33》 消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 課税売上割合は、原則として、課税事業者が課税期間中に国内において行った資産の譲渡等の対価の額の合計額に占める課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の割合であるが、課税事業者の選択により、課税売上割合の計算を事業所単位または事業部単位で行うことができる。 2) 簡易課税制度の適用を受けない場合、課税期間における課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上のときは、原則として、課税売上に係る消費税額から個別対応方式または一括比例配分方式によって計算した仕入控除税額を控除する。 3) 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日から2カ月以内に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 4) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、そのうち1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上に対して適用することができる。 |
正解4

消費税は選挙の際に争点になることも多く、だれもが関心をもっているテーマだから質問を受けることも多いかもね。また、インボイス制度も話題になりやすいから最新ニュースに注目しておくことも必要だね。

1)課税売上割合は行っている事業によって決まるから事業所や事業部で決められるものではないね。
2)これも日本語が難しくて、意味を勘違いしやすいね。この条件に当てはまるのは課税売上割合が95%未満の場合だね。
3)「消費税簡易課税制度選択届出書」は事業年度開始前までに提出が必要だね。
4)これが正しいね。簡易課税制度の75%は暗記必須だね。