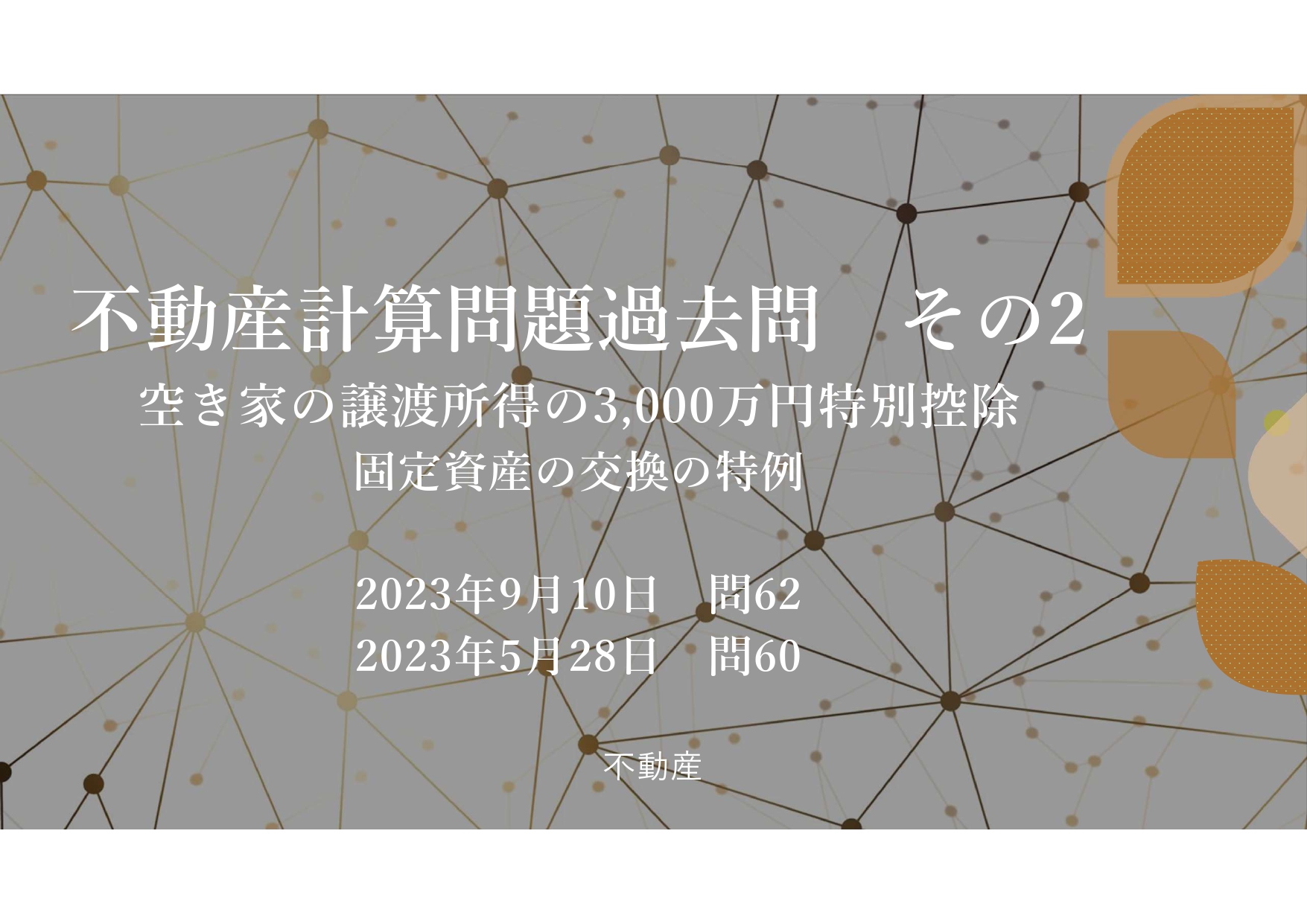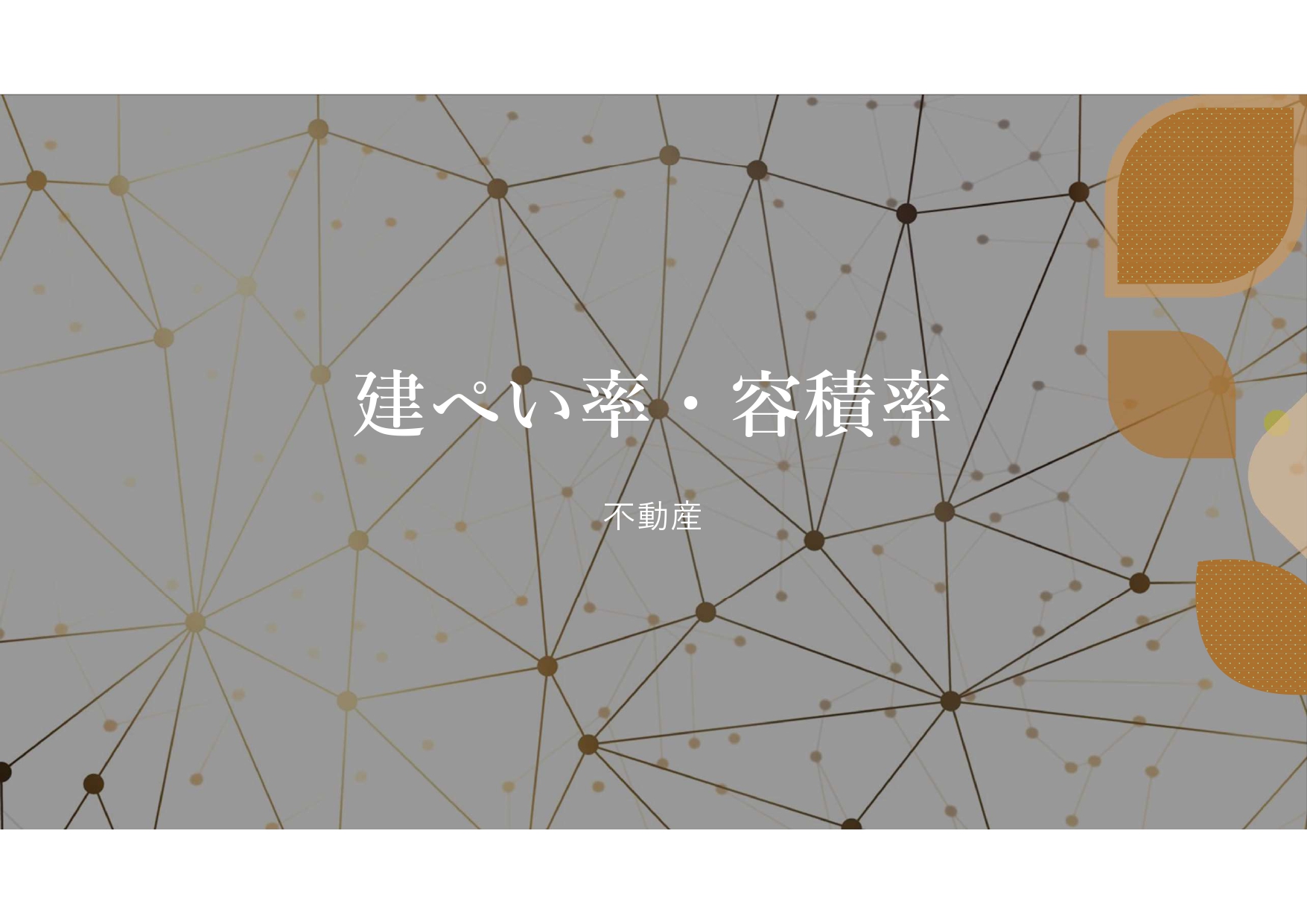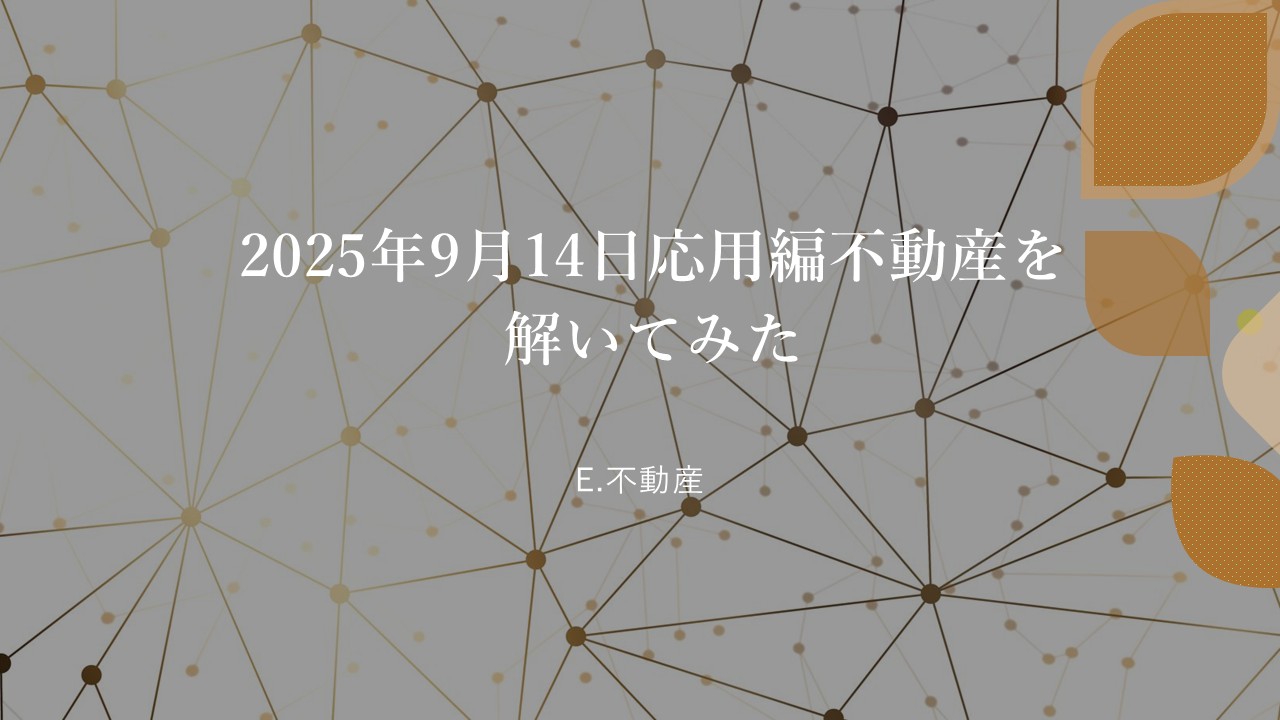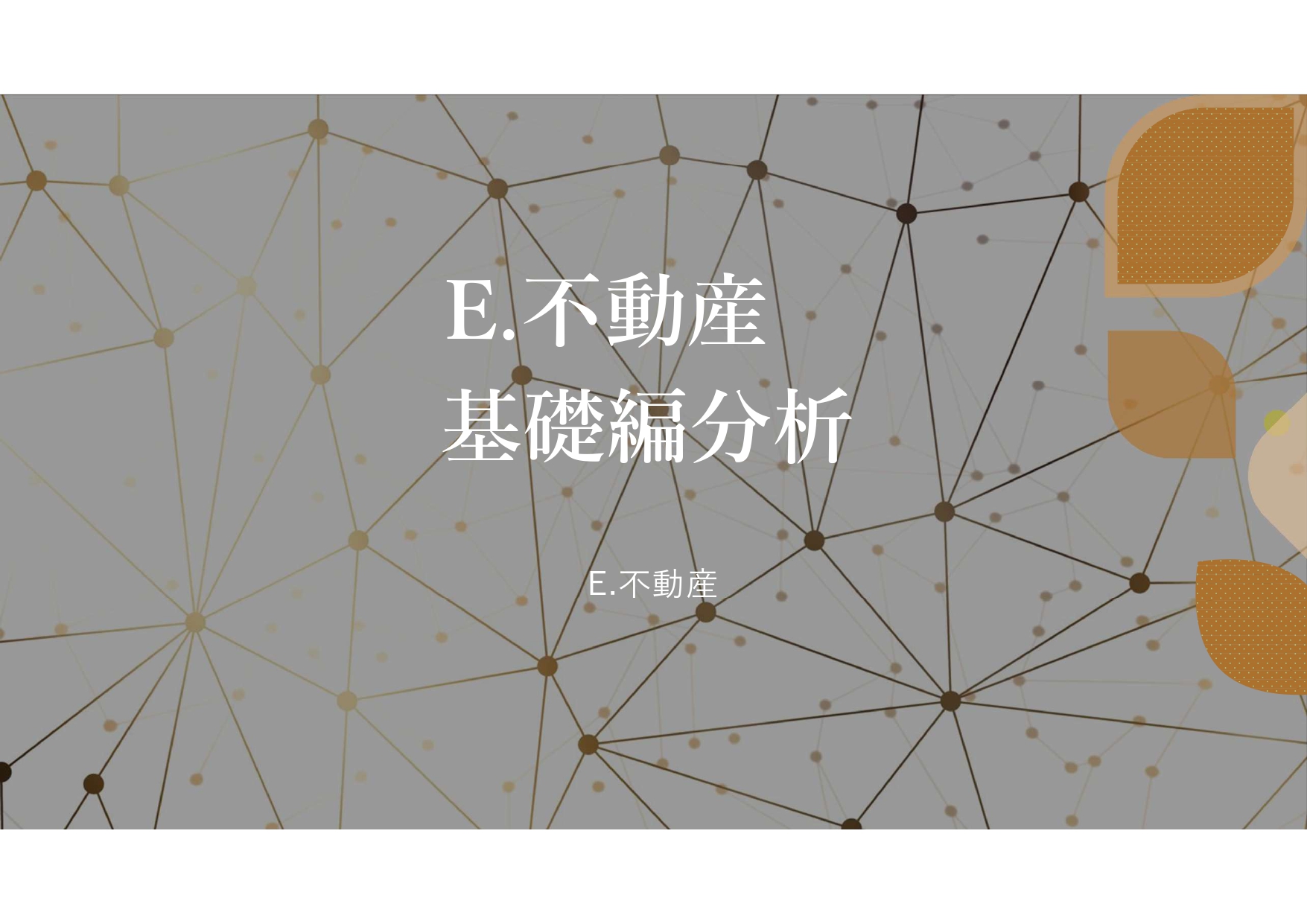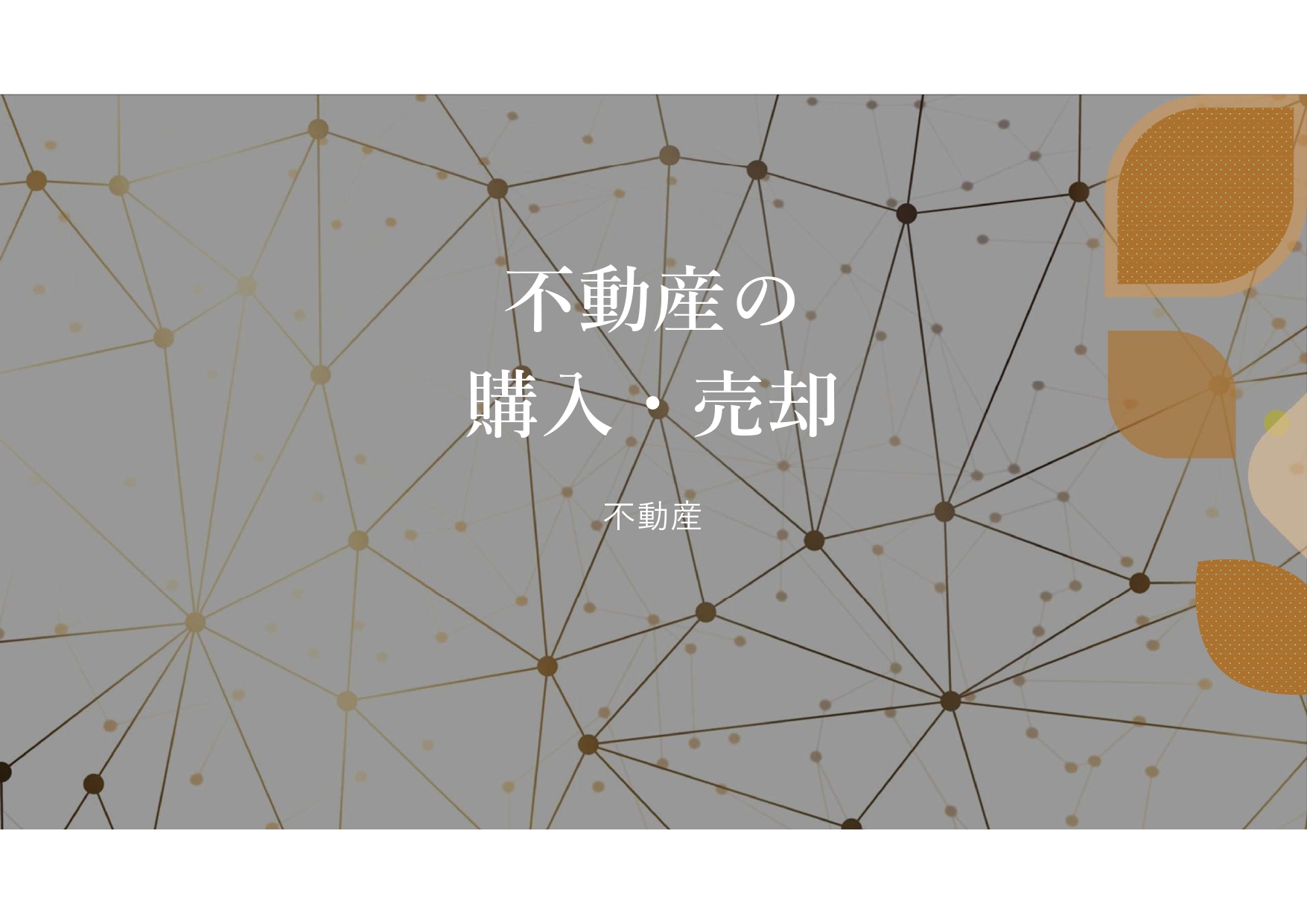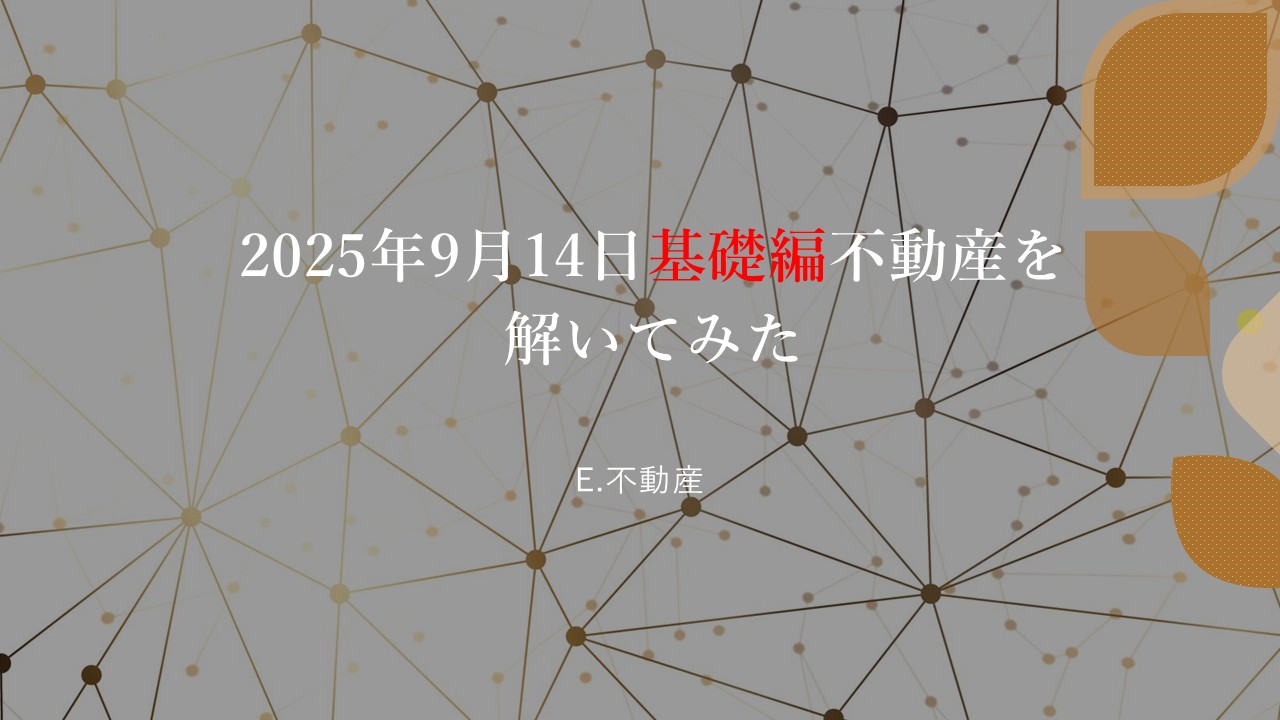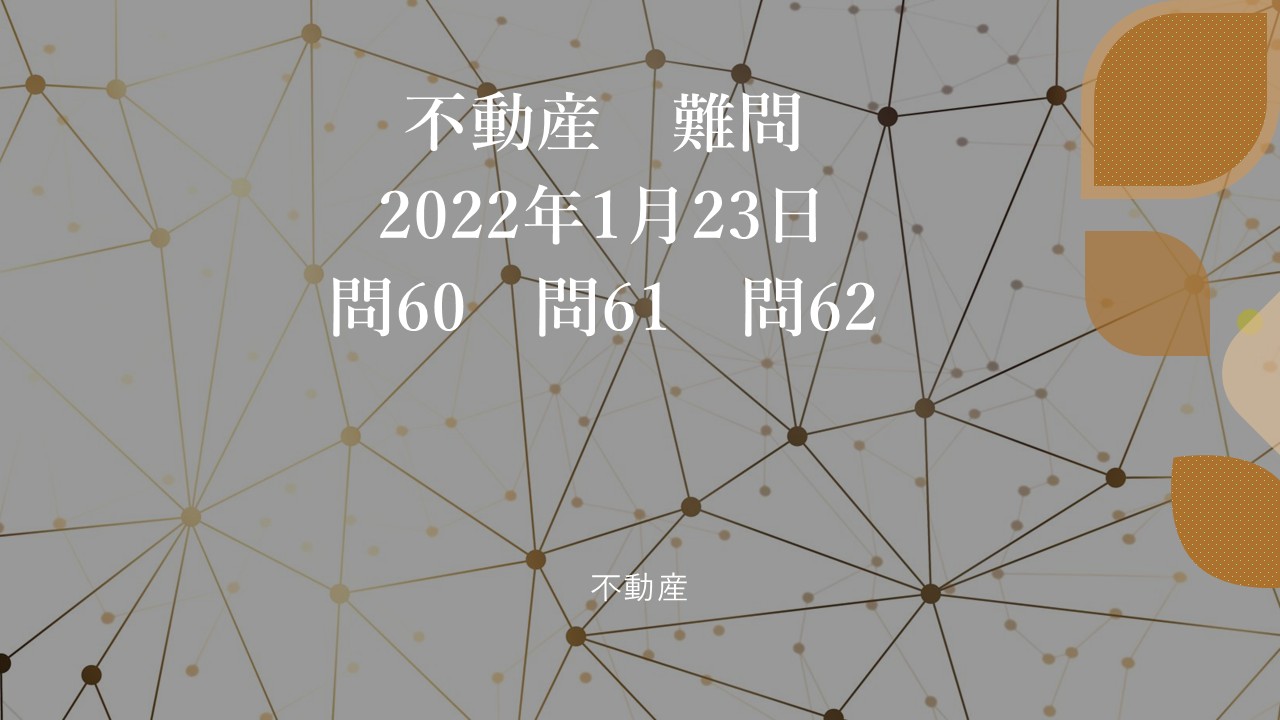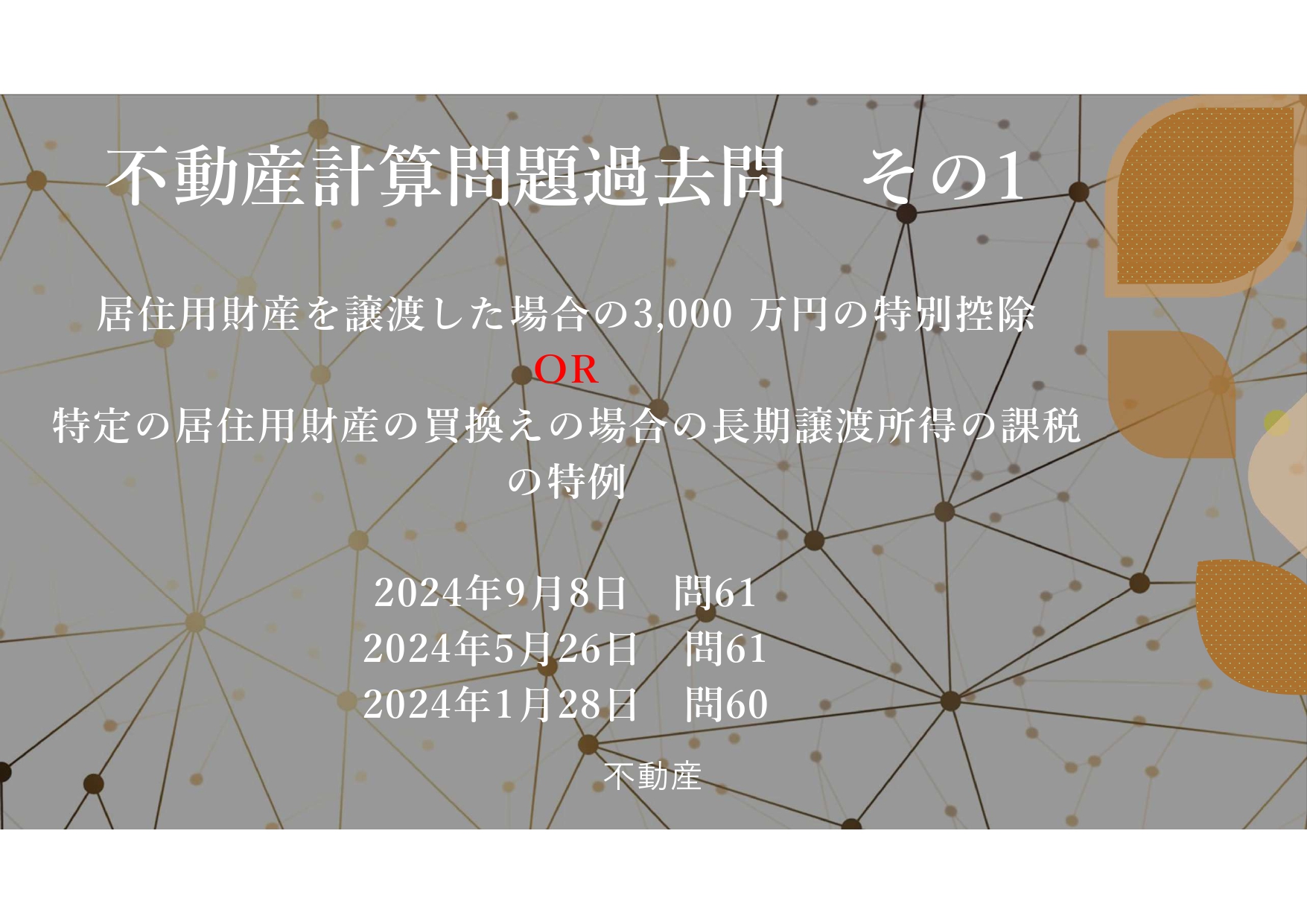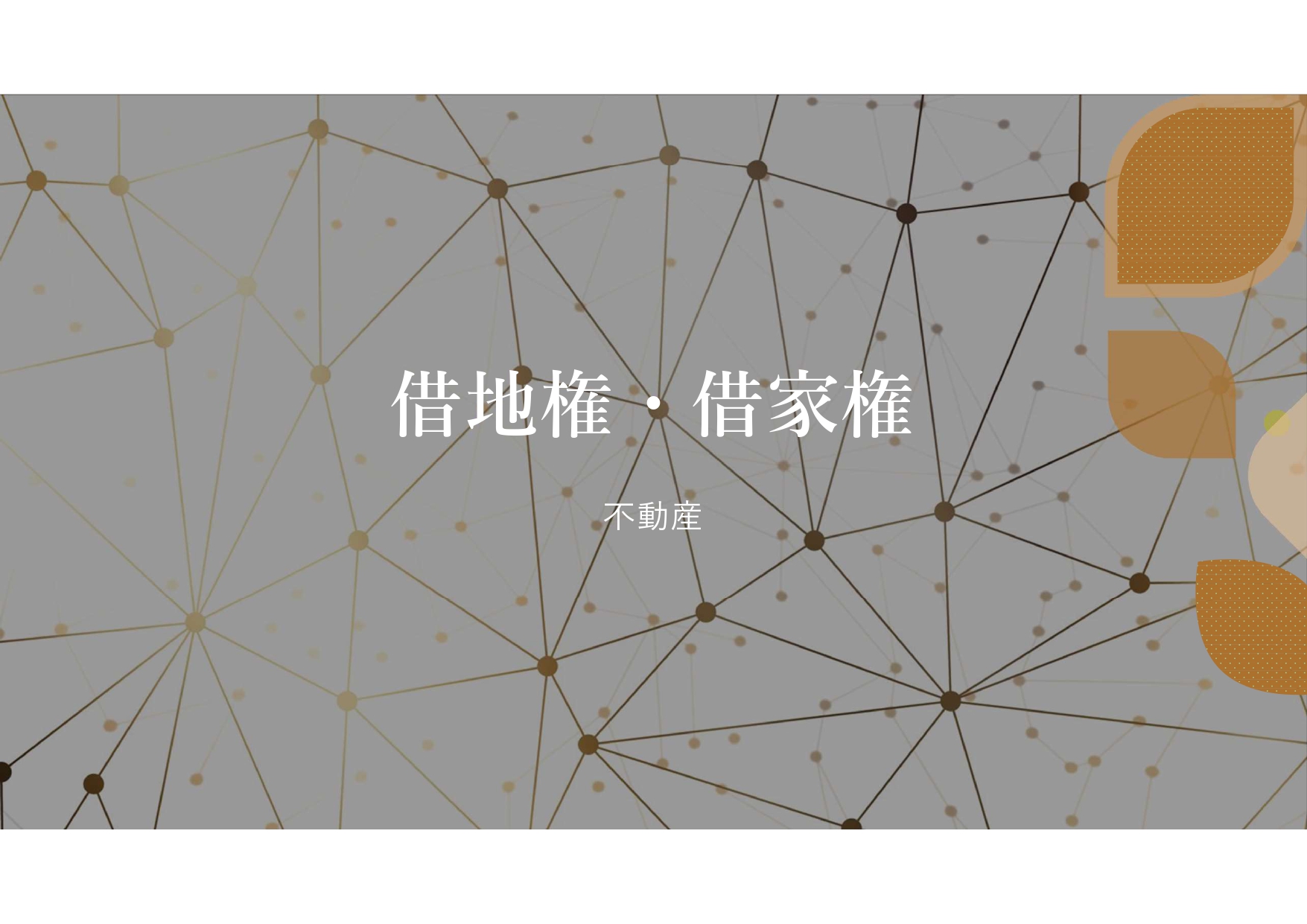2025年1月26日 基礎編 不動産

私自身、FP試験のうち最も苦手であったのが不動産でした。何回か不合格を重ね、苦手意識を払しょくしなければならないと思い、ショック療法として宅建試験の勉強をにわかにし始めました。
その時、ユーチューブで勉強しようと思い、
棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】https://www.youtube.com/@fudousandaigaku
というチャンネルで勉強をしました。このチャンネルで不動産のレベルアップが図れたため、苦手な方にはお勧めします。
では、解説を始めます。今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問34 不動産登記
| 《問34》 不動産登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 登記記録のうち、権利部の甲区には所有権の移転の登記、所有権に関する仮登記・差押え・仮処分などの登記事項が記録され、権利部の乙区には抵当権の設定、地上権の設定、地役権の設定などの所有権以外の権利に関する登記の登記事項が記録される。 2) 区分建物を除く建物に係る登記記録において、床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される。 3) 登記事項証明書および登記事項要約書は、インターネットを利用してオンラインによる交付請求をすることができ、その交付方法は、請求時に郵送または登記所の窓口で受け取る方法のいずれかを選択することができる。 4) 登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用してパソコン等で確認することができるサービスであるが、登記事項証明書とは異なり、取得した登記情報に係る電子データに登記官の認証文や職印は付されない。 |
正解3

登記記録についての問題だけど、FP試験を受ける方は、法務局で登記簿謄本を実際にとってみることをお勧めするよ。法人のものと土地についてのものを両方とってみて、実際にそこに何が書かれているのか見るのが覚えるのに有効だと思うよ。

1)これは正しいね。権利部の甲区、乙区に記載されている内容は正しいね。差押えは甲区、抵当権設定は乙区と間違えやすいから要注意だね。
2)これは基本的な問題だね。区分建物は内側線だから、問題文を読み違えないように注意が必要だね。
3)登記事項要約書は登記所の窓口で受け取る必要があるので不適切だね。
4)登記情報提供サービスはインターネットで登記情報を確認できる制度だけど、登記官の認証文や職印は無いよ。
問35 宅地建物取引業法
| 《問35》宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。 (a) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の20%を超える額の手付を受領することができない。 (b) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、買主が契約の履行に着手するまでは、宅地建物取引業者はその手付を買主に返還することで契約を解除することができる。 (c) 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めた場合に、その合算額が売買代金の額の20%を超えるときは、当該売買契約自体が無効となる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

宅地建物取引業法は頻出だからね。基本的な問題は解けるようにしておく必要があるね。

(a) これは、その通りだね。手付の20%は記憶必須だね。
(b) 宅地建物取引業者が解約する時は手付の倍額を支払う必要があるよ。こう聞くとすごそうだけど、手付に受け取ってるから、それを返すのと、同じ額を支払うということだね。
(c) 契約が無効となるわけでなく、2割を超える部分が無効になるということだよ。
問36 借地借家法
| 《問36》 借地借家法における定期建物賃貸借契約(定期借家契約)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、賃貸人および賃借人は、いずれも宅地建物取引業者ではない個人であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 定期建物賃貸借契約をする際は、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了することについて説明しなければならず、賃貸人がその説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは無効となる。 2) 定期建物賃貸借契約において、その賃料が近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は賃料の増減額をしない旨の特約をした場合、その特約は無効となる。 3) 定期建物賃貸借契約の期間が2年である場合に、賃貸人が期間の満了の10カ月前に、賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしたときは、その終了を賃借人に対抗することができる。 4) 自己の居住の用に供するために賃借している建物(床面積200㎡未満)の定期建物賃貸借契約において、転勤により建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は、解約の申入れの日から1カ月後に建物の賃貸借を終了させることができる。 |
正解2

定期借家契約はよく出題される問題だね。借地借家法というのは借主と貸主のどっちに有利かというのが問題になるけど、現状では借りている方に有利といえるかもね。

1)これは適切だね。定期建物賃貸借契約をした場合、大家さんは気をつけないといけないね。
2)一定期間、増額しない特約は有効だけど減額しない特約は無効だね。
3)契約期間1年以上の契約の場合、貸主から解約しよと思えば半年から1年前までに借主に伝える必要があるね。10カ月前に伝えているので対抗は可能だね。
4)これはその通りだね。
問37 建築基準法
| 《問37》 建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 建築基準法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地(セットバック部分)については、建築物を建築することはできないが、建築物の容積率の算定の基礎となる敷地面積に含めることができる。 2) 前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。 3) 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 4) 共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。 |
正解3

容積率の問題は応用編で計算問題が毎回出題されるので、図を見て計算するのには慣れているつもりだけど、その計算の際に、いつも迷うところが文章で問われているので迷うよね。

1)セットバック部分は容積率の計算に含めないよ。道路になるわけだからね。
2)これも記憶があいまいだと迷うね。前面道路は12m未満が正しいね。
3)これは正しいね。地階の3分の1と記憶がごちゃごちゃにならないように要注意だね。
4)これは3分の1じゃなく、すべてを含めずに計算するのが正しいね。都会で土地の制約が多い地域だと、この容積率の計算で建物が結構、変わったりするかもね。
問38 不動産取得税の税額
| 《問38》 Aさんは、2019年8月に父親から相続により借地権(借地借家法の定期借地権等ではない)と借地上の住宅を取得し、2024年12月に地主から、その借地権が設定されている土地の所有権(底地)を買い取った。下記の〈条件〉に基づき、Aさんの底地買取りに伴う不動産取得税の税額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈条件〉 ・底地の買取価額は1,800万円である。 ・この土地の固定資産税評価額は3,000万円である。 ・この土地の借地権割合は60%である。 ・不動産取得税の税率は3%である。 1) 27万円 2) 30万円 3) 36万円 4) 45万円 |
正解4

この問題は、1級実技試験で、直接問われないけど、計算して判断を求められる内容が出題されたりするね。実際、交換特例って使う人が多いのかもしれないね。

不動産取得税の計算は固定資産税評価額×3%で求められるのですが、課税標準を2分の1にする軽減税率も適用されるため 3,000万円×3%×2分の1=45万円で正解4)だね。
問39 住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例
| 《問39》 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 本特例の適用を受ける土地が300㎡である場合、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の2の額となる。 2) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を改築し、2024年9月に当該住宅の床面積の2分の1を超える部分を店舗とした場合、当該土地に係る2024年度分の固定資産税のうち、2024年10月1日以後に納期限が到来する分については本特例の適用を受けることができない。 3) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅を建替えのために2024年10月に取り壊した場合、2025年1月1日現在において新たな住宅が完成しておらず、建築中であっても、所定の要件を満たせば、当該土地に係る2025年度分の固定資産税について継続して本特例の適用を受けることができる。 4) 本特例の適用を受けていた土地の上の住宅が管理不全空家等に該当し、その所有者が市町村長から当該住宅が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導を受けた場合、当該土地に係る固定資産税について、その指導を受けた日の属する年度の翌年度分から本特例の適用を受けることができない。 |
正解3

固定資産税は毎年、支払うものなので、特例はありがたいんだよね。

1)固定資産税が200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は3分の1まで軽減されるという制度です。数字は間違いが作りやすいので要注意だよ。
2)固定資産税は1月1日の状況で判断されるので、9月の改築であれば、適用されるのは次年の1月1日からだね。
3)これは適切だね。改築が年をまたぐというのは、よくあることなのかもしれないね。
4)管理不全空家等は今後、しばらく頻出になりそうだね。適用対象外になるのは勧告だね。ちなみに指導は勧告の一歩手前だね。できれば指導の前の助言の段階で手を打つことがお勧めだね。親族やや関係者との相談も必要になるだろうしね。
問40 不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否
| 《問40》 不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) Aさんが、自宅(建物とその敷地)と1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を同一年中に譲渡した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることはできない。 2) Bさんが、1人暮らしをしていた父親の相続により2年前に取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることはできない。 3) Cさんが、40年前に取得した自宅(建物とその敷地)を譲渡し、新たな自宅(建物とその敷地)を取得した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について重複して適用を受けることはできない。 4) Dさんが、母親と2人で居住していた実家(建物とその敷地)を母親の相続により2年前に取得し、マンションに移り住むため、その実家を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受けることができる。 |
正解1

不動産の譲渡というテーマも応用編、実技試験で問われそうな問題だね。
3,000万円特別控除、軽減税率、空き家の3,000万円控除などは頻出だから、覚えておいて損はないよ。

1)よく出題される論点だね。居住用の3,000万円特別控除と空き家の3,000万円控除は併用可能だけど、合わせて3,000万円までが適用されるよ。
2)この2つは選択制なんだね。
3)これも選択制だね、応用編の計算問題で、2パターン計算する問題がよく出題されるよ。
4)これもよく出題されるね。FP試験では、居住用3,000万円控除と軽減税率はセットで出題されると考えるのが無難かもしれないね。
問41 DCF法
| 《問41》 毎期末に2,000万円の純収益が得られる賃貸マンションを取得し、取得から3年経過時点で3億円で売却する場合、DCF法による当該不動産の収益価格として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、割引率は年5%とし、下記の係数表を利用すること。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈年5%の各種係数〉 |
| 期間(年) | 現価係数 | 年金終価係数 | 資本回収係数 |
| 1年 | 0.952 | 1.000 | 1.050 |
| 2年 | 0.907 | 2.050 | 0.538 |
| 3年 | 0.864 | 3.153 | 0.367 |
| 1) 3億1,366万円 2) 3億5,446万円 3) 3億5,718万円 4) 3億6,306万円 |
正解1

DCF法の問題だね。これは解き方を覚えて、反復して練習することをお勧めするよ。
わかってしまえば得点源だから。
しかし、現在価値が将来受け取れる金額より、低いという感覚はなんとなくピンとこないんだよね。ゼロ金利に慣れすぎてるからだろうか。

(1年後の2,000万円の現在価値)
2,000万円×0.952=1,904万円
(2年後の2,000万円の現在価値)
2,000万円×0.907=1,814万円
(3年後の2,000万円の現在価値)
2,000万円×0.864=1,728万円
(3年後の3億円の現在価値)
30,000万円×0.864=25,920万円
1,904万円+1,814万円+1,728万円+25,920万円
=31,366万円
よって1) 3億1,366万円が正解だね。