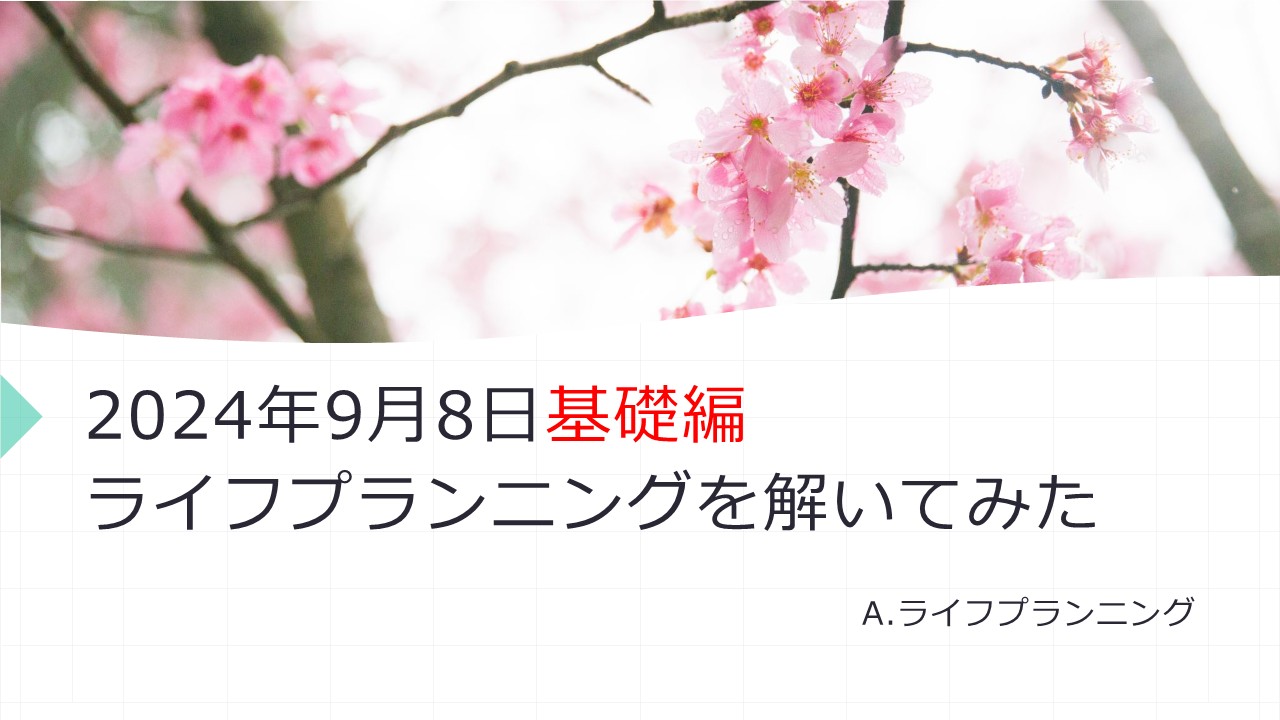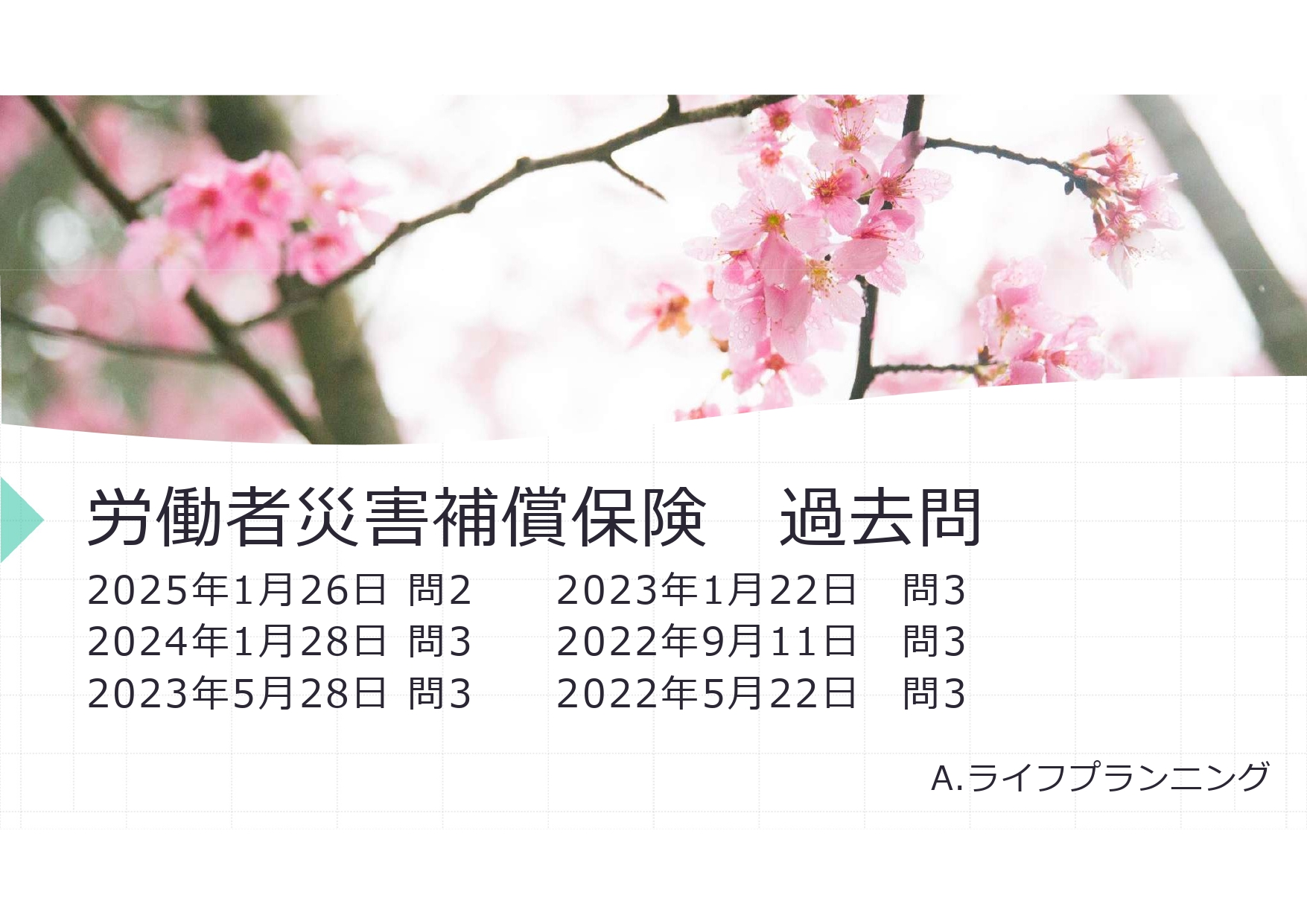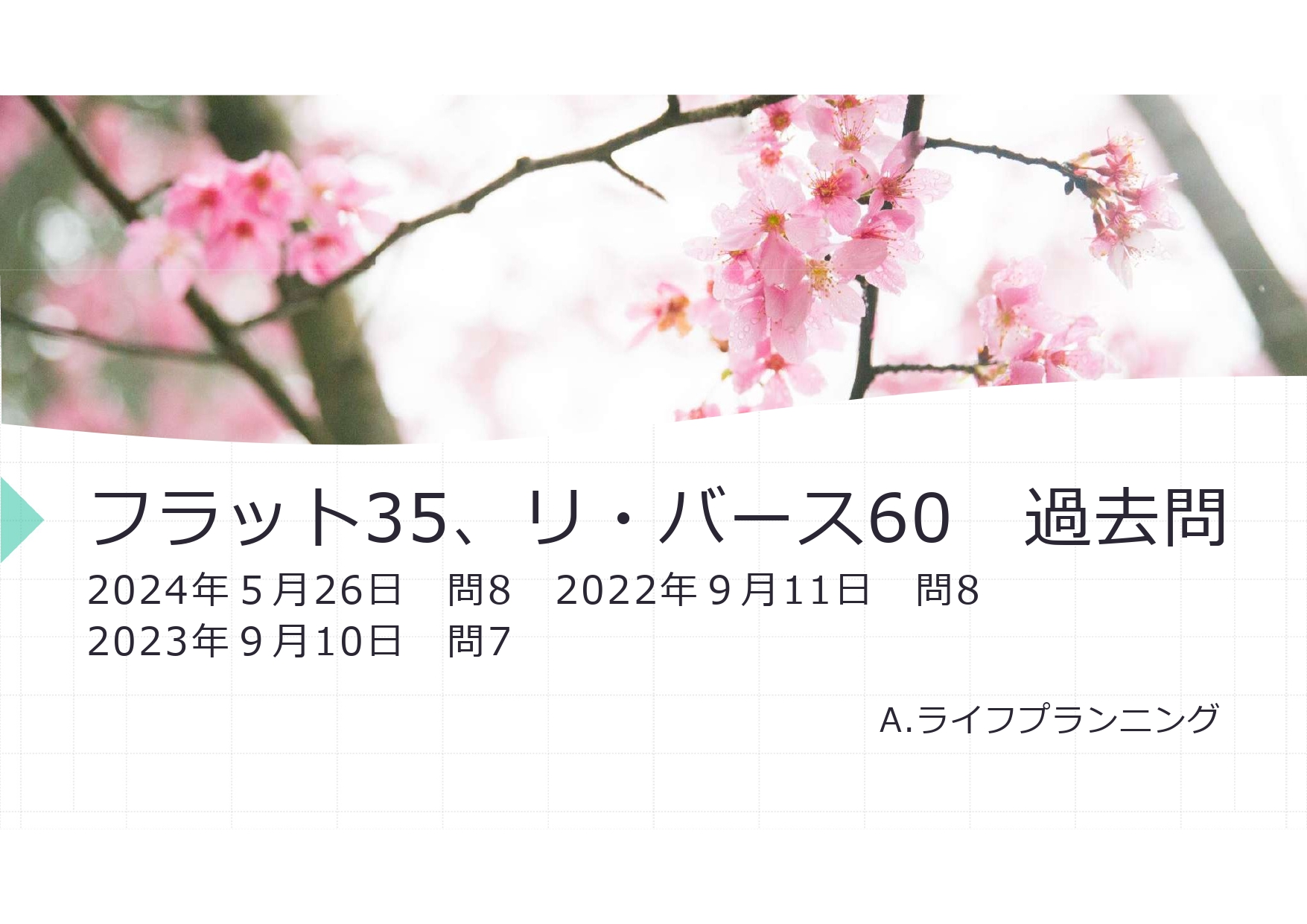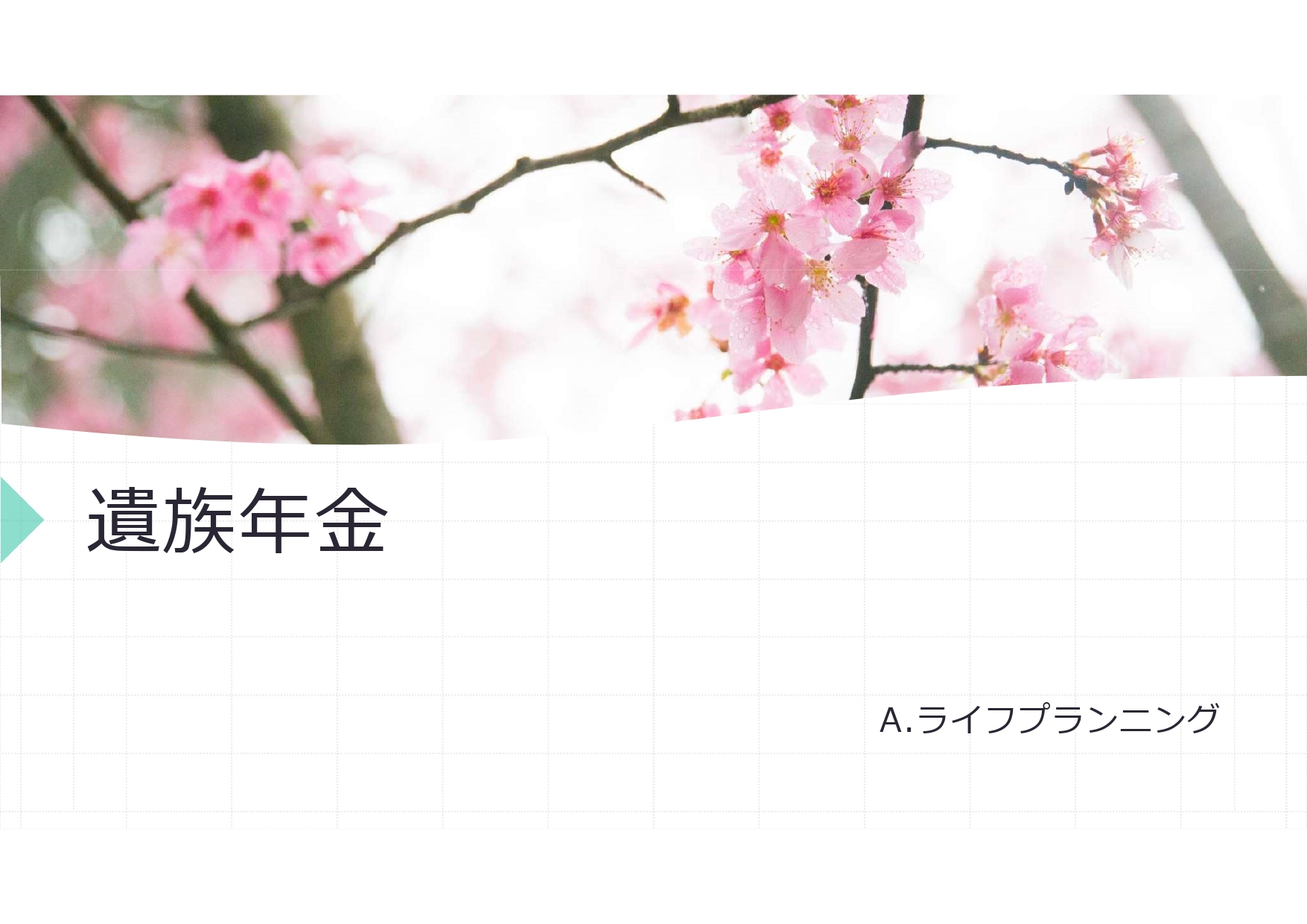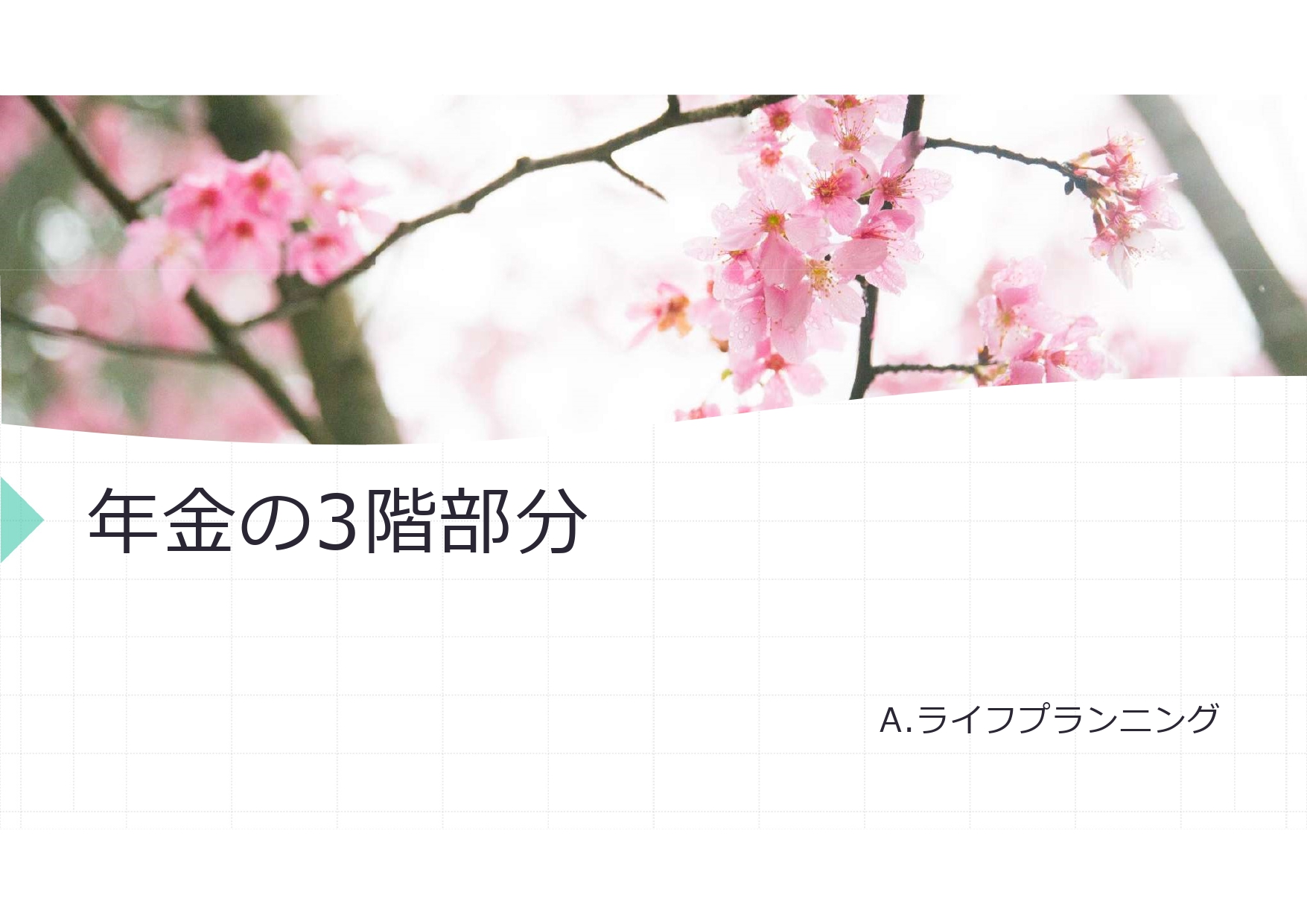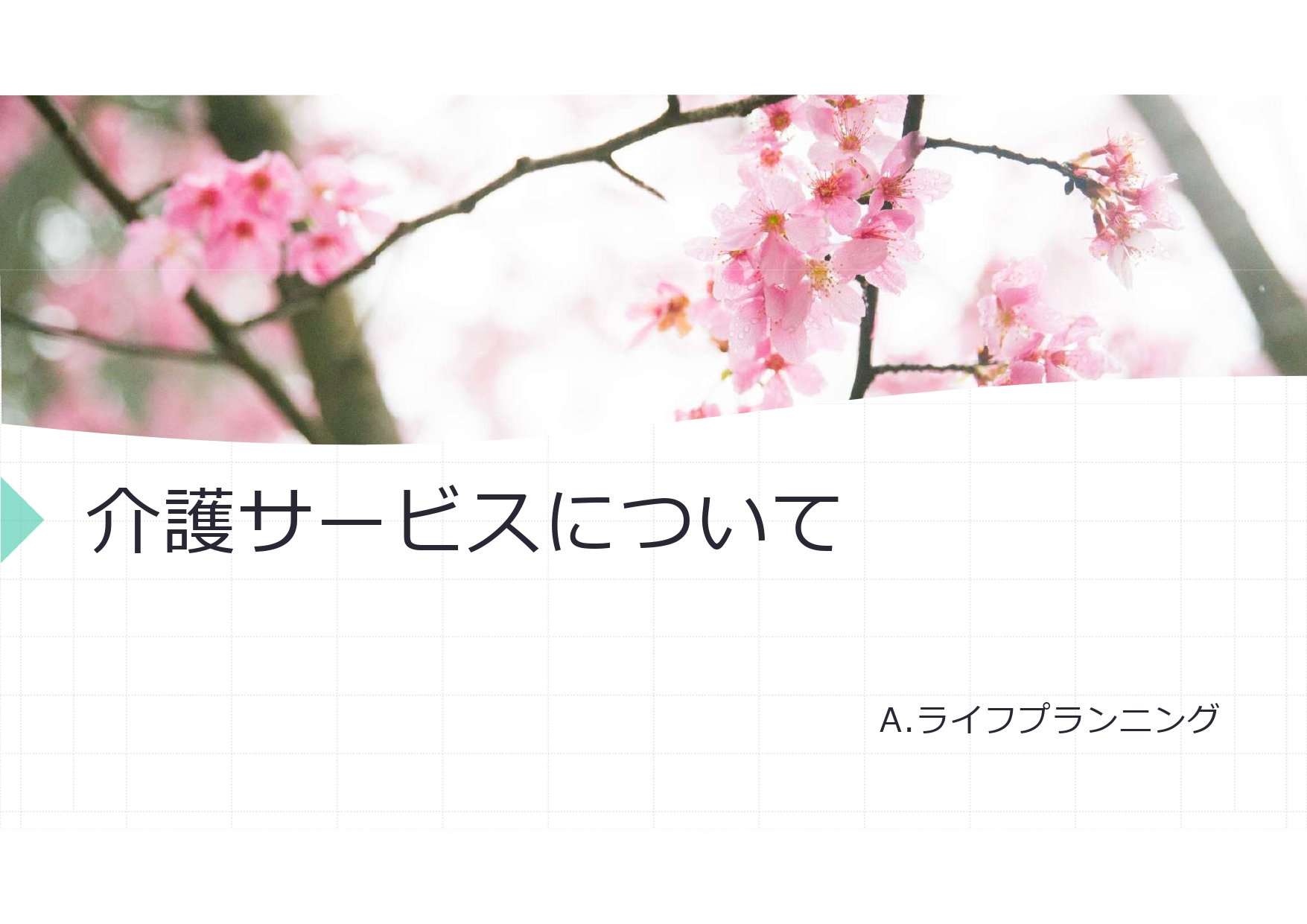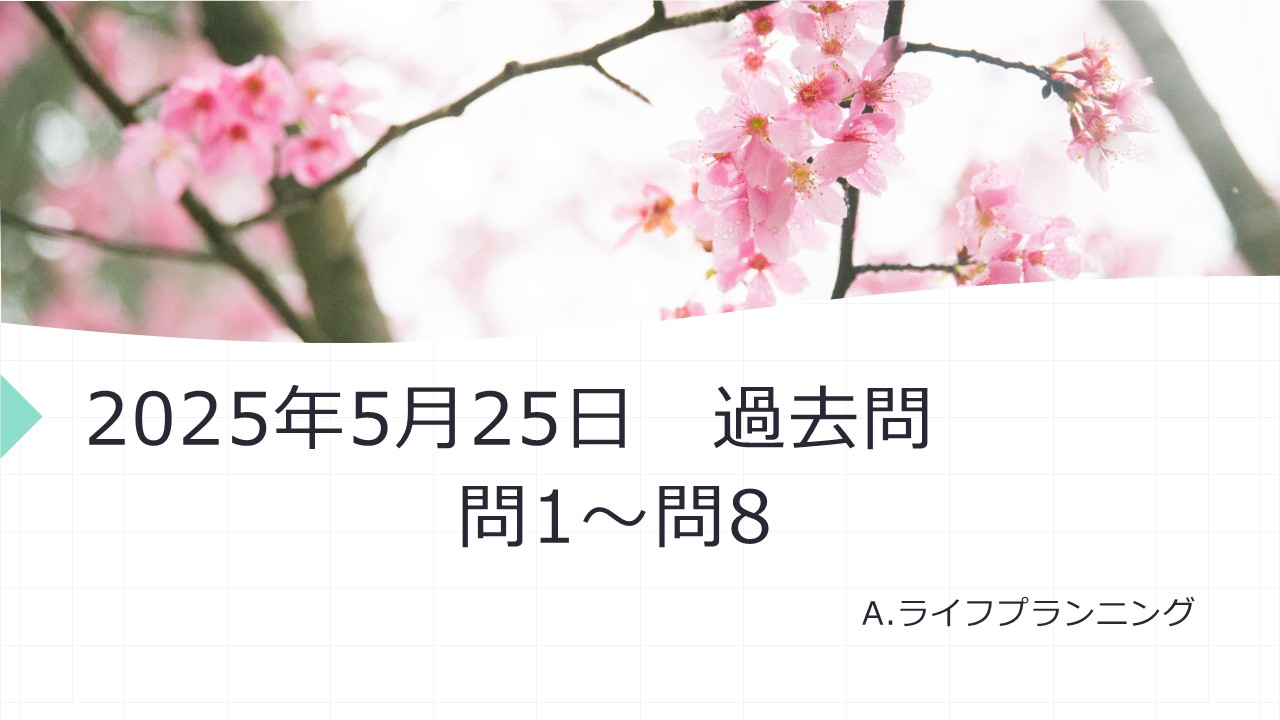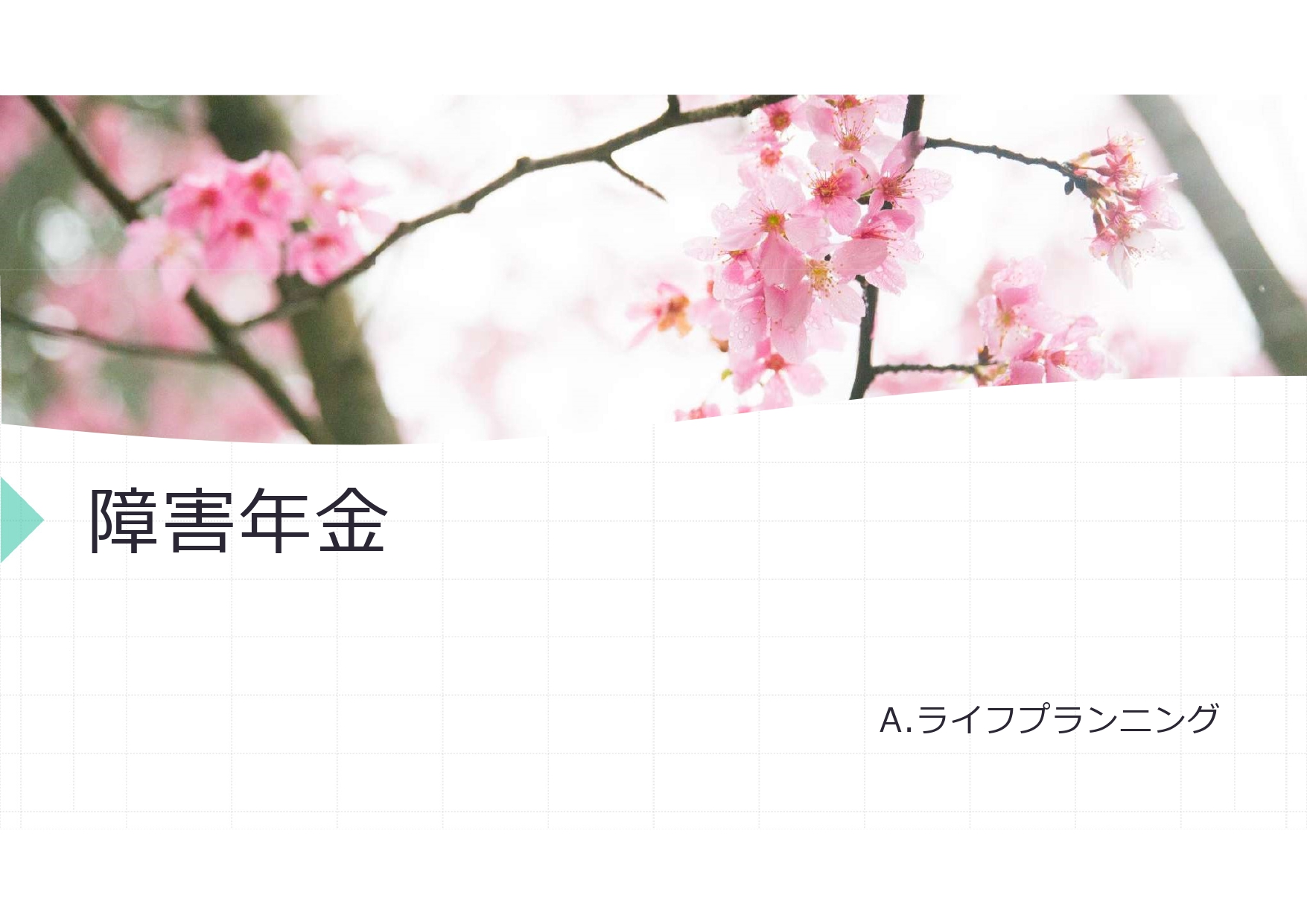2025年9月14日基礎編ライフプランニングを解いてみた
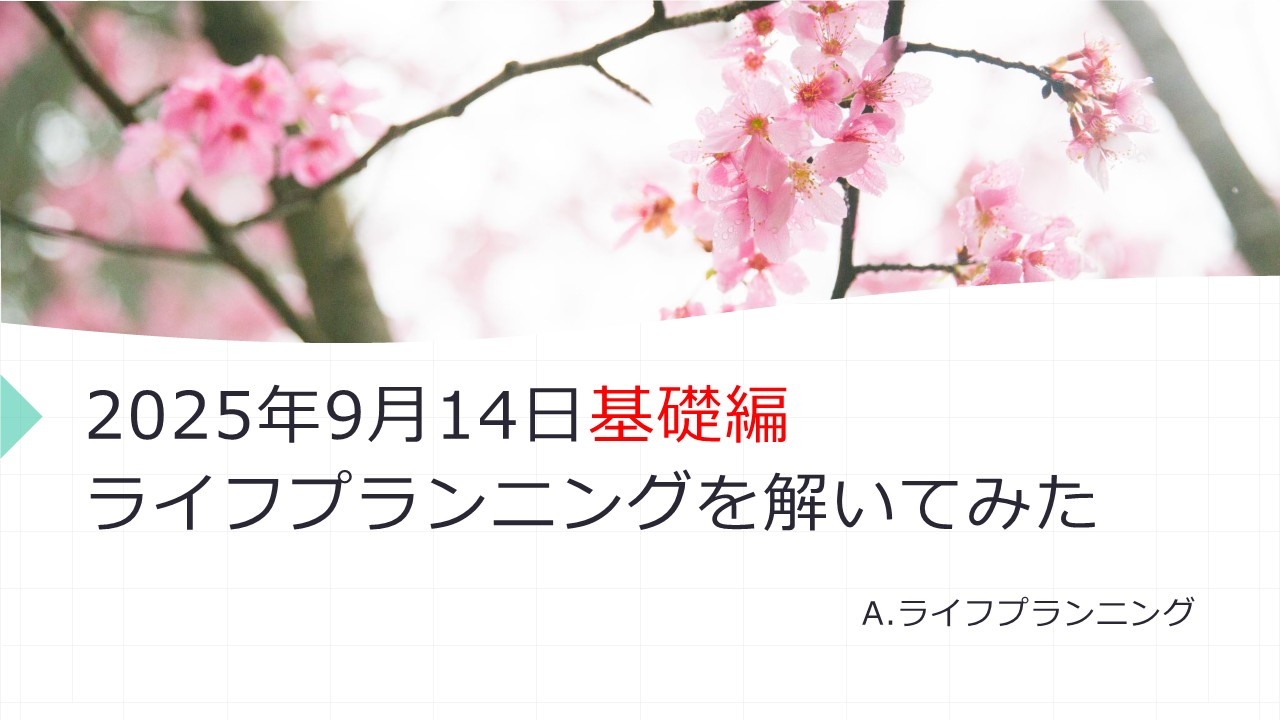
応用編につづいて2025年9月試験について基礎編の問題を見ていこうと思います。
何度か述べていますが、私は受験生時代、基礎編が苦手でした。
しかし1級ファイナンシャルプランニング技能士になった以上、逃げてはいられません。
FP自身の能力の啓発を継続するためにも、わからない選択肢についてはネットで調べながら解説を試みたいと思います。
受験生の皆様は時間が無い中、勉強されている方も多いと思います。少しでもお役に立てる情報を提供するつもりで記事を書いていこうと思います。
全科目の全選択肢を見たわけではなく、場合によっては解説に苦しむ内容もあるかもしれませんが、ご容赦ください。
また、なるべく毎日更新を目指しますが、原稿作成が間に合わないこともあるかもしれないので、9月30日までに基礎編解説を完了することを目標にしたいと思います。
不適切な解説などありましたらメール等でお知らせいただけると助かります。
今回も、問題は全て 出所:一般社団法人金融財政事情研究会です。
また、今回もつるさん、かめさんの吹き出しで解説しますが、つるさんが素の私で、かめさんがネットや書籍で調べた上でのコメントとなっています。
問1 6つの係数
| 《問1》 Aさん(50歳)は、老後の資金計画を検討しており、50歳から65歳までの15年間は毎年一定額を積み立て、65歳からはその積み立てた資金を取り崩して生活したいと考えている。Aさんが、65歳までに積み立てた資金を65歳から20年にわたって、毎年60万円ずつ取り崩す場合、50歳から65歳までの15年間の毎年の積立額として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、現在の貯蓄額は0円とし、積立期間および取崩期間中の運用利回り(複利)は年2%、積立および取崩しは年1回行うものとする。また、下記の係数表を利用して算出し、計算結果における万円未満を切り上げ、手数料や税金等は考慮しないものとする。 〈年2%の各種係数〉 |
| 終 価 係 数 | 現 価 係 数 | 年金終価係数 | 減債基金係数 | 年金現価係数 | 資本回収係数 | |
| 15年 | 1.3459 | 0.7430 | 17.2934 | 0.0578 | 12.8493 | 0.0778 |
| 20年 | 1.4859 | 0.6730 | 24.2974 | 0.0412 | 16.3514 | 0.0612 |
| 1) 49万円 2) 57万円 3) 70万円 4) 77万円 |
正解2

3回続けての6つの係数だね。しかし、今回は考えやすかったかもしれないね。 今回の問題だと、20年にわたって、毎年60万円ずつ取り崩すという点から考え始める必要があるね

20年にわたって、毎年60万円ずつ取り崩す場とあるから65歳までに、この資金を貯める必要があるね。20年の年金現価係数を使って
60万円×16.3514=981.084万円
この金額を15年間で貯める必要があるから、15年の減債基金係数を掛けて求めればいいよ
981.084万円×0.0578=56.70666 よって 2)57万円が正解だね
問2 健康保険
| 《問2》 全国健康保険協会管掌健康保険(以下、「健康保険」という)の高額療養費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、被保険者は70歳未満であるものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 高額療養費の算定上、差額ベッド代や保険適用となっていない医療行為に係る費用は合算の対象とならないが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額や入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は合算の対象となる。 2) 同居している夫婦がともに健康保険の被保険者である場合において、夫婦のそれぞれが医療機関等で支払った一部負担金等の額は、高額療養費の算定上、同一月中に支払ったものであっても合算することができない。 3) 高額療養費の算定上、健康保険の被保険者の自己負担限度額(高額療養費算定基準額)は、当該被保険者が療養を受けた月における標準報酬月額、被扶養者の数および高額療養費多数回該当の有無に応じて決定される。 4) 2025年6月から8月の3カ月間、国民健康保険の高額療養費の支給を受けた者が、2025年9月1日から健康保険の被保険者となり、2025年9月に受けた療養について健康保険の高額療養費の支給を受ける場合、高額療養費多数回該当により自己負担限度額(高額療養費算定基準額)が軽減される。 |
正解2

1)入院中の食事代は対象外というのは知っているけど、食事療養標準負担額と意味は一緒だろうか。
2)これが認められないんじゃないかな。夫婦の財布がひとつと考えたら家計の助けになるかもしれないけどね。
3)自己負担限度額は標準報酬月額で決まるという意識はあるけど、他の要因は頭にないな。
4)これは違う気がする。加入する健康保険が変わるわけだからね。

1)入院時の食事療養標準負担額は「高額医療費制度の対象外」だよ。
2)高額療養費を夫婦で合算できるということは残念ながらないね。これが適切だね。
3)被扶養者の数は高額療養費に影響することはないね。多数回該当は12か月の内、3回以上高額療養費が支給された場合、4回目から自己負担限度額が下がるという制度だね。
4)途中で保険者が変わった場合、回数の通算はされないね。あくまで新たな健康保険で受ける高額療養費は1回目だね。
問3 労災保険
| 《問3》 労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 複数の事業所で雇用される労働者が、そのうち1つの事業所において業務上の事由により負傷した場合、労災保険の給付基礎日額は、原則として、当該労働者を雇用する事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額のうち、最も高いものとなる。 2) 特別加入者に係る保険料は、原則として、当該特別加入者の前年所得および従事する事業に応じて決定される給付基礎日額に365を乗じて得た額に対し、特別加入保険料率を乗じて算出される。 3) 派遣労働者が派遣先で業務上の事由により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適用事業とされ、派遣労働者が通勤上の事由により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。 4) 労働者が勤務先からの帰宅途中に通勤経路から逸脱し、立ち寄ったスーパーの店内で日用品を購入中に転倒して負傷した場合、その負傷は通勤災害に該当しない。 |
正解4

1)ストレスの場合、複数の事業所で合算されるという話を聞いたことがあるけど
2)そもそも特別加入者という言葉を初めて聞いたな。
3)実際に仕事をしてたのが派遣先だから、そこの労災にならないのかな?
4)業務災害か通勤災害か、扱いも含めていつも迷うんだよね。

1)これは労災に合った事業所の業務災害と考えるのが正しいね。
2)特別加入者とは中小事業主・一人親方・特定作業従事者(芸能関係者)・海外派遣者のことだよ。前年の所得でなく「特別加入時の所得見込額」または「過去の所得」を基礎として算定されるよ。
3)派遣労働者が労災を申請する場合派遣先でなく派遣元だね。
4)これが正解だよ。通勤経路を逸脱してスーパーで買い物をした後、通常の通勤経路に戻っていたら通勤災害が認められる場合もあるけど
問4 雇用保険の基本手当
| 《問4》 雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職した場合において、当該勤務先において育児休業を取得し、育児休業給付金の支給を受けていたときは、所定給付日数における算定基礎期間に、育児休業給付金の支給に係る休業の期間は含まれない。 2) 雇用保険の一般被保険者が勤務先を退職し、基本手当を受給する場合において、その受給期間内に、妊娠、出産、育児、病気等により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があるときは、最長2年まで受給期間を延長することができる。 3) 雇用保険の一般被保険者が、正当な理由がなく、自己都合により退職した場合、一定の教育訓練を受けることにより、基本手当の給付制限が2カ月から1カ月に短縮される。 4) 雇用保険の高年齢被保険者が勤務先の倒産により離職した場合、所定の手続により、待期期間満了後、給付制限を受けることなく基本手当を受給することができる。 |
正解1

1)これはよくわからないね。自分自身、育児休業を実際に取得した経験もないからね。
2)これも経験ないな~奥さんに聞いても忘れてるだろうな~
3)こういう制度があるのは聞いたことあるような気がするな。
4)そもそも基本手当が受けれるのは65歳までじゃなかったっけ?

1)育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれないというのは正しいね。
2)妊娠、出産、育児の場合、最長3年まで受給期間を延長できるよ。
‘3)令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになったよ。
4)高年齢被保険者は基本手当を受けることはできないよ。条件次第で高年齢求職者給付金を受けれる可能性があるよ。
問5
問5 国民年金
| 《問5》 国民年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 20歳未満や60歳以上の国民年金の第2号被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額の計算上、保険料納付済期間とされないが、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。 2) 国民年金の第1号被保険者が保険料納付猶予制度(国民年金の保険料の免除の特例)の適用を受けるためには、当該被保険者が30歳未満であり、かつ、被保険者本人および配偶者の所得金額が一定額以下である必要がある。 3) 寡婦年金の額は、原則として、夫の死亡日の属する月の前月までの国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間を基礎として計算した老齢基礎年金の額の4分の3相当額であるが、当該保険料納付済期間が300月に満たないときは、300月とみなして計算する。 4) 国民年金の第1号被保険者が死亡し、その遺族が死亡一時金の支給を受ける場合に、当該被保険者が付加保険料を納付した期間が12カ月以上あるときは、死亡一時金の額に一定額が加算される。 |
正解1

1)これは応用編で見たことあるかも20歳前に厚生年金を納めているパターンだよね。
2)免除の30歳というと学生納付特例だけど、これとひっかけてるのかな?
3)この説明は遺族年金の説明じゃないかな?
4)死亡一時金の知識もまったくないな。サラリーマンには無縁だしね。

1)老齢基礎年金を受けるためには保険料を納付した期間と免除された期間を合算して10年の年金加入期間が必要だけど、これを満たせない場合、20歳より前か、60歳以降の期間を加算して10年以上にすることができるよ。
2)国民年金の保険料の免除の特例は50歳未満が条件だね。
3)寡婦年金は、国民年金に10年以上加入していた個人事業主(第1号被保険者)などの夫が亡くなった場合に、妻が60〜65歳まで受け取れる年金のことだよね。
4)付加保険料を納付した期間は36カ月以上あると8,500円が加算されるね。
問6
問6 老齢厚生年金
| 《問6》 老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 配偶者の加給年金額が加算される老齢厚生年金を繰り下げて受給したとしても、加給年金額は繰下げによる増額の対象とならない。 2) 繰下げ支給の申出により増額された老齢厚生年金について、在職老齢年金の仕組みにより支給調整が行われる場合、繰下げ加算額は支給調整の対象とならない。 3) 厚生年金保険の被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の支給を受けている者が婚姻し、その者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有することとなった場合、婚姻した月の翌月から老齢厚生年金に加給年金額が加算される。 4) 老齢厚生年金の支給を受けている厚生年金保険の被保険者が退職して再就職しない場合、原則として、退職した月の翌月から老齢厚生年金の年金額が改定される。 |
正解3

1)応用編の計算問題で出てきそうな内容は考えやすいかもね。
2)これは難しいね、そもそも繰下げるなら在職老齢年金にかからないようにするんじゃないかな?
3)芸能人とかで親子ほど離れた奥さんと高齢になってから結婚してる人とか加給年金を受けれるんだろうか?
4)在職定時改定は、毎年、基準日(9月1日)を基に10月から改定する仕組みって聞いたことあるけど・・違うね?

1)これは正しいね。加給年金の増額って計算したことないもんね。
2)これは正しいらしい。これに関する出題が応用編であったら悩むね。
3)老齢厚生年金の支給スタート時の配偶者でなければ加給年金の対象にはならないね。
4)これが退職時改定の説明だね。
問7
問7 確定拠出年金
| 《問7》 確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している期間は、個人型年金加入者掛金を拠出することができない。 2) 個人型年金加入者が老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り上げて受給した場合、個人型年金加入者の資格を喪失する。 3) 企業型年金加入者が、傷病により、その障害認定日において厚生年金保険法に規定する障害等級1級から3級に該当する程度の障害の状態に至った場合、所定の手続により、障害給付金の支給を受けることができる。 4) 個人型年金加入者が老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上必要となるが、当該期間には、原則として、60歳に達する日の前日が属する月以前の期間であって、掛金を拠出せずに個人別管理資産の運用指図のみを行っていた期間も含まれる。 |
正解3

1)iDECOは話題になっているけど、正直よくわからないんだよね。
2)これもわからないね。しかし、年金は支払うか、受け取るかの二者択一だと思うからあっているんじゃないかな。
3)これも合っているような気がするけど、どこが違うんだろう?
4)個人別管理資産の運用指図ができるというのは、最初、聞いたと思うけど正直やったことが無いんだよね。

1)これは適切だね。どちらかを選択する必要だね。
2)iDECOの加入要件のひとつに「公的年金の受給を受けていないこと」というのがあるので適切だね。
3)企業型年金加入者が障害給付金の支給を受けることができるのは国の障害基礎年金を受けられる程度の障害を有している場合なので障害厚生年金3級では受けられないね。
4)これは文章の通りだね。
問8 中小企業の資金調達
| 《問8》 中小企業の資金調達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) ビジネスローンは、一般に、資金使途が事業資金に限定されたローンであり、貸金業者が提供するビジネスローンを企業や個人事業主が利用する場合、貸金業法で定める総量規制の対象となる。 2) ファクタリングは、一般に、企業が保有する債権を担保として金融機関から融資を受ける方法であり、担保の対象となる債権には、売掛債権や診療報酬債権などがある。 3) 日本政策金融公庫のマル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が利用することができる融資制度であり、利用にあたっては、担保および保証人が不要とされている。 4) 信用保証協会の特定社債保証制度は、一定の基準を満たす中小企業が発行する私募債に係る保証制度であり、利用にあたっては、発行体の代表者と信用保証協会が共同で保証人となり、それぞれが発行額に所定の割合を乗じた金額について保証を行う。 |
正解3

1)問7には年金の3階部分が出て、問8には資金調達の問題が出るんだよね。
2)資金が乏しい零細企業にとって社員の給与を支払う場面とかでファクタリングって助かるもんね。
3)細部はよくわからないけど、読んしっくりくる選択肢だね。
4)私募債ってよくわからないな。借入だと普通、担保や保証人をつけるよね。

1)ビジネスローンに総量規制は適用されない、または例外となる場合が多いよ
2)ファクタリングは債権を譲渡する手法で担保にして資金調達するのとは微妙に違うね
3)これが正しいね。商工会議所経由でマル経は創業しようとする人は最初にお世話になると思うよ。
4)発行体の代表者個人が保証を求められるケースは、原則としてないよ。だからアイデアはあるけど資金が無い人に使われているんだね。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。