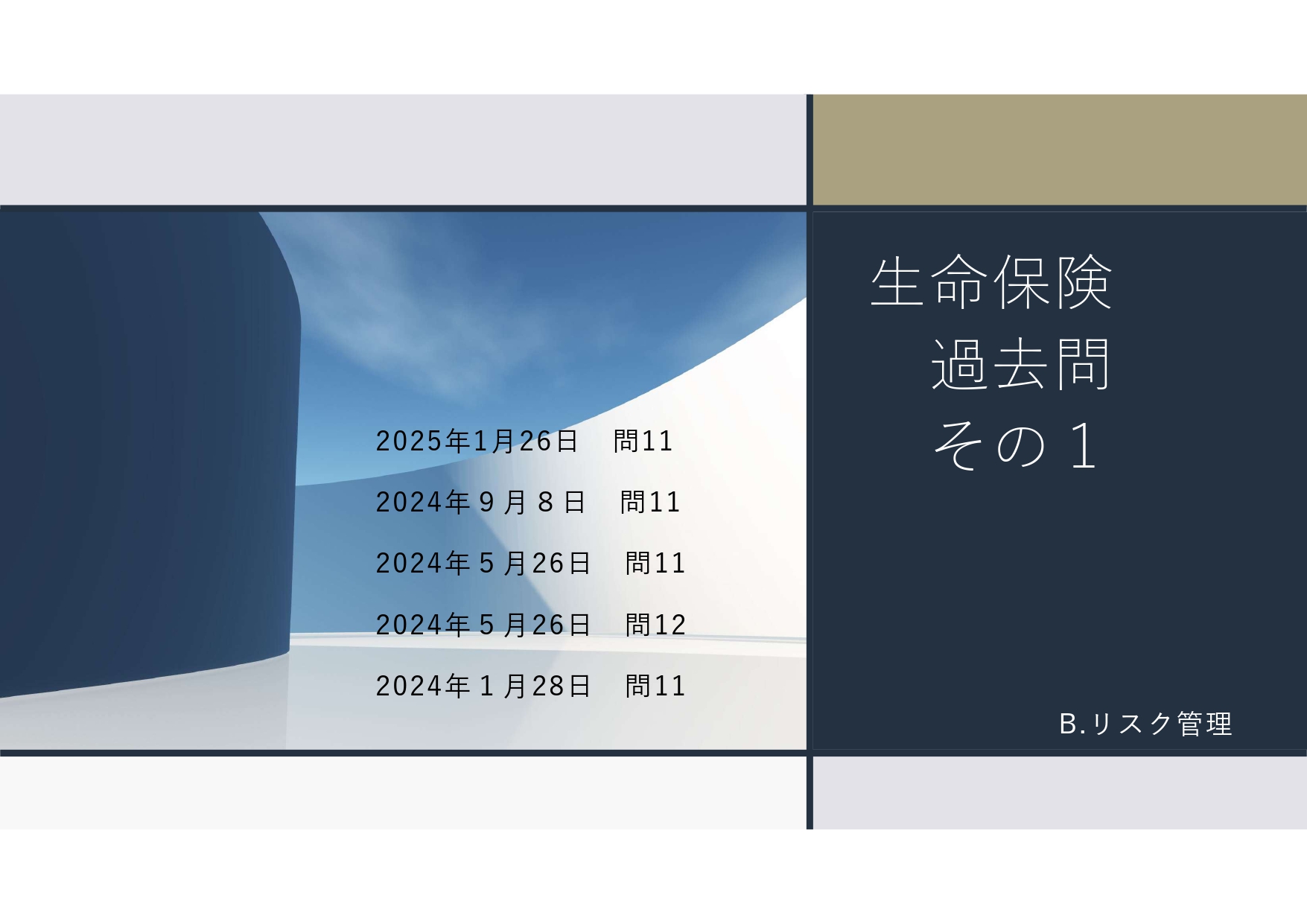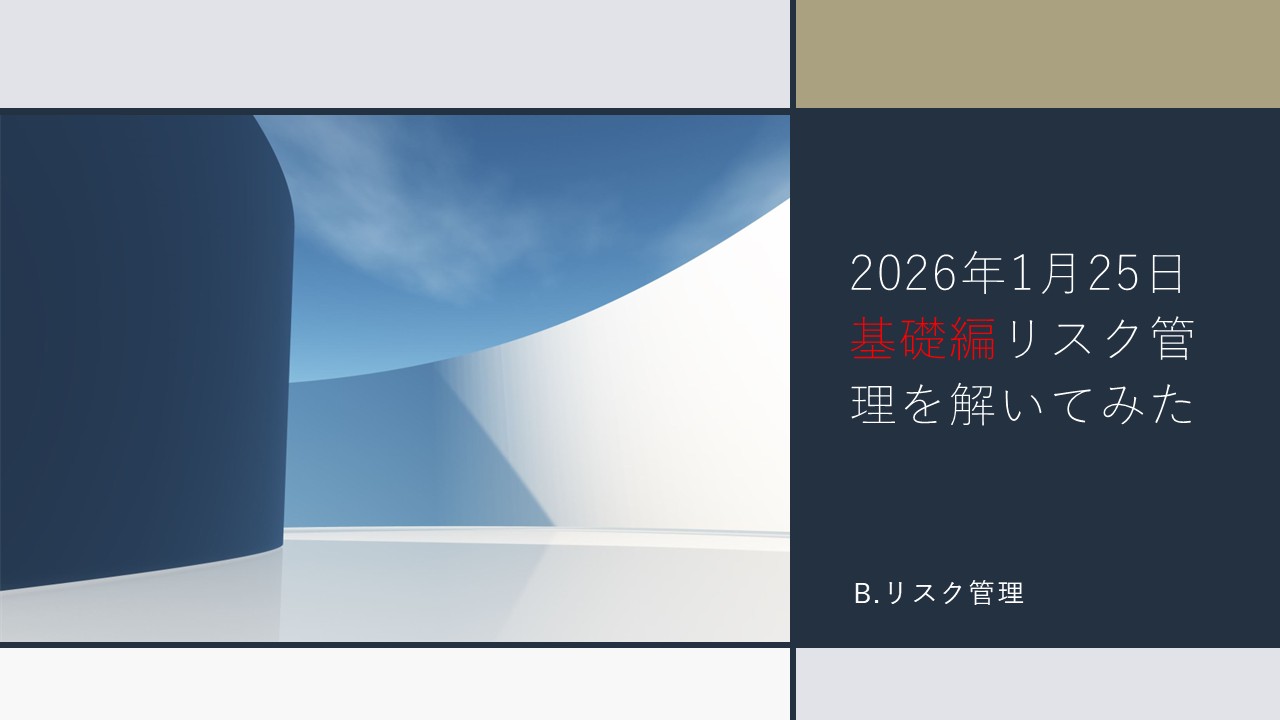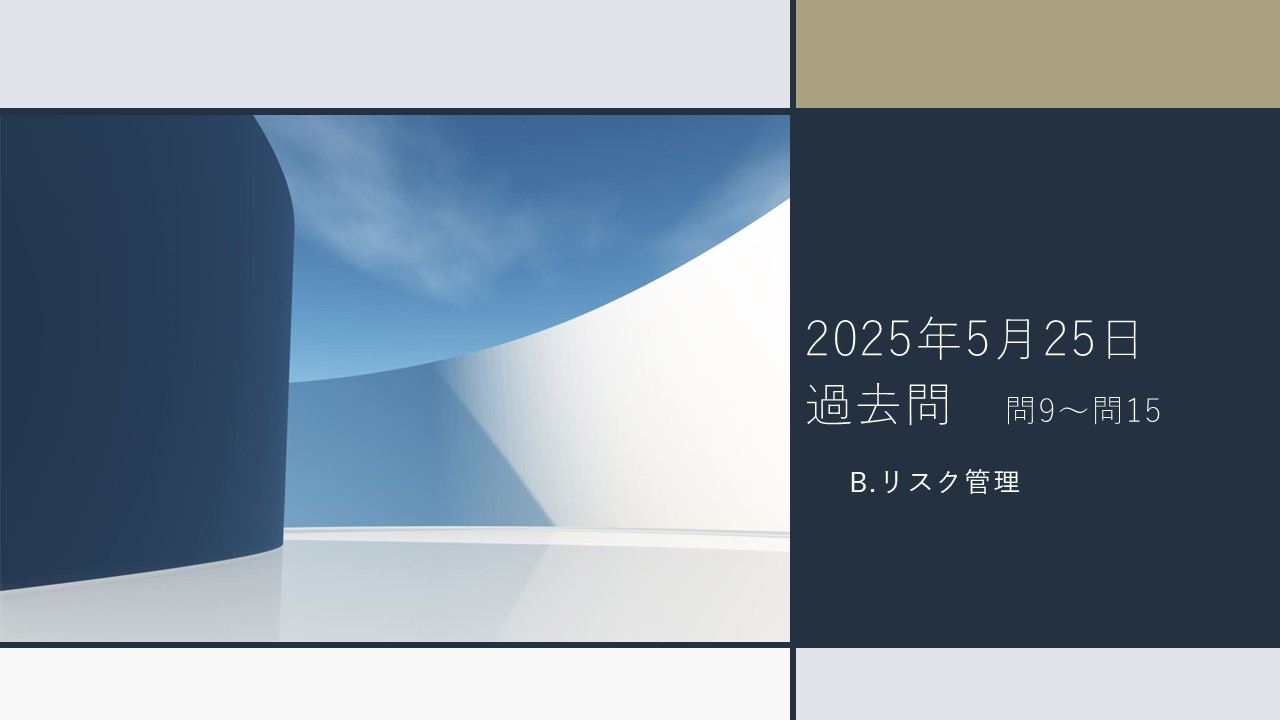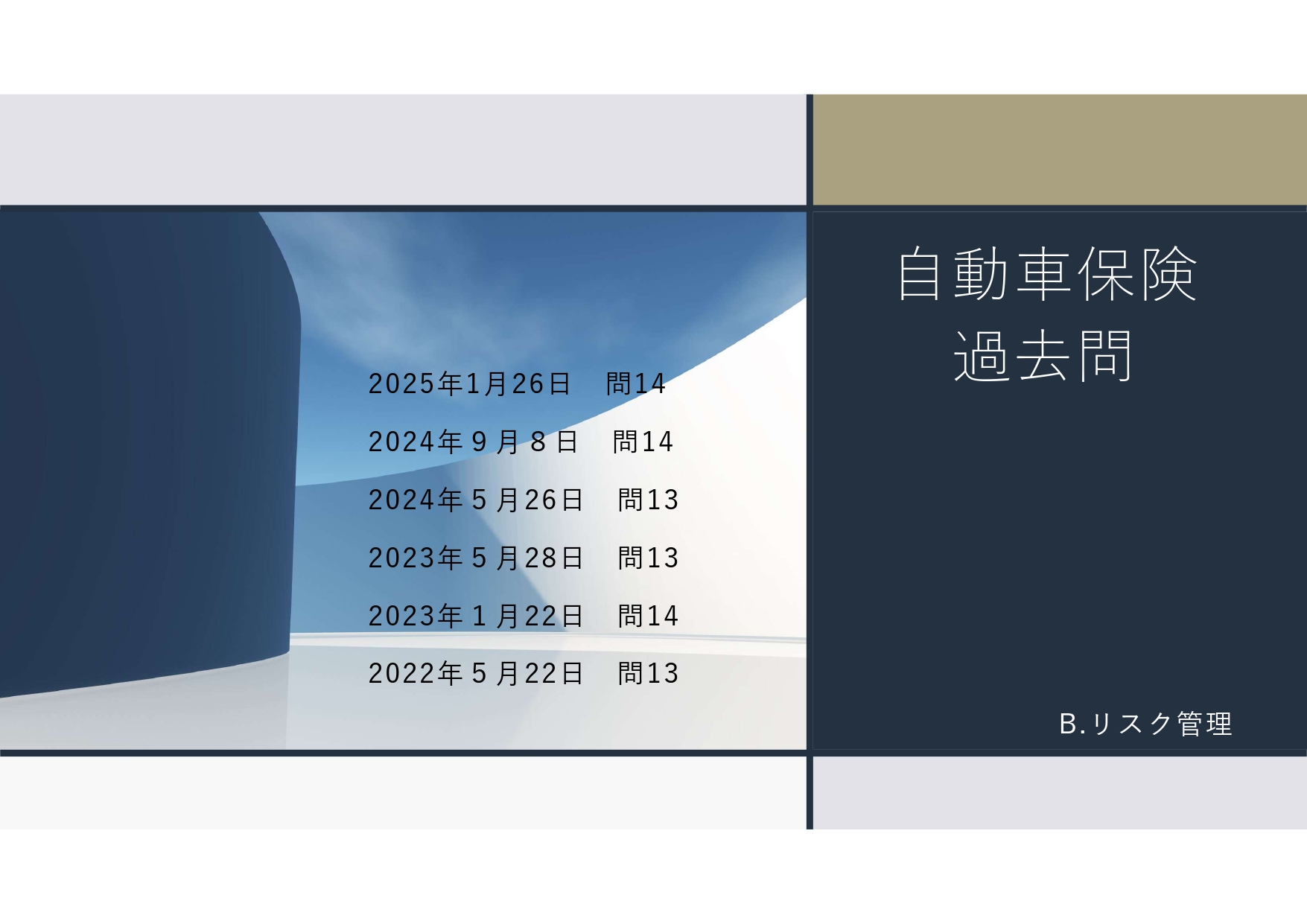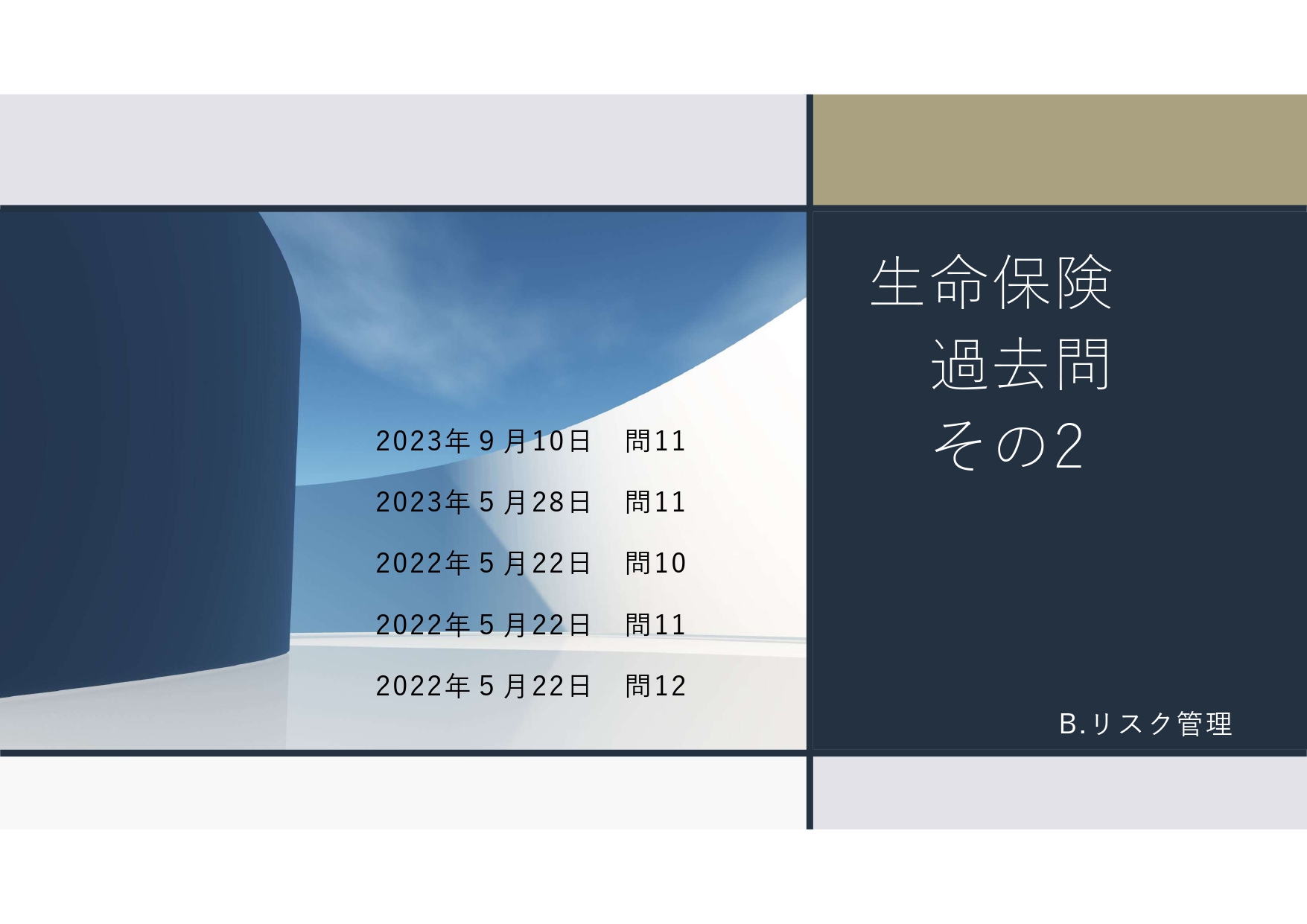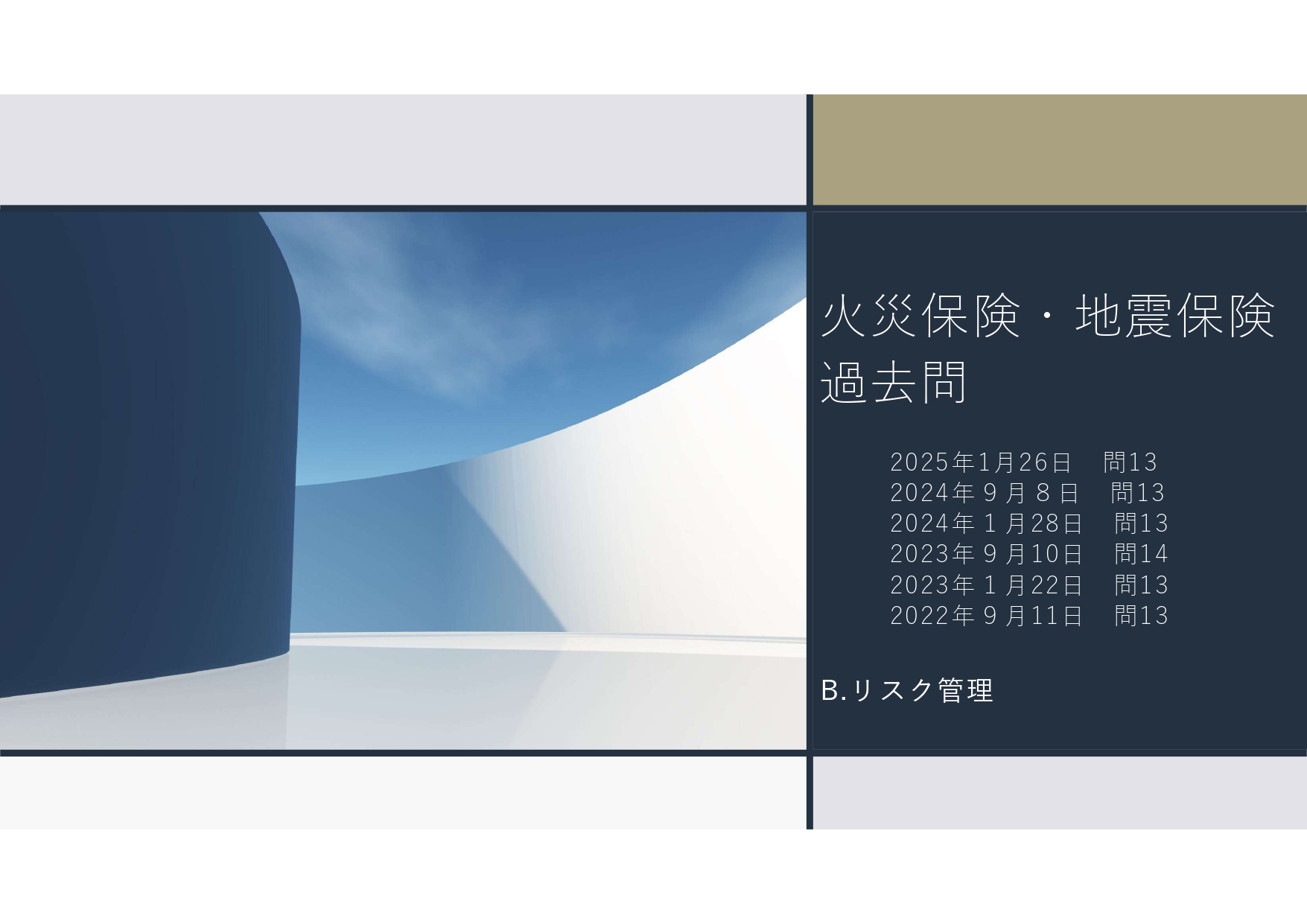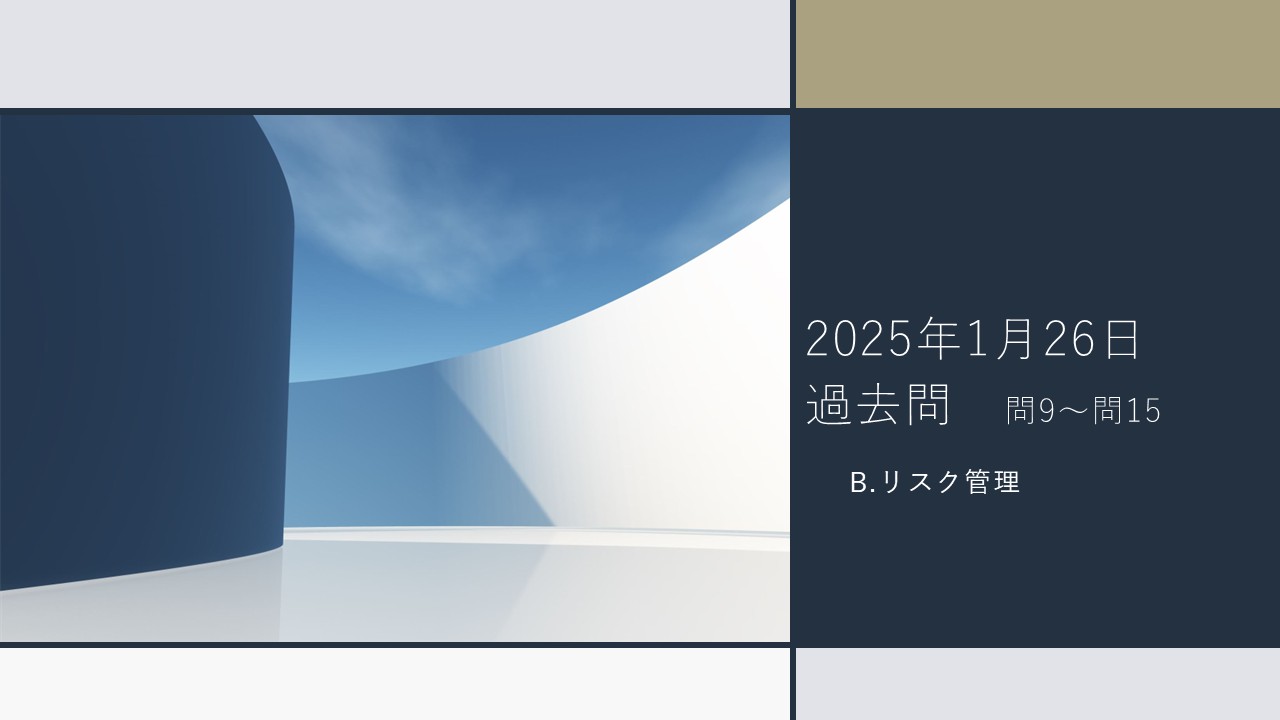2025年9月14日基礎編リスク管理を解いてみた
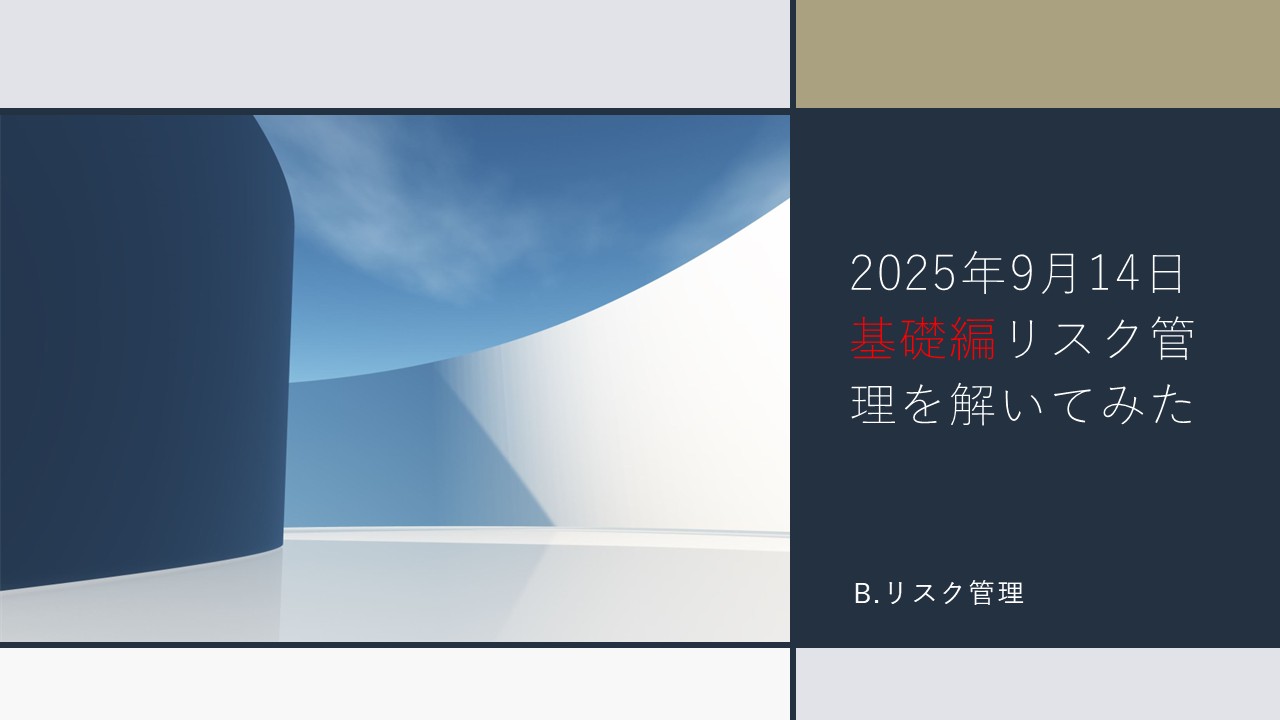
私が不動産とならんで、最も苦手だったのがリスク管理です。
FP1級を受験した当初、この分野は捨てていました。
理由は簡単で、応用編で受験科目でなかったからです。
2025年5月の学科試験で合格することができたのですが、それ以前では2021年1月に応用編でかなり手ごたえがあり、比較的合格に近づいたことがあったのですが、まさかのリスク管理が1問しか正解でなく不合格となったことがあります。
これではいけないと慌ててリスク管理の勉強を開始しました。
参考までに、苦手を緩和した手順をちょっと紹介します。他の分野でも応用できるかもしれません。
先ずは、過去問の徹底分析です。特にリスク管理は法改正が少ないので過去問を3年分くらい解きました。
以上(笑う)です。
厳密には、過去問を分類して、それぞれのジャンルごとに分析しました。
この過去問分析については過去に記事にしていますのでリンクを貼っておきます。
今回も出所:一般社団法人金融財政事情研究会です。
問9 生命保険の契約者配当金
| 《問9》 生命保険の契約者配当金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 (a) 「3利源配当タイプ」の有配当保険は、保険料の算定にあたって使用する3つの基礎率とそれらの実績率との差から生じた 利差益、死差益および費差益に基づく剰余金を、契約者配当金として分配するタイプの保険である。 (b)「利差配当タイプ」の有配当保険の保険料は、保険金額や保険期間等の他の条件が同一であれば、一般に、「3利源配当タイプ」の有配当保険の保険料よりも高い。 (c)有配当保険の契約者(=保険料負担者)が、保険期間中に受け取った契約者配当金は、配当所得として所得税の課税対象となり、保険期間満了時に満期保険金とあわせて受け取った契約者配当金は、一時所得として所得税の課税対象となる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

いくつあるか問題は苦手なんだよな~まさかの全部正解や全部不正解があるからね。
(a) 利差益、死差益および費差益ってちょっと聞き馴染みがない言葉だな
(b) 「利差配当タイプ」の有配当保険 と「3利源配当タイプ」どっちが保険料が高いかってわからないけど、優れている方が高いと考えるしかないね。
(c) 生命保険の税金関係は苦手なんだよね。

(a) 利差益、死差益および費差益これが正しいと思うけどな。
(b) 「利差配当タイプ」の有配当保険 と「3利源配当タイプ」を比べると後者が高くなるからこれが間違いだね。。
(c) 保険期間中に受け取った契約者配当金は、支払保険料から控除し課税されるが正しいからこれも間違いかな。
問10 生命保険の各種特約
| 《問10》 生命保険の各種特約の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が6カ月以内と判断された場合に、所定の金額の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約であり、特約保険金を受け取った後に被保険者が余命として判断された期間を過ぎて生存した場合であっても、特約保険金を返還する必要はない。 2) 特定損傷特約は、被保険者が不慮の事故により事故の日から所定の期間内に骨折、関節脱臼等に対する治療を受けた場合に給付金が支払われる特約であり、同一の事故による右腕の骨折に対する治療と左肩の関節脱臼に対する治療を受けた場合であっても、給付金が支払われるのは1回である。 3) 災害割増特約は、被保険者が不慮の事故による傷害が原因で死亡した場合には災害死亡保険金が支払われ、不慮の事故による傷害が原因で所定の身体障害状態に該当した場合には障害の程度に応じた金額の障害給付金が支払われる特約である。 4) 指定代理請求特約は、被保険者が受取人となる保険金等の支払において、被保険者が傷病により保険金等の請求を行う意思表示ができない場合やがん等の傷病名の告知を受けていないことにより保険金等の請求ができない場合などに、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金等を請求することができる特約である。 |
正解3

1)リビング・ニーズ特約は頻出だけど、確かに余命宣告を過ぎて長生きするってありえるよね。どうなるんだろう?
2)過去の経験から、「不慮の事故」にあたるかどうか考えたことがあるから、これはわかるよ。
3)私自身が障害者なので、この問題は敏感に反応できるね。
4)これは正しいね。特約をつけるタイミングで代理人を指名する感じだろうね。

1)これは適切だね。リビング・ニーズ特約の注意点は使い残しに対して相続税がかかることだね。
2)これは正しいよ。同一の不慮の事故による特定損傷に対する給付が1回限りとなるよ。
3)これが誤りだね。障害給付金は、傷害特約とは異なり、高度障害に至らない程度の障害状態では給付されないんだね。前半の災害死亡保険金は受け取れるよ。
4)これは正しいよ。指定代理請求できるのは①配偶者、②直系血族、③三親等内の同居している親族、というのも覚えておくといいね。
問11 団体信用生命保険
| 《問11》 金融機関の住宅ローンを利用する際に加入する団体信用生命保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 団体信用生命保険は、契約者(=保険料負担者)および被保険者を債務者である住宅ローン利用者、保険金受取人を債権者である金融機関とする生命保険である。 2) 団体信用生命保険は、クーリング・オフ制度による保険契約の申込みの撤回等をすることができない。 3) 団体信用生命保険の保険料は、住宅ローン利用者の契約時の年齢、性別および債務残高に応じて算出される。 4) がん保障特約付団体信用生命保険のがん保障特約部分の保険料については、住宅ローン利用者の介護医療保険料控除の対象となる。 |
正解2

団信は聞いたことがある。団信を使って家を建てたご主人が亡くなって、住宅ローンが免除されている人の話を聞いたことがあるな。

1)団体信用生命保険の契約者は金融機関だから不適切だね。
2)団体信用生命保険はクーリングオフできないね。法人の契約だからね。
3)団体信用生命保険は債務残高に応じて変動するけど、年齢によって変動することはないね。一定年齢以上だと加入できなかったりするけどね。
4)団体信用生命保険の契約者は金融機関だから、被保険者の生命保険控除は使えないね。
問12 個人年金保険料税制適格特約
| 《問12》 個人年金保険料税制適格特約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、契約者(=保険料負担者)、被保険者および年金受取人は同一人でなければならない。 2) 個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、当該保険契約は、年金受取人の年齢が60歳に達した日以後に終身にわたって年金が支払われるものでなければならない。 3) 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、保険料を全期前納した場合、翌年分以降、個人年金保険料控除の適用を受けることができない。 4) 個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険において、年金年額の減額を行い返戻金が発生した場合、返戻金は所定の利息を付けて積み立てられ、年金支払開始日に増額年金の買増しに充てられる。 |
正解4

個人年金保険は、将来、老齢年金で生活するのに不安を感じる方に民間の保険で補おうとう内容の保険だね。
iDeco、新NISAなどあるけど、どうやって老後の生活を補えばいいのか、団塊ジュニア世代には深刻な問題かもしれないね。

1)個人年金保険に個人年金保険料税制適格特約を付加する場合、必要な条件は、「年金取人が契約者またはその配偶者であること」、「年金受取人が被保険者と同一人物であること」、「保険料の払込期間が10年以上」、「年金の受取開始が60歳以降で、かつ受取期間が10年以上の定期年金または終身年金であること」を満たすことなので、必ずしも契約者・被保険者・年金受取人が同一である必要はないよ。
2)終身にわたって年金が支払われるものでなければならない。ということはないね。
‘3)個人年金保険料税制適格特約は税制適格要件を満たすことで全期間にわたる個人年金保険料控除を受けることができるよ。
4)これが正しいね。減額したからといって払い戻しが受けれるわけじゃないということだね。
問13 火災保険および地震保険
| 《問13》 火災保険および地震保険の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 火災保険の対象となる住宅建物は、その構造により、M構造、T構造、H構造に区分され、所在地が同じであれば、適用される保険料率はH構造が最も高い。 2) 住宅建物を対象として火災保険を契約する場合、その保険料の算定にあたって使用される水災料率は、所在地の水災リスクに応じた3つの等地区分に基づいて決められている。 3) 居住用建物を対象とする地震保険の保険料率(基本料率)は、イ構造、ロ構造の構造区分および所在地による3つの等地区分により都道府県ごとに決められている。 4) 地震保険の保険料の耐震等級割引には、居住用建物の耐震等級に応じて50%、30%、10%の3区分の割引率がある。 |
正解2

1)H構造って木造という覚え方をしていたな。
2)水災料率って初めて聞いた言葉だ。初めてだと選択肢から除外しちゃう癖があるんだよね。
3)地震保険と火災保険の料率がごっちゃになるんだよね。
4)地震保険の保険料の耐震等級割引以外にもあった気がする。

1)M構造(マンション構造)、T構造(耐火構造)、H構造(非耐火構造)で、リスクが高いのはH構造だから、正しいね。
2)水災料率は建物の市区町村ごとに5段階の「水災等地区分」に細分化されてるんだね。これが間違いだね。
3)これは正しいね。しかし昨今、保険料率が低い地域=リスクが低いとも言えなくなってるよね。
4)地震保険の保険料の割引制度には、「建築年割引」「耐震等級割引」「免震建築物割引」「耐震診断割引」があり、それぞれの割引制度の重複適用はできる。というのが過去にも出題されているよ。
問14 自賠責保険
| 《問14》 自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 交通事故の加害者が契約している自賠責保険の保険会社と任意の自動車保険の保険 会社が異なる場合、被害者は、任意の自動車保険の保険会社に請求することにより、 自賠責保険の保険金を含めて保険金が支払われる一括払制度を利用することができる。 2) 交通事故の被害者および加害者は、加害者が契約している自賠責保険の保険会社に 治療費などの当座の費用として仮渡金の支払を請求することができ、その金額は、被 害者の傷害の程度に応じて5万円、20万円、40万円である。 3) 自賠責保険の保険金の支払において、交通事故の被害者に重大な過失があり、被害 者の過失割合が7割以上となる場合、原則として、損害額が保険金額に満たないとき は損害額から、保険金額以上となるときは保険金額から、所定の割合による減額が行 われる。 4) 自賠責保険では、複数台の自動車による事故において、共同不法行為により他人の 身体に損害を与えた場合、加害者それぞれの自賠責保険に係る保険金額を合算した金 額が保険金の支払限度額になる。 |
正解2

交通事故って嫌だし、運転は気をつけないといけないね。
「自分の家族が事故にあったらどうしよう」という意識で運転しなきゃね。

1)任意・自賠一括払い制度というのがあるので、これは適切だよ。
2)交通事故の被害者が加害者が契約している保険会社と直接交渉することはできないよ。よってこれが不適切だね。
3)これは正しいね。過失割合7割というのは覚えておいてもいいかもね。
4)これは正しいし、よく出題される内容だね。
問15
問15 事業活動に係る各種損害保険
| 《問15》 事業活動に係る各種損害保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。 1) 家電修理業者が生産物賠償責任保険(PL保険)に加入することで、顧客から預かったテレビを修理中に誤って損壊させ、修復不能にした場合など、仕事の結果が原因となり、他人の身体や財物に損害を与えたことによる賠償責任に備えることができる。 2) 金属部品製造業者が機械保険に加入することで、従業員の誤操作等によって機械設備に不測かつ突発的な事故が生じて近隣の建物を損壊させた場合など、仕事の遂行が原因となり、他人の身体や財物に損害を与えたことによる賠償責任に備えることができる。 3) 建設業者が請負業者賠償責任保険に加入することで、請け負った工事の現場に設置した資材置場の管理ミスによって材木が倒れ、通行人がケガをした場合など、仕事の遂行に用いるための施設が原因となり、他人の身体や財物に損害を与えたことによる賠償責任に備えることができる。 4) 会社役員賠償責任保険(D&O保険)に加入することで、被保険者である会社役員が業務の遂行に起因して損害賠償請求を受けた場合に、判決に基づく損害賠償金や和解金のほか、罰金や課徴金等を支払うことによって被る損害に備えることができる。 |
正解3

会社経営をしていると、個人よりも多額の損害賠償を追うリスクがあるだろうから、事業によって適切な保険に加入しておくことが必要だね。それこそまさにリスク管理といえるのかもね。

1)この場合、保管物賠償責任補償(預かり品賠償責任保険)が使える可能性があるね。
2)機械保険は不測かつ突発的な事故を受けた場合の機械の修理費用を補償するための保険だね。
3)請負業者賠償責任保険はこの説明で正しいと思う。
4)D&O保険では役員が負う罰金や課徴金の支払いは基本的に補償の対象外とされているよ。