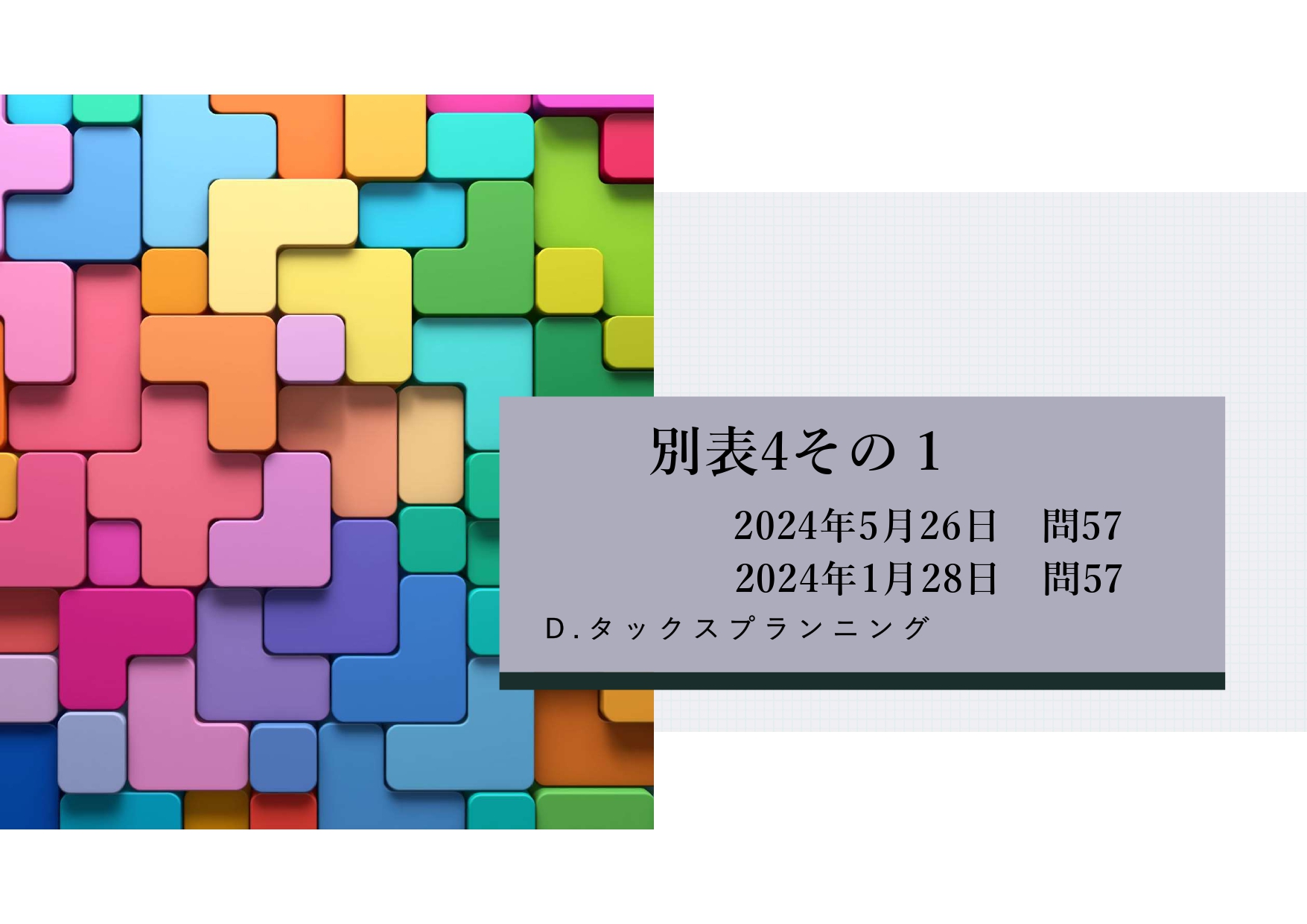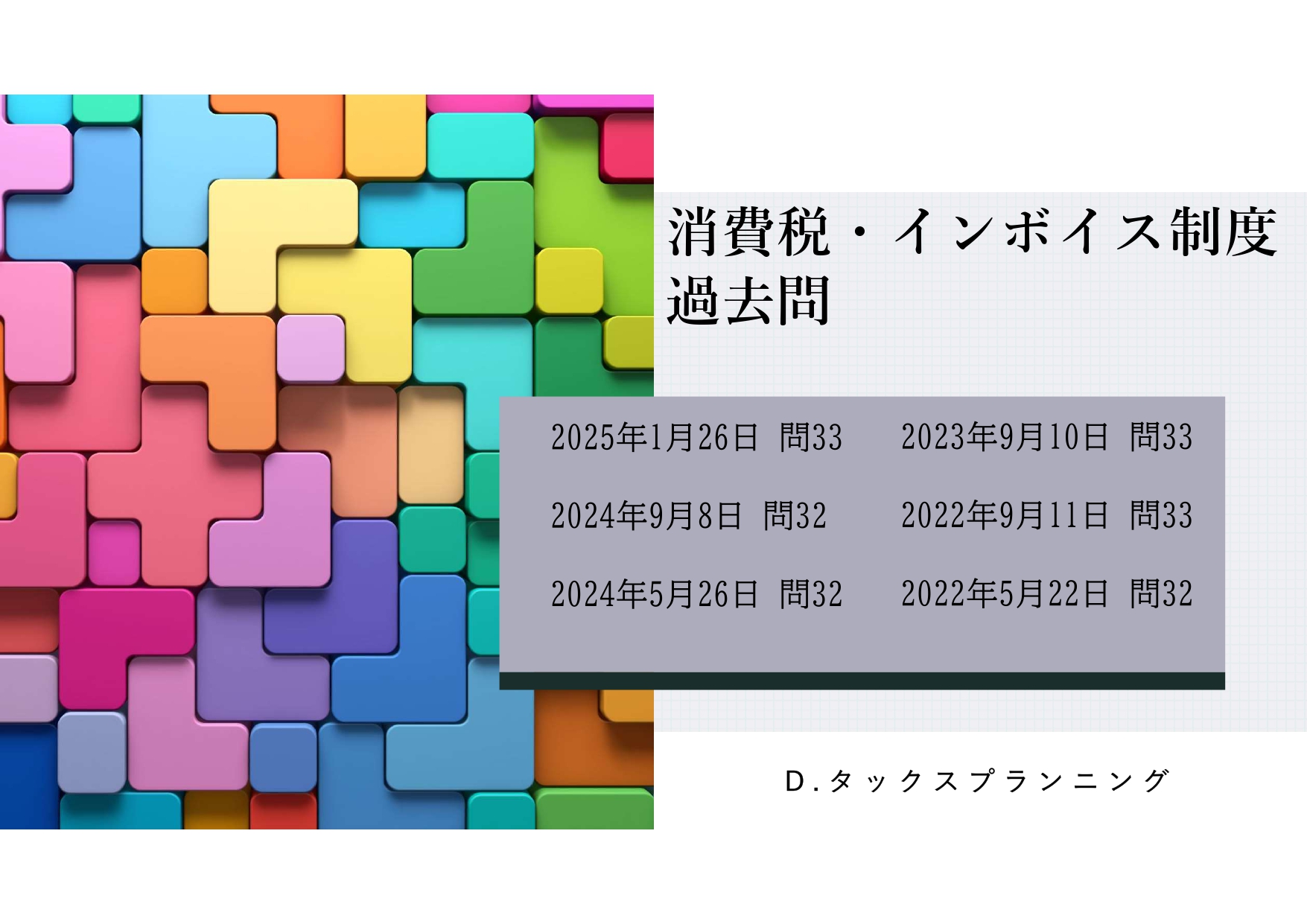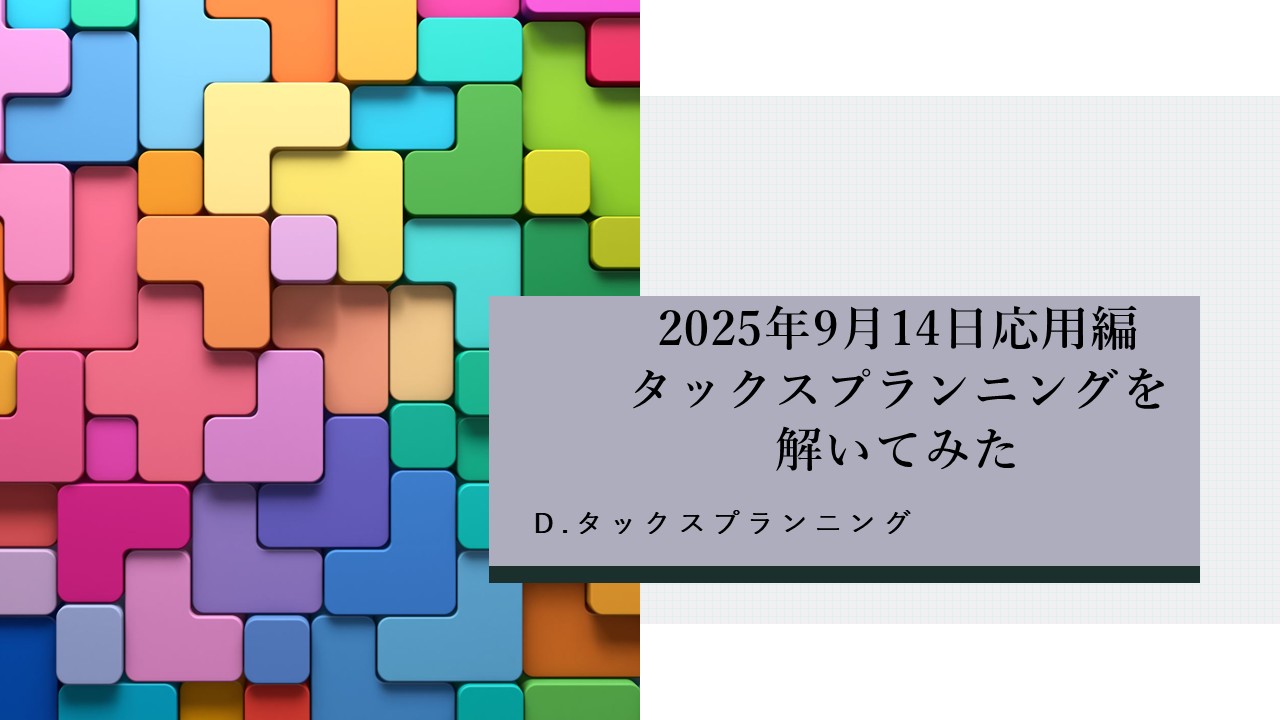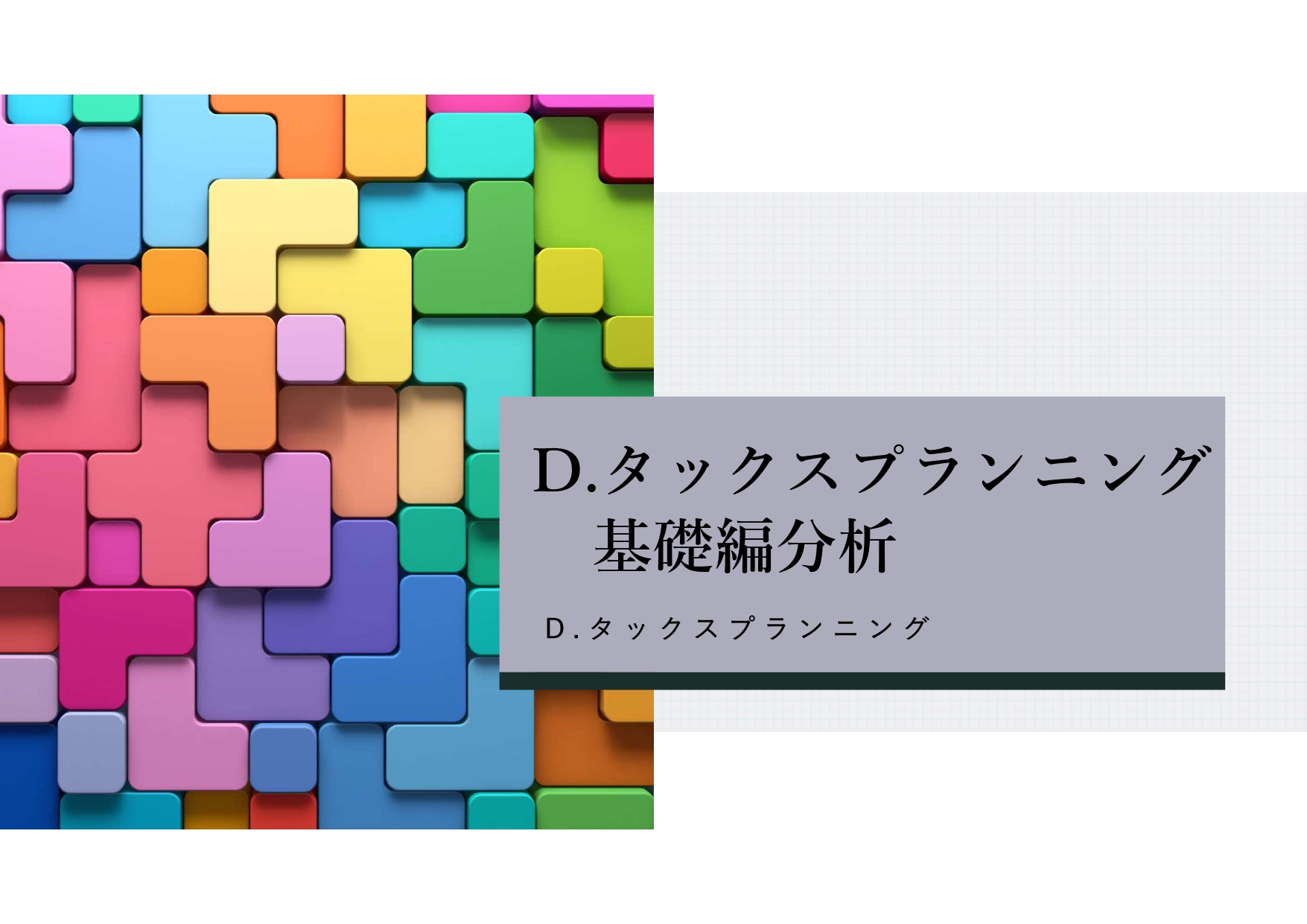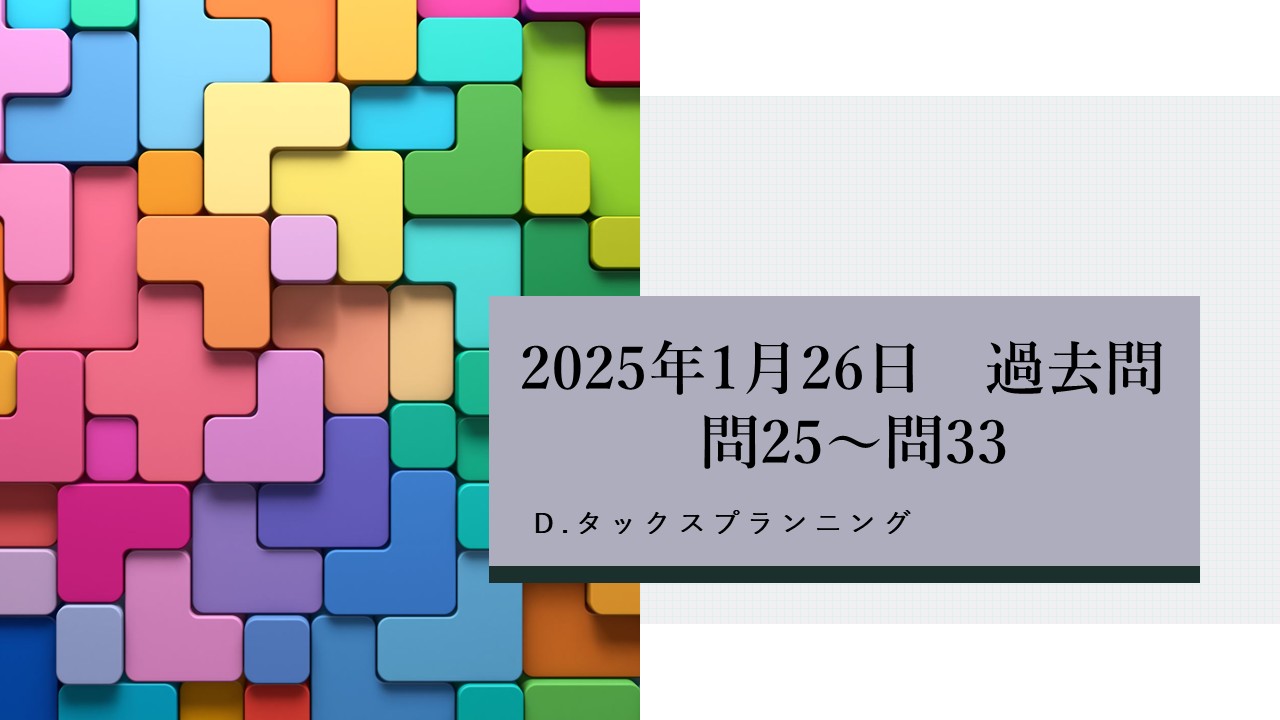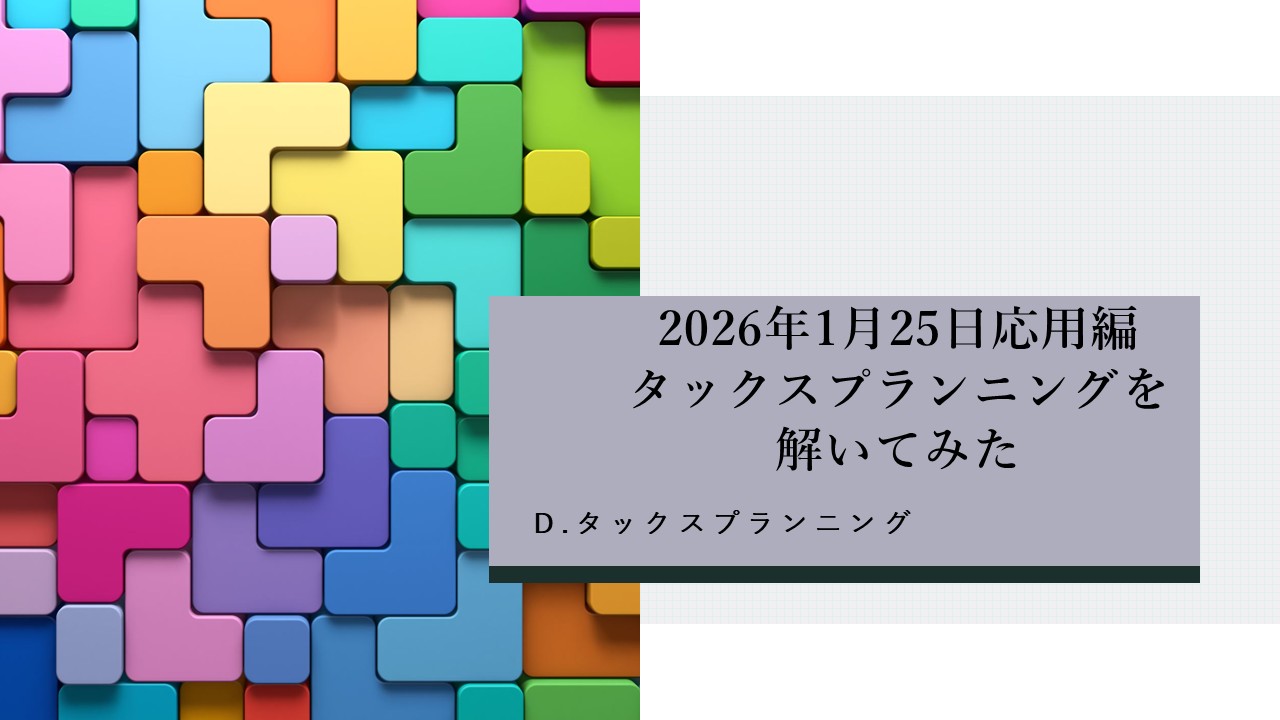2025年9月14日基礎編タックスプランニングを解いてみた
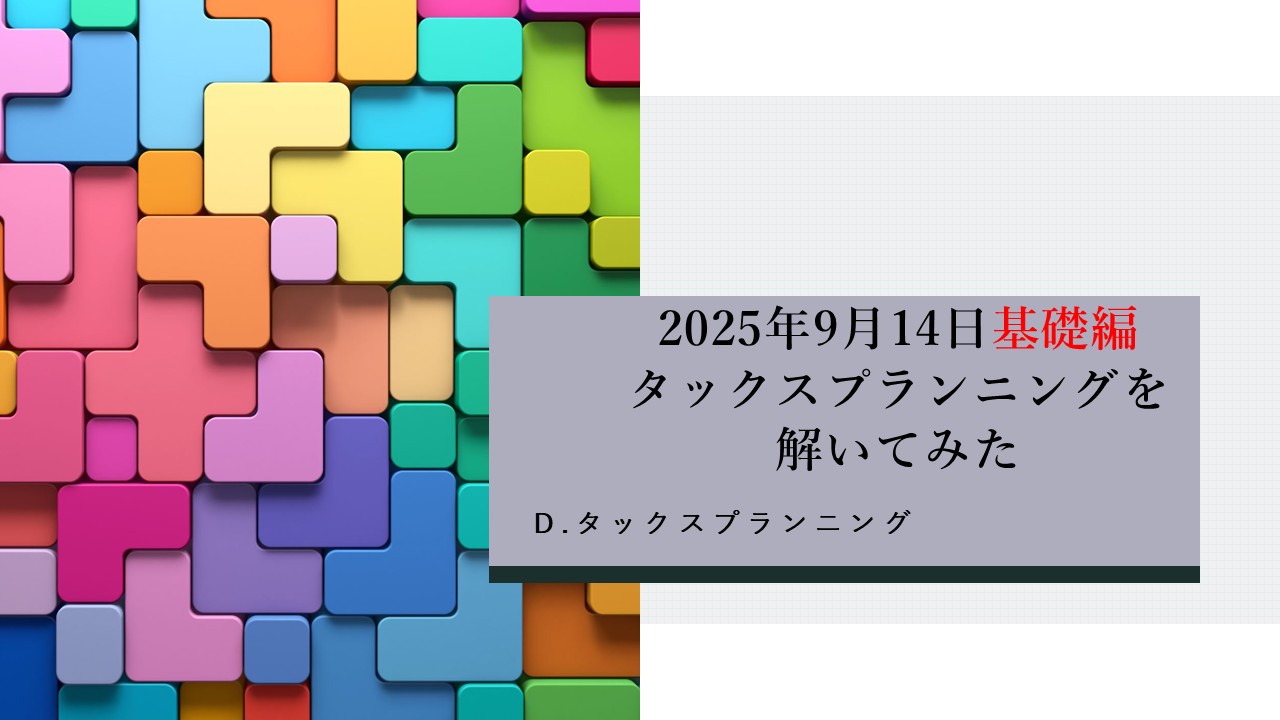
私は2019年にFP2級を合格しました。私の合格証は平成31年の日付が入っています。
その後、FP1級の勉強を始めた、2025年5月試験でやっと学科試験合格を果たしまし一部合格をつかむことができたので、なんと5年間FP1級の勉強にあけくれたことになります。
その間、心臓の手術をして心臓に人工弁を入れ、障害者手帳の保持者になりました。
その間、右目を失明し、FPの勉強をあきらめようかと思っていた際に、
入院中の病床で「ほんださん / 東大式FPチャンネル」というユーチューブのチャンネルに出会い、あきらめない決心をしました。
ほんだ先生もユーチューブでおっしゃっていた通りタックスプランニングから勉強を始めるのが私もベストな選択だと今は私も思っています。
全科目において税金というのは必ず登場し、しかも間違えるポイント、悪く言えばひっかけに使われることが多いです。
それでは、今回は2025年9月14日基礎編タックスプランニングをみていきたいと思います。今回も、問題は全て 出所:一般社団法人金融財政事情研究会です。
問25 事業所得
| 《問25》 居住者に係る所得税の事業所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 個人事業主が、販売用の棚卸資産を自家消費したときは、事業所得の金額の計算上、原則として、当該棚卸資産の販売価額の50%相当額を総収入金額に算入する。 2) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の遂行上、取引先に対して貸し付けた貸付金の利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。 3) 個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する建物を賃借して事業所得を生ずべき事業の用に供している場合、事業所得の金額の計算上、その配偶者に支払う家賃は必要経費に算入することができないが、その配偶者が納付した当該建物に係る固定資産税に相当する金額は必要経費に算入することができる。 4) 個人事業主が、事業所得を生ずべき事業の用に供した減価償却資産の使用可能期間が1年未満である場合、事業所得の金額の計算上、原則として、その取得価額の全額をその事業の用に供した年分の必要経費に算入する。 |
正解1

勉強を始めたころ、所得の種類10種類を懸命に覚えたけど事業所得は、頻出の問題だね。ある程度パターン化されているから過去問をひたすら解くのがいいかもね。

1)販売用の棚卸資産を自家消費したときは原則として、当該棚卸資産の販売価額で計上することになるけど、販売価額の70%相当額を総収入金額に算入することもできるからこれが不適切だね。
2)この選択肢の類似問題は2022年9月試験の問25でも出題されているね。正しいよ
3)この選択肢の類似問題は2020年1月試験の問25で出題されたものだね。正しいよ
4)この選択肢も難しいね。実際に事業をされている方は税理士さんに相談しながら処理しないといけないね。
問26 譲渡所得
| 《問26》 居住者に係る所得税の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 借地権を有する者が当該借地権の設定されている底地を取得し、その後、その土地の全部を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該土地の取得日は、底地に相当する部分と借地権に相当する部分とに分けて判定する。 2) ハウスメーカーに請け負わせて建築した自宅の建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、当該建物の取得日は、当該建物の引渡しを受けた日となり、請負契約を締結した日とすることはできない。 3) 資産を個人に対して通常の取引価額の2分の1未満の金額で譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡した時の通常の取引価額を総収入金額に算入する。 4) 所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、当該建物の賃借人に支払う立退料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用として総収入金額から控除する。 |
正解3

譲渡所得って不動産分野の問題かと思えるくらいの内容で、勉強開始時から大の苦手だったんだよね。
逆に考えれば、不動産分野を勉強するのに譲渡所得やそれに係る税金から勉強しておくと、最後の実技試験でも非常に役に立つよ。

1)これは正しいね。実技試験で問われそうな問題だね。
2)これも正しいね。実際オーナーが所有者のなるのは引渡しを受けた日だよね。
3)これが誤りだね、2分の1未満であれば、贈与とみなされるという考えでいいんじゃないかな。
4)これは正しいね。立退料は譲渡費用になるね。
問27 所得税の所得控除
| 《問27》 居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 医療費控除の対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られ、医療費控除額の計算上、支払った医療費から差し引く医療費を補塡する保険金等は、その年中に実際に受け取った金額に限られる。 2) 納税者と生計を一にする配偶者に支給される公的年金から介護保険料が特別徴収されている場合、特別徴収された介護保険料は、納税者が確定申告をすることにより、納税者の社会保険料控除の対象となる。 3) 控除対象扶養親族である子を有する納税者とその配偶者が離婚をし、別居している場合において、当該納税者が扶養義務の履行として元配偶者と同居している子の養育費を支払ったときは、当該納税者と元配偶者は、その支払のあった年分において、ともに子に係る扶養控除の適用を受けることができる。 4) 夫と死別した後に婚姻をしていない納税者が寡婦控除の適用を受けるためには、ひとり親に該当しないこと、合計所得金額が一定額以下であることおよび納税者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないことが要件とされ、扶養親族を有することは要件とされていない。 |
正解4

所得控除は条件に当てはまるのか判断するのが難しいよね。概要の説明は必要だけど、細かい内容は税理士さん、社労士さんに相談した方がいいね。間違えたら大変だもんね。

1)実際に年をまたいで入院生活をして、支払いが翌年になるってことはありえるもんね。この場合、実際に治療を受けた年の支払いになるね。
2)奥さんに支給される公的年金から介護保険料は奥さんの社会保険料控除の対象となるから不適切だね。
3)この場合、どちらも扶養控除を受けられるということは無いね。子どもの生計を主として維持している親が受けられるということなので、この記載だけではどちらとはいいがたいね。
4)これが正しいね。最後の「扶養親族を有することは要件とされていない」という表現が解釈に苦しむけどね。
問28 所得税の申告および納付
| 《問28》 所得税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 居住者が、年の途中で国内に住所等を有しないこととなるために納税管理人の届出をした場合、納税管理人は、原則として、当該納税者の所得について、国内に住所等を有しないことになった日から4カ月以内に確定申告をしなければならない。 2) 確定申告により納付すべき所得税額の2分の1に相当する金額以上の所得税を納期限までに納付した者が、納期限までに納税地の所轄税務署長に延納届出書を提出した場合、原則として、その納付した年の5月31日までその残額の納付を延期することができる。 3) 確定申告書を提出し、納付した所得税額が計算の誤りにより過大であったことが法定申告期限後に判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求書を提出して納めすぎた税金の還付を受けることができる。 4) 年末調整の対象となる給与所得者の給与所得以外の所得が一時所得のみである場合に、一時所得の金額に2分の1を乗じた後の金額が20万円以下であるときは、原則として、確定申告書を提出する必要はない。 |
正解1

申告および納付の問題も定番だから、覚えることを推奨するけど、間違いの選択肢は微妙に言葉を変えている場合があるから注意が必要だね。当たり前だけど、
〇〇できる、と〇〇できない、とでは意味が反対になるからね。

1)納税管理人の届出をした場合は翌年2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通じて確定申告及び納税をする必要があるからこれが間違いだね。
よって2)~4)は適切だね。
適切な選択肢を丸暗記するのは、直前の試験対策としては有効だよ。
問29 法人税の各種届等
| 《問29》 法人税の各種届等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 内国法人である普通法人は、事業年度が6カ月を超える場合、原則として、納税地の所轄税務署長に対し、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内に法人税の中間申告書を提出することとされている。 2) 事業年度開始の時における資本金の額または出資金の額が1,000万円を超える法人は、法人税の申告を、電気通信回線の故障、災害その他の理由により困難であると認められる場合を除き、e-Tax(国税電子申告・納税システム)により行うこととされている。 3) 新たに設立された法人は、原則として、その設立の日以後3カ月以内に、減価償却資産の償却方法の届出書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。 4) 新たに設立された法人が設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その設立の日以後2カ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告の承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することとされている。 |
正解1

法人設立って事業アイデアがあれば、誰でも目指すことだろうし、こういう人に適切なアドバイスをするのがFPの役割のひとつかもね。最初から税理士さんに頼むのってハードル高いかもしれないしね。

1)これが適切だね。この文章は覚える必要があるね。
2)e-Taxが義務化されたのは資本金1億円以上の法人だから間違いだね。
3)減価償却資産の償却方法の届出書の提出期限は最初の確定申告の提出期限だね。棚卸資産の評価方法と一緒だね。
4)第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までだから2カ月じゃないね。
問30 中小企業投資促進税制
| 《問30》 「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除」(中小企業投資促進税制。以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 本制度において、税額控除の適用を受けることができるのは、青色申告書を提出する中小企業者等のうち、資本金の額または出資金の額が1,000万円以下の一定の法人に限られる。 2) 本制度の対象となる資産は、製作後に事業の用に供されたことのない新品の機械装置等であって、一定の中小企業者等が購入し、指定事業の用に供したものであり、本制度の適用を受ける中小企業者等が自ら製作した機械装置等は、本制度の対象となる資産には含まれない。 3) 一定の機械装置等を取得し、本制度による特別償却の適用を受ける場合、その償却限度額は、取得価額の7%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額となる。 4) 本制度による税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、当該事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合、その控除しきれなかった金額について1年間の繰越しが認められる。 |
正解4

中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除はよく出題されるし、特別償却と税額控除の内容を覚えておかないとね。少なくとも令和9年までは出題されそうだからね。

1)税額控除の適用を受けることができるのは個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象だから1,000万円以下じゃないね。
2)Q&A集を見ると自ら製作した機械装置等も対象となるので不適切だね。
3)償却限度額は、基準取得価額の30パーセント相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額というのが正しい表記じゃないかな。
4)これは正しい表記だね。20%を超えた場合1年間の繰越が認められるんだね。
問31 役員給与
| 《問31》 法人税における役員給与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとし、役員に対して支給される給与は、退職給与に該当しないものとする。 1) 役員に対し、事前確定届出給与としてあらかじめ税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、当該役員賞与は、原則として、事前確定届出給与として届け出た金額を限度として損金の額に算入することができる。 2) 新たに設立した法人が、設立時に開始する役員の職務につき所定の時期に支給した給与を事前確定届出給与として賃金の額に算入する場合、原則として、設立後2カ月以内に納税地の所轄税務署長に事前確定届出給与に関する届出をしている必要がある。 3) 役員に対して支給する定期給与を、事業年度開始の日から6カ月経過後に開催した臨時株主総会により増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は定期同額給与に該当せず、増額改定後に支給した全額が損金不算入となる。 4) 業績連動給与として損金の額に算入することができる給与は、業務執行役員に対し、利益等の指標を基礎として算定される額を金銭で支給するものに限られ、株式や新株予約権により支給するものは当該給与に該当しない。 |
正解2

役員給与やストックオプションも出題頻度が高いテーマだよね。税制適格(非適格)ストックオプションが実技試験のテーマになったりするしね。

1)原則として、支給した賞与の全額が損金不算入になるから誤りだね。
2)これが正解だね。創業するときは事業計画を基に事前確定届出給与を届出る場合は2カ月以内だね。
3)増額改定した場合、原則として、増額改定後の定期給与は増額分は税務上損金不算入となるので誤りだね。
4)業績連動給与として損金の額に算入することができる給与に株式そのものやストックオプションも含まれるね。
問32 貸倒損失
| 《問32》 法人税における貸倒損失に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 取引先A社に対して有している売掛金600万円について、A社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合において、当該売掛金について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ、貸倒れとして損金経理をすることはできない。 2) 取引先B社に対して有している売掛金400万円について、B社の資産状況、支払能力等の悪化により取引を停止した時以後6カ月が経過し、かつ、当該売掛金に係る担保物がない場合、当該売掛金の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる。 3) 取引先C社に対して有している貸付金500万円について、C社に更生計画認可の決定があり、その決定により当該貸付金のうち400万円が切り捨てられることになった場合、400万円を貸倒れとして損金の額に算入することができる。 4) 取引先D社に対して有している貸付金300万円について、D社の債務超過の状態が相当期間継続し、当該貸付金の弁済を受けることができないと認められる場合において、D社に対して書面により当該貸付金の全額について債務免除することを明らかにしたときは、300万円を貸倒れとして損金の額に算入することができる。 |
正解2

貸倒って売り手、買い手双方にとって不幸な出来事だよね。経済環境の変化や、消費者行動の変化、場合によっては天災などで起こりうるもんね。
不測の事態に備えることも経営者にとって必要だね。
もし窮地に陥っても落ち着いて、紳士的に対応する必要があるね。
また、最悪の事態を避けるための仕組みを知って、場合によっては頼ることも必要だと思う。

1)これは正しいね。しかし担保の処分で簡単にできるんだろうか?
2)取引を停止した時以後6カ月が経過だけでは貸倒損失を計上することはできないね。回収する努力をすることが必要になるね。
3)これも正しいね。更生計画認可の決定がされた場合、裁判所の指示のもと再建を図ることになるね。
4)これも正しいね。債務免除は書面で行う必要があることと、みなし贈与となることがあるため、税理士さんへの事前相談も必要だね。
問33 消費税における少額特例
| 《問33》 消費税における少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 少額特例は、一定規模以下の課税事業者が行った税込1万円未満の課税仕入れについては、適格請求書の保存がなくても、一定の事項を記載した帳簿の保存により仕入税額控除の適用を受けることができる経過措置である。 2) 少額特例の対象となるのは、課税事業者が、適格請求書発行事業者から行った課税仕入れに限られ、適格請求書発行事業者以外の事業者から行った課税仕入れについてはその対象とならない。 3) 少額特例の対象となる事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下または特定期間における課税売上高もしくは給与支払額の合計額が1,000万円以下の課税事業者である。 4) 少額特例の適用を受けるためには、その適用に係る届出書を消費税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出するとともに、課税仕入れに係る帳簿にその適用を受ける旨を明記しなければならない。 |
正解1

消費税はインボイス制度に苦しめられている受験生も多いかもね。
消費税は歳入に占める割合が所得税、法人税より上の21.6%(令和7年)だからね。
少額特例ってあまり意識していなかった個所だな、ちょっと苦戦しそう。
ひょっとしたら法改正もあるかもしれないから、インボイス制度には注意が必要だね。

1)この説明は正しいね。少額特例=1万円未満は覚えておいてもいいかもね。
2)適格請求書発行事業者以外と行った取引であっても少額特例の対象になるよ。よって誤りだね。
3)基準期間における課税売上高が1億円以下、または特定期間における課税売上高が5千万円以下で、給与支払額は関係ないね。よって違うね。ちなみみに基準期間は前々期、特定期間というのは前事業年度の開始後6カ月間を指すよ。
4)少額特例の適用にあたって事前の税務署等への届出は必要ないよ。
タックスプランニングの問題を見てきたけど、誰もが身近に接しているものであり、正しい知識を持って納税を行う必要があるね。
他の分野でもいえることだけど、収めた税金が少なければ指摘をするけど、収めすぎても、何も言ってくれません。
補助金でもそうですが、気付いて、申請すればお金を受け取れる可能性がありますが、見落としていたら、行政から教えてくれるということはありません。