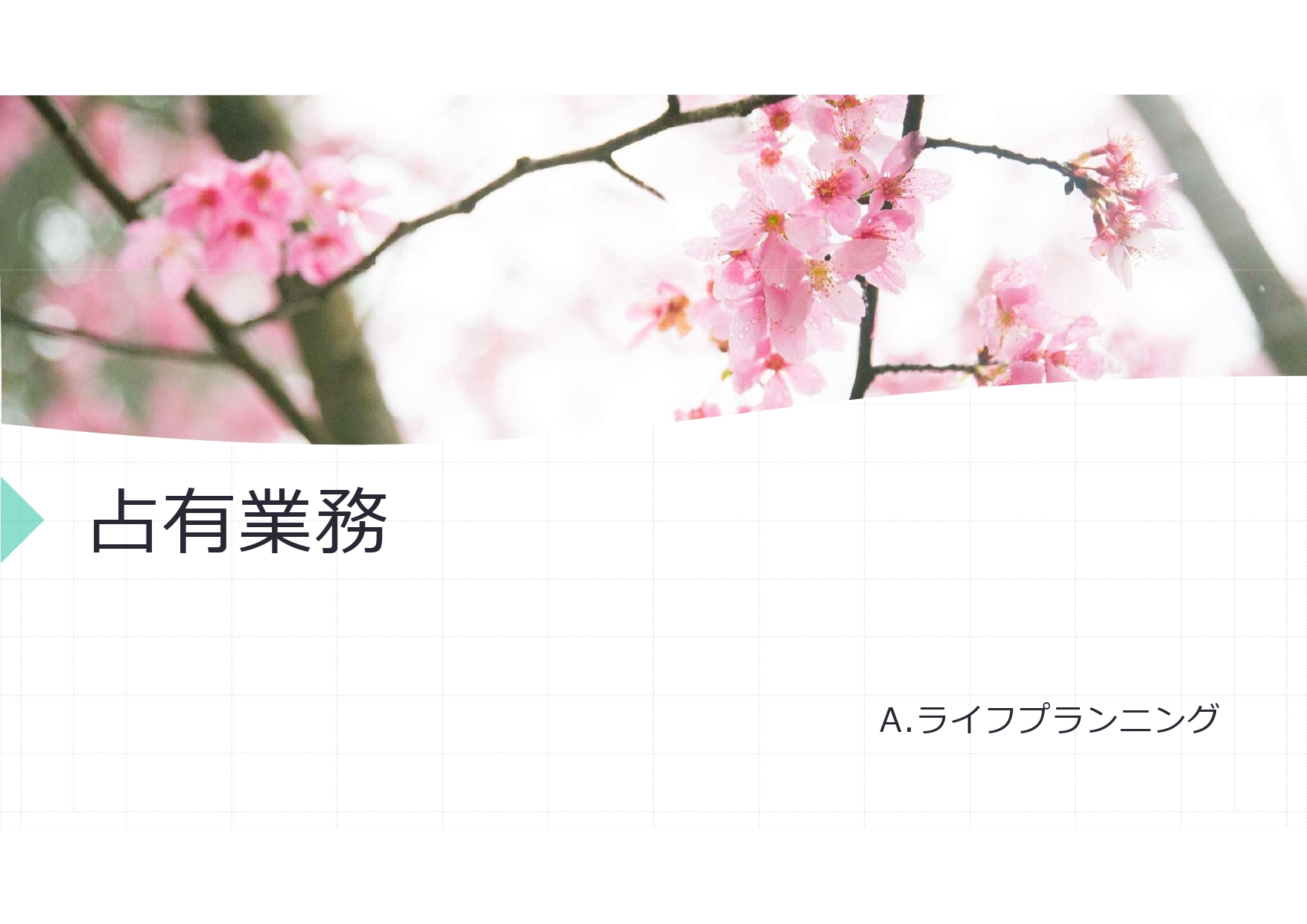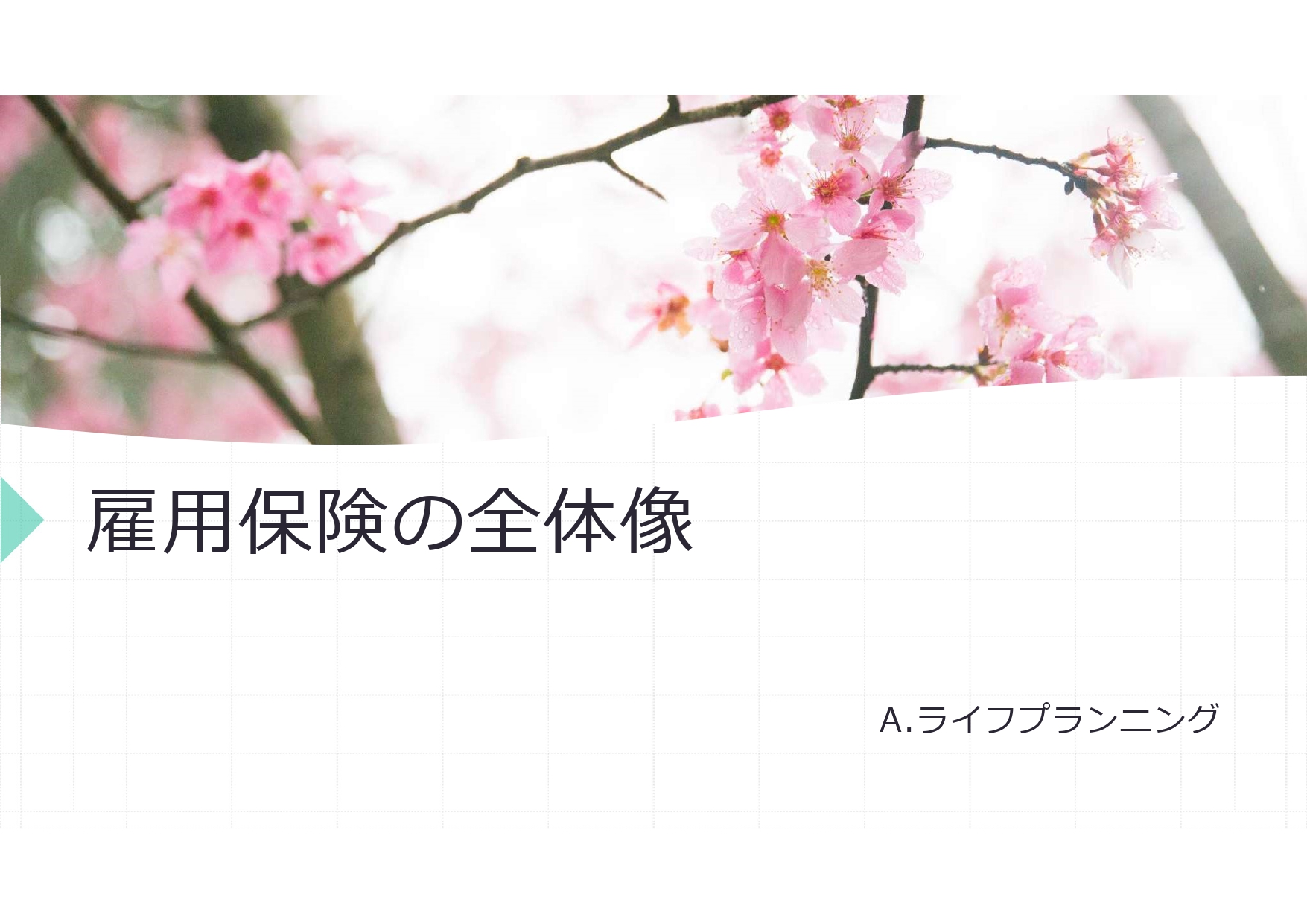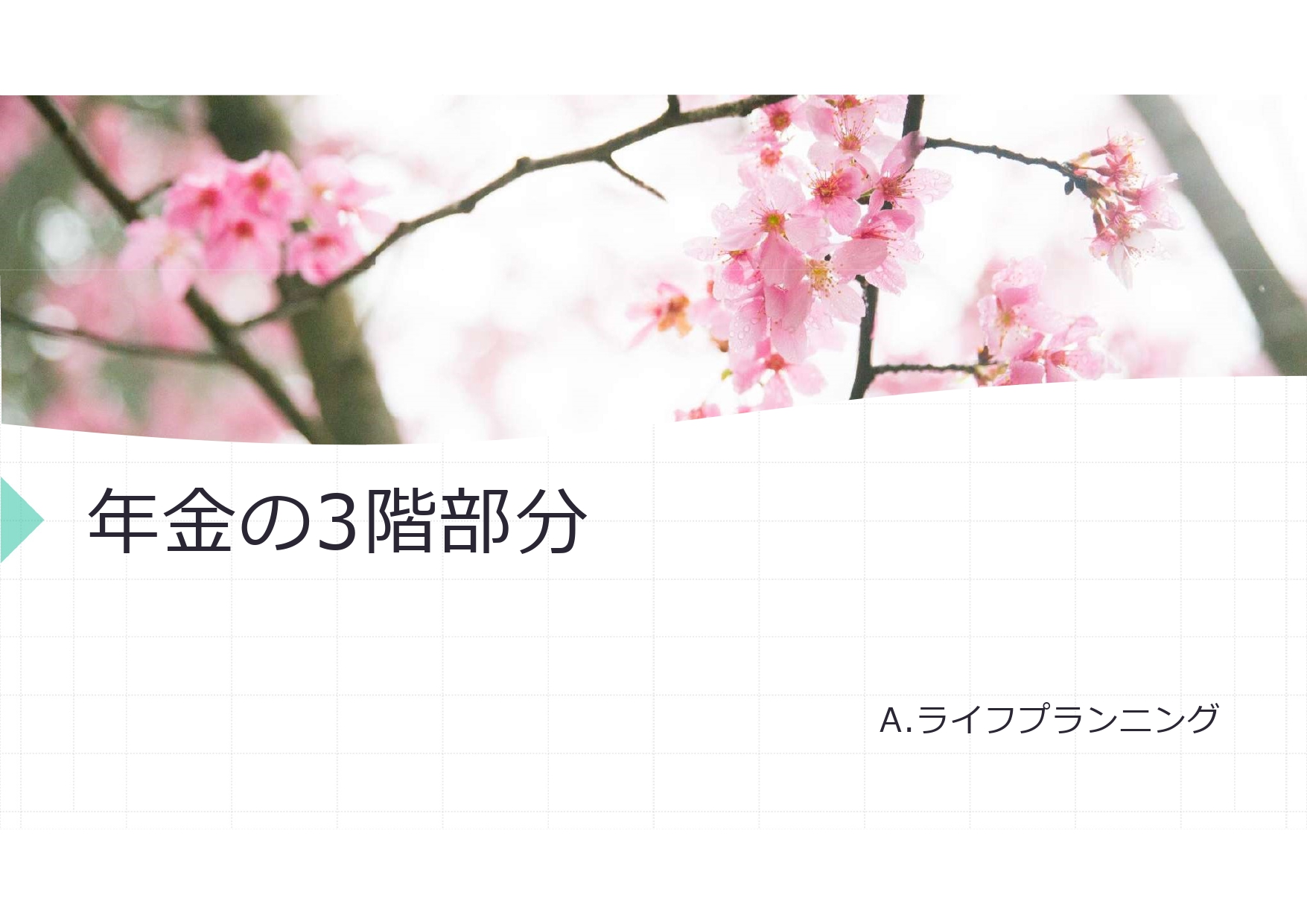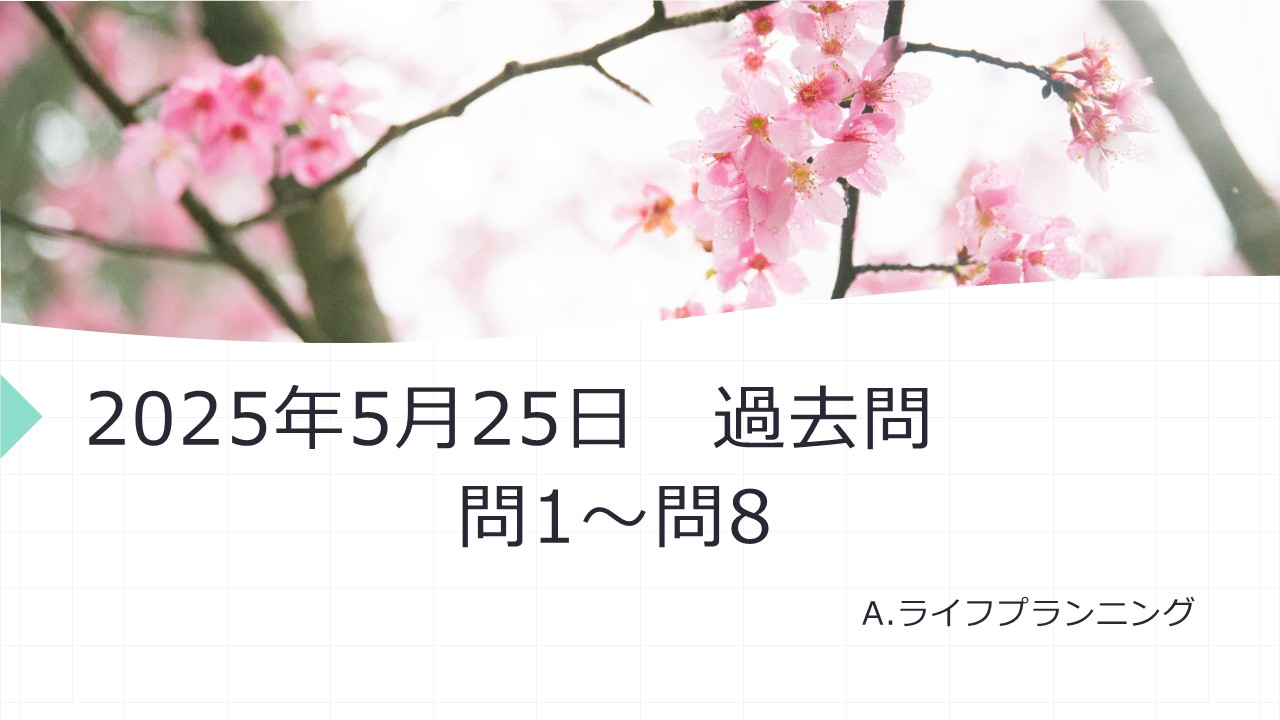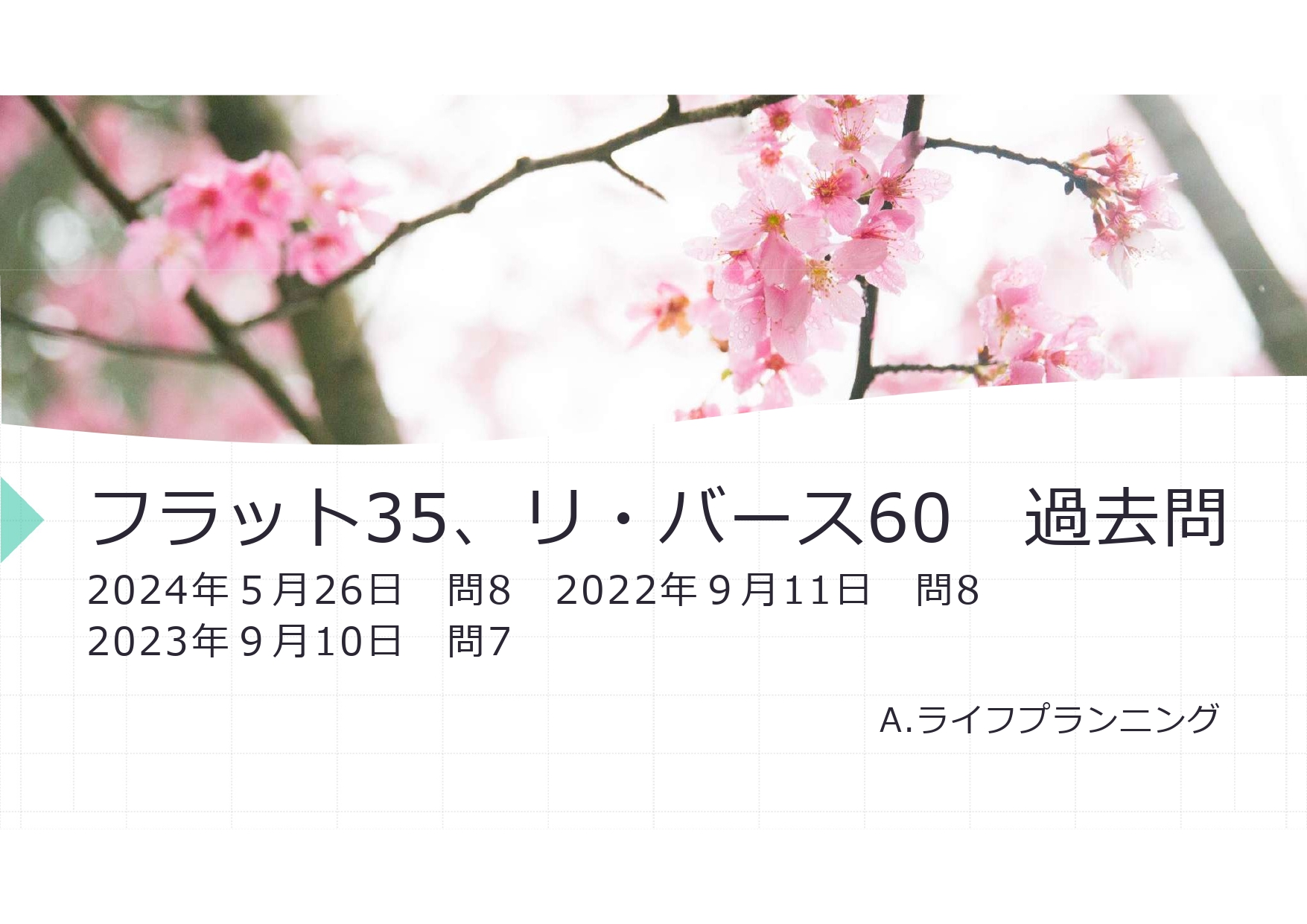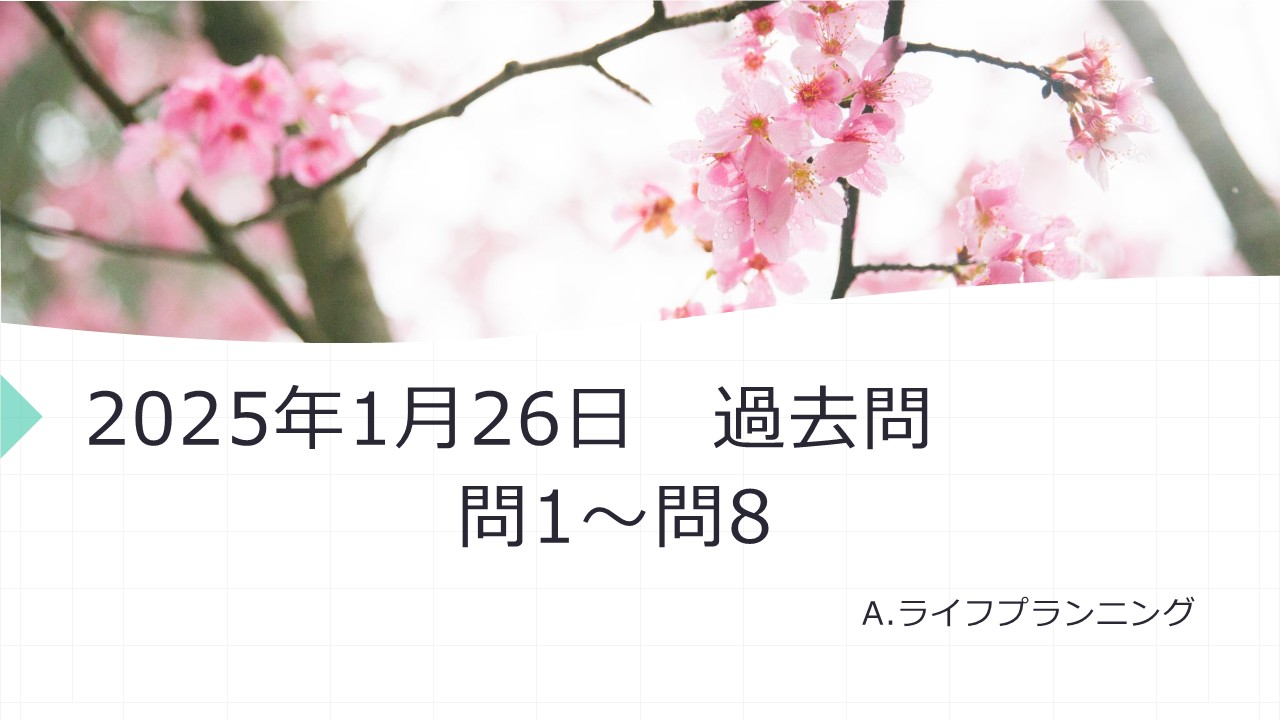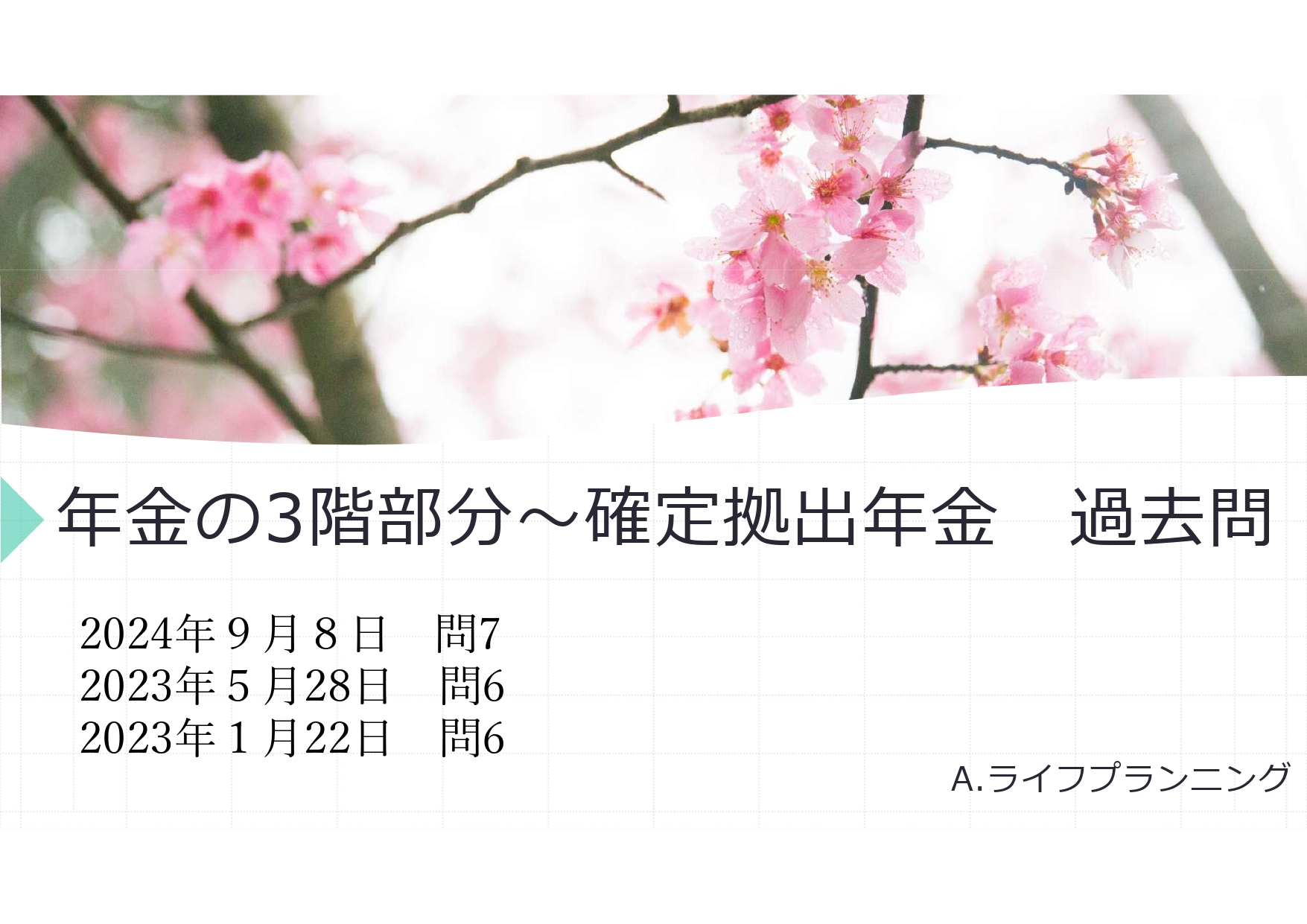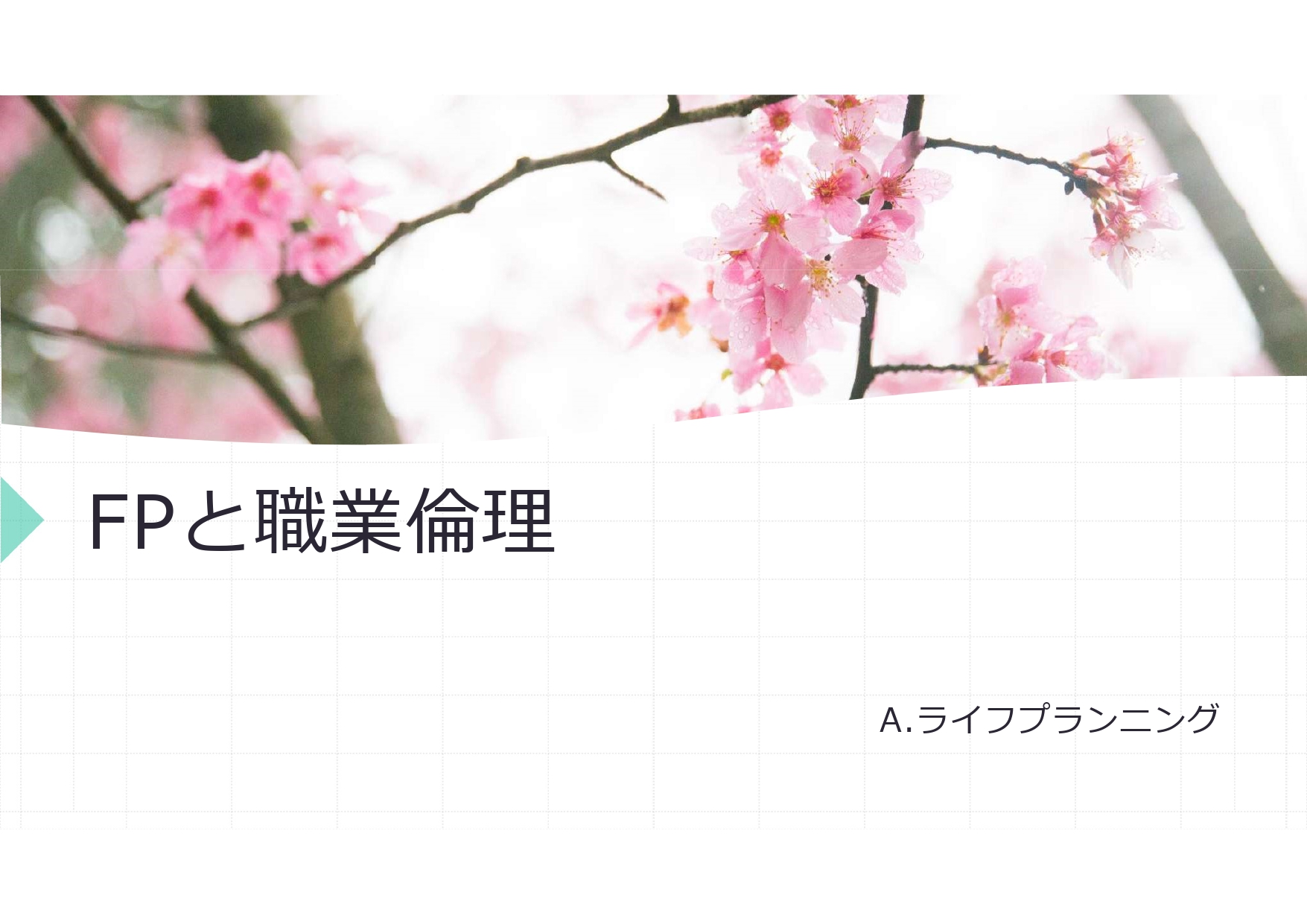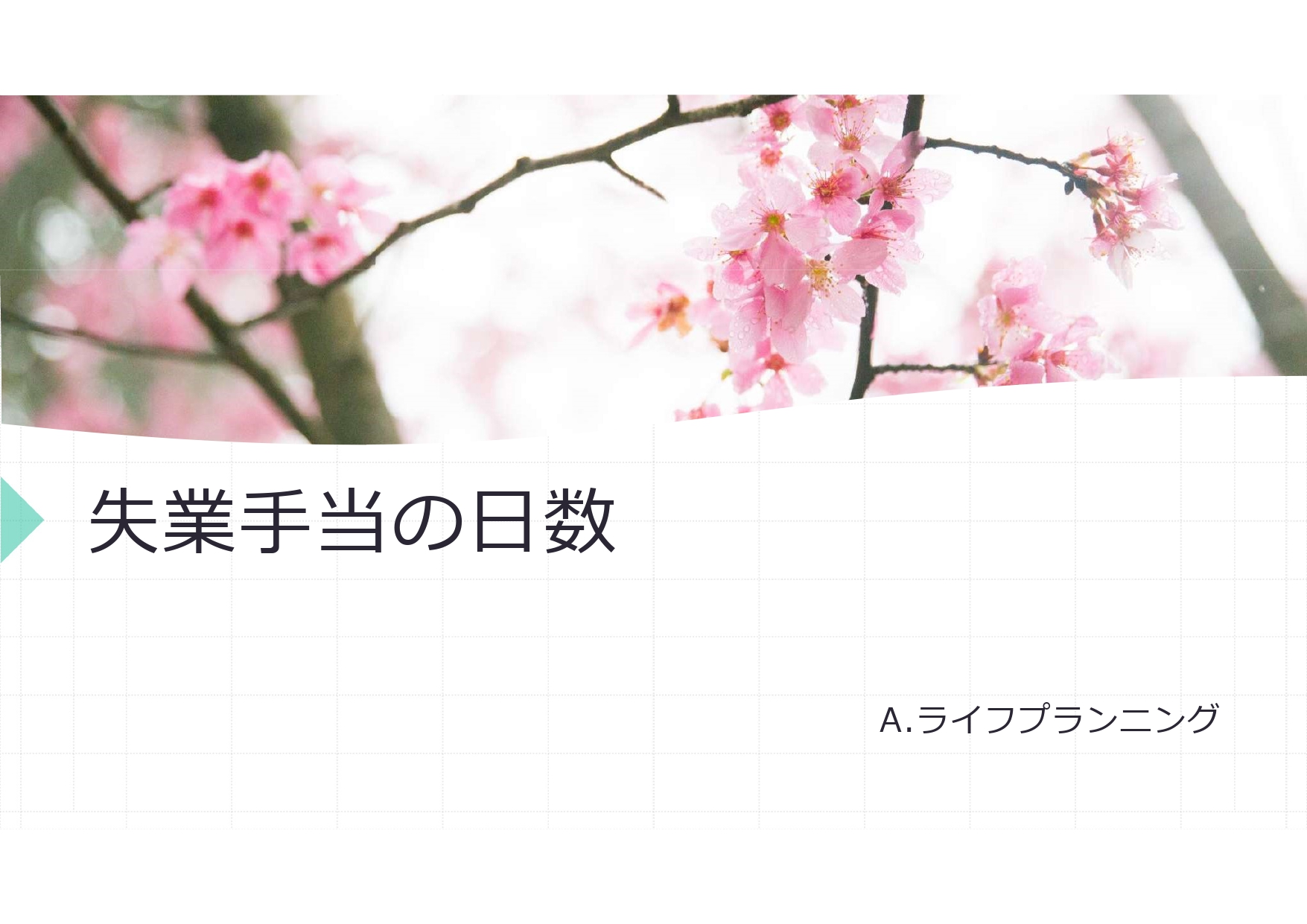2024年9月8日 ライフプランニング 基礎編
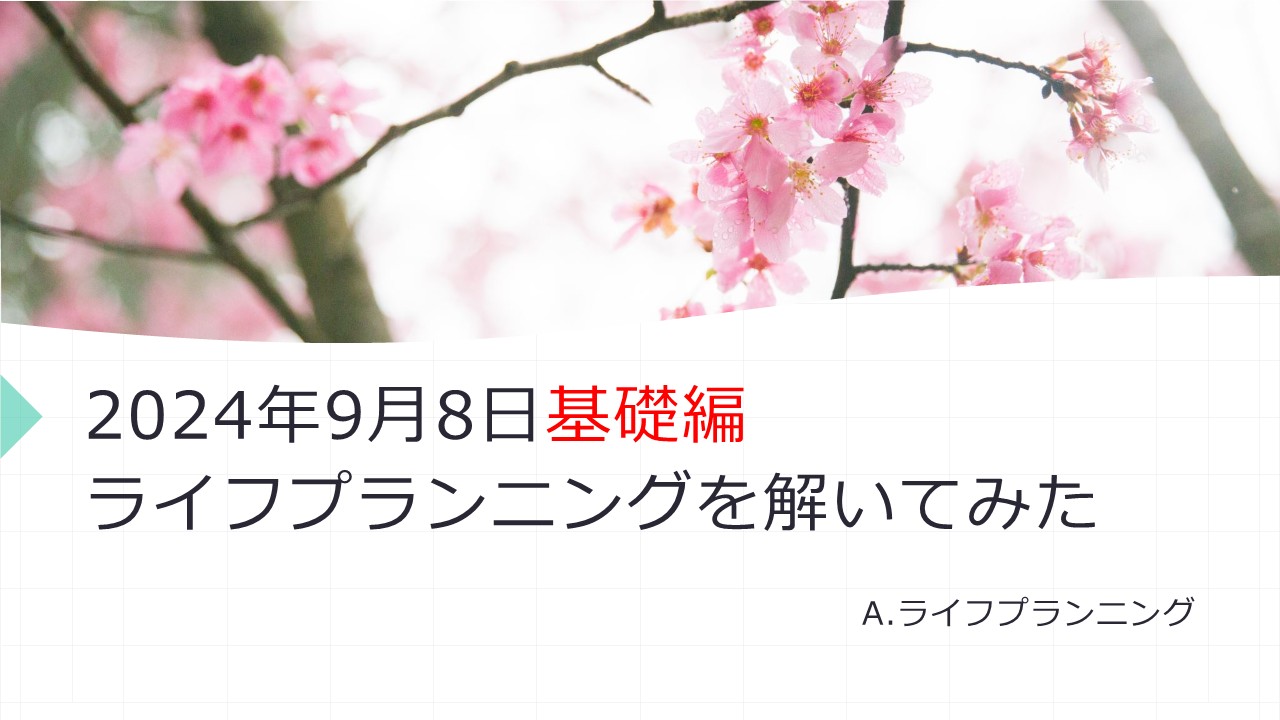
2026年1月試験に向けて勉強に励まれている方は、よろしければ、過去に投稿した記事を読んでいただけると喜びます。
今回からは2026年1月受験を考えられている方に向け、2024年9月試験の科目別の解説を試みたいと思います。
約1年半前の問題の解説なので、法改正になっている個所もあると思いますが、気付いた範囲で、そのことにも触れていきたいと思います。
学習の習慣をつけ、知識のレベルアップを図っておくことが合格のカギだと思います。
私は、応用編重視の勉強スタイルであり、基礎編は直前期に詰込み型の勉強をしてきました。
合格まで4年かかった原因のひとつが基礎編を軽視したことだと思っています。
このブログを見ていただいている方が、同じ失敗をしないために、コンスタントに基礎編の振り返りをしていきたいと思います。
今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問1 ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規
| 《問1》 ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における独占業務とは、当該資格を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別段の定めがある場合等は考慮しないものとする。 1) 税理士法により、他人の求めに応じて業として行う「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。 2) 不動産の鑑定評価に関する法律により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う「不動産の鑑定評価」は、不動産鑑定士の独占業務である。 3) 社会保険労務士法により、他人の求めに応じて報酬を得て業として行う事務であって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「帳簿書類の作成」「労使紛争に関する訴訟手続の代理」は、社会保険労務士の独占業務である。 4) 司法書士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、有償・無償を問わず、司法書士の独占業務である。 |
正解3

問1で6つの係数じゃなくてほっとした人も、残念な人もいると思う。
たまに、士業の占有業務が出題されるけど、この間違い探しも定番化しているので、これからはちょっとひねった出題が考えられるかもね。

3)「労使紛争に関する訴訟手続の代理」は弁護士の領域だね。よってこれが不適切だね。
占有業務の問題についてよく間違いの選択肢になることについての私見だけど、
・司法書士=権利部、土地家屋調査士=表題部の登記が反対に記述されている。
・税務相談は税理士でないとできないが、一般論の説明ならFPにもできる。
・不動産鑑定士の標記は正しいことが多い
・社会保険労務士の業務内容については要注意だね。
問2 後期高齢者医療制度
| 《問2》後期高齢者医療制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者については、原則として、生活保護を受けている世帯に属する者であっても被保険者とされる。 2) 後期高齢者医療制度の保険料は、原則として、被保険者につき算定した所得割額および均等割額の合計額となるが、被保険者の収入が公的年金の老齢給付のみであって、その年金収入が153万円以下の場合、所得割額は賦課されない。 3) 後期高齢者医療制度の被保険者が医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合は、当該被保険者が現役並み所得者である場合は2割であり、それ以外の者である場合は1割である。 4) K県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者であって、その区域内に住所を有している者が、S県の介護老人保健施設に入所したことにより当該施設の所在する場所に住所を変更した場合、原則として、S県の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療制度の被保険者となる。 |
正解2

期高齢者医療制度が受けられるくらい元気で長生きしたいもんだね。しかし、将来は75歳では後期高齢者とみなされないかもしれないね。

1)生活保護受給者は医療扶助制度があるから後期高齢者医療制度をうけられないね。障がい者は65歳以降で受けられることにも注意が必要だね。
2)これが正しいね。年金収入と負担割合についても直近の情報を確認しておく必要があるね。
3)現役並み所得者である場合は3割だね。2割負担は単身200万円、複数320万円(年金+その他収入)だね。
4)介護施設に入居した場合は、例外的に前の住所地の保険者のままだよ。現役時代に納税をしていた都道府県の財源でお世話をするのは合理的だと思うよ。
問3 雇用保険の基本手当
| 《問3》 雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 一般被保険者が会社の倒産により離職を余儀なくされて失業した場合、原則として、離職の日以前 2年間に被保険者期間が通算して6カ月以上あれば、所定の手続により、基本手当の支給を受けることができる。 2) 基本手当の支給を受けるためには、離職した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に出向いて求職の申込みを行い、受給資格の決定を受けて、失業の認定を受けなければならない。 3) 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を180で除して算出されるが、下限額および受給資格者の年齢区分に応じた上限額が設けられている。 4) 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から1年間であるが、離職が60歳以上の定年退職によるものである場合、離職の日の翌日から2カ月以内に申し出ることにより、最長で3年間まで延長される。 |
正解3

雇用保険といえば、基本手当(失業手当)が定期的に出題されるね。年齢、勤続年数と基本手当の日数は暗記必須だね。
過去に投稿した記事があるから、よかったら見てね・

1)2年間に6カ月以上でなく1年間に6カ月以上が正しいね。
2)事業所の所在地でなく、受給資格者の現住所の所在地を管轄する職業安定所が正しいね。
3)これが正しいよ。半年分の給与を基に算定されるよ。
4)最長1年間の延長が正しいね。最長2年まで受給可能ということだね。
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金なども検討する価値はあるかもね。
問4 厚生年金保険
| 《問4》 厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 厚生年金保険では、原則として、被保険者が4月、5月、6月に受けた報酬の総額をその報酬を受けた月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額が決定され、当該標準報酬月額が、その年の10月から翌年の9月までの各月の標準報酬月額となる。 2) 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、1等級から32等級までの等級区分から決定され、報酬月額が100万円である被保険者の標準報酬月額は65万円となる。 3) 標準賞与額は、原則として、被保険者が賞与を受けた月において、その賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて決定されるが、当該標準賞与額が150万円を超えるときは、その月の標準賞与額は150万円となる。 4) 厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率18.3%を乗じて算出され、被保険者と事業主が折半して負担する。 |
正解1

この問題に限らず、数字が出てくる問題は誤答が作りやすいから、正確な記憶が要求されるね。専門家でも、ふと言われると間違えちゃうかもね。

1)4~6月は正しいけど、10月からでなく9月からが正しいね。よってこれが間違い。
2)これは正確に覚えていないと間違えるね。迷ったら選択しちゃうかもね。
3)標準賞与額150万円は覚えておく必要があるね。
4)厚生年金保険の保険料の保険料率18.3%は固定されているので覚える必要があるね。
問5 老齢年金の繰上げ支給
| 《問5》 Aさん(女性、1963年10月5日生まれ)は、61歳0カ月で老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰上げ支給の請求をするつもりである。その場合に受給することができる年金額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、Aさんは、繰上げ支給を受けなかった場合、下記の〈Aさんに対する老齢給付の額〉の年金額を受給することができるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈Aさんに対する老齢給付の額〉 ・特別支給の老齢厚生年金の額 1,110,000円(報酬比例部分) ・65歳時の老齢基礎年金の額 765,000円 ・65歳時の老齢厚生年金の額 1,110,250円(報酬比例部分の額:1,110,000円、経過的加算額:250円) 1) 1,515,202円 2) 1,558,390円 3) 1,621,762円 4) 1,695,226円 |
正解3

年金を繰上げ受給するか、繰下げ受給するかという問題は、60歳を迎えようとする多くの人が関心を持っている事柄だよね。実際、どちらが得をするんだろうね。
特別支給の老齢厚生年金の対象となる方は、今年が出題のラストイヤーかもね。

この問題はAさんが1963年生まれの女性なので63歳から特別支給の老齢厚生年金を受給できることに気付くことが必要だね。そして、①特別支給の老齢厚生年金、②老齢基礎年金、③経過的加算額に分けて計算する必要があるね。
①特別支給の老齢厚生年金 1,110,000円(1-9.6%)=1,003,440円(24月繰り上げ)
②老齢基礎年金 765,000円×(1-19.2%)=618,120円(48月繰上げ)
③経過的加算額 250円×(1-19.2%)=202円(48月繰上げ)
1,003,440円+618,120円+202円=1,621,762円
実際はコンピューターで計算しているだろうけど、人が手で計算しようとすると間違えるね。
というか、計算間違いをしてても気づけないね。
問6 社会保険の給付に係る併給調整や支給停止
| 《問6》 社会保険の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前はいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。 2) 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳到達以後は老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金および老齢厚生年金のうち、受給権者が選択したいずれか一方の年金が支給される。 3) 業務上死亡した労働者の遺族が、労働者災害補償保険の遺族補償年金と遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、遺族厚生年金の支給を受けている間、遺族補償年金は支給されない。 4) 業務上の負傷または疾病により障害の状態となった労働者が、労働者災害補償保険の障害補償一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が全額支給され、障害補償一時金は支給されない。 |
正解1

併給調整や支給停止は頻出で、上に厚生年金、左に基礎年金を並べて数字の4を書いて併給できるかどうかの判定をするが有名だね。あまり深く考えず、この判定で正否を見極めるのがお勧めだね。
しかし、将来的には遺族年金と労災の給付の併給とか計算問題が出題されることも予想されるね。

1)これが正しいね。65歳前にどちらが有利か判定するのは、年金事務所に相談しないとわからないかもね。
2)65歳を超えた時は自身の老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金が超えていた場合は、その超えている部分が支給されるよ。計算問題が応用編で出題されたら混乱するだろうね。
3)業務上の死亡の場合、遺族基礎年金、遺族厚生年金が全額支給されるけど、遺族補償年金は減額されるけど同時に支給されるよ。
4)この場合、障害補償一時金が支給され障害手当金は支給されないから説明が逆だね。
問7 確定拠出年金の個人型年金
| 《問7》 確定拠出年金の個人型年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 障害基礎年金の受給権者であることにより国民年金保険料の納付が免除されている国民年金の第1号被保険者は、個人型年金に加入することができない。 2) 国民年金の任意加入被保険者のうち、個人型年金に加入することができるのは、日本国内に住所を有する者に限られる。 3) 個人型年金加入者が確定給付企業年金を実施している事業所に就職し、確定給付業年金の加入者となる場合、所定の要件を満たせば、その者の申出により個人別管理資産を確定給付企業年金に移換することができる。 4) 確定給付企業年金のみを実施している事業所の事業主は、使用する第1号厚生年金被保険者が300人以下である場合、個人型年金加入者である従業員の加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出することができる。 |
正解3

DB、DCなどの私的年金は、毎回のように出題されるけど、毎年のように制度が変わるから記憶をアップデートするのが難しいんだよね。
そもそも高齢者の面倒は国が見てくれるという考えは古いんだろうか。

1)原則、国民年金の未納者や免除者は個人型年金に加入はできないよ。ただし例外的に障害年金1,2級で免除になった方は、加入が可能だよ。
2)個人型年金の加入要件は国民年金と同じなので、国外在住でも加入可能だよ。
3)これが正しいね。詳しくないのでちょっと調べます。
4)加入者掛金に上乗せして中小事業主掛金を拠出というのはイデコプラスの説明だからDBではできないということだと思う。
問8 中小企業の資金調達
| 《問8》 中小企業の資金調達に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 日本政策金融公庫の国民生活事業における新事業活動促進資金は、経営革新計画の承認を受けた者など新事業活動に取り組む者が利用することができ、その融資限度額は7,200万円(うち運転資金4,800万円)である。 2) 日本政策金融公庫の国民生活事業における新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は、女性や35歳未満もしくは55歳以上の者の創業を支援する融資制度であり、既に事業を開始している者は融資の対象とならない。 3) 信用保証協会保証付融資(マル保融資)は、中小企業者が金融機関から受ける融資について信用保証協会が保証を行うものであり、中小企業者がその保証を利用するためには、業種に応じて定められた売上高および資本金または出資金の額の要件を満す必要がある。 4) 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度であり、取引先事業者の倒産により売掛金の回収が困難になったときは、無担保かつ無保証人で、納付した掛金総額の5倍を限度として共済金を借り入れることができる。 |
正解1

創業期の資金調達をしようとすると、先ずは日本政策金融公庫や商工会議所に相談に行くと思うけど、実際にどのような融資が受けられるのかを知っておいて、アドバイスをする必要があるね。

1)これが正しいね。新事業活動促進資金の融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)は覚えておいてもいいかもね。
2)新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)は2期の事業中までであれば対象となるよ。
3)信用保証協会保証付融資(マル保融資)は売上の条件はないよ。
4)掛金総額の10倍を限度が正しいね。細かい数字は覚えるのが大変だね。
創業には資金がかかるけど、新しい事業を起こすことで、経済は活性化するといえるよね。しかし失敗は怖いので、慎重な計画と勝算が必要だね。
ライフプランニングが苦手な時には、あえて問16の金融資産運用から初めて、最後まで解き終えてから、最初に戻って解いていた時もありました。
当日の夕方、模範解答が公表されて自己採点をする際にも、前半が×つづきだと、それだけで心が折れたことがトラウマになっています。
何度か試行錯誤を繰り返しましたが、結局、社会保険分野にある程度、強くないとFP試験は突破できないと思い知りました。
個人的には、実際の生活でもいちばんお金につなげているのがライフプランニングの分野です。その詳細については、改めて記事にしたいと思いますが、とにかくライフプランニングの攻略がFP1級試験突破の最大のカギだと思います。