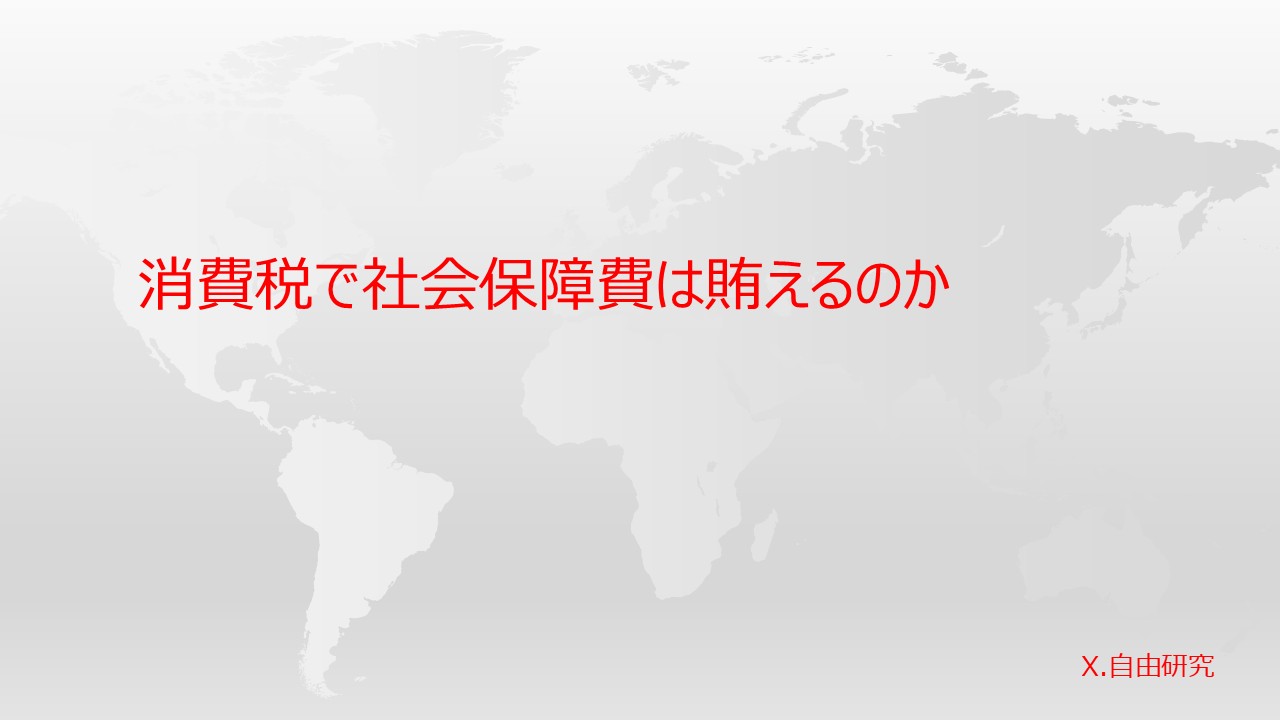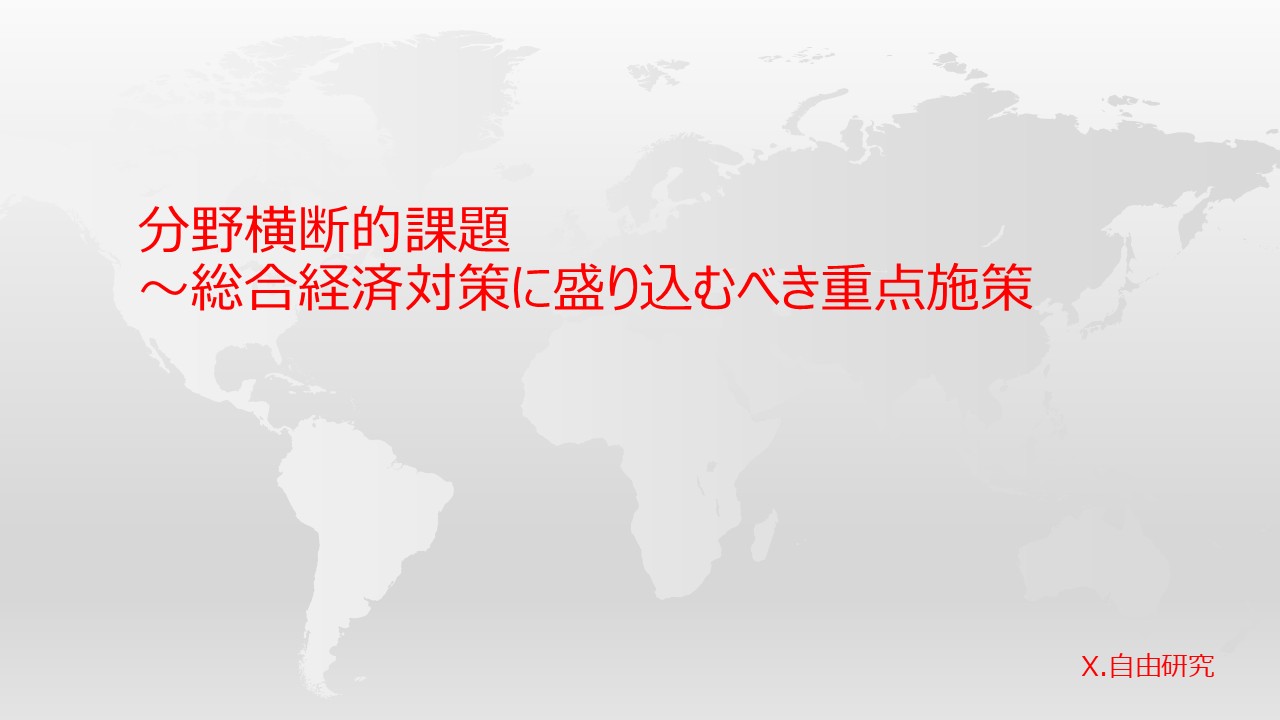ノーベル賞

現在、ノーベル賞の受賞が発表され、日本から坂口志文氏(大阪大学)が生理学・医学賞を、北川進氏(京都大学)が化学賞をそれぞれ受賞しました。
坂口氏は「免疫系を制御する「制御性T細胞」の発見とその役割の解明」
北川氏は「金属有機構造体(MOF)」の開発
というのが授賞理由ということです。
2024年に日本原水爆被害者団体協議会が平和賞を受賞したことも記憶に新しいと思います。
毎年ニュースにはなるのですが、正直、日本人の受賞者がある時にしか気にしていないのが正直なところです。
そもそもノーベル賞は知っていても、詳しい内容は知らないし、恥ずかしながら、毎年の受賞者の研究が私たちの生活にどのような影響を与えるのか理解できていないというのが正直なところです。
ノーベル賞ができたきっかけ
アルフレッド・ノーベルが、自らの死を伝えるフランス紙の誤報「死の商人、死す」にショックを受けたことが設立のきっかけとなったとする有名な逸話があります。
ノーベルはダイナマイトの発明者であり、巨額の富を築いたのですが、その発明が戦争に使用されている現実に心を痛めていたのだと思われます。
ノーベル賞の種類
ではノーベル賞って何賞があるの?という問題ですが
部門としては、「生理学・医学賞」「物理学賞」「化学賞」「文学賞」「平和賞」および「経済学賞」の6つであり、ダイナマイトを発明したアルフレッド・ノーベルの遺言により設立された財団により運営されているものです。
遺言には経済学に関する賞は入っていなかったのですが、1968年にスウェーデン国立銀行がノーベル財団に働きかけて設立されたものです。
ちなみにノーベル賞の賞金は1100万スウェーデンクローナ(約1億7000万円)ということです。
日本人受賞者
それでは6つの部門の日本人の受賞者を受賞年と研究テーマをわかる範囲で記載したいと思います。氏名は敬称略です。
また、日本生まれで受賞時、外国籍であった方を含めます。
生理学・医学賞
1987年 利根川進 「多様な抗体を生成する遺伝的原理の解明」
2012年 山中伸弥 「様々な細胞に成長できる能力を持つiPS細胞の作製」
2015年 大村智 「線虫の寄生によって引き起こされる感染症に対する新たな治療法に関する発見」
2016年 大隅良典 「オートファジーの仕組みの解明」
2018年 本庶佑 「免疫チェックポイント阻害因子の発見とがん治療への応用」
2025年 坂口志文 「末梢性免疫寛容に関する発見」
物理学賞
1949年 湯川秀樹 「中間子の存在の予想」
1965年 朝永振一郎 「 量子電気力学分野での基礎的研究」
1973年 江崎玲於奈 「半導体におけるトンネル効果の実験的発見」
2002年 小柴昌俊 「 天体物理学、特に宇宙ニュートリノの検出に対するパイオニア的貢献」
2008年 小林誠・益川敏英「小林・益川理論とCP対称性の破れの起源の発見による素粒子物理学への貢献」
2008年 南部陽一郎 「素粒子物理学における自発的対称性の破れの発見」
2014年 赤﨑勇・天野浩 「高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明」
2014年 中村修二 「高輝度で省電力の白色光源を可能にした青色発光ダイオードの発明」
2015年 梶田隆章 「ニュートリノが質量を持つことを示すニュートリノ振動の発見」
2021年 真鍋淑郎 「気候の物理的モデリング、気候変動の定量化、地球温暖化の確実な予測」
化学賞
1981年 福井謙一 「化学反応過程の理論的研究」
2000年 白川英樹 「導電性高分子の発見と発展」
2001年 野依良治 「キラル触媒による不斉反応の研究」
2002年 田中耕一 「 生体高分子の同定および構造解析のための手法の開発」
2008年 下村脩 「緑色蛍光タンパク質 (GFP) の発見と生命科学への貢献」
2010年 根岸英一・鈴木章 「クロスカップリングの開発」
2019年 吉野彰 「リチウムイオン二次電池の開発」 2025年 北川進 「金属有機構造体の開発」
文学賞
1968年 川端康成 『伊豆の踊子』『雪国』など
1994年 大江健三郎 『個人的な体験』『万延元年のフットボール』など
2017年 カズオ・イシグロ 『日の名残り』『わたしを離さないで』など
平和賞
1974年 佐藤栄作 非核三原則の提唱 小笠原諸島・沖縄の日本復帰
2024年 日本原水爆被害者団体協議会 広島・長崎の原爆被害者を中心とする団体
経済学賞
なし
ノーベル経済学賞
日本人が唯一受賞歴のない経済学賞ですが、FPという立場からいえば、触れないわけにはいかないと思います。
受賞された研究テーマを2025年から2015年まで遡って記載します。また、受賞者の氏名や国籍については失礼ながら割愛させていただきます。
2025年 「イノベーション(技術革新)主導の経済成長の解明」
2024年 「社会制度が国家の繁栄に与える影響の研究」
2023年 「「女性の就労や賃金の変遷について」
2022年 「技術革新による成長の仕組み解明」
2021年 「自然実験」で因果関係推定
2020年 「オークション理論」
2019年 「実証実験による貧困対策」
2018年 「脱炭素」
2017年 「行動経済学」
2016年 「不完備契約の理論」
2015年 「消費・貧困・福祉の研究」
正直、研究テーマを聞いてなんとなくピンとくるものもあれば、正直、何を言っているのはイメージできないものもあります。またネットで検索した記事から記載していますので、正しく和訳されているのか、私にはわからないのでご容赦ください。
経済学賞が設立されたのは1968年と新しくできたものです。
他の5賞がアルフレッド・ノーベルの遺書によって設立されたことは有名ですが
経済学賞はスウェーデン銀行がノーベル財団に働きかけて設立されたものです。
私は経済学部の卒業ですが、受賞された方の研究テーマを見ても、正しく解説することができません。 知っていることは「ゲーム理論」に関する受賞が10回以上あるということくらいです。
研究は人類のため
ノーベル賞受賞者は伝記になっている方も多く、人類に役立つものがたくさんあります。
私が思いつくところでは1901年 レントゲン 「X線の発見」でしょうか、生理学・医学賞の内容を理解できていませんが、私が毎月、通院する病院においても、研究成果が役立てられていると思います。
こういった先人の研究に、今の私も支えられていると思うと、感謝の一言ですし、何か、自分も後の人類に役立ててもらえる叡智を残したいと思う、今日このごろです。