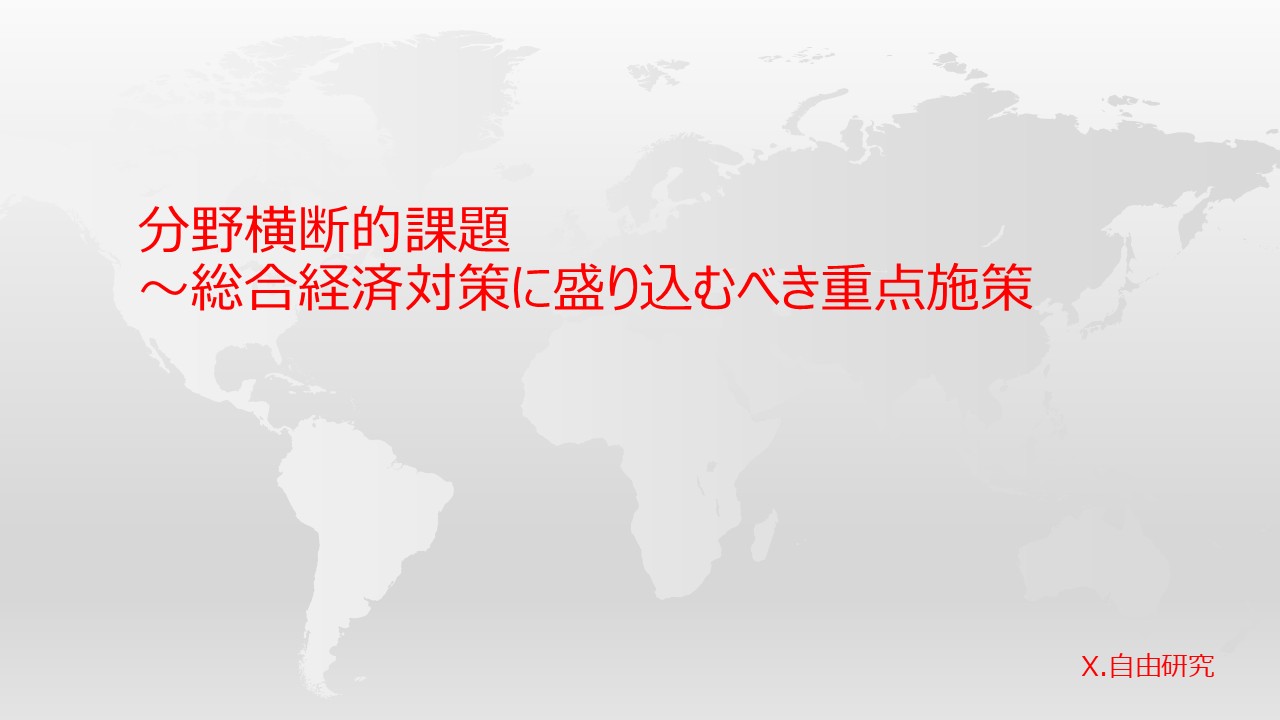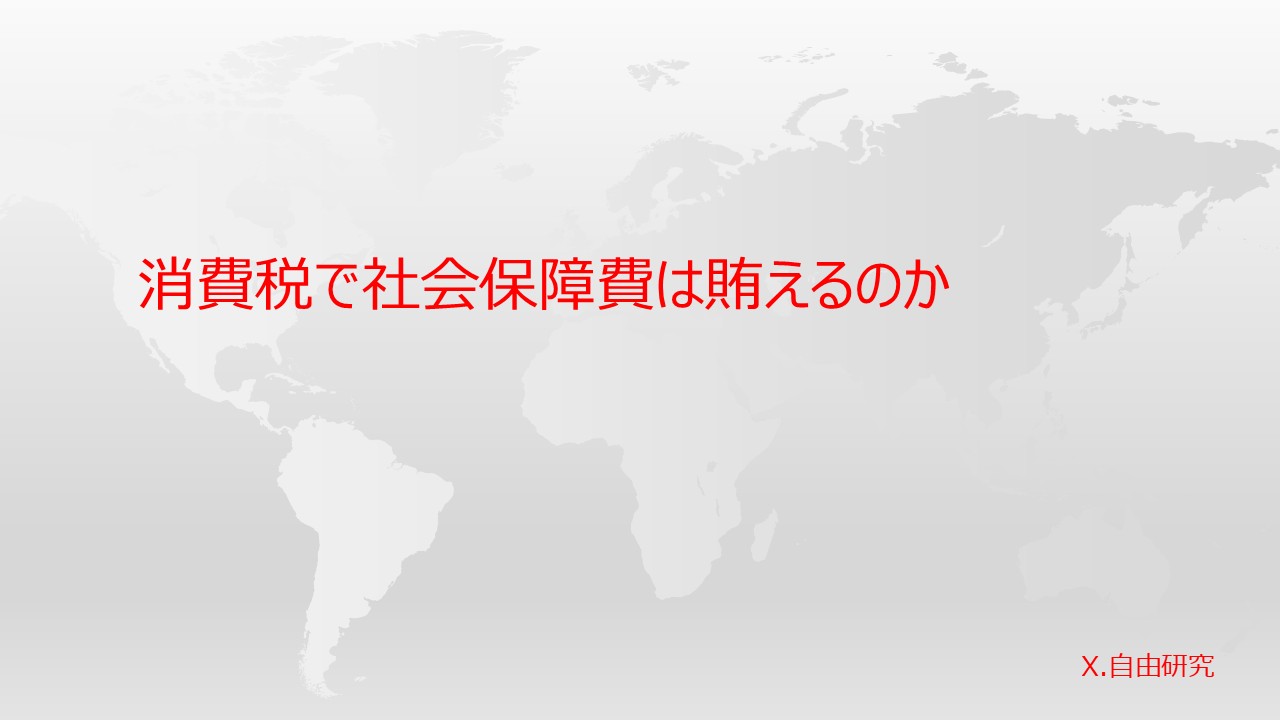食料自給率

約25年前、私は農業問題に関わる機会があり、食料自給率を調べたことがあります。
その際に食料品の細かい話は専門家に委ね、採算性の分析などを担当したのですが、平成15年くらいでも日本の食料自給率がカロリーベースで50%を下回ってることが報道で取り上げられている頃でした。
その際、私が率直に感じたのは、自給率が50%を下回っているのは大変だ!というものでした。
しかし、同じ統計で自給率は下降し続け、現在では同じカロリーベースでは令和6年現在、38%となっています。
しかし、疑問に思うのはカロリーベースでは38%の自給率ですが、生産額ベースでは64%というデータも公表されており、その違いがはっきりわからない状況です。
今回は、ニュースで耳にすることもある食料自給率でついて記事にしたいと思います。
カロリーベースと生産額ベースの違い
自給率の計算式はどちらも
生産量(額)÷消費量(額)です。これは容易に想像のつく話で、日本人が食べている量が日本国内で生産されているものの割合を計算したものです。では、なぜカロリーベースと生産額ベースで大きな開きがあるのか?
この両方の式をもっと細かく見ていくと、以下の通りです。
カロリーベース総合食料自給率(令和6年度)
=1人1日当たり国産供給熱量(860kcal)/1人1日当たり総供給熱量(2,248kcal)
=38%
生産額ベース総合食料自給率 (令和6年度)
=食料の国内生産額(12.8兆円)/食料の国内消費仕向額(20.1兆円)
=64%
カロリーベースの注意点
私もそうですが、スーパーで肉を買うときに、国内産かどうかに気をつけます。国産の肉を買って食べていれば国内の食品を100%食べているような気がしています。
しかし、国産の食品を買っていても
牛肉では10%、豚肉では5%、鶏肉では7%しか、国産の食品を消費していることにならないのです。
これはなぜか?
家畜の飼料のほとんどを海外からの輸入に頼っているからです。
鶏肉と同様の理由で、国内産であっても牛乳の自給率は28%となっています。
ここまで見てくると、カロリーベースの食料自給率はさほど意識しなくてもいいような気がしてきます。
生産額ベース総合食料自給率とは
カロリーベースがエネルギーという点に着目しているのに対して、生産額とは経済的価値に着目している計算方法です。この数値は令和6年現在で64%です。
こちらの方がイメージしやすいと思うのですが、スーパーで10,000円の食料品を買い物をしたとすると6,400円分が日本産のものということです。
人によって食料の内容は様々だと思いますが、私個人はしっくりくる数字です。
ほとんど国産と意識して買い物をしていますが、パスタやオリーブオイル、冷凍の魚介類など外国産の食品を36%くらいは買っている気がします。
これもカロリーベースと言われると、実は、ほとんど外国産を買っていることになるのかもしれませんが。
しかし、日本の食料自給率が低いと報道されることが多々ありますが、現状だけを見れば、そうも言えない、むしろ安定しているようにも感じます。
令和の米騒動に感じること
令和7年、米が高騰し、政府の備蓄米放出がニュースになりました。
総務省統計局の小売物価統計調査で2015年から1月時点でのお米5kgの金額を記載します。出所:小売物価統計調査による価格推移
| 2015年 | 1,847円 |
| 2016年 | 1,878円 |
| 2017年 | 2,001円 |
| 2018年 | 2,146円 |
| 2019年 | 2,155円 |
| 2020年 | 2,176円 |
| 2021年 | 2,139円 |
| 2022年 | 2,009円 |
| 2023年 | 2,033円 |
| 2024年 | 2,168円 |
| 2025年 | 3,828円 |
この表を見ると米の価格は10年前のほぼ2倍になっていることがわかります。
このデータは1月時点ですが、2025年9月時点では4,652円となっており、それは緊急事態といってもおかしくない状況といえます。
米が高ければ麺類や肉を食べればいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、私のような昭和生まれの人間としては、日本人は主食として米を食べたいいう気持ちがあり、食料自給率全体の話よりも、むしろ稲作をなんとかして欲しいという気持ちになります。
農業をもっと重視すべきでないか
農業の従事者の減少は、以前から問題視されています。私のような田舎暮らしをしていても米作りをしていても生活できないという理由で農業を辞めてしまう人の話をよく聞きます。
農林水産省のデータによれば基幹的農業従事者は減少傾向にあり、令和2年時点で65歳以上の従事者が70%、49歳以下の従事者は11%というデータがあります。
いきなり農業をしろと言われても、技術的に難しかったり、採算性の確保が難しいという問題があるのかもしれませんが、何か対策を立てることが必要だと思います。
農業を法人化して、補助金を支給するとか、私が知らないだけで、国もそれなりの対策を立てているのでしょうが、もっと施策の優先順位を上げてもいいのではないかと思います。
今回のブログは以上です。
これからも思いついたネタを記事にしていきたいと思いますが、FP1級の対策という従来の目的に徐々に戻りたいと思います。
また、自分自身の自己啓発のため、新たな試験の挑戦も試みたいと思います。
ここまで読んでいただいた方、ありがとうございます。