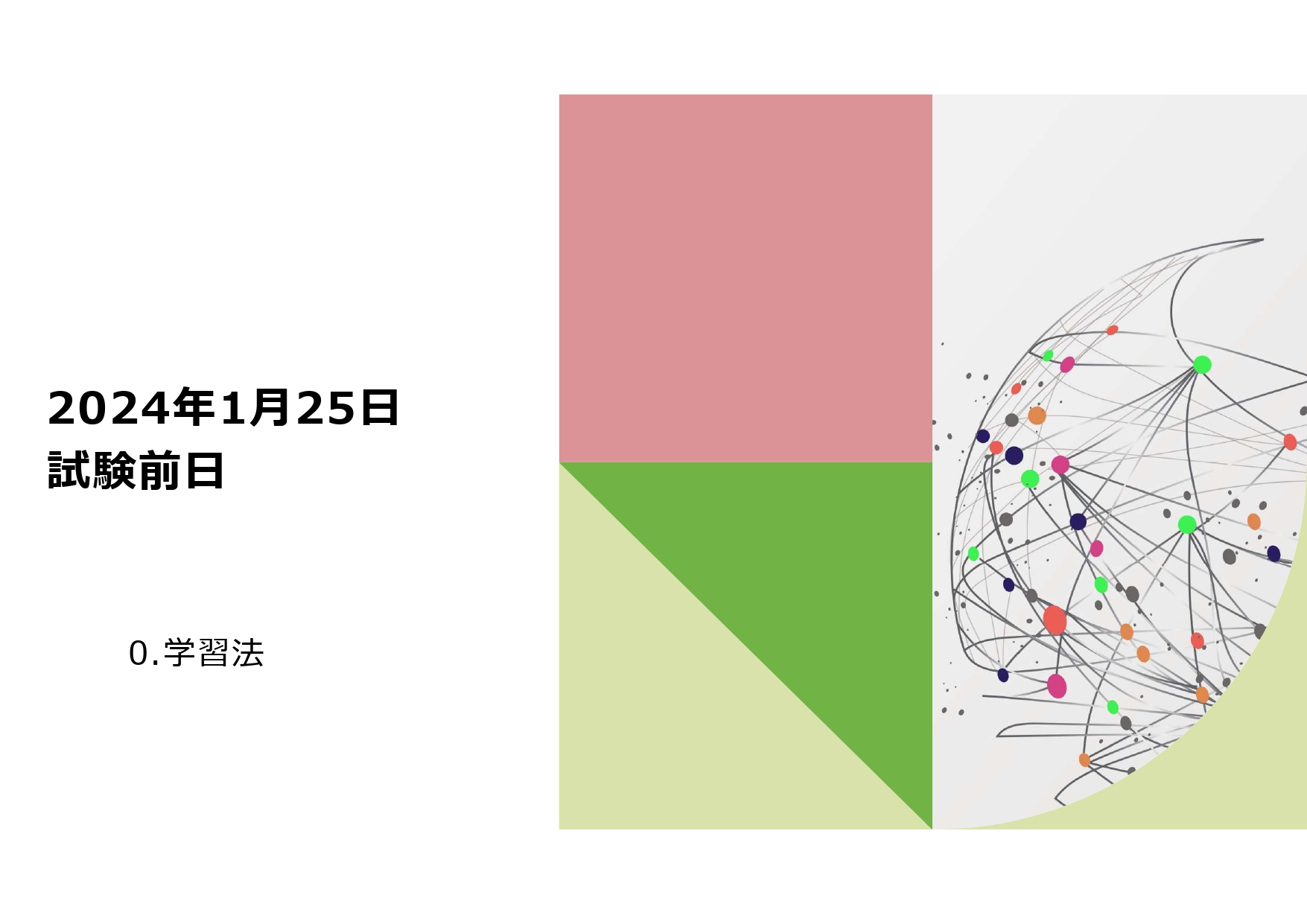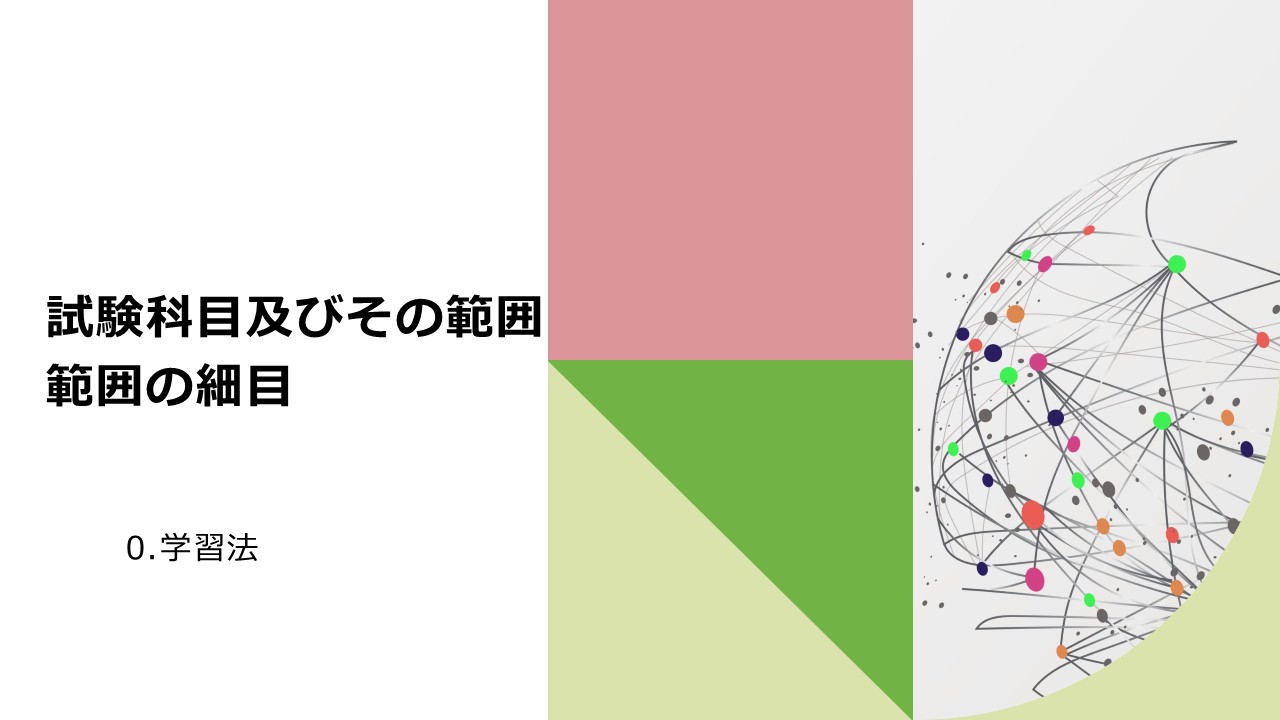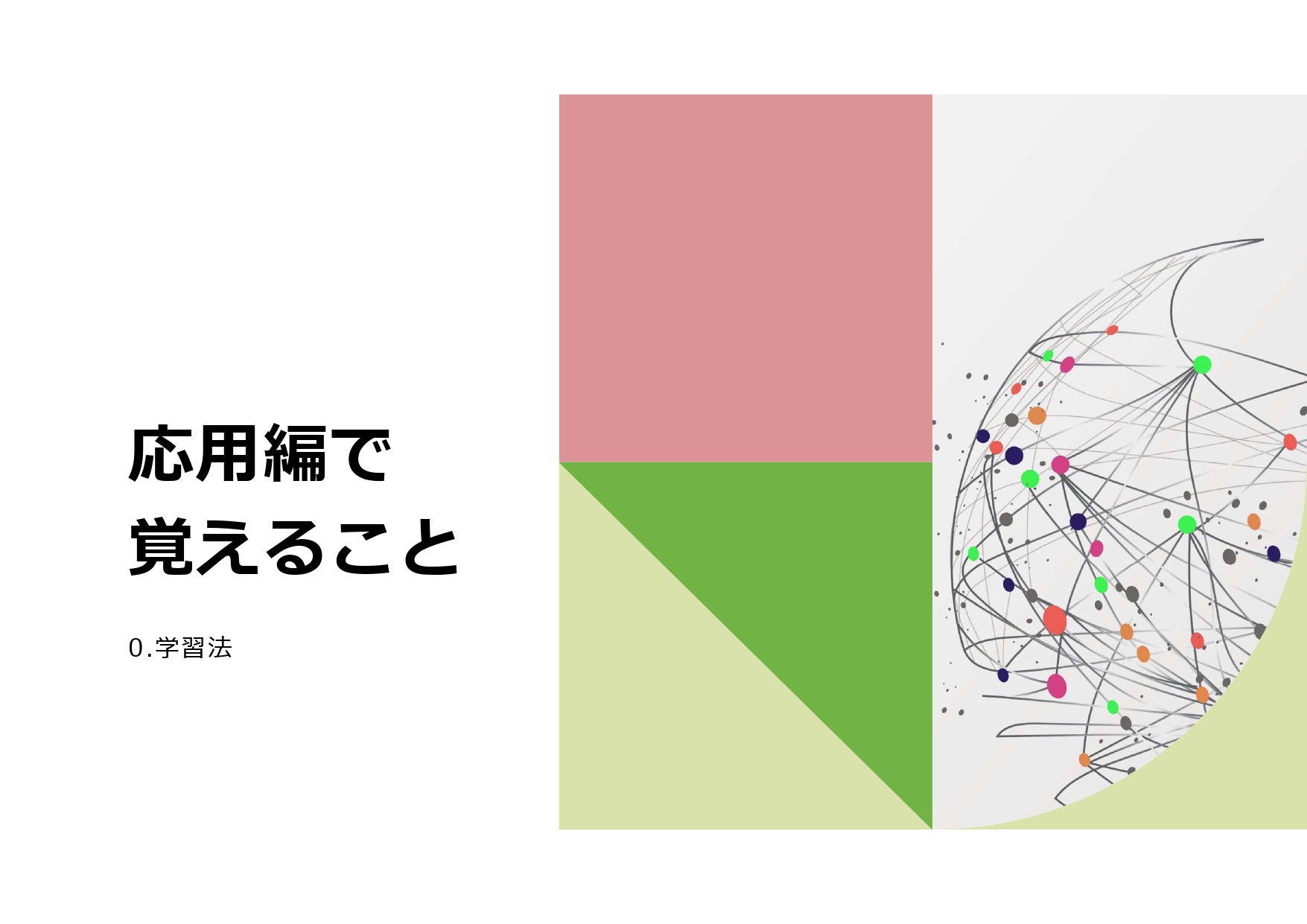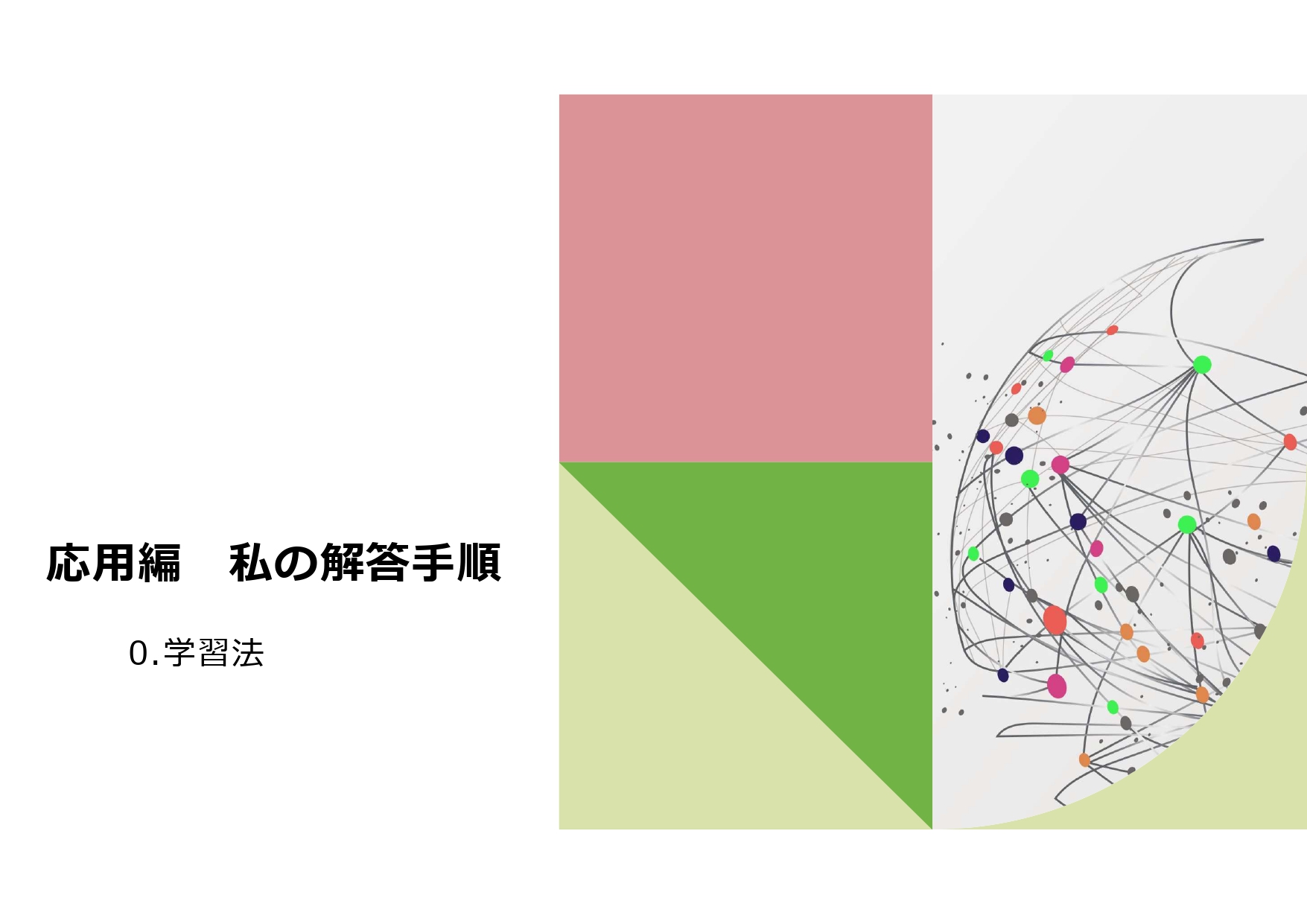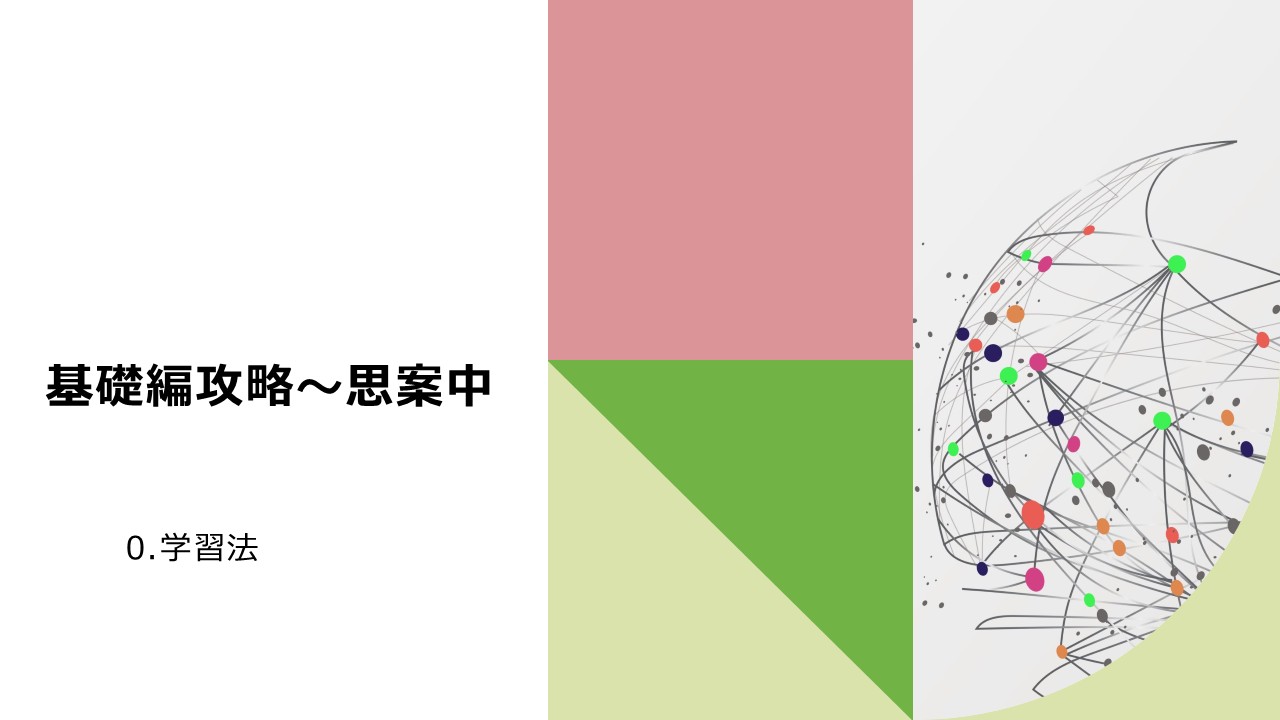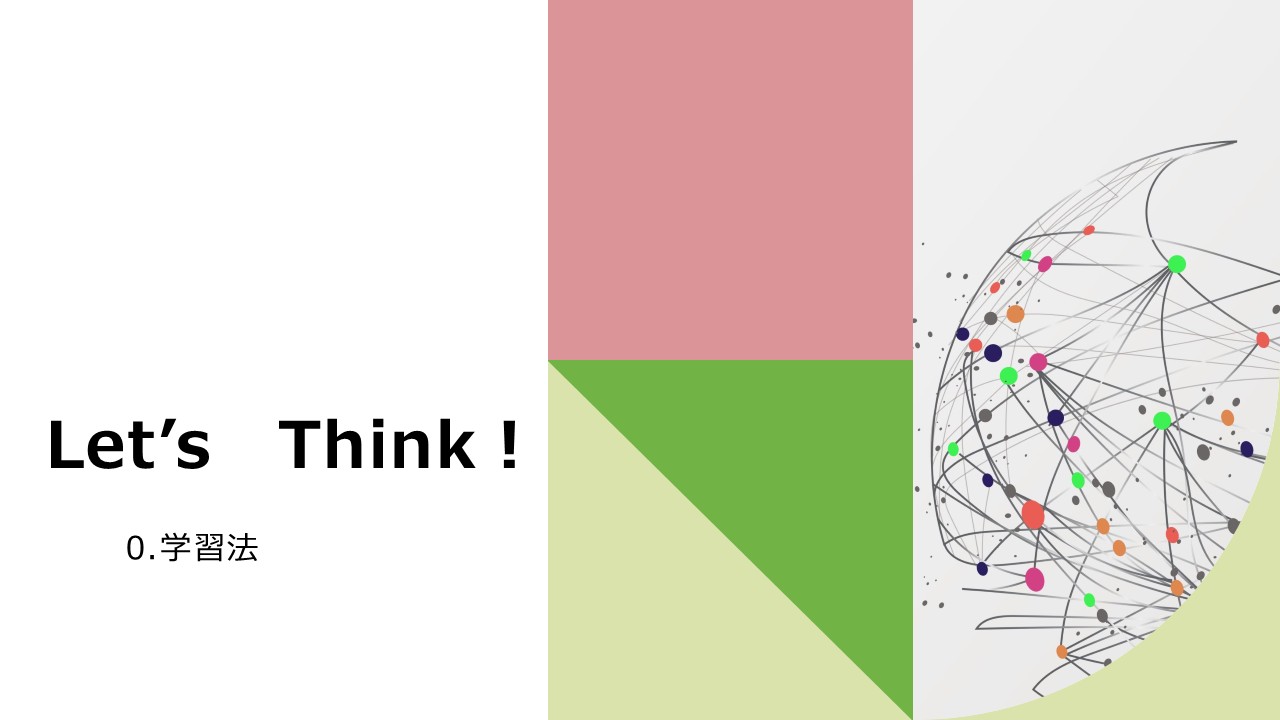基礎編で覚えること
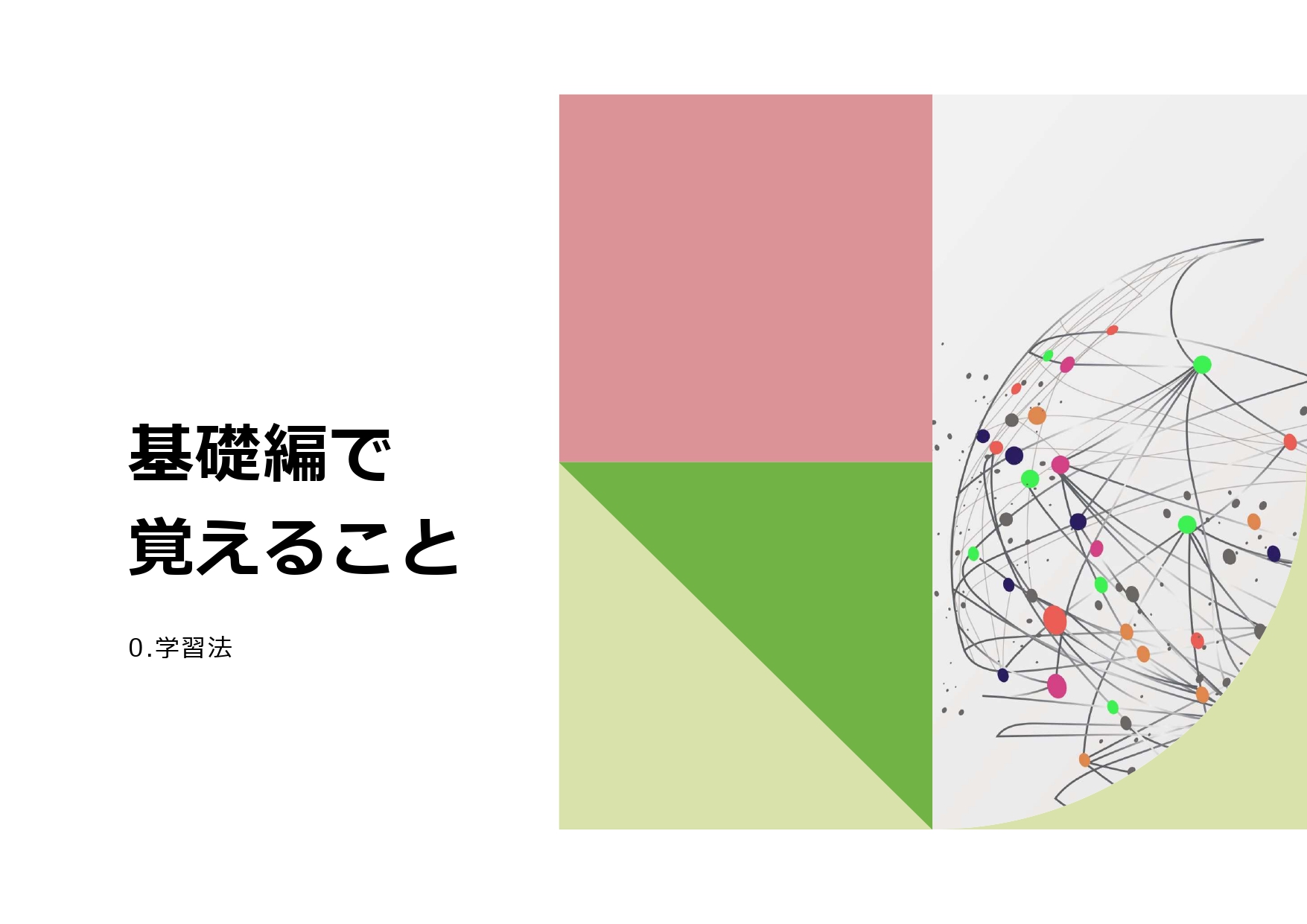
基礎編は応用編と比べると、出題範囲が広く、全ての内容を理解し、覚えることは不可能に近いと思います。
また、以下の列挙は私が学習した体験談を基に独断と偏見で行っており、出題を補償するものではありません。
全分野をまんべんなく学習することも大切ですが、ご自身の経験や、好きな分野から攻略して、得意分野である程度、得点が取れるようになってから、苦手分野の学習をすることをお勧めします。
基礎編の項目で上げていますが、同じテーマで応用編の穴埋め問題として出題されることもあるので、それも意識しながらの学習をするといいでしょう。
A(問1~問8)ライフプランニング
・FP倫理と関連法規
・6つの係数
・雇用保険
・労働者災害補償保険
・健康保険
・後期高齢者医療制度
・介護保険
・国民年金
・老齢年金の繰上げ・繰下げ
・在職老齢年金
・公的年金の遺族給付・障害給付
・企業年金・個人年金
・年金生活者支援給付金
・公的年金の併給調整
B(問9~問15)リスク管理
・保険法・保険業法
・保険契約者保護
・生命保険会社の健全性・収益性に関する指標
・生命保険商品・手続
・生命保険の特約
・生命保険料控除
・火災保険
・地震保険
・自動車保険
・法人の生命保険の経理処理
・法人の損害保険金と圧縮記帳
・外貨建て保険
・個人賠償責任保険・個人賠償責任補償特約
・損害保険による事業活動のリスク管理
C(問16~問24)金融資産運用
・経済指標
・金融政策
・投資信託
・ポートフォリオ運用
・債券の利回り
・新NISA
・オプション取引
・デリバティブ取引
・信用取引
・ROE・ROA計算
・債券の利回り計算
・財務諸表の指標計算
・外貨建て金融商品
・金融商品取引法・金融サービス提供法
・個人情報保護法
D(問25~問32)タックスプランニング
・所得税の課税・申告
・
・所得税の所得控除
・一時所得・雑所得
・不動産所得
・給与所得
・退職所得
・医療費控除(セルフメディケーション税制)
・住宅ローン控除
・事業所得
・減価償却
・白色申告
・青色申告
・役員給与
・法人と役員間の取引における課税
・インボイス制度
・賃上げ促進税制
E(問33~問41)不動産
・宅地建物取引業法
・不動産の登記
・借地借家法
・定期借地権・定期借家契約
・都市計画法
・建築基準法
・区分所有法
・生産緑地法
・不動産の投資判断手法
・不動産取得税・登録免許税
・土地の有効活用方法
・不動産関連業務と専門家
F(問42~問50)相続・事業承継
・取引相場のない株式の評価方法
・小規模宅地の特例
・暦年課税の贈与税・相続時精算課税制度
・住宅取得資金贈与の非課税
・教育資金の非課税特例
・結婚・子育て資金の非課税特例
・成年後見制度
・事業承継における相続税の納税猶予・免除
・会社法
・遺言
・地積規模の大きな宅地の評価
・相続税の延納・物納
・中心的な同族株主
・普通養子・特別養子
・医療法人持分の相続税評価
基礎編は応用編に比べて、対策がとりにくいです。
回によっても難易度がまちまちで、初見の問題も多く見られます。
私も最初は定番も覚えていなかったため、4割程度の正答率でした。
しかし、過去問を繰り返し、遡って解き始めてから、本番で「これは見たことがあるから解けるはずだ」、
「これは見たことが無いから他の人もできないはずだ」という判断がつくようになり、気持ちが楽になりました。
最も悔しいのが、見たことあるのに解き方を忘れた。。。というものなので、
こうならないために、繰り返し過去問で解き方をマスターするのみです。

基礎編は設問によって難易度の差が激しいですが、マークシートを飛ばしてしまうのが怖かったので、頭から解いていき、怪しい問題は問題用紙にチェックを入れておくようにしました。
また、ありがちな失敗として、問題文を読むうちに、正しいものを選ぶのか、間違っているものを選ぶのか混乱してしまうことが多かったので、問題用紙に正しいものを選ぶなら○
間違っているものを選ぶなら×を入れるようにしてから、凡ミスが減ったように思います。

慣れてくると、基礎編のパターンも頭に入ってきて、問1は6つの係数か専門家の占有業務の問題で、問50は事業承継税制か会社法の問題が出るというように・・・
個人的には、第1問と第50問は正解するように心がけました。
午後の応用編に向かう前に「できた」という手ごたえが欲しかったからです。