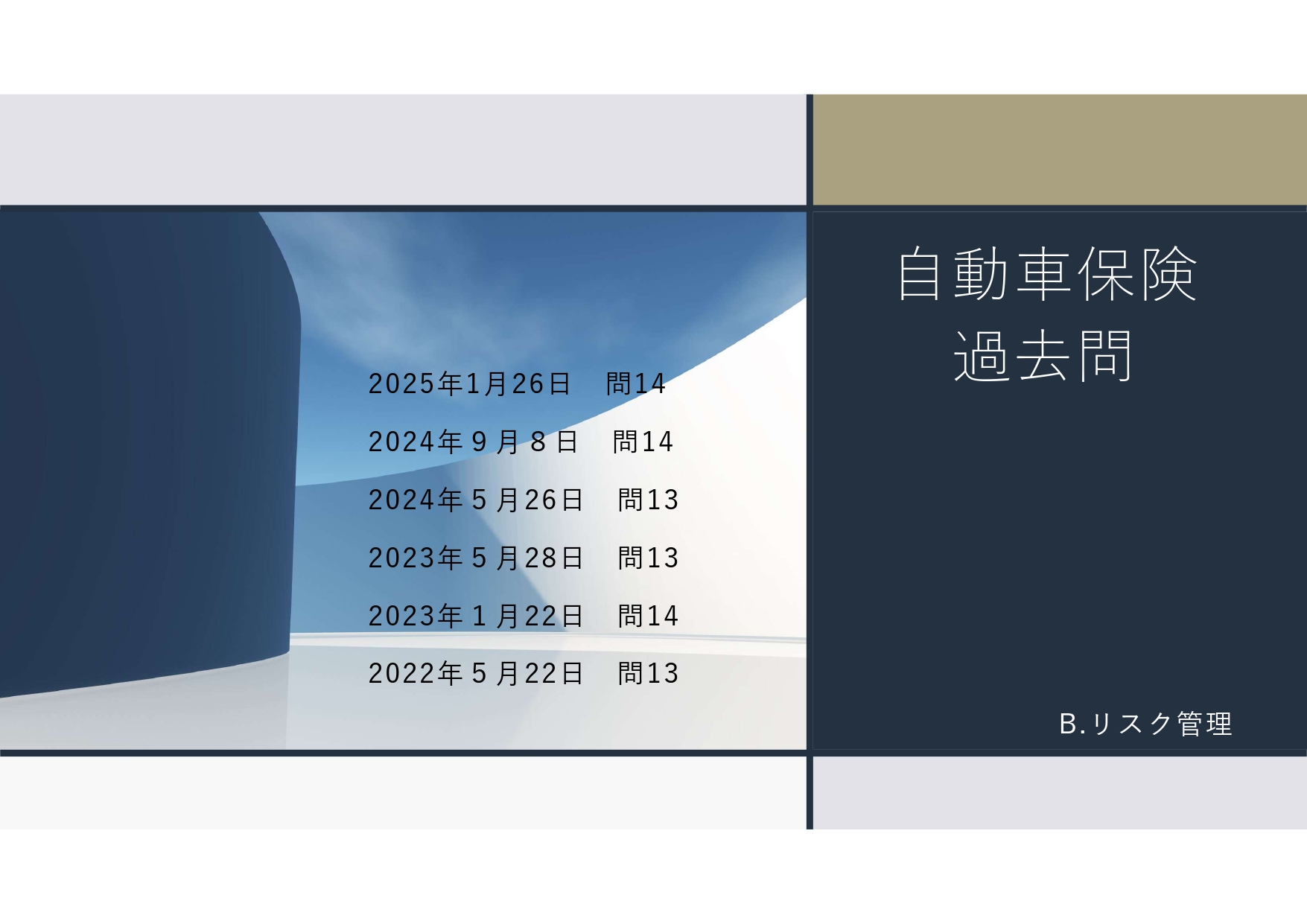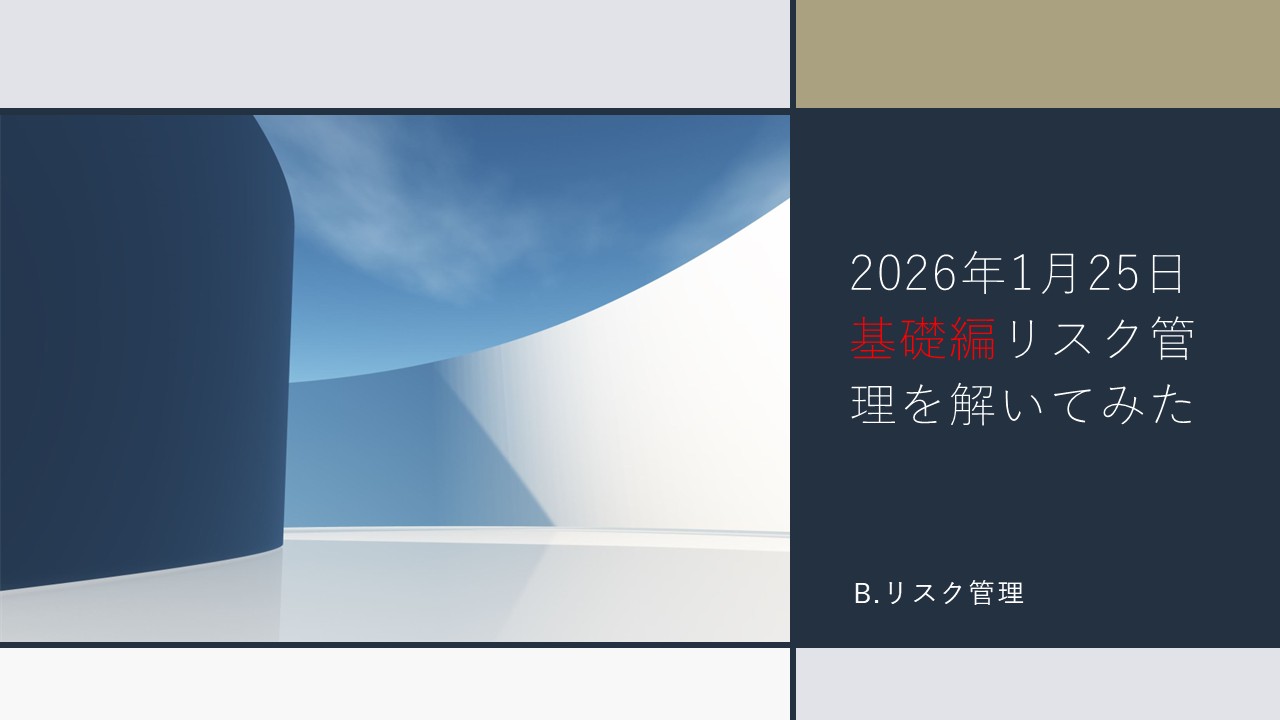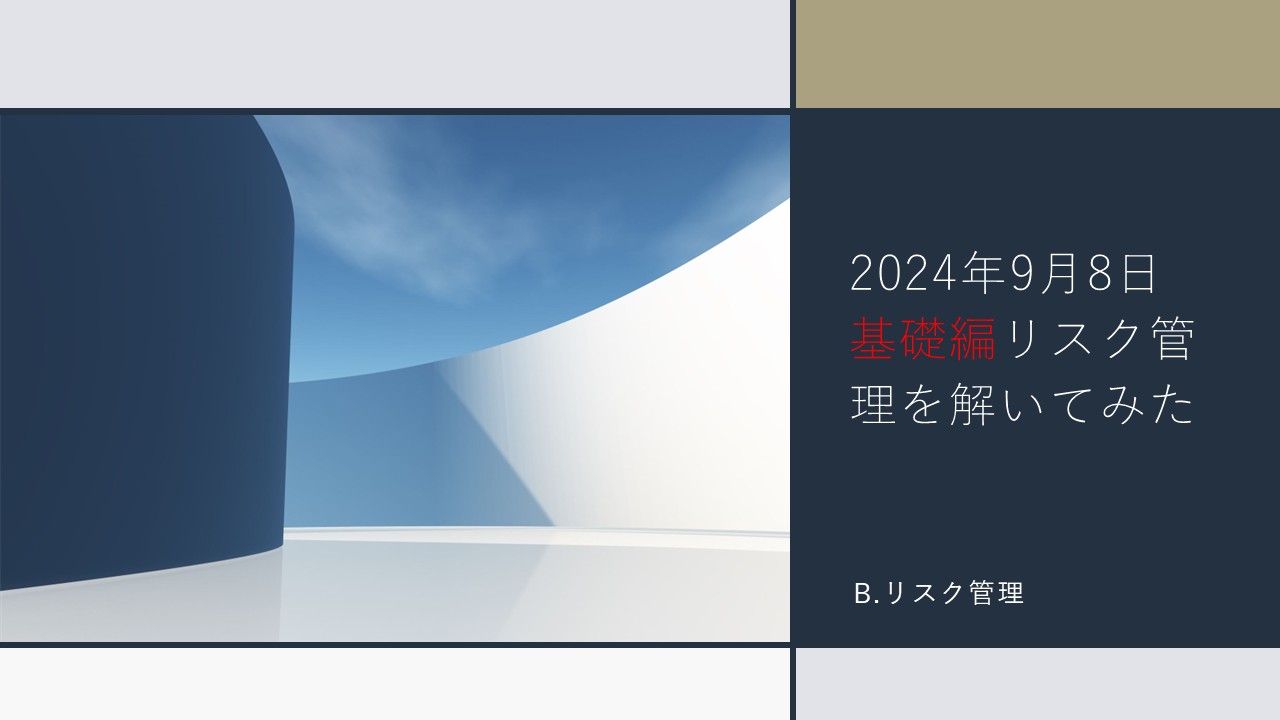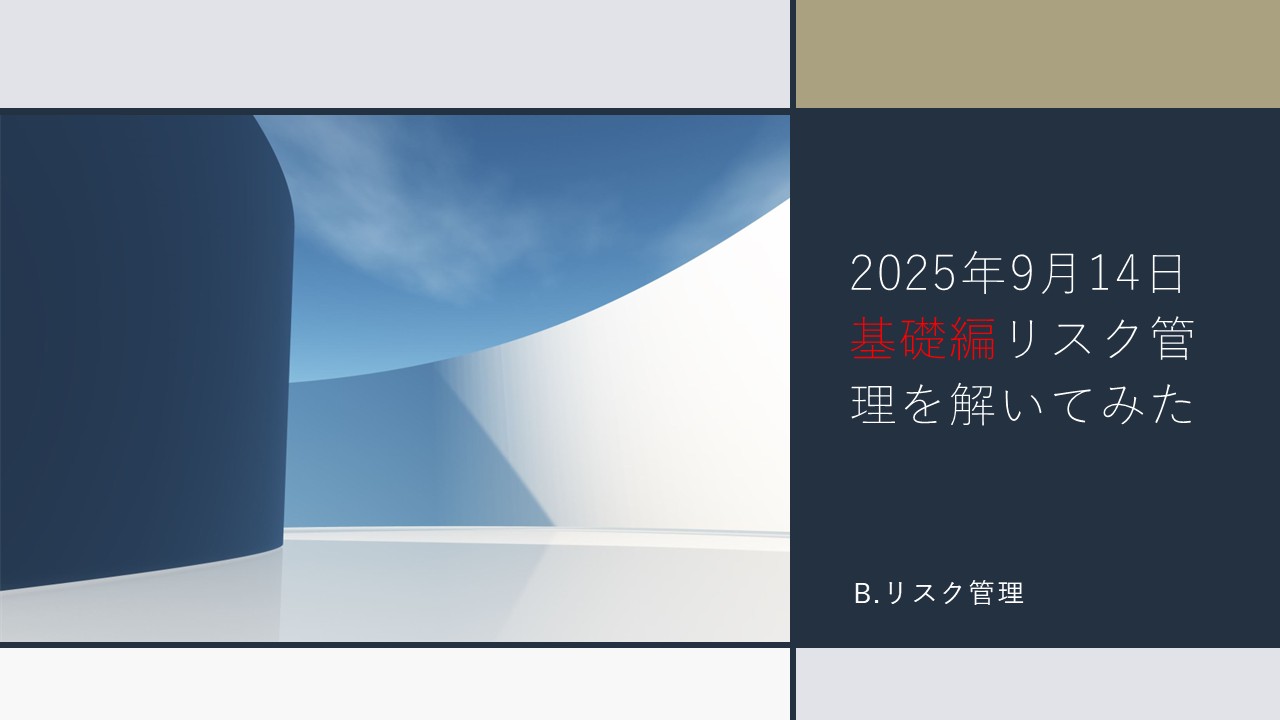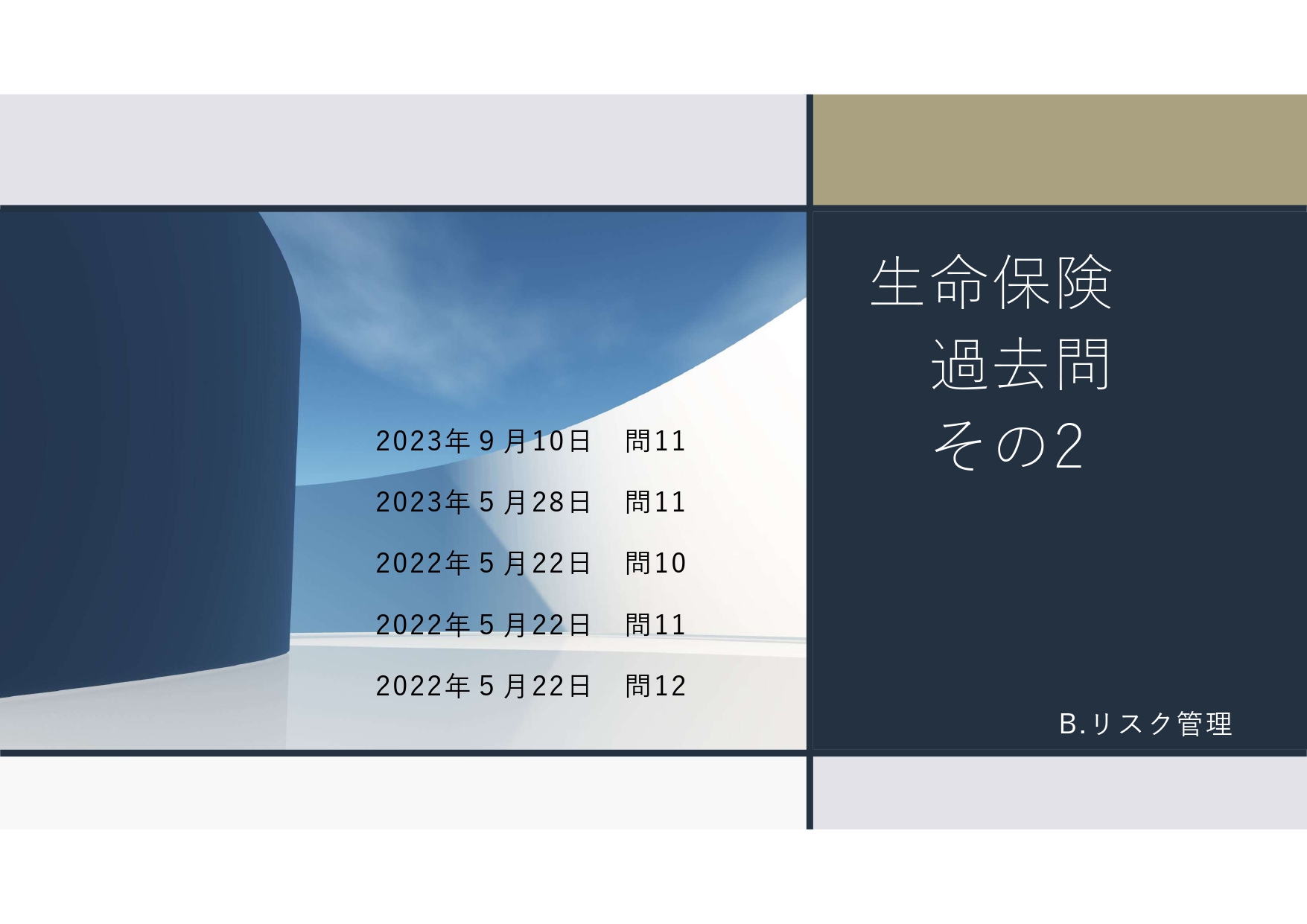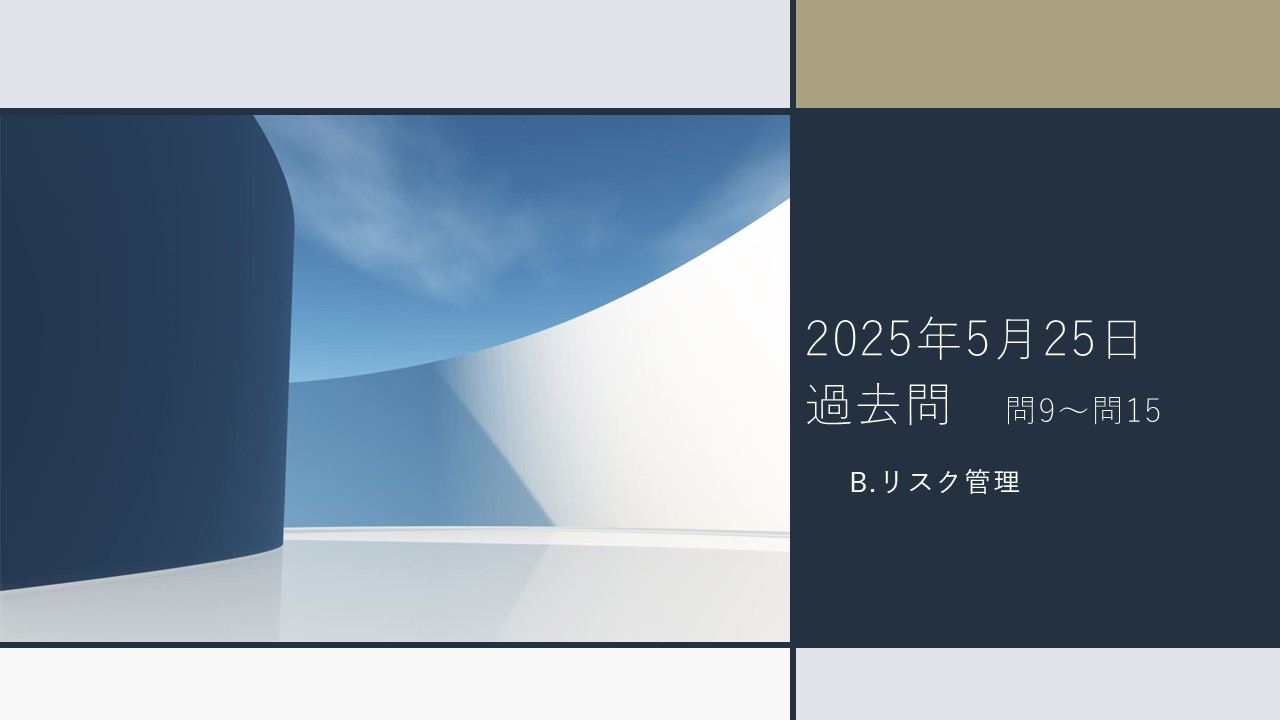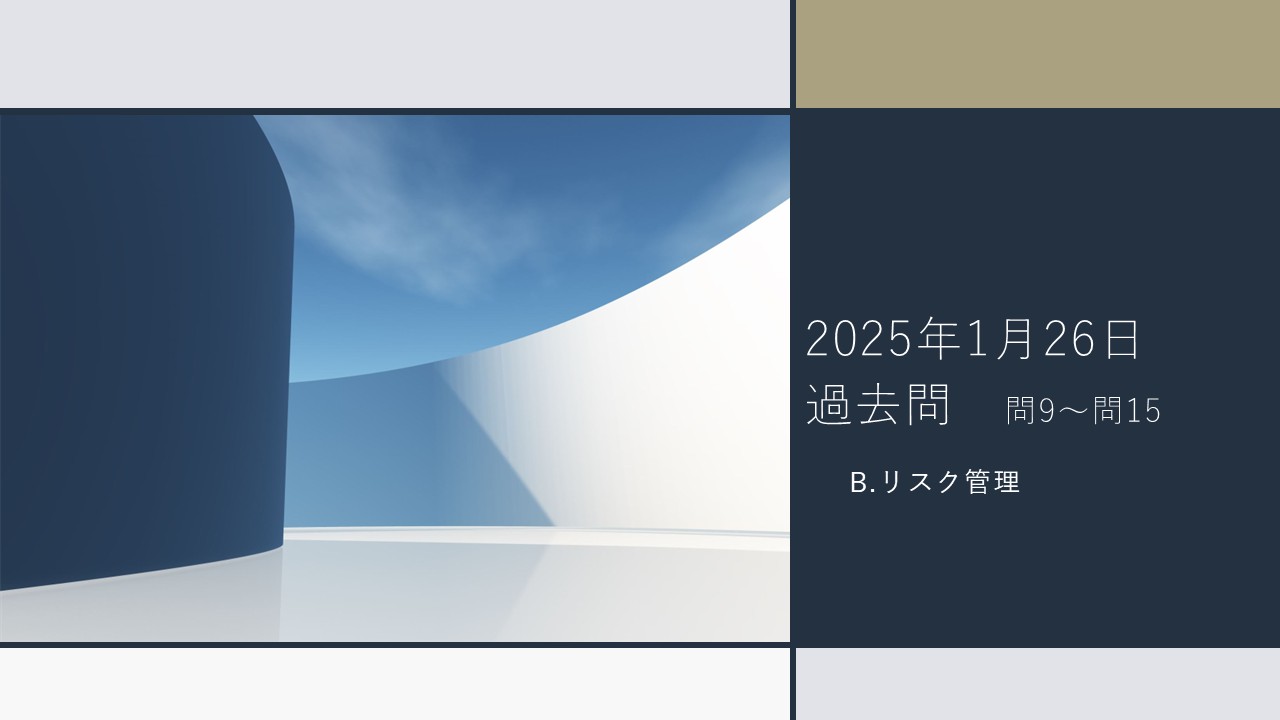火災保険・地震保険 過去問
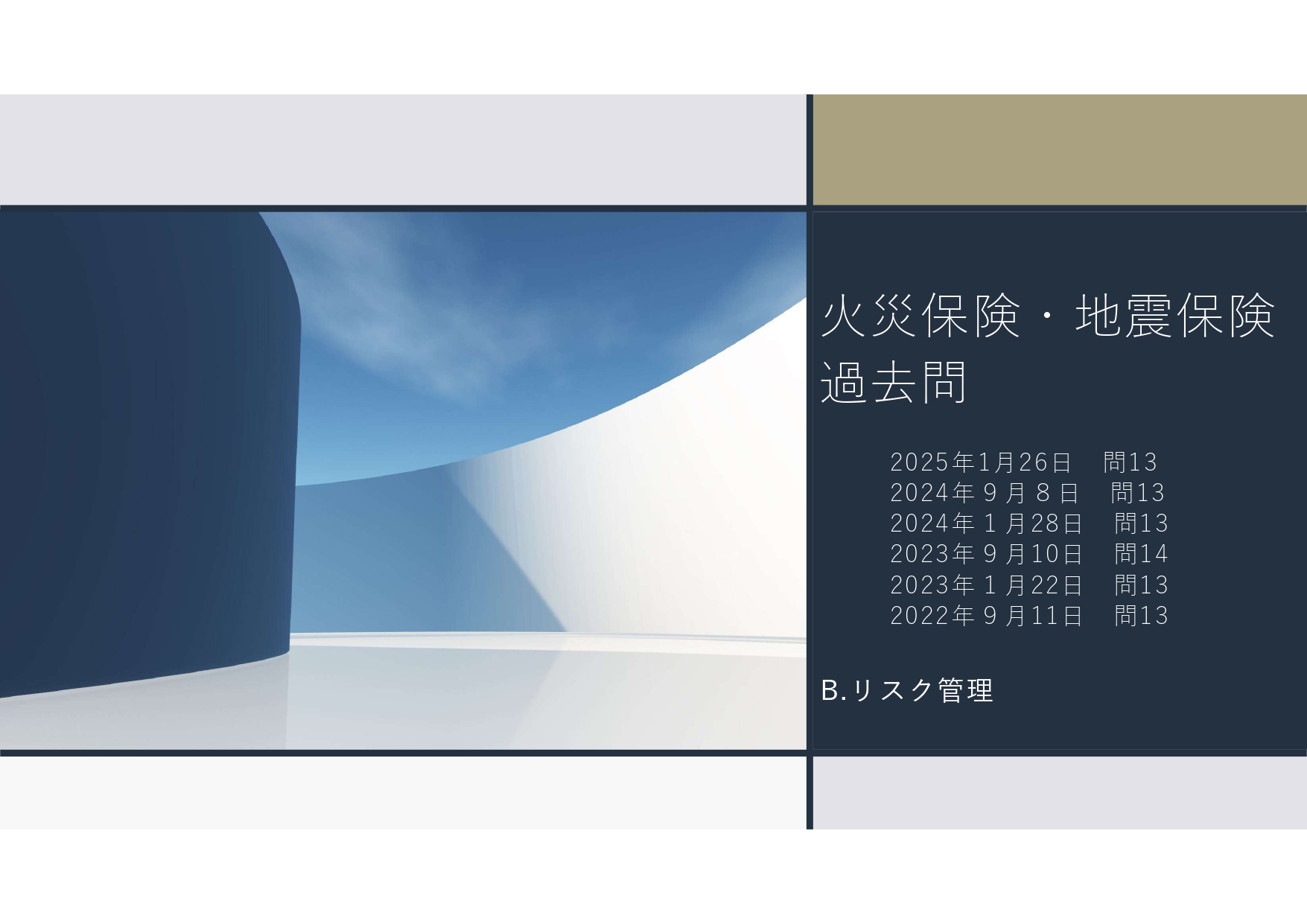
言わずと知れた、日本は地震大国であり、私が生きてきたこの50数年にも大きな地震を経験しました。
保険でのリスク管理といった場合、最も大きいのは生命保険かもしれませんが、それと同等か、場合によっては、それ以上に、備えておいてよかったと思えるのが今回のテーマ「火災保険・地震保険」かもしれません。
このテーマについて、2022年9月までさかのぼってみていきたいと思います。また、今回も一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>から問題文は引用しております。
2025年1月26日 問13
| 地震保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 火災保険では、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによって保険料が異なるが、地震保険では、保険金額や建物の所在地・構造等の他の条件が同一であれば、保険の対象となる住宅が専用住宅であるか併用住宅であるかによる保険料の差異はない。 2) 地震保険の保険料に係る免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて10%、30%、50%の3つに区分されている。 3) 生活用動産を対象とする地震保険において、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品については、契約時に申告して申込書等に明記することにより、補償の対象とすることができる。 4) 居住用建物を対象とする地震保険において、損害が全損と認定されるのは、地震等による主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が時価の70%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が延べ床面積の50%以上となった場合である。 |
正解1

地震って大規模なものもニュースになっていて他人事だと思えなくなってきたよね。

2) 地震保険の免震建築物割引の割引率は、10%です。10%、30%、50%の3つに区分されているのは耐震等級割引だよ。ややこしいね。
3)地震保険では、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董品は対象外だよ。
4)地震保険において、損害が全損と認定されるのは、主要構造部の損害割合が50%以上で、焼失または流失した床面積が70%以上だね。ややこしい
2024年9月8日 問13
| 住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 住宅建物および家財を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内の車庫に収容されている自転車や総排気量125cc以下の原動機付自転車に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。 2) 住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。 3) 住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で5年とされ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。 4) 火災保険に付帯する火災保険に付帯する地震火災費用特約は、保険の対象となる住宅建物が地震等を原因とする火災により半焼となった場合に保険金額の5%が支払われ、全焼となった場合に保険金額の10%が支払われる特約である。 |
正解4

火災保険って入っているけど、細かい条件など見たことが無いよ。

4) 地震火災費用特約では建物が半焼以上した場合には、火災保険金額の5%が支払われる特約みたいだね。
1)~3)は適切なんで、この選択肢を覚えておくといいと思うよ。
しかし、これは難問だね。
2024年1月28日 問13
| 所得税の地震保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 自己の居住用家屋を対象として少額短期保険業者と締結した地震補償保険の保険料は、地震保険料控除の対象となる。 2) 第三者に賃貸している居住用家屋を対象とする地震保険について、居住用家屋の所有者が支払った保険料は、地震保険料控除の対象とならない。 3) 保険期間が2024年1月1日から2年間である地震保険の保険料を一括で支払った場合、支払った保険料の全額を2024年分の地震保険料控除の対象とすることはできない。 4) 地震保険の対象である自己の居住用家屋が地震によって全損し、保険金が支払われて当該地震保険契約が終了した場合であっても、その年に支払った保険料は地震保険料控除の対象となる。 |
正解1

どの選択肢もありえるような、ありえないような気がして、ひとつに絞り込むのが難しい問題だね。

1) 少額短期保険は地震保険料控除の対象外だね。これは知ってれば取れる問題だから取りたいね。
2)~4)の選択肢がちょっとややこしくて、わからずに選んでしまいそうなので、1)を迷いなく選択することが大切だね。
2023年9月10日 問14
| 地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 地震保険では、72時間以内に生じた2以上の地震等は、被災地域がまったく重複しない場合を除き、一括して1回の地震等とみなされる。 2) 地震保険は、火災保険に原則自動付帯となっているが、契約者が地震保険を付帯しないことの意思表示をした場合は、付帯しないことができる。 3) 地震保険では、1回の地震等により支払われる保険金の額にかかわらず、支払われる保険金の総額の2分の1を民間(各損害保険会社および日本地震再保険株式会社)が負担し、残りの2分の1を政府が負担する。 4) 地震を原因とする地盤液状化により、地震保険の対象である木造建物が傾斜した場合、傾斜の角度または沈下の深さにより一定の損害が認定されれば、保険金が支払われる。 |
正解3

この選択肢3)が聞いたことないけど、残りの選択肢が合ってそうなので、消去法で3)かな。

そうだね、正解は3)だね。この設問も残りの3つの選択肢は覚えておいていい問題だと思うよ。
巨大地震が起きたときでも2分の1を民間が負担しないといけないなら保険会社がつぶれちゃうね。
2023年1月22日 問13
| 住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 火災保険の対象となる住宅建物は、その構造により、M構造、T構造、H構造に区分され、適用される保険料率は、同一地域であればH構造が最も高い。 2) 住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、敷地内の車庫に収容されている被保険者所有の自転車や総排気量が125cc以下の原動機付自転車は、家財として補償の対象となる。 3) 隣家で発生した火災の消火活動により火災保険の対象となる住宅建物が水濡れによる損害を被った場合、その損害は補償の対象となる。 4) 火災保険に付帯する地震火災費用特約は、火災保険の対象となる住宅建物が地震等を原因とする火災により半焼となった場合に保険金額の5%(300万円を限度)が支払われ、全焼となった場合に保険金額の10%(600万円を限度)が支払われる特約である。 |
正解4

地震火災費用特約って、再び出てきたね。じゃあこれが不適切かな。

1)~3)の選択肢は過去にも出てきたことある知識だから、消去法でも4)を選ぶことができたかもしれないね。
正しい選択肢を覚えるというのは、テキストを読むのと同等に勉強になるよ。
2022年9月11日 問13
| 地震保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 契約する火災保険の保険料払込方法が一括払いで保険期間が5年の場合、当該火災保険の契約時に付帯する地震保険は、保険期間1年の自動継続または保険期間を5年とする長期契約のいずれかを選択する。 2) 地震保険の保険料の免震建築物割引の割引率は、居住用建物の耐震等級に応じて3つに区分されており、割引率は最大50%である。 3) 地震を原因とする津波により、地震保険の対象である居住用建物の流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合、全損と認定される。 4) 地震を原因とする地盤液状化により、地震保険の対象である木造建物が傾斜した場合、傾斜の角度または沈下の深さにより一定の損害が認定されれば、保険金が支払われる。 |
正解2

地震保険って、FP試験でよく出るんだね。今回、過去問を見返してつくづく感じたよ。

2)免震建築物割引の割引率は区分されておらず、一律に50%だね。耐震等級割引は3つに区分されているから、こことの混乱を狙ったのかもね。
残りの選択肢は、知識のストックで判断したいところかもね。