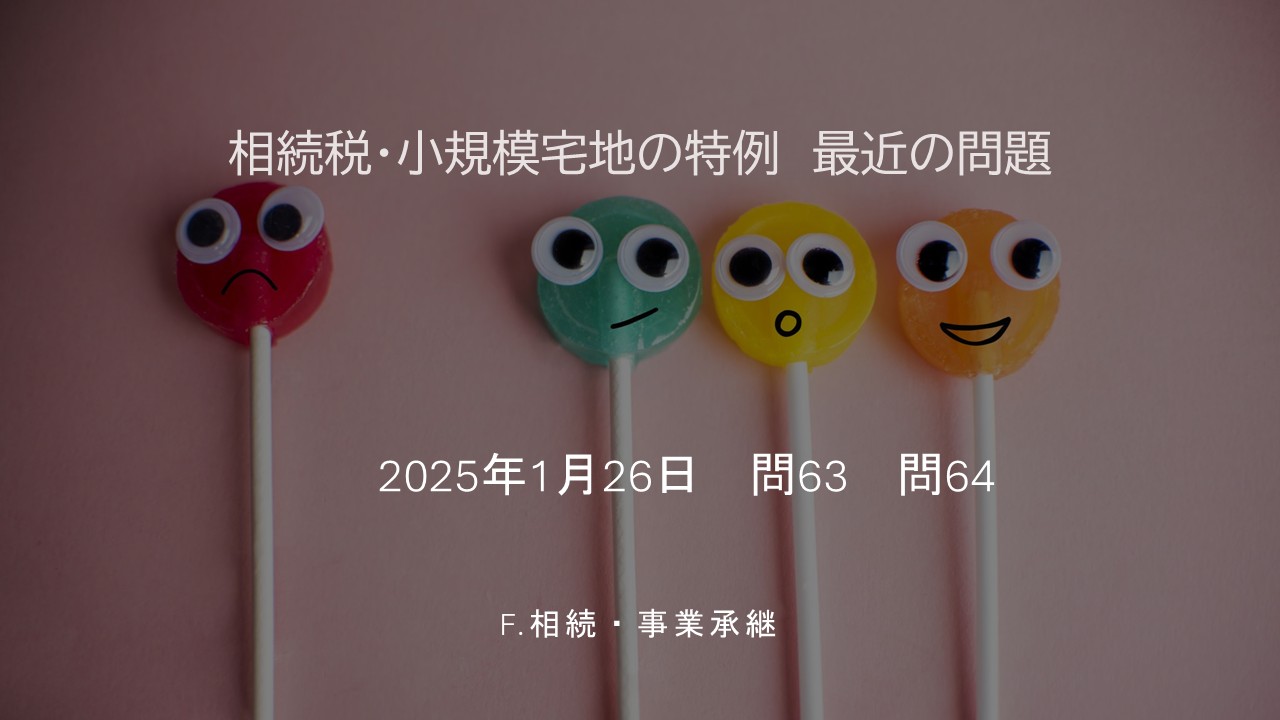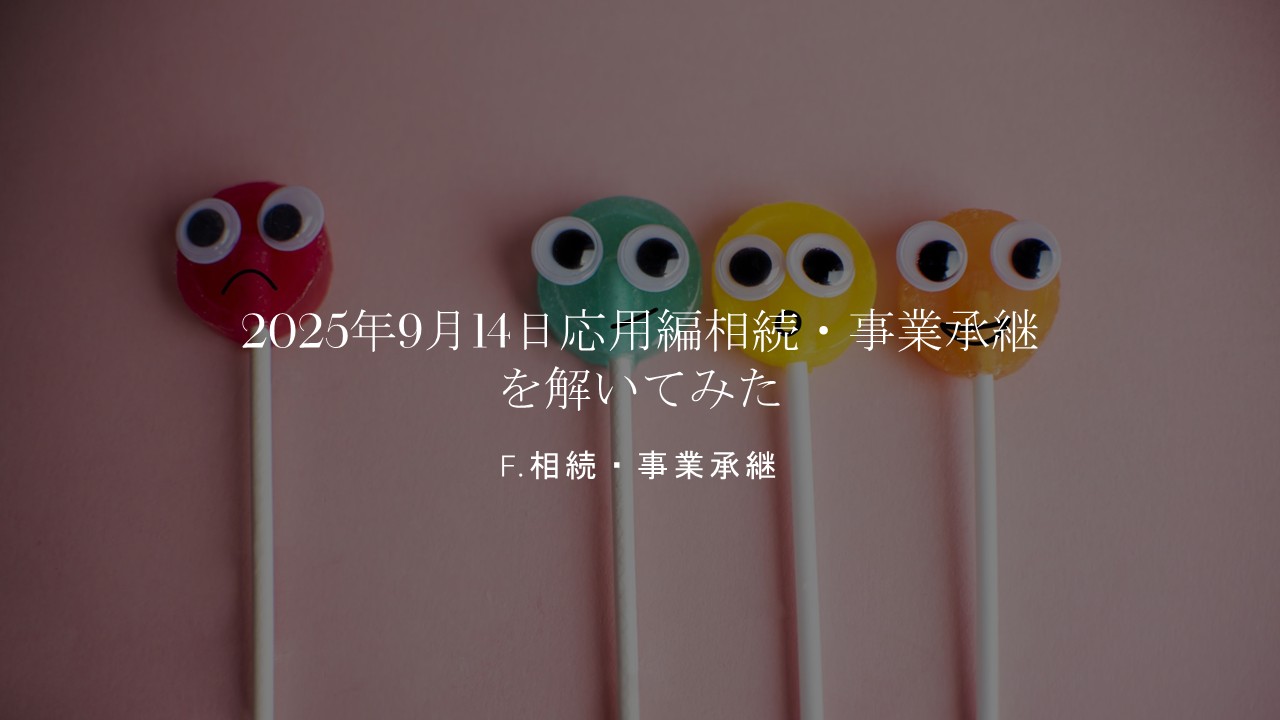事業承継における相続税・贈与税の納税猶予・免除

「事業承継における相続税・贈与税の納税猶予・免除」はFP試験において絶対に外せないテーマといえると思います。
昨年までは、「2024年3月31日までに、都道府県庁へ提出する必要がありましたが、これが、2026年3月31日までに延長されました。
特例措置の場合は、2027年12月31日までに贈与を行う必要があることは、延長されていないので、注意が必要です。
また、変更点としては、これまで後継者は「3年以上役員であることが必要でしたが」、変更後は「贈与の直前において役員であること」というように条件が緩和されました。
この部分は、基礎編の選択肢での出題が予想されるので、中小企業庁のHPなどで最新の情報取得をお勧めします。
過去問を3回分紹介し、解説しますが、ひょっとしたら最新の改正から照らし合わせて不適切な内容があるかもしれませんが、ここでは深堀をしませんので、ご容赦ください。
この分野も出所:一般社団法人 金融財政事情研究会1級 学科試験<基礎編>から問題を転載しております。
2024年5月26日 問50
| 「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 本特例の適用を受けるためには、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日までに、会社、後継者、先代経営者のそれぞれの要件を満たしていることについて都道府県知事の認定を受けなければならない。 2) 相続開始前に後継者が既に発行済株式総数の3分の2以上の当該非上場株式を保有していた場合、本特例の適用を受けることはできない。 3) 特例経営承継期間の経過後に後継者が会社の代表権を有しなくなった場合、特例経営承継期間を経過した日から後継者が会社の代表権を有しなくなった日までの期間に応じて、納税が猶予された相続税額のうち一定の金額を納付しなければならない。 4) 特例経営承継期間中は毎年、その期間経過後は3年ごとに、継続届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。 |
正解4

納税猶予は相続の場合と贈与の場合がわかれて、しかも一般措置と特例措置があるから、ややこしいね。
しかも、改正が行われることが多いから、以前、覚えた内容が通用するのか不安になっちゃうよ。

1)相続開始後5か月以内の申請が正しいね。
2)一般措置では発行済株式総数の3分の2が上限だけど、特例措置では100%が適用対象となるよ。
3)特例経営承継期間の経過後に後継者が代表権を失った場合、納税猶予は続くよ。
4)この記載は正しいね。
2022年5月22日 問50
| 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 自ら使用していない不動産の保有割合が総資産の総額の70%以上である資産保有型会社に該当する場合、原則として、本特例の適用を受けることはできないが、常時使用する従業員の数が5名(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)を超えなければ、本特例の適用を受けることができる。 2) 後継者である受贈者は、贈与の時において、会社の代表権を有していること、取締役や監査役等の役員等の就任から3年以上経過していること等の要件を満たす必要がある。 3) 本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。 4) 贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができる。 |
正解1

不動産保有特定会社の問題だね。株式保有特定会社もそうだけど、制約を受けることがあるから注意が必要だね。

1)大会社であれば、不動産の保有割合が70%であり、5名以上の従業員という表記は正しいけど、
中会社の場合は90%以上が土地保有特定会社の判定基準となるよ。
2)はこの時は正しかったけど、2025年現在は特例措置に関しては贈与の直前において役員であること」と緩和されているよ。
3)、4)は正しいんじゃないかな。
2022年1月23日 問50
| 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 先代経営者である贈与者は、贈与の時において、会社の代表権を有していないことが要件となり、有給の役員として残ることもできない。 2) 後継者である受贈者は、贈与の時において、原則として役員等の就任から3年以上経過していることの要件を満たす必要があるが、先代経営者である贈与者が70歳未満の場合、当該受贈者が役員等でなくても、本特例の適用を受けることができる。 3) 本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予される贈与税額と利子税の額の合計額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。 4) 贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続等により取得したものとみなして、相続時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、一定の要件を満たせば、引き続き、相続税の納税猶予の特例の適用を受けることができる。 |
正解3

事業承継税制は、会社の要件、先代経営者(贈与する人)、後継者(事業を受け継ぐ人)それぞれに要件があって、覚えなきゃいけなんだよね。

1)先代経営者は代表者は退任する必要があるけど、取締役として残るのとは可能だよ。
2)先代経営者の年齢によって、後継者の扱いが変わることは無いと思う。また、役員就任3年の条件も緩和されたしね。
3)これが正しい選択肢だね。
4)これは難しいな、相続税の課税価格に算入されるのは相続時でなく、贈与時の金額だね。