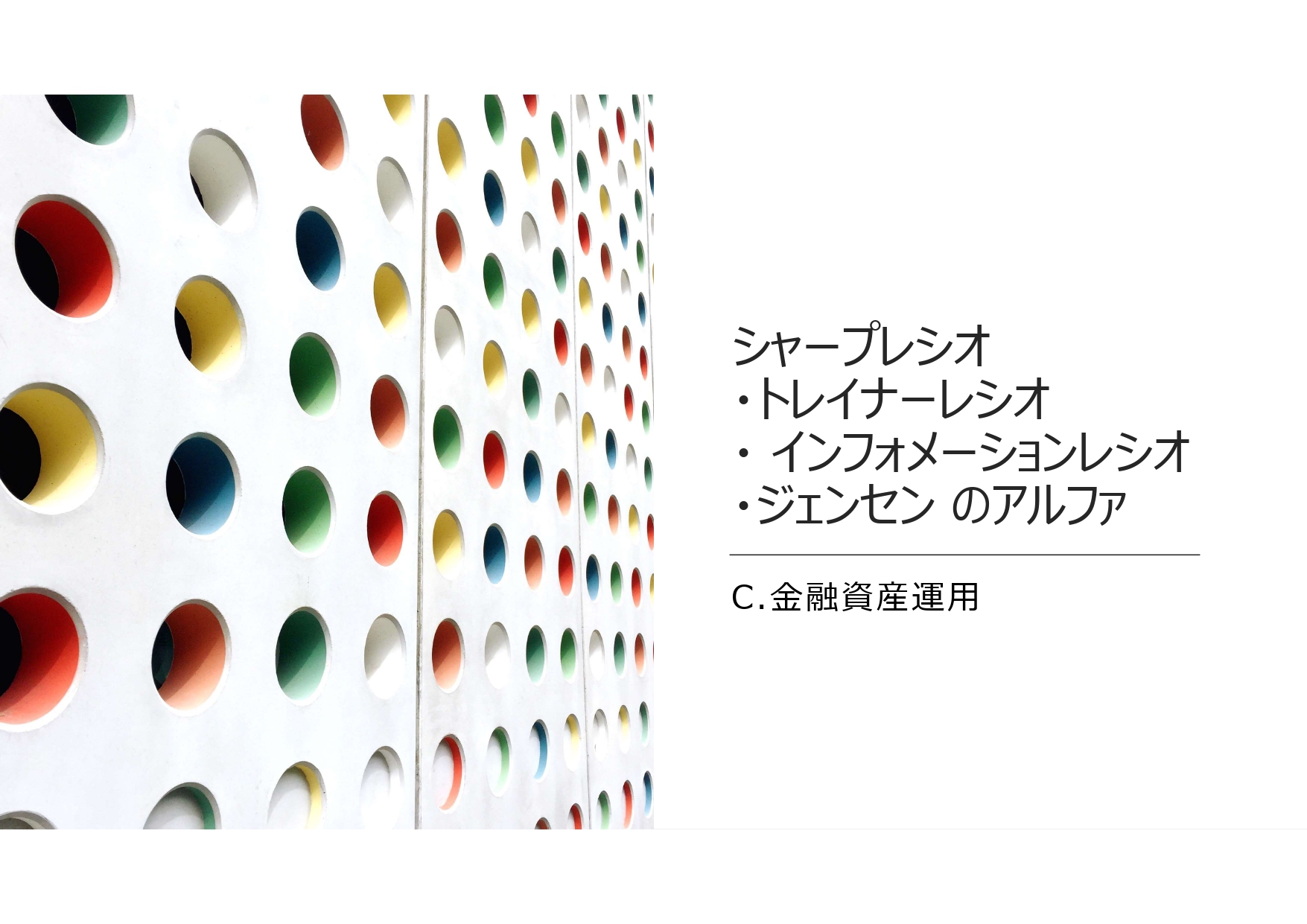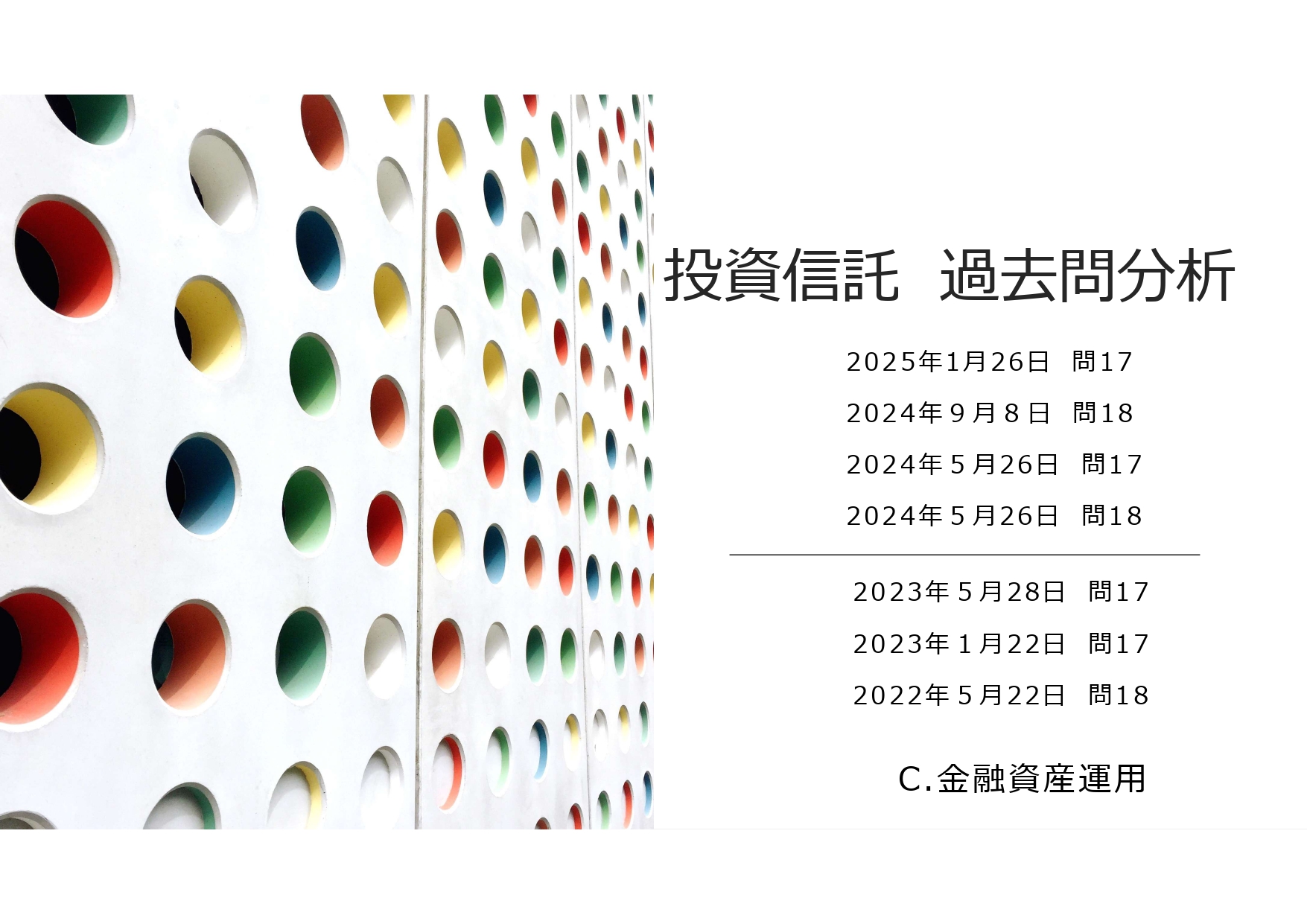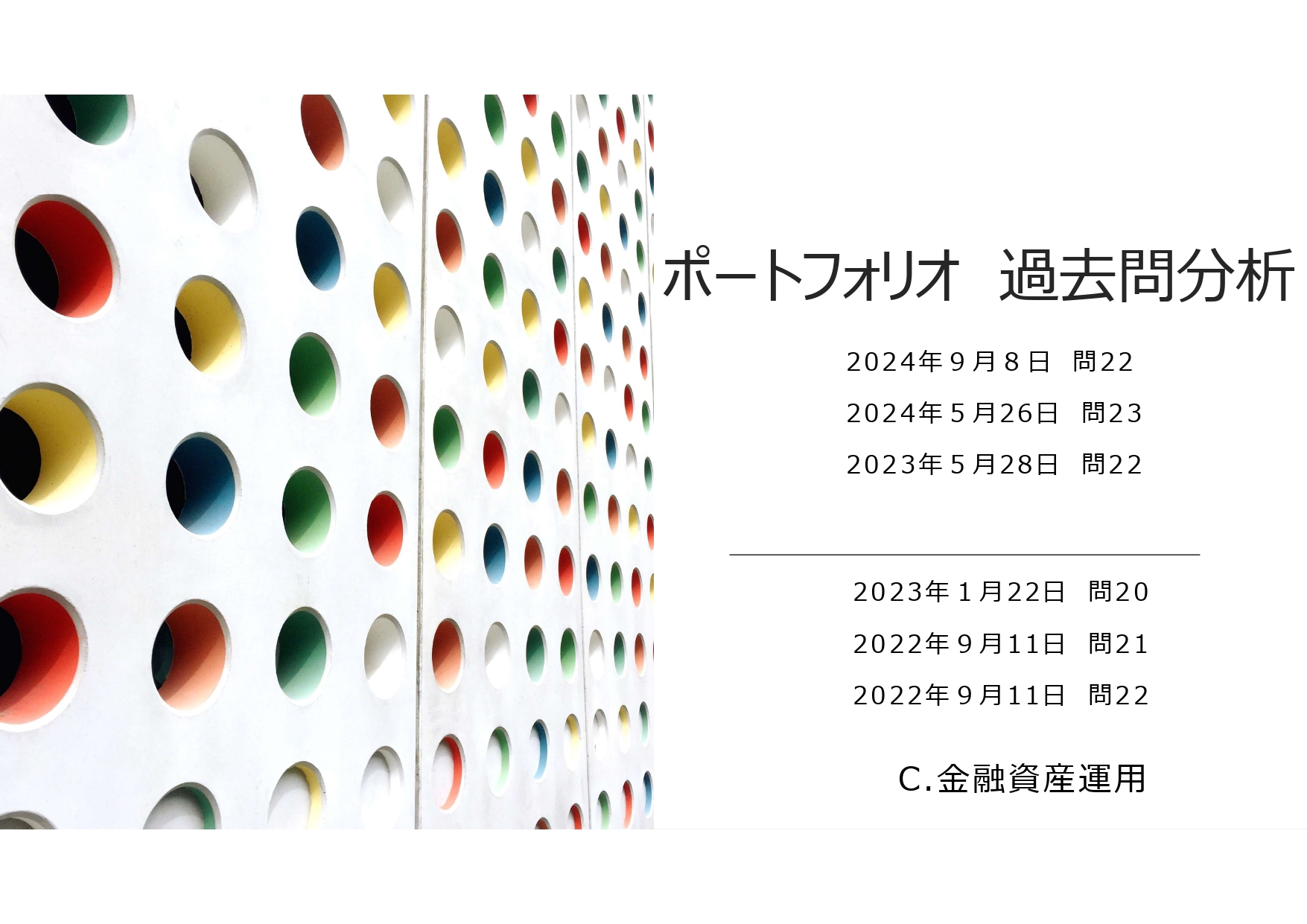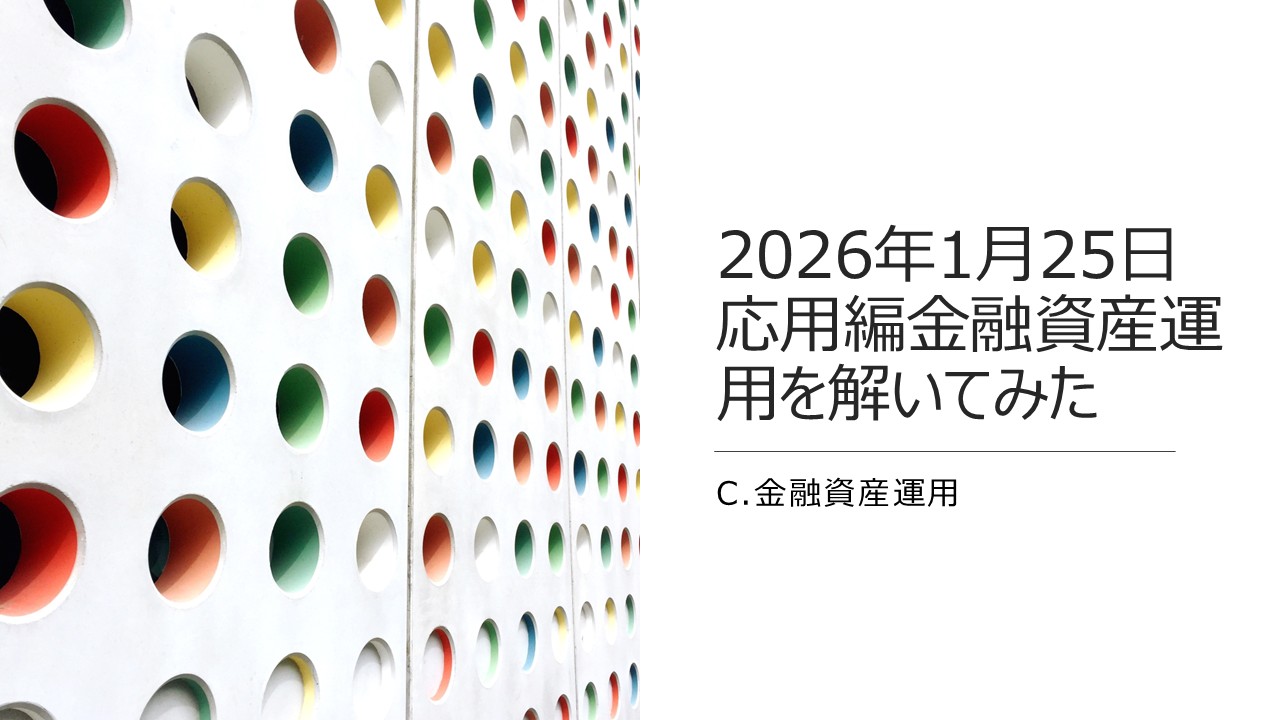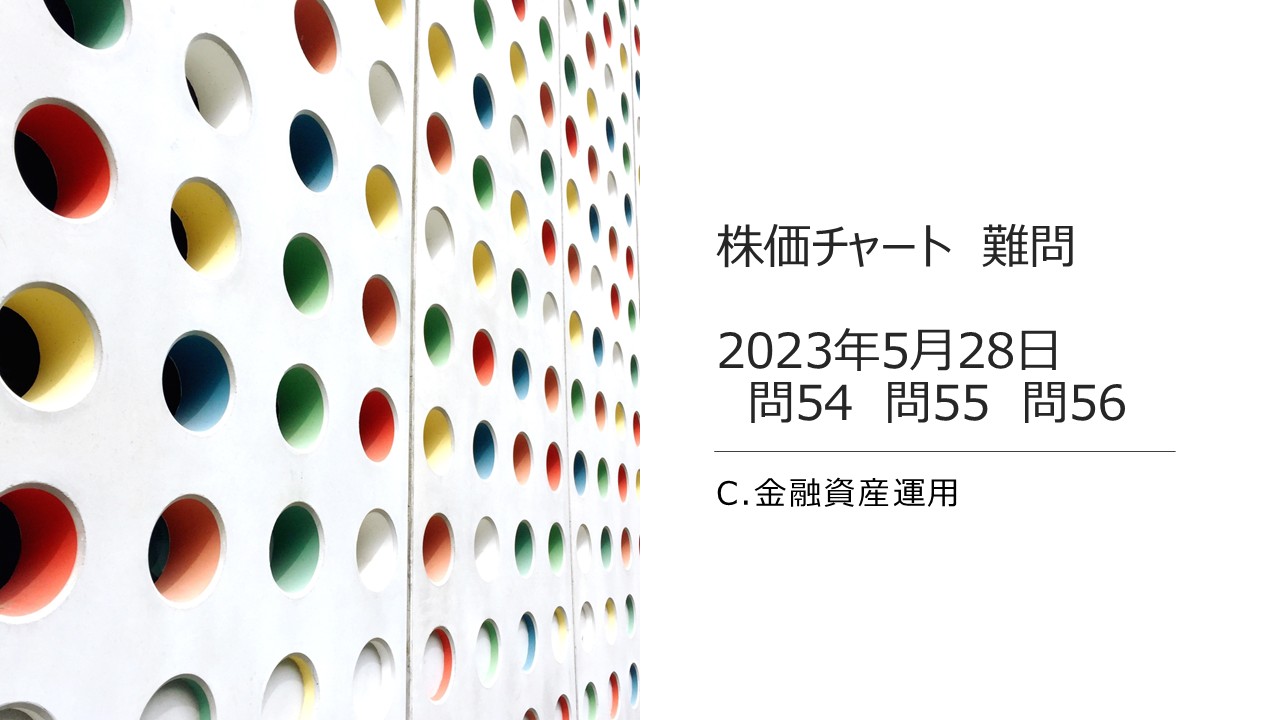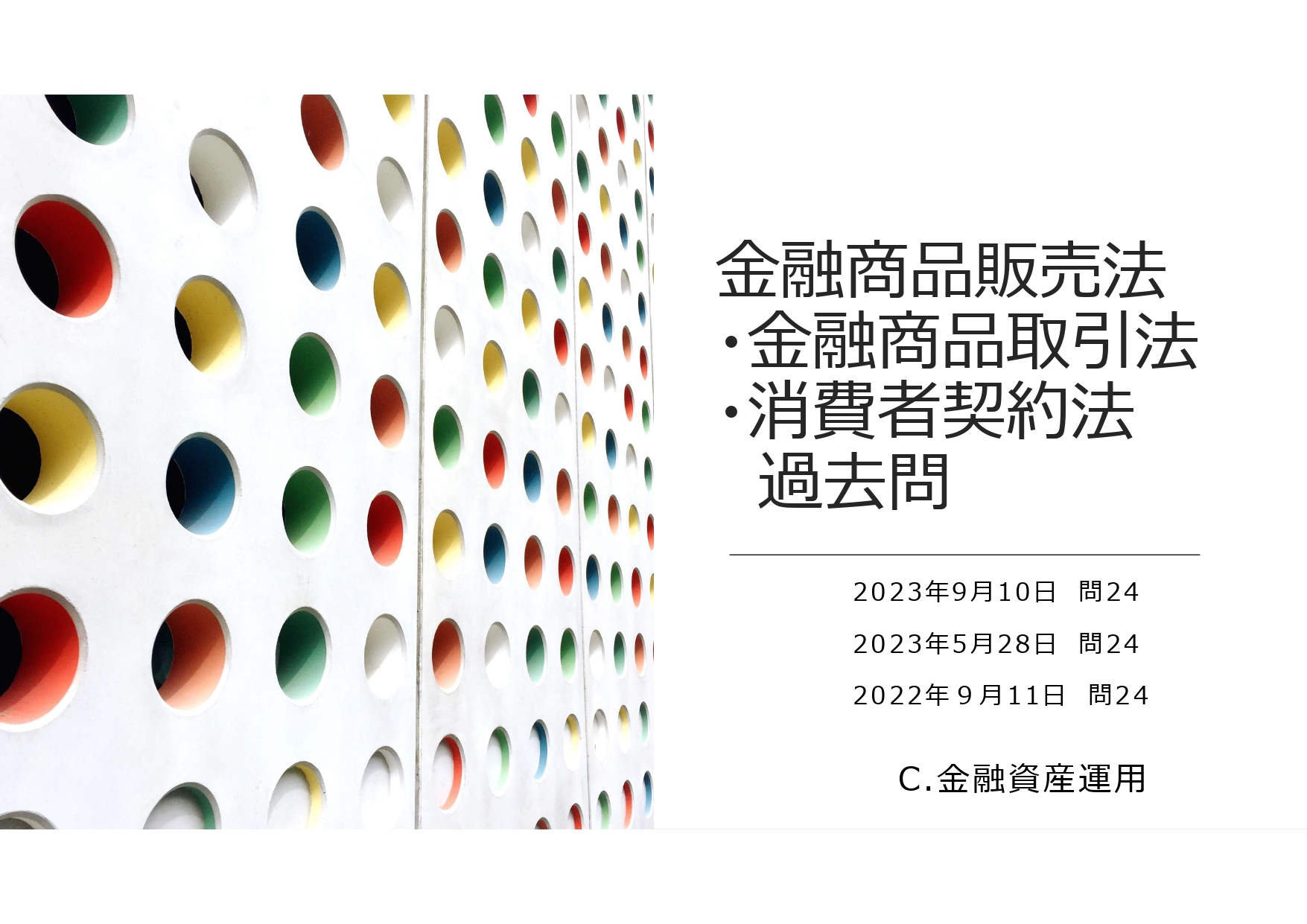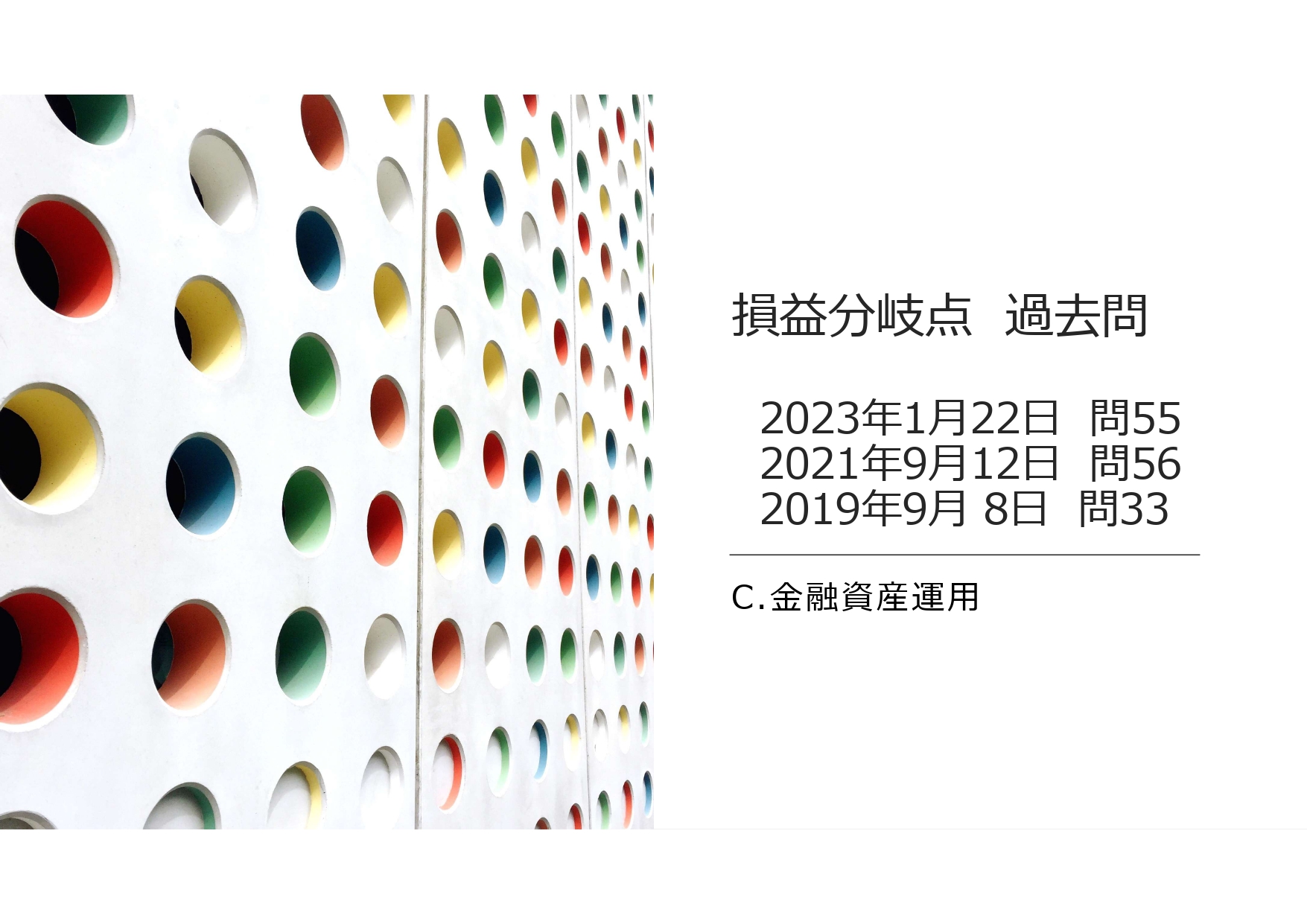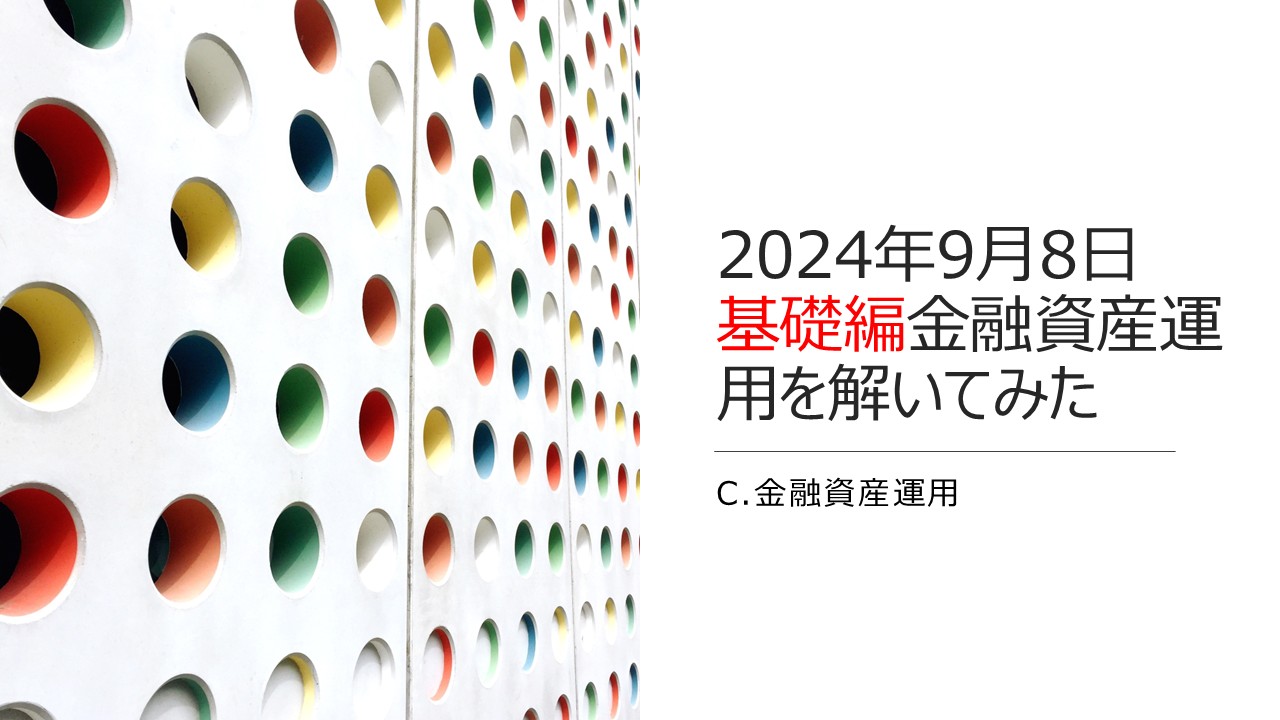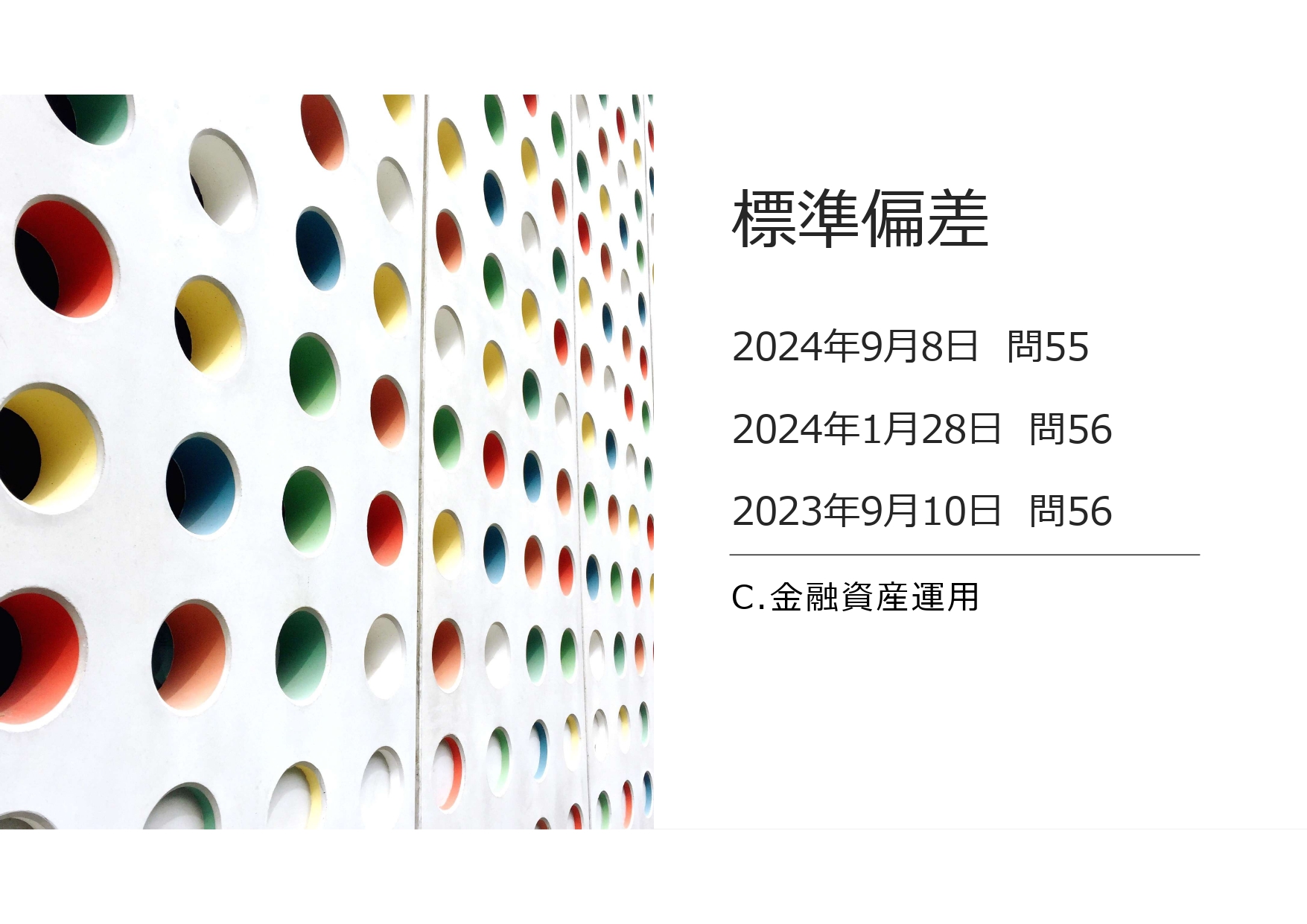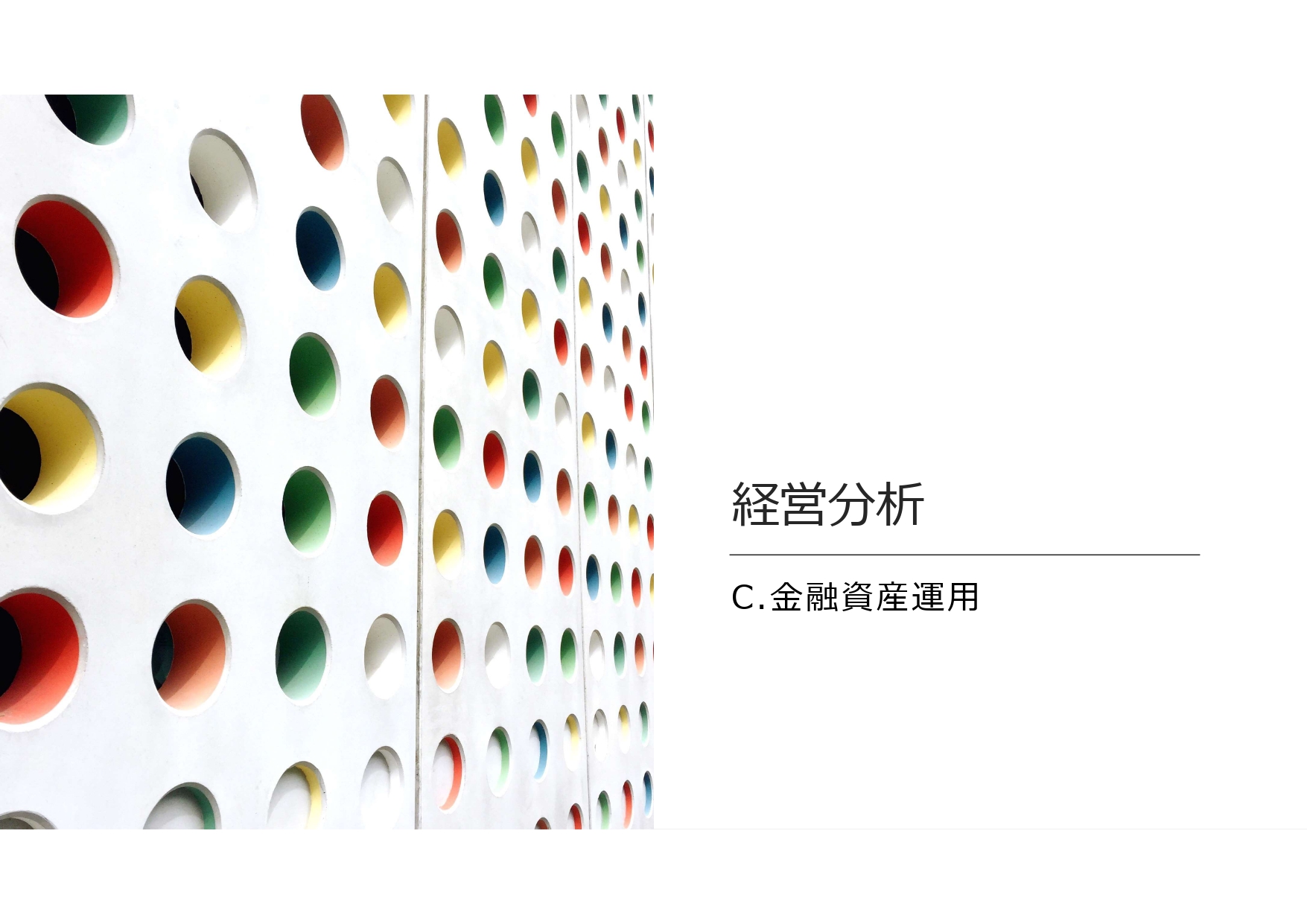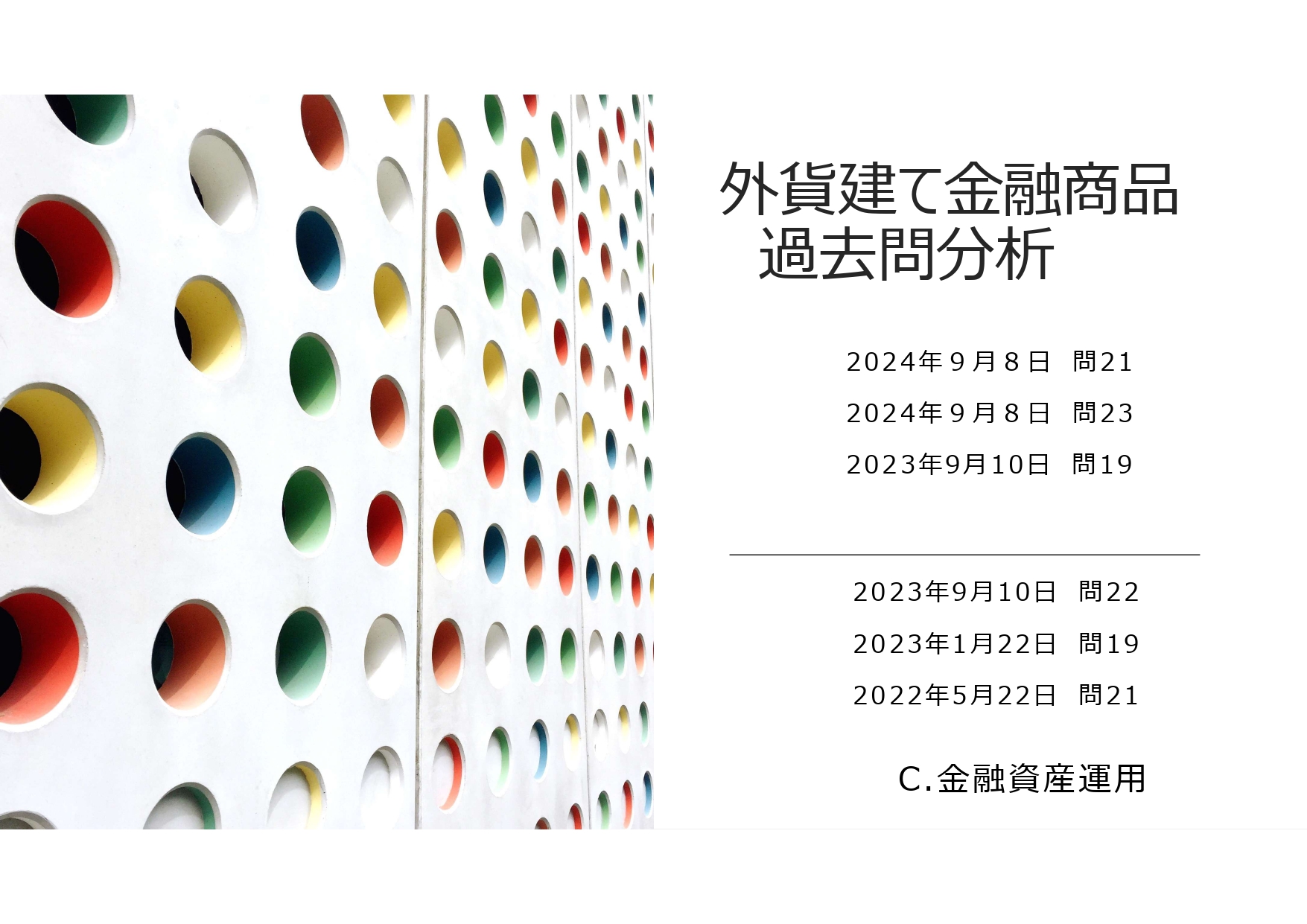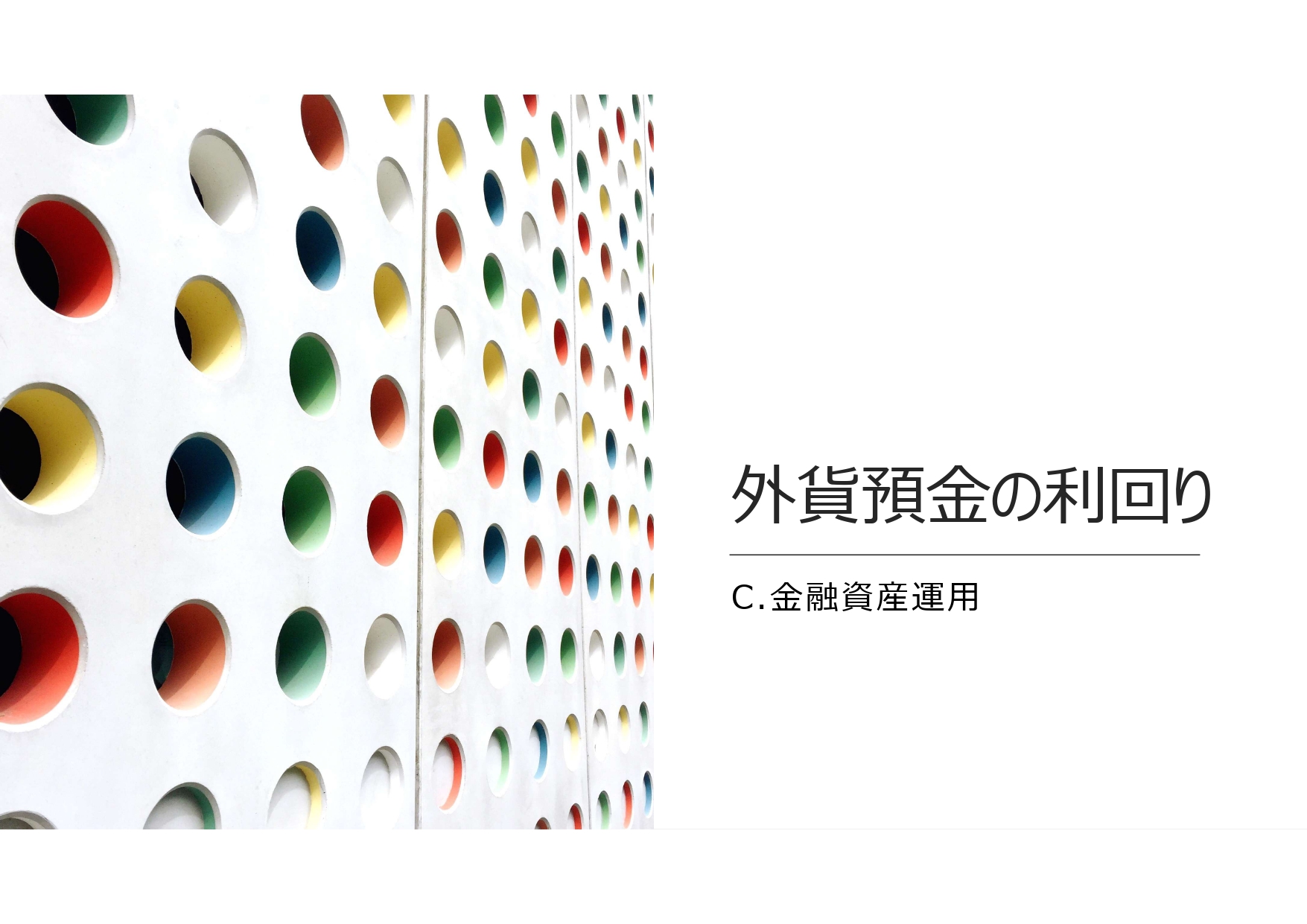2025年1月25日 基礎編 金融資産運用
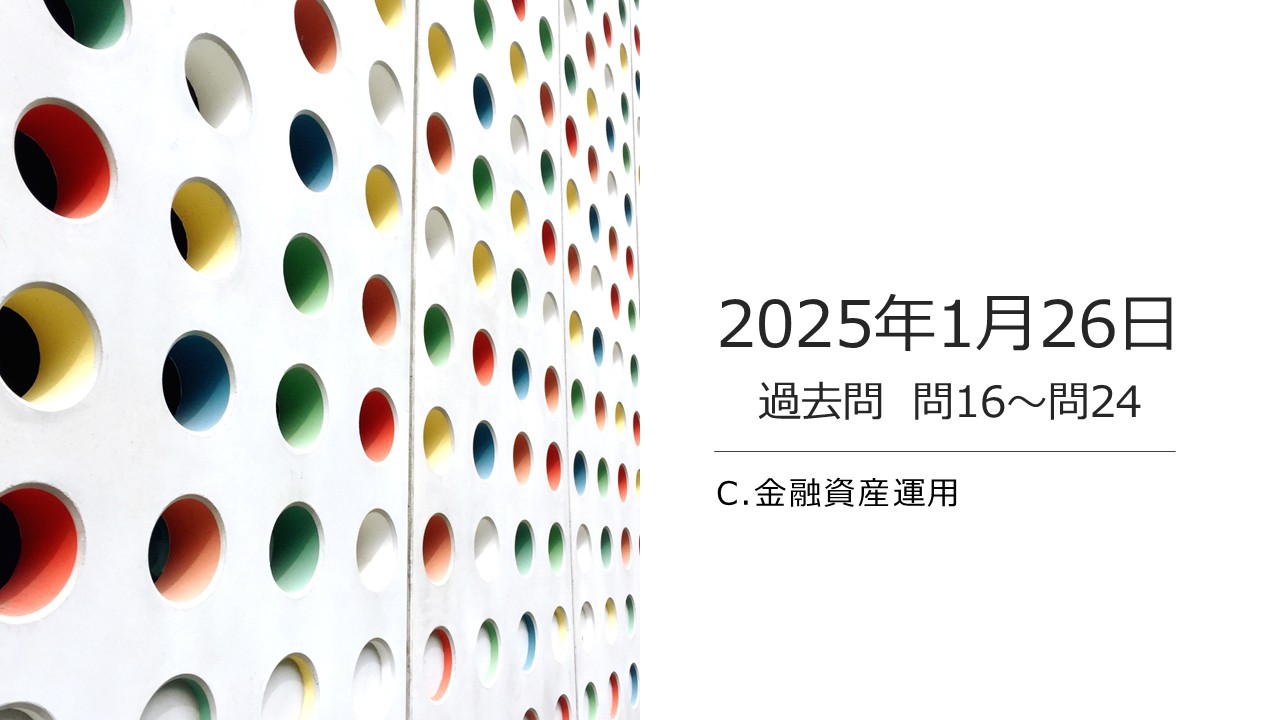
金融資産運用は私がFP受験を志すきっかけとなった科目です。
大学で経済学を学んだのですが、バブル経済崩壊から失われた30年に、何も前向きな提言ができず、後悔する日々です。
30年を振り返ると私は決して投資や資産運用が得意ではありません。
今思えば、あの時、この投資をしておけば今頃ということはありますが、後だしじゃんけんは誰でもできます。
それよりも自分や、社会が積み上げてきた失敗から学び、未来への礎にした方がいいのではないかと考えます。
FPは個別具体的な投資のアドバイスをする立場にはありません。将来の生活に不安を抱える方の資産形成に役立つ知識の提供ができれば、幸いです。
では、解説を始めます。今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問16 わが国の経済指標
| 《問16》 わが国の経済指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財やサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定したものであり、当該指数のうち、「生鮮食品を除く総合指数」は、内閣府が公表する景気動向指数の遅行系列に採用されている。 2) 企業物価指数は、企業が生産した財の出荷時の価格や企業が提供したサービスの価格の変動を、個別の取引総額に応じたウエイトを加味して測定したものであり、日本銀行が毎月公表している。 3) GDPデフレーターは、実質GDPを名目GDPで除すことによって算出される物価数であり、当該指数が持続的に上昇している場合、インフレーションの状態にあると判断される。 4) 原油価格などの輸入品価格の上昇は、その上昇分が国内の製品価格等にすべて転嫁されない限り、GDPデフレーターの上昇要因となる。 |
正解1

先行系列11、一致系列10、遅行系列9の合わせて30の名称はなかなか覚えられないんだけど、代表的なものだけでも覚えるよう努力が必要だね。
試験の直前30分前に見て、丸暗記したことを覚えているけど、名前を覚えるだけではだめで、どこから公表されているかを問う問題とか出題されたりするんだよね。

1)消費者物価指数が遅行系列は基本だね。しかし、最初と最後だけ読むと、途中の説明にひっかけがあったりするから注意が必要だよ。今回はこれが正解だね。
2)企業物価指数は企業間で取引される財の価格変動を測定する統計指標だからサービスじゃないね。財は所有権の移転を伴うものであるけど、サービスは所有権の移転を伴わないものだね。
3)GDPデフレーターは、名目GDPを実質GDPで除したものだから分母と分子が逆だね。
4)3)の正しい式がわかれば逆であることがわかるね。
問17 投資信託
| 《問17》 投資信託の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) ファミリーファンド方式の投資信託では、投資家がマザーファンドを購入することにより集まった資金を、国内外の株式や債券等を投資対象とする複数のベビーファンドに振り分けて運用が行われる。 2) ロング・ショート型の投資信託は、相対的に割安と考えられる銘柄を買い建てるとともに、相対的に割高と考えられる銘柄を売り建てることで、市場の変動にかかわらず、収益の獲得を目指すものである。 3) ブル型の投資信託は、原指標の変動率に一定の正の倍数を乗じて算出される指標に連動する運用成果を目指すものであり、市場の上昇局面ではより高い収益率を期待することができる。 4) 外貨建MMFは、主に外国の格付の高い公社債やコマーシャルペーパー等を投資対象として運用される外貨建ての投資信託であり、株式は投資対象とされない。 |
正解1

投資信託は新NISAで買っているけど、正直、証券マンから提示された選択肢の中から、なんとなく選んでいるだけで、深く考えていないんだよね。
FPとしては、せめて違いを説明できるようにならなきゃね。

1)これは単純にマザーファンドとベビーファンドの説明が逆だね。よってこれが不適切。
2)~4)は適切だから、この選択肢の文章ごと覚えることをお勧めするよ。
問18 債券投資
| 《問18》 債券投資に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 残存期間が長い債券の利回りよりも残存期間が短い債券の利回りのほうが低く、イールドカーブが右上がりの曲線となる状態を、逆イールドという。 2)イールドカーブが順イールドの状態である場合において、時間の経過とともに債券価格が上昇することによってキャピタル・ゲインが期待されることをロールダウン効果といい、一般に、イールドカーブがフラット化するほど、ロールダウン効果は高くなる。 3) 残存期間が同じであれば、利付債よりも、割引債のほうがデュレーションは短くなる。 4) 他の条件が同一であれば、債券の表面利率が低いほど、また残存期間が長いほど、デュレーションは長くなる。 |
正解4

これは基本的な知識と、文章の読解力の問題のような気がするね。
イールドカーブやデュレーションって投資しててあまり意識することないけどな。甘いのかな。

1)イールドカーブが右上がりだと順イールドだね。
2)坂道を連想すれば、フラット化は平面に近く、スティープ化は急斜面になるから説明が逆だね。
3)デュレーションは回収にかかる期間だね。利付債と割引債はたまに計算問題も出題されることがあるから要注意だね。計算式で考えたら説明が逆っていうのがわかるよ。
4)これが正しいね、デュレーションが短ければ早く回収できるとだけ覚えてもいいかもね。
問19 米国の株価指標
| 《問19》 米国の株価指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) S&P500種株価指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQ市場などに上場している500銘柄を対象とする修正平均型の株価指数である。 2) ダウ・ジョーンズ工業株価平均(ニューヨーク・ダウ)は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQ市場に上場している100銘柄を対象とする修正平均型の株価指数である。 3) ナスダック総合指数は、NASDAQ市場に上場している全銘柄を対象とする時価総額加重平均型の株価指数である。 4)ラッセル2000指数は、ニューヨーク証券取引所やNASDAQ市場などに上場している銘柄のうち、時価総額上位2000銘柄を対象とする時価総額加重平均型の株価指数である。 |
正解3

米国の株価指標も苦手だね。日本に比べてアメリカは株価が好調というイメージがあるから、ちゃんと理解して投資やアドバイスに活かさないといけないけどね。

1)S&P500は時価総額加重平均型だから違うね。
2)NYダウは30種平均だね。ニュースに耳を傾けていると強いかも。
3)これが正解だね。
4)上位2,000社ではないね。時価総額加重平均型が合っているから間違いやすいね。
ややこしいけど、以下のものは覚えておいてもいいかもね。
修正平均型・・・日経平均株価、NYダウ
時価総額加重平均型・・・東証株価指数TOPIX、SP500、ナスダック総合指数、ラッセル2000
問20 サスティナブル成長率
| 《問20》 下記の〈資料〉から算出されるサスティナブル成長率として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、自己資本の額は純資産の額と同額であるものとし、計算結果は 表示単位の小数点以下第3位を四捨五入すること。 〈資料〉 |
| 株 価 収 益 率 | 12.80倍 |
| 株価純資産倍率 | 0.80倍 |
| 配 当 利 回 り | 4.20% |
| 配 当 性 向 | 35.00% |
| 1) 4.06% 2) 5.60% 3) 5.99% 4) 10.40% |

苦手な国語の問題を終えて、やっと得意な数学の問題になったという感じだね。 この問題は、2025年1月にも出題されているので取りたいね。

この問題を解くためにはサスティナブル成長率=ROE×(-配当性向)という式が頭に入っていないといけないね。
次に問題なのがROEの求め方だけど株価純資産倍率÷株価収益率となるんだけど、これは覚えるというより、それぞれの式を分解して割り算で求める方が近道だね。
ピンとこなければ上場企業のROEは約10%くらいと覚えておいて見当をつけるというのもありだと思う。
今回の問題では0.80倍÷12.80倍×(1-35.00%)=4.06% で答えは1)だね。
問21 オプション取引
| 《問21》 オプション取引の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) ノックイン・オプションやノックアウト・オプションなどのバリア・オプションは、バリア条件のないオプションと比較すると、他の条件が同一である場合、通常、オプション料は高くなる。 2) フロアは、フロアの買い手が売り手に対してオプション料を支払うことにより、原資産である金利があらかじめ設定した金利を下回った場合に、その差額を受け取ることができるオプション取引である。 3) ITM(イン・ザ・マネー)は、コール・オプションの場合は原資産価格が権利行使価格を上回っている状態をいい、プット・オプションの場合は原資産価格が権利行使価格を下回っている状態をいう。 4) オプション取引において、権利行使期間中であればいつでも権利行使が可能なものをアメリカンタイプという。 |
正解1

先物取引とオプション取引の違いは先物取引が将来、「買う」か「売る」のを予約するものであるのに対して、オプション取引は、将来、「買う権利」を買うか「売る権利」を買うものというものだよ。

恥ずかしながらオプション取引は未経験なのでグーグル検索でわかる範囲で記載するよ。
1)バリアオプションの料率は通常より低いよ。これが間違いだね。
2)フロアは下限、キャップが上限だね。イメージで覚えよう。
3)インザマネーは投資家にとって有利な場面と覚えておけばいいかも。原資産価格と権利行使価格の関係は問題文のとおり覚えておくといいかも。
4)アメリカンタイプは問題文の通り、逆に満期日にのみ権利行使できるタイプはヨーロピアンタイプだね。
問22 A資産とB資産の相関係数
| 《問22》 下記の〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉から算出されるA資産とB資産の相関係数として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。 |
〈A資産とB資産の期待収益率・標準偏差・共分散〉
| 期待収益率 | 標準偏差 | A資産とB資産の共分散 | ||
| A資産 | 3.25% | 4.75% | 9.80 | |
| B資産 | 3.40% | 5.85% | ||
| 1) 0.17 2) 0.28 3) 0.35 4) 0.38 |

これは応用編の計算問題としても出題されそうな問題だね。
相関係数と共分散の関係は覚えておく必要があるよ。

相関係数=共分散÷(Aの標準偏差×Bの標準偏差)なので、
9.80÷(4.75×5.85)=0.35267・・
よって正解は3)0.35だね。 相関係数は―1~1の間で1に近づくほど正の相関、―1に近づけば負の相関があるといわれて、0に近いほど、無関係だっていわれるね。
問23 NISA
| 《問23》 NISAに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 一般口座や特定口座で保有する上場株式等は、NISA口座に移管することができない。 2) NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。 3) NISA口座を開設する金融機関について、現在開設している金融機関とは別の金融機関に変更するためには、変更を希望する年分の属する年の前年の10月1日から変更を希望する年分の属する年の9月30日までに所定の手続をする必要がある。 4) NISA口座を開設した者が海外転勤により出国する場合、当該口座を開設している金融機関に出国の日の前営業日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出することにより、出国後も引き続き当該口座で上場株式等を購入することができ、その譲渡益や配当等は非課税となる。 |
正解4

令和の現在、NISAといえば新NISAだけど、平成から投資をやっている人にとっては一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年だったんだよね。そのころから考えれば、投資しやすくなったよね。

1)これは実体験があった人は強いかもね。NISA口座には移せないね。
2)この問題も、応用編で株式数比例配分方式という単語をかかせる問題が過去にはあったね。
3)これも経験ある方は少ないかもしれないけど、正しいよ。
4)これが間違っているね、海外に転居する方はNISA口座で取引はできなくなるね。
問24 日本投資者保護基金による補償の対象
| 《問24》 国内に本店のある証券会社に一般顧客が預けた次の金銭のうち、日本投資者保護基金による補償の対象とならないものはどれか。 1) 株式の信用取引に係る委託保証金 2) 外国為替証拠金取引に係る証拠金 3) 東京金融取引所の「くりっく株365取引」に係る証拠金 4) 大阪取引所の日経225先物取引に係る証拠金 |
正解2

どれもやったことないけど、リスク高めの取引だよね。

1)信用取引は補償の対象だね。補償と保証で漢字間違えそうだけど、信用取引は30万円の保証金で100万の取引までできる取引だよね。
2)これは通称FX取引だよね。これが対象外なのは割と有名だね。
3)くりっく株365取引は知らないので、今後、調べます。
4)大阪取引所の日経225先物取引は対象なんだね。勉強を継続しなきゃいけないね。