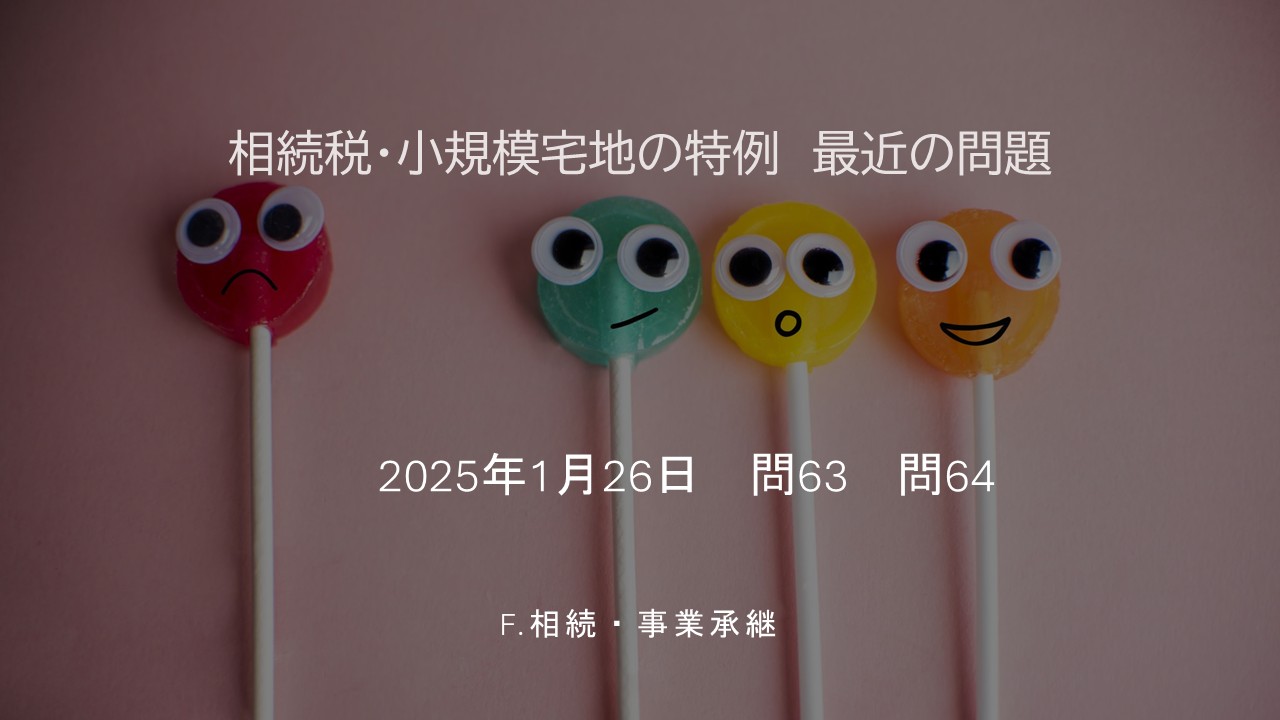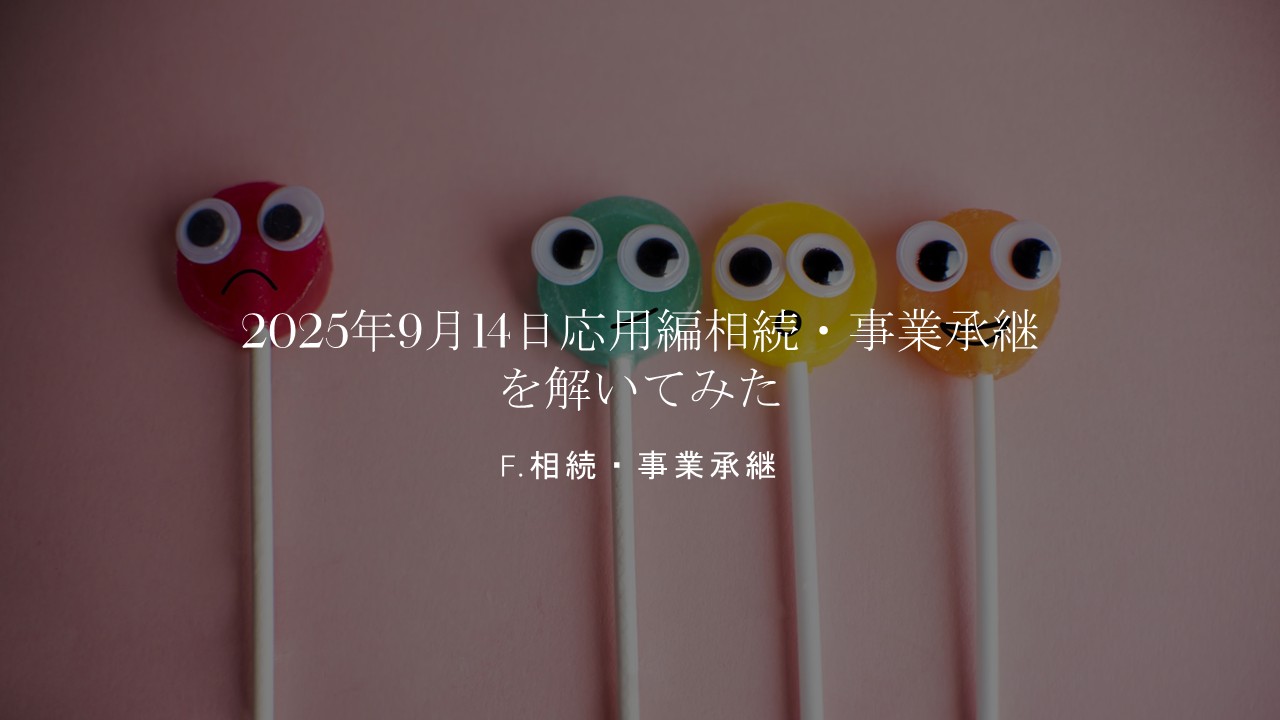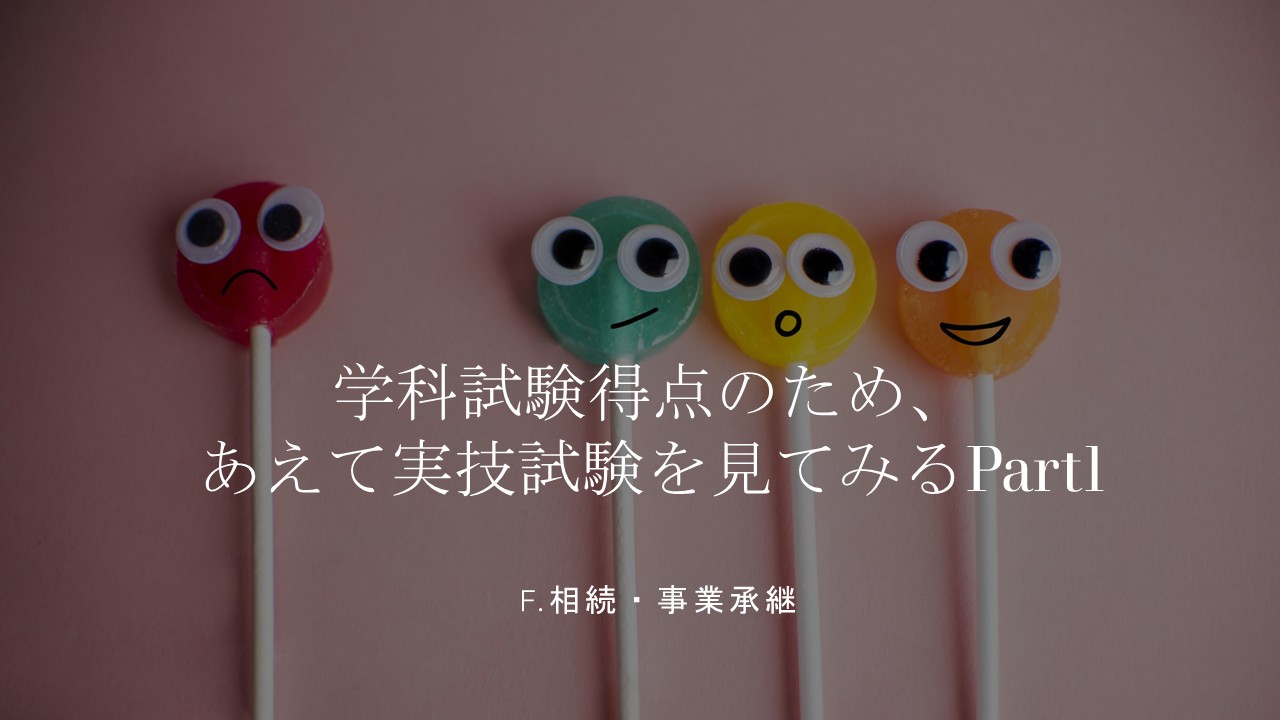2025.5.25基礎 相続・事業承継

FP1級試験を合格しようと思った時、一番のボリュームで合格を左右するのが相続・事業承継の分野だと思います。
応用編は難問が出題される回もありますが定番の問題も多く、得点源になることが多いですし、一般社団法人金融財政研究会の実技試験を受験される方は、具体的な事例をもとに、相続・事業承継を考えることになります。
皆さんの身の回りに相続税を払ったことのある方はどのくらいいるでしょうか。
少し古い統計データですが国税庁によると2020年の課税割合は8.8%だそうです。
このブログを始めた頃に投稿した「税金~日本の家計簿」という記事でも記載しましたが、歳入に占める相続税の割合は2.9%で、今、話題となっている消費税の21.2%と比べても規模が小さいことがわかります。
しかし、相続税はFPが相談を受けるテーマとなりやすいといえます。
事業を行っている方には顧問税理士がついていて相続対策をされているでしょうが、そういう方ばかりではありません。一般的な知識を広めるという意味でも、事前に準備できることもあることを広く知っていただくことは意義のあることだと考えます。
この分野に関わらず、一般の方にあまり知られていない知識というのはあると思いますので、私のわかる範囲でなるべくお伝えできればと思います。
それでは、2025年5月25日基礎編のラスト、相続・事業承継分野を説明したいと思います。出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問42 贈与
| 《問42》 贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 負担付贈与は、受贈者に一定の給付をなすべき義務を負わせる贈与であり、その受贈者の負担から利益を受ける者は贈与者に限られる。 2) 書面によらない贈与は、履行が終了した部分を除き、贈与者または受贈者が解除をすることができる。 3) 定期贈与は、贈与者が死亡した場合には、当然にその効力が失われるが、受贈者が死亡した場合には、その相続人に定期の給付を受ける権利が承継される。 4) 死因贈与の内容と贈与者が作成した遺言書の内容に抵触する部分がある場合、死因贈与が贈与者と受贈者との合意によってなされる契約であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示であるため、その抵触する部分は常に死因贈与の内容が優先される。 |
正解2

FPの勉強を始めてから贈与って意識するようになったけど、他人は別として親や祖父母からの贈与って意識することなかったよね。

1)負担付贈与は利益を受けるのは贈与者とは限らないよね、子の面倒をみてくれることを条件に知人に贈与するとかありえそうだもんね。
2)口約束では、双方から取り消し可能だね。そもそも言った言わないって第三者が証明も難しいしね。
3)定期贈与は相続の対象にはならないね。贈与って人間関係で成り立っていることも多いからね。
4)常識として、相反する意思判断を示す文書があったとしたら日付の新しいものが優先されるね。
問43 贈与税の配偶者控除
| 《問43》 贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 1) 夫から居住用不動産の贈与を受けた妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、夫との婚姻期間が贈与を受けた日の属する年の1月1日において20年以上でなければならない。 2) 夫から妻に対して、居住用不動産(相続税評価額2,500万円)の贈与が行われ、妻が贈与税の配偶者控除の適用を受けた年の翌年に夫が死亡した場合、夫の相続により財産を取得した妻の相続税の課税価格に390万円が加算される。 3) 夫が保険料を負担していた生命保険契約に基づき、贈与税の課税対象となる保険金を受け取った妻が、その保険金により居住用不動産を取得した場合、贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる。 4) 夫から妻に対して、店舗併用住宅の贈与が行われた場合、その家屋の専ら居住の用に供している部分の床面積が、家屋の床面積の2分の1以上でなければ、贈与税の配偶者控除の適用を受けることはできない。 |
正解3

贈与税の配偶者控除も実技試験で頻出の話題だね。面接官の突っ込みに答えられず、撃沈する恐れがあるからしっかり理解しよう。

1)これもよくひっかかるね。おしどり夫婦の特例は贈与時に20年だからね。不動産の特例は1月1日時点で〇〇年というのがあるから混同しないように注意が必要だよ。
2)おしどり夫婦の特例は相続税には加算されないよ。相続と贈与の課税関係は正確には税理士に相談することをお勧めするけど、FPとしても勉強を継続するよ。
3)これは正解の選択肢だね。相続税の配偶者控除と贈与税の配偶者控除が分けて理解するのが難しいけど、私ももっと勉強するよ。
4)店舗併用住宅の住宅部分の面積が問われることが多いけど、贈与税の配偶者控除については面積の要件はないと思うよ。
問44 相続土地国庫帰属法
| 《問44》 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律における土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認申請に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 相続人が相続等により取得した土地について、当該相続等を原因とする所有権移転登記をしなければ、当該土地に係る承認申請をすることはできない。 2) 相続等により取得した土地に係る承認申請にあたって、承認申請者は、所定の審査手数料を納付しなければならず、その承認に係る土地の所有権の国庫への帰属にあたっては、所定の負担金を納付しなければならない。 3) 土地が数人の共有に属する場合において、その有する共有持分の全部を相続等以外の原因により取得した共有者は、相続等により共有持分の全部または一部を取得した共有者と共同して、当該土地に係る承認申請をすることができる。 4) 抵当権が設定されている土地については、承認申請をすることができない。 |
正解1

相続土地国庫貴族法はニュースにもなってたから、やはり出題されるね。
実際に、田舎の土地を相続したけれど、使う予定がなく、売るにも売れず、固定資産税だけ払い続けている人って多そうだもんね。

1)相続による移転登記をしなくても承認申請は可能なので、これが誤りだね。そもそも相続した土地がいらないから使う制度だもんね。
2)審査手数料一筆につき14,000円、承認後の負担金は最低20万円が必要になるよ。検討の際は、相続した資産の固定資産税との比較で決めることになるかもね。
3)これは当然かもね、相続で土地が共有になることって、ありそうだもんね。
4)これも当然だね。ちなみに建物がある土地、境界があいまいな土地もこの制度は使えないよ。
問45 特別受益
| 《問45》 民法における特別受益に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 (a) 父の相続が開始する1年前に、父から時価1,000万円の農地の贈与を受けた子が、当該農地について宅地造成を行って自宅を建築したことにより、父の相続時における当該宅地の時価が1,200万円となった場合、原則として、特別受益に係る贈与の価額は1,200万円となる。 (b) 母の相続が開始する3年前に、母から居住用不動産の贈与を受けた子が、母の相続において相続の放棄をした場合であっても、当該居住用不動産は、原則として、特別受益の持戻しの対象となる。 (c) 夫が妻に対し、夫婦で居住の用に供している不動産を贈与した場合に、当該夫婦の婚姻期間が10年以上であるときは、夫は、その贈与について特別受益の持戻し免除の意思を表示したものと推定される。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解4

特別受益は、相続人間の不平等をなくすための精度で、特別受益を相続財産に加えて、計算することになるんだよね。

(a) これは贈与時の1,000万円が特別受益になるから、間違いだね。
(b) これもややこしいけど、相続放棄をしたら相続人ではなくなるから相続財産には含めないというのが正しいね。
(c) これは10年でなく20年が正しいね。「特別受益の持戻し免除の意思を表示したものと推定」って判例の用語ってわかりにくいね。
よって正しいものがなく4)が正解だね。なしを選択するのって勇気がいるけど、FP試験ではよくあるんだよね。
問46 配偶者居住権
| 《問46》 民法における配偶者居住権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 配偶者居住権は、居住建物の全部について無償で使用および収益をする権利であるが、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者は配偶者居住権を取得することができない。 2) 配偶者居住権を有する配偶者は、配偶者居住権を譲渡することができず、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用または収益をさせることができない。 3) 配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議等において別段の定めがされた場合を除き、配偶者の終身の間とされている。 4) 配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合、居住建物の所有者が、その消滅直前に当該配偶者が有していた配偶者居住権の価額に相当する金額を、相続または遺贈により取得したものとみなされる。 |
正解4

配偶者居住権も毎回のように基礎編で出題されるテーマだね。終の棲家の問題は、今後ますます注目される問題なのかもね。

1)配偶者居住権は共有者がいた場合には成立しないよ。円満な家族で皆さんの同意が得られるなら住処についての心配もすることないのだろうけどね。
2)これは適切な文章で、よく出題される論点だから覚えておくといいと思うよ。
3)これもその通り、修身の間、住み続けられる権利だからね。
4)これが間違いだね。配偶者居住権は相続の対象にはならないよ。
問47 相続税の課税財産等
| 《問47》 相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を父、死亡保険金受取人を子とする終身保険において、父の死亡により死亡保険金を受け取った子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。 2) 交通事故で重傷を負った夫に対して、その事故の加害者から損害賠償金が支払われることが決まっていたが、支払われる前に夫が死亡し、妻が当該損害賠償金を受け取ることとなった場合、その損害賠償金を受け取る権利は相続税の課税対象とならない。 3) 被相続人が死亡し、被相続人に支給されるべきであった退職金の支給額が被相続人の死亡後3年以内に確定した場合、実際に支給された時期が被相続人の死亡から3年経過した後であっても、その退職金は相続税の課税対象となる。 4) 被相続人の死亡によりその雇用主等から相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。 |
正解2

相続人が日本国籍と国内に住所を有する個人とあるから意識しなくてもいいけど、国外在住で国籍が外国のパターンもあるから、そのときは注意が必要だよ。
ちなみに「ほんださん/東大式FPチャンネル」というユーチューブに私は助けられたから、お勧めするよ。

1)これは正しいね、正し保険金が受け取れなくなるわけじゃないので注意が必要だね。
2)この場合、相続財産になるんだね。ちょっとわかりにくいけど覚えるしかないね。
3)これはよく見る論点だから、記憶必須だね。
4)これも正しいね。死亡退職金と弔慰金はわかりずらいけど、死亡退職金は本来、被保険者が受け取るはずだった退職金を遺族が受け取るものであって、弔慰金は会社から遺族の生活を慰めるために支給されるものだね。
問48 相続税の税額控除等
| 《問48》 相続税の税額控除等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 被相続人の配偶者は、相続の放棄をした場合であっても、遺贈により取得した財産があるときは、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。 2) 未成年者である相続人が相続税額から控除することができる未成年者控除額は、「相続開始時の未成年者の年齢×10万円」の算式により計算した金額となる。 3) 相続開始前に被相続人から暦年課税による贈与により取得し、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産がある場合、相続税額の計算上、当該財産の取得について課せられた贈与税額を控除することができ、相続税額から控除しきれない場合は、税額の還付を受けることができる。 4) 被相続人がその相続開始前20年以内に相続税を納付していた場合、当該被相続人から相続または遺贈により財産を取得した相続人の相続税額から、当該被相続人が納付した相続税額のうち、一定の割合で逓減した後の金額を控除することができる。 |
正解1

税額控除は所得税も相続税もややこしくて覚えるのがたいへんだね。

1)これが正しい選択肢だね。二次相続を考えなければ配偶者が相続税を払わずに済むような気がするね。
2)(18歳―相続時の年齢)×10万円が未成年者控除額だね。なにげなく問題文を読んでると勘違いしちゃうから要注意だね。
ちなみに障碍者控除は(18歳-相続時の年齢)×10万円(特別障碍者は20万円)だから、一緒に覚えておくといいよ。
3)相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加えることになるけど、贈与を受けた方が贈与税を払っていた場合は相続税から引くことはできるけど、還付を受けるということはできないよ。
4)相次相続控除の説明だと思うけど、20年じゃなく10年が正しいよ。
問49 X土地、Y土地(借地権)、Z土地の相続税評価額
| 《問49》 Aさんは、父から建物の敷地となっている下記のX土地、Y土地(借地権)、Z土地を相続により取得した。X土地、Y土地(借地権)、Z土地の相続税評価額の合計額として、次のうち最も適切なものはどれか。 |
| X土地 | ・Aさんは、父から使用貸借により借り受けているX土地にアパートを建築して、第三者に賃貸(入居率は100%)していた。 ・X土地の自用地価額は3,000万円、借地権割合は60%、借家権割合は30%である。 | |||||
| Y土地 | (借地権) ・Aさんの父は、借地権(定期借地権等ではない)を有するY土地にアパートを建築して、第三者に賃貸(入居率は100%)していた。 ・Aさんは、Y土地の底地(借地権の目的となっている土地)を第三者である地主から買い取り、「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署長に提出していた。Aさんは、父から地代を収受していない。 ・Y土地の自用地価額は4,000万円、借地権割合は60%、借家権割合は30% である。 | |||||
| Z土地 | ・Aさんの父は、第三者であるB株式会社にZ土地を相当の地代で貸し付けている(権利金は収受していない)。 ・B株式会社はZ土地を自社の社屋の敷地として利用している。 ・Z土地の自用地価額は4,500万円、借地権割合は60%、借家権割合は30%である。 | |||||
1) 6,840万円
2) 7,740万円
3) 8,280万円
4) 9,700万円
正解3

たまに出題されるXYX土地の相続税評価額の問題だね。これも解き方を覚えるのが大変だけど、実技試験でも同じ考え方を使う場面があるから、この問題の考え方はしっかり理解しておくことをお勧めするよ。

X土地・・・使用貸借をしている場合、借りている人の価値が0円なので、所有者は全額3,000万円になるよ。
Y土地・・・「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」とは借地権として使用していた土地を買い取った場合に登場する書類だね。
この場合、貸家建付借地権の計算が必要になり、評価額=自用地価格×借地権割合×(1-借家権割合×賃貸割合)という計算が必要になるね。Y土地に当てはめると
4,000万円×60%×(1-30%×100%)=1,680万円だね。
Z土地・・・相当の地代でB社に貸しているのだから自用地価格の80%がAさんの所有している価値となるね。
4,500万円×80%=3,600万円
X+Y+Z=3,000万円+1,680万円+3,600万円=8,280万円
問50 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)
| 《問50》 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 株主総会において議決権を行使することができる事項の全部または一部について制限のある非上場株式等は、本特例の適用対象とならない。 2) 本特例の適用を受けるにあたり、後継者である受贈者は、本特例の適用対象となる非上場株式等の全部を贈与税の納税猶予に係る担保として提供しなければならない。 3) 本特例の適用を受けるためには、非上場株式等の贈与の日において、贈与者である先代経営者は60歳以上でなければならず、受贈者である後継者は18歳以上でなければならない。 4) 本特例の適用を受けた場合、特例経営贈与承継期間においては毎年、その期間経過後は5年ごとに、一定の書類を添付した継続届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 |
正解1

基礎編最後の問題は、頻出の事業承継税制だね。午後の応用編に気持ちよく取り組めるように問50は絶対、取りたい問題だね。そういう気持ちで取り組んで、問50は必ず得点できるように心がけていたね。

1)事業承継税制は、事業を継続するために相続税・贈与税を有用する制度です。制限付き株式は役員、従業員に交付して将来売却することを前提に発行されるもので、事業を安定して継続するという趣旨にそぐわないと思われるため対象外だよ。
2)全部を贈与税の納税猶予に係る担保として提供することで、必要とされる担保を提供したとみなすことができるということであって、それ以外の担保提供が可能なら必要条件ではないよ。
3)後継者は18歳以上でないといけないけれど、現経営者の年齢制限は定められていないよ。
4)期間経過後は5年ごとではないよ。3年ごとだから注意して覚えてね。
長かった2025年5月25日基礎編の説明も一段落しました。
わかりにくかったり、間違っている解説などあればご指摘いただけると幸いです。