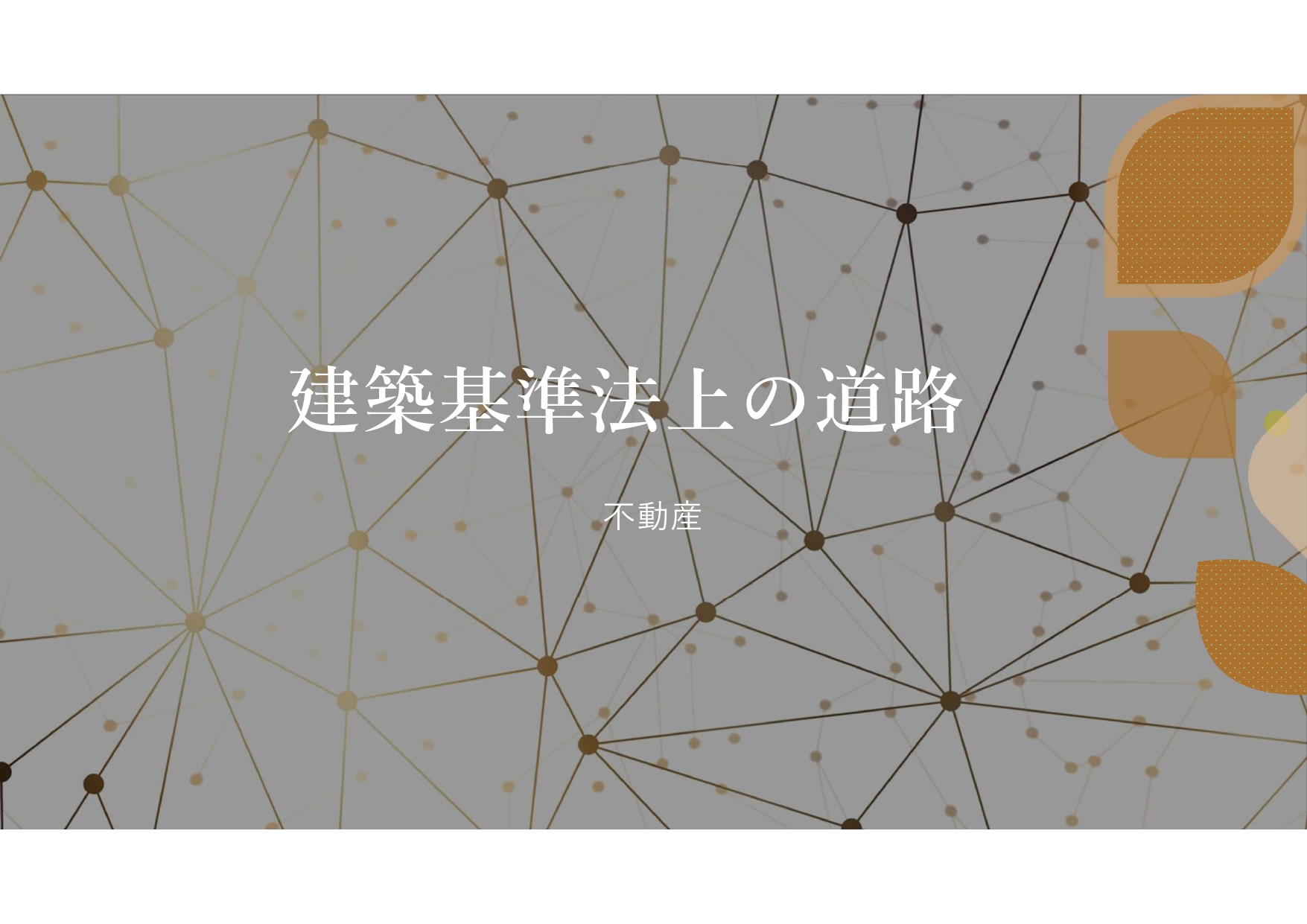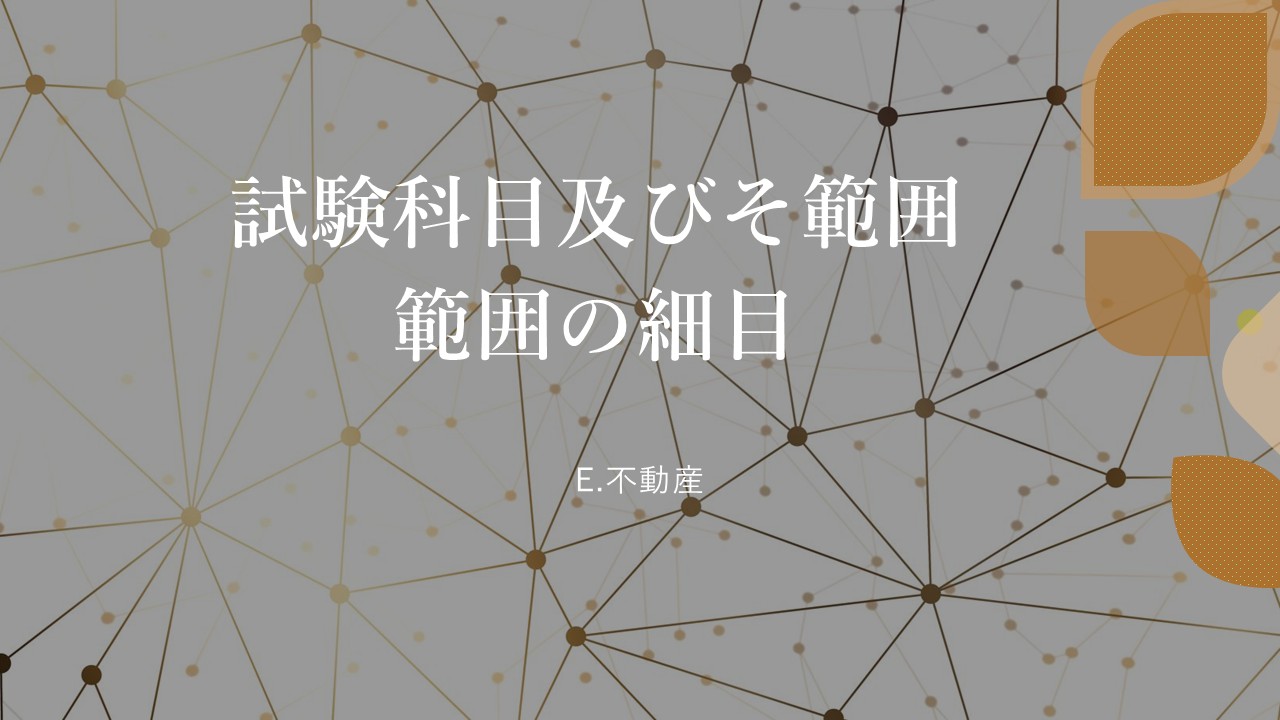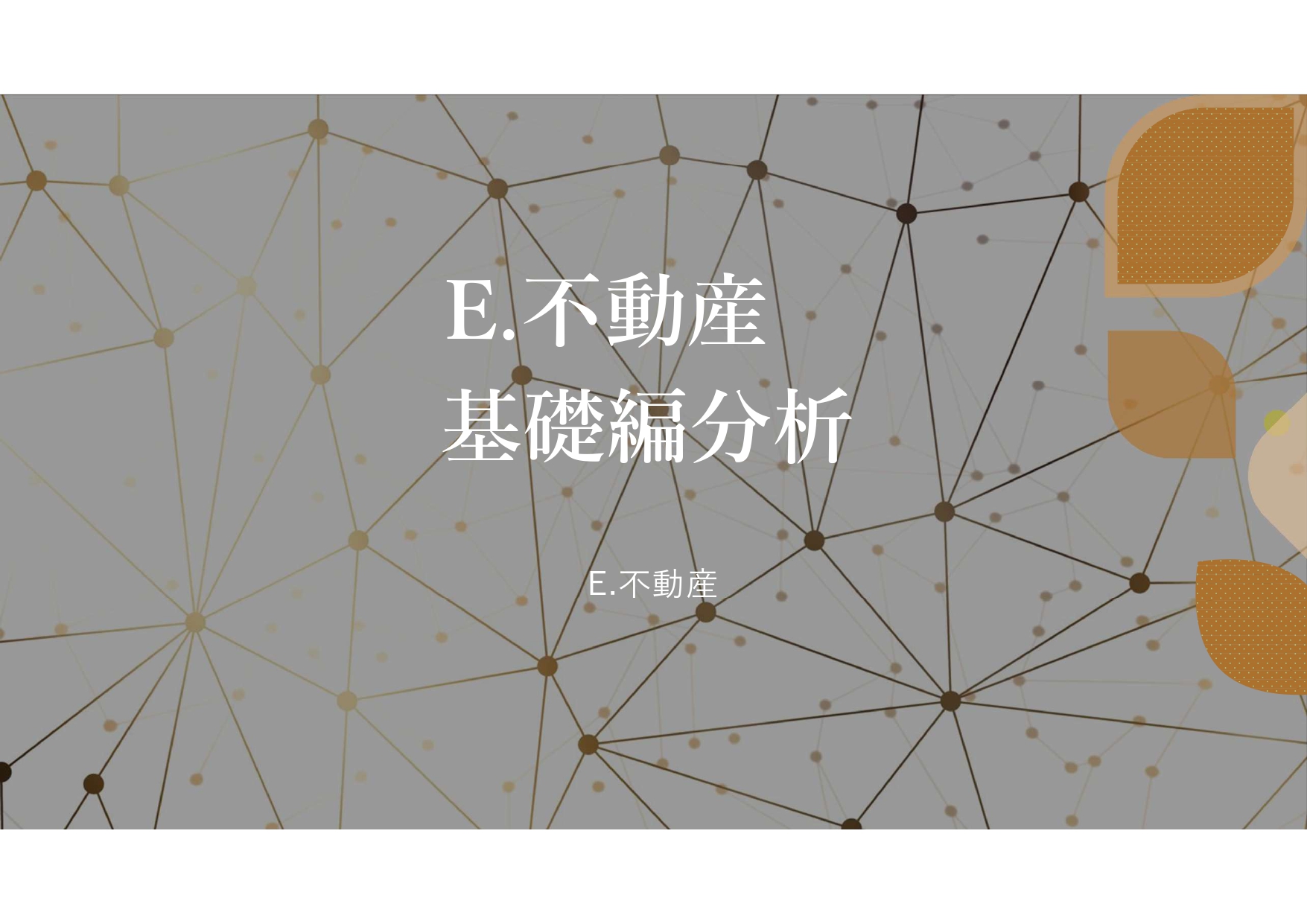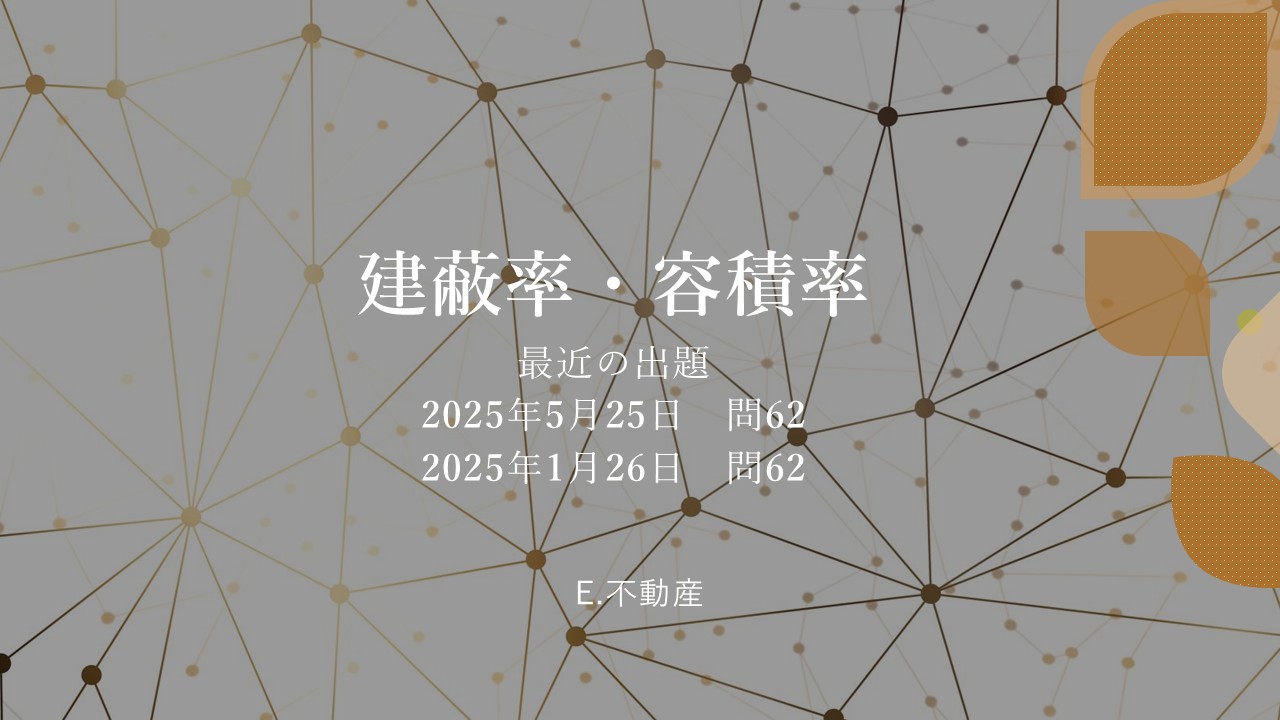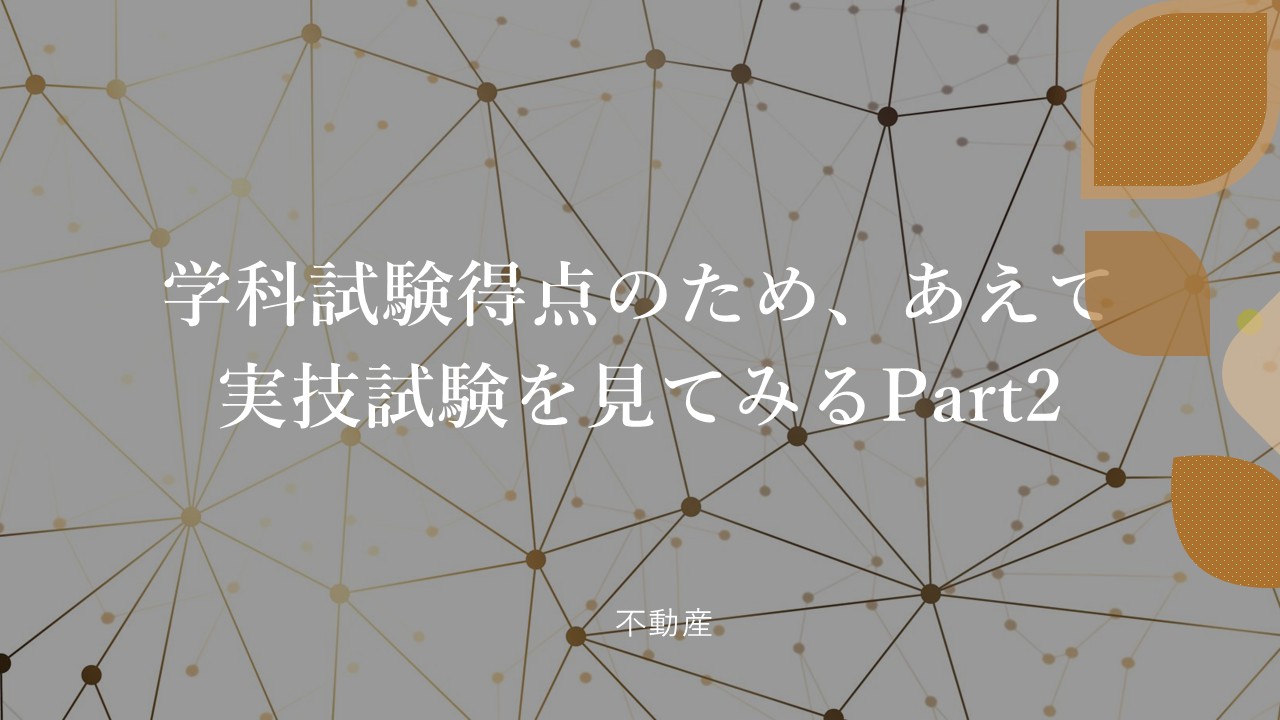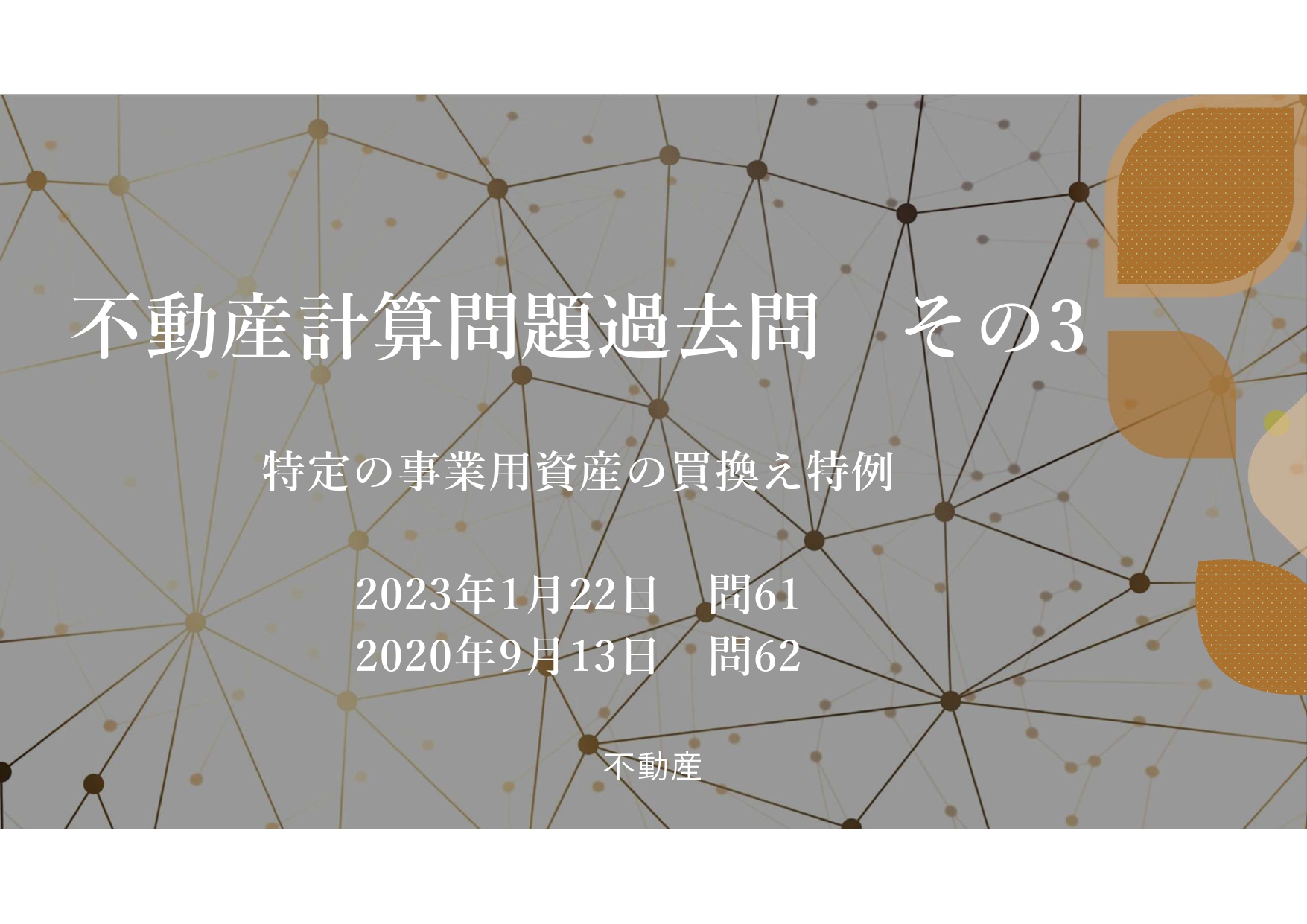2024年9月8日 不動産 基礎編
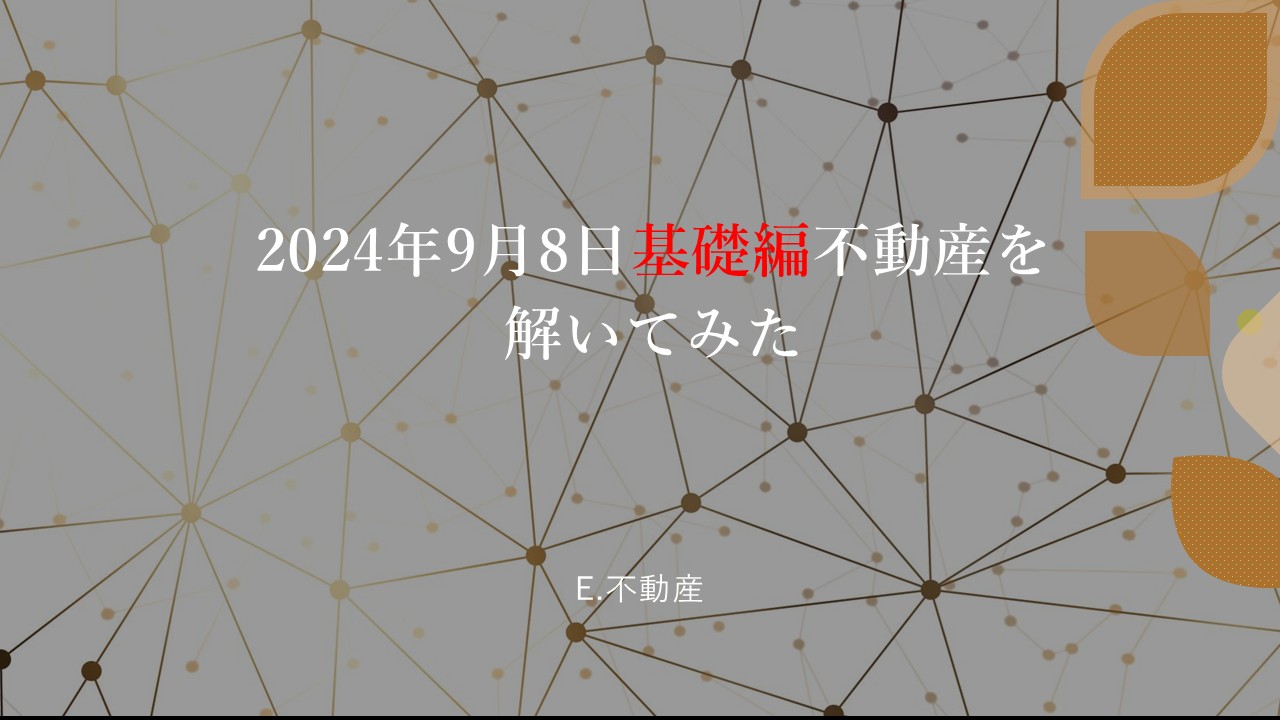
このブログで何度か、私は不動産が苦手ですと述べてきました。
その理由は明白で、私が田舎暮らしのため、問題文に出てくるような都市を前提とした内容を実際に見たことがないからです。
しかし、言い訳ばかりでは成長はありません。実際に見たことのない事例を基に、顧客から求められている質問に対して、自分なりの最適解を提案することがFPに与えられた役割だと思います。
私は以前、高齢者施設を建設するための土地探しをしたことがあります。
その時は真剣に、主要道路からのアクセスに不便はないか、道路幅は事故を防げるだろうか、災害が起こるリスクがどの程度あるのか、職員が通勤するのに不便はないだろうか、、、などいろいろ考えをめぐらしました。
専門家に求められるのは、経験に基づく知識ですが、時として、まったく未経験な検討がつかない場面での提案が求められることもあります。
そこであきらめるのではなく、知識と限りある経験からの想像力で乗り切らなければならないと思います。
今回も、問題文は出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問34 不動産の仮登記
| 《問34》 不動産の仮登記に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 所有権移転の仮登記は、実体上の所有権移転が既に生じている場合、申請することができない。 2) 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾または仮登記を命ずる処分がない場合、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。 3) 仮登記の抹消は、仮登記上の利害関係人の承諾または仮登記の抹消を命ずる処分がない場合、当該仮登記の登記名義人が単独で申請することはできない。 4) 抵当権設定の仮登記に基づく本登記は、その本登記について登記上の利害関係を有する第三者がある場合、当該第三者の承諾がない限り、申請することができない。 |
正解2

仮登記と本登記とか、経験がないと難しいね。FP試験でも頻繁に出題されるということは、土地の所有権についての、もめごとが世間では多いんだろうね。
しかし、不動産は図でも書いて理解しないと登場人物とその関係性を見失うんだよね。

1)所有権移転後の仮登記は可能だね。実物が移転していたとしても書類がそろっていなくて本登記ができないこともありえるからね。
2)仮登記は登記義務者と登記権利者が共同で行う必要があるので、権利者単独での申請は原則できないよ。義務者の承諾や裁判所の命令があれば話は別だけど。
3)仮登記の登記名義人は、利害関係人の承諾がない場合でも、裁判所からの「仮登記の抹消を命ずる処分」があれば、単独で仮登記の抹消を申請できるよ。この手続きの難易度はわからないけど。
4)所有権の登記は利害関係を有する第三者の承諾が必要だけど、抵当権設定の登記は可能だよ。
問35 筆界特定制度
| 《問35》 筆界特定制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 筆界特定は、表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置またはその位置の範囲を特定するものであり、所有権の及ぶ範囲を特定するものではない。 2) 筆界特定の申請は、あらかじめ隣接する土地の所有者の承諾を得た場合を除き、各土地の所有者が共同して行わなければならない。 3) 隣接する土地との筆界は、各土地の所有者同士が合意し、公正証書等の書面を連名で作成した場合であっても、変更することができない。 4) 筆界特定書の写しは、所定の手続により、隣接する土地の所有者などの利害関係者に限らず、誰でもその交付を受けることができる。 |
正解2

筆界と所有権界って、土地を持っている人が常に意識することだよね。その争いで世界では戦争も起こっていると考えたら、恐ろしいよね。
ちなみに実技試験でも話題になることがあるので、FP試験では最後まで付き合うことになるよ。

1)これは適切だね。筆界=所有権界ではないよ。
2)筆界特定の申請は、土地の所有者が単独で申請することが可能だよ。
3)これも正しいね、双方が合意していても法務局を窓口に筆界特定制度を利用する必要があるよ。
4)筆界特定書の写しは誰でも交付を受けることが可能だよ。
問36 都市計画法
| 《問36》 都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 都市計画区域のうち、市街化区域については用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。 2) 市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園および下水道を定めるものとされている。 3) 都市計画区域内の用途地域が指定された区域については、防火地域または準防火地域のいずれかを定めるものとされている。 4) 準都市計画区域については、用途地域を定めることができるものとされている。 |
正解3

都市計画法は毎回、FP試験で出題される問題だね。基礎編、応用編。実技試験でも求められる知識で不動産分野の本丸ともいえるね。
都市計画区域は日本の国土の約4分の1だけど、そこに人口の94%が居住しているんだね。

1)これは適切だし、基本的な内容だね。
2)これも正しいね、13の用途地域を覚える際に、道路斜線制限はすべての地域に適用されることから推察するのもありかもしれないね。
3)これが不適切だね。防火地域・準防火地域が定められていない地域もあるよ。
4)これも適切だね。ちなみに非線引き区域に定めることもできるよ。
問37
問37 農地法
| 《問37》 農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。 2) 市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000㎡以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000㎡未満のものはあらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。 3) 農業者である個人が、所有する市街化区域内の農地を駐車場用地として自ら転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。 4) 農業者である個人が、自らの耕作の事業のための農業用倉庫を建設する目的で、市街化調整区域内にある農地を取得する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。 |
正解3

子供の頃から田舎で生活していると、家の周りは田んぼか畑だったと思うのだけど、最近、農業従事者の高齢化に伴い、米を作る人が少なくなってきていると感じるね。
世間では米の価格高騰がニュースになっていて備蓄米の放出や輸入米をどこまで認めるのか議論になっているけど、個人的には日本米を守り続ける政策に期待するけどね。
とはいえ、自分自身でできるかといえば能力的にも体力的にも難しいけどね。

1)農地法3~5条許可を正しく理解する必要があるね。農地のまま譲渡する場合は3条による農業委員会への許可が必要だね。農業委員会は市町村と置き換えても問題がないと思うよ。
2)市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する場合、面積に関わらず農業委員会への届出で可能だね。
3)これが適切だね。市街化区域とは街にしたい区域で、市街化調整区域は街にしたくない地域という覚え方でも概ね正しいと思うよ。
4)市街化調整区域は街にしたくない地域なので農業の目的であっても倉庫建設の場合都道府県知事の5条許可が必要になるよ。
問38
問38 印紙税
| 《問38》 印紙税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) マンションの売主である不動産会社が、買主に対し、当該マンションの売買に係る領収証の交付に代えてその内容を記録した電磁的記録を提供する場合、印紙税は課されない。 2) 個人と不動産会社間の土地の交換契約書において、印紙税の課税標準となる金額は、それぞれの土地の価額が記載されている場合はいずれか高いほう(等価交換のときはいずれか一方)の金額となり、交換差金のみが記載されている場合はその金額となる。 3) 売主を国、買主を不動産会社とする時価1億円の土地の売買契約において、売買契約書を国と不動産会社が共同で2通作成して、それぞれ1通ずつを保管する場合、国が保管することとなる契約書には印紙税が課されるが、不動産会社が保管することとなる契約書には印紙税が課されない。 4) 「契約期間は10年、月額賃料は20万円、権利金の額は200万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書を個人と不動産会社間で作成した場合、当該契約書は、記載金額2,600万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 |
正解4

収入印紙というのは、たまに見ることがあるけど、どういう意味があるのか深く考えたことが無いね。何か契約をするときに相手の言われるがまま払っているイメージだね。
その目的をちょっと調べたら「取引当事者間の法律関係の安定化という面に担税力を見出して課税」とあるけど、頭が悪いのかちょっと意味わからないな。
古い資料だけど平成1~11年データを見ると歳入に占める割合が1.3%~1.4%ということがわかるね。

1)これは正しいよ、契約が全て電磁的記録になったら印紙税はなくなるのかな。
2)これも正しいよ、通常、交換差金に課税されるみたいだね。
3)これは類似の取引の現場を見たことがあるから知ってる。市区町村の所有する土地を購入する場合、印紙代がかからなかった覚えがある。
4)この場合、印紙税がかかるのは権利金200万円に対してだね。総額ではないよ。
問39
問39 固定資産税
| 《問39》 土地および建物に係る固定資産税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 年の中途に固定資産税の課税対象となる土地が譲渡された場合、譲渡人および譲受人は、その譲渡のあった日の属する年度内のそれぞれの所有期間に応じた固定資産税の納税義務を負う。 2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住の用に供する家屋の敷地である宅地に適用することができるものであり、賃貸アパートや賃貸マンションの敷地である宅地には適用することができない。 3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家屋が管理不全空家等に該当し、その家屋の所有者が市町村長から指導を受けた場合、当該土地は、その家屋を放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態が継続している間は、市町村長から勧告を受ける前であっても、当該特例の対象外となる。 4) 2階建ての認定長期優良住宅を新築して「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、当該住宅に係る固定資産税は、原則として、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税額に限り、床面積120㎡までの部分に対する税額の2分の1相当額が減額される。 |
正解4

固定資産税は土地、家を持っている人が払う税金で4月に納税通知書が届いて4月、7月、12月、2月の4回に分けて納税するっていうことは知っているけど、恥ずかしながら払ったことがないな。

1)固定資産税は1月1日時点での所有者に対して請求されるよ、日割り計算をしてくれることはないよ。
2)アパートやマンションなどであっても居住部分に特例適用が受けられるよ。
3)適用から外れるのは、勧告 を受けてからだね。指導の段階で手を打たなければいけないね。
4)これが正しいね、この問題文は頻出で実技試験でも問われることがあるので暗記必須だよ。
問40
問40 相続税の取得費加算の特例
| 《問40》 Aさんは、2022年4月に死亡した父親から相続により取得した自宅の建物とその敷地を2024年3月に売却した。Aさんが売却した自宅の敷地である土地に係る譲渡価額等が下記のとおりであった場合、当該土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、取得費はできるだけ多額になるように計算することとし、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるための要件は満たしているものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 〈売却した土地の譲渡価額等〉 |
| ・1985年4月 父親が祖父から相続により取得(取得費は不明) | ||||||||||
| ・2022年4月 Aさんが父親から相続(単純承認)により取得 | ||||||||||
| 当該土地の相続税評価額 : 3,000万円 | Aさんがほかに相続した土地はない | |||||||||
| Aさんの相続税の課税価格 : 7,500万円 | 債務控除前の金額 | |||||||||
| Aさんが納付した相続税額 : 480万円 | ||||||||||
| 相続登記関係費用 : 20万円 | 登録免許税、司法書士手数料など | |||||||||
| ・2024年3月 譲渡 | ||||||||||
| 当該土地の譲渡価額 : 4,000万円 | ||||||||||
| 仲介手数料 : 130万円 | ||||||||||
| 1) 350万円 2) 392万円 3) 412万円 4) 522万円 |
正解2

相続した土地を売却する問題ってよく出題されるんだよね。人口が増加している地域であれば需要はあるかもしれないけど、地方に住んでいると、相続が発生して空き家になるという場面をたくさん見るので、こっちもなんとかして欲しいけどね。

不動産の売却の際、取得費が不明の場合は売却代金の5%を概算取得費とすることができるよ。
①取得費:4,000万円×5%=200万円
また収めた相続税のうち、相続財産のうち、この土地の分も取得費に加算することができるよ。
②480万円×4,000万円÷7,500万円=192万円
①+②=392万円 よって正解は 2)だね。
問41
問41 ①DSCRおよび②NOI利回り
| 《問41》 下記の〈条件〉に基づく不動産投資における①DSCRおよび②NOI利回りの組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮せず、計算結果は小数点以下第3位を四捨五入すること。 〈条件〉 |
| 投資物件 : 賃貸マンション(RC造10階建て、築15年) 投資額 : 7億円(資金調達:自己資金2億円、借入金額5億円) 賃貸収入 : 年間4,500万円 運営費用 : 年間1,200万円(借入金の支払利息は含まれていない) 借入金返済額 : 年間2,270万円(元利均等返済、返済期間25年) |
| 1) ① 0.69 ② 4.71% 2) ① 0.69 ② 6.43% 3)①1.45 ②4.71% 4) ① 1.45 ② 6.43% |
正解3

DSCR、NOI利回りというのがピンとこないけど、選択肢の数字から逆に推測することはできるね。問題はどっちを選ぶかなんだけど

①DSCR
DSCR=NOI÷元利金返済額なので、まずNOIを求めます。
NOI=4,500万円-1,200万円=3,300万円
DSCR=3,300万円÷2,270万円=1.453744 → 1.45
②NOI利回り
NOI利回り=NOI÷投資額
3,300万円÷7億円=0.047143 → 4.74%
よって正解は 3) ① 1.45 ② 4.71%
不動産の勉強法
向き、不向きはあると思いますが、私は、実技試験の過去問を数年分さかのぼって、解いたことで、不動産の基礎編、応用編の苦手意識を一部、克服することができました。
この方法は強くお勧めします。
最終的に合格証をつかむためには、実技試験を突破する必要があります。
一般社団法人金融財政事情研究会で実技を受験しようと思われる方はいずれ立ち向かう試験です。
日本FP協会で受験しようと思われる方については2026年の春ごろ、解説を試みます。
このブログを見ていただいている方は2026年1月試験を目指されている方が多いと思いますが、私の印象では1月試験は難易度が高いことが多いような気がします。