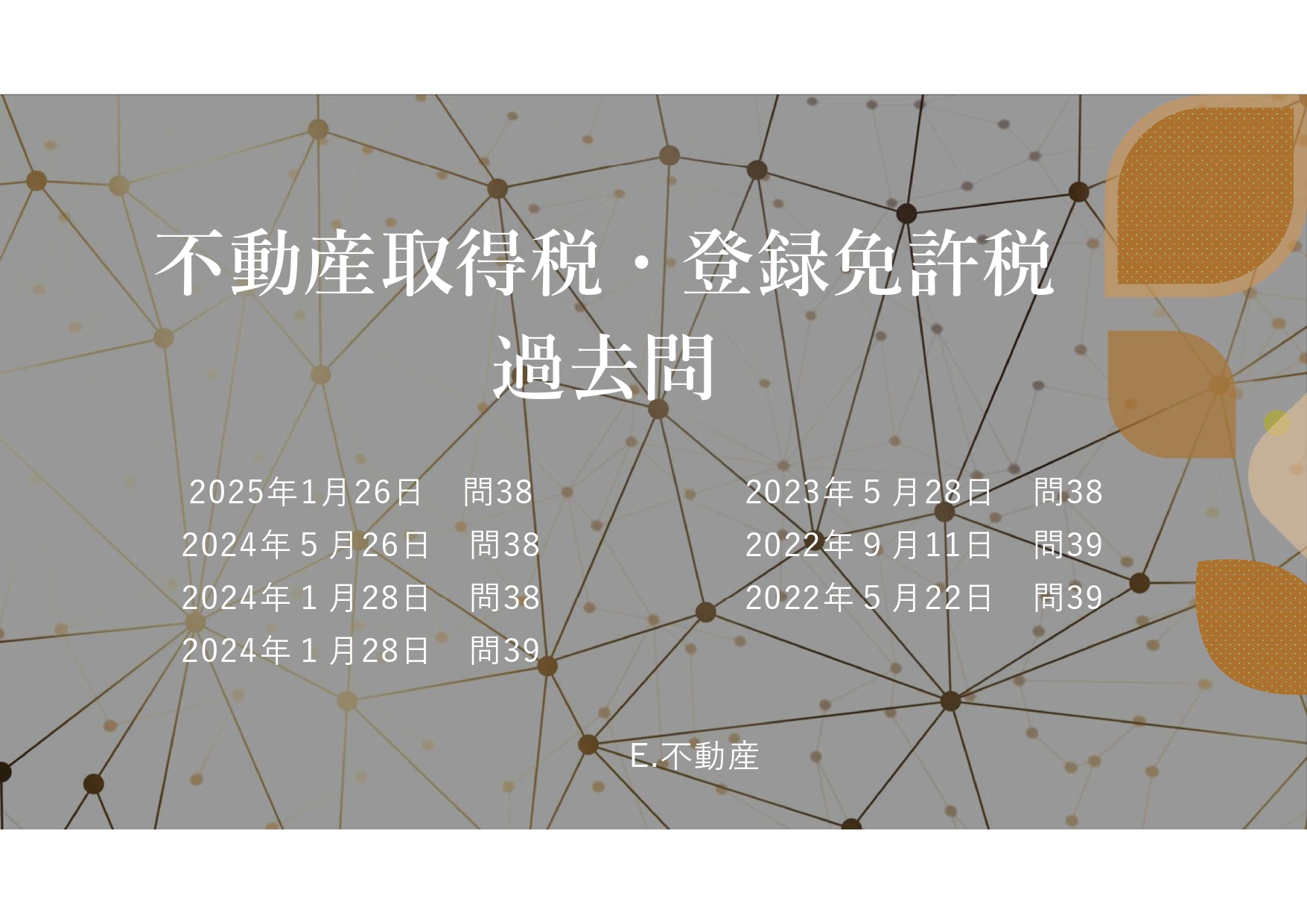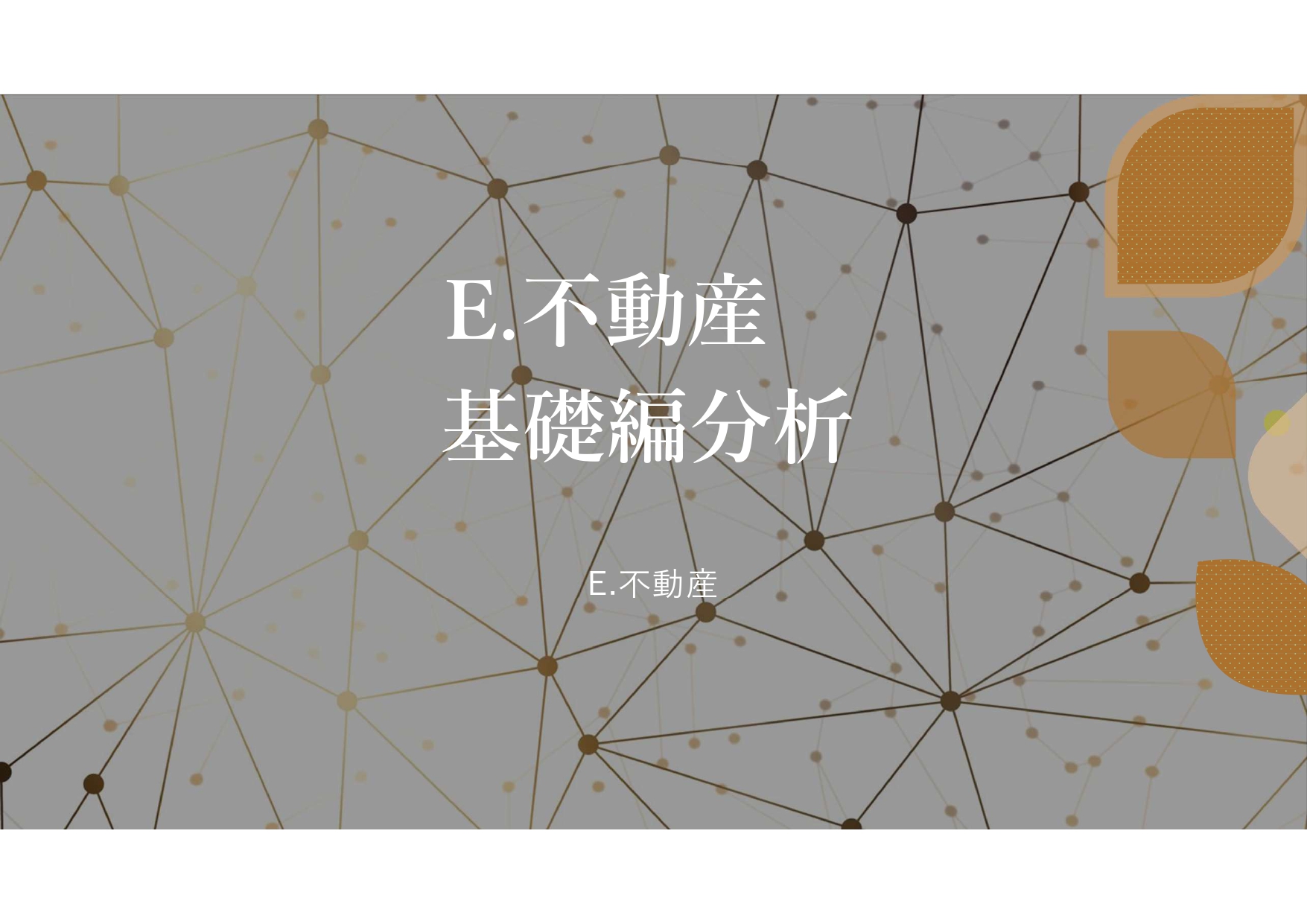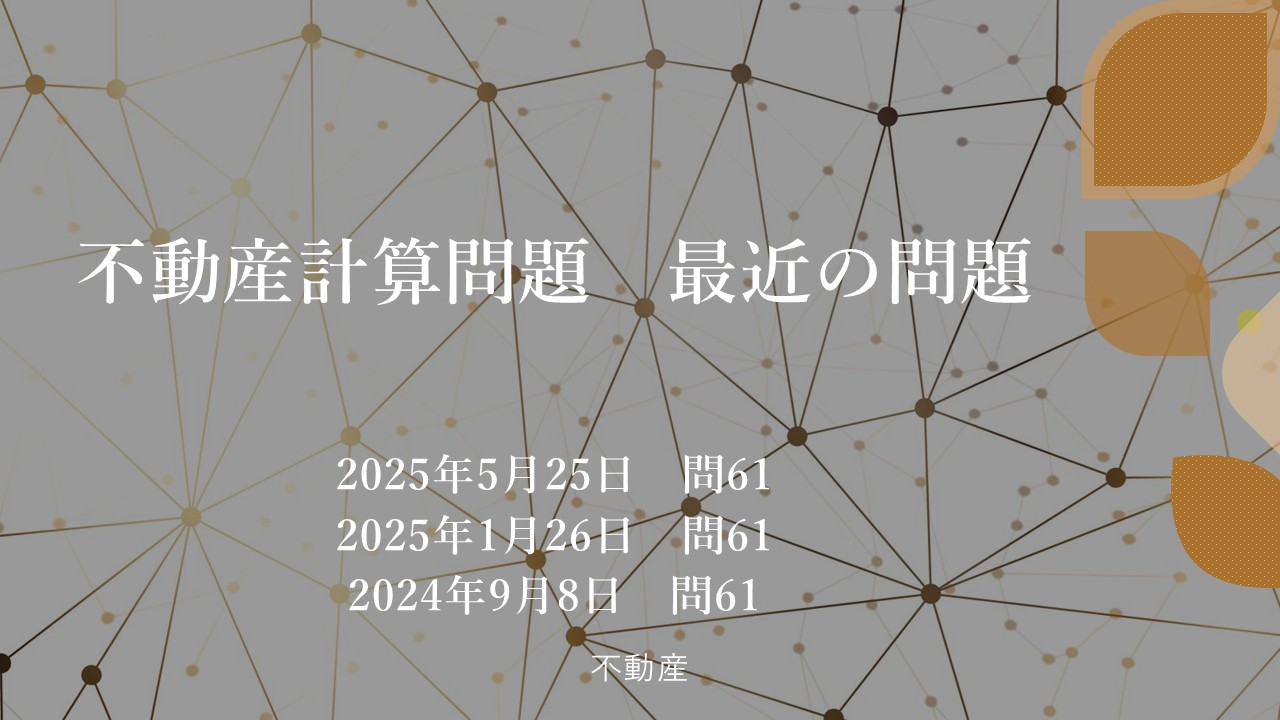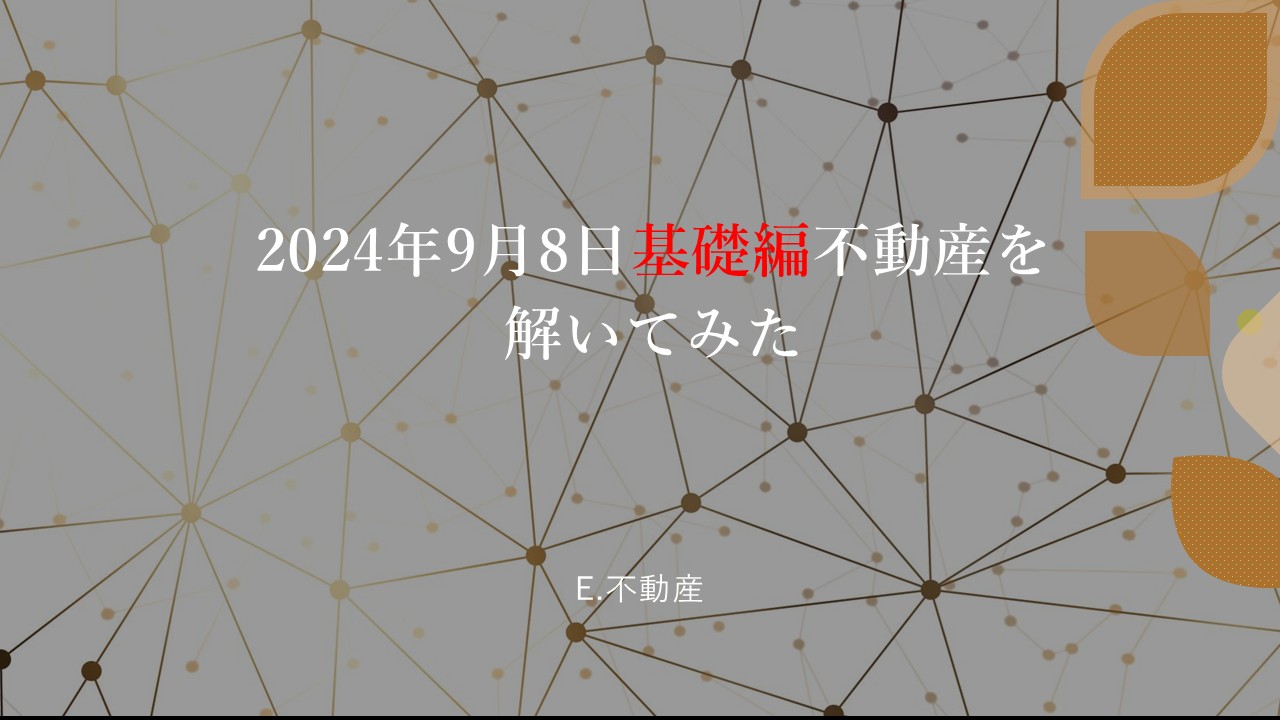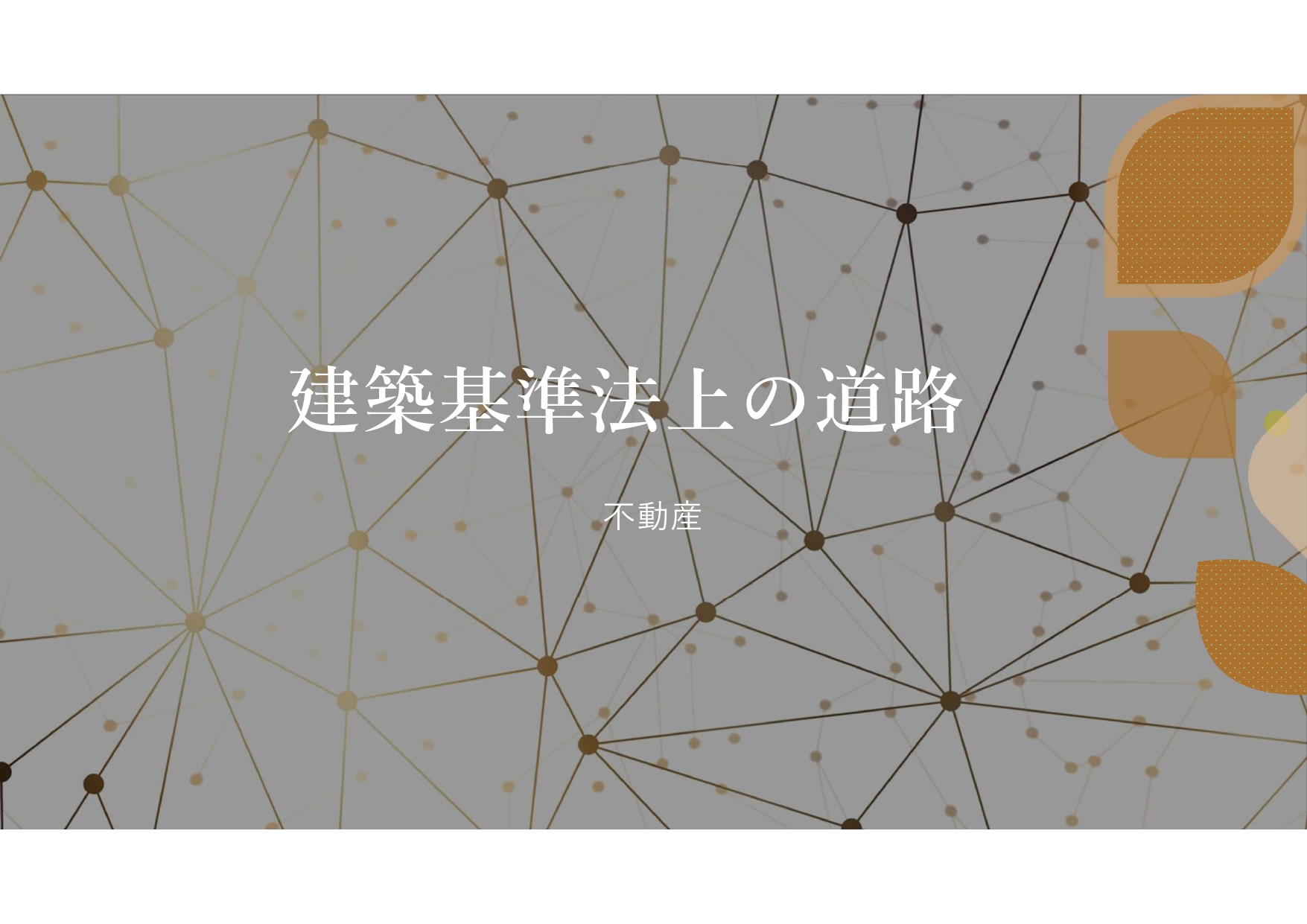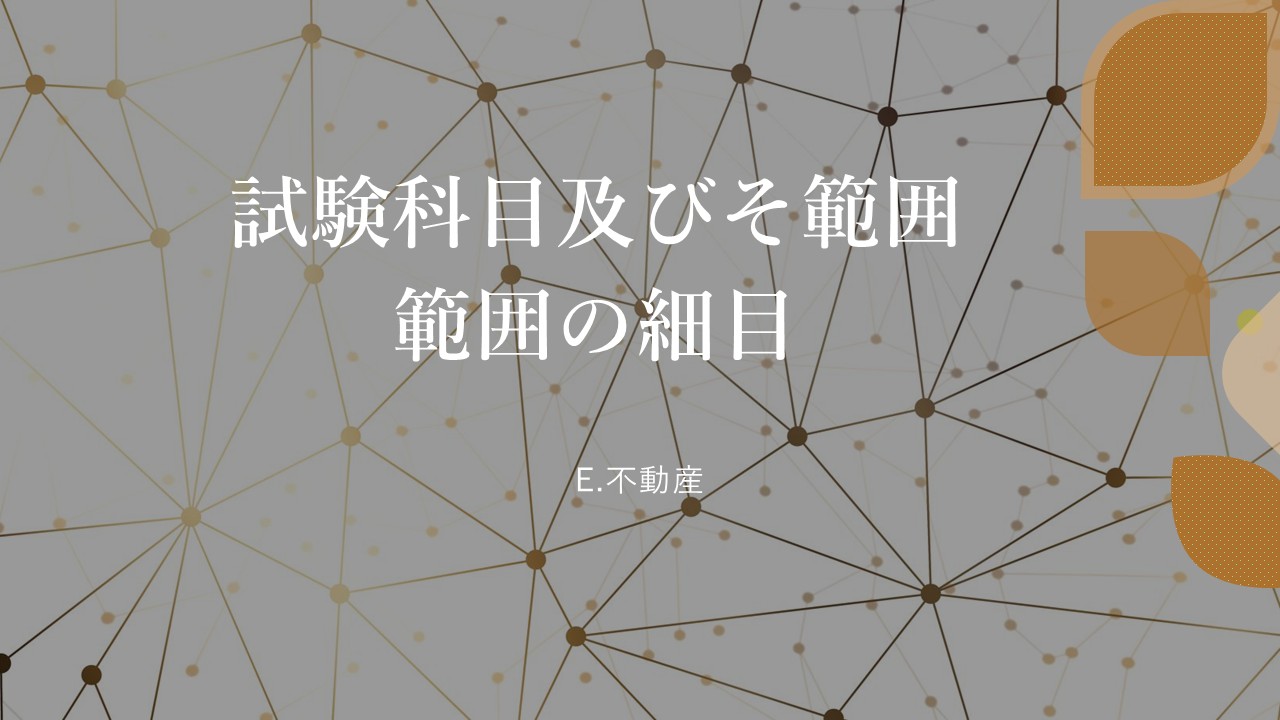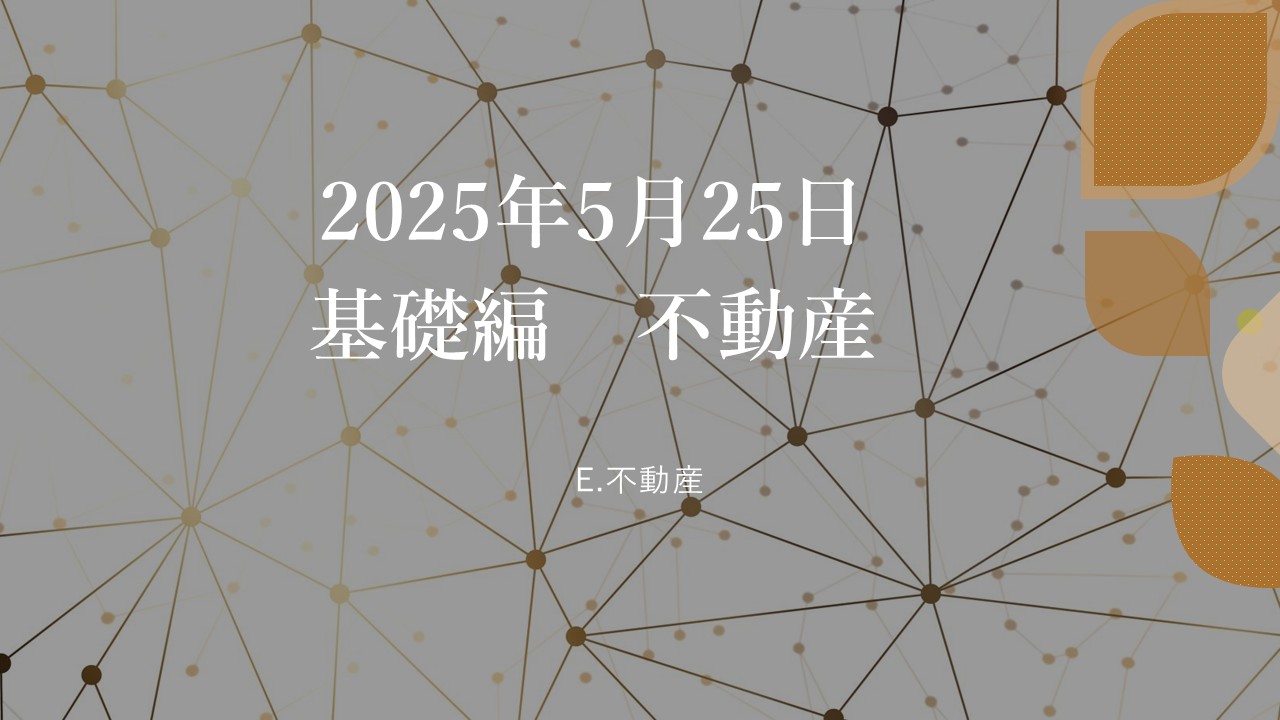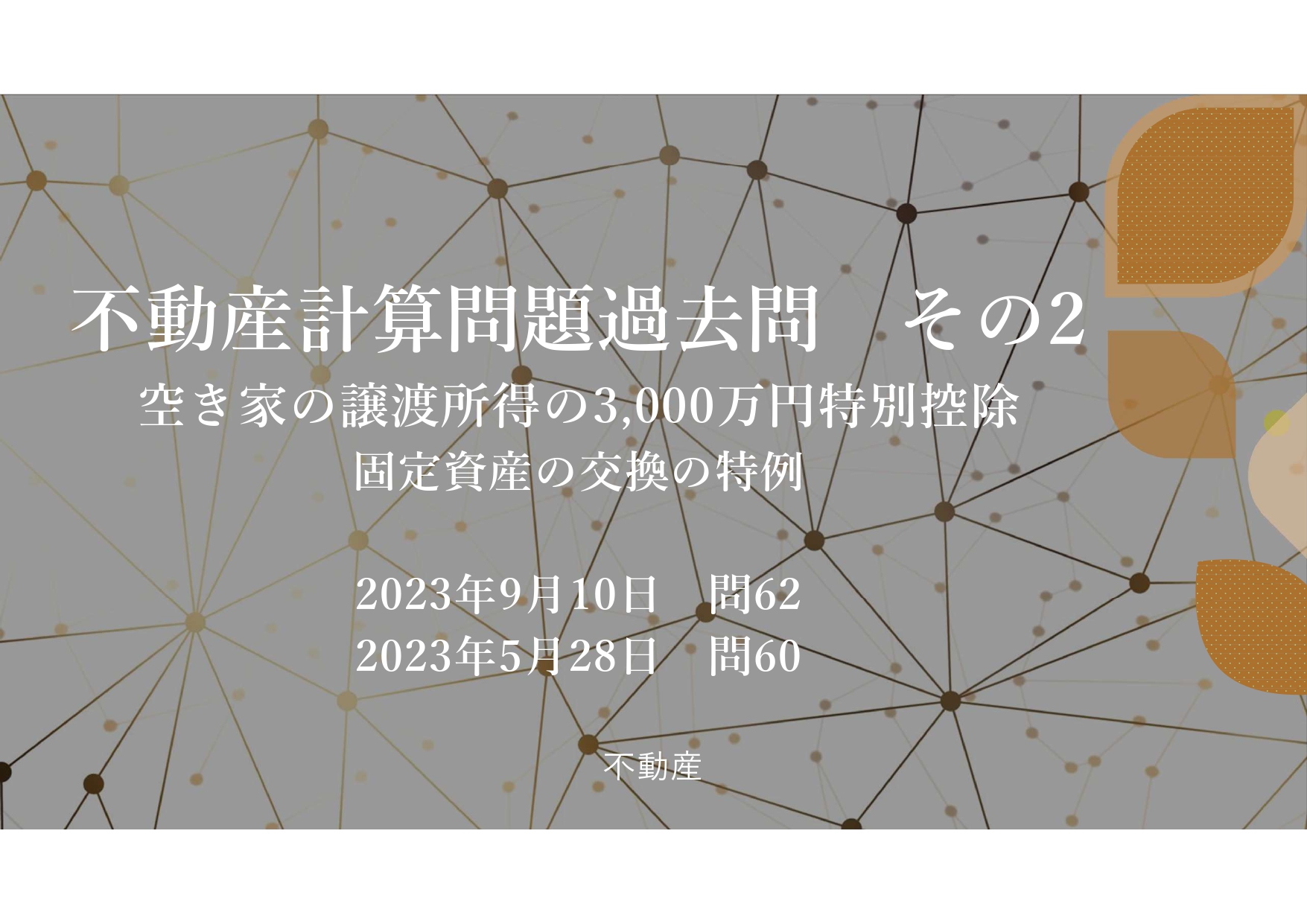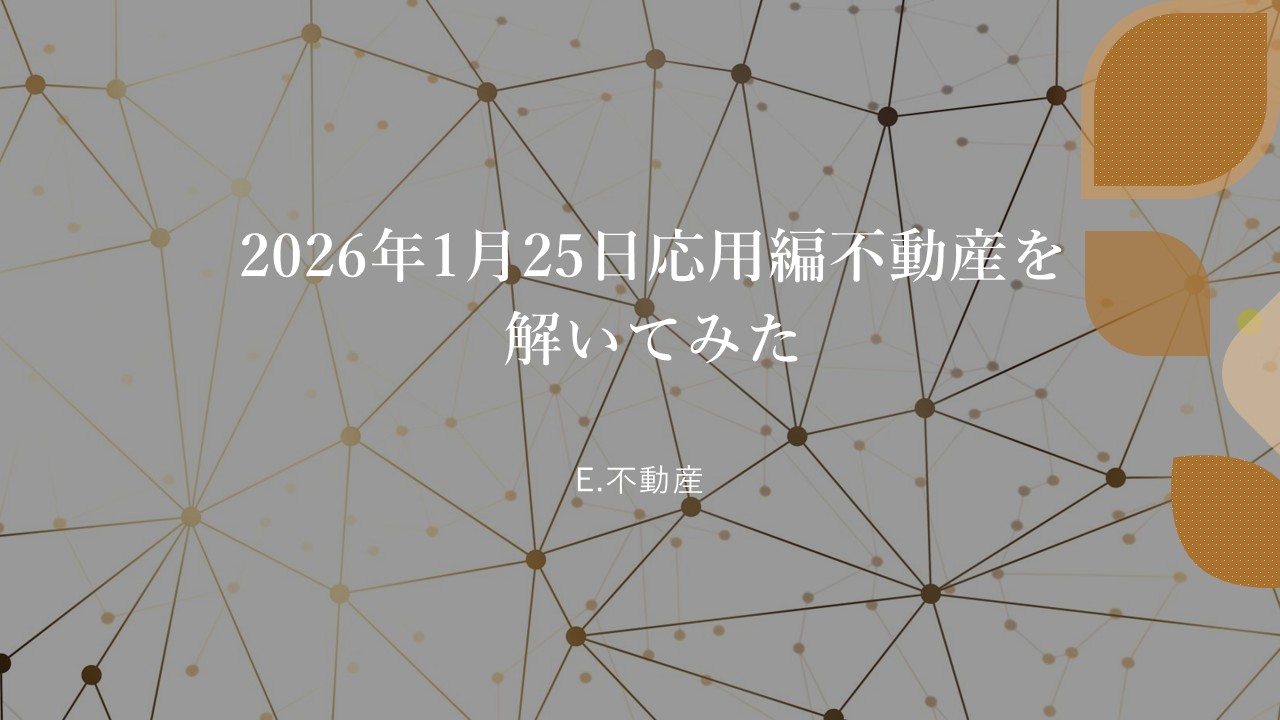2025年9月14日基礎編不動産を解いてみた
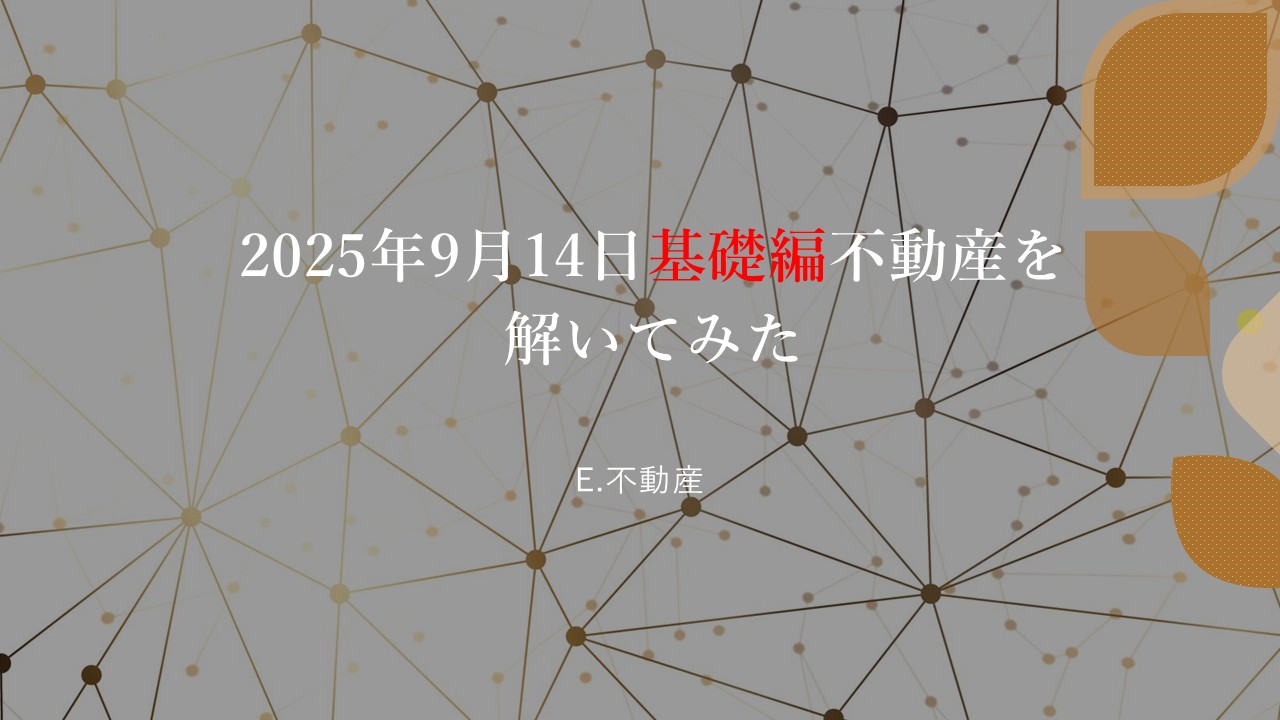
何度か述べていますが、FP試験で不動産分野の問題が最も苦手でした。正確には応用編の問題はある程度パターン化されていて、それほど苦手意識は無かったのですが、
基礎編は本当に苦労しました。おまけに不動産分野は実技試験のPart2でも問われるので、もし勉強をし始めた5年前に戻れるなら、不動産と相続・事業承継を徹底的に勉強したと思います。
勉強をしていく中で、タックスプランニングの知識が問われることも多くあるので、そこからタックスの勉強をした方が効率が良かったのではないかと思います。
そんなことを言っても後の祭りなので、時間はかかりましたが、無事合格できたことに感謝しています。
今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問34 不動産登記法
| 《問34》 不動産登記法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 分筆または合筆の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。 2) 相互に接続していない土地や地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。 3) 合筆しようとしている2筆の土地のうち、1筆のみに抵当権の設定の登記がある場合、抵当権者の承諾書を添付すれば、合筆の登記をすることができる。 4) 地目について変更があったときは、表題部所有者または所有権の登記名義人は、その変更があった日から1カ月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。 |
正解3

これは易しい問題だね。こういう問題なら基礎編も取り組みやすいのにな。
実は、過去に介護施設建設のために、土地の合筆の申請はしたことがあるんだよね。そのころ業務で法務局に通って、登記簿謄本をとったり、いろいろな申請をしたので、不動産は苦手と言いながらも役所への届出については、割と得意だったりするよ。

1)これは合っているね。土地家屋調査士はできるんじゃないの?という疑問は残るけどね。
2)これは合っているね。飛び地の合筆を認めたらややこしくなるもんね。
3)これは頻出のテーマだね。抵当権が設定されている土地の合筆はできないよ。
4)これも正しいね。〇月以内という期間の暗記は必須だね。
問35 不動産の取引において留意すべき民法の規定
| 《問35》 不動産の取引において留意すべき民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 代理権を有しない者が本人に代わって行った不動産の売買契約について、本人が追認する場合、別段の意思表示がない限り、当該売買契約の効力は追認をした時から将来に向かって生じる。 2) 同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。 3) 家屋の売買契約の締結後、売主が買主に家屋を引き渡すまでの間に、その家屋が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失した場合、買主は、その滅失を理由として代金の支払を拒むことができる。 4) 共有名義の不動産について、各共有者は、他の共有者の同意を得ずに自己の持分を共有者以外の者に売却することができる。 |
正解1

民法の規定ってちょっと難しいよね。宅建だともう少しつっこんだ内容も出そうだけど、FPではこれでも優しい問題なのかもね。

1)追認をした場合、契約時にさかのぼって効力を生じるというのが正しいので、これが不適切だね。
2)これは正しいね。先に不動産の「所有権移転登記」を完了させた者が、その不動産の所有権を対抗(主張)できるよ。
3)これは正しいね。2020年の民法の改正で、この形になったんだね。災害大国だから、危険負担はこれからも議論されていくだろうね。
4)これも適切だね。実技試験でも出てきそうなテーマだから暗記必須だね。
問36 借地借家法
| 《問36》 借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 普通借家契約において、賃借人が建物に付加した造作について賃貸借期間満了時に賃貸人に対して買取りを請求しない旨の特約をした場合、その特約は無効となる。 2) 普通借家契約において、その賃料が近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は賃料の増額をしない旨の特約をした場合、その特約は有効となる。 3) 定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借は終了するが、当事者間で合意すれば、同一の建物について定期借家契約を再契約することができる。 4) 定期借家契約の期間が2年である場合に、賃貸人が期間の満了の10カ月前に、賃借人に対し、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしたときは、その終了を賃借人に対抗することができる。 |
正解1

借地借家法は賃貸住まいの身には助かる内容が多いね。逆にオーナーには、ちょっと厳しい内容が多いかもね。 現在は借り手に有利な内容が多いけど、過去には貸し手に有利な時代もあったんだよね。

1)この特約は有効だね。マンションに自分でエアコンをつけたりすることってよくあるよね。よってこれが不適切だね。
2)増額をしない旨の特約をした場合、その特約は有効だけど、減額をしない旨の特約は無効なので一緒に覚えておこう。
3)これも正しいよ、かつ頻出のテーマだから暗記必須だね。
4)契約期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して「契約が終了する」旨の通知をすればよいので10カ月前の通知は有効だね。
問37 建築基準法上の道路
| 《問37》 建築基準法上の道路に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとし、地下における道路を除くものとする。 1) 都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に4m以上接していなければならない。 2) 建築基準法の集団規定が適用された際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となるが、その道の両側がいずれも宅地であり、建築物が立ち並んでいる場合には、原則として、道と宅地との境界線から道の側に水平距離4mの線がその道路の境界線とみなされる。 3) 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものである。 4) 道路法や都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、5年以内にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路となる。 |
正解3

これはちょっとややこしい問題かも。1)、2)は問題文に実際に図を描いてみるのがお勧めかもね。間違いに気づきやすくなるかも。

1)これは4m以上の道路に2m以上接するのが正しいね。急いで読んでいると勘違いしちゃいそうだね。
2)これも問題文を読み間違えそうだね。この場合道路の中心線から2m後退した位置が道路境界線と見なされるね。こういう場所では建替えのタイミングでセットバックが必要になるよ。
3)位置指定道路の説明で、これが適切だね。
4)道路法、土地区画整理法などに基づく事業計画がある道路でも、それが必ずしも建築基準法上の道路になるわけではないよ。都市計画法だと問題文の通りだけどね。
これは流し読みしてたら見落としそうだね。
問38 建築物省エネ法
| 《問38》 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 建築主が建築物の新築をしようとするときは、原則として、床面積の合計が50㎡以下の建築物を除き、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。 2) 建築主が建築物の増改築をしようとするときは、原則として、増改築をする部分だけでなく、建築物全体を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。 3) 建築物の販売または賃貸を行う事業者は、その販売または賃貸を行う建築物について、原則として、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。 4) 建築物のエネルギー消費性能の表示にあたっては、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が建築物のエネルギー消費性能の評価を行ったことを示す第三者認証を取得しなければならず、建築物の広告やチラシ等にその認証マークを明示する必要がある。 |
正解3

建築物省エネ法ってのはまったく守備範囲外の問題だね。いわんとすることはわかるような気がするけど。
違うという選択肢を除去する作業しかできないな。

1)建築物の新築を行う際、エネルギー消費性能の基準適合は、建築物の規模に関わらず義務だね。
2)改正建築物省エネ法では、増改築をする部分のみを建築物のエネルギー消費性能基準に適合させれば良いことになっているよ。
3)これが正しいね。内容はわからなくても「こうあるべきだ」と思えることが正解のことが結構あるよ。
4)「建築物のエネルギー消費性能の表示」にあたり、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が発行する「適合判定通知書」は認証マークではないということだね。これも「こうあるべきだ」と思える内容なので前言撤回だね。ごめんなさい。
問39 不動産取得税
| 《問39》 不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 被相続人の相続人以外の者が、被相続人の遺言による包括遺贈により固定資産税評 価額3,000万円の土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産取得税が課される。 2) 被相続人の相続人が、被相続人との死因贈与契約に基づき、被相続人の相続開始に 伴って固定資産税評価額3,000万円の土地を取得した場合、当該土地の取得には不動産 取得税が課される。 3) 個人が、土地区画整理事業の施行に伴い、所有する固定資産税評価額3,000万円の宅 地に係る換地を取得した場合、当該換地の取得には不動産取得税が課される。 4) 宅地建物取引業者が分譲するために新築した固定資産税評価額3,000万円の住宅につ いて、新築された日から6カ月を経過しても最初の使用または譲渡が行われなかった 場合、当該宅地建物取引業者をその住宅の取得者とみなして不動産取得税が課される。 |
正解2

土地区画整理事業、換地まさに2025年2月、6月の実技試験でつかまったテーマだね。
田舎暮らしの身には土地区画整理事業って無縁なので、考えるのも難しいんだよね。

1)包括遺贈であれば相続人以外でも不動産取得税はかからないんだね。特定遺贈は相続人限定なので注意が必要だね。
2)これが正しいんだね。死因贈与契約は贈与でなく相続の扱いになるんだね。勉強になった。
3)土地区画整理事業における換地の取得は一定の条件を満たせば不動産取得税が非課税となる特例措置があるんだね。まぁ、土地区画整理事業に協力するなら恩恵もないとね。
4)この場合、宅建業者が不動産取得税を負担するのは1年を経過して売れ残っていた場合だね。6カ月じゃないよ。
問40》 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
| 《問40》 「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 被相続人が居住していたマンションについて、区分所有建物である旨の登記がされている場合、当該マンションを相続により取得した被相続人の子は、その譲渡にあたって本特例の適用を受けることができない。 2) 被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、当該家屋およびその敷地を譲渡する場合に、その譲渡の対価の額が1億円を超えるときは、本特例の適用を受けることができない。 3) 被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、その譲渡にあたって本特例の適用を受ける場合に、当該家屋が母屋や離れのような複数の建築物からなるときは、それらの建築物のうち、被相続人が主として居住の用に供していた一の建築物のみが、本特例の対象となる被相続人居住用家屋に該当する。 4) 被相続人が居住していた家屋およびその敷地を相続により取得した被相続人の子が、当該家屋について一定の耐震基準を満たさないまま、その敷地とともに譲渡する場合、本特例の適用を受けるためには、原則として、その譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年3月15日までの間に当該家屋の耐震改修または取壊しが行われる必要がある。 |
正解4

出たね、応用編でも実技試験でも定番の相続空き家の問題、これは受験生は必ず、マスターしておく必要があるよ。
実際に、空き家は社会問題にもなっているから、有効な対策を提案したいね。

1)これは正しいね。区分所有登記は頻出だから抑えておきたいね。
2)これも定番だね。空き家の特例を使うためには1億円以下である必要があるね。
3)この場合、主として居住していた建物の敷地が対象だね。多くの場合、母屋だね。
4)3,000万円の特別控除を受けるためには、譲渡の日までに耐震改修または取壊しが行われる必要があるというのが正しいね。よってこれが誤りだね。
問41 不動産投資におけるNPV(正味現在価値)
| 《問41》 毎期末に1,000万円の純収益が得られる賃貸マンションを1億5,000万円で取得し、取得から3年経過時点で1億4,500万円で売却する不動産投資におけるNPV(正味現在価値)として、次のうち最も適切なものはどれか。 なお、NPV(正味現在価値)の算出にあたっては、その計算過程においてDCF法を用いることとし、割引率は年5%として下記の係数表を利用すること。また、記載のな い事項については考慮しないものとする。 〈年5%の各種係数〉 |
| 期間(年) | 現価係数 | 年金現価係数 |
| 1年 | 0.952 | 0.952 |
| 2年 | 0.907 | 1.859 |
| 3年 | 0.864 | 2.723 |
| 1) 120万円 2) 251万円 3) 2,223万円 4) 2,291万円 |
正解2

定番のNPVの計算問題だね。正直、この問題が出るとちょっとホットするね。しかし、落ち着いて計算しないと取りこぼしたら後悔するからね。

1年目: 1,000万円×0.952=952万円
2年目: 1,000万円×0.907=907万円
3年目: 1,000万円×0.864=864万円
売 却: 1億4,500万円×0.864=1億2,527万円
952万円+907万円+864万円+1億2,527万円= 1億5,251万円
1億5,251万円-1億5,000万円=251万円
今回は全体的にやさしかった印象です。私が受験していたら問38、問39、問40は難しかったけど、残りの問題はできたんじゃないかと思います。
やはり、6月まで実技試験の勉強をしていたのが大きいのかもしれません。