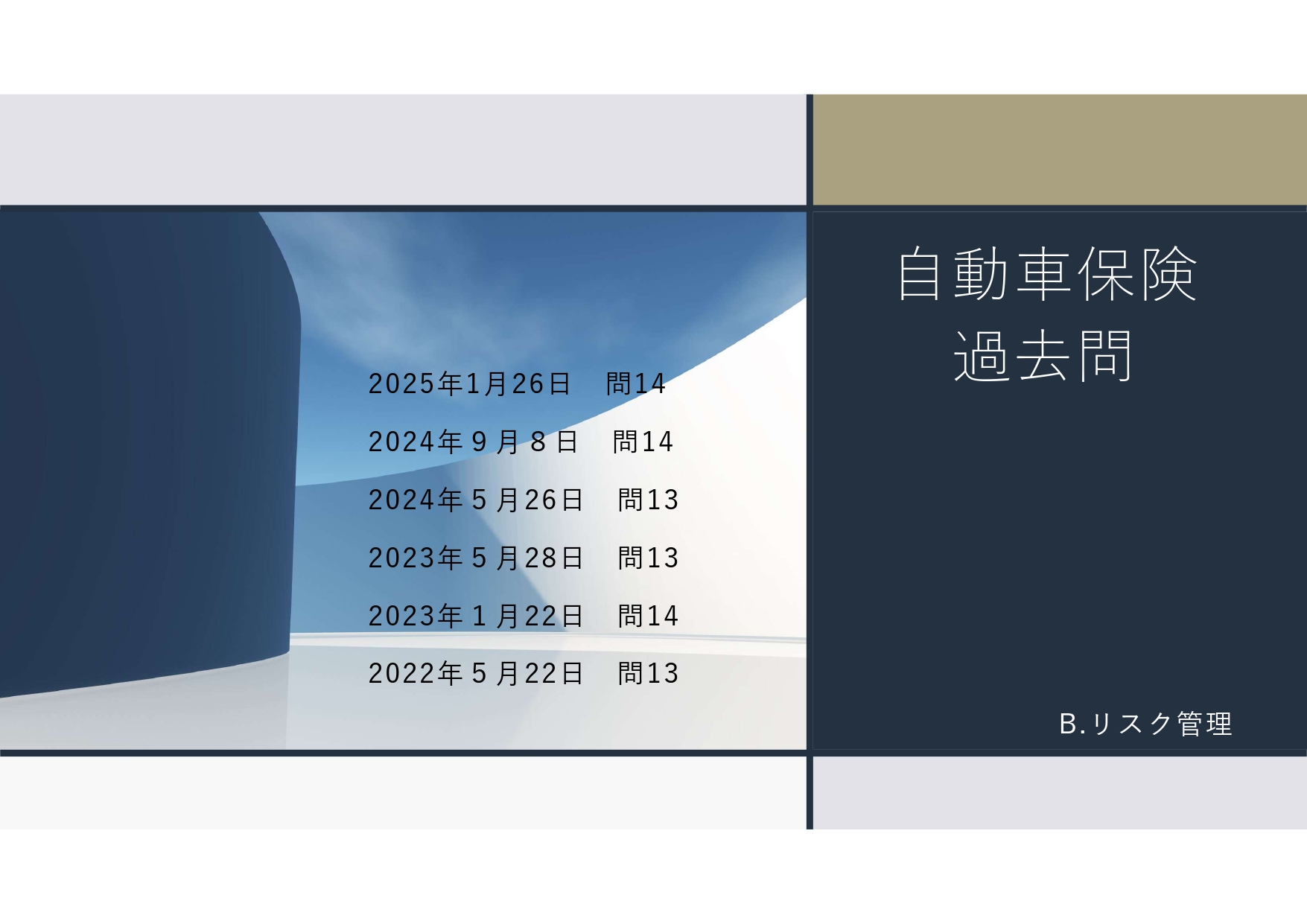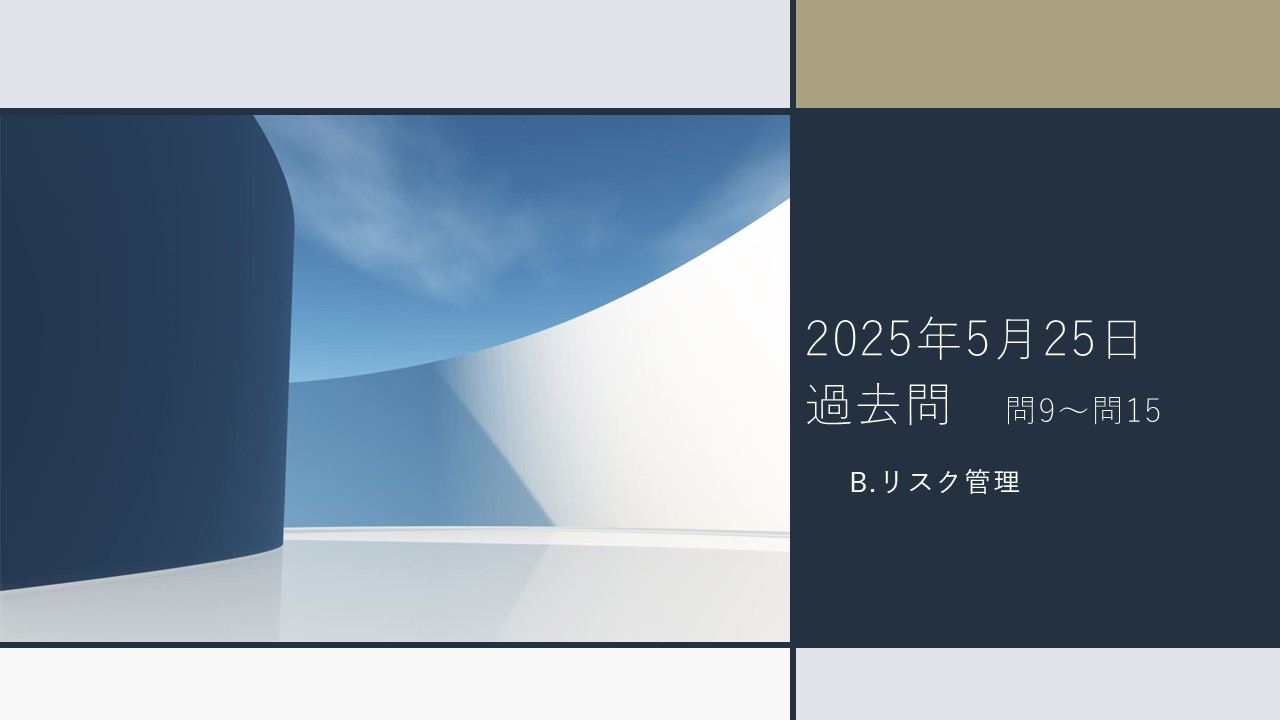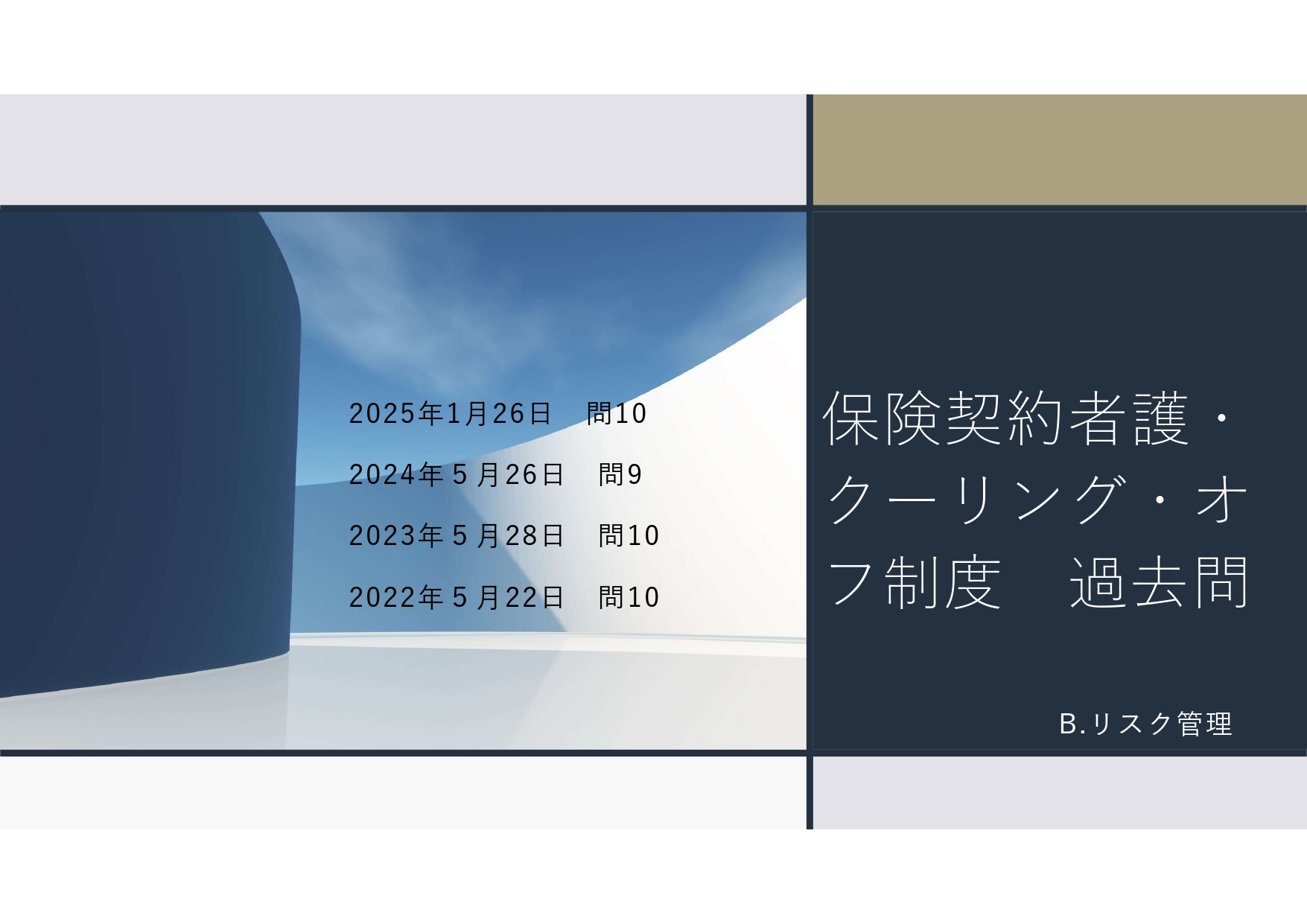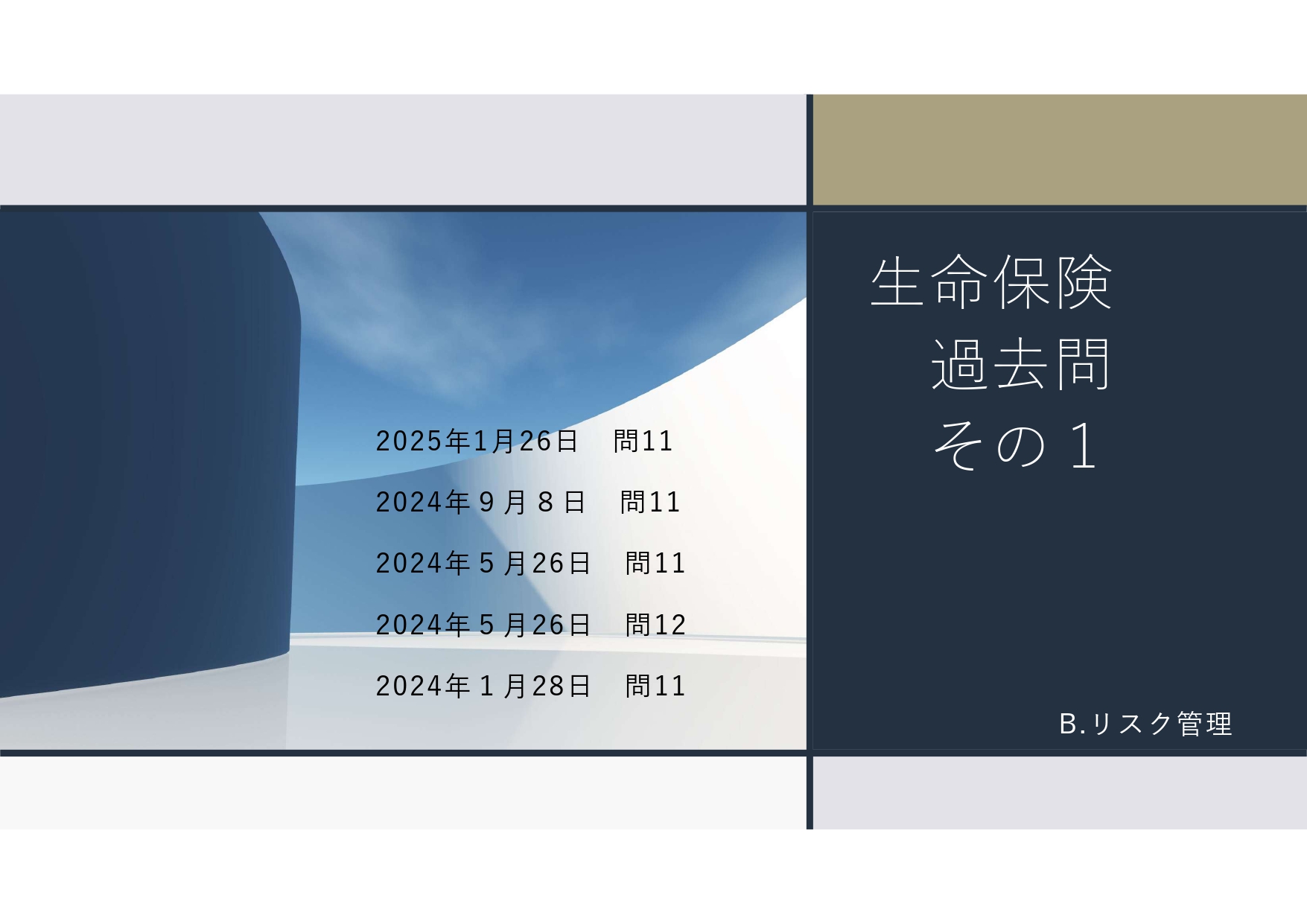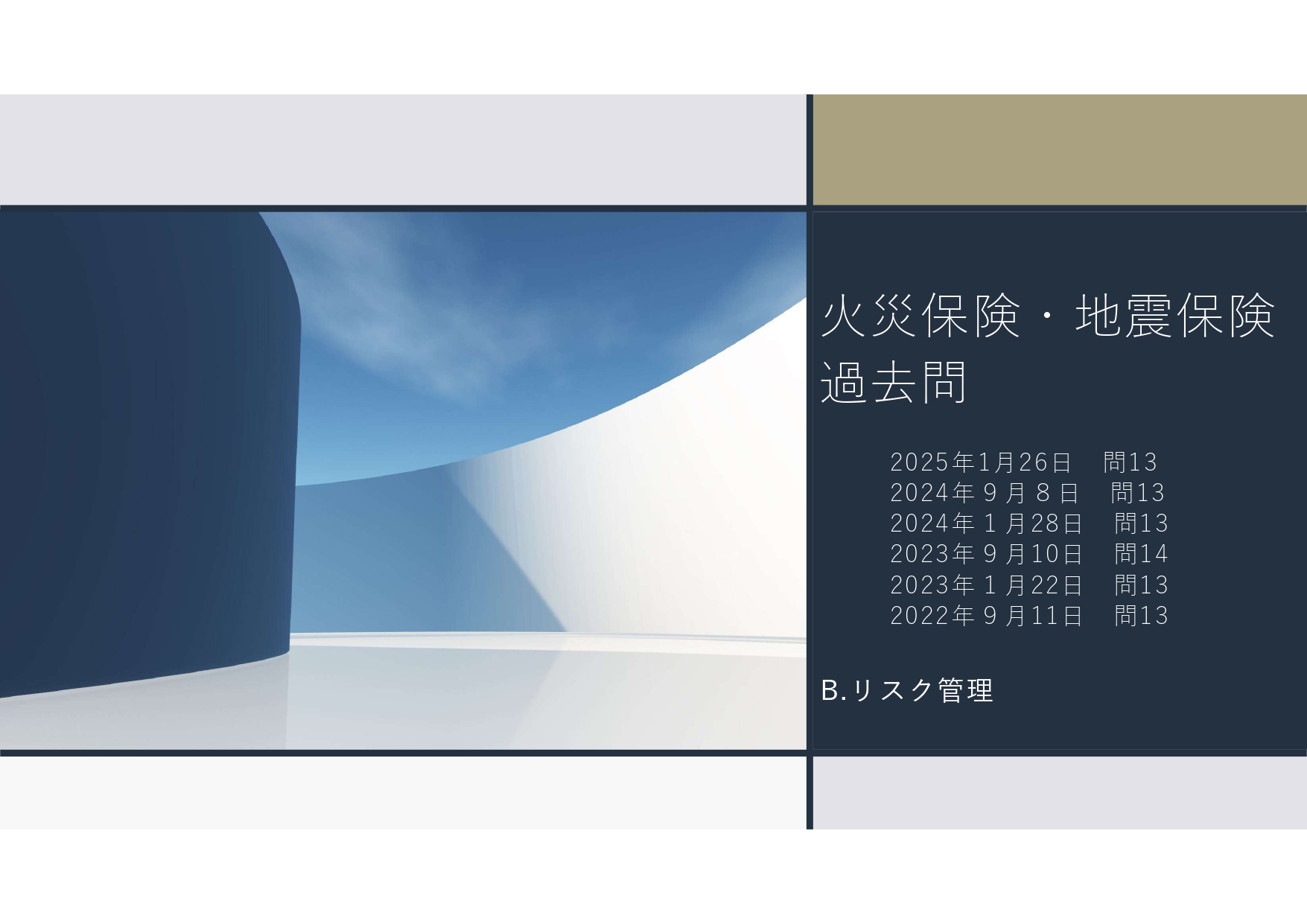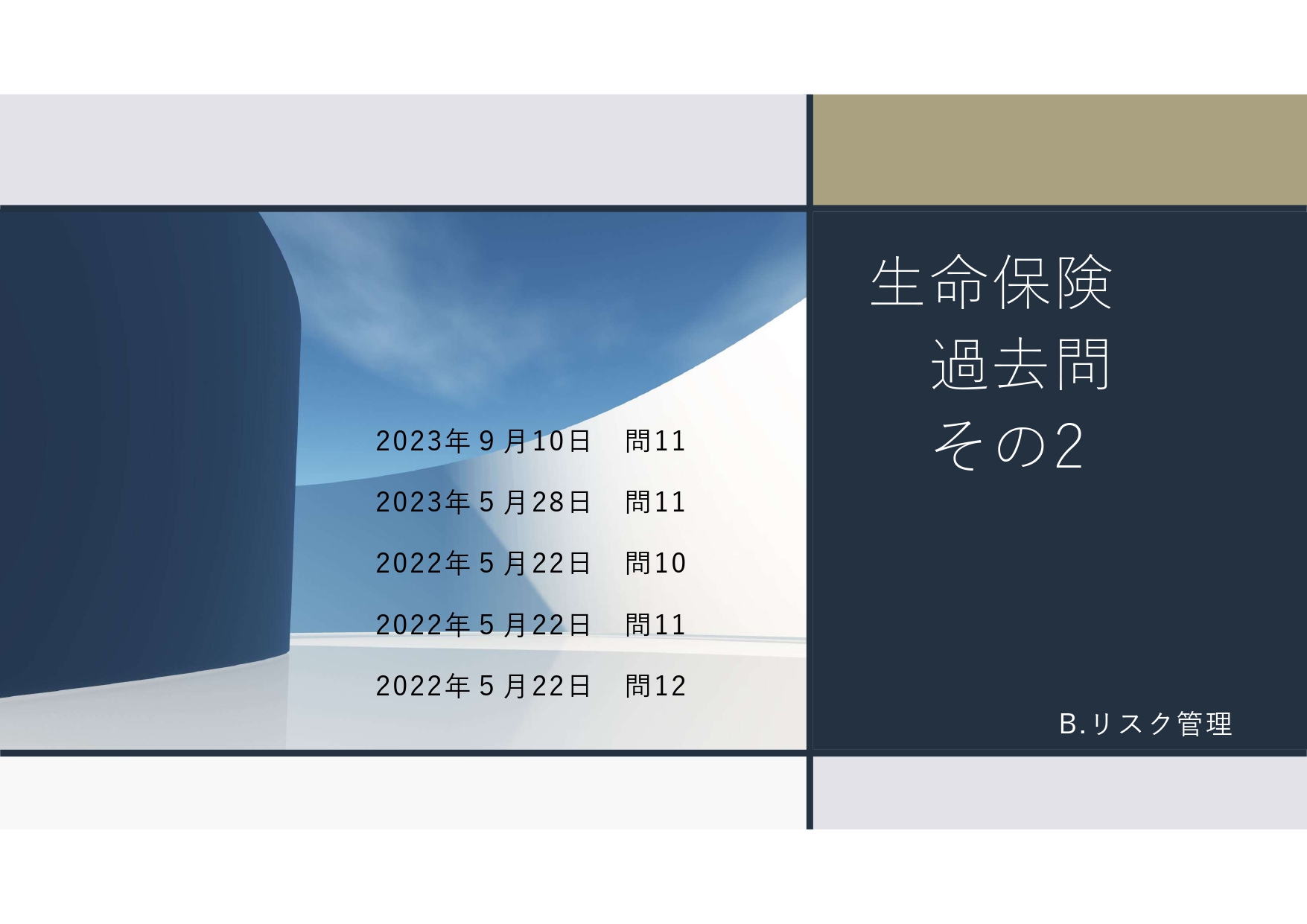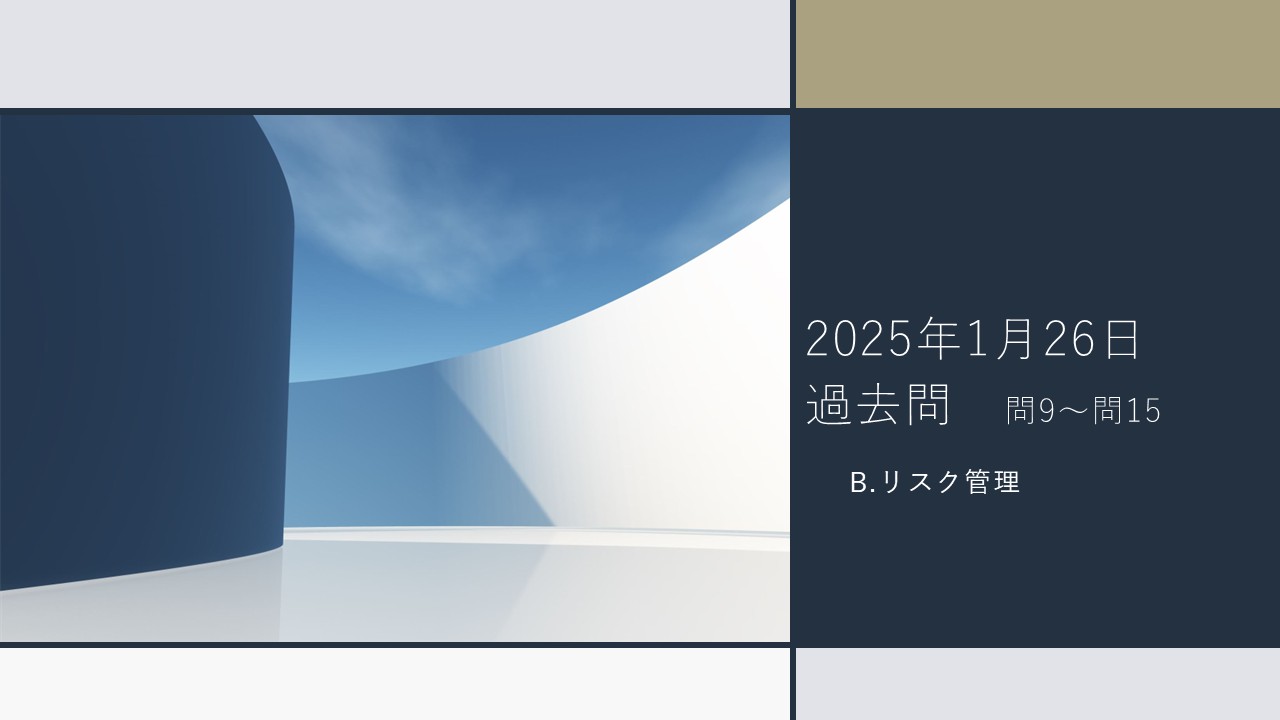2024年9月8日 リスク管理 基礎編
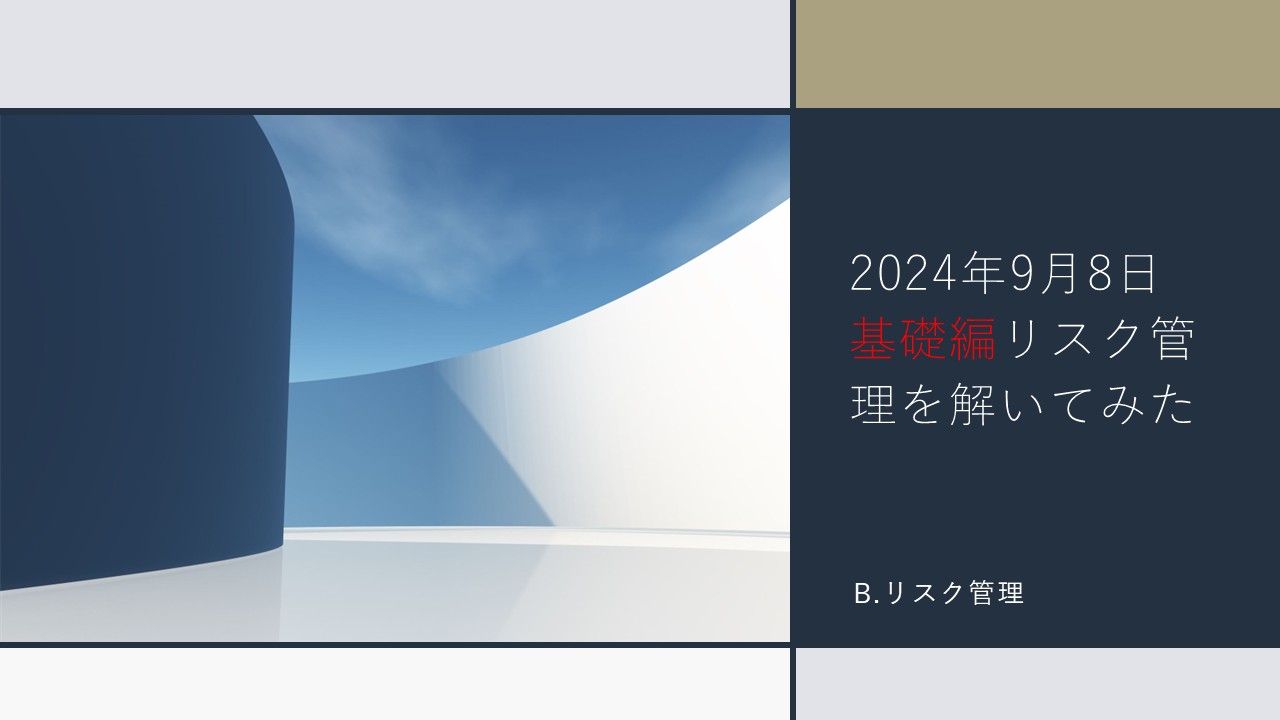
得意科目の得点アップか苦手科目の克服か
全ての科目がバランスよく得点できる方も、いらっしゃるでしょうが、私も含め、多くの受験生が得意科目、苦手科目があると思います。
私の場合、ライフプランニング、リスク管理が苦手だったため、最初から問題を解いていた時は、前半で心が折られ、モチベーションが下がった状態で中盤を迎えることになりました。
個人的な印象ですが、得意科目で70点から80点にアップを狙うより、苦手科目で30点を40点にする方が、楽で現実的です。
何度か不合格を積み重ねた私ですが、ライフプランニングとリスク管理の苦手意識を克服降ることで、受験が楽になりました。
では、解説を始めます。今回も出所:一般社団法人金融財政研究会です。
問9 保険法
| 《問9》 保険法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険事故の発生の可能性に関する重要な事項について、自発的に判断して保険者に対して申告しなければならないとされている。 2) 生命保険契約において、保険金受取人は、保険契約者との信頼関係が損なわれるような重大な事由が生じた場合や親族関係が終了した場合に、保険契約者に対し、その保険契約を解除することを請求することができるとされている。 3) 損害保険契約の締結時に保険金額が保険価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者は、原則として、その保険契約の全部について取り消すことができるとされている。 4) 保険契約者または被保険者の告知義務違反による保険者の保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1カ月間行使しないとき、または保険契約の締結時から5年を経過したときに消滅するとされている。 |
正解4

定番の問題だね。保険者(保険会社)、契約者、被保険者、保険金受取人がごっちゃになった選択肢もあるから気を付けた方がいいね。

1)保険者から求められた情報提供をしなければいけないのであって、自発的である必要はないね。
2)契約者は解除の請求ができるけど、保険金受取人はできないね。
3)全部を取り消すことはできないけど、今後の減額請求はできるよ。
4)これが正しいね。これは本文のまま覚えることをお勧めするよ。
問10 生命保険会社の健全性・収益性
| 《問10》 生命保険会社の健全性・収益性に関する指標等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 基礎利益は、保険会社の基礎的な期間損益の状況を表す指標であり、経常利益に危険準備金繰入額等の「臨時損益」を加え、有価証券売却益等の「キャピタル損益」を除くことで算出される。 2) 保有契約高は、保険会社が事業年度末において保障する金額の合計額であり、個人年金保険については、年金支払開始前契約の年金支払開始時における年金原資の額と年金支払開始後契約の責任準備金の額の合計額となる。 3)ソルベンシー・マージン比率は、保険会社が有する保険金等の支払余力を表す指標であり、この値が200%を下回った場合には、業務改善命令等の早期是正措置の対象となる。 4)実質純資産額は、有価証券や有形固定資産の含み損益等を反映した時価ベースの資産の合計から、価格変動準備金や危険準備金等の資本性の高い負債を除いた負債の合計を差し引いて算出される。 |
正解1

ソルベンシー・マージン比率、基礎利益、実質純資産額、エンベディッド・バリュー(EV)は計算式も含めて暗記必須だね。
計算式をちょっと変えると適切→不適切になるからね。

1)基礎利益=経常利益-臨時損益-キャピタル損益だから間違わないように注意が必要だね。これに気づいたら、2)以降は読まなくていいかも。計算式を文字で説明すると混乱する表現が増えるからね。 2)~4)は正しい説明だよ。
問11 生命保険契約の各種手続等
| 《問11》 生命保険契約の各種手続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1)契約転換は、現在加入している生命保険契約を活用して同一の保険会社で新規に契約する方法であり、転換(下取り)価格には、転換前契約の責任準備金が充当され、積立配当金は払い戻される。 2) 払済保険に変更した場合、予定利率は変更時点における予定利率が適用され、原則として、元契約に付加されていた特約は消滅するが、リビング・ニーズ特約は消滅しない。 3) 契約者貸付は、一般に、契約者が加入している生命保険契約の利用時点の解約返戻金額を限度として保険会社から貸付を受けることができるものであり、その返済前に保険金の支払事由が生じた場合、保険金から貸付金の元利合計額が差し引かれる。 4) 契約者貸付の利率は、一般に、生命保険契約の契約時期により異なる利率が適用され、予定利率が高い時期の生命保険契約に係る契約者貸付の利率は高くなる。 |
正解4

生命保険の契約を転換するとか経験ないから、苦手なんだよね。しかし、世知辛くなってくると仕方なく見直す方も増えるのかもしれないね。

1)契約転換をした場合、積立配当金は払い戻されず、新たな契約に充当されるね。
2)払済保険に変更した場合の予定利率は当初のままだよ。後半のリビングニーズ特約は消滅しないというのは正しいから、これに引っ張られて選択しちゃう人も多いかもね。
3)契約者貸付は解約返戻金額の7~9割が限度額になるよ。
4)これが正しいね。予定利率は保険会社が契約者から預かった資金の運用利回りのことだね。
問12 生命保険の経理処理
| 《問12》 X株式会社(以下、「X社」という)の社長であるAさんは、現在65歳であるが、2年後(2026年9月末)に勇退しようと考えている。その際、X社が加入している以下の定期保険を解約し、退職金の一部として受け取りたいと考えている。以下の定期保険を解約した場合の経理処理として、次のうち最も適切なものはどれか。 保険の種類 :無配当定期保険(特約付加なし) 契約年月日 :2019年12月1日 契約者(=保険料負担者) :X社 被保険者 :Aさん(加入時の年齢60歳) 死亡保険金受取人 :X社 保険期間・保険料払込期間 :98歳満了 基本保険金額 :1億円 最高解約返戻率 :77.0% 年払保険料 :450万円 2026年9月時点の解約返戻金 :2,400万円 2026年9月時点の払込保険料累計額:3,150万円 |
| 1) | 借 方 | 貸 方 | ||||||
| 現金・預金 2,400万円 | 雑収入 2,400万円 | |||||||
| 2) | 借 方 | 貸 方 | ||||||
| 現金・預金 2,400万円 | 前払保険料 1,890万円 雑収入 510万円 | |||||||
| 3) | 借 方 | 貸 方 | ||||||
| 現金・預金 2,400万円 | 前払保険料 1,575万円 雑収入 825万円 | |||||||
| 4) | 借 方 | 貸 方 | ||||||
| 現金・預金 2,400万円 | 前払保険料 1,260万円 雑収入 1,140万円 | |||||||
正解2

仕訳問題は難易度に差があるんだよね。最高解約変捩率50%以下、50%~70%以下、70%~85%以下、85%超で85%超は当初10年目と11年以降の全部で5段階に分けて考えるんだよね。
70%とか85%とか、どっちに含まれるか迷う出題が多いんだよね。

最高解約返礼率77%だから70%~85%以下のレンジに含まれるから支払保険料の10分の6なので、3,150万円×60%=1,890万円が資産計上されているから
解約返戻金2,400万円-1,890万円=510万円が雑収入となるんだね。
よって 2)が正解だね。
問13 火災保険
| 《問13》 住宅建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 住宅建物および家財を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内の車庫に収容されている自転車や総排気量125cc以下の原動機付自転車に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。 2) 住宅建物を対象とする火災保険では、保険の対象となる住宅建物の敷地内にある門や塀、垣に火災による損害が生じた場合、その損害は補償の対象となる。 3) 住宅建物および家財を対象として火災保険を契約する場合、保険期間は最長で5年とされ、長期契約の保険料を一括払いした場合には、所定の割引率が適用される。 4) 火災保険に付帯する地震火災費用特約は保険の対象となる住宅建物が地震等を原因とする火災により半焼となった場合に保険金額の5%が支払われ、全焼となった場合に保険金額の10%が支払われる特約である。 |
正解4

火災保険も頻出だから、過去問を数回さかのぼれば、だいたいの傾向はつかめると思うよ。

1)2)は何度も出題されているからわからないといけないね。
3)4)はちょっと迷うけど、
4)地震火災費用特約は全焼、半焼に関わらず、保険金額の5%が正しいということだよ。
正直、特約まで覚えるのは厳しいけどね。
問14 自賠責保険
| 《問14》 自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1) 自賠責保険は、自動車の運行中の事故に対して保険金が支払われるが、運行には、自動車の走行だけでなく、停車中のドアの開閉も含まれる。 2) 自賠責保険の保険料は、車種や保険期間等に応じて定められており、加入する損害保険会社や運転者の年齢による差異はない。 3) 自賠責保険では、自動車事故の被害者の過失割合が5割以上の場合、積算した損害額が保険金額に満たないときには積算した損害額から、保険金額以上となるときには保険金額から、被害者の過失割合に応じて2割から5割の減額が行われる。 4) 自賠責保険における被害者1人当たりの保険金の支払限度額は、加害車両が1台である場合、死亡による損害については3,000万円、傷害による損害については120万円、後遺障害による損害については障害の程度に応じて75万円から最高4,000万円である。 |
正解3

自動車保険もドライバーには、よくお世話になる保険だね。

不適切は3)だね。過失割合は5割でなく7割が正しいよ。
1)2)4)は一般知識として覚えておくことをお勧めだね。
4)は数字を変えて出題されることもあるから要注意だよ。
問15 第三分野の保険
| 《問15》第三分野の保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、 適切なものはいくつあるか。 (a)就業不能保険は、入院や在宅療養が一定日数以上継続して所定の就業不能状態に該当した場合に保険金・給付金が支払われる保険であり、うつ病などの精神疾患による就業不能を保障するタイプの保険もある。 (b) 介護保障保険は、公的介護保険における要介護認定を受けた場合や所定の要介護状態になった場合に保険金・給付金が支払われる保険であり、被保険者の年齢や保険期間等の他の契約内容が同一であれば、被保険者の性別による保険料の差異はない。 (c) 所得補償保険は、病気やケガによる休業や勤務先の倒産による失業によって所得を喪失した場合に保険金・給付金が支払われる保険であり、被保険者の年齢や職種により保険料が異なる。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解1

第三分野の保険は生命保険、損害保険にまたがる、またはどちらにも属さない保険で、代表的なものは医療保険、介護保険、傷害保険などだね。

(a)これは正しい選択肢だね。これに限らず、正しい選択肢を覚えるというのは時短の勉強法といえるかもね。
(b) 女性が男性より平均余命が長いので、保険料は女性の方が高くなるよ。よって間違いだね。
(c) 倒産による失業は所得補償保険の対象外だね。急いで読んでいると読み飛ばしそうだけど、病気やケガと失業ではちょっとニュアンスが違うもんね。
よって適切なのは(a)ひとつだから1)が正解だね。
リスク管理というのは保険の知識を身に着けるという意味合いが強く、応用編の科目になっていないので、どうしても後回しにしがちだけど、
一般社団法人金融財政事情研究会の実技試験でまれに問われることがあるし、日本FP協会の実技試験を受験される方は、現在加入している保険の保証内容を確認して、金額を求める出題がるので、油断はできません。
ほとんどの保険商品はいわゆる掛け捨てで、何もなければ、不要だったと思うこともあるかもしれませんが、何かあった時では遅いというのも、また事実だと思います。
何も無いことを祈り、お守りのつもりで保険の契約を検討するのもありだと思います。 私のように持病があると、入りたくても入れないという人もいるからです。