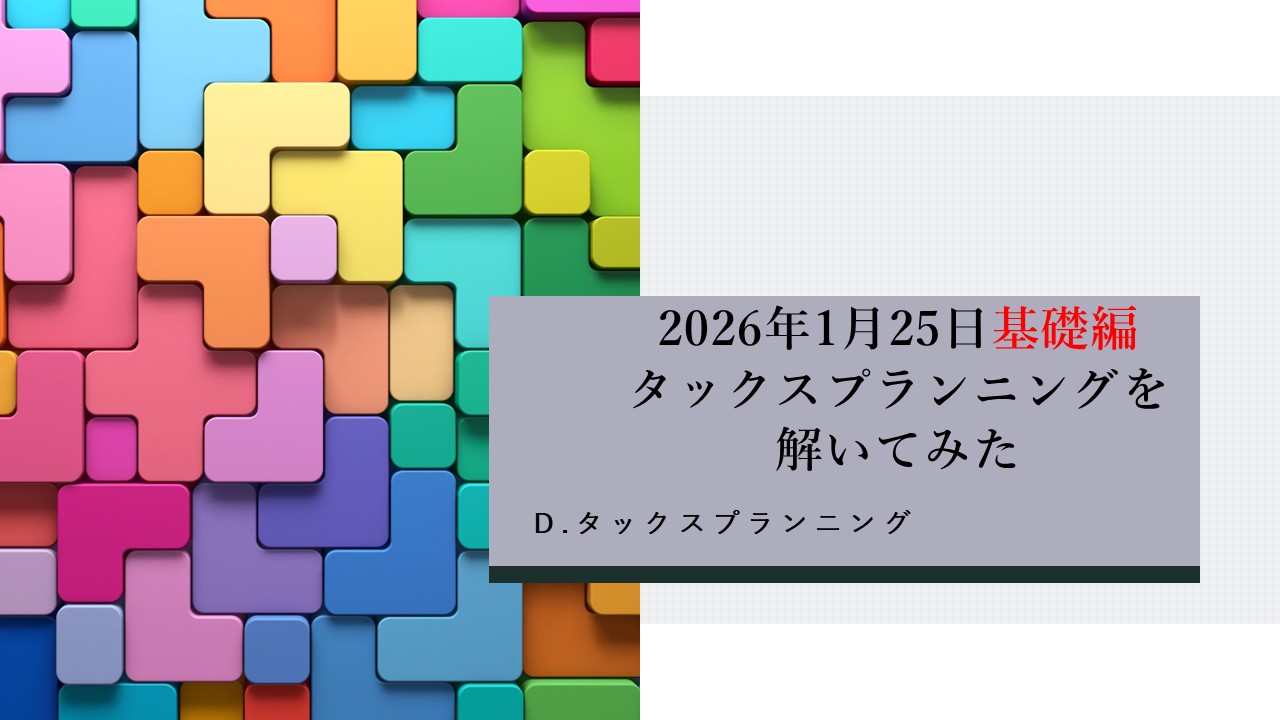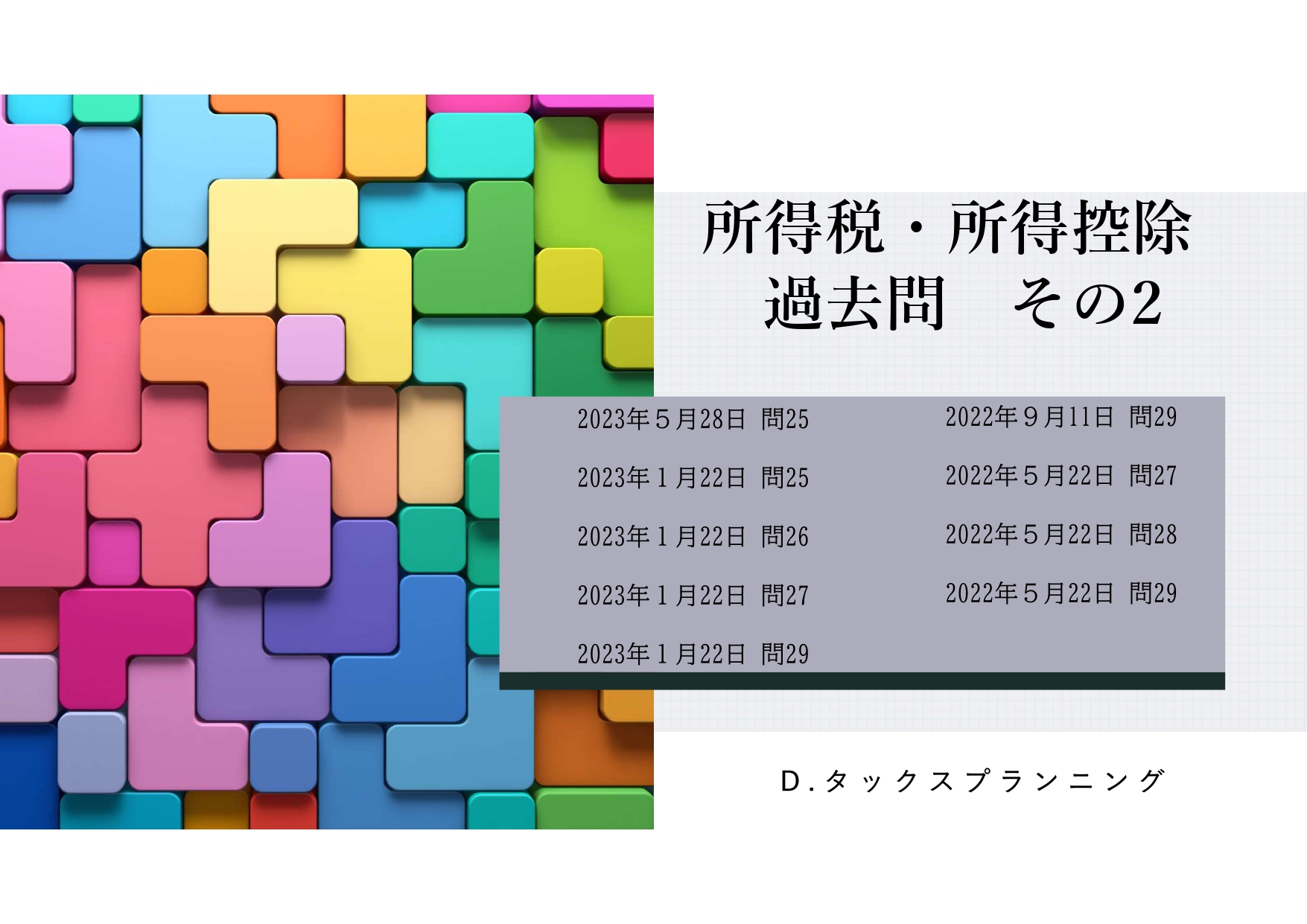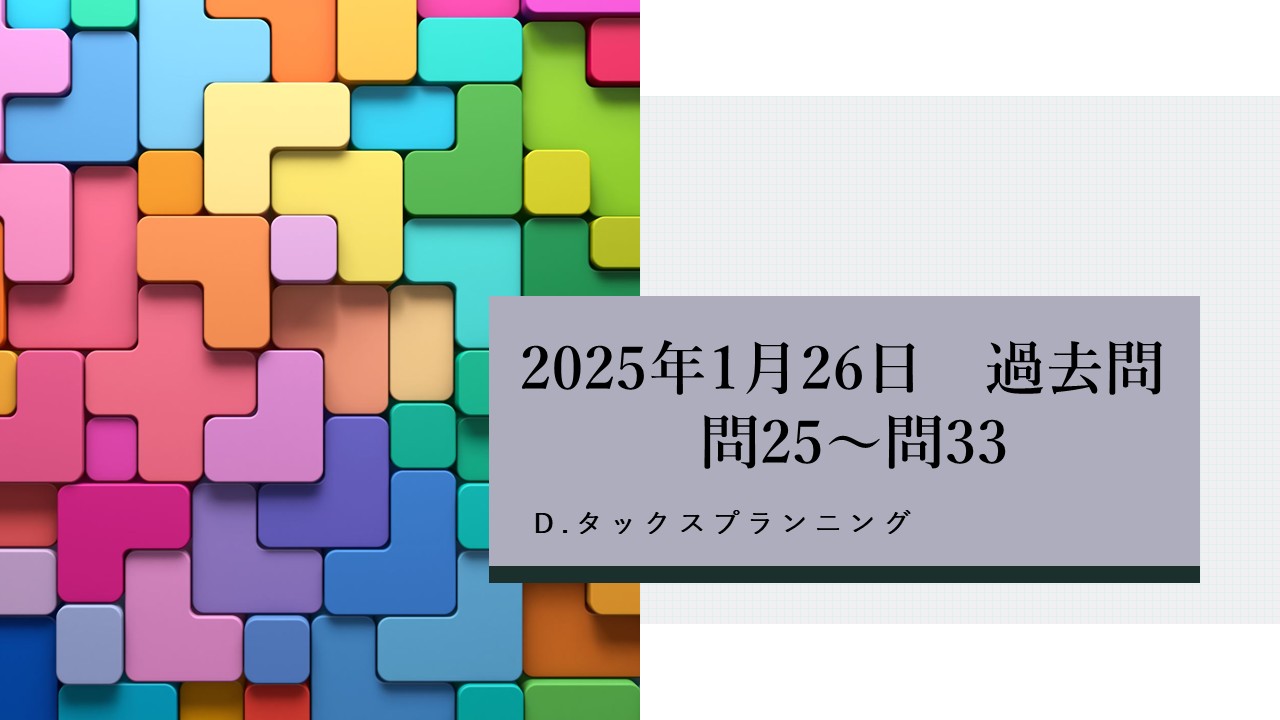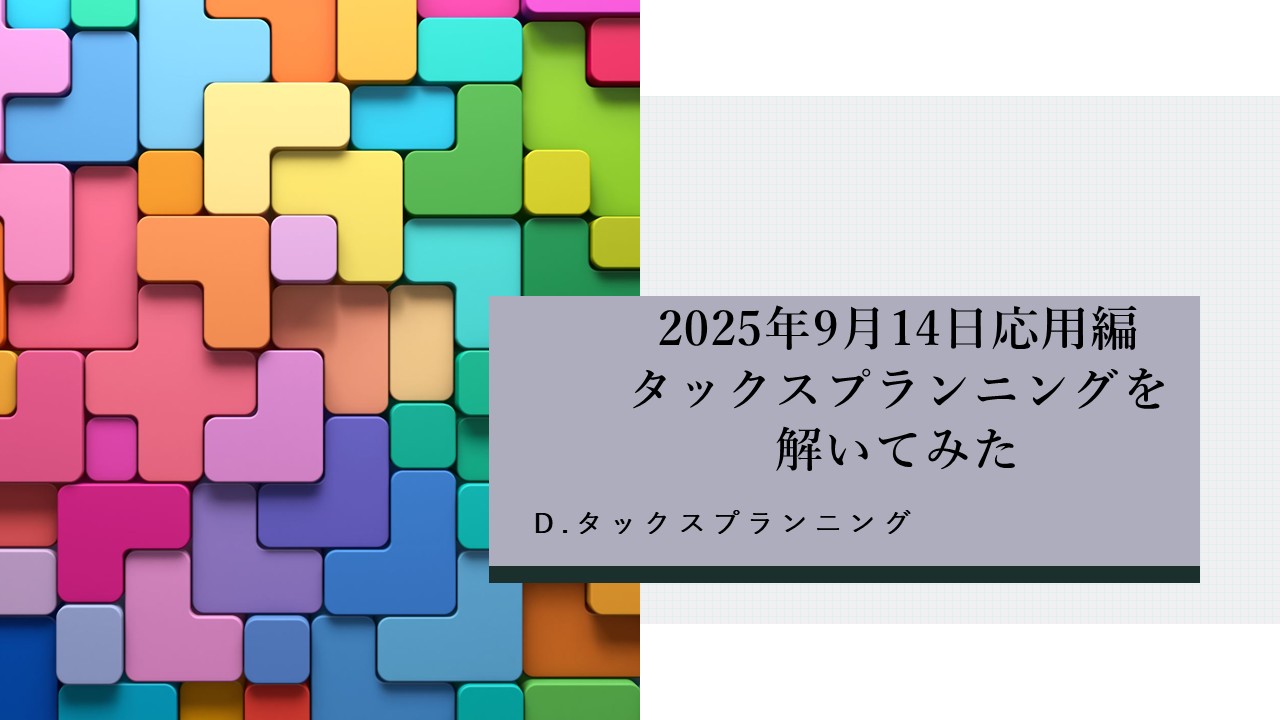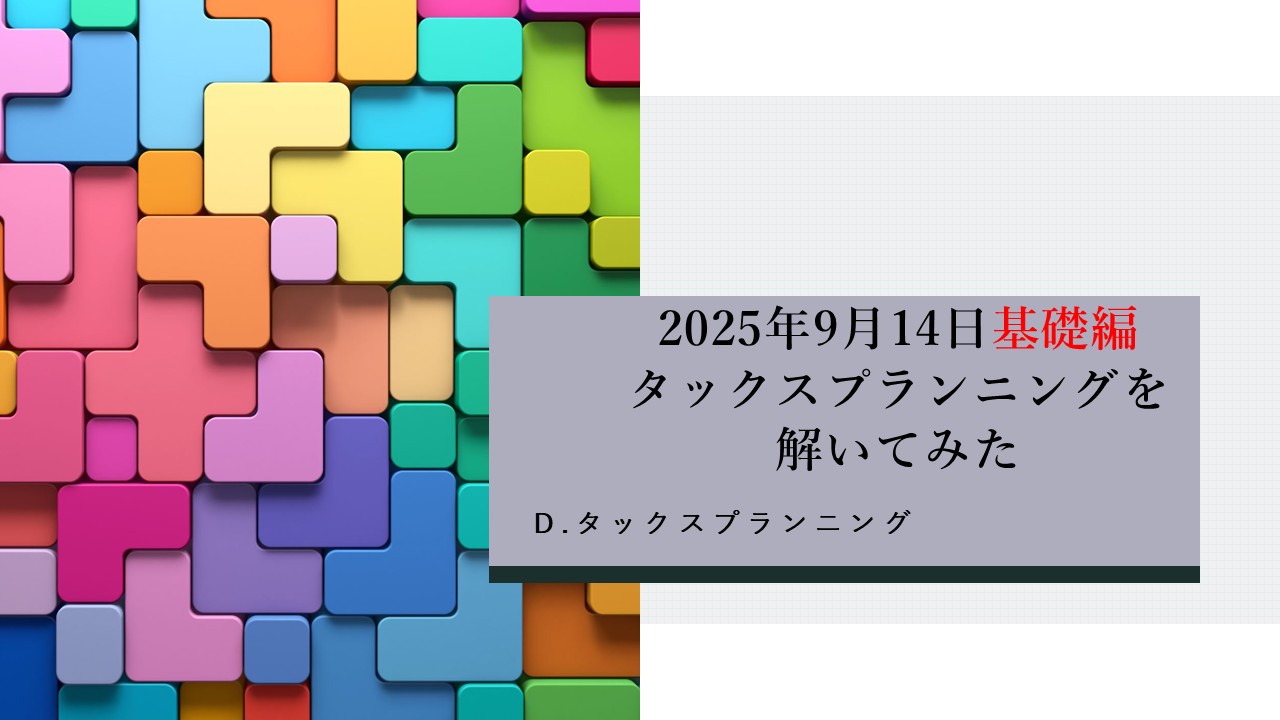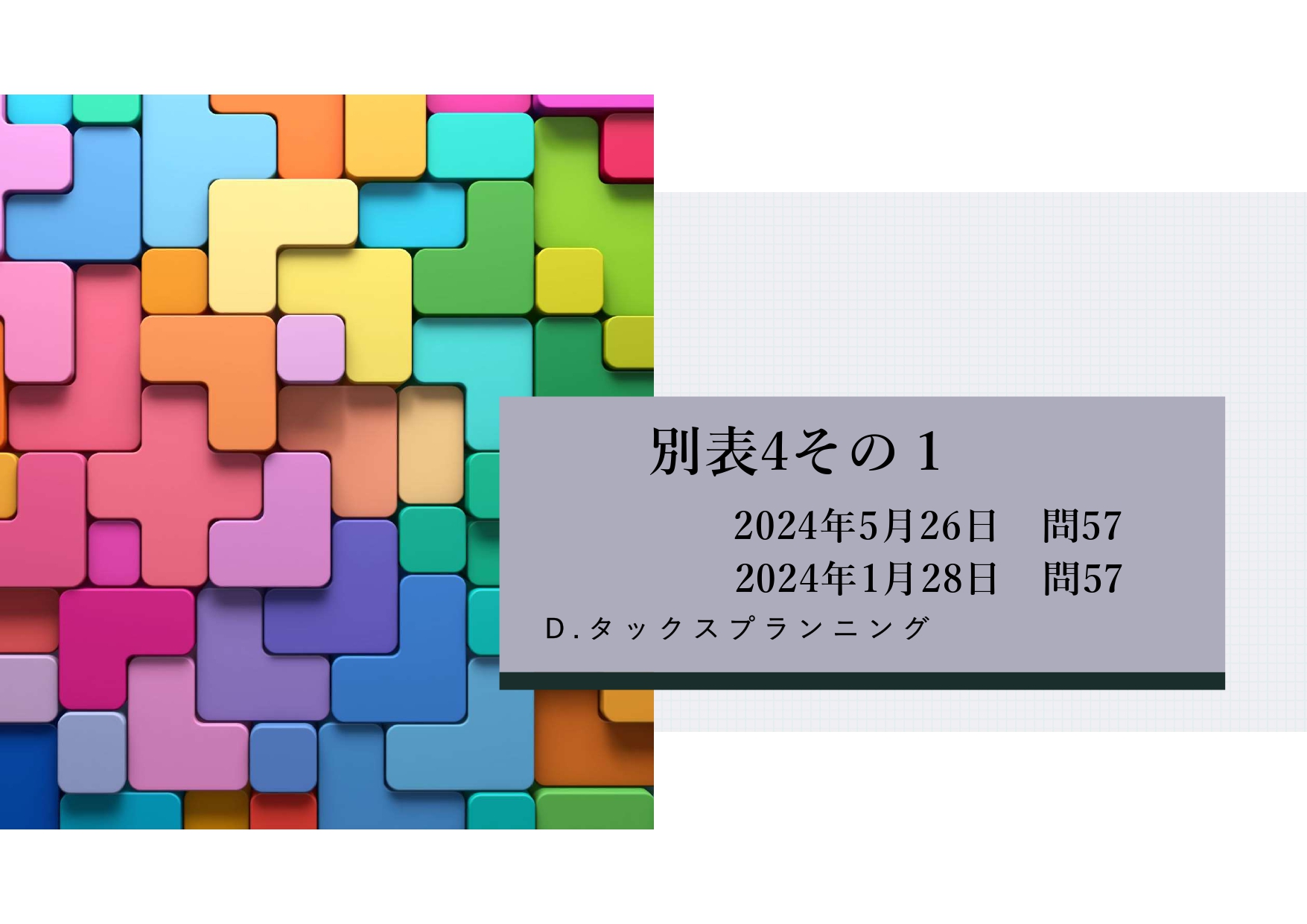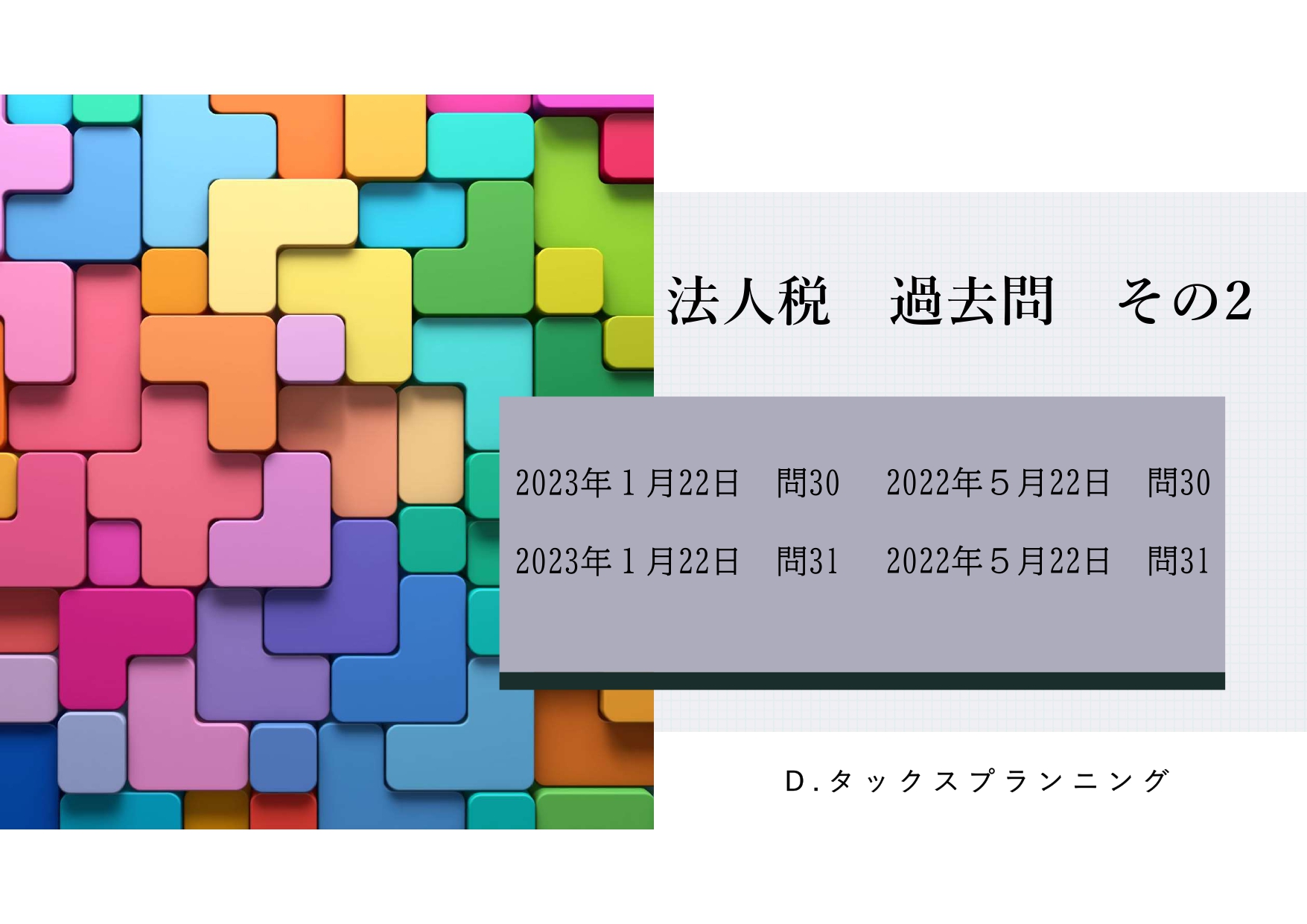2025.5.25基礎 タックス・プランニング
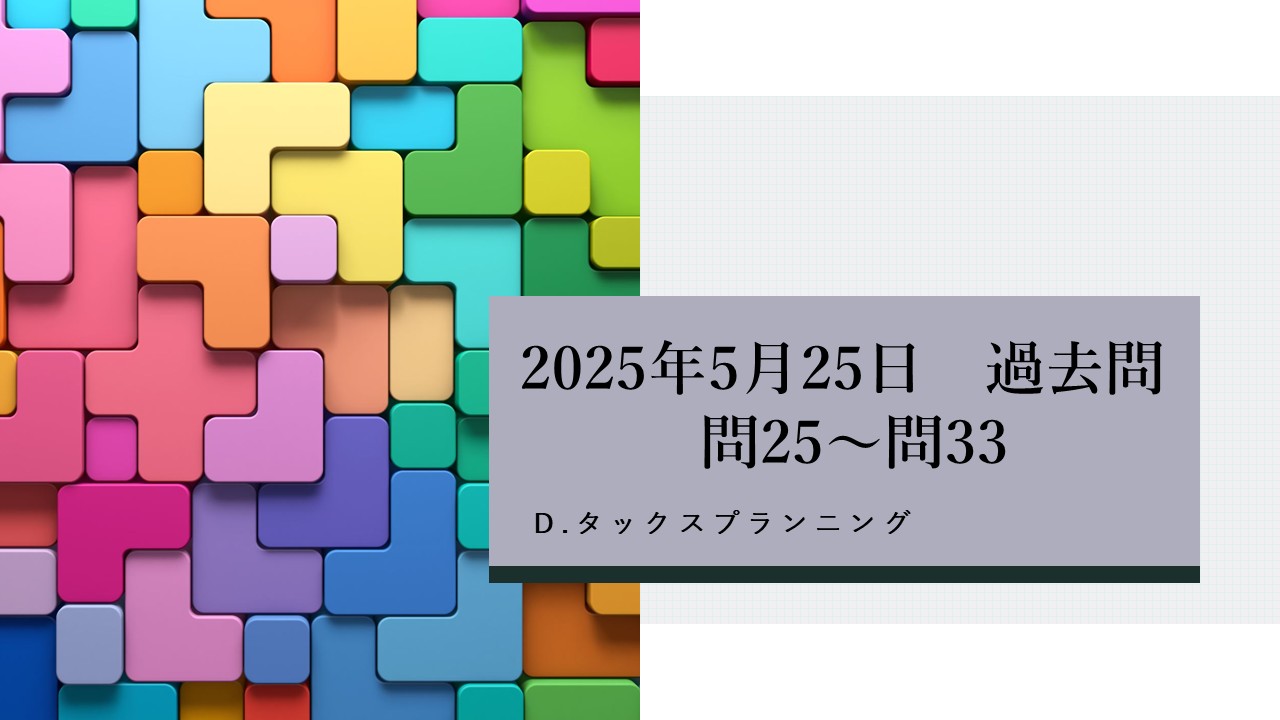
30年前頭の良い友人にお金があるならマンションをもって不動産収入で生活したらいいよ。と言われたことがあるけど、今考えたら、ある意味その通りだったと思います。
その頃はバブル経済が崩壊したばかりで、不動産投資で大損したなどマイナスイメージがあったのですが、その後を振り返ってみても、賃貸物件を持っている方はやはり手堅く収入を得て安定した生活を送っているような気がします。
不動産所得のネタはFP試験では不可欠です。具体的には会社員をしながら副業でマンション経営をしている方の損益通算や、確定申告など、実際の計算や申告は税理士さんに任せるとしても、一般的な知識の提供はFPでも可能だだと思います。
または、不動産所得が一定の規模を超えると脱サラして専従者になる方もいらっしゃいます。その方の節税対策や相続対策など、まさにFPが実力を発揮する場面ともいえるでしょう。
以下は出所:一般社団法人金融財政事情研究会です。
問25 不動産所得
| 《問25》 居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 賃貸人が、定期借地権の設定の際に賃借人から預託を受けた保証金(賃借人が返還請求権を有するもの)を定期預金に預け入れ、その利子を受け取った場合、当該利子は、不動産所得の金額の計算上、収入金額に算入される。 2) 賃貸人が、建物の賃貸借契約の際に賃借人から受け取った敷金(賃借人が返還請求権を有するもの)は、不動産所得の金額の計算上、原則として、その受け取った日が属する年分において収入金額に算入され、賃借人に返還する日が属する年分において必要経費に算入する。 3) 賃貸人が、所有する賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 4) 賃貸人が、所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、不動産の貸付が事業的規模に満たない場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除する前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。 |
正解4

不動産所得は毎回出題されるね。青色申告や白色申告の出題パターンもあり、所得の種類も不動産所得だけじゃなく、保証金や敷金などちょっとややこしいね。

1)敷金や保証金を預金として寝かせておくのでなく運用した場合は、利子所得だから不適切だね。
2)敷金って入居者が退去したときに返さないといけないから所得にしてはまずいよね。だから間違いだね。
3)立退料って不動産を手放すときに登場するから譲渡所得の費用にはなるけど、不動産所得じゃないね。
4)これはよく出る論点だね。事業的規模5棟10室じゃない場合は問題文の通りだね。事業的規模であれば全額が損金算入可能だから注意が必要だね。
問26 一時所得および雑所得
| 《問26》 居住者に係る所得税の一時所得および雑所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 会社員が退職後、再就職して受け取った雇用保険の再就職手当は、一時所得として総合課税の対象となる。 2) 法人の株主が株主である地位に基づいて当該法人から受けた経済的利益で、配当所得とされないもの(いわゆる株主優待券等)は、一時所得として総合課税の対象となる。 3) 所得税の還付申告により、還付金とともに受け取った還付加算金は、雑所得として総合課税の対象となる。 4) 地方公共団体に寄附(ふるさと納税)をした者が、寄附に対する謝礼として受け取った返礼品に係る経済的利益は、雑所得として総合課税の対象となる。 |
正解3

一時所得、雑所得という言葉は2023年1月の応用編ですごく印象に残っているんだよね。
この2つって正直、区別が難しいんだよね。

1)再就職手当は非課税だから誤りだね。社会保険から受け取る給付は基本非課税と覚えてもいいかもね。例外は老齢年金だね。
2)これも記憶がありまいだね。前半の配当所得は正しいけど、株主優待券等は雑所得だね。
3)還付加算金は雑所得だから、これが正しいね。
4)ふるさと納税の返礼品は一時所得なんだよね。これがややこしいところだけど、間違えやすいところだから暗記することをお勧めするよ。
問27 所得控除
| 《問27》 居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 父が入院中に死亡し、その後、相続人である子が父の入院中に生じた医療費を相続財産から支払った場合、当該医療費は、父に係る準確定申告において医療費控除の対象となる。 2) 納税者が、生計を一にする長男が未納にしていた過去2年分の国民年金の保険料を支払った場合、納めた全額がその支払った年分の社会保険料控除の対象となる。 3) 合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、生計を一にする配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除の適用を受けることができない。 4) 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者に該当しない。 |
正解1

所得控除というのもよく出題されるテーマだね。会社員の方は年末調整の際に、生命保険、損害保険会社から送られてくる証書を会社に持っていって記入してたりするんじゃないだろうか。また、103万円の壁が選挙の争点のひとつになったり、関心が高まっている分野ともいええるよね。

1)これが不適切だね。これは何度も出題されているので覚えている方も多いよね。準確定申告では、墓地、仏壇は認められるというのは覚えておいていいかもね。医療費は子の医療費控除の対象になることにも注意が必要だね。
2)これは適切だね、学生時代に年金を払えなかった人の親がまとめて支払うというのはありえる話だしね。
3)定番な論点だね、しかしちょっとアレンジした問題もありえるので注意が必要だけど、これは正しいね。
4)これも定番な論点だね、配偶者といえど事業専従者なら扶養しているという考えではないかもね。
問28 配当控除の計算
| 《問28》 居住者であるAさんの2024年分の所得の金額等が下記のとおりであった場合の所得税の配当控除の額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、配当所得は、東京証券取引所に上場している内国株式の配当を受け取ったことによる所得で、総合課税を選択したものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。 配当所得の金額 : 300万円 不動産所得の金額 : 920万円 所得控除の額の合計額 : 160万円 1) 15万円 2) 19万円 3) 27万円 4) 30万円 |
正解3

配当控除の計算問題も定番だね、

この問題も定番で、不動産所得と配当所得を足したら1,000万円を超えるパターンだね。
不動産所得920万円―所得控除160万円=760万円
1,000万円―760万円=240万円×10%=24万円(1,000万円以下の部分)
300万円―240万円=60万円×5%=3万円(1,000万円超の部分)
24万円+3万円=27万円・・・3)
問29 個人事業税
| 《問29》 個人事業税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 個人事業税は、第1種事業、第2種事業および第3種事業に該当する事業を行う個人に対して課せられ、これらの事業のいずれにも該当しない事業を行う個人には課されない。 2) 前年分の所得税の青色申告書を申告期限内にe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して提出している場合、個人事業税における所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高で65万円を控除することができる。 3) 個人が年の中途において事業を開始した場合、個人事業税におけるその年分の所得の金額の計算上、その年に事業を行った期間によらず、事業主控除として最高で290万円を控除することができる。 4) 個人事業税の納税義務者が年の中途において事業を廃止した場合、原則として、当該事業の廃止の日から2カ月以内に、その年の1月1日から当該事業の廃止の日までの事業の所得の金額等を事務所または事業所所在地の都道府県知事に申告しなければならない。 |
正解1

個人事業税というのが頭に入ってないな。

1)第2種(畜産業、水産業、薪炭製造業)第3種(資格や免許を要する仕事、医師・弁護士など)を覚えて、営利企業は第1種なんだけど、農業、林業は非課税だから含まれないね。
この選択肢は正しいよ。
2)青色申告特別控除65万円は所得税の話だね。事業税は290万円の事業主控除なので、ごっちゃにしないように要注意だね。
3)年の途中で事業を始めた場合は月割りで事業主控除が計算されるね。
4)事業を廃止した時の申告期限は1か月以内だね。
細かい知識が問われるね~
問30 修繕費
| 《問30》 法人税における修繕費に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、法人はいずれも内国法人(普通法人)であるものとする。 1) 法人が現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額は、修繕費に該当する。 2) 法人が一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が50万円である場合、その金額について修繕費として損金経理することができる。 3) 法人が一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合、その修理、改良等が当該固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その費用の額について修繕費として損金経理することができる。 4) 法人が耐用年数を経過した減価償却資産について修理、改良等をした場合、その修理、改良等が当該資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなるものであっても、その修理、改良等のために支出した費用の額は、その金額の多寡にかかわらず、修繕費に該当する。 |
正解4

修繕費の問題か、資産を使っていれば老朽化は避けられず、修繕というのは必要になるよね。
埼玉県八潮市の陥没事故でもわかるように定期的な点検と補修は必要だよね。自動車が生活に必要な地方に住んでいると痛感するね。

1)これは典型的な修繕費だよね。
2)60万円未満であれば修繕費として計上可能だね。
3)資本的支出が20万円未満であれば修繕費として計上可能だね。
4)これが不適切だね。修理・改良した結果、耐久性を高めて資産価値が向上しているから、新たな資産を取得したとみなされるね。
問31 青色申告法人の欠損金の繰越控除等
| 《問31》 青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。 (a)欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書であるである確定申告書を提出している場合、その後の事業年度においても青色申告書である確定申告書を提出しなければ、欠損金の繰越控除の適用を受けることができない。 (b) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。 (c) 2024年4月1日に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。 1) 1つ 2) 2つ 3) 3つ 4) 0(なし) |
正解2

(a)と(b)は覚えているけど(c)は記憶あいまいだな、以前は違ったんだよね。

(a) 欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書なら次年度が白色でも繰越控除可能だね。よって誤り。
(b)これは適切だね、古い年度分から繰り越されるね。
(c)2018年4月1日以降は10年で正しいよ。それ以前は9年間だったよ。
問32 消費税
| 《問32》 消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1) 適格請求書発行事業者として登録を受けた国内の課税事業者は、その基準期間における課税売上高の金額の多寡にかかわらず、簡易課税制度の適用を受けることができない。 2) 簡易課税制度の適用を受ける事業者が2種類以上の事業を行い、課税期間における課税売上高を事業の種類ごとに区分していない場合、事業の種類にかかわらず、最も低い第6種事業のみなし仕入率(40%)が全体の課税売上に対して適用される。 3) 小売業を営む適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付する場合、「税率ごとに区分した消費税額等」および「適用税率」については、いずれか一方の記載があれば足り、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は不要とされる。 4) 適格請求書発行事業者が行った課税資産の譲渡等について返品を受けたことにより、売上に係る対価の返還等を行う場合、原則として、当該売上に係る対価の返還等を受ける事業者に対し、適格返還請求書を交付しなければならないが、当該売上に係る対価の返還等の額が税込価額10万円未満であるときは、その交付義務が免除される。 |
正解3

適格請求書発行事業者ってインボイスのことだよね?呼び方変えられるとわからないくなるな。ちょっと賛否ある制度だから、ひょっとして変更もありえるかもね。しばらくFP受験生を悩ませそうだね。

1)簡易課税制度は適格請求書発行事業者より以前からある制度で、インボイス登録したから使えないということはないよ。
2)2種類以上の事業を行っている事業者は原則、事業ごとの税率が適用されるよ。区分できる場合は、より高い仕入れ税率で計算した方が有利だもんね。
3)これが適切だね。飲食店などで氏名を書かされるということは無いもんね。
4)税込価額10万円未満でなく1万円未満だね。数字は変えて選択肢になることが多いから要注意だね。
問33 会社とその役員の間の取引等
| 《問33》 会社とその役員の間の取引等における法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 1) 役員が所有する土地(取得価額3,000万円、時価2,500万円)を2,400万円で会社に譲渡した場合、会社側では100万円の受贈益が発生する。 2) 会社が所有する土地(取得価額2,500万円、時価3,000万円)を2,000万円で役員に譲渡した場合、役員側では時価と譲受価額の差額である1,000万円について、会社からの贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となる。 3) 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、会社側ではその債務免除を受けた金額が益金の額に算入される。 4) 役員が会社から無利息で金銭を借り入れた場合、原則として、会社側では通常収受すべき利息の額が益金の額に算入され、役員側では通常支払うべき利息の額が給与所得の収入金額となる。 |
正解2

会社と役員の取引ってよく出題されるけど、実際はオーナー社長と自分の法人の取引だと思っていいと思うよ。ルールを明確化しておかないとなんでもありになっちゃうからね。

1)この選択肢は正しいね。
2)これが間違いだね、役員側に有利な取引なら給与所得だね。
3)役員が会社に貸付ってよくありそうだけど、これは正しいね。実技試験ではよく出題される論点としてDESというのもあるので覚えておくといいかも。
4)本来、借入(貸付)は利息を伴うということだね。これを無利息で行ったら利息分が給与という扱いになるんだね。